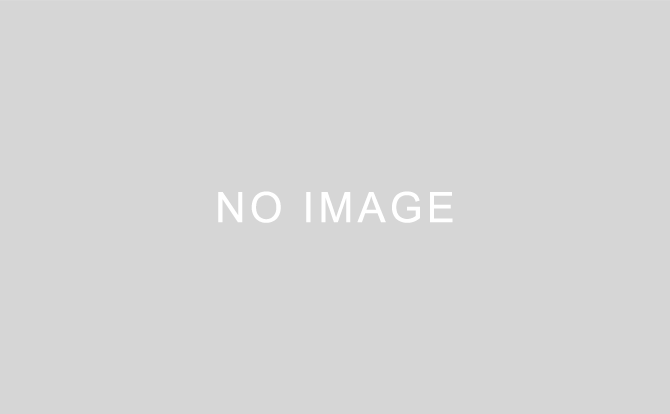本ページの一番下に、本ページのPDF版リンクを設けています。
最終改訂 2025.2.13 改訂箇所は改訂履歴のページ参照
このページは、「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」2(3)で概説した財産の取得、管理又は処分について、各論部分をもう少し詳しく説明するページです。
なお、一般的な概念説明のほか、特に財産の管理については、その対象財産および形態が多種多様であるため、下級審裁判例にあらわれた主な類型をとりあげての説明をしています。
【注】 参考事例の判決文は、必ずしも原文通りではなく、項目の表記にあうように若干の修正をしていることがあります。
1 総論
住民監査請求の対象とされるものが、地方自治法242条1項の「財産」にあたるのか、対象となる行為が、財産の「取得、管理又は処分」にあたるのかは、しばしば問題となります。
これは、財産という定義概念、取得管理処分という行為類型概念が、公金の支出のように明快で一義的なものではないことによります。そのため、判断に困惑する事案が多々発生する類型であることが特徴です。
まず住民監査請求の対象となる「財産」の定義についてですが、これは「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」2(3)アで述べた通り、地方自治法237条の「財産」と同一とされ※、実務上も当然の前提として扱われています。これは地方自治法237条の文理解釈によります。
| ※ 地方自治法237条1項で「この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう」という明文からくる法技術的解釈にくわえて、地方自治法における財務規律として、同条の財産概念と242条1項の財産概念を別とする制度的必然がない(法的規律があいまいな資産にまで住民監査請求・住民訴訟の対象を拡大することは、とりわけ住民訴訟で違法性の判断に苦慮することとなりかねない)ことによると考えられます。 |
一方で、財産の「取得、管理又は処分」は、モノではなく行為の問題でなり、しかも財産の取得、管理、処分に関わる行為は多様であるため、なにをもって住民監査請求の対象となる「取得、管理又は処分」に該当するというのか判断しづらいところがあります。
この点についてもっとも重要な判断基準は、次の最高裁判例が示すものになります(本判決は、財産管理行為または契約を扱ったものですが、考え方は住民監査請求の対象となる行為等全般に及ぶものです)。
★ 以下の説明は、「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」2(1)イの内容と同旨ですが、本項で押さえておくべきもっとも重要な事項となるので、重ねて説明します。
| 住民監査請求の対象となるのは、財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為・事実に限る 最判平2.4.12民集44.3.431
(市建設局長等は、市道工事施行決定書に押印決裁し、建設局要求に基づき、理財局において工事請負契約に関する入札等の事務手続を行い、工事請負契約決定書に理財局長決裁印を得て、工事請負契約が締結され工事が施行されたが、工事施行地は保安林指定の解除がなされておらず、工事中止を求める運動などが発生したため工事は一時中止、工事地の原状回復措置として再植栽が行われ、その費用を市が負担したことに関する建設局長等(上告人)に対する4号住民訴訟) ○ 上告人らの右行為は、市道予定地を道路状の形状にすることにより道路整備計画の円滑な遂行・実現を図るという道路建設行政の見地からする道路行政担当者としての行為(判断)であって、本件土地の森林(保安林)としての財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の財産管理行為には当たらないと解するのが相当である。 |
つまり、住民訴訟の対象(=住民監査請求の対象)となる財産管理等の行為は、住民監査請求制度の趣旨に照らし、財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為または怠る事実としての性質を有するものに限られ※、その上で、いくつかの行為等が関連している場合、これらを一体のものとして観察・判断するのではなく、これら行為等を個別の行為等の単位レベルに分解して観察・判断し、そのうえで上記の財務的処理を目的としないものについては、いかに財産の管理等に影響を与えるものであっても、直接これを住民監査請求の対象とすることはできないとしているのです※※。
本件の場合、建設局長等の道路工事施行決定と理財局の工事請負契約締結は、社会通念的には一連かつ一体的なものですが、住民監査請求の要件審査においては、これらを個々に分解して個別に観察することとし、その上で建設局長等の行為は、社会通念的には財務会計行為である有償の工事請負契約に直結するものに見えるものの、あくまでも工事請負契約締結行為とは別の行為であって、建設局の工事施行決定は、道路整備計画に沿って、具体的な○○の地に、具体的にどのような形状の道路を建設するか、という道路整備推進という行政上の目的を実現するための行為であって、それ自体は財務的処理を目的とするものではないので、建設局の行為を純粋に(行為単位に分解純化して)判断する限り、財務会計行為ではない、という結論となるのです。
| ※ 参照:上田豊三「時の判例Ⅰ」p.297 |
| ※※ 碓井p.79は、本判決について、工事の開始までに工事請負契約等一連の財務会計行為が介在しているが、最高裁は、一連の過程における行為を個別に分解した上で(それぞれについて)財務会計行為該当性を判断するという姿勢を示す、とする。 なお、判例において財務会計行為該当性の判断に目的を重視する点については、4版p.172・5版p.150(最判平10.11.12民集52.8.1705)解説(野呂充)参照。 |
このような判断となるのは、住民監査請求・住民訴訟制度があくまでも自治体財務運営の適正を図る仕組みであり、政策的問題ではなく、財務上の問題の違法(不当性)について問うことに対象を限定するかわりに、住民一人からでも提起できる仕組みとして構築されたものである以上、財務的処理を直接の目的としない、一般行政上の問題処理を目的とする行為を住民監査請求・住民訴訟で対象とすることは、上記のような制度の目的から逸脱することになるためであり、それゆえに、判例は、住民監査請求の対象となる行為を、限定的に解する方向にあります※※※。そして、この判断枠組みを基礎として、個別の類型・事案ごとに、住民監査請求の対象とされた事項が、地方自治法242条1項で定める住民監査請求の対象として取り上げ得るものか、判断されることになります。
| ※※※ 参照:大橋寛明「時の判例Ⅰ」p.300(最判平10.11.12民集52.8.1705関係) |
2 住民監査請求の対象としての「財産」
住民監査請求の対象となる「財産」の概念は、「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」2(3)アに説明する通りであり、以下では裁判例等を踏まえ、主な類型ごとの説明をします。
(1) 財産全般・・・現有財産ではないもの
住民監査請求の対象となる財産については、現に自治体が有する財産に限られ、自治体の所有になる予定の財産であっても、現に自治体の所有でないものは、住民監査請求の対象となる財産とは解されないとする事例があります。「予定」の確実性など考えれば、こうしたものを含めるのは、住民監査請求の範囲が際限なく拡大することとなるため、妥当な考え方と考えます。
【参考事例】
| 自治体の所有に属していない道路開設予定地に対する管理の当否は、住民訴訟の対象とすることはできないとした事例 大津地判昭47.7.31行裁例集23.6・7.597(町道開設予定部分のうち民間会社所有の土地について、これを買収すべき予算も計上されていながら正当な理由なく買収に着手せず、道路を開設しないことは、予算が失効したとしても、町議会が開設予定部分の道路を建設すべきことを議決しているのだから、違法に財産の取得を怠るものとする3号住民訴訟)
○ 地方自治法242条等の規定において「財産の管理」という場合の財産とは、同法237条1項所定の公有財産、物品、及び債権並びに基金で、すでに地方公共団体に属しているものと解すべきであり、原告らが主張するような、未だ町の所有に属さず、将来町道用地として買収を予定しているにすぎない土地のようなものは、前記の財産に当らない、と判示。 |
(2) 財産類型別の考え方
ア 公有財産
① 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
住民監査請求の対象として、物の使用に関する権利が、しばしば問題となります。これは、地方自治法238条1項4号の権利(見出しの権利)の定義が何か(「その他これらに準ずる権利」の範囲)、また物を使用する権利としては、物権(地上権等)のほか債権(賃借権、使用借権等)があり、権利の態様が多岐にわたるためです。
ところで、この点に関し、最判平2.10.25集民161.51は、すくなくとも使用貸借の権利(債権)は、「これらに準ずる権利」ではなく、住民監査請求の対象としての財産にあたらない、と判断しました※1。
なお同判決の原審である東京高判平2.4.25行裁例集41.4.882は、権利の性質や財産的価値からして、財務会計上の管理から観点の適否を論ずるべき余地がないから、としています。
| 道路法施行法5条1項の使用貸借による権利は、地方自治法238条1項4号のその他これらに準ずる権利にはあたらない 最判平2.10.25集民161.51
(敷地が道路法施行法5条1項により国有地を使用貸借する市道において、境界が未確定な箇所を占有する者があったため、不法占有排除等の怠る事実の違法確認を求める住民訴訟) ○ 本件道路敷地を使用する権利は道路法施行法5条1項に基づく使用貸借による権利であり、同項に基づく使用貸借による権利は地方自治法238条1項4号にいう「地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利」に当たらず、結局同法242条の2第1項、242条1項にいう「財産」に含まれないとして、本件訴えを不適法とした原審の認定判断は、正当として是認することができる、と判示。 上記最判の原審:東京高判平2.4.25行裁例集41.4.882 ○ 地方自治法242条1項所定の「財産の管理を怠る事実」について、同法237条は「この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。」と定め、同法238条1項が公有財産について(国有財産法2条1項とほぼ同趣旨である。)、同法239条が物品について(物品管理法2条1項とほぼ同趣旨である。)、同法240条が債権について(国の債権の管理等に関する法律2条1項と同旨である。)、同法241条が基金について、それぞれ定義しているのであるから、右の定義に従った「財産」の管理を怠る事実をいうものと解するのが相当である。 |
| ※1 本件に関する担当調査官解説(増井和男「時の判例Ⅰ」p.289)は、本訴は、市の財務会計上の行為を問題とするものではなく、道路管理上の行為を問題とするものであるから、この点においても不適法であるという考え方もあろう、とする。 |
また松本逐条では、「これらに準ずる権利」について、例示の権利のほか、法律上確立している用益物権※2または用益物権的性格を有する権利をいい、永小作権、入会権、漁業権、入漁権、租鉱権、採石権※3等が該当する一方、占有権、水利権、担保物件、賃借権、借地権※4等は該当しない、としています(松本逐条本条関係参照)。
つまり、ここでの「これらに準ずる権利」とは、「物を直接支配する権利」である物権(物権的性格を有するもの)に限られ、「相手方に対する請求権」である債権(特に社会的に広く利用されている賃借権、使用借権)は除外されるということになります。
監査実務においては、こうした事例等、また「財産」としての債権は地方自治法240条に明文の定義規定が置かれていることも踏まえれば、ここでの「その他これらに準ずる権利」については、法律上の根拠がある(民法175条参照。ただし慣習上の物権の存在に留意)用益物権に限る扱いとすることが適当であると考えます。
| ※2 用益物権とは、他人の土地を一定の目的のために使用収益する制限物権(法律学小辞典p.1302)。制限物権とは、所有権のように目的物を全面的に支配するのではなく、一定の限られた目的のために使用する物権(同p.756)。物権とは、物を直接に支配する権利(所有権が代表)。物権は全ての人に対して主張しうる権利だが、債権は特定の人に対してある行為を要求する権利で、原則として第三者に権利を主張できない性質を持つ、とされる(同p.1142)。 用益物権は、物の価値の属性としての「交換価値」と「利用(使用収益)価値」のうち「利用価値」を支配する権利である。なお所有権は利用価値、交換価値のいずれも支配し、担保物権は交換価値を支配するとされる(参考:内田貴「民法Ⅰ(第4版)」東京大学出版会(2008年)p.350、潮見佳男「民法(全)」有斐閣(2017年)p.112)。 |
| ※3 永小作権は民法270条、入会権は直接の民法上の定義はないが同263条、294条、漁業権の物権的性格については漁業法77条1項、入漁権の物権的性格については漁業法98条1項、租鉱権の物権的性格については鉱業法71条、採石権の物権的性格については採石法4条3項参照。 |
| ※4 占有権は本権ではなく、事実上の物の支配状態に対して権利としての保護を与えるもので、仮の権利とされる(法律学小辞典p.801)。水利権は、国土交通省Webサイトによれば、河川の流水を排他的継続的に利用する権利とされるが、ここでの権利から除外されているのは、河川の流水は私権の目的とならない(河川法2条2項)ことによるものと推測する。担保物権(抵当権等)はそもそも用益物権ではなく、財産の取得、管理、処分を対象とする住民監査請求の対象としての性格に合致しづらいためと推測する。賃借権は債権(民法601条)、借地権は土地の賃借権のこと(借地借家法2条1号の借地権のうち地上権を除く)。 |
なお、公物管理権(公物、たとえば道路などを適切に利用できるよう維持管理するために公法上認められた権限。下※6参照)や、行政財産の使用許可によって得られる「利用権」は、地方自治法238条1項4号の「これらに準ずる権利」に該当するかが問題となることがありますが、裁判例では一般に該当するとは認められていません。地方自治法238条1項4号の権利は、法律上確立している用益物権または用益物権的性格を有するものとされていますが(松本逐条238条関係参照)、公物管理権などの「権利」は、公物の管理上、特に認められた権能であり、物(の利用価値)を支配して利用するという用益物権的性格をもたないためです。
つまり、公物管理権や、行政財産を使用許可によって使用することは、住民監査請求の対象としての財産とは一般に認められないということになります※5。
| ※5 公物管理権については、それが「財産」に該当するかという論点と、公物管理権による管理行為が「財産管理行為」に該当するかという論点が併存するので、注意して下さい。財産管理行為については、下記3(2)で説明しています。 |
【参考事例】
★公物管理権の地方自治法238条1項4号の権利該当性※6等(河川港湾の財産該当性)
| 河川・港湾およびこれらの公物管理権が、いずれも住民訴訟の対象となる県の財産に当らないとした事例 (いわゆる田子の浦ヘドロ訴訟) 東京高判昭52.9.5行裁例集28.9.893
(田子の浦に排出されたヘドロの除去のための浚渫工事に要した費用をその原因を作った会社に負担させるべき等であるとする住民訴訟) ○ 控訴人らは、沼川、潤井川、滝川、田宿川及び瀬戸川並びに田子の浦港が県の財産であるとし、県の財産であることの根拠を、右各河川及び田子の浦港を管理する行政主体が県であること及び河川管理権、港湾管理権が地方自治法第238条第1項第4号にいう地上権等に準ずる権利に該当することに求める。 (【参考】 本件の一審:静岡地判昭49.5.30行裁例集25.5.470) ○ 地方自治法第238条1項4号の「地上権・・・その他これらに準ずる権利」とは、まさに同号の例示にあるように地上権、地役権、鉱業権に準ずる不動産の用益物件ないし用益物権的権利を指称するものと解するのが相当であり、公物管理権がこれに該当すると解することはできない。(中略) |
| ※6 公物は、自然公物を含め大抵の場合、「その目的を増進したり、目的阻害行為を防御したりするための作用、管理作用が必要にな」り(自然公物でも堤防造成、浚渫、河川区域内土地占用許可などが必要)、「公物についての行政作用はすべて、公物管理権として現れる」とされます(塩野Ⅲp.406)。つまり、公物に対する一般管理作用は、行政作用としての公物管理権による作用、ということになり、逆に公物管理権の性格もそこから説明可能となります。 そして公物管理権とは、その法的根拠は諸説ありますが(塩野Ⅲp.408は物に対する所有権その他の権原が公物管理権の根拠であり、公物管理法が制定されている限り、管理権の根拠はその公物管理法に吸収されるとし、これが現在の有力説とされる(三好規正「公権と私権」(高木・宇賀(編)「Jurist増刊 行政法の争点」有斐閣(2014年)p.222))、その内容をさらに具体化すると「公物を公の目的に適合させる作用で、それは、その目的に適合するように装置をなすことと、公共用物にあっては、公共の利用を調整する作用として説明される」(塩野Ⅲp.416)、「公物の存立を維持し、これを公の目的に供用し、できるだけ完全にその本来の目的を達成させるために行政主体が有する権能」(法律学小辞典p.392)とされます。さらにこれを具体のアクションとしてカタログ化すれば(公物の種類によって異なるところはあるが)、公物範囲の確定、維持・修理、公物に対する障害防止、公物隣接区域に対する規制、使用関係の規制など(塩野同)、公物範囲の確定、公物の維持・保管およびそれに必要な公用負担特権、公物の目的に対する障害の防止・除去、公物の使用関係の規制(道路占用許可及び占用料の徴収等)(法律学小辞典同)といったものが挙げられるとされます。公物管理権のポイントは、これが公物の目的を達成するための作用であり、これら公物の機能維持・増進のためのものである、ということにあります(塩野同)。 こうした公物管理が、一般的な財産管理行為とどのように異なるのかについては、「公物の管理は、私物の管理と異なり、物を財産的価値の客体として管理するのではなく、公物本来の機能である公共用又は公用に供するという目的を達成させるために管理する」とする田中Ⅱp.317の説明に端的に現わされているところです。 つまり公物管理作用は、公物に期待される社会的(ソフトウェア的)機能を、その公物の目的に沿って発揮させるためのものであるので、物(の利用価値)を支配的に利用するという用益物権的なものとはいえず、また自治体の財産たる公物の有体物(ハードウェア)としての価値を維持保全する行為とも異なる(よって、下記3(2)(財産の管理)にある公物管理権に基づく公物管理行為は、地方自治法242条1項の財産管理行為にもあたらない。なおそもそも公物管理は、その公物がその自治体の財産であることを必須の前提として行われるものではない)、というのが、裁判例等での一般的な理解であると推測します。 なお上記田子の浦ヘドロ訴訟では、原告住民は公物管理権の帰属をその公物が当該自治体の財産となることの論拠と主張していますが、控訴審(東京高判)で端的に判示される通り、公物管理権は他有公物についても成立するものであり(公物管理権が所有権(のみ)から導かれる作用であり、所有権⊇公物管理権の関係が成立しない限り、公物管理権の帰属から所有権の帰属を導出できないのは論理的に自明だが、公物管理権がそのような性格のものでないことは、上記説明から明白)、公物管理権の帰属をもって財産権の帰属を判定し得るものではありません。住民監査請求の実務において本件一審・二審裁判例は、前記判断例たるもののほか、①公物管理権は地方自治法238条1項4号の財産にはあたらないと判断した例 のほか、②河川や港湾は住民監査請求の対象となる財産性を否定する判断を示した例 ③河川および港湾管理行為は非財務事項であり地方自治法242条1項の財産管理行為ではないと判断した例(下記3(2)関係) として、自治体実務における参考となるものと考えます。 |
★行政財産の使用許可を得て使用する権利の地方自治法238条1項4号の権利該当性
| 公営住宅の一部を行政財産使用許可を得て無償で使用する権利は、住民訴訟の対象となる財産に当らないとした事例
東京地判平14.12.20判例時報1856.97 (市が都営住宅の一部を学童クラブとして使用するため行政財産使用許可を受け使用料免除を受けていたが、実際には障害者授産施設として運営しており、これが発覚して都は使用料相当額の損害賠償の支払を求め、市がこれを支払った。これに対し、市長が使用許可あるいはその更新に際して使用条件の変更を求めるなどの措置をとらないで放置していたことは使用許可に係る権利ないし使用借権の管理を怠る事実に当たり違法であるとして、市長個人に損害賠償を請求した住民訴訟) ○ 行政財産の使用許可による使用権は、公法上の権利ないし地位にすぎず、使用借権ではないというべきである。そして、地方自治法238条1項4号所定の地上権等に準ずる権利とは、同号に例示されている権利の内容及び性質に照らし、法律上確立している用益物権又は用益物権的性格を有する権利のことをいうと解するのが相当であるが、市が本件建物部分について有する使用権、すなわち、行政財産の使用許可により設定された公法上の権利ないし地位は、〈1〉行政財産の使用許可を受けた者に対し、当該行政財産を直接かつ排他的に支配する権原を付与する法令の規定が存在しないこと、〈2〉むしろ、法238条の4第6項が、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為があると認めるときは、その許可を取り消すことができると定めているなど、その目的物が行政財産であることに由来する制約が課されていることに照らし、法律上確立している用益物権又は用益物権的性格を有する権利すなわち、地上権等に準ずる権利に当たるものではないというべきである。 【補注】 行政財産使用許可の財産権性の有無については、最判昭49.2.5民集28.1.1(宇賀・交告・山本編「行政判例百選(第7版)Ⅰ」有斐閣(2017年)p.182、斎藤・山本編「行政判例百選 (第8版)Ⅰ」第8版(2022年)p.176も参考となろうかと思われますので念のため。 |
★契約上の地位の地方自治法238条1項4号の権利該当性
| 市が公有水面埋立事業の施行に当たり公有水面埋立免許を得るため漁業協同組合との間で締結した漁業権放棄契約によって取得される契約上の地位は、住民訴訟の対象となる財産に当らないとした事例 山口地判昭57.5.6行裁例集33.5.967
(市長に、指定海域部分についての埋立工事主体者としての地位を、電力会社に譲渡してはならないことを求める住民訴訟) ○ 原告は、本件における違法な処分の対象たる「財産」は、市が漁協との間の漁業権放棄契約に基づき取得した本件海域に対する海域利用権であり、同利用権は当該海域につき独占的に埋立免許出願を行ない、かつ埋立を行なうについて支障をきたす行為を排除し得ることを内容とする排他的な支配権であって、地方自治法238条1項4号の公有財産に該当するとして、排他的支配権としての海域利用権といった権利が存し、かつこれを市が本件海域につき取得した旨主張する。 |
② 出資による権利
地方自治法238条1項7号の出資による権利は、出資したことによって取得する権利(社員権・持分権)そのものを指し、出資そのものをどうするかという権利は含まないとする裁判例があります(下記山形地判)。出資による権利は、法文からみても、出資により直接生ずる権利であると解するのが自然です。
【参考事例】
★出資による権利
| 地方自治法238条1項7号の「出資による権利」とは、出資したことによって取得する権利(社員権・持分権)そのものを指し、出資契約上の履行請求権は上記の「出資による権利」に含まれないとした事例 山形地判昭62.9.21行裁例集38.8・9.1023
(県から出資を受けた美術館が出資の趣旨に反して出資金の全額を基本財産に組み入れなかった場合には、知事は出資契約上の履行請求権に基づいて出資金の全額を組み入れるよう請求するか、出資契約を解除することができるところ、これらの権利の不行使に対して怠る事実の違法確認を求めた住民訴訟) ○ 地方自治法238条1項7号の「出資による権利」とは出資したことによって取得する権利(社員権、持分権)そのものを指し、出資契約上の履行請求権は含まれないと解すべきである。 |
| 市が出資している第三セクターである株式会社の株主総会において、同社の代表取締役である市長が、同社の所有財産を売却する旨の仮契約を承認するために議決権を行使する行為は、非財務的見地からなされるものであるから、住民訴訟の対象となる財務会計上の行為に当たらないとした事例 浦和地判平6.10.31判例地方自治140.22
(事実関係は上記の通り) ○ …本件会社は、本件建物等及びA駅東口再開発事業区域内の公共施設の管理を主たる目的としていわゆる第三セクターとして設立された会社である。即ち、市は右のような管理に関する行政目的を実行するために本件会社に出資したのであるから、市がその所有する株式に基づき議決権を行使することは、一般に右行政目的を遂行するためであるということができる。そして、本件会社は、前記のようにPが本件建物の賃貸借契約につき解約申入をしたことに伴い、Mとの間で本件仮契約を締結し、本件臨時株主総会において右仮契約の承認の件につき決議を受けることとしたところ、…によれば、本件会社は、Pとの間の右賃貸借契約が終了することにより保証金残金約50億円を返還しなければならなくなったが、右金額は本件会社にとって容易ならざる額であったため、右解決方法、即ち右返還資金を入手する方法として本件売却物件を売却することとしたことが認められる。そうすると、本件臨時株主総会における本件仮契約の承認の議題の実質的な主旨は、第三セクターである本件会社が経営上存続し得る方策の如何であるということができ、そして、本件会社が経営的に存続し得るかどうかは、市が本件会社に出資した行政目的を遂行できるかどうかに関わることは明らかである。したがって、市が本件臨時株主総会において本件仮契約を承認する旨議決権を行使した行為は、右のような行政目的の遂行に関するものであり、非財務的行為であるから、住民訴訟の対象となり得ないものである。 |
| 「出資による権利」とは、利益配当や残余財産の分配請求権など、法人や組合の事業に対する出資により取得する財産上の権利をいい、ダム使用権設定予定者の地位をもって「出資による権利」に当たるということはできないとした事例 東京高判平26.3.25判例時報2227.21
(特定多目的ダムに関し、関係する県の地方公営企業管理者がダム使用権設定申請を取り下げる権利の行使を怠ることの違法確認を求めた住民訴訟) ○ 地方自治法238条1項7号の「出資による権利」とは、利益配当や残余財産の分配請求権など、法人や組合の事業に対する出資により取得する財産上の権利をいうものと解される。ダム使用権の設定予定者は、特定多目的ダム法7条に基づき多目的ダムの建設費を負担するが、これにより何らかの財産上の権利を取得するものではないから、ダム使用権設定予定者の地位をもって「出資による権利」に当たるものということはできない、と判示。 |
|
経営危機となった出資株式会社が資産売却等を行うことについて株主総会で議決権を行使して承認し原案通り議案成立したので資産譲渡が実行されたことについて同社の財産的価値が減じ長に損害が生じたとする4号訴訟で、前記議決権行使は財務会計上の行為であるとはいえないとした事例 高知地判平27.3.10判例時報2322.49
(事実関係は上記の通り) ○ そして、証拠…によれば、本件総会における議案は、A(注:出資株式会社)が所有する固定資産を林産組合に有償ないし無償譲渡することの賛否であるとの事実が認められるところ、株主の有する議決権は、株主が会社経営に参与し、あるいは、取締役等の行為を監督是正する権利である共益権の一種である上、前記認定事実によれば、上記議案についての議決権の行使は、経営危機に陥ったAにおいて木材の乾燥業を継続することは困難である一方、Aの保有する乾燥機を利用してきた業者にとってその使用を継続する必要があるため、乾燥業の受け皿となる林産組合が設立されたことを前提として、その林産組合にAの有する固定資産を譲渡すべきかが、Aの経営上問題となったことから、Aの株主である仁淀川町として、その経営上の判断の是非に賛否を明らかにすべく、町長は、町の代表者として、本件総会において議決権を行使したのであるから、この議決権の行使は、株式の財産的価値の維持・保全を図る財務的処理を直接の目的とするものであるとはいえず、したがって、本件総会におけるY町長による議決権の行使は、財務会計上の行為であるとはいえない。そして、原告らの主張するその余の町長の行為については、予算を議会に提案した行為も含め、それが財務会計上の行為であるといえるようなものはない、と判示。 |
|
保有株式の価値を保全する行為は財産管理行為に該当することを前提として本案判断を行った事例 東京地判平27.7.23判例時報2315.37
(自治体全額出資会社の行為により株式の価値が下がったところ、同社の代表取締役に会社法847条の責任追及等の訴えを提起しないのは財産の管理を怠るとする3号訴訟) (→ 上記の通り、本件については本案判断が行われている) 同前 東京地判令4.2.18判例地方自治507.24 (自治体全額出資会社の行為により全株式を保有する当該自治体の財産に損害を与えたとして、同社の代表取締役に会社法847条の責任追及等の訴えを提起しないのは財産の管理を怠るとする3号訴訟) ○ A区監査委員は、(地方自治)法242条1項に規定する「財産の管理を怠る事実」といった場合の「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金を指すものであり(法237条1項)、ここにいう「債権」とは、金銭の給付を目的とする地方公共団体の権利をいう(法240条1項)ところ、責任追及等の訴えの提起を請求することを内容とする権利は、当該株主が金銭の給付を受け取ることを目的とするものではなく、同項に規定する「債権」には当たらないから、本件監査請求…は「財産の管理を怠る事実」に該当せず不適法であると判断したものである。 ○ しかしながら、法237条1項に規定する「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいうとされ、法238条1項6号は、地方公共団体の所有に属する財産のうち株式、社債、地方債及び国債その他これらに準ずる権利を公有財産とする旨を規定しているものである。 ○ A区は本件公社の発行済株式の全部(本件株式)を保有しているものであるから、本件株式はA区の公有財産に該当するところ、株式とは株式会社における株主の地位を意味し、株主の有する個々の株主権は株主の地位に包含されるものであるから、A区の本件公社に対する株主権もA区の「財産」に該当するというべきであり、その行使は「財産の管理」に該当すると解するのが相当である。 ○ 本件監査請求…は、A区の「財産」である本件株式の管理を財務会計上の行為とした上で、その管理の一環として、本件公社の役員等の違法行為により発生したA区の「財産」である本件株式の価値の減損による損害を回復する手段として、(代表取締役)に対する提訴請求をすべきであることを前提に、これを違法に怠る事実について住民監査請求を求めているものと解される。 ○ そうすると、本件監査請求…は、住民監査請求として適法なものであるということができ、これを不適法として却下した部分の本件監査の結果は失当である。 |
イ 物品
住民監査請求の対象となる財産としての物品は、公有財産、現金、基金以外の動産(地方自治法239条)です。
なお、物の財産的価値に着目した次のような裁判例もあり、参考となるものと考えます。
【参考事例】
★上水
| 町の上水を供給することは町財産の管理・処分に相当するから、同給水行為は財務会計上の行為に当たるとした事例
東京高判平6.2.28判例地方自治126.50 (国モデル事業地内への町の上水供給の差止めを求める住民訴訟) ○ 町の上水道施設により浄化、殺菌等の処理を施し上水として供給されることが可能となった水は、自然界にあってそのままでは飲料に供し得ない水とは異なり、財産的価値のあるものである。 |
★公営プールの回数券
| 町が設置した温水プールの回数券は、(当時の民法の規定上)無記名債権であり、したがって動産であるから地方自治法237条1項の「物品」に該当し、条例に基づかないで無償譲渡することは違法に財産の管理を怠ったものと評価できるとした事例 名古屋地判平12.4.21判例地方自治220.26
(町が設置した温水プール利用回数券が無償譲渡されたこと等が違法であるとして、町長個人に損害賠償を請求した住民訴訟) ○ 回数券は、無記名債権であって、動産であるから(注:民法86条3項(令和2年4月から当該条項は改正されて存在しない))、地方自治法237条1項の「物品」に該当するが、物品は、条例又は議会の議決による場合でなければ、適正な対価なく譲渡することができないものであり(同条2項)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例は、物品について、「公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体または私人に譲渡するとき」は無償で譲渡することができるとしているから、町が、回数券を右条例に基づいて譲渡したと認められるものであれば、右無償譲渡は適法であるが、譲渡自体が認められないもの、あるいは、譲渡自体は認められるが右条例に基づかないと認められるものについては、違法に財産の管理を怠ったものと評価できる。 注:無記名債権を動産とする民法86条3項の規定は、現在は上記の通り削除されています。そのため、今後回数券類について同様の判断ができるかどうかは不明であり、あくまでも一つの参考事例として参照下さい。 |
ウ 債権
住民監査請求の対象となる財産としての債権は、金銭債権に限定されます(地方自治法240条1項)です。
したがって、下記のように、金銭債権に該当しない債権に関する事項は、「財産の取得、管理又は処分」として住民監査請求の対象とすることはできません。たとえば下記事例の工事修補請求権などは、住民監査請求の対象となる債権には該当しません。また、債権の対蹠概念となる債務も当然ながら対象外です。
【参考事例(債権該当)】
★負担金の請求権
| 道路法58条1項、61条1項、地方自治法224条に基づく負担金は、地方自治法242条1項の財産(債権)に該当するとした事例 福島地判平11.4.27判例地方自治208.74
○ 道路法58条1項、61条1項、地方自治法224条に基づく負担金等は地方公共団体の権力的作用に基づいて、地方公共団体が原因者等に対して負担させることにより発生する金銭債権であり、不当利得返還請求権としての金員請求権は、地方自治法240条1項の定める「債権」に該当し、同法237条1項、242条1項の定める「財産」に包含されると解される。 |
【参考事例(債権非該当)】
★工事の瑕疵補修請求権
| 町発注工事に瑕疵がある場合の瑕疵修補請求権は、地方自治法237条1項の債権には該当しないとした事例 旭川地判平31.4.23判例地方自治458.72
(町発注の工事に瑕疵があるのに瑕疵修補請求権を行使しないことは違法に財産の管理を怠るとして、これが違法であることの確認を求める3号住民訴訟) ○ 民法634条2項所定の瑕疵修補請求権は、請負契約の施工者に対し瑕疵の修補を求める権利であって、金銭の給付を目的とする権利でないことが明らかであるから、地方自治法237条1項の「債権」には当たらず、瑕疵修補請求権の不行使につき、財産の管理を怠る事実の確認を求める請求は不適法、と判示。 【注】民法634条は、令和2年施行の民法改正により、当時の条文が現存しない(現在の民法634条は別の内容である)。ただし担保責任が追及不能となったものではない。 |
★補助金取消権
| 補助金交付決定の取消権は、地方自治法237条1項の財産に当たらないとした事例 福岡高判平18.10.30判例タイムズ1254.126
(町が違法な補助金を支出しており、補助金交付決定の取消しを怠ることは違法であるとする住民訴訟) ○ 地方自治法でいう「財産」とは「公有財産、物品及び債権並びに基金」をいい、その債権とは「金銭の給付を目的とする普通公共団体の権利」をいう。そこで、補助金交付決定の「取消権」なるものが上記の金銭債権に当たるかが検討されなければならないが、仮にその「取消権」が補助金交付決定という「行政処分」を取り消す権利であれば、金銭債権であるはずはないし、補助金交付決定が私法上の贈与契約の性質を持つとすれば、「取消権」はその「約定解除権」であることになるから、やはり金銭債権そのものではない。 |
★自治体が有するであろう非特定の抽象的・一般的な債権※
| 怠る事実の対象である財産は、地方公共団体が有するであろう一般的、抽象的な財産ではなく、地方公共団体に具体的に帰属する個別的な財産を意味するとした事例 東京地判平7.7.26行裁例集46.6・7.722
(公道敷地上に道路占用許可を受けずに設置された自動販売機について不当利得又は不法行為の債権請求を怠る事実の違法確認を求める住民訴訟) ○ 本件は、都が私人に対して有する不当利得債権ないし不法行為債権を行使しないことを「怠る事実」として、その違法確認を求めるものであるから、その個別具体的な金銭債権の不行使が財務会計上の作為義務の懈怠といえるかどうかを審理、判断するためには、その行使すべきであるとする個々の債権が具体的に特定されていなければならない。 ※ 本判決の論点は主に、要件審査における「請求の対象となる財務会計行為等の特定」の問題となります。「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」4参照。 |
★債務(負の財産)
| 地方自治法242条1項にいう「財産の管理を怠る事実」の「財産」には、いわゆる「負の財産」を含まないとした事例 東京地判昭59.9.27判例地方自治10.109
(市道(国有地)の不法占有が恒常化し正当化されれば市道の中心線が移動し建築基準法44条の関係で本件市道に接する原告らの所有地に重大な建築制限をもたらすことになるが、このような建築制限がもたらされたときは土地所有権に対する侵害となり国家賠償法3条にいう「管理に当る者及び費用負担者」として損害賠償責任を都等が負うとして、道路管理者(市長)が道路としての維持管理等の道路行政を十分行い得る状態を作出する措置を都知事が怠る事実が違法であることの確認を求める住民訴訟) ○ 地方自治法242条の2第1項3号、242条1項にいう「財産の管理を怠る事実」の「財産」にいわゆる「負の財産」も含まれるべきと解釈すべき法理上の根拠はない。いわゆる「負の財産」は、地方自治法237条ないし241条所定の財産に該当しないことは明らかであり、地方自治法242条及び242条の2についてのみ、「財産」の意義を同法237条1項以下の定義規定と別異に解すべき理由はないから、住民訴訟の対象たる「財産」に該当しない。 |
★入札保証金
| 入札保証金は地方自治法242条1項の公金又は財産のいずれにも該当せず、入札保証金の免除は財務会計行為に該当しないとした事例 東京地判平2.9.5判例タイムズ756.183
(事実関係省略) ○ 普通地方公共団体が地方自治法施行令167条の規定に基づいて実施する競争入札は、契約の前段階の行為として、契約の相手方を選定するために行われるものであるから、競争入札自体が(地方自治)法242条1項にいう「契約」に当たらないことは明らかである。また、入札保証金は、落札者との契約の締結をより確実なものとし、かつ、落札者が契約を締結しなかった場合の損害を填補する趣旨で入札参加者にあらかじめ納付させる金員であって、入札参加者が落札しながら契約を締結しない場合には当該普通地方公共団体の所得となるものであるが、入札者が落札しなかった場合又は落札した者が契約を締結した場合には納付した者に返還されるべきものであるから、これが法242条1項所定の「公金」又は「財産」に該当しないことも明らかである。 |
★生活保護法78条による返還請求権
| 生活保護法78条は、被保護者の困窮状態や不正の程度等の事情によっては、徴収額をその費用の一部に限る余地がある場合を考慮して、費用の徴収に支弁者の裁量を認めていることから、法が特別に定めた公法上の請求権と解すべきところ、これを地方自治法242条の2第1項4号の請求の対象とすれば、徴収権者の裁量や相手方の地位を害するおそれがあることから、その対象にはならないとして、本件訴えを不適法とした事例 仙台地判平17.6.30
(生活保護法に基づく保護費の支給が同法10条、4条に違反するとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、福祉事務所長に対し、被保護者等に生活保護法78条に基づく返還請求をすることを求める4号訴訟) ○ (生活保護)法78条は,「不実の申請その他不正な手段により保護を受け,又は他人をして受けさせた者があるときは,生活保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は,その費用の全部又は一部を,その者から徴収することができる。」と規定している。不正な手段により生活保護費の支給を受けた場合には,そもそも受給資格がないのであるから,その受給費用全額について徴収されるのが原則である。しかし,法78条の文言は,費用の徴収に支弁者の裁量を認めており,これは,被保護者の困窮状態や不正の程度等の事情によっては,徴収額をその費用の一部に限る余地がある場合を考慮した規定と解される。そうすると,同条は,不当利得に基づく返還請求権又は不法行為に基づく 損害賠償請求権とは別個の,法が特別に定めた公法上の返還請求権であると解すべきである。 |
3 財産の取得、管理又は処分
(1) 財産の取得
財産の取得は、何らかの法律上の原因(契約等)により、自治体に財産取得の効果を発生させる執行機関または職員の行為をいいますが(参照:実務住民訴訟p.135。松本逐条(149条関係)は、購入、交換、寄附受納等とする)、財務的処理を目的としない行為(例:下記昭和51年最判※)や、公金の支出・義務の負担ないしは財産上の損失を伴わない単なる収入(利得)を発生させるにとどまる行為(参照:下記昭和48年最判。ただし昭和38年自治法改正前の条項に基づくものであり、事案としては金員の贈与契約である)は、住民監査請求の対象とはならないとされています。
| ※ 昭和51年最判は、土地区画整理事業における換地処分を住民訴訟の対象としない理由を詳らかにしていませんが、その点について、やはり土地区画整理事業(保留地処分)を扱った最判平10.11.12民集52.8.1705の担当調査官解説(大橋寛明「時の判例Ⅰ」p.300)では、同判決で扱った土地区画整理事業を同様に争点とする最判昭51.3.30集民117.337において換地処分が住民訴訟の対象である財務会計行為に該当しないとされたことについて、換地処分が法に基づく事業達成という一定の行政目的実現のために行われるもので、直接財産取得を目的としておらず、結果として他の財務的行為の介在なく土地が事業施行者である自治体に帰属するものであり、このような処分を住民訴訟の対象とすると、一般行政上の違法を直接住民訴訟で争うこととなり、住民訴訟の目的を逸脱する、と説明しています。(「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」2(1)イ再掲) |
【参考事例】
★土地区画整理事業における換地処分
| 土地区画整理法に基づく換地処分を住民訴訟の対象とすることは許されない 最判昭51.3.30集民117.337
(市施行の土地区画整理事業で市が換地処分により土地を取得したことは違法な財産の取得に当たるとして、当該処分の取消しを求める住民訴訟) ○ 地方自治法242条の2所定のいわゆる住民訴訟の対象となるものは同法242条1項所定の地方公共団体の執行機関又は職員による同項所定の一定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実に限られるものであり、これと同旨の見解のもとに、被上告人が…土地区画整理事業の施行者としてした各行為の取消しを求める本件訴えが同法242条の2に定める住民訴訟の定型に該当せず不適法である、と判示。 |
★自治体を受贈者とする贈与
| 自治体を受贈者とする贈与契約は、地方自治法(旧)243条の2第4項所定の住民訴訟の対象とならない 最判昭48.11.27集民110.545
(住民を贈与者、町を受贈者として締結された金員贈与契約が違法であるとする住民訴訟) ○ 昭和38年法律第99号による改正前の地方自治法243条の2第4項に基づく住民訴訟は、法律の定める限度で許される訴訟であって、旧法243条の2第1項掲記の行為に徴すると、公金の支出、義務の負担ないしは財産上の損失を伴わない単なる収入を発生させるにとどまる行為は、かりにそれが違法な場合であっても、同条4項所定の住民訴訟の対象とすることはできないものと解するのが、相当である。 |
(2) 財産の管理・処分
ア 総論
財産の管理・処分は、一般に、財産についての財産的価値に着目し、その価値の維持、保全、実現という財務的処理を直接の目的とする執行機関または職員の行為とされます(参照:上記1掲載平成2年最判。また参照:地方財務実務提要、実務住民訴訟p.136、下記平成9年宇都宮地判。松本逐条の定義については、「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」2(3)イ参照)※、※※。
なお、上記の「財務的処理を直接の目的とする」ことについては、上記平成2年最判で示された財務会計行為等とそうでないものの切り分け判断のポイントとなるものであり、よって財務会計行為全般にわたる判断枠組みとなるものですが、同判決は財産管理行為について扱った事案であるため、とりわけ本項においては重要なものとなります。
| ※ ちなみに、自治体の財産と同様の法的規制がされる国有財産について、国有財産法9条の5で「管理及び処分の原則」として「各省各庁の長は、その所管に属する国有財産について、良好な状態での維持及び保存、用途又は目的に応じた効率的な運用その他の適正な方法による管理及び処分を行わなければならない」と規定しており、国有財産法は、国有財産の公物管理法(行政財産の公物としての規律を定める)としての位置づけは弱く、むしろ行政財産の財産的側面に着目した規律とする考えがあることを踏まえれば(参照:塩野Ⅲp.388)、地方自治法242条1項にいう財産の管理・処分は、この国有財産法9条の5に例示される作用(行為)が中心的概念になり、上述2(2)アの公物管理権はこれに含まれないとすることが、厳密ではないにせよ、いささかなりとも分かりやすい概念整理手段となるのではないかと考えます。 |
| ※※ 地方財務実務提要において、違憲の公選法改正による選挙について、監査委員は同法を違憲と判断し、選挙のために公共施設を使用させないよう首長に求める住民監査請求の適法性に関する設問で、違憲判断は監査委員の職務にはなじまないものであるが、それはさて措き、一般に公共用物の管理とは、公共用物の管理者が、公共用物としての本来の機能を発揮させるためにする一切の行為をいうとし、公共用物の本来の目的は、一般公衆の利用に供することにあり、その機能を発揮させるための作用が公共用物としての管理の特色であることであり、常に物を財産的価値の客体として管理することとは別の範疇にあるとしています。 その上で、住民監査請求の対象となる財産の管理とは、財産的価値の維持保全を目的とした行為なり事実であり、公共用物の目的を達成させるための積極的、消極的作用は、原則として住民監査請求の対象とはなり得ないと考える、としています。そして、設問については、財務会計上の財産の管理の領域に属するとは解されず、住民監査請求の対象とはなり得ないのではないかと考える、としています。 |
なお上記平成2年最判の枠組みを適用するにあたって、公の目的に供される財産(公物)、たとえば道路などを、その目的に沿って適切に使用できるようにする管理行為(公物管理権に基づく行為、たとえば道路を適切に運用するための、所要の工作物設置や障害物排除などの管理行為)が監査対象となり得るかが、しばしば問題となります(公物管理権については、上記2(2)ア①昭和52年東京高判(田子の浦ヘドロ訴訟)説明参照)。
この点について、上記2(2)ア①※6でも説明した通り、一般にこうした行為等は、住民監査請求の対象としての財産管理行為には該当しないとされています(あわせて上記※※も参照)。
ただし、こうした行為等が自治体財産の価値に直接の影響を与える(たとえば道路に使用する自治体所有地の価値を毀損するような物件を排除することを怠る等)場合は、住民監査請求の対象としての財産管理行為の問題となり得るとされています(各論的な詳細は、下記イ以下で主な類型別に説明)。
雑駁な説明ですが、公物をどのように利用するか、ということは、政治的・行政的な判断そのものであり、一方で、公物を通常の利用形態を実現できるように管理をすることにより、その財産的な価値そのものに影響を与えることは、普通はないと考えられます。(上記※※が分かりやすい例であるように、公共施設をどのように利用するかは行政的判断そのものであり、通常の利用形態である限り、たとえそれが違法不当な利用の場合、たとえば詐欺集団の勧誘会と分かっていて公共施設を利用させたとしても、それにより施設の財産的価値に影響が生ずるものではないことは明らかです)。
また財産には公共用施設などの有体物、つまりハードウェアもあれば財産たる権利のようなソフトウェアもありますが、公物の住民監査請求の対象たる財産管理とは、ハードウェアとして存在する有体物を財産としての面から観察して、その価値の維持保全を図る行為というものであるところ(上記1平成2年最判参照)、公物管理権による管理は、公物が社会的公共的な機能を果たすことを予定されるものであることを前提に、そのソフトウェアとしての機能が合目的的に発揮されるようコントロール・マネジメントするための行為であり、その点において、ハードウェアとしての物の価値自体を維持する目的の行為とは異なるものです(上記2(2)ア①※6参照)。
つまり、一般には公物管理行為は、地方自治法242条1項の財産管理行為にはあたらない、とするのが、裁判例等を通じた一般的な理解となっているものと考えます(詳細は、下記イ以下の各主要類型別の説明もご覧下さい)。
ただし、財産の管理作用を概念的にとらえれば、上記の財産管理作用とそれ以外の作用、つまり財産の機能管理作用に区分されるのですが、現実・実際の行政作用はこれらが一体となってなされるものも多いことでしょう。この場合は、行為内容を必要な単位にこれを分解して(上記1平成2年最判参照)、財務的処理を直接の目的とするものについてのみ適法な住民監査請求の対象と判断すべきこととなります※。
| ※ なお最新地方自治法講座p.229(佐藤英善)は、最判昭57.7.13民集36.6.970(いわゆる田子ノ浦ヘドロ訴訟)の判示事項(汚染ないしヘドロ堆積等の除去に要する費用の支出につき、①自治体が行政上当然に支出すべき部分、②自治体がその行政裁量により特別の支出措置を講ずるのを相当とする部分、③汚水排出者の不法行為等による損害の填補に該当し終局的には当該汚水排出者に負担させるのを相当とする部分、に区分)も念頭に、財産価値管理(財産保全)作用と機能管理作用(公営造物作用)が明確に区別しがたいこと、それを無視して観念的にしかも厳格に両者を区別し公物管理は本号請求の対象にならないとするのでは、3号訴訟の意義は大きく没却することから、公有財産の管理の形態に即してその財産保全的側面を抽出して3号請求の対象たりうるか否かを判断していくべきとし、たとえば公営造物管理であっても、その行政財産としての管理(公営造物管理)が杜撰なため、その外形や機能が失われるような管理は3号訴訟の対象となるべきとし、純粋に公営造物管理の場合は原則として3号訴訟の対象にはならないが、それが財産的損失と関連する限りでは、3号訴訟の可能性をケース・バイ・ケースで判断していくべきこととなろう、と指摘しています。 またこれとは逆に財産管理対象範囲の制限する方向での論旨ですが、上記田子ノ浦訴訟最判では、汚染ないしヘドロ堆積等の除去又は予防のために講ずべき浚渫作業又は施設の設置・改善等の措置、そのために支出すべき費用及びその分担についてはなお公物管理権者の合理的かつ合目的的な行政裁量に委ねられている部分がある(行政裁量により特別の支出措置を講ずることが許されることもある)と判示しているところ、これは怠る事実の対象となる財産管理行為について財産管理行為と公物管理行為のクロス・オーバー部分の分解に関する判断事例ととらえることができるでしょう。 |
【参考事例】
★土地区画整理事業における保留地の処分(財産的価値に着目し財産処分性を肯定)※※
| 市がその施行する土地区画整理事業において土地区画整理法96条2項、104条11項に基づいて取得した保留地を随意契約の方法により売却する行為は、住民訴訟の対象となる「財産の処分」及び「契約の締結」に当たる 最判平10.11.12民集52.8.1705
(市が土地区画整理事業の保留地として取得した土地につき、本件事業の施行規程所定の要件がないのに随意契約の方法で売却した違法及び時価より低廉な価額で売却した違法があるとして、市長を被告に提起した4号住民訴訟) ○ 普通地方公共団体の所有に属する不動産の処分は、当該不動産が当該普通地方公共団体の住民の負担に係る公租公課等によって形成されたものであると否とを問わず、同法242条1項所定の「財産の処分」として住民訴訟の対象になるものと解される。また、右の不動産について売買契約を締結する行為は、同項所定の「契約の締結」に当たり、住民訴訟の対象になるものと解される。 |
| ※※ 上記(1)掲出の昭和51年最判は、本件と同じく土地区画整理事業について争われ土地区画整理事業における換地処分を住民監査請求の対象なる財務会計行為と認めなかったところですが、本判決において同じ土地区画整理事業でも保留地の処分を住民監査請求の対象としたのは、平成2年最判の判断枠組みを基礎として、対象物の財産的価値に着目した財務的処理を目的とする行為かどうか、という判断によるということになります。 |
★決算添付書類としての財産調書の作成(財産管理行為該当を否定)
| 地方自治法242条1項にいう「管理」とは当該財産の財産的価値そのものの維持、保全又は実現を直接の目的とする運用を指すものと解され、管理者が実体的管理に付帯してこれを帳簿に記録することは財産の管理に含まれるが、決算の添付書類としての財産に関する調書を作成することは同法242条1項にいう財産の管理には当たらないとした事例 宇都宮地判平9.5.28判例時報1646.60
(決算に添付する財産に関する調書の誤りを修正しないことが違法に財産の管理を怠る事実に該当するとして違法確認を求める住民訴訟) ○ 地方自治法242条1項にいう「管理」とは、当該財産の財産的価値そのものの維持、保全又は実現を直接の目的とする運用を指すものと解され、管理者が実体的管理に付帯してこれを帳簿に記録することは、実体的な管理を十全にするものであるから、財産の管理に含まれるというべきであるが、決算の添付書類としての財産に関する調書を作成することは、同法170条2項5号の記録管理それ自体ではなく、財産の記録に基づき、別途報告用の文書を作成することに過ぎず、財産の維持、保全又は実現という観点に照らすと、二次的、間接的な運用というべきであるから、同法242条1項にいう財産の管理には当たらない。 |
★公共施設の用途廃止(財産管理行為該当を否定)
|
市の公共施設について建物の用途廃止を行い行政財産から普通財産に転換の上売却し、当該建物を借り受ける内容のセール・アンド・リースバックを締結したことにつき、当該建物について当該施設としての使用を継続したまま行政財産としての用途を廃止することは違法、無効であるなどと主張して本件用途廃止が無効であることの確認を求めた2号訴訟において、これは公共施設の使用可能性及び行政内部における管理区分上の分類に関する措置ないし判断であって、本件の土地建物の不動産としての財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の財産管理行為には当たらないとした事例
京都地判令元.5.24 ○ …本件用途廃止は、被告○市長が、被告○市の所有に属する本件土地建物について、公有財産として公共の用に供することをやめること、すなわち、行政財産(公共用財産)を普通財産とすることを決定するものであるが、これは、公共施設の使用可能性及び行政内部における管理区分上の分類に関する措置ないし判断であって、本件土地建物の不動産としての財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の財産管理行為には当たらないと解するのが相当である。 ○ 原告は、公共用財産の用途廃止により、当該財産が住民の利用に供されなくなるという不利益が生ずると主張するが、住民による当該財産の利用可能性に影響を及ぼす行為であることをもって直ちに、これが財務会計上の行為に該当すると解することはできない。また、原告は、本件用途廃止が行政財産から普通財産へと公有財産の性質を変更させる行為であるから、財務会計上の行為に当たるとも主張する。しかしながら、用途廃止により普通財産となった公有財産を処分する行為については、これをもって財務会計上の行為ということができるとしても、用途廃止それ自体は、公有財産を処分する行為ではなく、また、その財産的価値に着目して価値の維持、保全を図るという意味での財産管理行為にも当たらないことは、上記に判示したとおりである。 ○ 以上によれば、本件用途廃止は、財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為に当たらないから、本件訴えのうち本件用途廃止の無効確認を求める旨の訴えは、不適法である、と判示。 |
以下では、財産管理行為のうち主な類型を取り上げ、裁判例に基づき説明します。
イ 道路管理(占用許可等は下記カ参照)
道路は身近な公共用物であるため、比較的事案が多いようです。
① 路線認定廃止等
路線の認定や廃止は、道路行政上の政策判断結果そのものであり、裁判例では、財務的処理の目的性の判断により、住民監査請求の対象としないとするのが一般のようです。
② 道路効用維持行為としての工作物設置、障害物排除(妨害物の排除)等
道路の効用を維持するために行う工作物設置、障害物排除等は、住民監査請求の内容としてみれば、道路の妨害物排除請求をその本旨とするものと解され、通常それは財産的価値の保全意図を含意するため、財務的処理を目的とする内容とも思えます。
ところで、この点について、裁判例の方向は次のようになっていると見受けられます(上記ア参照)。
○ 道路の効用維持を図るために行う工作物の設置や、障害物の排除は、道路の道路としての機能(交通流動路提供というソフトウェアとしての行政サービス)の維持という一般行政上の目的によるものであり、それにより財産としての不動産(等=ハードウェア)たる道路用地等の財務的処理(財産的価値の維持)を直接の目的とするものではないから、住民監査請求の対象となる財務会計行為・怠る事実ではない(住民監査請求の対象とならない)※1
| ※1 たとえば交通事故の危険が高いため、そうした危険性を低下させるべく、路側からの流入や反対車線への進入、Uターンを排除するためのフェンスを道路路側や中央線に設けたとして、それにより路側からの進入などを常としていた近隣住民等からすれば道路の利便性は低下することはあるかもしれませんが、フェンスの設置行為によって道路の財産的価値に影響を及ぼすものではなく、そもそもその行為が道路の財産としての価値の維持保全等を目的とするものでないことも自明でしょう。 |
○ ただし、道路に係る自治体の財産(自治体の所有する道路敷土地など)の価値を毀損する事情が見受けられる場合は、これらの行為等は住民監査請求の対象となり得る※2
| ※2 たとえば道路に堅牢なバリケードを築く、道路脇法面を掘り返し用地の使用に危険を生じさせる(このような事例でしょうか)、重量制限超過で舗装を大きく損壊する、などは、道路に係る自治体財産の価値を毀損するとされると判断される可能性が高そうです。 |
まず上記第1点について、一般的な工作物の設置や、とりわけ非固定的・非固着的な性質をもつ障害物の除去といった行為は、道路の効用をどのように維持するか、という道路管理上の理由からなされるものであり(これは上述の通り、道路という公共用物を通じて行政サービスとして提供するかというソフトウェア的機能の維持向上という政策的、行政的な目的です)、また上記のような工作物や障害物が一般に自治体の財産(道路敷土地等)の価値に影響を与えるものではないことから、上記平成2年最判の判断枠組みを踏まえ、裁判例では一般に、住民監査請求の対象となる財務会計性を否定しています。
一方で下記昭和54年東京地判では、道路境界の2メートル程度のフェンスでは、市が有する財産の財産的価値に変動が生ずるとは到底考えられない(これは、工作物の設置が道路に係る自治体財産の価値を毀損し得るという前提による判断ともいえる)ため、フェンス除去をしない不作為は道路行政上の管理の問題とし、平成6年岡山地判ではさらに直截に、障害物によって道路としての効用が妨げられているのみならず、道路敷地の土地としての財産的価値が減少しているような場合には、障害物の設置や障害物除去を怠ることが、自治体の財産的価値に影響を与える(毀損する)可能性はなくはない(ただし本件障害物除去の不作為は道路管理上の問題と判断)としていることからすれば、裁判例のベクトルとしては、一概に道路管理の問題が住民監査請求の対象とならない、というわけではなく、特に障害物の存在等により道路の自治体財産としての価値を毀損するような事情が見受けられるとなれば、道路管理上の問題を超えた財産権侵害の問題となり、よって住民監査請求の対象としての財産管理上の問題となり得る、と理解するのが適当と考えます(なお財務会計行為性を認める場合、道路管理上の問題というロジックではなく、自治体の財産権侵害、というロジックになる。そして当然ながら、それは監査対象物がその自治体の地方自治法237条1項の財産(自有地や地上権を有する土地に建設した等)であることが前提となる)。
たとえば令和2年前橋地判の事例※3など、そもそも環境基準を超える有害物質を含む材料を道路工事(工作物設置と類似)に使用し、結果として有害物質が道路工作物の一部として固定固着しているのであり、一般的な障害物妨害物の排除とは異なるという事情があることからも(道路に妨害物があり道路の効用が妨げられているのではなく、道路構造物に有害物が含まれているので、道路行政上の道路管理問題ともいいがたい)、同判決は、このような環境基準を超える有害物質の放置は、公有財産たる市道の財産的価値を毀損するという前提を置いて判断しているものと推測されるところです。
| ※3 令和2年前橋地判では、撤去請求権は所有権に基づく妨害排除請求権※4に基づくものであり、財産権に他ならない、としており。その論法による限り、住民監査請求の対象として取り上げ得るロジックとなります。そして、たとえば自有公物であれば、物権的請求権としての妨害排除請求権は一般に主張可能です。しかし本件のような事例を除く一般的な障害物排除等の事案においては、その管理作用は行政上の目的(適切な行政サービスの提供維持)で行われる道路管理行為(非財産管理目的行為)と一般にみなされており、その限りにおいて財産権的請求権である妨害排除請求権の出番はなく、自治体の財産的侵害が認められるケースでの撤去請求権の論拠においてのみ、妨害排除請求権の出番がある、と考えた方がよさそうです。 |
| ※4 蛇足ですが、適法に市道として供用開始されたと認められる道路について、敷地所有権はさておき(市有地かどうか紛争がある)、道路管理者として、その土地の管理権に基づき道路上の妨害物の撤去を求めることができるとする事例(最判平8.10.29民集50.9.2506)や、市道として供用される道路敷土地の寄附を受けた国が移転登記していなかったところ、その土地の所有権移転登記がされ、所有者を主張する者から市へ道路敷の買取要求がされたが、市が拒否したところ、その者が市道の通行を妨害する態度に出たため、市が民法199条の占有訴権に基づき妨害予防の訴えを提起した事案について、最高裁は、自治体が道路を一般交通の用に供するために管理しており、その管理の内容、態様によれば、社会通念上、当該道路が当該自治体の事実的支配に属するものというべき客観的関係にあると認められる場合には、当該自治体は、道路法上の道路管理権を有するか否かにかかわらず、自己のためにする意思をもって当該道路を所持するものということができるから、当該道路を構成する敷地について占有権を有する、と判断した(最判平18.2.21民集60.2.508。なお本件は、原審が市の占有権を認定しなかった判断を最高裁が是認せず破棄差戻としたもの)事例がありますが、こうした論拠による妨害物排除行為を住民監査請求の対象(財産管理行為)となし得るかは、疑問があると考えます(前者は、住民監査請求の対象としての自治体の財産権の存在を前提としておらず、後者は結局占有権や国有地の使用借権であり、住民監査請求の対象となり得る自治体の財産ではない(上記2(2)ア参照)))。 |
以上をまとめれば、住民監査請求の実務においては、道路効用維持のための工作物設置や障害物除去等の行為は、一般には住民監査請求の対象としての財産管理行為に該当しないものの、それらによって自治体の財産価値を毀損するような事情が生じてないかについて、検討をすることが適当と考えます(ただし、下記③の不法占有と比べれば、財産価値毀損の例は少ないものと考えられますので、念のためのものとなりましょう)。
③ 不法占有
道路敷の不法占有の問題について、国有地を道路法施行法5条により借り受けた道路敷の不法占有の排除を怠る事実の違法確認は、裁判例においては、自治体の自有財産ではなく、また用地使用権原は地方自治法238条1項4号の用益物権にも該当しないとされているため、財産管理行為にあたらず、住民監査請求の対象外とする方向での判断が重ねられているようです(上記②の※※参照)。
一方で道路敷が自治体所有の場合は、統一的な判断のベクトルが見出しづらい状態です(肯定:平成15年東京高判、平成20年さいたま地判は、道路所有権の阻害が生ずるので、財産管理上の問題が生ずるとする。否定:平成8年東京高判は、普通財産や公用財産は左記肯定の理論が妥当するが、道路等の公共用財産については住民監査請求の対象にはならないとする)。
この点について、住民監査請求の実務においては、「公有財産を不法に占有されているにもかかわらず何らの是正措置を講じない」場合を財産の管理を怠る事実の例としてあげる行政実例(昭38.12.19)も踏まえれば、自治体所有地上の道路(地上権を権原とするものでも同様と考えます)について、自治体財産権の侵奪性(自治体の財産権を長期・固定的かつ排他的に第三者のものとするような性質を有する行為・事実状態があるかどうかということ。終局的には、取得時効を主張されかねないような状態など)が認められるような不法占有がある場合には、占有排除は財産管理行為であり住民監査請求の対象とすることが適当と考えます。
なお、不法占有に伴い発生する占有料相当額の不当利得返還請求権(損害賠償請求権)は、地方自治法上の財産である金銭債権であり、その管理は財産の管理として財務会計行為等に該当するとされます(参照:最判平16.4.23民集58.4.892、判例行政法p.16(石津廣司))。
【参考事例(肯定)】
| 公有財産たる道路敷地が広範囲かつ恒常的に不法占有されている場合は、道路管理権行使の支障にとどまらず敷地の所有権行使阻害すなわち財産権管理の問題となり、明渡請求権の行使の有無は損害賠償請求権又は不当利得返還請求権の管理の問題ともなるとした事例 東京高判平15.4.22判例時報1824.3(町道上の町有地の並木敷を権原なく広範囲かつ恒常的に占有・利用しているにもかかわらず、明渡しを求めず、また占用料相当額の不当利得返還請求をしないのは、違法に財産管理を怠っているとして、町に代位して建物収去土地明渡、不当利得返還等を求める4号住民訴訟)
○ 道路法上の道路の利用に関する法律関係は、道路法上の道路管理者が道路敷地について権原を取得して、これを利用者の利用に供するものである。そうすると、第三者が道路の敷地を占有する場合には、場所的に狭く、時間的に恒常性がないなどの限局的、一時的な場合は別にして、それ以外は、一般的に道路が本来の目的に供されないことになり、道路管理権の行使に支障をもたらすことになるとともに、道路敷地の所有権の行使が阻害されることになるので、敷地の財産権の管理の問題ともなる。 |
| 市有地である道路の不法占有につき、本件道路と原告らの土地と不法占有者の土地との境界を確定しないこと及び不法占有者に明渡請求等をしないことの違法確認を求めた住民訴訟において、道路敷地の占有は道路管理の問題にとどまらず所有権行使阻害により道路の財産管理の問題を生ずることとなるので、占有の場所的な広がりおよび恒常性があれば、境界を明確にしないことや占有者に対し明渡請求等を怠ることは住民訴訟の対象となるとした事例 さいたま地判平20.1.30判例地方自治307.82(原告らの土地に隣接した市有地である道路がAらに不法占有されているとして、市長に対し、本件道路と原告らの土地とAらの土地との境界を確定しないこと及びAらに明渡請求等をしないことの違法確認を求めた住民訴訟)
○ 第三者が本件道路(法定外公共用物としての里道)を占有する場合には、道路が本来の目的に供されないことになるので、道路管理権の行使に支障をもたらすことになり、第三者が道路を排他的に恒常的に占有するような場合には、それは単に道路の管理にとどまらず、道路に対する所有権の行使が阻害されることになるので、財産の管理の問題が生じることになる。 |
| 市道施工に使用した鉄鋼スラグに基準超の有害物質を含む場合の鉄鋼スラグ撤去請求権は公有財産たる市道の所有権による妨害排除請求権に基づくものであり、この撤去請求は財務会計上の行為に該当するとした事例 前橋地判令2.8.5判例地方自治473.71(A社排出の鉄鋼スラグを使用して市道工事を施工したが、この鉄鋼スラグを含む採石から基準値を超える有害物質が検出されたため被覆工事をしたところ、住民から提起された、A社に対し本件市道上の鉄鋼スラグの撤去請求をすることを怠る事実の違法確認を求める住民訴訟)
○ A社に対する本件スラグの撤去請求権は、市の公有財産である本件市道の所有権による妨害排除請求権に基づくものであり、財産権にほかならないのであるから、上記撤去請求は、本件市道の土地としての財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする行為(権利行使)であると認めるのが相当である。したがって、A社に対する本件スラグの撤去請求は、財務会計上の行為に該当する、と判示。 |
【参考事例(否定)】
| 市有道路敷と私有地の境界に設置されたフェンスにより周辺住民が道路使用に不便を感ずることがあり道路の効率的運用が妨げられているとしても、フェンスによって市有財産の財産的価値に変動が生ずるとは到底考えられないので、フェンスを除去しない不作為は専ら道路行政上の管理の問題に過ぎず、住民訴訟の対象とはならないとした事例 東京地判昭54.12.20行裁例集30.12.2047
(市道と住民私有地の境界に設置されたフェンスについて、フェンスを除去しないことは違法に財産を怠るとする住民訴訟) ○ フェンスが道路敷地と原告所有土地との境界線上に設置された金網状のフェンスで高さが1.8メートルないし2.2メートルのものであるが、このような形状のフェンスが存在するか否かによって道路敷地について市が有する財産の財産的価値に変動が生ずるとは到底考えられないのであるから、本件フェンスを除去しないという不作為によって本件道路周辺の住民がその使用にあたって不便を感ずることがあり、本件道路の効率的運用が妨げられているとしても、本不作為は専ら道路行政上の管理の問題であって住民訴訟の対象たりえない。 |
| 道路区域変更処分は、道路法に基づく公物管理のための行為であって道路として管理される区域を明確にすることを主眼とするものであり、財務的処理すなわち公有財産の財産的価値に着目して行う管理行為とは性質を異にするものであり、住民訴訟の対象となる財務会計上の行為にあたらないとした事例 浦和地判昭55.4.28行裁例集31.4.1039(道路区域変更処分の無効確認等を求める住民訴訟)
○ 道路法18条1項に基づいて行われる道路区域の変更処分は、道路を構成する敷地の幅員及び長さによって示されている従来の道路の区域に新たな区域を追加し、又は道路の区域の一部もしくは全部を廃止してこれに代るべき新たな道路区域を決定するという一連の手続行為を行う行政処分であり、道路の一部を変更する場合は、路線の起点、終点又は重要な経過地点を変更する場合を除き、すべて道路区域変更によってなされるものであって、その本質は全体として道路区域の決定と同じく道路の範囲を変更して新たに確定する行政上の確認行為と異なるものではない。 |
| 道路法に基づく市道の路線の廃止若しくは認定、区域の決定若しくは供用の開始又はこれらの公示は、円滑な道路交通の確保及び発達という非財務的見地から行われる道路行政上の行為にほかならず、道路施設の財産的価値の維持、保全又は実現を目的とするものではないから、地方自治法242条の2に規定する住民訴訟の対象とならないとした事例 東京地判昭55.10.9行裁例集31.10.2069○ 本件取消請求の対象である本件各処分は、道路法に基づく路線の廃止、その認定、道路の区域の決定若しくは道路の供用の開始又はその旨の公示であり、それ自体としては、いずれも、円滑な道路交通の確保及び発達という非財務的見地から行われる道路行政上の行為にほかならず、道路施設の財産的価値の維持、保全又は実現を目的とするものではない。 ○ 本件の各市道は市の設置、管理する公の施設であるが、公の施設そのものは地方自治法にいう「財産」(同法237条)には当たらないから、その設置又は廃止のためになされる行為を目して当然に財務的なものであるということはできないし、また、本件各処分により、右公の施設としての市道を構成する道路敷地等の財産的価値に何らかの影響が生じ、あるいは、市において道路標識や安全施設の設置等の道路維持管理費の出費を余儀なくされることがあるとしても、そのことは本件各処分の本来的直接的な効果ではないから、それを理由として本件各処分が財務的性質の行為であるということもできないのである。 ○ 原告らは、本件各処分が本件公金支出(注:道路工事代金の支出)と密接一体の関係にあることを強調するが、右公金支出が違法であるとするならば、その支出自体を住民訴訟の対象とし、その過程において本件各処分を争えば足りるのであり、本件各処分までを右公金支出と不可分的に財務会計上の行為と解すべき根拠はない。 ○ そうすると、本件各処分は住民訴訟の対象となり得る行為には当たらないものであるから、本件取消請求にかかる訴えは不適法といわざるを得ない。 |
| 都が国から無償貸付を受けている都道敷の不法占有に対する管理上の措置は、専ら道路法上の(道路管理の側面からの)行政処分としてなされることを法は予定しており、都知事が右不法占有を放置していることは、財務会計上の怠る事実を対象とするものには該当しない(一方で不法占有者への損害金の徴収懈怠の違法確認請求は適法)とした事例 東京高判昭62.4.9行裁例集38.4・5.360○ 都道の使用を巡る都の管理行為に、観念上、道路法に基づく道路管理の側面と財産管理の側面とがあるが、道路の不法占有に対する管理上の措置はもっぱら道路法に基づく行政処分としてなされることを法は予定しているものと解するのが相当であり、その懈怠の違法確認を求める控訴人らの訴えは、財務会計上の怠る事実を対象とするものには該当しない。(本件原審東京地判昭61.3.4行裁例集37.3.257において「一般的には道路法71条による道路管理者としての権限に基づく監督処分としてこれをなすべき」)
※本件原審では「損害金の徴収懈怠の違法確認の訴えについて、被告は、道路管理上の管理の懈怠を論ずることになり、財務会計上の処理を直接の目的とするものではないから、不適法であると主張するところ、この訴えは都に損害金請求権という金銭債権が生じているのにその徴収を怠っているとして、その懈怠の違法の確認を求めるものであり、この金銭債権は地方自治法240条1項の債権にほかならないから、同法237条1項、242条1項の財産に該当し、その徴収の懈怠があれば、監査請求及び住民訴訟の対象とすることができるものである。同債権の発生原因が道路管理上の過怠の有無と関り合うものであったとしても、同債権が占用料徴収債権とは別個の一般不法行為法上の損害賠償請求権(占用料相当の損害金債権)として成立しうるものであるかぎり、その徴収の懈怠は財務会計上の怠る事実にほかならない」と判示。 |
| 道路使用により占有料が発生するにしても、道路管理権限に基づく妨害排除命令は占用料の確保や道路の経済的価値の確保・保存といった財務的処理を直接の目的として発せられるものとは認められないので、妨害排除命令に財務会計行為該当性を認めることはできないとした事例 大阪高判平元.6.14判例地方自治464.75(市有道路敷地を不法に占拠しているにもかかわらず市長がこれを放置していることが違法であるなどとして、土地の明渡請求又は妨害物の撤去命令の発出を怠ることの違法確認及び土地の地代等相当額等の支払請求をすることの義務付け、市長個人に対しての損害賠償請求等を求めた住民訴訟)
○ 控訴人は、道路については、その使用につき占用料が発生するから、道路の独占的占有や道路の損壊を伴う行為に対する妨害排除命令は、公用物の経済的価値の確保・保存という「財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為」であり、補助参加人に対する妨害排除命令の財務会計行為該当性を肯定すべきである旨主張する。 |
| 公道の用途廃止は、通常、住民の負担に転嫁されるような財務会計上の効果を生ずるものとは考えられず、住民訴訟の対象となる財務会計行為には当たらないとした事例 高知地判平5.4.23判例地方自治119.78(市がその所有に係る市道の一部を用途廃止したうえ他に売却したことが違法であるとして提起された無効確認(2号)住民訴訟)
○ 道路の用途廃止それ自体の効果は、市の内部における所管者・管理主体の変更であって、通常、住民の負担に転嫁されるような財務会計上の効果を生ずるものとは考えられず、弁論の全趣旨によっても、市に損害が生ずると認めるに足る事情は認められない。 |
| 市有地の市道上の容易に移動可能な障害物を除去しないこと及び未認定道路について市道路線の認定をしないことについて、障害物除去・市道認定行為はいずれも円滑な道路交通の確保のための道路行政上の行為であって財務的処理を直接の目的とする財務会計上の事項には当たらず(これによって道路としての効用が妨げられているのみならず道路敷地の土地としての財産的価値が減少しているような場合には障害物の除去は市有財産の管理行為に当たると解しうる場合があるが)住民訴訟の対象となる財産の管理を怠る事実に関する訴えとはいえないとした事例 岡山地判平6.7.27判例地方自治133.71(市道上の障害物(容易に移動可能等)を除去しないこと及び未認定道路について市道路線の認定をしないことの違法確認を求める住民訴訟)
○ 道路管理としての道路の障害物の除去は、円滑な道路交通の確保のための道路行政上の行為であって、財務的処理を直接の目的とする財務会計上の事項には当たらないから、地方自治法242条の2の住民訴訟の対象とはならない。(障害物によって、道路としての効用が妨げられているのみならず、道路敷地の土地としての財産的価値が減少しているような場合には、障害物の除去は市有財産の管理行為に当たると解しうる場合があるが、本件の場合は土地の財産的価値を減少させるものとはいえず、道路の各障害物を除去しないことをもって、住民訴訟の対象となる財産の管理を怠る事実があるとはいえない) |
| 町道敷を不法に占有する者に対して住民が町に代位して提起した明渡請求の訴えについて、道路等の公共用財産は元来個々の行政目的に従って一般公衆の共同使用に供されるものであり、その供用自体は単なる財産管理とは次元を異にする性質のものであるから、当該公共用財産の具体的な供用自体の回復という問題は、関係する個々の行政分野での行政権の行使の問題に属し、財務会計上の問題として住民訴訟の対象とすることはできないとした事例 東京高判平8.1.29(公有地上の道路を占有する鳥居等の撤去を求める住民訴訟)
○ 一般に、地方公共団体の所有する財産が第三者によって不法に占有された場合、当該地方公共団体の当該財産に対する支配が妨げられ、その財産的効用が害されることになるから、これにより地方公共団体が被る財産的損害の回復を図ることは財務会計上の行為であって、地方公共団体が右損害の回復のための措置を怠るときは、住民は、いわゆる住民訴訟により、地方公共団体に代位して、不法占有者に対し、損害賠償、妨害排除等の請求をすることができるものと解すべきである。しかしながら、地方公共団体の所有する財産の中でも、普通財産や、当該地方公共団体自身の用に供される公用財産については、その効用の侵害は純然たる財産管理の問題として全面的に財務会計的見地からの処理に委ねられるべきものと解され、これが不法占有されることによって地方公共団体の財産に生じた侵害の回復についても、専ら一般的・経済的な損失の回復という観点からのみ把握されるべきものであるのに対し、道路等の公共用財産は、元来個々の行政目的に従って一般公衆の共同使用に供されるものであり、その供用自体は単なる財産管理とは次元を異にする性質のものであるから、当該公共用財産の具体的な供用自体の回復という問題は、関係する個々の行政分野での行政権の行使の問題に属し、財務会計上の問題として住民訴訟の対象とすることのできない事柄というべきである。 |
| 国有地上の市道の不法占有について、本件道路敷の使用権は道路法施行法5条の使用借権であり地方自治法238条1項4号の財産にあたらないが、不法占有者に対する不当利得返還請求を怠る事実の違法確認については、不当利得返還請求権は金銭給付を目的とする権利であり、地方自治法242条1項の財産に該当するので、適法な請求とした事例 大阪地判平15.11.6判例地方自治270.95
○ 市が本件道路敷地を本件道路として使用する権利は道路法施行法5条1項に基づく使用貸借による権利であるところ、同項に基づく使用貸借による権利は、地方自治法238条1項4号にいう「地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利」に当たらず、同法242条の2第1項、242条1項にいう「財産」に含まれないものと解される。 (なお本判決は、本案の判断において、国有地の不法占有によって自治体に財産的意味での損失が生じることは一般的には考え難く、不法占有のため道路の占用の許可による占用料の徴収の可能性が損なわれているとしても、道路の占用の許可は、主として道路管理行政上の観点からされる行為であって、占用料の徴収の可能性を喪失すること自体によって、当該都道府県又は市町村に具体的な財産的損失を観念することはできないとも考えられる一方で、使用貸借契約に基づく権利も、現実には社会生活上重要な機能を果たしているから、一概に財産的価値がないということはできず、その機能・管理の態様いかんによっては、その対象土地が不法占有されることにより財産的損失が生ずることも全く観念できないというわけではなく、道路の占用の許可による占用料の徴収にも、道路の占用に対する対価的給付という財産的側面があると解することはできるところ、そのような占用料を徴収する機会を失うことは、当該自治体にとって、抽象的には財産的な損失ということも可能と判示) |
| 市道を廃止して道路敷を普通財産とした処分は、円滑な道路交通の確保及び発達という非財務的見地から行われる道路行政上の行為にほかならず、道路施設の財産的価値の維持、保全又は実現を目的とするものではないから、住民訴訟の対象となる財務会計行為ではないとした事例 横浜地判平19.5.30判例地方自治303.63(市道を廃止して道路敷を普通財産とした処分の無効確認を市長に求めた2号住民訴訟)
○ 市道廃止処分は、旧市道を廃止して道路敷きを普通財産としたうえで、A会社との間で本件土地交換契約を締結して当該道路敷き(本件市元所有地)とA会社元所有地とを交換し、これによって取得したA会社元所有地を道路として認定するといった一連の作用のうちの一つであるが、道路法に基づく路線の廃止、その認定、道路の区域の決定もしくは道路の供用の開始又はその旨の公示といった作用自体は、いずれも円滑な道路交通の確保及び発達という非財務的見地から行われる道路行政上の行為にほかならず、道路施設の財産的価値の維持、保全又は実現を目的とするものではない。 |
| 道路使用により占有料が発生するにしても、道路管理権限に基づく妨害排除命令は占用料の確保や道路の経済的価値の確保・保存といった財務的処理を直接の目的として発せられるものとは認められないので、妨害排除命令に財務会計行為該当性を認めることはできないとした事例 大阪高判令元.6.14判例地方自治464.75 (市有道路敷地を不法に占拠しているにもかかわらず市長がこれを放置していることが違法であるなどとして、土地の明渡請求又は妨害物の撤去命令の発出を怠ることの違法確認及び土地の地代等相当額等の支払請求をすることの義務付け、市長個人に対しての損害賠償請求等を求めた住民訴訟)
○ 控訴人は、道路については、その使用につき占用料が発生するから、道路の独占的占有や道路の損壊を伴う行為に対する妨害排除命令は、公用物の経済的価値の確保・保存という「財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為」であり、補助参加人に対する妨害排除命令の財務会計行為該当性を肯定すべきである旨主張する。 |
ウ 都市公園管理(占用許可等は下記カ参照)
都市公園に関する事案も比較的事例が多いところ、裁判例の方向は概ね上記イの道路と同じく、都市公園の管理に関する行為は、一般に住民監査請求の対象としての財産管理行為にはあたらない判断が積み重ねられているようです。公園をどのようにするのかは、本来、行政サービスのあり方という行政判断そのものの問題となるため、そのような判断となるものと考えます。
なお平成元年東京地判の事例など、記念碑の形状等からすれば公園の財産的価値に影響は及ばないことを理由としていますが、これも道路管理(工作物等)と判断ベクトルが近似するとも考えられます。
以上を踏まえれば、住民監査請求の実務においては、上記イの道路管理同様、公物管理権の行使に基づく行為は、住民監査請求の対象からは除外しつつも、公園の財産価値を毀損するような事情がないかについては、念のため検討をすることが適当と考えます。
【参考事例】
| 都市公園の管理および使用規制上の不作為は怠る事実の違法確認の対象とならないとした事例 東京高判昭54.5.24
○ 都市公園は、これを利用する住民の保健、休養及び教化に資することを目的とするものであるから、本件公園を管理し又はこれが使用を規制する行為は、普通地方公共団体の長が当該財産である本件公園の財産的価値の維持保全又は実現増殖を直接の目的とする行政行為には当らない。 |
| ある土地を都市公園区域から除外する都市公園区域変更処分は、その土地を都市公園法の定める公共目的達成のために用いるかどうかを定める同法上の処分であり、土地の財産的価値に着目し、財産的効果を生じさせること自体を法律上の目的とするものではないから、住民訴訟により無効確認、取消しを求めることのできる処分には該当しないとした事例 京都地判昭61.1.23行裁例集37.1・2.17(都市公園区域変更の処分を取り消すことを求める2号住民訴訟)
○ 地方自治法242条の2の住民訴訟は、地方公共団体における財務の適法性を守ることを目的とするものであるから、同条1項2号により無効確認、取消しの対象となる処分は、抗告訴訟の対象となる行政処分の性格を有していることのほかに、その処分が法律上、物の財産的価値に着目し、それ自体で財産的な効果を生じさせることを目的としてされるものでなければならない。 |
| 公園内に設置された記念碑を撤去しないことは公園管理を怠った違法があることを確認する住民訴訟において、記念碑を撤去すべきかどうかは行政的管理上の問題であり財務的管理上の問題ではないから不適法であるとした事例 東京地判平元.6.23行裁例集40.6.603○ 住民訴訟の制度は、専ら地方公共団体の公金、財産等に関する財務会計上の違法行為又は怠る事実の是正を目的とするものであって、行政に対する一般的な監督の制度として、行政上の違法行為一般の是正を目的とするものではないから、住民訴訟の対象とされる「違法な行為又は怠る事実」とは、公有財産の財産的価値に着目してその価値を維持保全する財務管理についての違法な行為又は怠る事実をいうものと解すべきであり、公有財産のうち行政財産をその公用又は公共目的に沿って管理する行政管理に係る行為又はその管理の懈怠は、住民訴訟の対象となり得ない。 ○ 本件使用借権(注:国有地を公園敷地として無償貸付)ないし本件公園が住民訴訟の対象となる財産に該当するとしても、本件記念碑の形状、設置場所からすれば、本件記念碑が設置してあることによって本件使用借権ないし本件公園の財産的価値に影響が及ぶと考えることはできないから、結局、本件記念碑を撤去すべきかどうかは、使用借権等の財産的価値の維持保全を直接の目的とする財務的管理上の問題ではなく、本件公園を設置した行政目的を達成、維持するための考慮に基づく本件公園の行政的管理上の問題であるといわざるを得ない。 ○ よって、本件訴えは住民訴訟の対象とならない行為又は事実を対象とするものであり、不適法なものといわなければならない、と判示。 |
エ 学校管理(用途廃止)
下記は学校校庭用途廃止決定に関するものですが、このような決定は、平成5年浦和地判判示の通り、財務的処理を目的とするものではないとされています。おおむねこの種の用途決定等は、学校財産に限らず、公共施設等の機能の運用行為である限り、原則的に住民監査請求の対象とならないものとすることが適当であると考えます。
【参考事例】
| 市が賃借していた土地についてした小学校の仮運動場としての用途を廃止する決定は、財務会計上の行為とみることはできないとした事例 大阪高判昭62.7.16行裁例集38.6・7.561○ 本件廃止決定は、本件土地の仮運動場としての用途を廃止することを内容とするものであって、仮運動場としての使用を目的とする私法上の使用借権を土地開発公社に返還する旨の内部的な意思決定であるにすぎないから、財務的処理を直接の目的とするものではないというべきである。
※本件原審 大阪地判昭57.3.24行裁例集33.3.564 |
| 校庭の用に供する土地の用途廃止決定は、教育委員会が職責とする教育行政上の観点から行われるものであって、教育財産の財産的価値に着目し、その維持、保全又は実現を直接の目的とするものではないから住民訴訟の対象となる財務会計行為には該当しないとした事例 浦和地判平5.7.19行裁例集44.6・7.621○ 被告は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第23条第2号(平26法76改正により現在は21条2号)、同法第28条第1項により、市長の総括のもとに市の教育財産の管理をしているが、この管理行為は被告が職責とする教育行政上の観点から行われるものであって(同法第23条)、教育財産の財産的価値に着目し、その維持、保全又は実現を直接の目的とするものではないから住民訴訟の対象となる財務会計行為には該当しないものである。 ○ 原告らが本件訴えによって差止めを求めている本件教育財産の用途廃止決定は正にこのような教育行政上の観点から行われる管理行為なのであるから、住民訴訟の対象となる財務会計上の行為ということはできない。したがって、原告らの本件訴えは住民訴訟の対象とすることのできない事柄を対象とするものであるから不適法というべきである、と判示。【注】 注:本判旨を字義通りに解すると、地教行法(現)21条2号、28条1項による教育財産の管理行為がすべて住民監査請求の対象となる財務会計行為としての性格を有しないともとれますが、そのように解することには疑問があります。本条による権限と地方自治法149条6号の財産管理権限は同質のもの、つまり本条の財産管理権限は自治法149条6号首長権限の控除的な法定権限移転というしかなく(参考:松本逐条149条関係、松本要説p.444、木田宏(著)教育行政研究会(編著)「第四次新訂 逐条解説 地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第一法規(2015年)p.199)、本判旨の表面的解釈をそのまま是認すれば、逆説的に、前記地方自治法149条6号による首長の財産管理行為も、すべて財務会計行為性を否定されることになるからです(いうまでもなく、地方自治法149条6号による財産管理行為が、地方自治法242条1項の財務会計行為性を全面的に否定されることは、あり得ないことです)。本判旨は、地教行法21条2号等による教育委員会(関係職員)の行為のうち、教育財産用途廃止等の教育行政上の目的による行為は、という留保が当然に含意されているものと解するべきです。 |
オ 物品管理
物品の利用に関し、下記のような裁判例があります。本例のような、物品の通常の管理利用行為に関する限り、物品の財産的価値に影響を与えるものではないので、原則的に住民監査請求の対象となる財務会計とはならないものとすることが適当であると考えます。
【参考事例】
| 教委のカセットテープ購入、君が代録音と学校配付は、教育委員会職員が教育の円滑実施と運営を図るという教育行政の見地からする教育行政担当者としての行為であり、本件テープの物品としての財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の財産管理行為に当たらないし、テープを教育委員会から学校長に公的に配付するのは物品所管換えにすぎず、これにより市に損害は生じないし、かかる所管換えは財産処分にあたらないとした事例 京都地判平4.11.4判例時報1438.37○ カセットテープを、君が代を録音して小中学校の校長に配付する目的で購入し、テープに君が代を録音し小中学校長に配付し、本件テープの君が代を消音して、新たな録音をすることは、録音した君が代がその目的を達した時までは許されていなかったものであるところ、購入したテープに教材として何を録音するかとか、録音されたものの消音を認めないとかいう問題は、財務会計上の行為とはいえず、教育委員会の職員が教育の円滑実施と運営を図るという教育行政の見地からする教育行政担当者としての行為であり、本件テープの物品としての財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の財産管理行為に当たらない。 ○ 本件テープは市教育委員会から小、中学校の校長に、公的に配付されたものであるから、これは市内部の機関相互の物品の所管換えにすぎない。物品を内部の部局から他の部局へ所管を移したとしても、市が物品を保管していることに変わりはなく、これにより損害を生ずることもないし、そもそもこのような所管換えは、地方自治法242条第1項の財産の処分に当たらない |
| 原発予定地の公有水面埋立許可に関する事務を違法として関係文書の作成送付に要する職員給与や作成送付経費の返還を首長に求める4号訴訟において、給与費支出は本案審査を行う一方、切手用紙等の消費については、それ自体、金額はともかく、何らかの費消がなされたという意味では財産の処分といえなくもないが、費消された切手や用紙等は、いずれも一般的な目的で自治体が所有していたものであると解され、本件郵送及び本件各作成業務という一般行政上の行為に伴ってそれが費消されたにすぎず、郵便切手や用紙、インクといった物品について、その財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の財産管理行為がなされたとは認められないとし、この部分の請求は財務会計行為を対象としない不適法なものとした事例 山口地判令6.11.6
○ 以上(注:最判平2.4.2)を前提に、本件各支出等が住民訴訟の対象となる財務会計行為に該当するか否かを検討すると、本件各支出等のうち、予算執行権を有するA知事による本件各給与支出については、地方自治法上の「公金の支出」に該当する行為であるといえるから、一応、本件各給与支出が当該財産の財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図るものであるといえる(なお、本件各給与支出につき、日時、支出額等が具体的に特定されているとはいい難いが、給与の支出自体は、本件各審査作成業務という一般行政上の行為とは別個独立した財産上の行為であることが明らかであるから、財務会計行為の該当性を認めるに差し支えない。 )。 ○ 他方、本件各支出等のうち、切手の消費及び用紙等の消費については、それ自体、金額はともかく、何らかの費消がなされたという意味では財産の処分といえなくもないが、費消された切手や用紙等は、いずれも一般的な目的で普通地方公共団体である○県が所有していたものであると解され、本件郵送及び本件各作成業務という一般行政上の行為に伴ってそれが費消されたにすぎず、郵便切手や用紙、インクといった物品について、その財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の財産管理行為がなされたとは認められないと解するのが相当である。 ○ そうすると、 本件訴えのうち、 本件各給与支出の違法を前提とする部分は、それ自体が財務会計行為を対象とした適法なものであるし、この部分については、原告らは適法な監査請求を前置したといえる。他方で、本件訴えのうち、切手の消費及び用紙等の消費の違法を前提とする部分は、それ自体財務会計行為を対象としない不適法なものであるし、この部分について、原告らは適法な監査請求を前置していたとはいえない(なお、用紙等の消費については、前提事実…のとおり、そもそも本件監査請求において、何らかの措置を講ずべきことが請求されていたとは認めがたい。 )から、却下を免れない。 |
カ 行政財産の使用許可・使用料減免
○ 占用許可(特許使用)
行政目的の達成という行政上の見地からなされるものであり(参照:平成元年東京地判)、住民監査請求の対象としての財産管理行為にはあたらないとされます(たとえば道路や都市公園に電柱を立てたり水道電気通信ガス管を引いたり地下鉄の駅路線を敷設するのは、多くの場合、そこを利用するしかないからであり(民有地にそんなものが簡単に造れるなら苦労はしない)こうした行為に財産運用的な要素が見いだせるとは考えづらいところです)。
○ 目的外使用許可
松本逐条242条関係では、違法又は不当に財産の管理を怠る事実の例として「行政財産を目的外に使用許可させている場合に許可条件に著しく反する使用がなされていることを黙過している場合」をあげています。こうした例は格別として、目的外許可の事例は、裁判例によって判断が分かれるところがあります。これは、目的外使用許可に、行政目的達成のための公物管理的な側面と、財産管理的な側面が併存しているから、と考えられます(対象となる行政財産の効用を増すために、行政財産の機能を阻害しない範囲で使用許可を与えるのは、公物管理的な行為といえるし、財産そのものの運用的な行為である場合は財産の価値を利用するものであるため財産管理的な行為といえる)。
なお裁判例では、住民監査請求の対象としての財産管理行為に該当しないとするのが一般と見受けられますが、一方で、行政財産の効用維持増進という観点を超えて、普通財産の貸付に近い、財産そのものの運用的要素が見られる場合は、住民監査請求の対象となるとするもの※もあります。なにをもって運用的要素が見られるというのかは、難しいところがありますが、住民監査請求の実務においては、こうした要素を考慮して判断することが適当と考えます(参考:下掲平成5年東京地判、またあわせて上記松本逐条想定例)。
| ※ なお下記裁判例のうち、平成20年大阪地判の例は、遊休地活用的要素があるため、ある意味分かりやすいものですが、昭和61年浦和地判の例は、結婚式場仕様の公共施設の事実上の全部委託の事案であり、財産運用的な事案という意味では、平成20年大阪地判事例と類似しますが、指定管理者制度がない時代の事案でもあるため、当時の判断としてはともかく、今日的には例外的事案の性格といえるとも思われます。 |
○ 使用料免除処分
使用料は金銭債権そのものであることから、一般に住民監査請求の対象とされており、また、行政財産に関し発生する損害賠償請求権等の請求についても、これら請求権は金銭債権であり、地方自治法242条1項の財産なので、その請求をどうするかは、住民監査請求の対象である財産の管理行為に該当するとするのが一般です。
| 本項について参考:判例行政法p.14(石津廣司)、碓井p93、実務住民訴訟p.138 |
【参考事例:財産管理該当性を肯定したもの】
| 市民会館の使用許可が住民訴訟の対象となる財務会計上の行為に当たるとした事例 浦和地判昭61.3.31判例時報1201.72(結婚式挙式用に設計建設された行政財産たる市民会館について結婚挙式事業者に対してした目的外使用許可を取り消す等を請求する住民訴訟)
○ 公の施設の管理には、その本来の設置目的を達成するための見地からなされる行政上の管理とその財産的価値に着目して、これが維持、保存、運用のためなされる財産上の管理とが考えられ、後者についての行為又は怠る事実のみが住民訴訟の対象となるものというべき。 |
| 市営住宅の入居者に市営住宅内の敷地の一部を駐車場として無償で使用することを許諾した行為は、客観的・外形的にみて当該敷地の財産的運用という側面を有するものであり、住民訴訟の対象となる財務会計行為に当たるとした事例 大阪地判平20.8.7判例タイムズ1296.188(市営住宅敷地の一部を駐車場として使用許諾。なお公営住宅法2条9号、同施行規則1条6号で定める共同施設としての駐車場について、市営住宅条例により使用許諾したと市は主張)
○ (財産管理行為に関する最判平2.4.12を引用した)上で、一定の行政目的実現のためにされる行為は一律に財務会計行為性が否定されると解すると、かえって、地方自治体の財務会計の適正な運営の実現という上記住民訴訟の目的に沿う訴えまでも排斥してしまいかねないことから、問題となる行為が、客観的・外形的にみて、当該財産の財産的運用たる側面を有する場合は、それにつき財務的処理の違法の問題が生じることがないなどの事情がある場合を除き、地方自治法242条1項所定の財務会計行為と扱うのが相当である。 |
| 使用料減免を伴う行政財産使用許可の取消しを求める住民訴訟で、行政財産使用許可と減免は一体の処分であり、住民訴訟の対象となる財務会計行為に該当するとした事例 札幌高判平24.5.25判例地方自治370.10(原審:函館地判平23.11.11判例地方自治370.17 事案内容はそちらを参照:下記財産管理該当性否定裁判例に掲出)○ 町では、行政財産の使用については町財務規則で行政財産の使用許可の要件が定められており、使用許可をすることができる場合として、「直接又は間接に町の便宜となる事業又は施設の用に供するとき」、「その他特に町長が必要と認めたとき」と定めているが、この規定は、行政財産はその用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができるとする地方自治法238条の4第7項にいう「その用途又は目的を妨げない限度」の具体的内容を明らかにした規定であると解される。そして、町長がした行政財産使用許可処分は、町の行政財産について町財務規則に基づいてされた処分である。 ○ 使用料の徴収については、地方自治法225条は、同法238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができると規定し、同法228条1項前段は、使用料に関する事項は条例でこれを定めなければならないと規定しているところ、町では、これを受けて、行政財産の使用料徴収条例が定められ、使用料の減免については、同条例8条においてその要件を定め、4号において、「前各号に定めるもののほか、町長が特別の事情があると認めるとき。」と定めている。 ○ 以上を前提に本件使用許可処分と本件使用料減免処分の関係を検討すると、そもそも町長が行政財産につき使用を許可するか否かを判断するに当たっては、「直接又は間接に町の便宜となる」又は「特に必要」と認められるかという観点から、財産の所在地、対象財産、使用期間、行政財産の復旧方法、使用方法等が検討され、その判断要素として、行政財産の使用に対しての反対給付としての使用料を徴収するか否か、その金額、減額、免除等が関連するものと解されるから、本件使用許可処分と本件使用料減免処分は一体の関係にあると解するのが相当である。 ○ 町においては、行政財産の使用料徴収条例により、原則として使用料を徴収するものとされているから、使用許可により使用料の徴収義務が生じることになる。そして、使用料は、行政財産である本件土地の使用に対してその反対給付として徴収されるものであり、他方、使用料を減免する行為は、上記徴収義務を免除するものであるから、本件土地の財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為としての財産管理行為に該当するものと解される。 ○ よって、本件使用料減免処分を含めた本件使用許可処分は、住民訴訟の対象となる財務会計行為に該当する、と判示。【注】 当審は、使用許可と使用料を一体的にとらえており、その点で行政財産使用許可を普通財産の貸付に接近させる判断といえます。 しかし、本件の原審は、行政財産使用許可と使用料の徴収(減免)を別個のものとしてとらえており、(許可に当たり使用料を徴収するのは一般ではあるものの、普通財産の賃貸と異なり)あくまでも使用許可自体は行政目的に基づく行為、つまり財務会計行為性をもたないとしています。そして(各裁判例の判断は個別事案の内容に依拠するところはありますが)そのような判断(目的外使用許可と使用料減免決定を分離して判断)が、裁判例の判断としては主流のように思われます。念のため、本件の原審判示内容も参照下さい。 |
【参考事例:財産管理該当性を否定したもの】
| 市道の一部についてした道路占用許可処分は、一般交通の用に供するという道路本来の機能を維持する等、もっぱら道路行政上の見地からなした処分であり、住民訴訟の対象となる市の財産の管理・処分には当らないとした事例 千葉地判昭53.6.16行裁例集29.6.1127○ 道路の占用とは、一般公衆の自由な通行という道路本来の用法をこえて道路の地上又は地下に一定の施設を設け、これを継続的に使用する特別の権利(占用権という)の設定されている関係をいい、また、道路の占用許可とは、道路管理者が、一定の申請に基づき、一般交通の用に供する為の公の施設としての道路本来の機能を阻害しないように、申請が占用許可要件を具備しているか否かを判断し、道路管理権の作用として占用権を特許する行為であって、一定の申請を要件とする特殊行政行為(原則として道路管理者の自由裁量に属する)たる性質を有するものと解される。 ○ 本件処分は、占用許可申請に基づき、同市の財産たる本件各道路部分につき、一般交通の用に供するという道路本来の機能を維持するとともに、公共用地としての本件道路部分を交通以外の用に供することを許可するか否かの、もっぱら道路行政上の見地からなした処分であって、地方自治法242条1項所定の財務会計上の行為ということはできないので、本件処分は住民訴訟の対象となる財産の管理もしくは処分行為には当らない、と判示。 |
| 都市公園法6・7条による公園の占用許可は、公園管理者が公共性の強い一定の物件又は施設等に関し公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼさず、必要やむを得ないと認められるものであるか否か等を検討したうえで決定するものであり、専ら公園管理上の見地から都市公園とその他の公共施設等との調和を図るためになされるものであるから、住民訴訟の対象となる財務会計上の行為に当らないとした事例 東京地判平元.10.26判例時報1333.87(電力鉄塔設置のための公園占用許可の取消しを求める住民訴訟)
○ 占用許可は、都市公園法6条及び7条が規定する公園の占用許可であるところ、同法6条1項は、都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならないと規定し、これを受けて、同7条は、公園管理者は、右許可の申請に係る工作物その他の物件又は施設が電柱、電線、変圧塔その他これらに類するものなどの所定のものに該当し、都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであって、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、右許可を与えることができる旨を規定している。右規定によれば、占用許可は、公園管理者が、公共性の強い一定の物件又は施設等に関し、当該占用が公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであるか否か等を検討したうえで決定するものであって、専ら公園管理上の見地から都市公園とその他の公共施設等との調和を図るためになされるものであることは明らかであり、当該公園敷地の財産的価値に着目し、専らその財産的価値の維持や保全等の財務的処理を目的とするものではないといわなければならない。 |
| 公民館の館長が公民館の使用の許否を決する行為は、公共用物である公民館の設置目的を達成するためにする行政的管理行為であり、住民訴訟の対象となる財務会計上の行為に当らないとした事例 大阪地判平2.10.24行裁例集41.10.1650(風俗営業に類する者に対して、公民館の使用を長期的かつ独占的に許可し、その使用許可を取り消さないことが、違法な財産の管理に当たるとして、地方自治法242条の2第1項3・4号に基づき、許可の取消しを怠る事実の違法確認と許可の取消しを求める住民訴訟)
○ 公民館長の被告が、公民館の使用の許否を決する行為は、公共用物である同公民館の設置の目的を達成するためにする行政的管理行為であって、同公民館の財産的価値に着目して、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為には当たらない。 |
| 行政財産たる港湾設備用地の目的外使用許可は、港湾管理という行政目的の実現のためになされる行為であり、また、行政財産目的外使用許可は、行政財産の効率的利用の見地からされるもので、必ずしも専ら財産の運用としてされるものとはいえないから、目的外使用の許可であれば直ちに住民訴訟の対象たる財務会計上の行為に該当するということにはならないと判示した事例 東京地判平5.3.22判例時報1461.60(変電所の設置を目的とする港湾設備用地の使用許可が違法であるとする処分取消請求住民訴訟)
○ 本件許可は、港湾設備の利用を適正かつ効率的に行うとの目的の下で、当該使用が、港湾の利用の増進及び管理の改善に必要な機能を有する設備を対象とするものか否か、また、その設置が港湾設備本来の機能を阻害しないと認められるか否かといった観点からなされるものであって、その性質上、港湾管理という行政目的の実現のためになされる行為であることは明らかであり、もっぱら港湾設備の財産的価値に着目して、その維持・保全・管理等を図る行為ではないというべきである。したがって、本件各許可は住民訴訟の対象たる財務会計行為に該当しないものというべきである。 |
| 市立病院施設等にプリペイド式テレビ等を設置するための目的外使用許可は、行為の性質として市の財産管理的な側面があることを全く否定することはできないが、主として病院施設の管理という行政目的から決定されたもので、結局本件使用部分の財産的価値に着目してその維持及び保全を図る財務的処理を直接の目的とする財産管理行為とは言い難いといわざるを得ないから、住民訴訟の対象となる財務会計行為に該当しないとした事例 大阪地判平10.2.12判例時報1670.7(市立病院においてプリペイドカード式のテレビ、洗濯機、冷蔵庫等を設置するため、業者に建物等の一部の目的外使用許可をしたことが違法であるとして、市長に前記許可処分の無効確認及び建物等を使用させることの差止めを求めた住民訴訟)
○ 一定の行政目的実現のためにする行為が、他面では財産の管理という性質も有し、結果として地方自治体に財産的影響が及ぶ場合については、当該具体的な行為の法的性質、内容、具体的事情の下において、その行為が、主として一定の行政目的実現のために決定されるものか、それとも、主として財務会計上の観点から決定されるものかによって、財務会計行為としての「財産の管理」に該当するかどうかを個別的に判断するのが相当である。 |
| 学校施設の目的外使用許可は、学校施設の目的外使用を施設管理者の見地から許可する教育行政担当者としての行為であり、住民訴訟の対象となる財産管理行為に当たらない(使用料免除決定は財産管理行為に該当する)とした事例 神戸地判平12.2.29判例地方自治207.72(神社の祭典参加者の休憩所として市立小学校校庭及び体育館を無償で使用させたことについて使用許可・使用料免除をした職員に損害賠償を請求した住民訴訟)
○ 使用許可処分を対象とする地方自治法242条の2第1項4号前段の請求の適法性について、市立学校施設の目的外使用について定めた条例には、学校施設を目的外に使用しようとする者に使用申請書を提出させ、許可しようとするときは学校長等の意見を聞かなければならず、当該学校又は幼稚園において使用の必要を生じたときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し若しくは制限することができると定められていることが認められるから、本件使用許可は、行政財産である小学校施設の目的外使用を施設管理者の見地から許可する教育行政担当者としての行為であることが明らかであって、学校施設の財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為としての財産管理行為には当たらないと解するのが相当である。そうすると、被告が本件使用許可をした行為は地方自治法242条の2に定める住民訴訟の対象となる行為とはいえないから、本件使用許可を対象とする同条1項4号前段の請求は、不適法というほかない。 |
| 同前 東京地判平22.3.30判例時報2087.29(有料特別補習のため任意団体に学校教室の使用許可をしたことについての無効確認(2号)施設管理を怠る事実の違法確認(3号)損害賠償請求(4号)住民訴訟)
○ 教育財産の目的外使用許可処分である本件許可処分は、行政財産はその用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができるとする地方自治法238条の4第7項及び同項の趣旨を学校施設の場合に敷衍して、学校教育上支障のない限り学校の施設を社会教育その他公共のために利用させることができるとする学校教育法137条を踏まえ、同項にいう「その用途又は目的を妨げない限度」の具体的内容を明らかにした規定であると解される教育財産管理規則に基づいてされた処分であるところ、これらのことに加え、そもそも、地方自治法238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については借地借家法の規定は適用されず、当該使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき等は普通地方公共団体の長又は委員会はその許可を取り消すことができるとされており(同条8項及び9項)、その使用料の額の決定及び減免については別途の処分が予定されていること(同法228条1項前段、学校施設使用料条例)、教育財産管理規則では、教育財産の使用を許可することができる場合が同規則に列記された特定の目的の場合等に限定されているほか、使用許可の手続として、使用しようとする目的及び方法等を記載した申請書の提出が要求され、また、同規則の規定に基づき教育財産の使用許可を決定したときは、申請者に対し、公有財産管理規則に掲げる条件のうち必要な条件を付して使用許可書を交付すべきものとされており、公有財産管理規則には、使用許可の取消し又は変更及びその際の損失不補償といった条件が掲げられ、公用又は公共用に供するため必要を生じたとき等の地方自治法238条の4第9項に規定する理由に該当すると認めたときは、教育委員会は所定の手続により使用許可の取消しをしなければならない旨規定されていることにかんがみれば、教育委員会による教育財産の目的外使用の許否の処分は、教育行政を所掌する施設管理者として、教育財産である学校施設の使用につき、教育上及び公共上の政策的な見地から、学校施設の管理に係る教育行政上の処理を直接の目的として、その許否を決する処分であるというべきであって、学校施設の財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為としての財産管理行為又はその怠る事実には当たらないと解するのが相当である。 |
| 使用料減免を伴う行政財産使用許可の取消しを求める住民訴訟で、行政財産使用許可と減免は別の処分であり、行政財産使用許可取消請求を不適法、減免処分は本案審理をした事例 函館地判平23.11.11判例地方自治370.17(町行政財産である土地の駐車場利用についての使用許可取消を求める住民訴訟)
○ 町長がした使用許可処分は、町の行政財産について財務規則に基づいてされた処分であるところ、同規定は、行政財産はその用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可することができるとする地方自治法238条の4第7項及び同項にいう「その用途又は目的を妨げない限度」の具体的内容を明らかにした規定であると解される。そして、同法225条は、目的外使用許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができると規定し、同法228条1項前段は、使用料に関する事項は条例でこれを定めなければならないと規定し、被告においては、同法228条1項前段を受けて行政財産使用料徴収条例が定められ、使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等に関しては、同条例が必要事項を定めるものとされ、使用料の減免については同条例8条にその要件が定められている。 (使用許可処分の取消しを求める部分は却下、使用料減免処分の取消しを求める部分は本案審理(棄却)) |
| 教育財産の目的外使用の許否の処分は、使用料等が必要な条件とされてはいるものの、これはあくまで附帯条件にとどまり、学校施設の管理に係る教育行政上の処理を直接の目的としてその許否を決する処分なので、財務会計上の行為としての財産管理行為又はその怠る事実には当たらないとした事例 東京地判平25.6.11判例地方自治383.22(教育委員会が国際交流学級を運営する学校法人及びNPO法人等に対して小学校の一部につき行政財産使用許可をするとともに行政財産使用条例に基づいて使用料を免除したこと等が違法であるとして、使用許可の取消、当時の首長等に損害賠償の請求をすることを首長に求める住民訴訟)
○ 教育委員会がした本件使用許可について見ると、本件使用許可は、地方自治法238条の4第7項、教育財産管理規則に基づくものとしてされた処分であるところ、教育財産管理規則が「その用途又は目的を妨げない限度において」行政財産の使用を許可することができるとする地方自治法238条の4第7項を受けて規定されたものであり、また本件施設は地方教育行政法28条1項の教育財産であるとともに、学校教育法137条の学校の施設であるとも解されることからすると、教育財産管理規則の「やむを得ないと認められる場合」に該当するか否かは、地方自治法238条の4第7項のみならず学校教育上支障(その支障には、物理的支障に限らず、教育的配慮の観点から、児童に対し精神的悪影響を与え、学校の教育方針にもとることとなる場合も含まれ、現在の具体的な支障だけでなく将来における教育上の支障が生ずるおそれが明自に認められる場合も含まれる。)のない限り学校の施設を社会教育その他公共のために利用させることができるものとする学校教育法137条の趣旨も踏まえて判断すべきものと解される。 |
| 市の指定管理者に対して行った市立図書館の一部の書籍販売及び喫茶営業に係る使用許可を、許可権限のない市長が行っていたとしても、教育上及び公共上の政策的見地から教育行政上の処理を直接の目的としてその許否を決すべき処分としての性質が変わるものではなく、財務会計上の行為としての財産管理行為には当たらず、損害賠償請求に係る訴えは不適法とした事例 横浜地判平29.1.30判例地方自治434.55○ 地教行法21条2号所定の教育財産であるA図書館の目的外使用についての使用許可(地方自治法238条の4第7項)は、本来、市の教育財産の管理権限を有している市教委(地教行法21条2号)が、その管理行為の一環として行うべきものである。そして、地教行法は、教育財産について、その取得及び処分を地方公共団体の長の権限とする一方で(22条4号)、その管理を教育委員会の権限としていること(21条2号)、地方自治法238条の4第7項の許可を受けてする行政財産の使用については借地借家法の適用がなく(同条8項)、当該使用を許可した場合において、公用若しくは公共用に供するため必要が生じたとき等は、普通地方公共団体の長又は委員会はその許可を取り消すことができるとされており(同条9項)、使用料の額の決定及び減免については別途の処分が予定されていること(同法225条、228条1項前段参照)に照らせば、市の教育財産である図書館の目的外使用の許否処分それ自体は、教育行政を所掌する教育財産の管理者である市教委が、教育上及び公共上の政策的な見地から、図書館施設の管理に係る教育行政上の処理を直接の目的としてその許否を決すべき処分というべきであって、当該図書館施設の財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為としての財産管理行為には当たらないと解するのが相当である。 ○ 図書館の本件目的外使用につき被告がした本件使用許可は、許可権限のない市長が誤って行ったものであるが、そうであるからといって、教育上及び公共上の政策的な見地から図書館施設の管理に係る教育行政上の処理を直接の目的としてその許否を決すべき処分である図書館の使用許可の性質が変わるものではないから、市長がした本件使用許可も、財務会計上の行為としての財産管理行為に当たらないというべきである。 ○ よって、市長がした本件使用許可は、地方自治法242条の2第1項が定める住民訴訟の対象となる行為であるということはできないから、本件使用許可が違法であるとして、当該行為をした当時の市長であるAに対する損害賠償の請求をすることを求める訴えは、不適法である、と判示。 |
キ その他の財産管理類型
次のような事例があり、参考になるものと考えます。
【参考事例】
| 文化財として適切に管理し保存する手続をとらないことの違法確認を求める訴えは、財務会計行為としての財産の管理行為ではなく不適法とした事例 大阪地判平5.12.22行裁例集44.11・12.1038○ 市長に対する本件土地を文化財として適切に管理し保存する手続をとらないことの違法確認を求める訴えは、財務会計行為としての財産の管理行為ではなく、文化財についての管理、保存等いわば文化財保護行政に関する行為を怠ることの違法確認を求めるものである。 ○ よって同請求は不適法、と判示。 |
| 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法8条1項に基づく歴史的風土特別保存地区内における工作物等の新築等の行為の許可は、専ら対象財産の歴史的文化的側面に着目し、歴史的文化的価値の維持、保存を図る文化、環境行政の見地からの行為であると判断するのが相当であり、住民訴訟の対象となる財務会計上の財産管理行為に当たらないとした事例 京都地判平6.6.13行裁例集45.5・6.1386(歴史的風土特別保存地区内の行政財産における訴外会社に対する工作物の設置等の許可処分に違法な点があるとして提起された2号住民訴訟)
○ 古都保存法は、古都の歴史的環境及び歴史的文化遺産の保全、維持を目的としており、歴史的風土特別保存地区内において、歴史的風土の保存に影響を及ぼすおそれのある行為を一般に禁止し、申請によりそれを許可する同法8条1項の許可処分は、同法の目的の趣旨に従えば、専ら対象財産の歴史的文化的側面に着目し、歴史的文化的価値の維持、保全を図る文化、環境行政の見地からの行為であると判断するのが相当であるので、本件許可処分は、対象財産の経済的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の財産管理行為にはあたらない、と判示。 |
| 粉飾決算は財産の価値の維持、保全又は実現を直接の目的とする財務会計上の財産管理行為に該当せず住民訴訟の対象になりえないとした事例 神戸地判平13.10.24判例地方自治228.47(土地造成事業に粉飾決算があるとして市長に造成地の管理を怠る事実の違法確認を請求する住民訴訟)
○ 原告主張の粉飾決算は、A事業会計が管理する本件各事業の会計方式が地方公営企業法20条ないしは地方公営企業法施行令9条に則っていないという点であり、結局は、同事業会計の会計方式が違法であると主張していることに帰するといわざるを得ないが、原告ら主張の会計方式の違法は、仮にそれがあったとしても、そのことによって本件造成地の財産的価値それ自体に直接影響・変動を生じさせるものではない。換言すると、会計方式それ自体は、財産の適切な管理のための手続ないし手段ともいうべきものであって、財産の財産的価値の維持・保全又は実現という点に着目すると、直接的なものでなく間接的なものに過ぎず、専ら経理上の事務処理方法の当否の問題である。 |
| 指定管理者の指定は、地方自治法242条の2第1項2号の財務会計行為に該当しないとした事例 大阪地判平18.9.14判例地方自治294.17○ 指定管理者制度は、公の施設の管理を指定管理者に行わせることにより、民間事業者が有するノウハウを活用して多様化する住民ニーズに効率的に対応し、これにより地方公共団体が自ら管理するよりも一層向上したサービスを住民が享受できるようにすることを目的とする制度である。そして、指定管理者には、公の施設が本来の目的を達成できるようにするため、当該公の施設の使用許可処分等も含めた管理権限が委任されており(地方自治法244条2項括弧書及び244条の4第3項は、指定管理者が指定された場合には、当該指定管理者が当該公の施設の使用許可等の処分権限を有することを前提としている。)、指定管理者の有する管理権限は、当該施設ないし附属設備の維持、修繕、使用関係の規制等、公の施設が本来の目的を達成させるために行われる管理一般に幅広く及ぶものである。 ○ したがって、指定管理者の指定自体は、公共用物設置の目的を達成するために行う行政管理的行為であって、当該公共用物の財産的価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為には当たらない。 |
ク 財産の処分
財産の処分は、自治体の財産の保有価値に直接的な影響を与えるのが通常ですから、そうした外形を有する行為は、通常は住民監査請求の対象としての財務会計行為に該当すると考えるべきです。
なお、ある行為が財産処分行為といえるのか、その点が請求要件該当性の判断にどのように影響するかに関しては、下掲平成4年京都地判が参考となるものと考えます。
【参考事例】
| 教育委員会が君が代を録音したテープを小中学校長に配付した行為は、市内部機関相互の物品の所管換えに過ぎず、地方自治法242条1項の財産処分行為には当たらないとした事例 京都地判平4.11.4判例時報1438.37(上記オ掲出裁判例の再掲)(被告・被告参加人は、テープの配付が、市内部の機関相互の所管換えにすぎないもので、財産処分に当たらず、住民訴訟の対象でないから本件訴えは不適法であると主張するが、原告・原告参加人らは、前示のとおり、テープの配付は、校長であった被告ら個人に交付されたものであって、これが地方自治法242条1項所定の財産処分に当たると主張して、本訴を提起しており、原告・原告参加人らの主張を前提とする限り、これが同条項にいう財産処分に当たることは明らかであるので、これが、被告・被告参加人主張のように市の機関相互間の配付、即ち、市教育委員会から各校長職に配付されたものであって、校長職にある被告ら個人に配付されたものでないか否かは、本案の事実認定の問題であるとして、本案の検討において以下の通り判示) ○ テープは市教育委員会から小、中学校の校長に、(注:校長個人に私的に配付したのではなく)公的に配付されたものであるから、これは市内部の機関相互の物品の所管換えにすぎない。物品を内部の部局から他の部局へ所管を移したとしても、市が物品を保管していることに変わりはなく、これにより損害を生ずることもないし、そもそもこのような所管換えは、地方自治法242条1項の財産の処分に当たらないというべきである。 ○ ・・・これらの者にテープを配付したのは財産処分に当たらない。したがって、同被告らに財産処分による不当利得に基づく返還義務が生ずるいわれはない。よって、その返還を求める原告らの請求は失当である。 |
| 解体予定の校舎の備品移転に伴い町長の指示で校舎を損壊した行為が校舎解体行為と認定された場合において、当該行為を財務会計上の財産処分行為とした事例 大津地判平17.7.4判例地方自治280.69(用途廃止前の学校において町長の指示で備品移転・校舎解体を目してこれを損壊した行為に係る損害賠償請求住民訴訟)
○ 町においては、本件校舎の老朽化による耐震性の低下が問題となり、本件校舎の解体及び新校舎の建設が計画されたことが認められるところ、学校として使用されている校舎が、耐震性その他の観点から学校としての使用を継続することが適当でないと判断された場合に、教育財産の用途廃止をすることは、教育行政上の管理行為であって、財務会計行為には該当しないと解される。 |
| 退職した市議会議員等に対して市営地下鉄・市営バスの優待乗車証を支給する行為は住民監査請求の対象である財産処分行為とした事例 大阪高判平19.10.19判例地方自治303.22(退職した市議会議員等に対して市営地下鉄・市営バスの優待乗車証を支給したことが違法であるとして市長個人に損害賠償請求をすることを市長に求めた住民訴訟)
○ 優待乗車証は、記名式でありその譲渡・換金性がないものの、交通機関における運送役務の給付債権を表章する債権証券と解され、これが呈示された場合、その呈示者に対し、無償で乗車させるべき義務があるのであり、一定の財産的価値を有することは明らかである。したがって、市が、待遇者等に対し、本件優待乗車証を無償で支給することは、市に財産上の損害を生じさせる「財産の処分」(地方自治法242条1項)に当たるといわなければならない。 |
注:記名証券に関しては、令和2年の民法改正を考慮する必要があります。
| 現行庁舎・公会堂の解体は財産処分行為となるとした事例 東京地判平29.12.21判例地方自治442.10
○ 解体差止請求は、現庁舎及び現公会堂の各建物の解体の差止めを求めるものであるところ、これらの解体は、地方公共団体が有する財産の財産的価値に着目してされる「財産の処分」(地方自治法242条1項)として住民訴訟の対象となると解される。 |
| 固定資産税の免除は財産処分行為となるとした事例 宇都宮地判令4.1.27判例時報2552.5
(地元サッカーチームのメインスポンサー企業が、市の都市公園内にサッカー専用施設を建設することとなり、企業と市が当該施設の固定資産税を免除する協定を締結したことに対し固定資産税免除の差止めを求める1号訴訟) ○ 被告の本件会社に対する本件建物の固定資産税を徴収する権利は、金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利であり、地方自治法にいう「財産」(地方自治法237条1項)の一つである「債権」(同法240条1項)に当たるところ、被告による固定資産税の免除は、このような債権を消滅させる行為であるから、地方自治法242条1項所定の「財産の処分」に当たる。なお、債務免除の意思表示は積極的に債務を消滅させる行為であるから、被告による固定資産税の免除が不作為であるとする被告の主張は当たらない。 |

これも見れば何処か大体分かますね(笑)。この写真は2020年1月下旬に撮影。この時は海賊船の船着き場には外国人がわんさといました。まさかこの直ぐ後にあのような事態になろうとは。