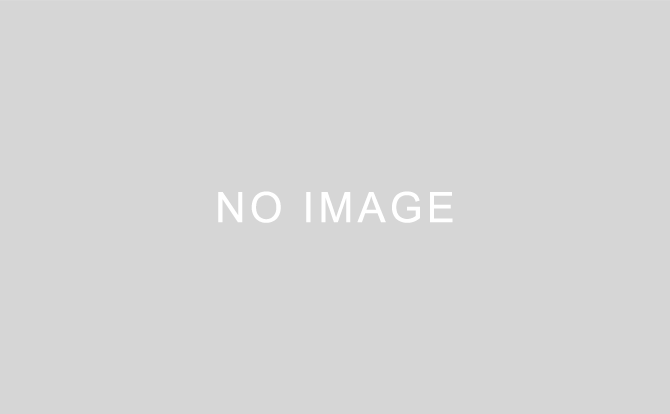本ページの一番下に、本ページのPDF版リンクを設けています。
最終改訂 2025.2.13 改訂箇所は改訂履歴のページ参照
○ 請求の対象となるのは、請求人が違法不当と認める、その自治体の以下の行為に限られ、これら以外を対象とする住民監査請求は、請求の要件を満たさない不適法な請求となります。
・ 財務会計上の行為
(財務会計上の行為については、当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合も、対象とすることができる)
・ 公金の賦課・徴収や財産の管理を怠る事実
○ これらは、財務的処理を直接の目的とする行為(怠るとされる行為も同じ)としての性質を有するものであることを要します。こうした性質を有しない行為・事実は、上記の財務会計行為・怠る事実としての(またはこれに類する)外形を有していたとしても、住民監査請求の対象とすることはできません。
○ 住民監査請求の対象とする財務会計行為等は、請求人が、監査請求書などによって、個別具体にこれを特定しなければなりません。監査の対象を具体的に特定することなく監査を求めるような請求は、不適法です。
★本ページは、住民監査請求の対象となる「財務会計行為」「怠る事実」について、概説的に説明し、個別の事項に関する下級審裁判例など踏まえた説明は、別ページ掲載(本ページ各事項標題にリンク貼り付け)
|
はじめに 本ページで説明する、「請求対象が当該自治体の財務会計行為・怠る事実であること」は、「0.2 住民監査請求の要件は?」冒頭で説明の通り、 この要件をもう少し具体化すると、 本ページでは、「請求要件としての財務会計行為・怠る事実」について、全体的な概説を行い、個別の細目要件については、別ページを設けて、裁判例等を中心とする説明をします。 |
| ※ 「監査を行う実益がないことが、要件審査段階で明白(請求の利益がない)」ので、監査を行うことが無意味(よって適法な請求として扱うことができない)、ということです。ただし、対象とする事項が存在しない場合でも、その対象事項が自治体財務運営への影響を生じさせている場合(たとえば、約定の支払を怠り遅延損害が生じた。支払は完了したが、遅延損害は消滅しないので残存している、など)があるので「原則として」としています。 なお、住民監査請求の対象となり得る事項を財務会計行為等とすることは、地方自治法242条1項に明文規定がありますが、この点は特段の明文規定がなく、判例等で定式化されたものでないことを踏まえて、このような扱いとしています。 |
1 違法・不当
(1) 違法
違法な財務会計行為等とは、法令の規定に反する財務会計行為等などを言います。
「違法な公金の支出」とは、法規に違背した支出の意味となります(行実昭23.12.25)。つまり、法令上禁止されている支出などがこれにあたります。
(2) 不当
不当とは、違法ではないが、妥当性がない、又は適当でない財務会計行為等をいいます。
例えば、額がいくらかであるかに関わらず、支出そのものが不適当な場合や、支出そのものは不当とはいえないが、金額が不適当な場合、といったものです(松本逐条)。
なお、財務会計行為等の違法性は、住民監査請求に後続する住民訴訟で問題とすることができますが、財務会計行為等の不当性は、住民訴訟で取り上げることはできません(地方自治法242条の2第1項参照)。裁判所は行為等の違法性については判断できますが、違法性までは帯びないが不当な行為等の効力をどうするかに対しては、三権分立の仕組み上、触れることができない(不当な問題の処置は、あくまでも政治的・行政的な領域の問題)ためです。逆に、監査委員が不当な行為等に対しても勧告等ができるのは、監査委員が首長などと並ぶ当該自治体の執行機関であり、自治体の行政権限の一部を担う組織だからです※、※※。
| ※ 行政不服審査も違法・不当な処分について争うことができますが(行政不服審査法1条1項)、行政訴訟では不当性について争うことができないことと同様です。 |
| ※※ 住民監査請求が行政不服審査同様、違法のみならず不当な行為等も対象とできる以上、監査の判断においては、法適合性の審査を絶対的要件とすることは要せず、実質的な不適合性が客観的・具体的に認められれば、所要の措置の勧告ができることとなるので、違法性と不当性の違いを突き詰める必要性は、実務的にはあまりないということになります(上記の松本逐条の説明が、実際にはわかったようでわからないものとなっているのも、不当概念の定義がその粒度であっても、特に実務的な問題がないことを意味することとなります)。 その上で、違法と不当の概念をもう少し見てみると、次のように説明されています。 「法律に適合しない」・・・「違法」、「公益目的に合致しない」・・・「不当」(櫻井敬子、橋本博之「行政法(第6版)」弘文堂(2019年)p.229) 「不当は、法には違反していないが制度の目的からみて適切でないことをいう。例えば、裁量権のある者が権限の枠内で不適切な裁量をした場合には、違法ではないが不当であるなどという」(法律学小辞典p.33) また塩野Ⅱ p.9において、行政上の不服申立て制度の存在理由につき「裁判過程においては、裁判所の審査は処分の適法性の問題に限定される。裁判所は法律上の争訟について法律的問題のみを取り上げて判断するのだからであり、仮に裁判所が、処分の当・不当まで判断することになると、憲法上の問題を生ずることとなる。これに対して、行政上の不服申立ての場合には行政部内の自己統制であるから、当・不当の問題についてまで裁断機関の判断を及ばせても憲法上の問題は起こらないし、立法政策的にもそうすることに行政上の不服申立て制度を置くことの意義が見出される」としており、参考となるものと考えます。 |
(3) 請求要件としての違法・不当の区別
住民訴訟の場合は、三権分立の原則からも、地方自治法242条の2第1項にあるように、違法な財務会計行為等のみに請求の対象は限定され、違法ではないが不当な財務会計行為等を訴訟の対象とすることはできません。
しかし住民監査請求では、上記(2)の通り、不当な行為等も請求の対象とすることができます(地方自治法242条1項)。
そのうえで、請求内容における、違法・不当性に関する請求人の主張の内容や適否等は、要件審査においては、判断の対象となる問題にはならないものです※。
これはそもそも、財務会計行為等に付着する違法不当性に関する判断は、要件審査ではなく監査において行われるべき事項、つまり監査の領分の事項であり、そのうえ住民訴訟と異なり、住民監査請求においては、請求人は監査の対象である財務会計行為等を特定して監査委員に監査を求めればよく、請求人の請求内容に、求める措置の内容やその法的構成が記載されていても、監査委員はこれに拘束されることなく、みずから判断で、違法不当性の判断、その法的構成、措置内容の決定をすることができるのであれば(参照:最判平10.7.3集民189.1)、なおさらに、請求人が主張する違法不当性の内容やその当否を要件審査段階で精査判断する必要性が生じないからです。
| ※ 筆者は下記4(3)ウに説明の通り、一定の場合、請求人は請求の対象とする財務会計行為等についてこれを財務会計法規上違法・不当と認める一定の具体的理由を、請求内容により明らかにすべきと解していますが、同欄の説明の通り、住民監査請求の要件審査においては、その違法性等主張の内容について厳密な法的正確性などを要求する必要はないものと考えます。 ただし、監査の着眼点を的確に設定するためにも、請求書等からは何を違法不当と考えるのか曖昧・不明確な場合や、明らかな錯誤・勘違いの場合は補充説明等を求めるべきでしょう。 |
2 請求の対象となる財務会計行為等
ここでは、住民監査請求の対象となる財務会計行為(怠る事実)は、どのようなものがあり、どのような属性を備えることを必要とするのかについて、基本事項((1)総論)および地方自治法242条1項に示される個別類型ごとの各論((2)から(6))により説明します。
住民監査請求は、本項で示す要件に該当する行為(事実)のみが、その対象となり得ることとされています。
(1) 総論
ア 住民監査請求の対象となる行為・事実
住民監査請求の対象となるのは、地方自治法242条1項所定の ①財務会計上の行為 か ②公金の賦課・徴収や財産の管理を怠る事実 のどちらかに限られます。
具体的には下記①②に示すものであり、①、②以外の事項を対象とする住民監査請求は、不適法です。
なお実際は、住民監査請求の対象となるには、外形上これらの行為等類型に該当することに加え、下記イの条件を満たすことが必要です。
| 住民訴訟の対象となるものは地方自治法242条1項所定の地方公共団体の執行機関又は職員による同項所定の一定の財務会計上の違法為又は怠る事実に限られる 最判昭51.3.30集民117.337
【事実関係】 【判示事項】 |
【地方自治法242条1項に定める財務会計行為等の類型】
★①、②の各事項の成立要件は、下記(2)以降で説明
①に関するもの
・ 公金の支出
・ 財産の取得、管理又は処分
・ 契約の締結又は履行
・ 債務その他の義務の負担
【注】 以上4つの行為については、まだ行われていなくとも、これら行為がなされることが相当の確実さで予測される場合も請求は可能です。
②に関するもの※
・ 公金の賦課又は徴収を怠る事実
・ 財産の管理を怠る事実
| ※ 「怠る事実」は、すべき行為がなされていない、という事実を指すのであり、よって財務会計上の「行為」は存在しない状態、ということになります。 |
ある行為が複数の類型に同時に該当することがあり得ます(例:土地の買受契約の場合は、財産の取得、契約の締結履行に該当し、売買代金の支払局面では公金の支出にも該当する)。
| 【Q】 法定受託事務の財務会計行為等は、住民監査請求の対象になるのか? |
【A】
なります。
○ 地方自治法242条は、住民監査請求の対象となる財務会計行為等について、法定受託事務を排除する規定を設けておらず、また地方自治法のその他の規定からしても、法定受託事務に関する財務会計行為等を、住民監査請求の対象から排除することを適当とする規定は見当たりません。
○ なお法定受託事務もその自治体の事務であり、これに関する財務会計行為等においては、自治体に属さない国等の固有の財産等を用いるのではなく、その自治体の財産等を用いるのですから、制度論的にも、法定受託事務に関する財務会計行為等を住民監査請求の対象から排除する理由がありません。
イ 財務会計上の行為(怠っている行為を含む)としての性質を有することの必要性
判例は、外形上、上記アの行為・事実の類型に該当(する可能性がある外観を呈)し、自治体の財務に影響を与え得るような行為等であっても、それは財務的処理を直接の目的とするものでなければならず(下記平成2年最判)、こうした性質を有しないものは、地方自治法242条1項所定の、住民監査請求・住民訴訟の対象となる財務会計行為等には該当せず、よってそのような行為等を対象とする請求は、不適法であるとしています。
上記アが、地方自治法242条1項に掲げる外形的な行為類型の枠組み規定に関する説明となり、本項イでは、アの類型に外形的に該当することに加え、こうした性質を有する行為(怠る事実)についてのみ、地方自治法242条1項所定の財務会計行為等として住民監査請求の対象になるもの、としています。その意味で、この財務会計上の行為たる性質を有することは、財務会計行為等に該当するかどうかの実質的な要件ということができます。
| 保安林内の市有地に市道を建設するに際し、市建設局長らが請負人をして道路建設工事をさせる旨の工事施行決定書に決裁をしてこれに関与した行為は、道路整備計画の円滑な遂行・実現を図るという道路建設行政の見地からする道路行政担当者としての行為(判断)であって、住民訴訟の対象となる財産管理行為には当たらない 最判平2.4.12民集44.3.431
【事実関係】 【判示事項】 【ポイント】 |
| ※1 本判決の調査官解説(上田豊三「時の判例Ⅰ」p.298)では、「市道は道路法上の道路であり、市長による路線の認定・公示、道路区域の決定・公示、道路区域内の土地につき所有権その他の権原の取得、道路建設工事請負契約の締結、請負人による道路建設工事、道路供用開始の工事といった手続を経て、市道が成立する。これら市道の建設に関する行為のうち、路線の認定・公示、道路区域の決定・公示、道路供用開始の公示は、円滑な道路交通の確保及び発達という非財務的見地から行われる道路行政上の行為であって、これらの行為により当該市道の敷地やその周辺の市有地等の財産的価値に影響を及ぼすことになるとしても、上記行為は財務会計上の行為には当たらないと解される(中略)。市長が道路区域内の土地につき所有権その他の権原を取得するための土地売買契約等を締結する行為は、一面で財産の取得、他面で契約の締結ないし債務負担行為であり、財務会計上の行為である。市長と請負人間の道路建設工事請負契約の締結は、契約の締結ないし債務負担行為であり、財務会計上の行為である。また、請負人に請負代金を支払う前提として、請負人が契約どおりにその義務を履行しているかどうかを監督又は検査する行為(中略)も財務会計上の行為である」と説明しています。 また、碓井p.79は、本判決について、工事の開始までに工事請負契約等一連の財務会計行為が介在しているが、最高裁は、一連の過程における行為を個別に分解した上で(それぞれについて)財務会計行為該当性を判断するという姿勢を示す、としています。 |
したがって、外形上財務会計行為に該当する、たとえば契約の締結行為が、住民監査請求の対象とされた場合、契約の締結は、たしかに地方自治法242条1項に規定がありますが、その契約が財務的処理を直接の目的としない内容であるときは、上記の目的・性質論上の判断の結果として、地方自治法242条1項に定める住民監査請求の対象としての契約締結行為には該当しない、という結論となります(例:水戸地判平元.3.14判例時報1344.126)※2。
また上記昭和51年最判事案のように、土地区画整理事業の換地処分の結果として市が土地を取得することは、外形上は財産(不動産は地方自治法237条1項、同238条1項1号で、ここで定義される「財産」に該当)の取得の外見を呈しますが、やはり行為の目的・性質的判断として、地方自治法242条1項の財産の取得には該当しないことになります。
| ※2 なお本件は単純に理財部門が実施した工事請負契約締結等を請求対象にすれば、少なくとも請求適格の問題は生じなかったということになリますが、一方で損害賠償請求権の原因が道路工事施行決定にあるのであれば、最判平4.12.15民集46.9.2753と同種の問題(違法性の承継)が争点となり得る、と考えます。 |
このような判断となるのは、「0.1 住民監査請求の制度設計の考え方」で述べた通り、住民監査請求・住民訴訟制度が、あくまでも自治体財務運営の適正を図る仕組みであって、住民一人からでも提起できる仕組みとする一方で、その対象を財務会計上の行為等(またその問題)に限定するものとして構築されたものである以上、財務的処理を目的※3としない一般行政上の問題を(たとえば自治体機関・職員の一般行政上の行為等を通じて)住民監査請求・住民訴訟で対象とすることを認めては、上記のような制度の目的から逸脱することになるためです※4。またそれゆえに判例は、住民監査請求の対象となる行為が財務会計行為としての性質を有するかについて、厳密に判断する傾向にあります。
そして、この判断枠組みを基礎として、個別の類型・事案ごとに、住民監査請求の対象とされた事項が、地方自治法242条1項で定める住民監査請求の対象として取り上げ得るものか、判断されることになります。
その意味で、請求の対象が地方自治法242条1項の財務会計行為等にあたるかどうか、すなわち同項列挙の行為等の類型に外形的に該当するのみならず、その行為等が財務会計上の行為等としての性質を有するかどうかの判断は、住民監査請求制度の運用上、もっとも根幹的な問題となるものです。
| ※3 「財務的処理を直接の目的とする」かどうかという、行為の目的を判断において重視する点については、参考:最判平10.11.12民集52.8.1705に関する地方自治判例百選4版p.172/5版p.150解説(野呂充)。 |
| ※4 前記※※平成10年最判に関する担当調査官解説(大橋寛明「時の判例Ⅰ」p.300)では、同判決で扱った土地区画整理事業を同様に争点とする最判昭51.3.30集民117.337において換地処分が住民訴訟の対象である財務会計行為に該当しないとされたことについて、換地処分が法に基づく事業達成という一定の行政目的実現のために行われるもので、直接財産取得を目的としておらず、結果として他の財務的行為の介在なく土地が事業施行者である自治体に帰属するものであり、このような処分を住民訴訟の対象とすると、一般行政上の違法を直接住民訴訟で争うこととなり、住民訴訟の目的を逸脱する、とする判例時報掲載のコメントを引用しています。 |
なおこの問題は、監査請求ができる期間の問題と並び、自治体の監査実務担当者にはもっともわかりづらい領域ですが、まずは、最高裁判例・下級審裁判例は、監査の対象となる財務会計行為等か否かをかなり厳密に区分していることは、理解しておくとよいでしょう。
(2) 公金の支出
ア 公金
自治体がその目的を達成するための作用を行うにあたって用いる金銭であり、公の財産※の一部とされます(法律学小辞典p.362)。歳計現金、基金に属する現金、歳入歳出外現金、一時借入金がこれにあたります(参照:新自治用語辞典編纂会編「新自治用語辞典」ぎょうせい(2000年)p.253/同改訂版(2012年)p.263)※※。
| ※ 法律学小辞典p.70では、公の財産を、地方公共団体の所有する財産といい、公金を含む概念としています。つまり、自治体の所有であることがポイントとなります(ただし、自治体の管理下にある金銭である歳入歳出外現金も含まれる)。ここでいう「財産」は、普通名詞としての財産であり、地方自治法237条の財産とは一致しません。下記(3)ア参照。 |
| ※※ 行実昭23.10.12 では、公金とは、法令上当該普通地方公共団体又はその機関の管理に属する現金、有価証券をいうとされており、この通知は現行の地方自治関係実例判例集にも登載されているので、現在でも有効なものと観念されているようですが、地方自治法財務関係規定は昭和38年に大幅に改正されており、現行の地方自治法170条2項1、3号や238条1項6号等の規定を見る限り、本通知の通りに「有価証券」を(単純にそのまま)公金の範囲に含まれると解するべきではなく、上記の自治用語辞典の定義によるべきです。なお地方自治法231条の2第3項の代用納付証券が現実には現金と同視される有価証券と考え得なくもないですが(同項に関する松本逐条も参照)、住民監査請求・住民訴訟で問題となるのは「公金の支出」であり「公金の収入」ではない(収入した公金の管理に対する住民監査請求・住民訴訟は別の類型:たとえば損害賠償請求の懈怠などの問題となる)点も考慮すべきです。 |
イ 支出
ここでの「支出」は、実際の支出行為(地方自治法232条の4第1項)のみならず、支出の前提となる支出負担行為(地方自治法232条の3)、支出命令(地方自治法232条の4第1項)の各行為を含みます。そして公金の支出は、支出負担行為⇒支出命令⇒支出、という一連の段階を踏みますが、それぞれの行為は独立したものであり、これらを行う権限も異なる機関(職員)が有しています(終局的には、支出負担行為・支出命令が首長、支出は会計管理者)。
そのため、公金の支出を対象とする住民監査請求においては、これらの支出負担行為、支出命令、支出が、個々別々の具体的行為として※、それぞれ対象となり得ます。請求においては、これら行為を併せて監査請求することも、支出負担行為・支出命令・支出を個別に取り出して監査請求することもできます(最判平14.7.16民集56.6.1339)。この場合、たとえば前記の一連の行為をいちいち特定摘示することなく一体のものとして住民監査請求の対象としても、下記4の請求対象の特定の問題を生ずることはありません。
| ※ 金銭債務負担を伴う契約の場合、一般に、契約の締結は支出負担行為、契約の履行は支出命令・支出となりますが、最判平25.3.21民集67.3.375は、契約の締結と履行が異なる財務会計行為であることを前提として、最判平4.12.15民集46.9.2753及び最判平20.1.18民集62.1.1の判旨に基づき、締結された契約の違法性と契約の履行である支出命令の違法性の関連を論じています(締結された契約の違法により、直ちに契約履行行為である支出命令が違法になるものではない)。上記平成14年最判の考え方を前提とする結論といえます。 |
(3) 財産の取得、管理又は処分
ア 財産
ここでいう「財産」は、地方自治法237条1項にいう「財産」、すなわち公有財産、物品、債権、基金で、自治体の所有に属する財産権の対象となるもの※、とされます(同項では「この法律において『財産』とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう」としており、地方自治法242条の「財産」と237条の「財産」を別概念とする理由がありません)。
| ※ 参照:松本逐条242条、237条。なお松本逐条237条、松本要説p.566によれば、歳計現金は、自治体の所有に属するものであっても、ここでいう「財産」には含まれません。ただし、地方自治法242条の財産には現金を含むと解するべきとする学説もあります(参照:最新地方自治法講座p.33(橋本勇))。 |
またこの財産は、住民の負担した公租公課等によって形成されたものに限定されず、他の原因で取得されたもの(例:土地区画整理事業で取得した保留地)も含まれます(最判平10.11.12民集52.8.1705)※※。
| ※※ 昭和38年改正前の旧法規定下での最判昭38.3.12民集17.2.318では「(いわゆる納税者訴訟の)対象となるべき財産とは、住民の負担にかかる公租公課によって形成された地方公共団体の公金および営造物以外の財産を意味」する、としていますが、現在は、財産について上記のように定義されています。なおこの点について上記平成10年最判の担当調査官解説では「昭和38年の判決は、本判決が理由中に引用した地方自治法の『財産』に関する諸規定が整備される前のものであり、旧規定に基づく納税者訴訟につき、その対象となるべき財産とは、住民の負担に係る公租公課等によって形成された地方公共団体の公金及び営造物以外の財産を意味すると判示している。しかし、上記の整備により明文上『財産』の内容が明らかとされた以上、規定を離れて公租公課により形成されたものに限ることはできなくなったというほかはない。例えば、寄附によって取得した財産であっても、違法に処分すれば、住民訴訟の対象になることは明らかである。したがって、上記判例(昭和38年最判)は現行法に当てはまるものではない」としています(大橋寛明「時の判例Ⅰ」p.300)。当時は住民訴訟が「納税者訴訟」と観念されていたからといえます。 |
なお、上記の財産のそれぞれの項目に対する具体的な定義は、次の地方自治法の条項に定められているところによります。
| 公有財産 | 238条1,2項 |
| 物品 | 239条1項 |
| 債権 | 240条1項 |
| 基金 | 241条1項 |
| 【Q】 現金が財産に該当しないということは、職員の現金亡失を対象とする住民監査請求は不適法ということか? |
【A】
不適法ではありません。
○ 現金をなくす等による自治体の損害については、現金が財産でない以上、住民監査請求において、現金の亡失そのものをとらえて、違法不当な財産管理と構成することはできません。
○ しかし、現金亡失等については通常、地方自治法243条の2の2または民法709条により職員の賠償責任が発生します。民法上の請求権はもとより、地方自治法上の自治体の職員に対する損害賠償請求権は、同法243条の2の2第3項の首長の命令を経なくとも発生するものであり(最判昭61.2.27民集40.1.88)、損害賠償請求権は地方自治法上の財産としての金銭債権そのものにほかならず、請求の放置は財産管理上の違法となり得るので(最判平16.4.23民集58.4.892)、住民監査請求においては、同請求権が行使されないことによる損害補てんを求める請求と構成することが考えられます。
① 公有財産
住民監査請求で請求対象となる「公有財産」は、自治体の所有に属する財産のうち、次のものとされています(地方自治法238条1,2項)。また公有財産は、行政財産と普通財産に区分されます(同3項)。
以下のカッコ内注記は、松本逐条の説明によります。
不動産(土地および土地の定着物:民法86条1項)
船舶、浮標、浮桟橋、浮ドック、航空機(不動産に劣らない重要な価値をもつ動産)
上記に掲げる不動産・動産の従物(民法87条1項:左記を公有財産とする趣旨は同上)
地上権、地役権、鉱業権、これらに準ずる権利(用益物権・・・「これらに準ずる権利」は、法律上確立された用益物権や用益物権的性格をもつもの※1。よって占有権や担保物権、債権※2は含まれない。)
特許権、著作権、商標権、実用新案権、これらに準ずる権利(知的(無体)財産権・・・「これらに準ずる権利」は、意匠権等、左記例示されていない知的(無体)財産権※3)
株式、社債、地方債・国債、これらに準ずる権利※4
社債・・・特別法で設立した法人の発行債券で表示される権利を含む※5
238条2項に定める短期社債等を含まない
出資による権利(地方自治法221条3項)
財産の信託の受益権
| ※1 松本逐条では、例として、永小作権、入会権、漁業権、入漁権、租鉱権、砕石権等を財産に含めています。 なお、公物管理権や行政財産の使用許可による「利用権」がこの権利に該当するか争われた事案が住民訴訟で多数ありますが、裁判例は概ね該当しないと判断しています。「2.1.2 財務会計行為各論:財産の取得、管理又は処分」2(2)ア①参照 |
| ※2 松本逐条・松本要説p.566は、賃借権、借地権を、この公有財産に該当しないとしていますが、これら権利の物権化が見られる中では議論があるところです。実際、裁判例において、一定の賃借権を住民監査請求の対象たる財産とする事例もあります(岡山地判平17. 5.24(県主導のテーマパーク事業に係る住民訴訟において、建物所有目的・期間50年間の定期借地権につき、物権に準じた経済的価値を有し、現実にこれを公有財産として管理する必要があって、これをあえて地上権等と区別して取り扱うべき現実的根拠に乏しいから、地方自治法238条1項4号の「地上権」等に準じ、同項にいう公有財産である、とする))。また参照:実務住民訴訟p.134。 なお使用貸借については、道路法施行法5条1項に基づく国有地たる道路敷地の使用貸借による権利は、地方自治法237条1項4号の権利に該当せず、よって住民監査請求の対象となる財産ではない、とする判例があり(最判平2.10.25集民161.51)、担当調査官解説では、本件権利は民法593条の権利と異なるところはなく、住民訴訟が法により特に創設された制度であることや、国有財産法2条1項4号の解釈との整合も考慮されている、としています(増井和男「時の判例Ⅰ」p.288)。 |
| ※3 松本逐条は、特許を受ける権利(特許法33条)、通常実施権(同78条)、専用実施権等(同77条)、商標登録出願により生じた権利(商標法13条2項により準用される特許法33条)は、法律上不確定な権利なので、ここでの財産には含まれないとします。 |
| ※4 松本逐条は、投資信託の受託証券、貸付信託の受託証券等をいうとしています。 |
| ※5 松本逐条は、農林債券、商工債券、放送債券、以前の道路債券等、地方住宅供給公社や地方道路公社の発行する債券等を例示しています。 |
② 物品
住民監査請求で請求対象となる「物品」は、以下のものが該当します(地方自治法239条1項)。
・ 自治体の所有に属する動産
・ 自治体の所有には属さないが、自治体が使用のために保管する動産
なお、地方自治法239条1項各号に掲げるもの(現金(現金に代えて納付される証券を含む)、公有財産・基金に属するもの)は、物品ではありません。
また、自治体管理物品のうち、都道府県警察が使用している国有財産及び国有の物品(警察法78条1項により無償で使用させるもの)も、ここでの物品からは除かれます(地方自治法239条1項本文かっこ書、地方自治法施行令170条)。
③ 債権
住民監査請求で請求対象となる「債権」は、金銭の給付を目的とするもののみが該当します(地方自治法240条1項)。つまり、金銭債権以外の自治体の有する債権は、ここでの債権には該当しません。たとえば自治体が業者と締結した業務委託契約で自治体側が有する役務受給権などは、自治体の財産たる「債権」とはなりません。
なお金銭債権である限り、その内容がいかなるものであるか、たとえば公権力に基づき徴収する地方税、その他法令に基づき徴収する使用料、手数料、分担金等のたぐいであるか、契約に基づく金銭債権(物件売払代金、貸付料等)であるかを問わず、会計整理上は歳入にはならない過払戻入金のたぐいも、ここでの債権に含まれます(松本逐条 240条)。
多くの住民訴訟(4号訴訟)で対象とする、損害賠償請求権、不当利得返還請求権は、この債権に該当します。つまり、このような住民訴訟(先行する住民監査請求)では、自治体の財産たる債権(損害賠償請求権等)の請求をしない、つまり管理を怠る※ことが、問題とされます(参考:最判昭57.7.13民集36.6.970)。
| ※ 財産たる損害賠償請求権等(金銭債権)の管理を怠る点については「地方公共団体が有する債権の管理について定める地方自治法240条,地方自治法施行令171条から171条の7までの規定によれば,客観的に存在する債権を理由もなく放置したり免除したりすることは許されず,原則として,地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はない」(最判平16.4.23民集58.4.892)とされることにも留意しましょう。 |
④ 基金
住民監査請求で請求対象となる「基金」は、次のものをいいます(地方自治法241条1項)。
・ 特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てるためのもの
・ 特定の目的のために定額の資金を運用するためのもの
イ 取得、管理又は処分
① 取得
なんらかの法律上の原因により、自治体がその財産を保有する効果を発生させる行為です※。
| ※ 松本逐条(149条関係)では「財産の『取得』とは、購入、交換、寄附の受納等をい」う、としています。 |
ただし、自治体が財産を保有することとなる行為のすべてが、住民監査請求の対象となる財産の取得行為となるわけではないことに留意が必要です(上記(1)イ参照。なお最判昭51.3.30集民117.337は、土地区画整理事業の換地処分による土地取得は、住民訴訟の対象とならないと、また最判昭48.11.27集民110.545(ただし旧法の事件)は、財産ではなく自治体に対する金員の贈与契約を対象とするものであるが、公金の支出、義務の負担ないしは財産上の損失を伴わない単なる収入を発生させるにとどまる行為を住民訴訟の対象外としており、この論理からすれば、金員以外の財産の取得も、それが公金の支出、義務の負担ないしは財産上の損失を伴わない限り、住民監査請求の対象とならないと解される)。
② 管理※
財産の財産的価値に着目して、その価値の維持・保全を図る財務的処理を直接の目的とする行為とされます※。
なお上記(1)イの最判平2.4.12民集44.3.431は、直接的には財産管理行為に該当するかどうかの判断事例ですが、このうち「財務的処理を直接の目的とする」という部分は、財産管理行為だけではなく、地方自治法242条1項で住民監査請求の対象となる財務会計行為(怠る事実において怠っている行為)すべてにおいて必要とされる属性です※※※。
財産管理行為は多種多様な形態があり、また管理行為自体は財産の取得・処分と異なり、その資産的価値を直接増減させるものではないため、住民監査請求・住民訴訟では、しばしばその財務会計行為としての該当性が問題・争点となっているものです※※※※。
| ※ 参考:宇都宮地判平9.5.28判例時報1646.60「(地方自治)法242条1項にいう「管理」とは、当該財産の財産的価値そのものの維持、保全又は実現を直接の目的とする運用を指すものと解される」(決算添付の財産調書の修正は、財産の管理といえるが、財産の維持、保全又は実現という観点に照らすと、二次的、間接的な運用であり、地方自治法242条1項の財産の管理に該当しないとした事例)。また国有財産法9条の5参照。 |
| ※※ 松本逐条(149条関係)では「『管理』とは、その財産の移転又は消滅を生ずることなくその性質を変更しない範囲内において使用し、収益し、維持改良し、信託し、時効を中断する等の法律上および事実上の行為をい」う、としています。 |
| ※※※ 参照:上記平成2年最判に関する上田豊三「時の判例Ⅰ」p.297。 |
| ※※※※ たとえば道路などの開設廃止行為や、公物管理権による維持管理行為、また行政財産の使用許可などが、しばしば地方自治法242条1項の財産管理行為に該当するか住民訴訟で争われてきましたが、裁判例においては、財産運用的性格のある使用許可など例外的な事例を除き、おおむねこれら行為は、財務的処理を直接の目的とするものではなく、道路などの効用を維持するための行政判断、行政目的実現行為であるとして(参照:平成2年最判)、住民監査請求の対象とはならないとの判断が重ねられています。「2.1.2 財務会計行為各論:財産の取得、管理又は処分」3(2)参照。 |
③ 処分
地方自治法242条1項の「財産の処分」に関する明確な定義はありませんが、この用語自体は民法(424条の2など)等でも普通に使用されており、一般には、その財産的価値の移転・消滅(売却、廃棄等)または価値の変動(価値の制限・減少。貸出等の使用権の設定、担保提供など。価値の増加については、その部分は財産の取得に観念され得ると思われる)などを生ずる行為と考えればよいでしょう。
法律学小辞典では、「処分行為」について、単なる保管の域を超えて財産(財産権)の性質や現状を変更する行為としています(同書p.706)。
また補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律21条は、「財産の処分の制限」として、補助金等の交付の目的に反する使用、譲渡、交換、貸付け、担保提供を制限しており、参考となるでしょう(ただし目的に反する使用は、「処分」ではなく「管理」の問題ではないかと思われます)※、※※。
| ※ 松本逐条(149条関係)では「『処分』とは、売却、交換、贈与等財産について権利を移転することのほか、消費、廃棄等の事実上の変更を加えることをいう」としています。 |
| ※※ 最判平10.11.12民集52.8.1705は、土地区画整理事業において土地区画整理法96条2項・104条11項に基づいて取得した保留地を随意契約の方法により売却する行為は、住民訴訟の対象となる「財産の処分」及び「契約の締結」に当たるとする。ただし、この判決は「財産の処分」について何らかの積極的な定義を示すものではありません(土地の売却が「財産の処分」になるのは、上記の趣旨からしても当然のことです)。 |
(4) 契約の締結又は履行
ア 契約
住民監査請求の対象となる契約は、法律行為としての契約のうち、自治体を一方の当事者として、財務的な処理を直接の目的とするもの(契約と称しなくても、契約としての実質をもつものを含む)をいいます。このような限定が入るのは、上記(1)イの平成2年最判の判示事項などからの当然の帰結です。
イ 締結・履行
契約の「締結」・「履行」については、住民監査請求制度において、民法と異なる独自の意味合いを考慮する必要はないでしょう。
なお、上記(2)イの通り、契約の締結と履行は、公金支出を内容とする契約の場合の支出負担行為と支出命令・支出に相当し、これらが別の財務会計行為であるとされることとパラレルの考え方として、契約の締結行為と履行行為は、別の財務会計行為とされます(参照:最判平25.3.21民集67.3.375)
(5) 債務その他の義務の負担
自治体が、契約以外の理由で債務などの財務上の義務を負う行為をいいます。職員の給与決定などがその例となります。
(6) 公金の賦課徴収又は財産の管理を怠る事実
ア 公金の賦課徴収
「公金の賦課徴収を怠る事実」とは、自治体の公金の賦課徴収について、法令等で義務付けられた行為が行われていない状態をいいます。「公金」については、上記(2)アと同義です。
松本逐条(242条関係)では「『違法又は不当に公金の賦課若しくは徴収を怠る事実』とは、例えば、法令または条例の根拠なくして特定の者に対し地方税の課税を免除し、又は使用料等の徴収を免除することなどをいう」としています。
「公金の賦課」とは、自治体が公権力に基づき、特定の相手方に対し、個別具体の金銭の納付義務を課する行為であり、税法でよく使用されることが示す通り、権力的行為であることが特徴です※1。
つまり、一般的な契約により自治体が金銭債権、つまり相手方に対する金銭の請求権を獲得することは、ここでの「公金の賦課」には該当しません。
「公金の賦課」の対象となる収入としては、地方税、分担金、使用料、加入金、手数料などが該当するとされます(地方自治法では、242条を除き、地方税以外について「賦課」の用語を使っていませんが、ここでは公権力に基づき徴収する金銭債権全般が想定されています)※2。
また「賦課」の対象とならないような、例えば民事契約により自治体が有する金銭債権に関する義務を怠った場合(例:不用の公有車を売却した際の売払代金債権を時効消滅させた等)は、「公金の賦課徴収を怠る」ではなく、下記イの「財産の管理を怠る事実」に該当するとされます(参照:松村p.26)。
| ※1 「新自治用語辞典」 ぎょうせい (2000年)p.769では、賦課について「国又は地方公共団体が、特定の人に対して、公権力をもって公租公課を割り当てて負担させることをいう。法律又は条例の規定によって定められた抽象的な納税義務その他の金銭納付義務は、一般に、この賦課処分によってはじめて具体的に画定するのである」とします。なお、法令における「賦課」の用例は次の通りであり、いずれも公権力に基づく債権であることが特徴です。 ○地方税法2条 地方団体は、この法律の定めるところによつて、地方税を賦課徴収することができる。 ○国税通則法16条1項2号 賦課課税方式 納付すべき税額がもつぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。 ○地方自治法149条3号 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。 |
| ※2 参照:松村p.26、実務住民訴訟p.152。なお公権力に基づき科す金銭債権である過料を科さないことは、住民監査請求の対象としての「公金の賦課徴収を怠る事実」に当たらないというのが、下級審裁判例における一般的な判断です。 |
「公金の徴収」とは、「賦課徴収」の用語があるように、一般には公権力に基づき賦課した金銭債権の取り立て行為を指すと観念されていますが※3、地方自治法の「徴収」については、こうした公権力により課された債権以外の取り立てについても使用されている場合があり※4、裁判例において、債権一般の取り立て行為と解する例もあります※5。
ただし、契約その他の原因により生ずる金銭債権の取り立てをしないケースについては、下記ウにある通り、「財産の管理を怠る事実」により住民監査請求の対象とすることが可能であり、その意味からすれば、「公金の徴収」の概念を厳密に整理する実益は乏しいところがあります※6。
なお、怠るとされる行為は、財務会計行為としての性質(上記(1)イ参照)を有することが当然に必要ですが、公金の賦課徴収について、これが問題になることはまずないと思われます。
| ※3 例えば地方自治法149条3号は、首長の担任事務として、地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すことをあげています。 なお参考として、松本逐条(149条関係)では「『徴収』はその具体的となった義務(注:地方税の『賦課』により)実際に履行させる(現実に納付させる)ことを言うと解される。本法上、この両者の概念を使い分けて賦課徴収という語を使用しているのは地方税についてのみであり(法223参照(中略))、分担金、使用料、加入金、手数料については『徴収』という語を使用しているが、このうちには賦課の概念が全然入る余地がないとはいえない(法224~229参照)」としています。 |
| ※4 例えば地方自治法240条3項の「徴収停止」の対象は、前記※の滞納処分が行い得る債権以外の債権とされ(地方自治法施行令171条の5)、また地方自治法243条による徴収委任の対象債権は、使用料・手数料のほか、賃貸料、物品売払代金、寄附金、貸付金の元利償還金といった非公法債権も含まれています(地方自治法施行令158条1項)。なお、地方自治法施行令158条の「徴収」については、調定・納入通知・収入受入れ行為を指すとされています(行実昭38.12.19、松本逐条243条関係)。 |
| ※5 大津地判昭57.9.27判例時報1073.57では「地方自治法においては、「徴収」という用語は多義的に用いられ(同法223条ないし227条、240条等)、必ずしも、行政主体が法令の規定に基づきその優越的地位において住民に対して金銭給付義務を発生せしめる行政処分をすることを意味するにとどまらない。殊に、同法240条3項は債権の「徴収停止」を規定しているところ、右債権とは「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利」(同条1項)を言い、これには不当利得に基づく債権も含まれると解されるから、同法においては、「徴収」という用語に、不当利得に基づく債権の取立てという意味をも包含させているものと言わざるを得ない。そして、同法242条1項所定の「徴収」の意義についても右と別異に解する理由はない・・・」、同控訴審大阪高判昭59.5.31行裁例集35.5.679は「地方自治法において、「賦課」とは…地方公共団体が法令の定めるところによりその優越的地位においで住民に対して金銭給付義務を課する行政行為をいうのであるが、「徴収」とは、公金についてみても、地方公共団体の歳入を調定し、納入の通知をし、収納する行為をいうのであって、同法上「徴収」という用語は、地方税…ばかりではなく、分担金…、使用料…、加入金…及び手数料…等にも用いられており、要は、地方公共団体がその有する債権を取立てて収納する行為をいうに過ぎないものである。それ故同法242条にいう「徴収」も、地方税や分担金のみならず使用料や手数料債権の収納をも意味すると解するのが相当であって、必ずしも強制徴収等の行政処分を意味するとは解し得ない」とする。 一方、横浜地判昭56.4,27行裁例集32.4.698のように、公金の徴収を、公金の賦課同様、公権をもって一方的に特定人に対し債務を納付させること(つまり公権力の行使による金銭債務の回収)とする例もある。 |
| ※6 碓井p.100は、地方自治法242条1項が「公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」を一括して「怠る事実」と定義しており、これらのいずれかに該当するのであれば、それ以上に「公金の賦課徴収」と「財産」を分離して、どちらかに該当するかを詮索する意味は、ほとんどないというべきであるし、公金の「賦課」と「徴収」を厳密に分けようとする試みは不用であろう、とする。 |
イ 財産の管理
「財産の管理を怠る事実」とは、自治体の財産の管理について、法令等で義務付けられた行為が行われていない状態をいいます。
地方財務実務提要では、財産の管理を怠る事実について「一般的には、財産について規定する法の各条に従った管理がなされていない場合をいうものと解されます」としています。
「財産の管理」については、財産の定義、管理行為の定義を含め上記(3)と同義です。よって上記(3)イ②の通り、財産の管理は、財務的処理を直接の目的とするものであることを要し、また対象となる目的物は、当然に地方自治法237条1項の財産であることを要します。
分かりやすい事例として、公有財産(市有地など)が権原のない第三者に占拠されているのに放置している場合(行実昭38.12.19)や、上記アの売却代金の時効消滅のようなパターンを考えればよいでしょう。
なお、債権も地方自治法上の財産に該当するため、その管理は、一般に住民監査請求の対象になりますが、債権管理については、「地方公共団体が有する債権の管理について定める地方自治法240条,地方自治法施行令171条から171条の7までの規定によれば,客観的に存在する債権を理由もなく放置したり免除したりすることは許されず,原則として,地方公共団体の長にその行使又は不行使についての裁量はない」(ただし「地方公共団体の長は,債権で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて,「債権金額が少額で,取立てに要する費用に満たないと認められるとき」に該当し,これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは,以後その保全及び取立てをしないことができるものとされている(地方自治法施行令171条の5第3号)」)とされており(最判平16.4.23民集58.4.892)、債権管理に関する首長等の義務は、おおむね明確であるため、請求の放置等は、住民監査請求の対象になり得るものです。実際、住民監査請求、住民訴訟の実務では、債権の訴求に関する財産管理を怠る事実を対象とする事案が多数提起されています。
ところで松本逐条(242条関係)では「『違法又は不当に財産の管理を怠る事実』とは、普通財産を権原なく占有する者があるにもかかわらず、是正のための措置を何ら講じていない場合(行実昭38.12.19)、行政財産を目的外に使用させている場合に許可条件に著しく反する使用がなされていることを黙過している場合等をいう。特段の事情がない限り、地方公共団体の長その他の財務会計職員の財務会計上の行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって、財産の管理を怠る事実とする場合も含む」としています。
そして、この松本逐条説明のうち、「地方公共団体の長その他の財務会計職員の財務会計上の行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって、財産の管理を怠る事実とする場合」は、最判昭62.2.20民集41.1.122、最判平22.3.23集民233.279が参照されています。
この「地方公共団体の長その他の財務会計職員の財務会計上の行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって、財産の管理を怠る事実とする場合」についてですが、財務会計行為を行う権限のある担当職員が行った違法な財務会計行為(たとえば違法な公金支出等)を対象として住民監査請求を行うに際しては、違法な財務会計行為(公金支出等)を担当した職員(地方自治法242条の2第1項4号の「当該職員」)への地方自治法243条の2の2第1項や民法709条による損害賠償請求や、違法な公金支出を受けた第三者に対する不当利得の返還請求を行うよう求める、という直接的な是正(損害補てん)を請求することが考えられますが、これに加え、自治体がこれらの職員、第三者に有する損害賠償請求権、不当利得返還請求権の行使を怠っている(つまり、請求すべき債権を放置するという、財産管理を怠る事実がある)ので、その是正等を求める、という請求形態で「怠る事実」について請求することも可能である、ということです(この点は、同一の財務会計行為等について、争点を変更しての再度の住民監査請求は許されるか、住民監査請求後の住民訴訟で、どのような請求を構成することができるか、監査請求期間をどのように考えるか、という際に問題になります(この点に関する監査請求期間の問題については、詳細を別ページで説明)。監査委員は、本例のような違法公金支出についての監査請求がなされた場合は、請求人の求める是正等の措置の内容がどのようなものであれ(最判平10.7.3集民189.1参照)、上記のような観点を網羅して監査する必要があり、逆に、必要があれば、請求に含まれない是正等の措置の勧告ができるのです※)。
| 首長その他の財務会計職員の財務会計上の行為を違法、不当としてその是正措置を求める住民監査請求は、特段の事情がない限り、当該行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使を違法、不当とする財産の管理を怠る事実についての監査請求をもその対象として含むものと解すべきである 最判昭62.2.20民集41.1.122
【事実関係】 【判示事項】 |
| ※ なぜこのようなある意味奇妙な類型分別の発想がでてきたのかというと、大きくは、 ① 同一人による同一内容の住民監査請求は許容されないが(上記昭和62年最判)、同一人が同一の財務会計行為について、その内容を変えて請求した場合、たとえば最初は違法な財務会計行為を行った職員への損害賠償請求を求め、最初の監査請求の後、次に、違法な財務会計行為による損害賠償請求権を行使しないことを行使しないという怠る事実について請求した場合、後の住民監査請求は、前の請求との同一重複請求であり不適法、とすべきなのか、 ② 住民監査請求の請求期間は、当該行為のあった日又は終わった日から1年以内とされており(地方自治法242条2項)、たとえば違法な公金支出を対象とする住民監査請求は、公金支出日から1年を過ぎると原則としてできませんが、怠る事実に対する住民監査請求は(起点となる行為がなく、起点日の設定ができないため)この住民監査請求の請求期間に関する規定の適用はないとされており(最判昭53.6.23集民124.145)、では、違法な公金支出に対する損害賠償請求ではなく、自治体が損害賠償請求を怠っている事実があるとする住民監査請求では、請求期間をどうとらえるのか、という問題が発生したため、ともいえます(上記昭和62年最判参照)。 なお、この結論に従えば、請求人は、上記のような事例について住民監査請求を提起し、当該公金支出を違法とする首長への損害賠償請求を求める主張のみをした場合であっても、その後の住民訴訟で、公金支出の相手方に対する不当利得請求権の行使を怠る事実として、請求義務付けを求める内容の請求とすることも可能です。なぜならば、ある特定の財務会計行為等について住民監査請求を経ているということは、後続の住民訴訟で、その特定の財務会計行為等を対象とする限り、上記のような請求内容を含めて、住民監査請求を経ていることになるからです。最高裁は、そのような住民監査請求と住民訴訟での請求内容等の変更を認めています(最判平10.7.3集民189.1)。 |
この「財産の管理を怠る事実」という請求対象の類型は、執行機関や職員の行為(直接の財務会計行為とは限らない。例えば施策・事業が結果として失敗に終わった等)により自治体に損害が発生した場合、責任職員(首長等)は自治体に損害賠償責任を負っており、その債権請求をしないことは財産の管理を怠る事実であるとして、直接その職員(首長等)に損害賠償請求を(自治体に代位して)する、という形態で、平成14年地方自治法改正前のいわゆる4号訴訟で多用されたものです(なお参照:実務住民訴訟p.301)。
ウ (違法・不当な)怠る事実
なされるべき「公金の賦課徴収」「財産の管理」行為がなされていない(ために、違法・不当の法的評価を受ける)状態としての事実をいいます。要は「行われるべき公金の賦課徴収・財産管理という財務会計行為」が「違法不当」に「行われていない」状態です。
(a) 要件審査における原則・・・請求時点での不作為状態存在が要件
このうち請求要件となるのは、「行われるべき公金の賦課徴収・財産管理という財務会計行為」が「行われていない」状態が存在することです。もう少し解析すると、
① 上記の「公金の支出」「財産の取得、管理又は処分」「契約の締結又は履行」「債務その他の義務の負担」の場合は、何かの行為がされていますが、「怠る事実」では、行為がなされていない事実状態※1を指します。
② したがって、違法・不当な怠る事実は、「行為義務がある(なされるべき)行為が、違法不当になされていない」事実状態を指します(通常、行為義務があるのにそれを行わないのは、違法の評価を受けます)。例えば、非課税、課税免除や減免対象、免税点未満ではない所在建物(つまり、通常固定資産税が賦課されるべき建物)に対して、固定資産税の賦課徴収をしていない場合などです(可能な職務を尽くしてもなお賦課徴収をできないといった事情でもない限り※2、このような場合に固定資産税の賦課徴収をしない状態は違法です)。
③ そのうえで、怠るとされる不作為事実の状態が、現に存在することが、「怠る事実」を請求対象とする住民監査請求の適法要件となります。現に不作為事実が存在しなければ、その不作為事実を監査対象として特定して監査を求めることに法的な意味がないこととなり、また不作為事実について監査を行い、その結果として当該事実を改める措置の勧告等を行う(そのことを検討する)意味もないからです。
④ したがって、不作為とされる行為がなされたことにより怠る事実が事実状態として現に存在しないときは、当該「怠る事実」を対象とする請求は、原則として※3不適法となります。そのような過去の怠る事実は、住民監査請求では当該「怠る事実」を対象とする請求としては、取り上げることができません。ただし、怠るとされる作為義務の内容である請求権(たとえば自治体が請求すべき請求権を放置といったケース)が時効や除斥期間経過等で消滅したという場合、法的評価としてみれば「怠る事実」は消滅していますが、作為義務の消滅による怠る事実の消滅は下記(b)の例と同様、対象とされる「怠る事実」に対する作為義務の法的評価の問題そのものであり、監査を経て評価されるべき事項です(怠る行為がなされた場合は原始的に怠る事実が解消されたと言えますが、作為義務の内容である請求権の時効等消滅の場合はこれと異なり請求権の行使は依然なされていない状態であるということができます)。つまり、こうしたケースは「怠る事実の不存在」により請求不適法とすべきではありません※4。
| ※1 公金の支出がなされた事例に対し、その支出の違法確認を求める住民訴訟(3号訴訟)は不適法とする裁判例があります。このような事例は4号訴訟(損害賠償請求)の対象とすべきであり、当然の帰結と思われます(京都地判昭54.11.30判例時報962.57)。 |
| ※2 参考:横浜地判昭54.10.31判例時報947.35。在日米軍基地内の家屋について、課税調査のための基地立ち入りを基地司令官に拒否されたために固定資産税の賦課ができなかったのは、違法に公金の賦課徴収を怠ったとはいえないとした事例。 |
| ※3 怠るとされた行為が、住民監査請求の事前または事後に実際になされた場合、なすべきと摘示する行為がなされたのですから、通常は請求人にとっては肯定的評価がされる事実状態のはずですが、不作為を摘示された行為と実際になされた行為の間に同一性があり、請求人において、当該行為義務が十分に果たされていない等によりなされた行為に違法不当性が付着するとして、その行為に対する住民監査請求を提起する意思が認められる場合、監査請求期間の終期が迫り、また当該財務会計行為を「怠る事実」として請求対象として摘示したことについてやむを得ない事情があるときは、その実際になされた財務会計行為の監査に請求対象を振り替えることを認める余地もなくはないと考えます。 なおこの場合、住民監査請求と住民訴訟で請求(訴訟)要件の考え方が異なるところ、この点について、住民監査請求は住民訴訟ほど拘束的な請求の枠組みを採用していない(参照:下記3(3)イ※※※)ことを踏まえれば、結果として住民監査請求と住民訴訟の要件に相違がでることはやむを得ないものと考えます。 |
| ※4 京都地判昭54.11.30判例時報962.57は、怠る事実に係る作為義務が事後的になされた事案ではなく、公金の支出自体を3号訴訟の対象とするものだが、判決説示の判断枠組みにて、支払済み公金支出に係る怠る事実の違法確認の訴えを不適法とする。また広島地判昭50.8.29行裁例集26.7・8.952は、固定資産税の賦課徴収を怠る事実があったとしても、住民訴訟提起時においては賦課徴収済である事案について(監査係属中に徴収)、被告の不作為状態は解消されているので、地方自治法242条の2の規定に基づく怠る事実の違法確認を求める訴は、その利益を失うとします。 なお過去の怠る事実、つまりその行為を過去することができたが、現在では消滅時効の完成、法規改正等でその行為を行うことができなくなっているときについては、大阪高判平7.12.20判例タイムズ914.151(その不作為は現在では違法でないものとする他ない(住民としては3号訴訟以外の形態の住民訴訟による他ない))、東京地判平成16・3・25(固定資産税の賦課を怠る事実を対象とする3号訴訟のうち税債権が時効消滅した部分について、「被告は、固定資産税の法定納期限から5年を経過することにより、固定資産税の徴収権が消滅するため、…年度の固定資産税の賦課に係る部分は、訴えの利益を欠き不適法なものである旨主張する。しかし、徴収権に係る時効期間の経過があったとしても、それにより、原告の主張する「怠る事実」がそもそも存在しなかったことになるものではなく、地方自治法が住民訴訟の類型として直接的に違法状態の是正を求めることなく、単に違法の確認という請求をも認めている趣旨にかんがみると、違法確認の請求は、その認容判決が確定した後に違法状態自体を是正し得るか否かにかかわらず適法なものと考えるべきであるから、徴収権が時効消滅したとしても、そのことにより本件…年事件の訴えの利益がなくなるものではないというべきである」と判示)が参考となるでしょう。 |
(b) 要件審査における違法不当性審査の必要性
上記③(請求要件)においては、②(違法不当に怠る事実の説明)には記載されている「違法不当」の部分がありません。
要件審査の段階においては、請求人が違法不当と主張する、財務会計行為の不作為事実が存在することが特定確認されれば、なされていない財務会計行為が「なされるべきものか」、つまり、なされていないとされる行為について行為義務があるのかについては、要件審査段階ではなく、監査で判断されるべき事項と解されます※5。
なぜならば、行為義務の存否は、その「行為がなされていない状態」が違法(不当)か判断するための核心的な要素であり、監査により判断されるべき事項だからです。これはたとえば、違法な公金支出を対象とする住民監査請求がなされた場合、公金支出の事実が特定確認できれば、監査によって、その公金支出が違法かどうか判断される(要件審査段階で、公金支出の違法性の判断はしない)のと一緒です。
地方自治法242条1項には「違法・不当な公金の支出・・・」又は「違法・不当に公金の賦課徴収、財産の管理を怠る事実」とありますが、この法文は「公金支出・・・」「怠る事実」という監査対象事項にそれぞれ「違法不当」という法的評価が連結した規定となっているところ、要件審査段階の問題は、請求対象が「財務会計行為」または「怠る事実」であるのか、すなわち「公金支出・・・」「怠る事実」に相当する事実があるかどうかが要点であり、一方で、違法不当性の法的評価は請求の本案部分であり、監査で判断されるべき事項となります(要件審査と監査の役割分担です)。そして地方自治法は「違法不当な公金支出・・・(財務会計行為)」「違法不当な怠る事実」と、同様の法文構造で規定していることに留意すれば、上記の結論が法規定の素直な解釈となるものと考えます。
したがって、外形上「行為が行われていない状態」について住民監査請求が提起され、実際にそのような(請求人が違法不当に怠ると主張する)不作為の状態の存在が(事実証明書等で)現に事実として認められる場合は、一般に(要件審査の段階で「行為がなされていない状態」に違法不当性が認められないことが明らかな事案は別として)、「行為義務に反して行為がなされていないのか」の点については、監査によって判断すべきものと考えます※6。
また以上を踏まえれば、請求人の摘示する不作為の事実があったとしても、要件審査段階では、事情変更により行為義務が消滅するなど行為義務を履行する余地がなくなった事情がうかがわれる(可能性がある)場合も、要件審査の段階で行為義務の消滅等(行為義務を履行する余地の不存在)が明らかに認められる場合を別として、上記と同様、監査によって判断すべきものと考えます(上記(a)④後段も参照)。これは行為義務の消長判断は、上記のような行為義務の存否判断と、本質において、なすべきことに何ら変わりがないことが通常だからです。
| ※5 最判平13.12.13民集55.7.1500では、自治体所有地の地下に第三者がその所有する鉱さい処理施設を埋設し土地を無権原占有しているとして、首長が収去請求しないことが財産の管理を怠る事実であることの違法確認訴訟(3号訴訟)において、原審は、当該第三者が公有地を占有しているものではないと判断した上で、それを根拠に怠る事実はないのだから本訴は不適法と判断したところ、最高裁は、現に公有地の財産的価値に影響を及ぼし得る施設が存在し、当該自治体の首長が収去請求をしていない以上、原告の主張する「不作為」自体は存在しており、その第三者が当該施設を所有して公有地を占有しているかどうかは、収去請求権の有無(つまり首長に収去請求をすべき義務があるかどうか)に関する本案の問題であると判断しています。本判決は本件事案のもとでの判断であり、一般的に首長の収去請求の不行使さえあれば、常に適法な住民訴訟となるとまでいうものではないであろうとされますが(竹田光広「時の判例Ⅰ」p.310)、いずれにしても重要な参考事例であると思われます。 また東京高判平15.4.22判例時報1824.3(町道敷地の占有者に明渡請求をしないことについて争う(旧4号妨害排除請求)住民訴訟であり3号(確認)訴訟ではない)では、違法に怠る事実がなければ、住民訴訟の提訴要件を欠き、訴えを不適法として却下すべきとも思われるが、訴訟の本質からみれば、請求権の存否だけではなく違法な行為であるかあるいは違法に怠っているのかどうかが住民訴訟の主題であり、その点についての裁判所の判断には、一定の場合に不可争力が与えられるべきであるとして、類型的一般的に違法な怠る事実がないと評価される場合で、住民訴訟の主題にふさわしくないものであるなど、不可争力を与えるまでもない場合等を除き、訴え却下ではなく本案判決をすべきものと判示しています。住民監査請求は、地方自治法242条の2第1項のような訴訟類型の拘束的な枠組みがなく、監査委員も自ら必要と認める措置を勧告する権限がある仕組みであることを踏まえれば、やはり重要な参考事例であると思われます。 |
| ※6 なおたとえば「行為がなされていない」状態が存在しており、一定の行為義務が設定されている場合であっても、行為者に裁量権が認められている場合は、その裁量権の範囲内であれば、違法の評価は受けませんが、その部分に関する判断は本案、つまり住民訴訟であれば、却下ではなく請求認容か棄却の判断をされる問題であり、住民監査請求であれば、監査を行って判断すべき問題です。参照:上記※5平成15年東京高判、また実務住民訴訟p.153。 なお実際には、税の賦課などを除けば、自治体の行為義務については、裁量が認められるケースは、決して少なくないものと思われます。実務住民訴訟p.158は、最判平16.4.23民集58.4.892について、自治体が客観的に存在する債権を理由なく放置・免除することについて、『原則として』裁量はないとしており、こうした債権管理事案について、自治体の裁量権が絶対的に否定されるものではないことに注意を促しています。 |
3 財務会計行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合
(1) 要旨
請求の対象である財務会計行為(公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担)が未だなされていない場合であっても、これがなされることが相当の確実さをもって予測される場合は、その行為を対象として住民監査請求をすることができます。いうまでもなく、この財務会計行為は、住民監査請求の対象となり得るものに限られます。
この「相当の確実さをもって予測される」とは、その行為がなされるおそれがある場合、単に可能性が漠然と存在するというだけではなく、その可能性、危険性等が相当の確実さをもって客観的に推測される程度の具体性を備えている場合を指す、とされています(松本逐条。なお併せて、「どの程度の要件を備えれば『相当の確実さ』を有するといいうるかは、個々具体的に判断するほかない」としています)※。
| ※ 行政実例において、職員の昇給決定が違法・不当に行われた場合、将来の職員退職時に不当な額の退職手当が支給されることが条例上予測されることを、「相当の確実さをもって予測される」ケースとする事例があります(行実昭49.7.11)。 |
(2) 「相当の確実さをもって予測される」ことの請求適法要件性
ア 一般論
未だなされていない財務会計行為を対象とする場合、「相当の確実さをもって予測される」ことは、請求の適法要件と解されます※。つまり、未だなされていない公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担のうち、これらがなされることが相当の確実さをもって予測される程度に至らない状態で、これらを対象として住民監査請求を行っても、不適法な請求となります※※。
住民監査請求の対象となり得る財務会計行為は、公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担の4種類であり、既成のこれら行為のほか、行為が未成ではあっても相当の確実さをもって予測される場合は、既成の行為同様、住民監査請求の対象となる、とするのが法文の素直な読みであり、そうなると例えば、公金の支出は住民監査請求の対象となりますが、既成の公金支出行為は当然これにあたるとして、相当の確実さをもって予測される状態にある未成の(予測される)公金支出も、既成の行為同様、地方自治法242条1項で住民監査請求の対象とされる公金の支出に該当する、つまり地方自治法242条1項所定の公金の支出である、ということになります。
これを逆に言えば、未成の行為で、相当の確実さをもって予測される状態にないものは、地方自治法242条1項で住民監査請求の対象として列挙される行為に該当しないので、そのような行為を対象とする請求は不適法、ということになります※※※。
| ※ 大分地判平11.9.20判例地方自治200.48では「地方自治法242条の2第1項1号の差止請求訴訟は、未だ行われていない財務会計上の行為の差止めを求めるものであり、同法242条1項が、このような財務会計上の行為について、「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」には、これを対象として住民監査請求をすることができるとしていることからすると、右のような場合であることが、住民監査請求及びこれに対応する差止請求訴訟の適法要件になると解される」とし、あわせて「相当の確実性の要件が、住民訴訟のみならず、これに前置された住民監査請求の適法要件でもある以上、住民監査請求の時点で相当の確実性の要件を備えておらず、右監査請求が不適法である場合には、当該行為等の違法又は不当についての実体的判断による予防の機会が監査委員に与えられていない点で、他の適法要件が欠缺する場合と異なるところはない」とする。 また大阪地判平23.1.14判例地方自治350.19は「地方自治法242条1項は、普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長その他の財務会計職員について、「違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。)と認めるとき」に監査請求をすることができる旨規定し、「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」には、まだされていない当該行為を対象としてその防止等を求める監査請求ができることを明らかにしている。そうすると、上記規定の文理上、「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」に該当しない場合には、普通地方公共団体の住民は、当該行為がされる前にその防止等を求めて監査請求をすることはできないと解される。したがって、「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」(相当の確実性)の要件は、当該行為がされる前にその防止等を求める監査請求の適法要件であるということができる」とする。 |
| ※※ 参考:実務住民訴訟p.28 |
| ※※※ ただし、相当の確実さをもって予測される状態かどうかは判断の要素があるため、要件審査段階で相当の確実さをもって予測される状態にはないことが明らか、とはいえない場合は、監査を行ってこの部分の判断を行う(その上で、相当の確実さをもって予測される状態と判断されれば、本案部分の判断を行う)しかないものと考えます。 |
イ 予測される行為が「違法(不当)」であることの必要性
行為が「相当の確実さをもって予測される」場合が住民監査請求の要件審査における適法要件に該当することはともかくとして、さらに「違法(不当)な行為」または「行為が違法(不当)に行われる」ことまで適法要件として求めるか(単なる行為発生の予測だけではなく、それが違法(不当)であることが予測されることまで要求するか)否かについては、碓井p.15はこれを要求するのが裁判例の傾向としています。一方、判例行政法p.109(石津廣司)は、裁判例により見解が分かれている旨の説明をしています(要求する例として東京地判平5.9.8判例時報1478.99、前記平成11年大分地判(ただしいずれも住民訴訟について)。要求しない例として大阪高判平9.2.21判例地方自治168.42※)。
筆者としては、上記の通り裁判例の方向が明確でないところはありますが、たとえば既成の公金の支出の場合は、公金の支出の事実があれば、住民監査請求の要件は充足し(違法不当性の有無は、監査によって決せられる(本案の)問題である)、かつ、未成の公金の支出であっても、上述の通り「相当の確実さをもって予測される」の要件を満たせば、地方自治法242条1項の住民監査請求の対象である公金の支出が存在する場合と同様に扱う、つまり請求要件判断の場面では、未成の公金支出行為が既成の公金支出行為と等価であることとの均衡を考慮すれば、事実としての行為の確実な予測があれば、それが違法に行われるかの予測までは、要件審査において要求する必要はないと考えます※※。
ただし、下記4(3)ウで述べる通り、請求人がその未成の財務会計行為を違法不当と認める論拠の主張は、当然に必要です。
| ※ 上記平成5年東京地判は、対象財務会計行為が行われることが相当の確実さをもって予測されると認めた上で、その財務会計行為が違法性を帯びるかは当時点では判断できないので、同行為が違法に行われることについては、それが相当の確実さをもって予測される場合であるとは認め難く、現時点においては、本件行為を対象としてその差止めを求める住民訴訟を提起する要件が欠ける、とした。 一方平成9年大阪高判は、地方自治法242条の2第1項1号に基づく差止請求は、差止めの対象である財務会計上の行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合に限り許されるものと解されるが、当該行為が違法であるか否かは専ら実体法上の判断であり、当該行為に違法性のあることが差止請求の訴えの適法要件であると解することはできない、とした。 |
| ※※ 次のようにも考えられるのではないでしょうか。 すなわち住民訴訟においては、訴状が受理されれば口頭弁論が開かれて本案の問題も本案前の問題も同時に審理され、結果として訴訟判決(住民監査請求の請求要件欠缺)で終結することも本案判決に至ることもあります。一方で住民監査請求においては、要件審査は住民訴訟における訴状審査(民事訴訟法137条)に類似するプロセスとなり、ここで請求要件欠缺判断がなされれば住民訴訟における口頭弁論に相当する監査委員の監査は実施されないこととなります。 しかしいうまでもなく違法不当性の存否は通常、監査を経てはじめて監査委員としての判断がなされるべき本案の事項であり、監査実施前の請求要件判断時点で違法性の存否を確定できるとは限らないし、監査の実施を省略して監査委員がそのように判断することの制度目的的な適切性にも疑問が生じるところです。 そうなると、違法不当性の存否は、住民監査請求の請求要件審査においては、違法性の存否に疑念があったとしても、事実としての蓋然性要件が満たされると判断すれば、監査して判断すべきものとする他はなくなる、というべきです。。 |
(3) 「相当の確実さをもって予測される」状態の変動
ア 請求後に「相当の確実さをもって予測される」状態では無くなった場合
住民監査請求の提起時点で、未成の財務会計行為が「相当の確実さをもって予測される」段階にない場合は、その請求は不適法なものと解されます(上記(2)ア※平成11年大分地判参照)が、住民監査請求時点では、財務会計行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合であっても、その後、その行為がなされることが相当の確実さをもって予測されることがあり得なくなった場合、住民訴訟では、訴えは不適法となります※。
| ※ 参照:最判平23.10.27集民238.105、実務住民訴訟p.217、判例行政法p.112(石津廣司) |
住民監査請求においても、その過程でこのような事態となったときは、既に対象とすべき財務会計行為が存在しないのと同然なので、(住民訴訟の例に倣い)不適法な請求とすべきですが、請求から要件審査までの段階において事情変更が認められるケースでは、要件審査段階での予測可能性の消滅判断が容易とは限らないことからすれば、一見明白に「相当の確実さをもって予測される」状態ではない場合、監査を行って、相当の確実さの判断を先行してするしかないと考えます。
イ 請求時点で予測段階だった行為が請求後実際になされた場合
請求時点では予測段階であった行為が、住民監査請求の提起後、監査終了までに実際になされた(完了した)場合、予測段階の財務会計行為を対象とする請求と局限的にみれば不適法な請求といえるものです※
しかし、現になされた財務会計行為が存在する状態となっており、かつ請求人にとっては従前にも増して看過しがたい状態が出現していると考えられること、さらに適法な住民監査請求を経ていることが住民訴訟提起の要件となっていることも考慮すれば、対象となる財務会計行為の同一性が請求時と現在で実質的に変更がなく、請求人が当該財務会計行為の違法不当性を問題とする請求意思・請求内容に変更がないのであれば、実際になされた財務会計行為の監査に振り替えることを検討することが適当であると考えます※※。
なお以上に関する限り、住民訴訟と住民監査請求で請求要件についての取扱い方が異なる結論となり得るところ、この点はやむを得ないところがあると考えます※※※。
| ※ 1号住民訴訟の要件について、実務住民訴訟p.215、判例行政法p.111(石津廣司) |
| ※※ 実務住民訴訟p.102は、住民訴訟において訴訟の途中で、差止対象の対象財務会計行為がなされた場合、4号請求に変更することは、比較的容易に認められるとする(同一事実について既に監査委員の監査を経ており、請求の類型を変更しても、監査委員の判断は変わらないと考えられるため)。また参照:井上p.221、判例行政法p.157(石津)。 |
| ※※※ 自治体の財務運営の自浄機能を担う住民監査請求においては、住民要件を欠いたり請求対象がまったく地方自治法242条1項の類型に該当しないなど明らかに不適法な請求の場合は別として、住民訴訟ほど厳格に請求要件適合性に拘束されなければならない必要性がないことによります(地方自治法242条の2第1項の訴訟類型に相当する定めがなく、違法不当と認め得る財務会計行為等が存在する限り、監査を行うことは幅広に認め得ること、住民監査請求では最判平10.7.3集民189.1に示されるように監査委員は請求人の請求の趣旨に拘束されない考え方がなされていること、住民訴訟においても1号請求から4号請求に訴えの変更を認めた事例があること(横浜地判平23.10.5判例タイムズ1378.100)を考慮。また請求対象特定要件における厳密性の考え方ではあるが参考:下記4(1)※5最判判解、4(3)ウ※7最判判解、仙台高判平17.10.12)。また、住民監査請求と住民訴訟は、自治体財務運営の適正化を図るという作用の点で同様の機能を持ち、かつ住民訴訟が住民監査請求を前置して連続して行われる仕組みであることからすれば、請求要件はできるだけ斉一的であることが望ましいともいえますが、一方で、住民監査請求は裁判所という第三者による裁定機能である住民訴訟と違い、自治体内部における自浄的機能であることを考慮すれば、住民訴訟より請求要件を幅広くとることにも合理性・合目的性があるものであり、その点において、住民監査請求と住民訴訟で要件判断のずれが出るのはやむを得ないものと考えます。 なお「財務会計行為の同一性」について念のため、上記平成23年横浜地判においては、同件の差止(1号)請求から損害賠償等(4号)請求への変更前後について、「財務会計上の行為に係る「事実」の同一性がある」(訴え変更後の監査請求前置判断において)としており、実際こうしたケースではかかる判断が適当となる事例が多くなるものと推測します。参照:判例行政法p.157(石津廣司)、実務住民訴訟p.348。 |
4 請求の対象行為等の特定
(1) 請求の適法要件としての「対象の特定」及びその趣旨
地方自治法242条1項には明文規定がありませんが、最高裁判例により、住民監査請求においては、その請求の対象が上記2(請求対象となり得る財務会計行為等)に該当し、かつ、請求の対象となる財務会計行為等が、請求人が提出した請求書その他の資料などから判断して一定の個別具体の範囲で特定されていなければならない、つまり請求人は、監査委員が何を監査すべきか(監査の対象となる財務会計行為等)を個別具体に特定して摘示しなければならない、とされています。
監査の対象となることがらが、請求人によって特定されていなければ、その住民監査請求は不適法な請求です。つまり、請求の対象が上記2の財務会計行為等であっても、この特定を欠く場合は、住民監査請求の適法な請求要件を欠くことになるのです※1。
| ※1 ここで「特定」の対象となる事項とは、監査の対象となる財務会計行為等(財務会計行為・怠る事実)、つまり監査対象となる事実関係の単位のことを指します。 これに付随する事項、つまり、誰にどのような措置を求めるのかの特定、当該財務会計行為等に関する財務会計職員等の特定、当該財務会計行為等に関する違法不当性の特定については、いったん脇におきます。この点については、下記(3)を参照して下さい。 |
平たく言えば、具体的に何を監査するのかは、請求人が何らかの方法で示し、これにより監査委員が「具体的に何を監査すべきか」特定できなければならない、ということであり、たとえば「ここからここまで全部調べて、問題のありそうなものを監査委員がピックアップせよ」的な請求は認められない、ということです。
請求対象の特定を住民監査請求の適法要件とすることについては、上記の通り地方自治法242条の明文の規定にはなく、次の判例が、基本的な判断の枠組みを示しています。
| 住民監査請求は、その対象とする財務会計上の行為又は怠る事実を他の事項から区別し、特定して認識できるように個別的、具体的に摘示し、また右行為等が複数である場合には、右行為等の性質、目的等に照らしこれらを一体とみてその違法又は不当性を判断するのを相当とする場合を除き、各行為等を他の行為等と区別し、特定して認識できるように個別的、具体的に摘示してしなければならない 最判平2.6.5民集44.4.719
【事実関係】 【判示事項】 |
最高裁が、地方自治法242条1項明文の規定がないにもかかわらず、このような請求要件の枠組みを設けるのは、住民監査請求の制度趣旨によるものです。
地方自治法は、住民参政の仕組みとしての監査請求制度として、事務監査請求制度(地方自治法75条)を設け、これを利用する条件は厳しい(有権者総数の50分の1以上の連署が必要)ものの、この制度では、自治体の事務の執行について(財務のみならず事務執行全般に及ぶ)監査を求めることができます。この制度の目的は、住民が行政運営上に生ずる諸問題に関連してその責任の所在及び行政の適否を究明するためとされます(新自治用語辞典編纂会編「新自治用語辞典」ぎょうせい(2000年)p.93)。
一方で住民監査請求制度は、住民一人からでも請求できる一方、監査対象事項は地方自治法242条1項において、同項所定の財務会計行為等に限定されており、かつ違法性判断機能としての住民訴訟制度を後置する仕組みです。
(司法権の作用は、立法・行政権において顕著な政治的意思表示作用とは対蹠的なものであり、国民の行使する参政権も、主に立法・行政権に向けた政治的意思の表明行為に外なりません。一方で司法の行う違法性の判断は、本来政治的に中立かつ技術的なものです※2。またその違法性は、その対象を財務会計行為(怠る事実もその怠っているとするなされるべき行為は財務会計行為である)に限定している以上、財務会計法規上の観点※3から判断されるべきものです(参照:最判平4.12.15民集46.9.2753))。
とすれば、あくまでも住民監査請求における請求の対象は、財務会計法規上の点から評価可能な、地方自治法242条1項所定の具体的な行為等(参照:田中 中p.115)に限られるべきものであり、事実上は政策の当否を問う、網羅的・包括的な監査請求は、住民監査請求制度で対応すべき事項の枠外であって、そうした問題は、参政権的作用である事務監査請求制度で取り扱われるべきもの、となります※4、※5。
したがって、もとより住民監査請求は住民一人から請求できるため、事務監査請求より簡単に利用できるものですが、そのためをもって、住民監査請求で目的を異とする政策判断の当否を問うような請求を認めることは、制度論的観点からみて適切ではないということになります(なお上記平成2年最判は、本質的には請求内容の定性的な点を問題としているのであって、定量的な点、つまり監査対象事項が大量となることを問題としているのではありません(無論、60日以内に監査委員が消化できるかどうかという実務的問題はありますが))。
最高裁の判断や、下級審の裁判例における判断は、まず根底にこのような考え方があることを理解しておくことが必要でしょう。
| ※2 こうした司法権の特質については、古典的な見解ですが「司法権の固有の領域は、具体的事件に対する法の適用である。司法権の行う作用は、法の維持または擁護を本質とし、もともと法的作用であって政治的作用ではない。したがって、裁判官は、政治的に無色・中立であり、政治闘争の圏外に立つことが要請される。司法権は、立法権や行政権のような政治的権力ではない。モンテスキューは、これを「いわば無」であり、ゼロの権力である、といった」(清宮四郎「憲法Ⅰ(第3版)」有斐閣(1979年)p.96)が、端的な説明となるでしょう。 |
| ※3 (本Webサイトの趣旨からすれば傍論的な論点です) まず財務会計行為等の違法不当性の評価が財務会計法規上(地方自治法第9章の規定を中心に)の観点からなされるのは、概念論的に見れば当然のことです。ただし、財務会計法規とは何か、また対象行為等の違法不当性の評価を財務会計法規上の観点からのみとすべきなのかについては、論争的なところがあります(参照:碓井p.139)が、監査実務上は、裁判例等も参考に、現実的な問題解決的視点から判断するしかないでしょう。 |
| ※4 参考:青柳馨「最高裁判解(平2)」p.226 |
| ※5 ただし上記最判判解(青柳)p.227ではあわせて「もとより、法が、住民監査請求について、住民訴訟におけるのと同程度に厳密に請求を特定することを要求しているものとは解されない。実務では、事実を証する書面も、特段の形式を要せず、事実を具体的に摘示していれば足り、監査請求人が他人から聞知したことを書面に作成したものや新聞記事の切抜き等でもよいとされている。本判決も、そのように厳密に特定することを要するといっているのではなく、その趣旨は、一定期間にわたる当該行為等を包括して、これを具体的に特定することなく、監査委員に監査を求めるなどは許されていないとする点に重点があるとみなければならない。監査請求の趣旨をできるだけ意味のあるものとして理解するという原則に立った上で、当該請求を個別的、具体的な請求と見ることができるかということが問題とされているのである。住民監査請求における事実摘示に不備な点があっても、できる限り意味のあるものとして理解し、当該請求が個別的、具体的なものとして理解される以上、これを適法なものとして監査を行うべきである。本判決は、監査請求書およびこれに添付された事実を証する書面の各記載、監査請求人が提出したその他の資料等を総合してこれを判断すべきものとしている」「本判決は、住民監査請求が請求の特定を欠き不適法である場合、監査委員は『右請求について監査をする義務を負わない』としているにとどまる。監査委員は、必要があると認めるときは、いつでも普通地方公共団体の財務に関する事務の執行等の監査ができるのであって(略)、右監査請求を端緒にして右職権を発動することができるのはいうまでもない」としています(なおこれは、多少の不備があっても善解可能なものについては善解することが適当であるという考え方ではありますが、あくまでもこれは方法論の問題であり、前記により請求人が請求対象特定の一義的責任を有しなくなる(転嫁される)、ということではありません)。 |
(2) 「特定」の具体的内容
ア 前提
再掲となりますが、上記平成2年最判の判示事項のポイントは、住民監査請求に当たっては、単に監査委員に監査の端緒を与えるだけではなく、具体的に何の財務会計行為等に対する監査を求めるのか、請求人において、監査委員が対象の行為等を他の事項から区別して特定認識できるように、個別的、具体的に摘示して特定しなければならない、というものです※。
| ※ 請求人は監査の端緒を与える程度に請求の対象を特定すれば足りる(ある程度漠然としていても可)、という考え方は取らない、ということです。学説では、監査の端緒を与えればよいという考え方は一般に監査の端緒説といわれ、有力な見解とみなされています。参照:上記平成2年最判の園部逸夫裁判官反対意見、人見剛「地方自治判例百選」4版p.147/5版p.137、また碓井p.58。 |
したがって同判決が、3か年度にわたり会議接待費等の名目で5千万円以上の偽装支出がされたとする事案に対し、「(住民に対し)一定の期間にわたる当該行為等を包括して、これを具体的に特定することなく、監査委員に監査を求めるなどの権能までを認めたものではない」としていることからも、一定の期間にまたがる包括的な財務会計行為等を監査の対象とするような請求は、不適法となります。
イ 複数の財務会計行為等の特定
① 原則
ひとつの財務会計行為を請求対象とするなら、特定の問題は通常起きないでしょう。この問題は、複数(多数)の財務会計行為等を対象とする場合に顕在化するものです。
では、上記の事例のように複数の財務会計行為等を請求の対象とする場合はどのように監査の対象を特定する必要があるのでしょうか?
上記平成2年最判では「当該行為等が複数である場合には、当該行為等の性質、目的等に照らしこれらを一体とみてその違法又は不当性を判断するのを相当とする場合を除き、各行為等を他の行為等と区別して特定認識できるように個別的、具体的に摘示することを要する」としています。
要は、請求対象の個数がいくつであろうが、対象の特定の必要性およびそのレベルはかわらない、ということになります(特定のレベルは、下記エで説明)。
② 例外・・・「当該行為等の性質、目的等に照らしこれらを一体とみてその違法又は不当性を判断するのを相当とする場合」
上記平成2年最判が示す「当該行為等の性質、目的等に照らしこれらを一体とみてその違法又は不当性を判断するのを相当とする場合」は、複数の財務会計行為等であっても、請求人がそれぞれ個別的・具体的に摘示することを要する、という原則に対する例外です。
これは、何らかの複数の財務会計行為等に共通する(共通項としての)指標があり、この指標によって、対象となる財務会計行為等がおのずから特定でき、かつその指標を通じることで、それら財務会計行為等の違法・不当性をまとめて(一体のものとして)評価できるのであれば、個別具体に対象となる財務会計行為等を一件一件示さなくとも、その指標を示せばよい、ということです。
この要件のポイントは、A)特定の指標を用いれば、監査委員において、対象財務会計行為等を一意的に特定できる B)この指標(共通項)で括られる財務会計行為等は、この指標を通じることで、一体として違法不当性の評価ができる(個別の財務会計行為等に対して一件一件個別に、違法不当性の評価をしなくても、その指標に関する法的評価により、おのずから、ここで括られた財務会計行為等の法的評価が定まる) という点にあり、この条件を満たすのであれば、上記の通り、請求人が一件レベルで財務会計行為等を個別に摘示しなくてもよい、ということです。
これは見ようによっては、包括的な監査対象の摘示を許容するものともいえます。ただし包括的に指定される財務会計行為等の群の中味は、客観的に個別の財務会計行為等に分離特定できなくてはなりません。
この点については、次の最高裁判例が、判断の基準となります(後者の平成5年最判は参考例)。
| 市の施行する予定の土地区画整理事業は違法であると主張し,市作成の当該年度一般会計歳入歳出決算書の抜粋等を添付して,同年度に同事業のために支出された公金を市に返還し,今後もこのような不当,違法な事業に対し公金を支出しないよう適切な措置を求める旨の住民監査請求につき, ①上記事業にかかわる公金の支出を全体として一体とみてその違法性又は不当性を判断するのを相当とする場合に当たること ②上記監査請求において返還を求めるべきであるとされた公金の支出が上記決算書の抜粋に特定の経費として記載されたものを指すことは明らかで,監査委員において各支出行為を容易に把握することができること ③上記事業を特定することにより差止めの対象となる公金支出の範囲も識別することができること ④上記監査請求の時点では事業計画の決定及び公告がされていなかったとはいえ,土地区画整理事業の都市計画決定がされて施行区域も定まり,市の事業計画(案)も縦覧に供され,施行規程も制定されるという段階に至っており,差止めの対象となる公金支出がされることが相当の確実性をもって予測されるかどうかの判断も可能であったこと など判示の事情の下においては,上記監査請求は,請求の対象の特定に欠けるところはない 最判平18.4.25民集60.4.1841【事実関係】 特定の土地区画整理事業が違法であるとして、X年度の決算書抜粋を添付して、X年度に当該土地区画整理事業に支出した公金を自治体に返還し、今後もかかる事業に公金支出しないよう適切な措置を求める住民監査請求を行った事例【判示事項】 ○ 住民監査請求においては,その対象が特定されていること,すなわち,対象とする財務会計上の行為又は怠る事実(以下「当該行為」という。)が他の事項から区別し特定して認識することができるように個別的,具体的に摘示されていることを要する。しかし,その特定の程度としては,監査請求書及びこれに添付された事実を証する書面の各記載,監査請求人が提出したその他の資料等を総合して,住民監査請求の対象が特定の当該行為であることを監査委員が認識することができる程度に摘示されているのであれば,これをもって足り,上記の程度を超えてまで当該行為を個別的,具体的に摘示することを要するものではない。また,対象となる当該行為が複数であるが,当該行為の性質,目的等に照らしこれらを一体とみてその違法性又は不当性を判断するのを相当とする場合には,対象となる当該行為とそうでない行為との識別が可能である限り,個別の当該行為を逐一摘示して特定することまでが常に要求されるものではない。そして,地方公共団体が特定の事業(計画段階であっても,具体的な計画が企画立案され,一つの特定の事業として準備が進められているものを含む。)を実施する場合に,当該事業の実施が違法又は不当であり,これにかかわる経費の支出全体が違法又は不当であるとして住民監査請求をするときは,通常,当該事業を特定することにより,これにかかわる複数の経費の支出を個別に摘示しなくても,対象となる当該行為とそうでない行為との識別は可能であるし,当該事業にかかわる経費の支出がすべて違法又は不当であるという以上,これらを一体として違法性又は不当性を判断することが可能かつ相当ということができる。また,当該行為を防止するために必要な措置を求める場合には,これに加えて,当該行為が行われることが相当の確実さをもって予測されるか否かの点についての判断が可能である程度に特定されていることも必要になるが,上記のような事案においては,当該事業を特定することによって,この点を判断することも可能である場合が多い。したがって,そのような場合に,当該事業にかかわる個々の支出を一つ一つ個別具体的に摘示しなくても,住民監査請求の対象の特定が欠けることにはならないというべきである。 ○ 本件監査請求において,上告人らは,本件事業自体が,基本的人権等を定める憲法の諸条項,民主的な住民参加等を定める都市計画法の諸条項,最少経費の支出を求めている地方自治法及び地方財政法の条項等に違反する不当又は違法なものであるから,その事業に関する公金の支出は不当又は違法であると主張し,本件事業に関するX年度以降の一切の公金の支出を対象として,既支出分の返還と今後の支出の差止めの措置を求めているのであって,本件事業にかかわる公金の支出を全体として一体とみてその違法性又は不当性を判断するのを相当とする場合に当たる。そして,上告人らが本件監査請求において返還を求めるべきであるとしたX年度の1億・・・円の支出が,監査請求書に添付された前記決算書(写し)に「○駅西口地区整備事業に要する経費」として記載されているものを指すことは明らかであり,対象外の支出との区別は可能である。本件監査請求において対象となる各支出行為の年月日や金額等が具体的に摘示されていなくとも,監査委員としては,当該事業を担当する○課への確認,同課からの書類提出等により本件事業に関する各支出行為を明らかにさせることによって,本件監査請求の対象である各支出行為を容易に把握することができるものというべきである。また,上記決算書における記載からも明らかなように,○市においては,既に,本件事業のための経費が,特定されて予算に計上され,決算上もそのような支出として整理されていたことがうかがわれ,本件事業の事業計画が決定され公告された後に,本件事業の位置付けや本件事業のための経費に関する予算上又は決算上の会計区分は変動するとしても,本件事業の同一性が失われるものではなく,本件事業のための経費支出の特定性が失われるとも考えられないのであって,本件事業を特定することにより差止めを求める対象となる公金の支出の範囲も識別することができるものということができる。さらに,本件監査請求の時点では土地区画整理法上の事業計画の決定及び公告がされていなかったとはいっても,土地区画整理事業の都市計画決定がされて施行区域も定まり,○市の本件事業に関する事業計画(案)も縦覧に供され,施行規程も制定されるという段階に至っている以上,本件事業及びこれに伴う公金の支出がされることが相当の確実性をもって予測されるかどうかの判断を可能とする程度の特定性もあったということができる。事業計画の正式な決定前であるため,その後に本件事業の基礎的事項に変更があり得るとしても,上告人らの主張する違法性ないし不当性の内容からして,その変更が本件事業及びこれに伴う公金の支出の適否等の判断に大きく影響するものとは考えられない。したがって,将来の公金の支出についても,住民監査請求の対象の特定として欠けるところはないということができる。そうすると,本件監査請求は,請求の対象の特定に欠けるところはないというべきである。【注】 将来の(未成)事業については、事業そのものの成熟度(相当の確実性の要件)の問題が生じ得るところですが、本判決では、上記監査対象の特定の手段としての事業の特定において、その事業の定義として「特定の事業(計画段階であっても,具体的な計画が企画立案され,一つの特定の事業として準備が進められているものを含む。)」としており、具体的な計画が企画立案される等、事業としての具体性が客観視できる熟度であれば、将来の事業を、特定する対象の事業としても差し支えないものとしています。この部分は上記3「財務行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」かどうかの判断時の一つの参考基準といえますが、本判決の主題は未成事業の監査対象としての特定可能性であり、判決では「当該行為を防止するために必要な措置を求める場合には,これに加えて,当該行為が行われることが相当の確実さをもって予測されるか否かの点についての判断が可能である程度に特定されていることも必要になるが,上記のような事案においては,当該事業を特定することによって,この点を判断することも可能である場合が多い」と判示しています。 |
| 地方自治法242条の2第1項1号に基づく差止請求において、複数の行為を包括的にとらえて差止請求の対象とする場合、その一つ一つの行為を個別、具体的に摘示することまでが常に必要とされるものではなく、当該行為の適否の判断のほか、当該行為が行われることが相当の確実さをもって予測されるか否かの点(及び当該行為により当該普通地方公共団体に回復の困難な損害を生ずるおそれがあるか否かの点)について判断することが可能な程度に、対象行為の範囲が特定されていることが必要であり、かつ、これをもって足りる(注:細字部分は法改正により現行規定とは異なる) 最判平5.9.7民集47.7.4755
【事実関係】 【判示事項】 |
この条件に該当する想定例として、上記最判の例(明確な事業単位での抽出)のほか、自治体があるひとつの行事を実施した際、その行事そのものが違法であり(たとえば政教分離原則に違反する行事)、これに関わる支出全体が違法となる場合は、その事業を特定して、これに関する支出のすべてを対象とすれば、監査の対象とすべき財務会計行為等は特定可能ですし、その支出全体も一体として違法性評価が可能なので※、それ以上に「各行為等を他の行為等と区別して特定認識できるように個別的、具体的に摘示することを要する」ものではない、ということになります。
またその他の想定例として、職員へ一定の基準で違法に給与支給した場合(例えば条例に根拠のない手当を新設し、条件に該当する職員に所定の基準で支給した等)には、その支給基準と支給時期が請求人において具体的に摘示されれば、それ以上に個々の職員の支給事実まで摘示しなくとも、監査の対象は特定でき、すべての該当給与支給を一体的に違法性判断できるということであり、そのようなケースを想定したものである、とされています(上記説明については、あわせて上記平成2年最判青柳判解p.228も参照)。
| ※ このような場合は通常、監査委員が担当部局に問い合わせれば、監査対象となる財務会計行為等は容易に特定できると考えられ、そうしたことを想定しています(上記平成18年最判参照)。なお上記平成18年最判の事案では当該事業決算書が請求書に添付されており、決算数値が対象財務会計行為を特定するための監督数字として利用できるでしょう。 なお近時多くの自治体で、比較的容易に財務関係文書類の開示が認められていると思われ、なれば本来的には文書開示請求により得た財務会計行為の資料等によって、請求人自ら対象財務会計行為等を特定摘示することが望ましいものですが、最高裁は、請求人の特定義務を、その目的を超えて過度に厳格に解することを戒める態度をとっている(参照:人見剛「地方自治判例百選」4版p.147/5版p.137)ことも踏まえ、また監査請求期間や情報開示請求に要するコスト、また開示請求によっても完全に情報を取得できない可能性がある(非開示対象文書が存在する可能性のほか、一般住民には簡単に開示対象範囲が簡単に画定できない事情がある等により、必要な文書を全部確実に入手できない場合があり得る)ことを想定すれば、過度に請求人にすべての財務会計行為等の情報摘示を要求することは、行き過ぎとなり得る、といえるでしょう。この点は、下記ウの内容とも通じます。 |
では、どのような事例だと、逆にこの条件に該当しないことになるのでしょうか。
大雑把に言えば、複数の行為等を括る共通項としての指標に対して違法不当の評価をすれば、おのずから下位にある個々の行為等の法的評価も定まるものもあれば、複数の行為等は類似性があり、その類似性(共通項)で括った集合体と見ることができはするが、各財務会計行為等の違法不当性の判断は、その括り(共通項)を用いて一括して行うことはできず、結局は個々の行為等ごとに違法不当性を評価せざるを得ないものもあります。そして、後者のものが「一体とみて・・・」には該当しないものとなります。
たとえば、上記最判の例での「特定されたひとつの事業全体が違法」であれば、その事業に関するすべての支出は一括して違法との評価が可能ですし、「市が○月○日に宗教性のある○○行事を行う」のであれば、その行事そのものが政教分離原則により違法の評価を受けることとなり得ますので、その行事に関するすべての支出を違法と評価することができます。これが前パラグラフの前者の例です。一方、「市の○月分の接待費支出は違法」との請求があった場合、「○月分接待費」の支出自体を違法とするルール等がないのであれば、○月分接待費の何十件何百件を一体的に(一括して)「○月分接待費」という共通項を用いて違法不当と評価判断をすることはできず、結局は個々の支出の内容に立ち入って違法不当性を審査せざるを得ません。なるほどこれらの支出は○月分接待費という共通項を持つものの、その共通項のみでは違法不当性の判断ができないため、「当該行為等の性質、目的等に照らしこれらを一体とみてその違法又は不当性を判断するのを相当と」認めることはできず、これが前パラグラフの後者の例となります(下記ウ平成16年最判、同※※参照)。
ウ どのような資料等により特定するのか
上記アの通り、特定は請求人においてなされるべきものです。上記平成2年最判判示の通り、この特定は、監査請求書及びこれに添付された事実を証する書面の各記載、監査請求人が提出したその他の資料等によるものであり、請求の対象がどのように特定されているかは、これら資料の内容を総合して判断されます。
つまり請求人は、請求対象を特定するための、これら情報の一次的な提示提出責任を負っている、ということになります。
ただしそのことは、請求人の提出した請求書その他の資料類『のみ』により判断すべきということではなく、請求人が提出する資料等では、対象とする財務会計行為等が概括的に特定されるに過ぎない場合でも、その提出資料等によれば、監査委員が利用可能な他の資料(例:その自治体の調査資料※)が存在し、それらを利用すれば請求の対象が特定できる場合は、それら他の資料まで請求人が提出しなくとも差し支えない、とされています。重要な判断基準としては、下記平成16年最判の判旨となりますが、そもそも上記(1)※5掲出の平成2年最判判解の趣旨などを敷衍すれば、本平成16年最判の判旨は、確認的なものといえましょう※※。
| ①住民監査請求においては,対象とする財務会計上の行為又は怠る事実を,他の事項から区別し特定して認識することができるように,個別的,具体的に摘示することを要するが,監査請求書及びこれに添付された事実を証する書面の各記載,監査請求人が提出したその他の資料等を総合して,住民監査請求の対象が特定の財務会計上の行為等であることを監査委員が認識することができる程度に摘示されているのであれば,これをもって足りるのであり,このことは,対象とする財務会計上の行為等が複数である場合であっても異ならない ②県が,複数年度につき特定の費目に該当する費用の支出について個々の支出ごとに不適切な支出であるかどうかを検討する調査を行い,不適切な支出の合計額を公表したという事実関係の下においては,上記の調査において不適切とされた支出が違法な公金の支出であるとしてされた住民監査請求は,対象とする各支出について,支出した部課,支出年月日,金額,支出先等の詳細を個別的,具体的に摘示していなくとも,請求の対象の特定に欠けるところはない 最判平16.11.25民集58.8.2297【事実関係】 県の複写機使用料に不正の疑いが生じたため、県が複写機使用に係る個々の支出ごとに適否検討を行い、数億円規模の不適切支出の総額を公表、これに対し住民が、関連新聞記事を事実証明書として、上記公表額について、県知事に賠償させる等必要な措置を講ずることを求める住民監査請求を提起した【判示事項】 ○ 住民監査請求においては,対象とする財務会計上の行為又は怠る事実(以下「当該行為等」という。)を,他の事項から区別し特定して認識することができるように,個別的,具体的に摘示することを要するが,監査請求書及びこれに添付された事実を証する書面の各記載,監査請求人が提出したその他の資料等を総合して,住民監査請求の対象が特定の当該行為等であることを監査委員が認識することができる程度に摘示されているのであれば,これをもって足りるのであり,上記の程度を超えてまで当該行為等を個別的,具体的に摘示することを要するものではないというべきである。そして,この理は,当該行為等が複数である場合であっても異なるものではない【要旨①】。(略) ○ 前記事実関係等によれば,本件監査請求は,X年度,X+1年度,X+3年度及びX+4年度の県庁全体の複写機使用料に係る支出のうち,県の調査の結果不適切とされたものの合計額4億2021万2000円が違法な公金の支出であるとして,これによる県の損害を補てんするために必要な措置等を講ずることを求めるものであり,県の上記調査においては,対象期間中の複写機使用料に係る個々の支出ごとに不適切な支出であるかどうかが検討されたというのであるから,本件監査請求において,対象とする各支出について,支出した部課,支出年月日,金額,支出先等の詳細が個別的,具体的に摘示されていなくとも,県監査委員において,本件監査請求の対象を特定して認識することができる程度に摘示されていたものということができる【要旨②】。 |
| ※※ 本件は、県全体の複写機使用枚数に一定の乗率を掛けて、その分を架空支出したといった性格のものではなく、複写機契約一件ごとに状況が異なるため、上記イ②での「当該行為等の性質、目的等に照らしこれらを一体とみてその違法又は不当性を判断するのを相当とする場合」ではなく、個々の支出ごとに支出内容の判断をしなければならないケースであり、よってその前提として、監査すべき対象が特定されていなければなりません。平成2年最判の原則にしたがえば、本来は、請求人において対象となる複写機使用料支出を各件個別特定摘示して監査請求すべきものです。 しかし、その個別特定の資料は、請求人の提出資料によらなくとも、請求内容から判断される県の調査結果をみれば特定できる、つまり、請求人提出資料以外の資料を活用することを通じて、請求対象の財務会計行為等が特定できるのであれば、その住民監査請求は、特定の要件は充足する、という判断です(参考:判例行政法p.58(海老名富夫)。なお同書当該部分は、増田稔「最高裁判解(平16下)」p.724を参照。また最判平18.4.25民集60.4.1841判示事項および同判決に関する人見剛「地方自治判例百選」4版p.147/5版p.137解説)。 |
ただし、前記パラグラフ下線部(後半・・・ただし書き)の趣旨は「請求人が本来提出すべき請求対象を特定する資料等(手段含む)が、監査委員が利用可能なものとして別途存在していれば、請求人はその資料等を摘示すれば、それ以上に請求人が個別具体の財務会計行為等を一件一件摘示しなくてもよい」ということではありますが、これは、その資料等を利用すれば、監査対象の財務会計行為等が一意的に特定できることが前提であり、それを超えて、請求人が監査対象を監査委員自ら探索するよう委ねるような趣旨まで含むものではありません(たとえばその資料は一般論を述べるに過ぎず、その資料を見ても、対象となる財務会計行為等がどれか具体的に特定できない場合は、その資料の利用により監査対象を一意的には特定できません)。
また、請求人が監査委員において容易に利用できない外部資料の参照を求める場合なども、結局それでは請求対象の特定ができないことに等しいのですから、特定の要件を満たさないものとすべきです(資料の存否が不明確な場合、監査委員がどこまでみずから捜索するかどうかは、状況に応じた監査委員の判断問題でしょう。監査委員による財務会計行為等の特定に複雑困難さが伴う場合も同様と考えます)。
住民監査請求は、本質的に監査委員に監査の端緒を与える行為ですが、あくまでもそれは請求人が特定した個別具体の財務会計行為等についての監査の端緒であり、その対象が特定されていない状態での監査の端緒ではありません。上記平成16年最判も、請求人が監査の対象を個別具体に特定することを要するという原則は、あくまでも維持されており、その上で、請求人が示す情報を利用すれば、たとえば公知かつ参照利用可能な資料(公表された調査報告等)の利用や、事業担当部局への照会により(参照:上記平成18年最判)、監査委員において監査対象が一意的に特定できるのであれば、請求人が個別の監査対象を一々請求書や添付書類に記載する必要はない、という手段レベルでの現実的な解(方法論的緩和)を述べているものであって、請求人の請求対象の特定責任が監査委員側に転嫁された、という趣旨ではありません。
エ 特定のレベル
「当該行為等を他の事項から区別して特定認識できるように個別的、具体的に摘示」という、同判決が要求する特定のレベルについては、上記平成16年最判において、「住民監査請求においては,対象とする財務会計上の行為又は怠る事実・・・を,他の事項から区別し特定して認識することができるように,個別的,具体的に摘示することを要するが,監査請求書及びこれに添付された事実を証する書面の各記載,監査請求人が提出したその他の資料等を総合して,住民監査請求の対象が特定の当該行為等であることを監査委員が認識することができる程度に摘示されているのであれば,これをもって足りるのであり,上記の程度を超えてまで当該行為等を個別的,具体的に摘示することを要するものではないというべきである。そして,この理は,当該行為等が複数である場合であっても異なるものではない」としています。
上記ウは「ゴールにたどり着く手段」の観点でしたが、これを「ゴールはどのようなもの(こと)か」の観点であり、要は、監査請求書や事実証明書の記載内容、請求人提出資料等の内容(場合により請求人が摘示する外部資料等)を総合して、監査の対象となる財務会計行為等が監査委員において一意的・具体的に特定できるものとなっていれば、それ以上に、請求人が請求対象となる財務会計行為等を一番細かいレベルまで厳密に一件一件特定して摘示する必要はない、ということです。住民監査請求制度が住民自治的な制度目的をもつことを踏まえた現実解であり、請求人に対し、特定要件の目的を超える過剰な負担を要求すべきではないという考え方が基礎となります。
オ 小括
この「対象特定要件」についてまとめると、住民監査請求制度が個別特定の財務会計行為等の違法(不当)を問う制度であることを踏まえ、
○ 請求人が、監査請求書や事実証明書その他の提出資料を用いて、
○ 監査(や訴訟)の対象となる財務会計行為等が何か、監査委員が、他の事項と区別して特定認識できるよう、個別具体に摘示する必要がある※。
○ なおそれが特定の目的である以上、請求人が上記程度の特定ができる内容の資料・情報を示しており、その情報をもって、監査委員等が(容易に)、監査対象を一意的に、個別具体に特定できるのであれば、請求人において、前記資料等の粒度を超える細かな対象財務会計行為等の個別情報を請求人が示さなくとも、住民監査請求の要件審査事項としての請求対象特定の条件は満たされる、となります(「当該行為等の性質、目的等に照らしこれらを一体とみてその違法又は不当性を判断するのを相当とする場合」についても同様)。
| ※ この点は、請求人にとっての義務的要素と解されます。しかしながら、この要件は裏面から見れば、適法な請求である限り、請求人が摘示した財務会計行為等について監査委員に監査を強要できるということでもあります。仮に探索的監査請求(「とりあえずここからここまで監査せよ」的請求)を容認する場合、監査委員が裁量判断として抽出監査を行うこともあり得るのであり(それを違法とする明白な論拠がない)、とすれば本要件には、監査対象範囲の画定から自治体側の裁量性(あからさまな言いかたをすれば恣意性)を排し、住民監査請求の自浄的作用に客観性をもたせる(財務運営の内部的是正を図るにあたり、その対象を自治体外の者である一般住民が指定する)側面があることを否定し得ないと考えます。また、あくまで仮定の話ですが、探索的監査請求を認めた場合の住民訴訟の対象事項が、仮に「現に監査委員が監査を行った範囲」とされれば、さらに問題は深刻となります(監査請求前置を前提とする限り、実際に監査を行った範囲を「適法な監査請求を経た」と制度構成される可能性はゼロではありません)。その場合は、請求人による監査対象の特定摘示には、住民訴訟における処分権主義の外延化という側面もあることになります。 |
(3) その他の「特定」に関する事項
上記(2)では、請求人が、監査の対象とする財務会計行為等を個別具体に摘示して特定されていること(なにを監査するのかが、請求人により特定されていること)が、住民監査請求の請求要件であることを説明しました。
ところで、地方自治法242条1項では「当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な(財務会計行為等)があると認めるとき」に、「(行為の防止・是正・損害補てん等の)必要な措置を講ずべきことを請求することができる」とされているので、対象となる財務会計行為等を「だれが行ったのか(執行機関・職員)」、「なぜその財務会計行為等が違法不当なのか」、「(誰に)どのような措置を求めるのか」についても、当然一定の特定が必要となるのではないか、という疑問が生じます。
ア 誰にどのような措置を求めるかの特定
この点については、次の平成10年最高裁判例により、請求人は請求内容において特定(明示)する必要はないとされています。(あわせて参照:最判昭62.2.20民集41.1.122。また松本逐条242条関係※)※※。
| 監査請求の際、請求人は、監査の対象である財務会計上の行為又は怠る事実を特定して必要な措置を講ずべきことを請求すれば足り、措置の内容及び相手方を具体的に明示することは必須ではなく、仮に執るべき措置内容等が具体的に明示されている場合でも、監査委員は、監査請求に理由があると認めるときは、明示された措置内容に拘束されずに必要な措置を講ずることができる 最判平10.7.3集民189.1
【事実関係】 【判示事項】 |
| ※ 松本逐条においては「監査委員の勧告の『必要な措置』とは、一般的には、請求人の請求内容である必要な措置を指すものであるが、監査委員は、必ずしも請求人の請求内容に拘束されず、これを修正して必要な措置を勧告することもできるものと解すべきである」とする。 |
| ※※ 参考までに、いわゆる田子ノ浦ヘドロ訴訟の最判昭57.7.13民集36.6.970は、県が負担したX年度港湾ヘドロ浚渫費1億5千万円についてA製紙株式会社等の大製紙企業に浚渫費用を負担せしめることとする住民監査請求の内容に関し、前記製紙会社が、住民訴訟においては、訴訟の対象となるべき具体的事項につき地方自治法242条の住民監査請求を経由した旨の主張をしなければならず、これを本件についていえば、原告の本件監査請求の上記に記載された内容の住民監査請求を経由したという主張だけでは足りず、本件監査請求は、県知事が前記製紙会社に対してヘドロ浚渫に関する不法行為による損害賠償請求権を行使しなかったことが違法に財産の管理を怠る事実にあたることの請求を含む旨の主張をしなければ、県に代位して前記製紙会社に損害賠償の請求をすることはできない、と主張したが、最高裁は、地方自治法242条1項は、同項にいう当該行為又は怠る事実によって自治体の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことにつき住民監査請求をすることができる旨規定するにとどまるのであって、同規定を解釈して、住民監査請求においては、上記上告人主張のように、より具体的に損害賠償請求権の不行使が怠る事実に当たるとまで主張しなければならないと解することはできない、と判示し、その上で、本件請求には県がX年度に支出したヘドロ浚渫費1億5千万円について、これを原因者に何らかの形で負担させるべきであるという主張が含まれているものと解するのを相当とし、その限りにおいて、本件住民監査請求の趣旨は明確であり、地方自治法242条の2所定の住民訴訟の前提としての同法242条所定の住民監査請求の要件を充足しているものと見るべき、とした。 |
イ 執行機関・職員の特定
住民監査請求の対象とする財務会計行為等に関った(関わる)執行機関・職員(地方自治法242条1項の「当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員」)を、請求人が請求書等でどこまで特定明示しなければならないかは、見解の相違がありますが※、筆者は、厳密正確な特定明示は必要ではなく、極論すれば、監査対象とする事項、つまり対象の財務会計行為等が適法に特定されていれば、端的にはこれら執行機関・職員の特定がなくとも、請求要件判断には影響しないと考えます。
| ※ 行実昭40.5.12は監査請求の文面において、具体的に対象となる職員が明示されていないが、請求の内容は○年度議長交際費に関するものであるから、該当する議長の行為が対象となっているものと解し、地方自治法242条の請求要件は一応具備すると解して差し支えないかとの質問に対し、これを是認しています。なお、地方財務実務提要では、これに基づく内容の質疑応答を掲出しています。 なお筆者の上記見解に類似する見解として、松村p.33、東京高判平3.10.30行裁例集42.10.1721等。なお実務住民訴訟p.31は、違法、不当な財務会計行為に関わった執行機関又は職員を特定して行うのが原則としつつ、請求書及び添付資料全体から執行機関又は職員を特定することができる場合は、執行機関又は職員の指定があるものとして取り扱う、違法・不当とされる財務会計行為を特定すれば、自ずと財務会計行為の主体等は判明することがあり、必ずしも当該財務会計行為を行った執行機関・職員を特定する必要がない場合もあり得る、とします。 筆者の上記見解と必ずしも見解が一致しないものとして、名古屋高(金沢支)判平9.9.3判例タイムズ972.172。 |
住民監査請求においては、上記の通り、請求人は対象財務会計行為を個別具体に摘示することが求められます。
ところで、住民監査請求の対象とする財務会計行為等の特定、という要件で考えれば、たとえば公文書公開請求により得た契約書や稟議書・決議書の写しにより、○年○月○日に○市と相手方○○の間で締結された○○契約(契約金額○円、○市の同契約に基づく金銭債務弁済日○年○月○日)、または○年○月○日支出命令(支出命令番号○番)命令額○円支出日○年○月○日支出相手先○○理由○○、などと示せば、監査委員にとって何を監査すべきかは瞭然としており、監査の執行は十分に可能です。つまりこれ以上に、この契約の締結権限がどの執行機関またはどの職員であったのかという情報を示さなければ、監査対象の特定ができず、監査ができない、というわけではありません(監査対象機関の特定は必要ですが、それは摘示された財務会計行為等から監査委員が判断決定すればよいだけですし、本来は、監査を行う監査委員が主体的に決定すべき事項です)。
これに加え、現実問題として、財務会計行為等に関わる者については、支出負担行為、支出命令は首長、支出は会計管理者に本来の権限がありますが、実務ではほとんどすべての財務会計行為は委任・専決で処理されており、このレベルとなると、自治体組織の外部者である住民には非常にわかりにくく、委任・専決規程を住民が精査して正確に把握することも大変困難です(「中の人」ですら良く分からないことが多いものです)。一方で、自治体の内部機関であり、監査権限をもつ監査委員にとっては、事項としての監査の対象行為等が個別具体に明瞭に特定されていれば、その行為等に権限を有する執行機関・職員を特定することは、容易なことです。
また損害補てんの措置勧告には相手方の特定が必要ですが、住民監査請求においては、対象財務会計行為等が特定されていれば、損害補てんの措置勧告等を行う段階において監査委員が責任職員を特定すればよいだけの話です。監査委員は自ら責任職員を特定する権限があり、また現実としても、そのようなこと行うのは、監査委員にとってはなんら雑作がないことです。
このように、対象を特定する要素として、「どの財務会計行為か」ということを示す標識は必要ですが、「その財務会計行為をだれが行ったのか(誰の権限か)」という標識は、一般に、監査を実施するための手段としての対象特定に必要な事項とはいえず、監査の実施の障碍になるわけでもないので、その特定を請求人に要求する必然性がありません。
であれば、住民監査請求において、請求人が財務会計行為等に関与する執行機関・職員を特定することは、請求人に要求すべき本質的な事項ということはできず、要件審査事項とはならないと考えます。事項としての財務会計行為等を特定できれば、監査はできるし、その結果を通じて勧告もできるのです。
逆に、こうした情報について徒に厳格にその特定を請求人に求めることは、住民監査請求制度の趣旨に沿うものとはいえず、かえって監査委員の住民監査請求に対する姿勢を疑われかねないものともいえると考えます。
ウ 違法・不当性の特定
地方自治法242条は、住民(請求人)は、違法不当な財務会計行為があると認めるときは、監査委員に監査を求め、当該行為の防止是正や損害の補てん等を請求することができるとしています。
これによる限り、請求人が請求において主張する財務会計行為等の違法不当性は、監査委員に「なぜ監査を求めるのか」という理由そのものであるため、適法な請求の前提であるとも解し得ます(参照:実務住民訴訟p.31、判例行政法p.62(海老名富夫))。
しかし、どの程度まで違法不当性の論拠を明確にすべきかの基準については、厳密に形成されているように見受けられず、一定の結論は出しづらいとも考えられます※1、※2。
| ※1 参照:判例行政法p.62(同)。松村p.33 |
| ※2 なお実務住民訴訟p.31は、下記東京地判平3.3.27行裁例集42.3.474に基づき「当該行為又は怠る事実の違法性、不当性の主張については、具体的な理由を記載しなければなりませんが、それが掲げられていれば、法令に違反するとか、不適当であるとかの指摘で足り、特定の法令の名称をあげてこれに違反する旨を常に摘示しなければならないというものではありません」としています。 |
筆者はこの点に関し、原則として、請求人は、請求の対象とする財務会計行為等のすべてについて、違法不当と認める論拠(ただしその根拠は、国や自治体の法令等に限られるものではなく、関係者間の約束ごとでも、また客観性のある論理的不整合や一般的な経験則違反といったものも含め、幅広に認め得るし、疑いレベルのものでも客観性があれば差し支えない)を、何らかの客観的な形、内容で、摘示する財務会計行為等と結びつけて示すべきであると考えます。
これは、地方自治法242条1項の法文からも明らかなように、請求人は財務会計行為等に違法不当性を認めるがゆえに監査委員に監査を求めることができ、その請求により監査委員は監査を義務付けられるのですから、請求人が認識する違法不当性は何か、を請求人自ら明らかにすることは、監査請求をなす(監査委員側にとっては監査義務が発生する)前提条件というべきだからからです。
たとえば、違法不当性の論拠を示さずに特定の財務会計行為等に対する監査を請求することを認め得るとすると、請求人が当該財務会計行為等を違法不当と認めたかどうか判然としないまま監査請求が可能となる、つまりいわば思い付きで監査委員を振り回すことすら可能となります。しかしそもそも住民監査請求が、住民が特定の財務会計行為等について違法不当性を認めた場合に、監査を求めることで自治体が自ら財務運営の是正を図ることを要求する制度であることからすれば、請求人が違法不当の理由を示さないのに、なにゆえ監査委員は監査を義務付けられるのか、合理的な理由が見いだせず、また常識的に考えて、そのような請求で監査を義務付けても、行政資源の浪費になりかねないことは自明です(探索的請求監査を認めない最判平2.6.5民集44.4.719の趣旨と通じます。また住民監査請求に要する経費は住民自治のため必要なコストですが、上記のような案件にまでコストを負担すべき理由がありません)。
とすれば、請求人の違法不当性の主張内容の当否はともかく、その主張は、監査委員がその内容がどういうものであるか認識し、主張の論拠性を理解(同意するかではない)し得る程度の客観性をもった形、内容で摘示することが必要と考えます※3。
| ※3 無論、「書いてあることが論理的には一応理解できる」ものであっても、一見明白に理由として成立しないものは論外とすべきです。たとえば「アンドロメダの法律によれば・・・」(アンドロメダ云々は刑事訴訟法の某教科書の有名な例によっていますが要は荒唐無稽)、論拠が憲法や法律に明らかに違反し、他の救済的解釈も取り得ない理由構成など。 |
たとえば対象財務会計行為の違法不当性が談合に起因すると請求人が主張するのであれば、請求対象の財務会計行為等に談合が疑われることを示す客観性のある根拠(社会的認知のある報道機関の報道情報等)を事実証明書や添付資料で示すべきであり、そうしたものがない、たとえば単なる請求人の主観的主張のみでは、結局、違法不当性の論拠を示さないのと何ら変わるところがありません。
なお、上記客観性のある根拠は、第三者情報(報道等)を常に備える必要はなく、一般経験則違反等の客観性のある論理的な説明でその論拠が明示できるのであれば(たとえば法令及び財務規則上競争入札にすべきものを随意契約とした等)それで差し支えはないものです(そもそもこの例で、契約締結の事実証明書以外の第三者的資料が存在することが、あまりないでしょうが)。また、住民監査請求が通常、住民において特定の財務会計行為等に違法不当性の疑いを抱いた段階で提起されるものでなされることを考えれば、違法不当性の論拠は、その内容に客観性を備える限り、疑いレベルのものであっても差し支えないことも当然です(それを確定的に判断するのが、監査や住民訴訟の役割です)。いずれにせよ、要求すべき客観性のレベルは、住民監査請求が住民自治的機能を有することなどを考慮すれば、過度に厳格にすべきではないと考えます。
また、上記(前段)の点から派生して、次のような問題をも考慮すべきです。
適法な住民監査請求がなされたときは、監査委員は監査を行う義務が生じることは、言うまでもないことであり、その要件の一つとして監査対象の特定があげられているのは、既述の通りです。
しかし、請求人が請求において、情報公開請求開示で得た一定期間分の大量の支出命令書を提出するものの、これら支出のどれにどのような違法不当性があるのか明確とされない場合や、請求対象のどの財務会計行為等が違法なのか請求人の主張のみでは判然としない場合、外形的には監査対象の財務会計行為等が特定されているようにも見えますが、上記本項前段の趣旨からすれば、実質的には、どの財務会計行為等を監査すべきなのか、監査の対象が特定されていないのと同然となります。
そもそも前提として上記本項前段の通り、最判平2.6.5民集44.4.719の判旨では、適法な監査請求によって監査委員に監査を義務付ける(言い方を変えれば、住民一人の意思により、監査委員に監査行動を強要できることを意味する)には、請求人が、監査すべき財務会計行為等を監査委員が識別できるよう摘示すことを要求しており、より広い範囲の対象の中から部分集合たる「監査すべき対象」を監査委員に探索し特定させるようなことは認めていません。そして探索的な監査請求を認めないということについて前段の趣旨も含めれば、請求対象として摘示する財務会計行為等はどれなのかを(事項として)特定するのみならず、なぜその財務会計行為等について監査を求めるのかという点をあわせて、請求人が監査委員に対して明瞭にすべきであるとすべきこととなります(でなければ、結局違法不当性があり得る監査対象財務会計行為等を一群の財務会計行為等のうちから監査委員に探索させることに等しい)。
そうなるとたとえば下記平成10年東京地判※4のような請求形態(を上記のように純化した場合)は、実質的に、上記平成2年最判で明確に否定された、探索的な、包括的・非特定の財務会計行為等を請求対象とする内容と本質的に変わるところがないといえ、いかに外見上、財務会計行為等が事項としては明示特定されていたとしても、実質的には、監査対象の特定には欠けるといわざるを得ないものであると考えます。
| ※4 参考:東京地判平10.9.16判例タイムズ1041.195。約200件の食糧費支出のうち6件は領収書等を添付した上で同一店なのに年度によりサービス料の扱いが異なる等の理由が摘示されているが、残りの支出については「具体的な違法性又は不当性に関する指摘はなく、領収書等の添付もなく、ただ、情報公開請求に対して一部非公開部分があるのにかかわらず、「一部をみただけでこの有様である。すべて領収書が偽造され、また、違法支出が隠されている疑いが濃厚である。」と記載されているに止まる」状態の住民監査請求について、「本件監査請求において指摘された右6例の支出の違法、不当の事由はそれぞれ異なる事由であって、これらを一体とみてその違法性又は不当性を判断するのを相当とする場合には該当せず、また、右6例について指摘された違法性、不当性の根拠とされた事由からその余の支出を違法、不当とすべき事由が当然に推認されるものではない。したがって、原告の本件監査請求は、右6例を除く支出については、違法又は不当な行為があることを証する書面の添付を欠き、単に違法、不当の疑いがあるとして、その調査を求め、違法又は不当な行為があった場合にその是正を求める趣旨と解すべきものであり、結局、「違法、不当な行為」を個別的に特定するものではないというほかない」。 本事案は、かなり乱暴な言い方をすれば、「食糧費支出のうち6件は明らかに怪しさ満載なので、ほかの200件も怪しい」という当て推量と解され得るものであり、この場合、請求対象の支出自体は事項として認識可能ではありますが、結局このような請求は、監査委員に監査対象の探索を求める趣旨の請求形態を認めず、また包括的な請求も否定した最判平2.6.5民集44.4.719の判旨に照らせば、判旨の通り、請求対象不特定とすべきものでしょう。なお類似する参考事例として、東京地判平10.10.14判例地方自治189.29。また横浜地判平14.4.24判例地方自治238.29など。 |
よって、とりわけこうしたケースにおいては、事項(事実)としての財務会計行為等を特定して示すだけでなく、その財務会計行為等それぞれについて、どのように違法不当性があると認めるのかの客観的な論拠まであわせ示すことにより、はじめて財務会計行為等の特定、つまり請求人が監査委員に監査を要求(義務付け)する理由としての意味をなすものというべきです(平成2年最判のいう「当該行為等の性質、目的等に照らしこれらを一体とみてその違法又は不当性を判断するのを相当とする場合」は、請求人において一件一件の財務会計行為等に違法性の論拠がどのように結びつくか示す必要はないにしても、最終的には、請求人の摘示する財務会計行為等が、すべて請求人が主張する違法不当性の論拠と結びついており、さらにその前提として、対象財務会計行為等が特定可能である点で、上記の要請が実現できていることになります)。
ちなみに、請求人が違法不当性の論拠を示した上で、監査委員がどのような観点で監査し、違法不当性の判断においてどのような法的構成をとるのかは、また別の問題です。
以上の理由により、本項首記の通り、住民監査請求をなすにあたっては、請求人が、請求対象とする財務会計行為等のすべてについて、どのような理由で財務会計法規上違法不当であるとするのか、その理由・論拠を、何らかの形で※5、一定の客観性をもって示し※6、それを対象とする個別の財務会計行為等に結びつけて摘示することが、請求の原則的な適法要件とすべきものと筆者は考えます。
| ※5 何らの違法不当の論拠が明示されていなくとも、対象となる財務会計行為等の内容から判断できる場合は、請求人の趣旨を解釈して、違法性の摘示があるとすることもあり得るでしょう。たとえば○年度会議費のうち○○会議費支出は、宗教団体X教団への支出、という請求が特定されていれば、おのずから政教分離原則違反を違法性の論拠にしているものと解釈が可能であり、○○会議費すべての支出について、請求人が監査を求めるという意味でも、請求対象たる財務会計行為等の事項特定に疑義は生じません。一方で、そうした属性表示なく、単に○年度会議費一切の支出(一覧別紙の通り合計○円、または○○会議費・・・)を、支出明細一覧表等を添えて監査を求められた場合、上記本文のような問題が生じ得るものです。 |
| ※6 住民監査請求を行う際は、事実証明書を付することとされています(地方自治法242条1項)。また平成2年最判はその他の資料の提出も想定しています。事実証明書の精度はあまり厳密には要求されていない(行実昭23.10.12、上記(1)※5平成2年最判判解参照)とされていますが、いずれにせよ対象財務会計行為等の事実の存否とともに、違法性の論拠についても、請求書の内容等でその説示が完結する場合を除き、事実証明書、添付資料類を通じて示すことが、一定の客観性をもって示す、という要求からすれば適切なあり方というべきです。たとえば、特定の公共工事に係る多数の支出負担行為や支出命令決議書・付属書類等の写し(それ自体事実証明書です)とともに、相応の信用力のある報道機関の「その工事には談合の疑いあり」との報道の写しなど、対象財務会計行為等の違法性を客観的に推認可能とする資料の添付等があれば、その違法性についての客観性のある論拠が示されたといえるでしょう。 |
一方で、上記平成10年最判などによれば、監査委員が監査の結果を決定し、措置勧告を行う際は、請求人の請求内容に拘束されるものではなく、監査委員は自らの判断でこれを行うことができるのであり、またそもそも(請求人の主張する違法不当性の当否を含めた)違法不当性の終局判断は監査で行うべき領分問題であるので、上記の通り要件審査の段階においては、上記の要件を満たしていれば、それ以上に、請求人の示す違法不当性の論拠を法令に限定したり、その正確性までも求める必要はなく、この内容が誤っていたからといって、請求の適法要件に欠けることにはならないものとなります※7、※8。
ただし、その違法不当性論拠の内容が、要件審査段階で一見明らかな勘違いや錯誤であるときは、状況に応じて(監査対象の特定の必要性やそもそもの監査の必要性の当否の判断に支障を生ずる場合もあろうし、監査の着眼点設定の上で、請求人の意図をより明確にすることが望ましいという、監査執行上の効率性の観点から必要とされる場合もあろう)、請求人に対して、補充説明等を求めることは、然るべき対応と考えます。
| ※7 参考:東京地判平3.3.27行裁例集42.3.474は、東京都清掃工場の建替に伴う地元還元施設の建設は、都と付近住民が締結した清掃工場跡地は原則として緑地とする旨の協定に違反するから、その設計委託料の支出は違法であるとする住民監査請求において「特定の法令に違反している等の具体的な事実の摘示がなく、住民監査請求において必要とされる違法性・不当性に関する主張がなされていない」として監査委員に請求却下された事例について、「監査請求において必要とされる財務会計上の行為あるいは怠る事実の違法性あるいは不当性に関する主張は、監査請求の全体の趣旨からみて、当該財務会計上の行為あるいは怠る事実が具体的な理由によって、法令に違反し、あるいは行政目的上不適当である旨を指摘すれば足り、特定の法令を挙げてこれに違反する旨までを常に摘示しなければならないものではない」とし、監査請求書に「東京都が、・・・協定3条により原則として緑地とする旨が合意されている場所に還元施設を建設することを前提として、反対同盟が生活建築研究所に作成せしめた還元施設基本設計図の作成料を支払うことは、右協定に違反し違法であるとする趣旨が記載されている」ことから「本件監査請求は、特定の法令を挙げてはいないものの、その全体の趣旨からみて、右の作成料の支払が、・・・協定3条に違反する施設の建設を前提としていることを理由に、その支払が法令違反となる旨を主張していることが明らか」であり、適法な請求である(監査委員が、特定の法令に違反している等の具体的な事実の摘示がないとの理由で本件監査請求を却下したのは、適法な監査請求を誤って却下した不適法なもの)と判断しており、違法不当性の論拠を幅広に認める判断例として参考になると考えます。 |
| ※8 上記最判昭62.2.20民集41.1.122の調査官解説(石井善則「最高裁判解(昭62)」p.78は、「住民監査請求においては、訴訟におけるような請求の趣旨・原因を明確に摘示することは要求されていない」とし、理由として、「住民の手で執行機関又は職員による財務会計上の非違行為を防止・是正するという制度を実効あるものにするためには、住民監査請求の段階における非違事実の摘示及び取(執)られるべき措置内容の提示に、厳密さや法律的整序を要求することには、ことの性質上無理があるからである」との関和夫・判例評論286号20頁の論説を引用しています。 |
5 財務会計行為等に先行する行為の違法性
住民監査請求で問題とできるのは、違法・不当な財務会計行為等に限られています。
ところで、住民監査請求の対象となる財務会計行為には、これに先行する何らかの判断・行為があり、この先行行為等が財務会計行為等の原因となっていることが多々あります(たとえば特定の職員に人事上の処分(昇任等)を行い、これに基づきその職員に、昇任後に適用されるべき級・号給による給与を支給する等。この場合、昇任が先行原因行為で、給与支給が財務会計行為になります)。
この場合、上記の原則からすれば、先行の行為がそれ自体財務会計行為等に該当しない限り、この先行行為を住民監査請求の対象とすることはできません※。
| ※ 住民監査請求の対象が、地方自治法242条1項により財務会計行為等に限定されている以上、同項の財務会計行為等には該当しない先行原因行為そのものを住民監査請求の対象とすることは、認められない(不適法な請求となる)ことは当然です。 |
なおこのような、先行原因行為等が違法である場合に、後続する住民監査請求の対象である財務会計行為等に先行原因行為等の違法性は影響するのか、するとすればどのようなケースなのか、住民監査請求・住民訴訟の領域ではしばしば問題となるところです※※。この点については、別ページ(7 違法性の承継)で説明します。
ただしこの問題、つまり財務会計行為等に先行する行為の違法性が、実際の財務会計行為等にどのように影響するかについては、財務会計行為等に対する監査を行った上で判断される問題であり、住民監査請求の要件審査における問題ではありません。
| ※※ この点に関する基本的な判断基準として、最判平4.12.15民集46.9.2753で「当該職員の財務会計上の行為をとらえて右の規定に基づく損害賠償責任を問うことができるのは、たといこれに先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、右原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られる」とされています。これは、先行原因行為の違法性を全面的に住民訴訟で問責できることとなれば、住民訴訟は財務会計行為等の非違是正に限定し、一般行政上の問題は対象外とした趣旨を逸脱することになるからです。そして、その趣旨からすれば、住民監査請求でもこの法理は当然適用されるものと考えます。 |
本稿のPDF版

バラの鉢植えを狭い玄関前で何とか。左のピンク蛍光色がMaria Callas、米国ではMiss All-American Beautyだそうで、その名の通りド派手な花が咲きトゲトゲも強力です。わが家ではトゲがエグく歌が上手いカラスにちなみ「キョエ」と。後ろの黄色い花がゴールデンシャトー、日本産の花です。名前がシャトー・ドールとかでないのは御愛嬌。前の薄いピンクの花はOphelia、こちらも名前の通りの色合いと端正な花姿で石鹸のような香りです。高島屋のバラのピンク版かも。右後ろ隠れているのがBlue Moon。いわゆる青バラ系統でダマスク香がたいへん結構なものです。