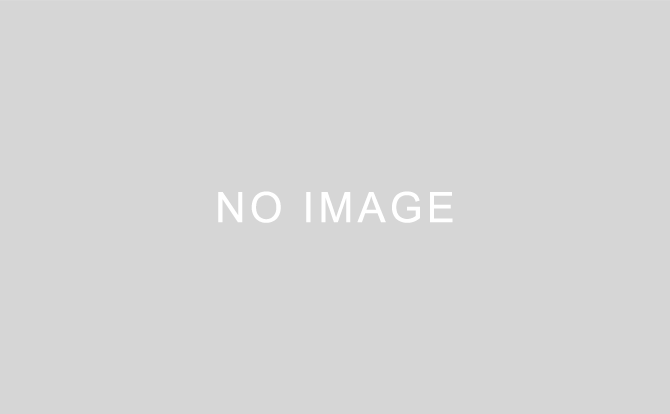本ページの一番下に、本ページのPDF版リンクを設けています。
最終改訂 2025.7.16 改訂内容は改訂履歴ページを参照(8.1 PDFの改頁不良を修正)
このページは、先行行為と後行財務会計行為等の関係に関する裁判例を紹介するページです。
ここでは最高裁判例・下級審裁判例を、原則としてすべて経年順で並べています。
なお、議会の議決と財務会計行為の関係(適法な議決の不存在等)も、先行後行行為関係ととらえることができるため、そうした事案も掲出しています。
【注】 参考事例の判決文は、必ずしも原文通りではなく、項目の表記にあうように若干の修正をしていることがあります。
【最高裁判例】 地方公共団体の議会の議決があったからといって法令上違法な支出が適法な支出となる理由はなく、議会の議決を経た公金の支出についても、(旧)地方自治法第243条の2第4項の訴訟によりその禁止、制限等を求めることができる 最判昭37.3.7民集16.3.445
(昭和29年警察法は違憲であるとして、同法を前提とする警察費の支出禁止を求める住民訴訟)
○ 地方自治法243条の2による住民の監査請求及び訴訟は、地方公共団体の公金または財産に関する長その他の職員の行為を対象とするものであって、議会の議決の是正を目的とするものでないことは原判示のとおりである。しかしながら、長その他の職員の公金の支出等は、一方において議会の議決に基くことを要するとともに、他面法令の規定に従わなければならないのは勿論であり、議会の議決があったからというて、法令上違法な支出が適法な支出となる理由はない。原判決は、かかる場合には、同法五章に定める議会の解散請求によって解決すべきものと考えるが如くであるが、同法が243条の2を五章とは別に規定した趣旨は、かかる直接請求の方法では足らず、個々の住民に、違法支出等の制限、禁止を求める手段を与え、もって、公金の支出、公財産の管理等を適正たらしめるものと解するのが相当である。かく解するならば、監査委員は、議会の議決があった場合にも、長に対し、その執行につき妥当な措置を要求することができないわけではないし、ことに訴訟においては、議決に基くものでも執行の禁止、制限等を求めることができるものとしなければならない。原判決が本件支出について○府議会の議決があった一事をもって直ちに上告人の請求を棄却すべきものとしたのは法令の解釈を誤った違法があるといわなければならない。以上の点について、論旨は理由があるものということができる。
宗教法人への町有地の廉価な土地売却について、町長の提案による議案につき議会の議決を経ることにより違法性が治癒されるものではないとした事例 盛岡地判昭46.12.28判例時報655.20
(町有地の一部について、寺院から町長・議長に売却の請願があり議会は請願を採択した。町長は町有財産処分の議案を提案したが、その価格は相当に低廉であった。なおこの売買に一部住民は反対の請願を行い、また県の市町村担当課は財産処分議決後売買契約締結前に、本件売買は地方自治法に違反することは明白であり対価は適正でなく当然無効のおそれがある旨町に注意しており、町長はその意見を承知していたが、議会には伝えなかった)
○ 本件売買は、前記認定のように、町の町有財産である本件土地および立木を極めて低廉な価格で宗教法人たる○寺に売却したものであるから、憲法89条、地方自治法212条に違反すること明白であり、この違法は当然無効をきたすと解すべきである。・・・
○ ・・・被告は、町の執行機関として町議会の議決事項を執行したにすぎないと主張するが、議会の議決を要する事項についても、その執行は執行機関の権限と責任において行なうべきものであるから、右のような言分は成り立たない。また、議会の議決があったからといって、違法なものが適法になったり、無効なものが有効になったりすることはない。
予算外の町長交際費支出について、後年度の補正予算措置によって予算外支出の違法が治癒されるものではないとした事例 松山地判昭48.3.29判例時報706.18
(町長が交際費を予算外支出した。後年度に監査委員の勧告に基づき追認措置として過年度分交際費の補正予算が成立した)
○ 地方自治法・・・は地方財政の健全な運営をはかる一手段として歳入歳出の計算にしめくくりをつけて会計経理を明確にするため、会計年度およびその独立の原則を定め、当該年度の歳出は、当該年度の歳入をもって賄い、又当該年度中においてのみ執行し得ることとした(旧法第234条地方自治法施行令(昭和38年政令306号による改正前のものー以下旧施行令という)第144条参照)。そして右原則を極端に適用すると実際の財政運営に適合しない場合を生じるので例外として継続費の逓次繰越・・・繰越使用・・・、過年度収入および過年度支出・・・、前年度剰余金の繰入・・・および翌年度歳入の繰上充用・・・の措置が認められているのである。(ちなみに例外として認められている過年度支出は既往年度所属の経費が債権者から請求されないことなどの事由により支出に至らなかった場合において現年度予算をもって支出することを言うのであって、本件の如く既往年度においてすでに支出のあったものについて過年度支出の予算措置をとることは許されない。)そして、補正予算は既定の予算に追加その他変更を加える必要が生じたときに作成出来るものであるが、右独立の原則にかんがみ、会計年度経過後においては、これを変更するため補正予算を作成することができないものである。(旧施行令第160条)しかるに本件補正予算は過年度(昭和35年度から昭和38年度まで)においてすでに支出されている交際費を昭和40年度において補正したというのであるから、旧法第234条旧施行令第148条に違反した違法な補正予算というべきである。
○ よって違法な補正予算措置(違法な補正予算案に対し議会の議決があったとしてもその議決自体が違法であって、これによって適法なる補正予算となるものではない)により被告の予算外違法支出が治癒されることはない。
予算成立前になされた工事請負契約について無予算の瑕疵を追認的行為で治癒するためには、その違法な行為の内容が事後的に明確に承認されることが必要であるとした事例 水戸地判昭48.8.23行裁例集24.8・9.828
(町の車庫建設のための工事請負契約を予算成立前に締結した)
○ 町議会において本件車庫建設工事についての予算が議決成立したのは、昭和43年12月19日であり、町と被告会社との間に本件車庫鉄骨工事の請負契約がなされた昭和43年11月23日当時には、まだ右予算が成立していなかったことは当事者間に争いがない。そして、地方自治法第232条の3には、普通地方公共団体の支出の原因となるべき契約その他の行為(支出負担行為)は、法令又は、予算の定めるところに従い、これをしなければならない旨を定めて、予算の裏付けのない請負契約を締結することを禁止しているのであるから、町と被告会社間の前記請負契約が右規定に反して違法に締結されたものであることは明らかである。
○ これについて被告らは、昭和43年12月19日に成立した予算は、車庫建設について、款を総務費、項を総務管理費、目を財産管理費、節を賃金および原材料費とするもので、その節によってこの予算が直営工事のためのものであることを示していても、予算の議決はその款および項についてなされるのであって、目および節についてなされるものではないから、この予算を請負工事のために支出することは議決に反しないので、この補正予算の成立によって予算成立前の契約締結という瑕疵は治癒されたと主張する。しかしながら、違法な瑕疵が事後の追認的行為によって治癒されるためには、その違法な行為の内容が事後的に明確に承認されることが必要であって、議決機関と執行機関とを分離して、議会の意思と承認にもとづいて執行機関に執行せしめようとする地方公共団体の町議会と町長の関係に鑑みると、予算と支出即ち支出負担行為との関係においては瑕疵の治癒については慎重に考えなければならない。本件の場合、町議会の予算の議決が款および項についてなされるものであって、目および節についてなされるものでないことは一般論としては首肯できる。又、当該補正予算は、節において賃金および原材料費であることを摘示して、それが直営工事のための予算であることが説明されているものであることは前認定のとおりである。したがって、右予算の款および項は、目および節の摘示によって初めてその支出目的が明らかになるものであって、その意味で町議会は直営工事による車庫建設を目的として予算を議決したものであることは明らかである。又、町が請負契約をするためには地方自治法第234条2項による一般入札の原則があって、例外的に特定の要件のある場合にだけ随意契約が認められるので、・・・によれば、町財務規則は随意契約をする場合の見積書の徴収、契約締結についての契約書作成などの手続を要求しており、請負契約によって工事を行う場合には厳正な要件が要求されているのであって、直営工事のための支出と請負工事のための支出には重大な要件的手続的相違があるのであるから、事後的承認に明確性の要求される本件のような場合に、直営工事のための予算が事後に成立したからといって、予算成立前になされた請負契約の締結についての瑕疵が治癒されたとは、到底いうことができない。又、被告らは町財務規則・・・に定める予算の流用を認める規定に準じ、直営でできない鉄骨工事の部分のために直営工事費を請負工事費に変更して支出することは、予算科目設定の趣旨に反しない旨主張する。しかし、同条が定めるいわゆる予算の流用は、予算に設けられている予算項目相互の間において、その金額を流用することをいうものであって、予算項目として設けられていない請負工事のために、予算で設けられている直営工事のための費用を流用支出することを許容するものではなく、もしかかる流用が執行機関によって行われることが許容されるとすれば、町議会の議決する予算による執行機関に対する拘束は著るしく損われることになり、町議会による予算制度の趣旨に反することになるから、予算流用の規定に準じてこれを許容することは到底認められず、被告らのこの主張は採用のかぎりでない。更に、被告らは町においては直営工事の一部を請負契約によって施工させることが慣例となっていたから、直営工事のための予算を本件鉄骨工事請負契約のために支出することは違法でないと主張するが、全証拠によるもそのようなことが慣例になっていたことを認めるに足りず、又、たといそれが同町の慣例となっていたとしても、違法性が阻却されるためにはこれに対する町議会の承認が不可缺であるところ、このような町議会の承認が行われていたことの主張も立証もないから、被告らのこの主張は採用するに足りない。
○ 以上のとおりであるから、町が被告会社との間に締結した鉄骨工事請負契約は予算にもとづかないでなされたものとして、その余の判断をするまでもなく違法たるを免れない。
【最高裁判例】 公金の支出は、単にその支出自体が憲法に違反する場合だけではなく、その支出の原因となる行為が憲法に違反し許されない場合の支出もまた違法となる 【津地鎮祭事件】 最判昭52.7.13民集31.4.533
(市体育館の起工式(市主催)を、神社神職主宰の神式で挙行し、公費でその費用が支出された。原審は、起工式は憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当し許されないものであり、従ってこれに基づき市長としてなした公金支出は、憲法89条の適用をまつまでもなく、基本となる権利義務関係が法律上許されない以上、違法な支出たるを免れないと判断)
○ 公金の支出が違法となるのは単にその支出自体が憲法89条に違反する場合だけではなく、その支出の原因となる行為が憲法20条3項に違反し許されない場合の支出もまた、違法となることが明らかである。所論(上告理由)は、本件公金の支出が憲法89条に違反する場合にのみ違法となることを前提とするものであって、失当である。
用地買収の追加経費支出が地方自治法96条1項5号の議決を経ていなかったが、その違法の瑕疵は事後の議決で治癒されたとした事例 大阪高判昭53.10.27行裁例集29.10.1895
(用地買収契約の金額が先行する地方自治法96条1項5号の議決の額を超えていた。町は、超過部分は売買代金の一部ではないと考え補正予算措置のみ行なっていたが、本訴訟の一審判決で売買代金の一部であると認定されたことから、議会は追認の特別議決を行った。この時点で売買契約から5年余り経過していた)
○ A、Bと町との間の本件廃川敷周辺土地の売買契約は地方自治法96条5号にもとづく「議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例」第3条による議会の議決を効力発生の条件とする契約に該当するところ、昭和48年1月20日に行われた本件売買契約に先立って行われた昭和47年12月22日の定例議会における特別議決においては、売買代金は6565万5000円とされていたのであり、実際に行われた売買の代金はこれに360万円を加えた金額ということになるから、議決の内容と実際に行われた売買契約との間にはそごがあるといわなければならず、右360万円の支出については特別議決を経ていない瑕疵があるというべきである。
○ しかし、控訴人は、「昭和53年3月25日の議会において右360万円を含めた売買につき追認する旨の特別議決がされた。」旨主張し・・・、町では、右360万円の支出当時これを売買代金の一部とは考えていなかったので、補正予算に計上するにとどめ、360万円に関し特別議決を経なかったが、昭和52年10月17日言渡の本件原判決により360万円は売買代金の一部であると認定され、その支出手続の瑕疵が指摘されたところから、町長である控訴人は、昭和53年3月11日開催の議会に、360万円の支出、その後に取得した廃川敷地の買取契約をも含め、町民運動場用地取得の全体について改めて議会の追認の特別議決を求める議案を提出し、同月25日その旨の特別議決をえたことが認められる。
○ ところで、地方公共団体の長は当該地方公共団体を代表しその事務を管理執行する権限を有するのであるが、地方自治法96条1項5号は条例で定める契約については当該地方公共団体の議会の議決を要するものと定めている。その趣旨は、右のような契約は地方公共団体ひいては住民に与える影響が大きく、その他その契約により特定の者が利益を受けることがありうるから、住民の代表機関である議会においてこれらの事柄を個別に審議したうえ、長はその議決に従って執行すべきものとするところにあって、長は、右契約については議会の議決を経ないかぎり地方公共団体を代表する権限を有しないものと解される。したがって、長が右契約について議会の議決を経ないでこれを締結したときは、右行為は無権限の行為として無効になるのであるが、のちに議会が右行為を追認する旨の議決をしたときは、長のした無権限行為は遡って有効になるものと解すべきである。けだし、議会において叙上の点を審議して長に当該権限を付与することを相当とするのである以上、その議決が事前にされたと事後にされたとにかかわらず等しくその効力を認めても叙上の法の趣旨に反しないからである。そうすると、前記追認の特別議決により右360万円の支出部分について事前に特別議決がされていない瑕疵は治癒されたものということができる。
○ この点につき、被控訴人らは、「360万円の支出は、別の名目で議会の承認のもとにされているのであるから、のちにこれを代金の一部として追認する旨の特別議決をしても、違法な支出が適法になるわけがない。」旨主張するが、前記認定の事実に徴すると、360万円を含めた本件売買の価格に格別不当な点はないのであり、ただこの360万円を代金の一部とみるか否かについて、当時町当局はこれを代金の一部とみなかったために特別議決を経る手続をとらなかったものにすぎないと認められ、むしろ、外形上360万円の支出は売買契約と一応別個の理由にもとづいているから、これを代金の一部とみなかった町当局の見解も全く理由のないものともいいがたく、本件において町当局が当時ことさらに売買代金を圧縮し特別議決をうることを容易にしようとする等の意図を有していたものと認めるに足る証拠もないから、のちにこの360万円を代金の一部とみる立場からされた追認の特別議決の効力を否定しなければならない理由はないというべきである。これに反する被控訴人らの主張は採用しない。なお、被控訴人らは、「控訴人が本件360万円を代金の一部と主張することは控訴人本人の宣誓供述に反する信義則違反の主張である。」旨主張するが、右主張は、すでに述べたところに照らして採用することができない。
○ そうすると、控訴人のした360万円の支出は適法に帰したということができるから、違法支出であることを前提とする被控訴人らの請求は、その余の主張について判断を示すまでもなく、失当として排斥を免れない。
税条例改正の専決処分に瑕疵があっても、事後の議会の承認でその瑕疵は治癒されるとした事例 名古屋高判昭55.9.16行裁例集31.9.1825
(市税条例改正について、地方税法の改正が年度末となる等により、事務スケジュールを勘案して専決処分を行い、事後に専決処分に関する議会の承認を得たところ、これによる市税賦課の取消しを求める訴訟(住民訴訟ではなく取消訴訟)。当審は一審判決を是認し、その理由を引用している)
○ 地方税改正法は昭和51年3月31日に成立し、同年4月1日から施行されたが、右地方税改正法は地方税のうち事業税における事業主控除額の引き上げ、個人住民税における障害者、老年者等の非課税範囲の拡大、住民税及び事業税における白色申告者の専従者控除限度額の引き上げ、住民税均等割、自動車税及び軽自動車税等の引き上げ、不動産取得税、固定資産税等の非課税等の特別措置の整理等多岐にわたっていること。市では地方税改正法の成立をまって、これに基づく市税条例の改正案作成作業に入り、昭和51年4月14日改正市条例の原案を仕上げ、内部的決裁を経た上、同月21日市議会議員9名を混えた総務委員協議会を開催してその了承を取りつけ、翌22日本件専決処分に及んだこと。なお、改正市条例案作成に当たり参照すべき自治省通達(準則)案については同年3月8日入手し、説明を受けていること。本件専決処分を告示した後、議案の作成、印刷等通常の手順により臨時市議会開催の準備を進め、昭和51年5月11日に招集の告示をし、同月18日から同月21日まで開かれた臨時市議会において本件専決処分が報告、承認されたこと。被告市長において地方税法321条の4・2項所定の5月31日までに同条の4・1項後段の規定による特別徴収義務者等に対する通知をしようとすれば、同月6日までに当該通知書を発送する必要があったこと。以上の各事実が認められる。
○ ところで地方自治法179条に規定する専決処分は地方議会の権限に属する事項を地方自治体の長が代わって行なうことができるとするものであるところ、同条にいう「長において議会を招集する暇がないと認めるとき」とは当該事件が急を要し、議会を招集してその議決を経て執行するときは時期を失する場合をいうものと解するのが相当である。
○ そこで、本件専決処分が右要件に該当する場合であるか否かについて検討するに、改正市条例は当該年度において賦課徴収すべき租税に関する規定を既に当該年度に入っている時期において改正しようとするものであるから、できる限り早急にこれを行うべきであることは当然であるが、そのことから直ちに改正市条例について議会の議決を経てその執行をすることが時期を失することとなるものでないことはいうまでもない。また、地方税法321条の4の規定の関係でも、前記認定のように5月31日までに特別徴収義務者等に対する通知をするには同月6日までに当該通知書を発送しなければならないとしても、同法自体321条の4・3項においてやむを得ない理由がある場合に右期日後に通知することを許容しているのであり、右通知が期日後になされたとしても、市の財政又は納税義務者に格別の不都合、不利益を与えるものとは認め難い。その他前記認定の本件専決処分承認までの経緯に照らしても前記要件を具備したものとは認められず、他にこれを認めるに足りる証拠もない。
○ 因に、・・・によれば、人口、区域とも市より多大なA市、B市、C市、D市、E市においては専決処分を行うことなく、最も早いところでは昭和51年4月15日、遅いところでは同年5月24日に地方税改正法に基づく市税条例の改正条例を議会で決議していることが認められ、また・・・によれば、県下の多くの市町村において同年3月31日又は同年4月1日に専決処分をもつて条例改正を行ったことが認められる。
○ ところで、条例の制定は本来議会の権限であるところ、普通地方公共団体の長の専決処分に対し議会の承認がなされた場合には結局議会の議決のあったのと同視してよいのであるから、専決処分が前記要件を欠いてなされた場合であっても後に議会の承認があれば右瑕疵に治ゆされると解するのが相当である。そして本件専決処分に対し市議会の承認のあったことは当事者間に争いがないのであるから、専決処分の前記瑕疵は治ゆされたというべきである。
○ 従って、専決処分が違法であるとの原告の主張は採用しない。
土地買収に係る専決処分に瑕疵があっても、事後の議会の承認でその瑕疵は治癒されるとした事例 大阪地判昭56.11.24行裁例集32.11.2070
(土地買収事案について専決処分を経て行った後、専決処分について議会の承認を得た)
○ (売主)は、すぐに取引をするよう求めたが、被告(町長)は、公共団体としての手続が必要であることを告げて同年4月7日ころまで待つよう承諾をとりつけた。町では、4月、5月にこれまで臨時に議会を開いた例がなく、定例の議会は、6月であるが、そのときまで本件取引を引きのばしておくことは、無理であった。そこで、被告は、同年3月30日、事務当局に対し、町総合計画審議会を同年4月2日に開催する旨の通知を発送させて、そのとおり同審議会を開催し、昭和56年度に町立産業廃棄物処理場を設置する計画を、昭和54年度の事業に繰り上げることの了承を取りつけた。被告は、同月3日、町議会議長に対し、同月6日議員全員協議会を開催するよう要請し、議長は、急遽、その旨の招集通知を発出した。この議員全員協議会は、正式な議会ではないから、議決されることはないが、事案について、議員の意見の交換を通じて議会の意向を知ることはできるのである。なお、臨時議会が招集されず、議員全員協議会が招集されたのは、前者の招集には、一定の期間が必要であることによる。このようにして開かれた議員全員協議会(欠席者2名)では、被告が本件山林を金9,000万円で買い受ける交渉を進めた経緯が説明され、市長の専決処分によって近日中に取引することの了承が求められた。被告は、この協議会を通して、議員の一部に反対があっても、6月の定例議会では、専決処分に対し承認が得られるものと判断した。被告は、同年4月9日、専決処分書・・・を作成するとともに、同日、共有者の代表であるAと、本件山林を金9,000万円(1平方メートル当たり金2,185円)で売買する旨の売買契約を締結して売買契約書・・・を作成し、本件山林の取引を終えた。・・・本件処分は、昭和54年6月6日、町議会で承認された。・・・
○ 専決処分は、普通地方公共団体の長が、議会の権限に属する事項を代って行うわけであるから、長が専決処分権を行使するには、厳格な法律上の要件に服すべきであることは、議会民主主義のうえから当然である。本件では、地方自治法179条1項に規定された「長によって議会を招集する暇がないと認めるとき」に該当するかどうかが問題になるところ、同法101条には、長に議会を招集する権限があり、急施を要する場合には、開会の日の前3日までにされなければならない告示をする必要がないと規定している。したがって、議会を招集する暇がない場合とは、極めて限定され、議員の参集を求めてその議決を得る時間的余裕がなく、しかもその執行の時機を失するような一層の急施を必要とする緊急事態が発生したと客観的に認められる場合であると解するのが相当である。
○ ところで、本件の事項が、そのような緊急事態であると認めることは無理である。本件では、被告は、臨時議会を招集せず、議員全員協議会を開催しているのであるが、臨時議会を招集しなかつた合理的理由を見出すことができない。
○ このようにみてくると、本件処分は、地方自治法179条1項の要件を欠缺していたとしなければならない。
○ 同条3項は、長が専決処分をしたときには、「次の議会においてこれを議会に報告し、その承認を求めなければならない。」と規定している。この議会の承認は、長の専決処分の法律上の責任を解除する趣旨であると解するのが相当である。そうすると、本件でも、被告のした本件処分について、町議会は承認したのであるから、これにより被告の本件処分による法律上の責任を解除したものとしなければならない。
人勧にもとづく差額支給のうち一部を専決処分による改正条例成立前に支出した事案について、改正条例附則に遡及適用条項があり、改正条例の規定により給与引上げは遡及して適用されるため、条例の専決処分による成立によって条例欠缺の瑕疵は治癒されるとした事例 奈良地判昭57.3.31行裁例集33.4.785
(人事院勧告にもとづく給与等改定に対応する条例改正につき、県からの条例準則送付を待っていたため議会会期に間に合わず、専決処分により対応したが、一部職員の差額は専決処分による条例成立前に支出された。なお改正条例附則には、当該条例は公布の日から施行し当該年度の4月1日に遡って適用するとの遡及適用条項が設けられていた)
○ 本件専決処分は12月23日に行なわれたものであることが認められ、また議員らに対する差額支給は右専決処分の前日である12月22日に行われていることは当事者間に争いがない。そうすると、本件第一次公金支出のうち・・・に対する差額支給は、単に予算の議決がなされ、条例改正がなされていない段階で支出されたものと認められ、右支出は法204条の2、同232条の4第2項の規定にそれぞれ違反する違法な支出であるといわざるを得ない。そうして右支出は被告Mが被告Tの了解のもとに行なったものであるから、同被告の違法な支出命令に基づくものと認めることができる。同被告らは、右支出は被告Mのいわゆる事務的裁量の範囲に止まる旨主張するが、給与等条例主義を定めた前記各規定の趣旨にてらすと、いかなる事情があったにせよ、条例改正がなされない段階で、支出命令・支出行為を行うことは是認されるものではなく、同被告らは、村長及び収入役として自らの行為が前記法規に反する違法なものであることを十分認識し、又はその職責上重大な過失によりこれを認識しなかったものというべきである。よって同人らは故意又は重大な過失により違法な右公金支出を行なつたものと認められる。
○ しかしながら、本件専決処分の成立によって右以降前記違法は治癒され、残る違法はそれまでの1日間のみとなる。そこで更に右1日間の村の損害の有無につき検討する。〈証拠〉によれば、特別職職員の給与又は報酬の引上に関する改正条例は、いずれもその附則中に右引上に関する規定につき「公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する」旨を定めていることが認められる。右附則によれば、条例の公布によって条例の発効と同時に引上分報酬等の規定の適用は昭和52年4月1日に遡ることとなり、これによって報酬等受給資格者は当然に同日に遡って値上げにかかる報酬等の受給権を取得するものと解される。そうすると(村議会)議員たる被告らは既に昭和52年12月22日の時点で受給権を取得していたものというべきであり、村は本来支払うべき報酬を支払ったに過ぎないものと認められる。そうすると村には本件公金支出につき具体的な損害はなかつたものというべきである。
○ よって本件第一次公金支出は専決処分成立までの1日間につき違法であるがこれによって村に対し損害を与えていないこととなる。
補正予算提出にあたり真の目的を秘匿してこれと異なる目的の説明を行い、結果成立した予算を真の目的のために契約締結・支出したことは違法とした事例 京都地判昭59.9.18行裁例集35.9.1366
(空港設置の検討を行うための行政内部の検討素材として専門機関に委託して調査を行うこととし補正予算に計上することとしたが、知事等の命により調査の事実を外部公表しないこととした。そのため議会では予算の内容を当時問題となっていた鉄道路線の整備促進のための経費と説明し、特に質疑等もなく当予算案は成立し調査委託契約は締結され、委託料が支出された。決算説明においても空港調査の件は秘匿されていたが某議員の質問により鉄道整備調査経費予算で空港調査を行なっていたことを認めた。決算は、上記の経緯について格別の問題とならず認定された)
○ 被告は、予算に関し議会の議決の対象となるのは「款」「項」のみであり、予算に関する説明書の「目」「節」の記載は審議資料にすぎず、また、本件説明書の「説明」欄の記載は、法定の予算説明に当たらないから、共に地方公共団体の長の予算執行を拘束せず、本件支出負担行為等は何ら違法ではないと主張する。しかし、(地方自治)法211条2項が予算を提出するときに予算に関する説明書をあわせて提出するよう定め、法の施行令がその様式を定めた趣旨、ひいては議会の予算審議権に鑑みると、知事が、空港調査という一定の施策に要する経費を予算に計上しながら、議会に対しては、これをことさらに国鉄輸送力増強推進という他の施策に要するものとして虚偽の説明をして、いわば議会を欺罔して予算の議決を得ている場合にも、なお、この予算の流用支出を、地方公共団体の長の予算執行権の範囲に属する適法な財務会計行為に属するとすることは、このような脱法行為を正当視することになり、到底是認されないと解するのが相当である。そして、このことは、本来の使途を明らかにした場合に議会が予算を議決したであろうと考えられる場合でも、同様である。
○ しかし、仮に本件支出負担行為等がこの点で違法であったとしても、これによって府に具体的な損害が生じていないことは明らかである。すなわち、府では、従前から地方空港設置の可能性について調査・検討を加えることが懸案になっており、その検討資料を得るために本件調査を行う必要があったこと、右の必要性自体は、府議会においても異議がなく、そのため本件調査の委託料金1250万円の支出を含む昭和55年度決算が府議会で認定され、かつ、昭和56年度以降も、引続いて、本件調査の継続に要する経費が予算に計上され議決されたこと、及び、本件調査委託料金1250万円の支出に対して、訴外会社からは、調査委託契約所定の仕様に見合った調査報告書が府に提出され、その後の施策の検討に利用されていること、以上のことからすると、右の調査報告書(本件調査の結果)は、府にとって有用であり、かつ、その金銭的な価値は、その対価である調査委託料金1250万円に見合うものであると推認される(原告は、この点を積極的に争っていない)から、右調査委託料の支出によって、府は、何らの損害も被っていないというほかはない。
【最高裁判例】 路線の認定及び道路区域の決定の手続を経ずに行われた道路用地の任意取得も違法ではない 最判昭59.11.6集民143.145
(道路の路線認定に関する議会の議決、路線の認定および道路の区域の決定を経ずに道路用地を買収して公金支出したのは違法とする首長を被告とする4号訴訟)
○ 特別区道の開設については、道路法により、路線の認定に関する区議会の議決、路線の認定、道路の区域の決定、道路の供用の開始という手続を経由すべきことが規定されているが、右手続は、道路法上の道路を成立させるための要件であるにとどまり、当該道路開設のためにその用地に対する権原を任意に取得するについての要件をなすものではないから、被上告人B1(注:特別区長)の前記土地買収が、本件計画道路に係る路線の認定に関する○区議会の議決、路線の認定及び道路の区域の決定を経ずに行われたことをもって、これを違法ということはできない。また、本件計画道路の開設が前記土地買収の動機目的をなすものではあっても、前記土地買収は、本件計画道路を開設する行為そのものとは区別され、それとは独立して、○区に対し当該土地に係る権原を取得させ、その代金の支払債務を負担させるという効果を発生させるにとどまるものであるから、仮に本件計画道路を開設することに所論のような違法事由が存するとしても、そのことにより前記土地買収が違法となるものではない。したがって、前記の土地買収及び公金支出をもって違法な行為ということはできない。原判決が、本件計画道路に関し前記の土地買収が行われた後である昭和○年○月○日に路線の認定及び道路の区域の決定がなされている点をとらえ、右の認定及び決定はいわゆる公定力を有する行政処分であるから、それに重大かつ明白な瑕疵が存しない限り、前記の土地買収及び公金支出が違法となるものではないとした点は、法令の解釈、適用を誤ったものといわざるを得ないが、前記の土地買収及び公金支出に違法がないとした結論は正当である。
【最高裁判例】 収賄容疑で逮捕された市職員を逮捕後4日目に懲戒免職でなく分限免職にして退職手当を支給した場合において、条例上分限免職処分の場合は当然に退職手当が支給されるため、分限免職処分は退職手当支給の直接の原因となり、分限免職処分が違法であれば退職手当支給行為も違法となるところ、本件においてその後間もなく、右職員が前記物品のほかに金員を収賄したとの事実で起訴され、有罪判決が確定したとしても、本件分限免職処分は違法ということはできず、よって右退職手当の支給をもって違法な公金の支出に当たるということはできない 最判昭60.9.12集民145.357
(事実関係は上記の通り)
○ ところで、上告人は、本件退職手当の支給の違法理由として、本件分限免職処分の違法を主張する。地方自治法242条の2の住民訴訟の対象が普通地方公共団体の執行機関又は職員の違法な財務会計上の行為又は怠る事実に限られることは、同条の規定に照らして明らかであるが、右の行為が違法となるのは、単にそれ自体が直接法令に違反する場合だけではなく、その原因となる行為が法令に違反し許されない場合の財務会計上の行為もまた、違法となるのである(最高裁昭和46年(行ツ)第69号同52年7月13日大法廷判決・民集31巻4号533頁参照)。そして、本件条例の下においては、分限免職処分がなされれば当然に所定額の退職手当が支給されることとなっており、本件分限免職処分は本件退職手当の支給の直接の原因をなすものというべきであるから、前者が違法であれば後者も当然に違法となるものと解するのが相当である。
○ そこで、本件分限免職処分を発令したことに違法性が存するかどうかを検討するに、前記の…を収賄したDは、地方公務員法28条1項3号にいう「その職に必要な適格性を欠く場合」に該当すると認められるから、本件分限免職処分は、同条項所定の要件を具備しているということができる。もっとも、本件条例によれば、懲戒免職処分を受けた職員に対しては退職手当を支給しないこととされているから、Dを懲戒免職処分に付することなく本件分限免職処分を発令したことの適否を判断する必要があるところ、前記の…の収賄事実が地方公務員法29条1項所定の懲戒事由にも該当することは明らかであるが、職員に懲戒事由が存する場合に、懲戒処分を行うかどうか、懲戒処分をするときにいかなる処分を選ぶかは、任命権者の裁量にゆだねられていること(最高裁昭和47年(行ツ)第52号同52年12月20日第三小法廷判決・民集31巻7号1101頁参照)にかんがみれば、上告人の原審における主張事実を考慮にいれたとしても、右の収賄事実のみが判明していた段階において、Dを懲戒免職処分に付さなかったことが違法であるとまで認めることは困難であるといわざるを得ない。また、本件分限免職処分発令後の経過に照らすと、本件分限免職処分が時期尚早の処分ではなかったかとの疑いをいれる余地がないとはいえず、その当不当が問題となり得ようが、本件分限免職処分の発令の段階でその後における事態の進展を予測することには相当の不確実性が伴うばかりでなく、分限処分の発令時期についても任命権者が裁量権を有しており、不適格な職員を早期に公務から排除して公務の適正な運営を回復するという要請にもこたえる必要のあることを考慮すると、発令時期の面から本件分限免職処分が違法であるとすることもできない。さらに、本件分限免職処分の発令後において、前記のとおり、Dは…の収賄事実で起訴されたほか、別件の収賄事実で2回にわたり追起訴されるという事態が発生したわけであるが、別件の収賄事実が上告人の原審における主張のようにDに対する本件退職手当の支払前に判明したとしても、本件分限免職処分の発令によりDの○市職員としての身分が既に剥奪されていることに照らせば、別件の収賄事実が判明した段階で本件分限免職処分を取り消さなかったことが違法であるということはできない。
○ 以上のとおり、本件分限免職処分を発令したこと及びこれを取り消さなかったことが違法とはいえないから、本件退職手当の支給もこれを違法とすることはできないものといわざるを得ない。
【最高裁判例】 ①随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約は、地方自治法施行令167条の2第1項の掲げる事由のいずれにも当たらないことが何人の目にも明らかである場合や契約の相手方において随意契約の方法によることが許されないことを知り又は知り得べかりし場合など当該契約を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える法令の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、私法上無効となる ②随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約が無効といえない場合には、地方自治法242条の2第1項1号に基づいて右契約の履行行為の差止めを請求することはできない 最判昭62.5.19民集41.4.687
(かねて町有地に地元住民が植林のための地上権を設定していたが、その期間が満了することとなった。町は小学校増改築財源確保のため、町有地を地上権者に売却することを考え、林野地の管理を行う林野組合に協議して同意を得るとともに、評価額情報を得た。しかし地上権者は評価額の1/5以上の額での買取りを拒絶したため、町が苦慮していたところ、評価額で買い取ると申し出る者があり、町は、随意契約の方法により、評価額での売却契約を締結した)
○ (地方自治)法234条2項は、普通地方公共団体が締結する契約の方法について「指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。」と規定し、これを受けて(地方自治法施行)令167条の2第1項は、随意契約によることができる場合を列挙しているのであるから、右列挙された事由のいずれにも該当しないのに随意契約の方法により締結された契約は違法というべきことが明らかである。しかしながら、このように随意契約の制限に関する法令に違反して締結された契約の私法上の効力については別途考察する必要があり、かかる違法な契約であっても私法上当然に無効になるものではなく、随意契約によることができる場合として前記令の規定の掲げる事由のいずれにも当たらないことが何人の目にも明らかである場合や契約の相手方において随意契約の方法による当該契約の締結が許されないことを知り又は知り得べかりし場合のように当該契約の効力を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える前記法及び令の規定の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、私法上無効になるものと解するのが相当【要旨①】である。けだし、前記法及び令の規定は、専ら一般的抽象的な見地に立って普通地方公共団体の締結する契約の適正を図ることを目的として右契約の締結方法について規制を加えるものと解されるから、右法令に違反して契約が締結されたということから直ちにその契約の効力を全面的に否定しなければならないとまでいうことは相当でなく、他方、契約の相手方にとっては、そもそも当該契約の締結が、随意契約によることができる場合として前記令の規定が列挙する事由のいずれに該当するものとして行われるのか必ずしも明らかであるとはいえないし、また、右事由の中にはそれに該当するか否かが必ずしも客観的一義的に明白とはいえないようなものも含まれているところ、普通地方公共団体の契約担当者が右事由に該当すると判断するに至った事情も契約の相手方において常に知り得るものとはいえないのであるから、もし普通地方公共団体の契約担当者の右判断が後に誤りであるとされ当該契約が違法とされた場合にその私法上の効力が当然に無効であると解するならば、契約の相手方において不測の損害を被ることにもなりかねず相当とはいえないからである。そして、当該契約が仮に随意契約の制限に関する法令に違反して締結された点において違法であるとしても、それが私法上当然無効とはいえない場合には、普通地方公共団体は契約の相手方に対して当該契約に基づく債務を履行すべき義務を負うのであるから、右債務の履行として行われる行為自体はこれを違法ということはできず、このような場合に住民が法242条の2第1項1号所定の住民訴訟の手段によって普通地方公共団体の執行機関又は職員に対し右債務の履行として行われる行為の差止めを請求することは、許されない【要旨②】ものというべきである。
住民訴訟の対象となるのは、財務会計法規に直接違反する行為のほか、首長等がその事務の適正な執行・運営を規律するための法規に違反し、また、明文の規定に違反していなくても公務秩序に照らし正当として是認し得ないような行為(先行行為)をし、これら先行行為が後行する公金の支出行為と事実上直接的な関係に立つ場合をも含むものと解するのが相当とした事例 仙台地判昭62.9.30判例時報1287.47
(自治体が国鉄職員のみを対象とする採用試験を行い、所要の経費を支出した)
○ 地方自治法(以下単に「法」という)242条の2の規定による住民訴訟の制度は、普通地方公共団体の長等が違法な公金の支出等、法242条1項所定の行為(以下これを「財務会計上の行為等」という)をなし、もしくはこれが相当の確実さをもって予測されるときに、これらの行為等が究極的には当該地方公共団体の構成員である住民(納税者)全体の利益を害するものであるところから、地方自治の本旨に基づく住民参政の一環として、住民に対しその補填、是正ないし予防を裁判所に請求する権能を与え、もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とするものである。換言すれば、右財務会計上の行為等の適法性ないしその是正の要否について地方公共団体の判断と住民の判断とが相反し対立する場合に、住民が自らの手により違法の防止又は是正を図ることができる点に制度本来の意義がある。このように、住民訴訟の対象は財務会計上の行為等(財務事項)に限られているのであるが、右「財務会計上の行為等」を、狭く財務会計法規違反の行為等に限定すると、公金の支出が違法として争われる場合の大部分は、直接公金の支出の規制を目的とする法規(いわゆる財務会計法規)につき手続的には一応これを遵守していることが予想されるので、住民訴訟の対象を右の如くに限定してしまうと、住民訴訟の持つ地方財務行政の適正な運営確保の目的はほとんど機能しないことになる。他方、地方公共団体において公金の支出を伴わない行政行為はおよそ存在しないのが実情であるから、それ自体は非財務行為であるところの行政行為についても、それが違法であることの故にこれに伴う公金の支出も違法となるとの主張を是認し、右行政行為の適法性を争う途を無限定的に認めると、住民訴訟は広く行政一般についての政策論争の場になるか、或いはこれが政争の具に利用されることにもなりかねず、かくては住民訴訟の対象を財務事項に限った趣旨を逸脱することになる。このような広狭両極端の運用は法の予定しないところであるというべきであるから、住民訴訟の対象となるのは、財務会計法規に直接違反する行為のほか、地方公共団体の長等がその事務の適正な執行・運営を規律するための法規に違反し、また、明文の規定に違反していなくても公務秩序に照らし正当として是認しえないような行為(これらを以下「先行行為」という。)をし、これら先行行為が後行する公金の支出行為と事実上直接的な関係に立つ場合をも含むものと解するのが相当である。けだし、住民訴訟の本来の目的から逸脱した訴権の濫用を防ぎ、違法な授益的行政により地方公共団体の財産が損なわれることを納税者たる住民の立場から監視しようとする住民訴訟制度の趣旨に最もよく適合するからである。そして、右にいう「事実上直接的な関係」とは、先行行為を行うことの主たる目的が実質的に見て後行する公金の支出に向けられていると評価できるものであること又は先行行為を行うことによって手続上他に何等の債務負担行為(支出決定)を要せず当然に地方公共団体が後行する公金の支出義務を負担することになることと解すべきである。
○ そこで、本件において原告らが違法であると主張する国鉄職員のみを対象とした県職員への採用試験と、採用試験実施の結果県がその費用を支出したこととの間に上述のような関係があるか否か検討するに、〈証拠〉によれば、次の各事実が認められ、この認定を覆すに足りる証拠はない。
1 政府は、昭和60年12月13日、閣議決定「国鉄余剰人員雇用対策の基本方針について」をもって、改革に伴い国鉄に生じた余剰人員を各省庁において相当数受け入れることを決定すると共に、地方公共団体に対し、昭和61年度から昭和65年度当初までの間において、国が講じる措置に準じ積極的に採用を進めるよう自治省から要請することとした。
2 右方針に則り、自治事務次官は、同年12月23日各都道府県知事及び政令指定都市市長に対し、自治公一第49号をもって、各地方公共団体における国鉄職員の受け入れを要請する旨の通知をし、さらに自治省行政局公務員部長は、同月24日、右知事及び市長に対し、自治公一第50号をもって、国鉄職員受け入れの実施手続についての指導に関する通知をした。
3 (地方公務員)法17条3項本文は、人事委員会を置く地方公共団体においては職員の採用は原則として競争試験によるものの、同項但書によれば、人事委員会の定める職について同委員会の承認があった場合は選考によることができるとされているところ、これを受けて任用規則28条1項は、選考により採用することができる職を定めており、同条3項は、これらの職への選考による採用については、人事委員会の承認があったものとみなしている。県知事は、自治省からの前記要請に応じることとし、採用しようとする職が右規則28条1項3号の二の「公共企業体に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者」に該当していることから、国鉄職員を対象に選考を行い、県職員に採用することとした。
4 県知事の請求により、同県人事委員会は、地方公務員法18条により、昭和61年6月6日及び同月20日、国鉄職員を対象として本件選考試験を実施した。
5 県においては、人事委員会の予算の執行は同委員会事務局長に補助執行させることになっており・・・かつ右予算執行事務は人事委員会事務局長の専決事項とされている・・・。専決とは、知事の権限に属する事務を常時その者に代わって決裁することを意味し・・・、県人事委員会事務局長は・・・自己に委ねられた専決権限によって、県出納長に対し、本件採用試験の経費の支出命令を発し、出納長は右経費を支出した。
以上の事実によれば、本件採用試験の目的が国鉄職員の県職員への任用という非財務的事項にあり、本件選考に費用を支出すること自体を主たる目的とするものでないことは一見して明らかである。加うるに、採用試験を実施するのに要する費用を支出するためには、別に支出決定が必要であることもまた明白である。
○ 以上検討してきたことから明らかなように、本件訴はそもそも法242条の2の住民訴訟によっては争えない事項を目的とするものであり、かかる訴は不適法といわざるを得ない。
普通財産の無償貸付に関する議会の議決は、議決された事項につき執行機関に対し一定の権限を付与するものではなく、自治体の意思を決定するものであると解されるから、議決に重大かつ明白な瑕疵があり無効である場合を除き、執行機関は、原則として議決事項の執行を義務づけられ、議会の議決に何らかの違法がある場合でも、議決に従ったものである限り、執行機関による執行行為は自治体との関係においては違法となることはないとした事例 東京地判昭62.10.27行裁例集38.10.1573
(特別区において、議会の議決を経て、病院誘致のため、普通財産を区医師会に無償で貸し付けた)
○ 地方自治法242条の2第1項4号前段の職員個人に対する損害賠償請求は、職員の地方公共団体に対する不法行為に基づく損害賠償責任の履行を住民が地方公共団体に代位して求めるものであるから、そこで問擬すべきは、地方公共団体との関係における職員の行為自体の違法性であり、言い換えると、当該職員の立場においてされた当該行為が、地方公共団体に対する違法行為になるかどうかの問題である。そして、地方自治法96条1項6号は、条例の定めがある場合を除いて、財産を適正な対価なくして譲渡又は貸し付けることを議会の議決事項としたものであるが、右議決の性格は、議決された事項につき執行機関に対し一定の権限を付与するものではなく、右事項に対する地方公共団体の意思を決定するものであると解されるから、執行機関は、原則として議決事項の執行を義務づけられる立場にあり、したがって、議会の議決に何らかの違法がある場合でも、右議決に従ったものである限り、執行機関による執行行為は地方公共団体との関係においては違法となることはないものというべきである。もっとも、執行機関は、議会の議決に重大かつ明白な瑕疵があってこれが無効である場合には、当該議決に拘束されず、むしろ、これを執行してはならない義務を負うものであるから、それにもかかわらず当該議決を執行した場合には、当該執行行為は、地方公共団体に対する関係において違法性を帯びるものというべきである。
そこで、以下、本件議決に重大かつ明白な瑕疵が認められるか否かについて検討する。
○ 原告らは、地方自治法237条2項の規定について、普通財産の無償貸付は、議会の議決による場合といえども、これを行政財産に準じて使用する場合又は対価を徴収することが公平の原則に反する場合に限り適法となるものであり、本件土地無償貸付には右要件が充足されていないので、これを可決した本件議決は、同項及びその基本にある地方財政法8条に違反し、違法無効である旨を主張する。しかし、地方自治法237条2項を右のように解釈する理由はないというべきである。同項は、地方公共団体の財政の健全な運営を確保するため、地方公共団体の普通財産について、適正な対価によらない譲渡、貸付を原則として禁止する一方、地方公共団体が公共的施策の実施等公益上の目的のためその普通財産を無償又は特に低廉な対価のもとに譲渡し又は貸し付けることが必要な場合があることを考慮し、そのような場合については、条例又は議会の議決により、右禁止を解除して無償又は低廉な対価で譲渡又は貸付ができることとしたものであって、右禁止を解除すべき場合についての一般的原則は条例で定めるが、臨時的なものなど条例の定める一般的原則によることができない場合については、個別的に議会において右禁止の解除の当否について判断のうえ議決することを当然予定しているものと解するべきである。したがって、原告らの主張する場合以外でも、右禁止を解除することを相当と認める場合には、議会は無償又は低廉な対価による譲渡又は貸付を議決することができるのであり、これと見解を異にする原告らの右主張は失当といわざるを得ない。
○ ・・・によれば、本件土地の無償貸付は、○区内に公的総合病院を誘致する政策の実現のための一施策として、公的病院の経営が困難であることに鑑み、右政策により誘致することとなった本件病院の経営を援助する目的で実施されたものであることが認められる。これに対し、原告らは、○区の財政状況・・・、本件病院の採算性・・・及び無償貸付という援助方法の不当性・・・からすれば、本件無償貸付を実施する必要性はないから、本件議決は違法無効である旨を主張する。確かに、適正な対価によらない普通財産の譲渡又は貸付は、公益上の必要がある場合その他特別の事情がある場合に限り認められるべきものであるが、右公益上の必要性等の有無についての判断は、議会の裁量に属するから、その判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があると認められる場合に当該議決が違法となるというべきであり、そして、この裁量権の範囲の逸脱又は濫用が明白である場合にはじめて、当該議決が無効となるというべきである。しかるに、原告の主張するところは、○区の財政は公債費比率が高く、公債償還額が区の財政を圧迫している状態にあり、他方、本件病院は、練馬区の医療需要からすれば本件土地の無償貸付を受けなくても採算のとれる事業であって、仮に経営が苦しくなった場合にはその都度補助金を支出すれば足りるものであるから、本件土地の無償貸付は、○区財政の健全性を害するのみならず、本件病院を経営する○区医師会に不当に利益をもたらすものであり、また、本件土地の無償貸付は隠れた補助金の支出となって区の予算の公正さ、明瞭さを害するものであるというのであるから、仮に原告の主張するこれらの事実が立証されたとしても、本件土地の無償貸付が、前記のとおり、○区内に公的総合病院を誘致する政策を実現するための施策として行われたものであることを考慮すれば、本件土地の無償貸付の公益上の必要性に関する議会の判断に裁量権の範囲の逸脱又は濫用があつたことが明白であるということは到底できないものといわなければならない。
○ そうすると、本件土地の無償貸付の不当性の故をもつて本件議決の違法無効をいう原告らの主張は理由がないといわざるを得ない。
契約の締結につき議会の議決を得ている場合であっても、首長が裁量権を濫用もしくは逸脱し、著しく高額な価格で財産を取得する契約を締結し自治体に債務を負担させた場合には、当該行為は違法と評価され、民法上の不法行為の要件に従って長は自治体に対し住民訴訟による代位行使の対象となる損害賠償責任を負うとの前提のもと、本件は契約締結行為は裁量権を濫用逸脱した違法なものにはあたらないとした事例 金沢地判昭62.11.27行裁例集38.11.1665
(県が土地買収の契約を締結するにあたり、買収価格はいくつかの不動産鑑定結果を参考に売主との交渉を行い、交渉は難航したものの土地42.5億円、建物7億円で最終決着した。なお鑑定は2件が売主側から提供され、県も自ら依頼したが(判決文別表(1)鑑定)上記の鑑定額より安価だったことや鑑定手法が前記鑑定と異なっていたことから更にもう1件の鑑定を県が自ら依頼した。また買収土地の最有効利用判定につき別表(1)とその他の鑑定が異なっていたことから、交渉において別表(1)鑑定を採用しないこととした。また本件につき議決を得るための議会説明では、別表(1)鑑定を除く鑑定を基礎とする説明をした(が鑑定(1)の存在は露見した)。なお当審は土地の価格については、採用された鑑定額には問題があり、採用されなかった鑑定の内容を参考に35〜36億円程度であり上記買収価格は不適正と、建物は県において必要のないものと認定した)
○ 長の行為が地方公共団体に対する民法上の不法行為を構成する場合には、長はこれによって地方公共団体が被った損害を賠償する責任を負うものというべきであるが、長の財産取得契約の締結がいかなる場合に不法行為における違法性を帯びるものと評価され、地方公共団体に対する損害賠償責任を負担するに至るかにつき考察するに、一般に地方公共団体が財産を購入する場合、その対価について規制した法令の定めはなく、長による地方公共団体の財産購入契約の締結は裁量行為であると考えられるので、たとえ契約の締結につき議会の議決を得ている場合であっても、長においてその裁量権を濫用もしくは逸脱し、著しく高額な価格で財産を取得する契約を締結し、被告に債務を負担させた場合には、右行為は違法と評価され、民法上の不法行為の要件に従って長は地方公共団体に対し住民訴訟による代位行使の対象となる損害賠償責任を負うものと解するのが相当である。・・・そうであるところ、地方自治法138条の2の定めに照らせば、一般的には、長としては、地方公共団体を代表して物件を購入する場合には、原告らの主張するように、できるだけ適正妥当な価格で取得し、地方公共団体に損害を与えないように努めるべき義務を負い、当該契約につき議会の議決を要する場合には、議会に対し契約の内容を十分に説明すべき義務も負っているものというべきであり、そのため県においては請求原因・・・記載のような「規則」・・・や「要領」等の規定が定められている・・・。しかし、購入価格は長において一方的に決定することはできず、契約の相手方の承諾が必要であること、地方公共団体が財産を譲渡する際の価格については、地方自治法237条2項により、適正な対価なくして譲渡することは一般的に禁じられているけれども、財産を購入する際の対価についてはこのような規定はなく、また財産を処分する場合であっても条例または議会の議決があれば適正な対価なくして譲渡することができる旨定められていること等に照らせば、長が右の義務もしくは「規則」、「要領」の手続等に反したことや、購入価格が客額的に判断される適正価格を超えることをもって直ちに長の契約締結行為を違法と断ずるのは相当ではなく、前記の裁量権の濫用ないし逸脱の有無の判断に当たっては、契約締結に至る経緯、当該物件の価格等を総合的に検討して判断しなければならないものというべきである。
・・・
○ 本件土地については、被告の締結した本件契約での購入価格は適正価格より高額であり、また、本件建物についても、前記・・・における検討によれば、価格自体は適正であるにせよ、不要の建物を6億円もかけて購入した被告の行為自体は、経済的観点からみて不当なものであったといわざるを得ない・・・。
○ しかし・・・本件契約に至る経緯に鑑みれば、大学(注:売主)は終始本件土地建物の一括売却を主張し、またその売買代金についてもかなりの高額を強く提示して、県の提案とは平行線をたどっていたのであり、大学において必ずしも県に本件土地を購入してもらわなければならないような状況にあったとも断じ難く、県としては当時従前の主張に固執するときは本件土地の購入ができなくなるに至る可能性も多分にあったものといえる。そして、同認定のような本件土地の位置関係及び両側に既に県有地があったこと等による同土地の非代替性、県としてのHの森周辺整備計画の重要性に鑑みれば、このような場合に本件土地建物を前記認定のような代金で購入するか、あるいは購入を締めるかは知事である被告に委ねられた政策的決断の問題というべきであって、原告らの主張する・・・ように本件土地建物の購入を差し控えなければならないものとは到底いい難い(なお、一般に、既に隣地の所有権を有している者が当該土地を併合買収する場合、あるいは立地条件に基づき場所的代替性のないいわゆる所望買いをする場合には、正常価格よりもある程度高額にて買い進むことも往々にしてあるのであって・・・そのような場合には通常の30パーセント程度高額で買い進むこともありうるとしている。)。また、大学において本件土地建物の売買代金により移転費用を賄おうとする意図を有していたことは前記認定のとおりであり、なるほど本件土地の売買代金額決定の資料から別表(1)の鑑定評価を除いたことは必ずしも相当ではなかったけれども、被告において右の意図に迎合し、この目的実現のためにことさらに右鑑定評価を除外して本件土地建物を前記のような代金額で購入しようとした事情も、これを認めることはできない。すなわち、前記認定のように県議会において当初別表(1)の鑑定評価の存在を明らかにしなかったことは議会に対して契約の内容を十分に説明すべき・・・長の一般的な義務に反したものといわざるをえないけれども、本件土地を前記認定のような代金で購入するに至ったこと、及び本件建物を存置建物として評価した代金額で購入したことには諸般の事情に鑑みれば無理からぬものがあり、本件土地の右代金額と前記認定の適正価格との開差及び本件建物購入の非経済性を勘案しても、結局、被告において本件契約を締結したことは、その裁量権を逸脱もしくは濫用した違法な行為であるということはできないものというべきである。
違法無効な条例に基づく退職手当の支給について、事後の予算措置(議会議決)によりその違法性は治癒されないが、事後的な遡及適用条項のある条例措置により治癒されるとした事例 京都地判昭63.11.9判例時報1309.79
(特別職に対する退職手当の額決定を知事に一任する内容の条例により退職手当が支給された。なおその後退職手当額を具体化する改正条例が成立した。改正条例附則には遡及効の定めがある)
○ 地方自治法204条3項は「給料、手当及び旅費の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。」と規定し、給与条例主義を定めている。さらに、同法204条の2は「普通地方公共団体は、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基かずには、これを第203条第1項の職員及び前条1項の職員に支給することができない。」と定めている(なお、地方公務員法25条1項にも同旨の規定がある)。これらの規定は、地方公共団体の給料、手当等の額及び支給方法を条例をもって規定するものとして、予算措置のみによるいわゆるお手盛防止の目的で納税者である住民の代表者である地方公共団体の議会の慎重な給与条例の制定を通じてこれをコントロールするために設けられたものであり、とくに同法204条3項が「手当の額」を条例で定めなければならない旨を明定していることに照らし、右の手当支給を定める条例では、手当の額を確定し得るものでなくてはならない(最判昭和50年10月2日判例時報795号33頁参照)。そして、本件退職手当条例7条のように特別職の退職手当の額を単に「知事が別に定める」旨規定し、その額や支給方法一切を知事の決定に委ねる条例は、その支給に関する金額、支給期日、支給方法の基準を示し、具体的な金額、支払期日、支給方法などは右基準の範囲内で定めるべきものとして、その決定を知事に任せることが条例で定められている場合でない限り、特別職に対する退職手当金の金額、支給方法などの決定をすべて無条件で知事に一任するものというほかなく、地方自治法204条3項、204条の2に違反し、無効であって、右退職手当条例7条に基づく本件退職手当の支給は同法242条所定の「違法な公金の支出」にあたるというほかない。そして、右規定所定の法律又は条例上の根拠を欠く場合に、たとえその支給について予算措置がなされその点につき議会の決議があった場合でもその違法性が治癒されるものではなく、それが違法、無効であることに変りはないというべきである。けだし、右各規定は、その改正前において、特別職の給与等については条例で定めることになっておらず、単なる予算措置のみで給与等が支給されても違法ではないとされていたため、一般職及び特別職を通じて給与等の実態が地方公共団体ごとに区々になり、混乱していた給与体系の公明化を目指し、これを条例で定めることによりその抜本的改正を求めるために設けられたものであるからである。したがって、本件退職手当の支給につき予算措置がなされていることを理由にその支給が右各規定に違反しない旨の被告の本案の主張・・・はその理由がなくこれを採用できない。
○ しかしながら、被告の本案の主張・・・の改正給与条例が昭和63年に施行されたことは当事者間に争いがなく・・・、右改正給与条例6条は「知事等が退職した場合には、その者に退職手当を支給する。 2 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料の月額に次項の規定により計算した在職期間を乗じて得た額に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。(1)知事 一〇〇分の八〇、(2)副知事一〇〇分の六〇 (3)出納長 一〇〇分の五五 3(以下略)」と定めており、同条及び改正給与条例の関連条項に照らし、知事等の退職手当の額が同条例自体で確定し得るものとなっていることが認められ、これによると同改正給与条例による知事等の退職金の支給は地方自治法204条3項、204条の2に適合するもので、これに違反するものでないといわねばならない。そして、同改正給与条例附則10項は、「適用期間〔昭和53年4月15日から同条例の施行の日の前日―昭和63年3月21日までの期間〕において次項の規定による改正前の退職手当条例第7条の規定により支給された退職手当は、改正後の知事等の給与条例第6条及び第7条の規定……により支給されたものとみなす。」と定めている。そして、この改正給与条例附則10項が適用される限り、府が被告○に対し、昭和61年末までに支給した知事の退職手当は前示のとおり地方自治法204条3項、204条の2に適合する同条例に基づき支給されたものとみなされ、これが遡及的に適法な支給となったものというべきである。
○ 原告は右改正給与条例附則10項が行政法規不遡及の原則に照らし無効である旨主張するけれども、行政法規であっても国民に不利益ないし義務を課し、既得権を奪い、かつ公益性を欠くものでない限り、その遡及的適用を求めることができるというべきである(なお、最判昭和33年4月25日民集12巻6号912頁、最判昭和53年7月12日民集32巻5号946頁参照)。そして、右附則10項が住民ないし国民に不利益ないし義務を課し、或いはその既得権を奪うものであるとはいえず、本件全証拠によってもこれを認めることができないから、同項を無効ということができない。したがって、原告の右主張は採用できない。なお、右附則10項の遡及適用については公金支出による住民の一般的利益の侵害の問題が生ずるが、給与条例主義をとる地方自治法の下で納税者である住民の一般的利益は、住民の代表者である議会が給与条例の制定を通じてコントロールすることにより保障されているところ・・・改正給与条例は府特別職報酬等審議会の答申に基づき府議会で可決成立したものであるから、右の一般的利益をもって右附則10項の効力を否定すべき根拠とすることはできない。さらに原告は改正給与条例6条2項が文意不明確であり、無効である旨主張するが、前認定の同条項はそれ自体明確で、文意が漠然不明確でこれを違憲・無効とすべきものでないことが明らかである。次に、原告は改正給与条例7条3項が憲法14条1項に違反し無効であると主張するけれども・・・、改正給与条例7条3項は、国家公務員から退職手当の支給を受けることなく引続いて副知事又は出納長となった者に対する退職手当の算定に当り、従前の勤続期間を在職期間に通算する場合などについて、その退職手当の額について規定したもので、それ自体合理的な規定であり、これが原告主張のように憲法14条1項に違反する不合理な差別的取扱をした規定であるとはいえない。よって、原告の右主張はいずれも採用できないものである。
○ したがって、被告○に対する原告の本訴不当利得ないし不法行為による金員支払の各代位請求は、その余の判断をするまでもなく、理由がないからいずれもこれを棄却すべきである。
財務会計行為が先行する非財務会計行為に対する支出として行われた場合、住民訴訟において非財務会計行為の違法性が財務会計行為の違法性と一体として評価されるのは、先行行為たる非財務会計行為を行うことの主たる目的が実質的にみて後行する公金支出に向けられていると評価できるものである場合、または先行行為たる非財務会計行為を行うことによって手続上他に何らの支出負担行為を要せず、当然に自治体が後行する公金の支出義務を負担することになる場合に限定されると解すべきとした事例 秋田地判平3.3.22判例時報1427.46
(食管法上の不正規流通米(自由米)の取締を図るため国は県に不正規流通米の防止対策につき協力を求め、県と食糧事務所は県警と協力して検問を実施。また県からの要請により村も検問に協力し、これに要する県費・村費が支出された)
○ (地方自治)法242条の2に規定されているいわゆる住民訴訟の制度は、地方公共団体の執行機関又は職員による同法242条1項所定の違法な財務会計上の行為又は怠る事実が究極的には当該地方公共団体の構成員である住民全体の利益を害することから、これを防止するため、住民に対しその予防又は是正を裁判所に請求する権限を与え、もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的として法律が特別に認めた制度である。このように、住民訴訟は自己の利害に関わりなく提起できる民衆訴訟として、法律で特別に認められた例外的な訴訟類型であるから、その要件を安易に拡張解釈することはできないものであり、仮にこれを拡張して、財務会計上の行為の原因となる非財務会計行為の違法がある場合には当該財務会計上の行為も違法となるものと解し、当該非財務会計行為の違法性も住民訴訟の審理対象になるとすれば、地方公共団体の事務で公金の支出を伴わないものはないから、住民訴訟によって、広く行政一般の非違をただすことを許す結果となり、住民訴訟の対象を財務会計上の行為に限った地治法の趣旨、目的を明らかに逸脱する結果となる。したがって、非財務会計行為の違法を主張することは、住民訴訟の本来の趣旨、目的に違反し、原則として許されないものと解される。
○ もっとも、住民訴訟において問擬すべき財務会計行為の違法性は、当該行為により地方公共団体に財産的損失を与えることが法の許容するところであるか否かという観点から判断すべきものであるから、財務会計行為それ自体の違法性に限定されず、当該財務会計行為の原因となった非財務会計行為をも含めて一体としてその違法性を評価しなければならない場合のあることも否定できないところであるが、このような場合にも、財務会計行為とその原因となった非財務会計行為との間には、これを一体として評価しなければならない緊密な関係が要求されるものと解するのが相当である。そして、これをさらに具体的な基準として展開するならば、当裁判所は、仙台地裁昭和62年9月30日判決(判例タイムズ672号154頁)【注:上掲】と同様の見解であり、<1>の先行行為たる非財務会計行為を行うことの主たる目的が実質的に見て後行する公金支出に向けられていると評価できるものであること、又は、<2>先行行為たる非財務会計行為を行うことによって手続上他に何らの支出負担行為を要せず、当然に地方公共団体が後行する公金の支出義務を負担することになる場合に限定されるものと解するのが相当である。また、住民訴訟において問擬すべき財務会計行為の違法性は、当該行為により地方公共団体に対する財産的損失を与えることが法の許容するところであるか否かという観点から判断すべきものであることからすると、公金支出の原因たる非財務会計行為に重大明白な瑕疵が存すれば、公金の支出は支出原因を欠き違法性を帯びるものと解されるから、このような場合にも住民訴訟の対象となり得るとするのが相当である。
○ そこで、右の基準に照らして、これを本件についてみるに、前記認定のとおり、県による本件検問は不正規流通米の防止をその目的として行われたものであって、本件検問の目的が実質的に見て後行する公金支出に向けられているとは評価できないところであり、また、本件検問の実施は当然にその費用の支出を伴うものであるが、本件検問の実施決定によって、手続上他に何らの支出負担行為を要せず当然に県が公金支出の義務を負担するものとはいえないから、仮に非財務会計行為としての本件検問が違法であっても本件検問費用としての県費の支出が当然に違法となるものではない。村も本件検問に協力して職員等を派遣し、その費用として村費を支出するためには、支出負担行為を要するものと解されるから、仮に本件検問が違法であっても本件検問の費用として村費の支出も当然に違法となるものではない。第二事件原告らは、本件検問と本件検問の費用の支出は、非財務会計行為とそれ自体に要する費用の関係にあるから、両者の関係は密接ないし直接的である旨主張するが、非財務会計行為とそれ自体に要する費用の関係をもって、違法な非財務会計行為を原因とする財務会計行為の違法性を認めることは、地方公共団体の事務のうち多くの事務について住民訴訟によってその違法性を争うことを可能にすることとなるが、かかる結果を住民訴訟制度が予想したものであるかについては、前記の住民訴訟制度の趣旨、目的に照らすと消極的に考えざるを得ず、第二事件原告らの右主張は採用できない。もっとも、前記のとおり、公金支出の原因となる非財務会計行為に重大明白な瑕疵が存すれば、公金の支出はその支出原因を欠き違法性を帯びるものと解されるから、かかる観点から更に本件検問の違法性を以下検討することとする。(以下略)
先行行為と後行財務会計行為の関係について、財務会計行為の原因となる先行行為が財務会計行為を適法に行うための要件となっている場合など前者が後者の直接の原因ということができるような密接かつ一体的な関係であることを要するものとの前提のもと、道路区域変更決定は後行する道路建設工事等の支出の違法原因とはならないとした事例 水戸地判平3.9.17行裁例集42.8・9.1503
(事実関係は下記の通り)
○ 原告らは、本件道路開設事業(本件道路の道路区域変更決定)が種々の理由により違法であるから、本件道路用地の買収、収用及び道路建設工事の各費用支出も違法であるとして、右支出を行ったとする被告らに対し、地方自治法242条の2第1項4号により損害賠償を求めている。
○ 地方自治法242条の2第1項4号の住民訴訟において、地方公共団体の執行機関又は職員がした財務会計上の行為自体に違法がある場合だけでなく、右行為とその執行機関又は職員がした当該財務会計上の行為の原因となる行為との間に一定の関係がある場合には、当該原因となる行為が違法であれば、当該財務会計上の行為も当然に違法となるものというべきであるが、右関係を緩やかに判断するならば、およそ公金の支出を伴う行政作用(このような行政作用が極めて広範かつ多岐にわたるものであることは明らかである。)であれば、その公金の支出の違法を争うことによって、その前提としての行政作用一般を争うことができるようになってしまい、住民訴訟の対象が財務事項に限定されているという原則に抵触することになることに鑑みると、右関係は、少なくとも、当該財務会計上の行為の原因となる行為が財務会計上の行為を適法に行うための要件となっている場合など前者が後者の直接の原因ということができるような密接かつ一体的な関係であることを要するものと解するのが相当である。
○ そこで、これを本件についてみると、道路区域変更決定は、円滑な道路交通の確保及び発達という非財務的見地から行われる道路法18条1項に基づく道路行政上の行政処分であって、この処分により当該道路の敷地等の財産的価値に影響を及ぼすことになるにしても、右処分自体財務会計上の行為ではない上、当該道路開設のためにその用地に対する権原を任意買収あるいは収用裁決により取得したり、道路設備建設のための工事請負契約を締結したりするための適法要件となっているものではないし、その直接の原因でもないというべきであるから、仮に、道路区域変更決定に何らかの違法があるとしても、その違法は道路用地の収用、買収、道路建設工事の各費用支出という公金の支出を違法ならしめるものではないといわなければならない。
○ したがって、本件道路開設事業すなわち本件道路区域変更決定の違法を理由として本件道路用地の収用、買収、道路建設工事の各費用の支出が違法であるとする原告らの主張は採用することができず、原告らの請求はその余の点について判断するまでもなく、失当として棄却を免れないというべきである。
違法な昇給期間短縮の是正として昇給期間延伸で措置したとしても、昇給時期が原状に復したにとどまり違法に昇給された期間の給与支給差額分に係る損害が回復したわけではなく、違法な昇給措置の違法性が失われるものでもないとした事例 東京高判平3.10.15行裁例集42.10.1627
(かねて市においてラスパレイス指数是正のための昇給延伸措置を取っていた上に政府の人勧実施見送りの影響もあり、労使間紛議が生じるおそれがでてきたため、一般職員の昇給を一斉に3ヶ月短縮する特別昇給措置を取ったが、これは給与条例等に定める特別昇給要件を満たすものではなかった。その後当該特別昇給分について一斉の3ヶ月昇給延伸がなされた)
○ 市の給与規則・・・は、給与条例の委任に基づき、「職員の給与の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正(昇給期間の短縮を含む。)を将来に向かって行うことができる。」と定めている。この規定は、国家公務員の俸給の訂正について定めた人事院規則九-八の45条の規定と同趣旨であり、過去の給与の決定に誤りがあった場合に、常に当該決定を遡及的に訂正しなければならないとするのは、給与に関する秩序を混乱させ、職員に不安を抱かせるおそれがあることなどにかんがみ、合理的裁量により、右遡及的訂正をすることなく、将来に向かってのみ効果を及ぼす訂正方法をとり得ることを認めたものである。この趣旨からすれば、本件のように昇給期間を短縮して昇給の発令及び給与の支給をしたことが違法とされる場合に、その遡及的取消に代えて、法的根拠のある範囲内で次期以降の昇給を延伸する方法により、将来に向かって違法の是正を図ることも、必ずしも給与条例の禁止するところではないと解するのが相当である。
○ しかし、違法な給与の支給によって現実に市に損害が発生している以上、単に将来に向かって違法が是正された(すなわち、昇給延伸措置についでいえば、これにより次期以降の昇給発令が本来のあるべき時期に戻った)というだけでは、過去の給与支給の違法性が治癒されるということはできない。当該の是正措置が具体的状況下で行政の自主的になし得る精一杯のものであったとしても、当然には治癒されない。少なくとも市に生じた違法な損害が実質的に回復されたと評価し得る程度に違法支出が補填されて初めて、右違法性の治癒を論ずる余地が生じるものというべきである。
○ しかるところ、引用にかかる原判決の認定事実によれば、本件昇給延伸措置は、昇給期間を3か月短縮した本件昇給を前提として、その1年後に予定されていた次期昇給を3か月間延伸するというものであるから、次期及びそれ以降の昇給に関しては、本件昇給をいわば帳消しにし、本件昇給がなかったと同じ状態に戻したものということができるが、本件昇給によって既に職員に支給された3か月間の違法昇給分の損害までを回復させるものではないというべきである。これを具体的にいうと、本件昇給がなければ昭和58年4月1日に昇給する予定であった職員の場合、本件昇給により同年1月1日に昇給し、その後もそれを前提とすれば毎年1月1日に昇給することが予定されていたところ、本件昇給延伸措置によって昭和59年1月1日に予定されていた昇給が同年4月1日まで延伸されたのであるが、このことは、右職員について違法な本件昇給がなかった場合の本来の昇給予定時期どおりに昇給がなされる状態が回復されたにとどまり、昭和58年1月から同年3月までの間支給された違法昇給分は右職員に支給されたままであり、それによる市の損害は何ら回復されていないことになる。
○ 被控訴人は、本件昇給延伸措置は本件昇給を取り消さないで行われたものであるから、本件昇給を前提として1年後の次期昇給時期が決められるのであり、本件昇給延伸措置により右昇給時期が3か月延伸されたことによって市がその分の支出を免れ利得にあずかったことになるので、これによって本件昇給による市の損害は回復された旨主張する。しかし、右主張は次の理由により採用することができない。市の給与条例・・・は、「職員が現に受けている給与の号給を受けるに至ったときから12月・・・を下らない期間を良好な成績で勤務したときは、その者の属する職務の等級における給与の幅の中において直近上位の号給に昇給させることができる。」と定めているが、この規定をもって、昇給時から1年を経過すれば次期昇給を請求できる権利を職員に与えたものと解することはできないし、他に職員が市に対して昇給請求権を有することを認めるべき根拠は見出せない。したがつて、本件昇給が取り消されず、又は法律上取消不能の状態になったとしても、本件昇給時から1年を経過した時期に次期昇給をさせることが職員に対する市の法律上の義務であるとすることはできない。それゆえ、3か月間の本件昇給延伸措置により、あたかも市が支給義務を負うべき次期昇給3か月分の支出を免れ利得をしたかのようにいう被控訴人の主張は法的根拠を欠くといわざるを得ない。のみならず、本件昇給の取消がなされなかったからといって、その違法性が失われるわけではないから、違法な本件昇給を前提として1年後に次期昇給が行われれば、その次期昇給もまた3か月短縮された分が違法たるを免れず、その分の損害を更に市に生じさせることになる。本件昇給延伸措置は、右の本件昇給を前提とした次期昇給による違法支出を防止するにとどまるものであり、本来違法として禁じられる支出をしないだけのことであるから、市にとって支出を免れることによる利得が生じるとする余地はない。被控訴人の主張するように、本件昇給延伸措置によって支出しなくなった次期昇給の3か月分が本件昇給による損害の回復に充てられたということは、結局、右3か月分相当額を次年度から支出して前年度の本件昇給による損害を補填したというに等しく、その結果、本件昇給による損害は観念上回復されたことになるとしても、その分だけ次年度の違法な損害として現れることになり、それ以降も同じ手法で実質的に当初の違法昇給による損害が順次後年度に繰り越されていくことになる。このような形式的、観念的な操作によって本件昇給による損害そのものが補填されたと認めることは、地方公共団体の利益の実質的保護の見地からも到底是認し難いといわなければならない。被控訴人の主張は採用できない。
○ 以上のとおり、本件昇給により市に生じた損害については、本件昇給延伸措置によっても何ら回復されていないというほかないのであり、それでもなお本件昇給の違法性が消滅したとするのを相当とすべき特段の事情があるとは認められないから、本件昇給延伸措置による違法性の治癒を肯定することはできない。
首長は、少なくとも条例の違法性が重大かつ明白な場合においては当該条例を執行すべき拘束を受けないものと解するのが相当であり、首長がそのような条例の規定に基づいて公金の支出をしたときは、それに固有の違法が認められない場合であっても条例の違法性を承継し、違法な公金の支出となるとの判断枠組みを示した事例 大阪高判平4.3.24行裁例集43.3.492
(違法な条例により特別職の職員等に期末手当を支給したとして首長個人に損害賠償を求める住民訴訟)
○ 地方自治法176条4項以下の規定等に照らせば、普通地方公共団体の長は、少なくとも、条例の違法性が重大かつ明白な場合においては、当該条例を執行すべき拘束を受けないものと解するのが相当であり、したがって、長が当該条例の規定に基づいてした公金の支出は、それに固有の違法が認められない場合であっても、右条例の違法性を承継し、違法な公金の支出となるものというべきである。
○ そうとすれば、条例が違法であることを理由として、右条例に基づく普通地方公共団体の長の財務会計上の行為につき住民が地方自治法242条の2の訴えを提起した場合においても、右訴えを当然に不適法として却下すべきものではなく、右支出行為の違法性について本案の審理をなすべきものである・・・
【最高裁判例】 地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づく代位請求に係る当該職員に対する損害賠償請求訴訟において、右職員に損害賠償責任を問うことができるのは、先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても右原因行為を前提としてされた右職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られる 【一日校長事件】 最判平4.12.15民集46.9.2753
(教育委員会が、勧奨退職に応じた教職員に対し、退職日に教頭から校長に昇任させ特別昇給を行い、これを受けて知事が、昇給後の号給を基礎に算定した退職手当を支給した)
○ 地方自治法242条の2の規定に基づく住民訴訟は、普通地方公共団体の執行機関又は職員による同法242条1項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実の予防又は是正を裁判所に請求する権能を住民に与え、もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とするものである(最高裁昭和51年(行ツ)第120号同53年3月30日第一小法廷判決・民集32巻2号485頁参照)。そして、同法242条の2第1項4号の規定に基づく代位請求に係る当該職員に対する損害賠償請求訴訟は、このような住民訴訟の一類型として、財務会計上の行為を行う権限を有する当該職員に対し、職務上の義務に違反する財務会計上の行為による当該職員の個人としての損害賠償義務の履行を求めるものにほかならない。したがって、当該職員の財務会計上の行為をとらえて右の規定に基づく損害賠償責任を問うことができるのは、たといこれに先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、右原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解するのが相当である。
○ ところで、地方教育行政の組織及び運営に関する法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱いその他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めるものであるところ(1条)、教育委員会の権限について同法の規定するところをみると、同法23条は、教育委員会が、学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止、教育財産の管理、教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事などを含む、地方公共団体が処理する教育に関する事務の主要なものを管理、執行する広範な権限を有するものと定めている。もっとも、同法は、地方公共団体が処理する教育に関する事務のすべてを教育委員会の権限事項とはせず、同法24条において地方公共団体の長の権限に属する事務をも定めているが、その内容を、大学及び私立学校に関する事務(1、2号)を除いては、教育財産の取得及び処分(3号)、教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の締結(4号)並びに教育委員会の所掌に係る事項に関する予算の執行(5号)という、いずれも財務会計上の事務のみにとどめている。すなわち、同法は、地方公共団体の区域内における教育行政については、原則として、これを、地方公共団体の長から独立した機関である教育委員会の固有の権限とすることにより、教育の政治的中立と教育行政の安定の確保を図るとともに、他面、教育行政の運営のために必要な、財産の取得、処分、契約の締結その他の財務会計上の事務に限っては、これを地方公共団体の長の権限とすることにより、教育行政の財政的側面を地方公共団体の一般財政の一環として位置付け、地方公共団体の財政全般の総合的運営の中で、教育行政の財政的基盤の確立を期することとしたものと解される。
○ 右のような教育委員会と地方公共団体の長との権限の配分関係にかんがみると、教育委員会がした学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関する処分(地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条3号)については、地方公共団体の長は、右処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合でない限り、右処分を尊重しその内容に応じた財務会計上の措置を採るべき義務があり、これを拒むことは許されないものと解するのが相当である。けだし、地方公共団体の長は、関係規定に基づき予算執行の適正を確保すべき責任を地方公共団体に対して負担するものであるが、反面、同法に基づく独立した機関としての教育委員会の有する固有の権限内容にまで介入し得るものではなく、このことから、地方公共団体の長の有する予算の執行機関としての職務権限には、おのずから制約が存するものというべきであるからである。
・・・
○ そして、以上の事実関係並びに原審の適法に確定した本件昇格処分及び本件退職承認処分の経緯等に関するその余の事実関係の下において、本件昇格処分及び本件退職承認処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものとは解し得ないから、被上告人としては、○教育委員会が行った本件昇格処分及び本件退職承認処分を前提として、これに伴う所要の財務会計上の措置を採るべき義務があるものというべきであり、したがって、被上告人のした本件支出決定が、その職務上負担する財務会計法規上の義務に違反してされた違法なものということはできない。
【最高裁判例】 条例根拠のない昇格昇給措置について、事後的に遡及適用のある条例措置がなされた場合は、前記の違法は治癒される 最判平5.5.27集民169.87
(町長は、町職員の給与が他団体より低く、これは条例等に定める基準での初任給決定時の前歴計算等が行われていなかったとの認識のもと、基準にのっとって初任給が決定されていた場合における職員のあるべき給料額と現実に支給されている額との差額につき分割して昇給昇格を実施することにより3年間程度をかけてあるべき給料額にまで改善を図ることとし、増額給与の支給をしたが、この昇給措置は条例所定の昇給条件とは異なるものであった。その後給与条例が改正され、改正附則において上記増額措置を遡及的に認める条項が設けられた)
○ 改正条例が、○年4月1日にさかのぼって本件特別調整と同じ目的で昇給の特例措置を採る権限を町長に付与するとともに、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与を改正後の条例の規定による給与の内払いとみなすものとしていることからすれば、町議会は、改正条例の制定によって、上告人のした本件特別調整及びこれに基づく増額給料分の支給の各行為自体を是認し、これをさかのぼって適法なものとしたものと解するのが相当である。そうすると、右改正条例が制定、施行された後においても、なお上告人について、増額給料分の各支給時から改正条例の公布施行の日の前日までの間の運用利息相当額の町に対する損害賠償義務があるとすることはできないというべきである。
○ 地方自治法242条の2第1項1号の請求は、行為の差止めを求めるものであるから、その行為がいまだ行われていないことが前提となる。これに対応する同法242条の監査請求は、当該行為を防止するため必要な措置を講ずべきことを求めるものであって、この請求は、同条1項かっこ内において当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含むとされていることにより、このような条件がある場合にのみ行うことができるものと解される。したがって、この監査請求に対応する訴えも、このような条件がある場合にのみ行うことができるものと解すべきことになる。そして、右にいう当該行為とは、住民訴訟においては、公金の支出等同条1項に列記された財務会計上の行為のうち違法なものをいうのであるから、同法242条の2第1項1号の請求による差止めの対象となる行為も違法な行為でなければならないこととなる。以上を要するに、同号の差止めの請求は、ある財務会計上違法な行為がなされることが相当な確実さをもって予測される場合でなければ行うことができないということになる。
○ 本件においては、本件児童遊園を廃止する条例が可決されており、その廃止は、甲土地を第三者に売却し、乙土地を第三者から購入して、本件児童遊園を甲土地から乙土地へ移転することを目的として行われるものであることは当事者間に争いがないから、いずれ本件行為が行われることは相当の確実さをもって予測される場合であるということができる。そこで、問題となるのは、本件行為が違法なものとして行われることが相当の確実さをもって予測されるかどうかである。
○ 原告が、本件行為の違法事由として主張するもののうち、本件児童遊園の移転に公益上の必要性のないことをいう分は、公園の設置目的に即した管理ないし維持という財務会計とは別個の行政目的の達成の有無の問題であるから、そのような違法があると主張して本件行為の差止めを求めることは、住民訴訟として行うことができないものというべきである。
○ そうすると、原告が、本件行為の違法事由として主張するもののうち、住民訴訟として意味のあるのは、被告が甲土地の評価額を現実の価額より著しく低廉に評価し、一方乙土地のそれを高額に評価して、両土地の客観的な価額が均衡を失していることを問題とする分であることとなる。
○ 《証拠略》によれば、児童遊園の設置、取得及び変更・廃止は、A区土木部土木管理課(施設管理係及び道路認定係)が所管するが、行政財産である用地の処分及び取得は総務部経理課が所管していることが認められる。そして、《証拠略》によれば、被告がA区の執行機関として甲土地の売却と代替地である乙土地の買取りを行う場合において、被告がそれら不動産売買契約の内容となる売却・買取価格を、地方自治法237条2項に規定する適正価格で行うため手続は次のとおりであることが認められる。まず、総務部経理課によって相手方との折衝や価格検討等の事務手続が行われ、被告において一応妥当と思われる額の原案を決定する。被告はそのうえで、A区財産価格審議会条例によって設置されているA区財産価格審議会に諮問し、その答申を受けて、契約の内容となる価格を決定する。そして、《証拠略》によれば、本件において業者に甲乙両土地の不動産価格の鑑定を委託したのはA区土木部であり、廃止条例の施行期日はいまだ決定されておらず、甲土地は、現在でも児童遊園として公共の用に供されA区土木部によって管理されている行政財産であり、売却の対象として総務部に所管が移されているわけではなく、もちろん右審議会に適正価格について諮問がされているわけでもないことが認められる。
○ 以上によれば、甲乙両土地については、いまだこれを売却・購入するについてよるべき価額がおよそ決定されていない段階に止まっているものというほかはない。そうであるとすれば、価格の決定のない物件についてその評価が低廉であるとか価額が均衡を失するとかいうことが生じることはありえないから、本件行為が違法に行われることについては、それが相当の確実さをもって予測される場合であるとは認め難い。したがって、現時点においては、本件行為を対象としてその差止めを求める住民訴訟を提起する要件が欠けるといわなければならない。
議会の議決なく負担付き寄附を受納した後に寄附の一部を返納することとなった場合において、返納直前に事後的になされた負担付き寄附の受納議決により前記の議決の欠缺は治癒したとした事例 奈良地判平6.3.30判例地方自治129.40
(特定目的以外に使用した場合は寄附金を返納するという負担付き寄附を議会の議決なく受納した(昭和63年)。寄附の一部は後日寄附者に返還され、議会の寄附受納議決は返還の直前に事後的になされた)
○ 本件寄附は、右のとおり負担付きであるところ、当初は(地方自治)法96条1項9号の議決がないため無効であったが、平成2年12月21日に前記の議決がされたことにより、その瑕疵が治癒され、遡及的に有効となったと解される。
○ したがって、本件寄附金のうちの・・・万円は、○会に補助金として使用されないときは被告会社に返還すべきものであり、平成2年12月21日、・・・万円を償還金として追加する旨の平成2年度第○回補正予算案が議決されているから、本件公金支出は適法である。
米国で追徴課税を受けた会社に対し租税条約による日米合意の結果国税(法人税)の減額更正がなされ、これを受け地方税(法人住民税、事業税等)の減額がされた事案において、予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が地方税の減額更正処分にあると認められる場合でない限り、国税の減額更正処分と地方税の減額更正処分を直接結合して違法性の承継を認めるべきではないとした事例 横浜地判平7.3.6判例時報1574.62
(市に法人住民税を納付する企業の米国子会社に対し米国が所得税の追徴課税を行い、日米租税条約による日米合意により同社の日本での所得税還付を行うこととなり、税務署長が法人税の減額更正処分をして減額分を還付、ついで法人住民税、事業税等の減額更正を申し立て、関係自治体から還付を受けた。本訴訟は地方税に関する更正処分が違法であることなどを理由に、その各処分の取消し(地方自治法242条の2第1項2号)を求めるとともに、同企業に対し、違法な更正処分により得た地方税の還付金が不当利得に当たるとしてのその返還(同項4号)を請求している。当審は上記日米合意は適法かつ有効に成立と判断)
○ 原告らは、本件国税処分の違法を前提に、それが本件更正処分に承継されると主張するが、右国税処分と本件更正処分とはそれぞれ別個の機関によりされた別個の処分であるから、同更正処分の取り消し請求においては、当該更正処分それ自体の違法事由をまず問題にすべきであり、地方自治法上の住民訴訟である以上、その制度目的からして、予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵がその更正処分にあると認められる場合でない限り、両者を直接結合して違法性の承継を認めるべきであるとするわけにはいかず、この点は、被告A社及び同B社に対する代位請求においても同様に解すべきである。また、被告らは、本件の住民訴訟においては、地方公共団体の権限に属しない本件国税処分の適否は、その判断の対象とはなり得ないとするが、国税処分による法人税の税額を課税標準とする本件更正処分ついて、予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵があると認められる場合には、直接ではないとしても右国税処分が審理の対象とされることもあり得ないわけのものではないと解される。
適正対価によらない市有財産譲渡につき議会の議決を経ていたとしても、首長の裁量を著しく逸脱し、または不法行為が成立すると認められる場合は、首長の財産譲渡についての違法性は阻却されないとした事例 奈良地判平7.7.19判例地方自治145.11
(市有地を議会の議決を経た後民間企業に相当安価な額で売り渡した。前記議決の際の議会での市当局の説明には虚偽があった)
○ 適正な対価によらない財産の譲渡又は貸付けは、当該普通地方公共団体が財産の運営上損失を蒙り、その財政破錠の原因となって住民の負担を増加させ、あるいは、特定の者の利益のためにその運営が歪められることとなり、地方自治を阻害する結果となる虞がある。そこで、(地方自治)法96条1項6号、237条2項は、普通地方公共団体の財産の市場価格以外による譲渡について、当該対価による財産の譲渡の必要性及び妥当性の審査、すなわち、当該対価による譲渡が当該普通地方公共団体の利益になるか否か、普通地方公共団体が財産的損害を受けることにならないか否か、当該譲渡が当該普通地方公共団体の財政にどのような影響を与えることとなるか、当該譲渡の対価が適切なものか否か等の地方自治的な政策判断の審査を住民を代表する議会で受けた上、その許可を経なければ譲渡ができないとしたものである。右の市場価格以外での譲渡の危険性に対する立法趣旨及び地方自治体の長は議会の議決の単なる執行者ではないことからすると、普通地方公共団体の財産の市場価格以外での譲渡が普通地方公共団体の長の裁量を著しく逸脱したと認められるか又は不法行為が成立すると認められる場合には、たとえ譲渡につき議会の議決があったとしても、その長の行為の違法性が阻却されるわけではなく、長の行為に加担し共同不法行為が成立する者に対する関係においても違法性は阻却されない。
○ しかも、法96条1項6号、237条2項の右立法趣旨からすると、地方議会における当該対価による財産の譲渡の必要性及び妥当性の審査に重大な瑕疵がある場合には、当然に違法性が阻却されることはありえない。
○ 本件土地の譲渡の議決については、前記・・・のとおり、議会において、市長側に譲渡の相手方、低廉譲渡する理由のいずれにも虚偽ないし重大な説明義務違反があり、しかも、転売禁止条項や用途指定が付されているのに何ら遵守されていないことからすると、M(市長)及びO(助役)はもとより、被告Y建設に対する関係でも、本件議決には重大な瑕疵があり、本件譲渡は適法な議決によっていないというべきであるから、本件土地の譲渡に関する違法性は阻却されない。
【最高裁判例】 市が職員に民間団体への出向派遣を発令し派遣者の給与負担をした場合(派遣法制定前)、派遣者が派遣先の事務に専念しつつ派遣元の市が職員の給与全額を負担するには、適法な職務専念義務免除に加え給与条例所定の勤務しないことについての適法な承認が必要であるところ、これは処分権者がまったく自由に行い得るものではなく、地方公務員法30条、35条や24条1項の趣旨に反しないものでなければならない 最判平10.4.24集民188.275
(市は職員を市商工会議所専務理事に派遣し派遣中の給与全額を負担した(当時は派遣法制定前)。派遣職員は派遣中、商工会議所の事務に専念し、市の事務は行っていない。本件は給与支給を対象事項として市長・商工会議所を被告とする住民訴訟)
○ 地方公共団体の職員の給与は条例で定めなければならないとされている(地方自治法204条3項、地方公務員法24条6項)ところ、本件給与条例・・・は、勤務しない時間に対する給与支給の可否について、「職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合・・・を除く外、その勤務しない1時間につき・・・に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。」と規定している。また、地方公務員法35条にいう特別の定めとして制定された本件免除条例は・・・職務専念義務の免除の要件を定めている。しかるところ、前記事実関係によれば、本件派遣職員はその派遣期間中市自身の事務に従事していないのであるから、本件免除条例に基づく適法な職務専念義務の免除が必要であることはもちろんであるが、これに加えて、市が本件派遣職員に対して給与全額を支給するためには、本件給与条例・・・に定める勤務しないことについての適法な承認が必要であると解すべきである。そして、被上告人(市長)は、被上告人会議所との間で本件協定を締結した上、本件派遣職員に対し、派遣命令を発するとともに、本件免除条例・・・に基づき本件職務専念義務の免除をし、派遣期間中の給与を支払ったというのであるから、本件職務専念義務の免除とともに、本件給与条例・・・の承認(以下「本件承認」という。)がされたことがうかがわれ、原審も、このことを前提として判断しているものと解される。
○ そこで、本件職務専念義務の免除及び本件承認の適否について検討すると、本件免除条例・・・及び本件給与条例・・・は、職務専念義務の免除や勤務しないことについての承認について明示の要件を定めていないが、処分権者がこれを全く自由に行うことができるというものではなく、職務専念義務の免除が服務の根本基準を定める地方公務員法30条や職務に専念すべき義務を定める同法35条の趣旨に違反したり、勤務しないことについての承認が給与の根本基準を定める同法24条1項の趣旨に違反する場合には、これらは違法になると解すべきである。そして、本件においては、本件派遣の目的、被上告人会議所の性格及び具体的な事業内容並びに派遣職員が従事する職務の内容のほか、派遣期間、派遣人数等諸般の事情を総合考慮した上、本件職務専念義務の免除については、本件派遣のため本件派遣職員を市の事務に従事させないことが、また、本件承認については、これに加えて、市で勤務しない時間につき給与を支給することが、右各条項の趣旨に反しないものといえるかどうかを慎重に検討するのが相当である。
○ 以上の観点から本件をみると、本件派遣の目的が、前示のように被上告人会議所との連携を強めることにより市の不振な商工業の進展を図るためのものであったとしても、本件職務専念義務の免除及び本件承認を適法と判断するためには、右目的の達成と本件派遣との具体的な関連性が更に明らかにされなければならないのであって、そのためには、被上告人会議所の実際の業務内容がどのようなものであって、それが市の商工業の振興策とどのような関連性を有していたのか、本件派遣職員の被上告人会議所における具体的な職務内容がどのようなものであって、それが市の企図する商工業の振興策とどのように関係していたのかなどの諸点について、十分な審理を尽くした上、市の右行政目的の達成のために本件派遣をすることの公益上の必要性を検討し、これらに照らして、本件職務専念義務の免除及び本件承認が前記各条項の趣旨に反しないかどうかを判断する必要があるといわなければならない。原審は、前記諸点について何ら具体的な認定をすることなく、前示のように、被上告人会議所と市の置かれていた一般的状況、商工会議所の法的性質、専務理事の一般的な職務権限等から、本件職務専念義務の免除が裁量権の逸脱、濫用にわたるものとまでは断じ難く、本件給与支出を違法とすることはできないと判断しているが、右のような事実のみをもってしては、いまだ本件職務専念義務の免除及び本件承認の適否を判断するには足りないといわざるを得ない。
財務会計行為の違法事由として、その原因ないし前提となった非財務会計行為の違法性を主張できるのは、当該財務会計行為の原因ないし前提となった非財務会計行為が当該財務会計行為を適法に行うための要件となっている場合など前者が後者の直接の原因ということができるような密接かつ一体的な関係にある場合であることを要することを前提とし、都市計画変更の違法は工事請負契約等の後行財務会計行為に継承されないとした事例 富山地判平10.6.10判例地方自治186.94
(都市計画事業の計画変更が違法であるとして、都市計画施設の工事費支出差止めを求める1号訴訟)
○ そもそも住民訴訟の対象とされる財務会計上の行為の違法事由としてもその原因ないし前提となった非財務会計上の行為の違法性を主張できるかについては、これをすべての場合に肯定すると、ほとんどの行政行為等には経費が必要であって、支出や債務の負担等の財務会計上の行為を伴うから、これらの財務会計上の行為をとらえ、支出や債務の負担等の原因ないし前提となった行政行為等が違法であるからその支出や債務の負担等も違法であるとして住民訴訟を提起することにより、地方自治法で定められた形態の財務会計上の行為についてのみその違法を是正することを目的とする住民訴訟において、実質的に非財務会計上の行為の違法性を争うことができることになる。そうすると、結局ほとんどの行政行為等が住民訴訟の対象となることとなって、より厳しい要件の下でしか認められない事務監査の請求を住民訴訟によってすることができることにもなり、住民が納税者の立場から、普通地方公共団体がその機関の違法な財務会計上の行為によって損害を被ることを防止し、あるいは、普通地方公共団体の被った損害を回復する手段として住民訴訟の制度を設け、これによって普通地方公共団体が適正な財務会計処理を行うことを保障することとした地方自治法の趣旨に反することになる。そして、右の地方自治法の趣旨からすると、財務会計上の行為の違法事由として、その原因ないし前提となった非財務会計上の行為の違法性を主張できるのは、当該財務会計上の行為の原因ないし前提となった非財務会計上の行為が当該財務会計上の行為を適法に行うための要件となっている場合など前者が後者の直接の原因ということができるような密接かつ一体的な関係にある場合であることを要すると解するのが相当である。
○ したがって、本件都市計画の変更及び本件都市計画事業の事業計画の変更の手続が都市計画法に違反し違法であるとした場合、右手続の違法性が本件工事に係る工事費用等の支出に承継されるか否かは、右手続が本件工事に係る工事費用等の支出を適法に行うための要件となっている場合など右手続が本件工事に係る工事費用等の支出の直接の原因ということができるような密接かつ一体的な関係にあるか否かによることになる。
○ そこで、都市計画ないしその変更及び都市計画事業の事業計画ないしその変更の手続と、都市計画施設に係る工事請負契約の締結ないし工事費用等の支出との関係について検討する。
○ 都市計画とは、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画」(都市計画法4条1項、以下括弧内においては、都市計画法のことを「法」と呼称する。)をいい、「農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきこと」(法2条)を基本理念として定められるものであり(例えば、下水道等の都市施設は、法13条1項6号により「土地利用、交通等の現状及び将来の見通しを勘案して、適切な規模で必要な位置に配置することにより、円滑な都市活動を確保し、良好な都市環境を保持する」という都市計画基準に適合するよう定められる。)、将来における都市施設の整備等に関する基本的事項につき一般的、抽象的に定めた都市の基本計画にとどまるものである。また、都市計画事業とは、「都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発事業」(法4条15項)をいうところ、都市計画において施行区域が定められた市街地開発事業はすべて都市計画事業として施行する必要がある(土地区画整理法3条の5、都市再開発法6条等)のに対して、都市計画施設の設置は、都市計画事業として施行することにより簡便な用地取得の制度等が認められる(法67条、69条ないし73条)が、既に事業に必要な土地を取得しているため新たに土地を収用する必要のないもの等については必ずしも都市計画事業として施行する必要はないと解される。さらに、都市計画事業の事業計画においては、事業地、設計の概要、事業施行期間が定められる(法60条2項)ところ、都市計画ないしその変更が認可されると、事業地内における都市計画事業の施行の障害となるおそれがある建築物の建築等は都道府県知事の許可を要することになる(法65条1項)など、事業地内の土地所有者の権利義務に対して具体的な変動がもたらされるが、反面において、都市計画施設の設置に係る工事請負契約の締結等が義務づけられるなどの法的効果は生じない。そして、都市計画法21条は都市計画の変更について、同法63条は事業計画の変更について規定しているが、前記都市計画及び事業計画の性質に変更を加えるものではない。
○ 以上からすると、都市計画施設に係る工事請負契約の締結は、必ずしも都市計画法に根拠を有することが要求されるわけではないし、都市計画ないしその変更及び都市計画事業の事業計画ないしその変更の手続が都市計画施設に係る工事費用等の支出を適法に行うための要件となっているわけではないから、都市計画に係る工事請負契約の締結ないし工事費用等の支出(財務会計上の行為)と都市計画ないしその変更及び都市計画事業ないしその変更の手続(非財務会計上の行為)との間に密接かつ一体的な関係があるとは認められないというべきである。
○ したがって、仮に本件都市計画の変更及び本件都市計画事業の事業計画の変更の手続が都市計画法に違反し違法であるとしても、そのことにより本件工事に係る請負契約の締結及び本件工事に係る工事費用等の支出が違法となるものではないというべきである。
懲戒事由たる非行のある職員からの辞職申出を承認し退職手当を支払った事例において、退職承認の処分権者と退職手当の支給権者がいずれも市長に帰属するところ、首長は業務誠実執行義務を負うのだから、支出の原因行為たる処分を首長自らが取り消し得る権限を有している場合は、その原因行為が違法であれば、首長はそれを取り消すべきであり、これをしないで財務会計行為を行った場合は、当該財務会計行為は違法となるとの判断枠組みを示した事例 大阪高判平10.12.11判例地方自治199.22
(市の総務局長たる幹部職員が公費で私的飲食等を行っていた。そのうちの一部が報道されたが、疑惑の確証は得られなかった。当該職員は市の他の幹部職員の不正に関する人事総括者としての責任およびみずから疑惑を招いたことに対する責任として辞職を申し出て、市長はこれを承認し、退職手当を支払った。当該職員は私的飲食の代金の一部しか市に返還していない)
○ 地方自治法242条の2第1項4号前段の規定に基づく代位請求に係る当該職員に対する損害賠償請求訴訟は、財務会計上の行為を行う権限を有する当該職員に対し、職務上の義務に違反する財務会計上の行為による当該職員の個人としての損害賠償を求めるものであるから、当該職員の財務会計上の行為をとらえて右の規定に基づく損害賠償責任を問うことができるのは、たといこれに先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、右原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解するのが相当である。もっとも、本件においては、右原因行為たる本件処分の権限と当該財務会計上の行為たる本件退職手当支給行為(正確には支出負担行為)に係る権限とは、いずれも市長に帰属しているが、このような場合、普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体に対して、その事務を誠実に執行すべき職務上の義務を負い(地方自治法138条の2)、右誠実執行義務もまた、財務会計法規上の義務の一内容を成すものというべきであるから、原因行為である行政処分について、長がこれを取り消しうる権限を有している場合には、右原因行為が違法なものであれば、長はこれを取り消すべきものと解され、これをしないで当該財務会計上の行為を行ったときには、右財務会計上の行為は違法となる。
国の水資源開発基本計画に基づき実施される事業の負担金に充てるため県が一般会計から公営事業会計へ長期貸付等で公金を支出した事案について、原因行為の違法の結果本件貸付けそれ自体が財務会計法規上の義務に違反することとなった事実に関する主張がないまたはその主張に理由がなく、また前記計画は違法であり本件貸付けもその違法性を承継しているから違法であるとする原告の主張は、実質的に県とは独立した機関である国の基本計画決定自体を争うに等しく、抗告訴訟制度ないし住民訴訟制度の目的を逸脱するものであるとした事例 名古屋地判平13.3.2判例地方自治217.29
(県が国の水資源開発基本計画に基づき実施されるA川河口堰建設事業の負担金に充てるために一般会計から工業用水道事業会計(公営事業会計)へ長期貸付け等の方法により公金を支出することが違法であるとする住民訴訟)
○ 原告らは、本件貸付けが違法であることの根拠として、本件基本計画自体が違法であり、その違法性がその後の本件実施計画、県による本件負担金を負担する旨の同意、本件負担金の支払方法の決定、同決定に基づく本件負担金の納付通知ないし本件貸付けへと承継されることを挙げる。しかしながら、住民訴訟において、当該職員に対して損害賠償を問うことができるのは、先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、上記原因行為を前提としてなされた財務会計行為それ自体が財務会計法規上の義務に違反する違法な場合に限られるというべきであり(最高裁平成4年12月15日第3小法廷判決・民集46巻9号2753頁参照)、この理は、法242条の2第1項1号の差止請求についても同様であると解され、これに反する原告らの主張は採用できない。
○ 本件においては、財務会計行為である一般会計から工業用水道事業会計への長期貸付金の交付である本件貸付けそれ自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものといえるかが検討されなければならない。しかるに、原告らは、本件基本計画の違法(その違法は、将来の水需要を誤ったというものであり、財務会計上の違法でないことは明らかである。)が、その後の本件負担金の負担の同意や本件負担金の納付通知へ承継されたとして、先行する原因行為(本件貸付けの原因行為は、本件負担金の支払の必要と工業用水道事業会計に本件負担金の支払原資がなかった事実であり、本件負担金の支払のみが原因行為ではないが、この点はひとまず措くこととする。)の違法を主張するだけで、原因行為の違法の結果、本件貸付けそれ自体が財務会計法規上の義務に違反することとなった事実を具体的に主張しない。原告らの主張中には、本件基本計画は違法であるから、これによって本件負担金の支払義務が生じることはないとの主張があるが、本件負担金債務は・・・本件堰の建設のために現実に要した費用を治水分と利水分に分けて国、都道府県及び流水の利用者で分担するという目的の下に県が負担したことにより発生したものであるから、本件基本計画の違法により直ちに本件負担金債務が発生しなくなるという原告らの上記主張には法論理上飛躍があり、にわかに採用し難く、これを根拠とする本件貸付けの違法の主張は理由がない。仮に、原因行為の違法が財務会計行為の違法につながる余地があるとしても、原因行為である非財務会計行為が国の行政機関や当該普通地方公共団体における行政組織上独立の権限を有する機関により、その権限に基づいてなされた行政処分その他の行為である場合には、一定の要件を満たした場合にのみ当該行為の効力を争うことを認めている抗告訴訟制度(行政事件訴訟法3条)に抵触することになるだけでなく、住民訴訟という枠の中で国の行政活動一般をも対象とすることになるものであって、住民訴訟の目的を著しく逸脱するものである。
○ これを本件についてみるに、本件基本計画は、促進法4条に基づき、内閣総理大臣が決定するものであるところ、原告らが同計画は違法であり、本件貸付けもその違法性を承継しているから違法であるとして本件貸付けの適法性を争うことは、実質的にみて、住民訴訟である本件訴訟において内閣総理大臣が行った本件基本計画の計画決定を争うものであって、明らかに住民訴訟の目的を逸脱するものであるといわざるを得ない。この点においても、原告らの主張は失当というべきである。なお付言するに、原告らは本件基本計画の違法事由として、同計画における将来の水需要の予測が著しく誤っていることを主張するのみであるが、かかる主張は国が行う同計画を含んだB水系における水資源開発政策の当否を問題にしているにすぎないというべきであって、本件基本計画の違法事由とはならないものであり、この意味でも失当である。
自治体が応訴した事件に関する和解をすべて首長の専決事項とする議決は違法無効であるが、34年前の同議決についてこれまでこれを適法とし疑義等が生ずることなく運用されるなどの事情からすればこの違法が一義的明白に違法とはいえない以上、同議決にもとづきなされた応訴事件の裁判上の和解について首長は損害賠償責任を負わず、また事後の議会の承認により本件和解の瑕疵は治癒されたとした事例 東京高判平13.8.27判例時報764.56
(東京都は応訴事件の和解はすべて専決事項とするとの34年前の議決に基づき、裁判上の和解をして和解金を支払った。したがって本件和解に関する個別の都議会の事前議決は経ていない)
○ ところで、(地方自治)法96条1項12号は、普通地方公共団体が行う訴訟上の和解については議会の議決を要するものと規定している。これは、普通地方公共団体が、紛争の一方当事者として、民事上の紛争を解決するについては、その紛争解決手段及び内容が地方公共団体の利害及び権利義務関係に重大な影響を及ぼす場合があることにかんがみ、当該和解の可否自体を議会が決するよう定めているものと解される。なお、和解は、長その他の執行機関による和解交渉が行われることが前提となるのであるから、同条項の議会の議決の法的性質は、当該和解に関する地方公共団体の意思を決定し、長その他の執行機関にその和解締結権限を付与するものと解される。
他方、法180条1項は、普通地方公共団体の議会は、議会の権限に属することであっても、軽易な事項については、議会の議決により特に指定して、普通地方公共団体の長の専決処分にゆだねることができるものと規定している。
○ したがって、上記…の事実関係からすれば、都議会は、都が応訴する訴訟事件に係る和解が法180条1項にいう軽易な事項に当たるものとして、同条に基づき、これを特に知事の専決処分にゆだねる旨の本件議決をしたものと認められる。
○ ところで、訴訟上の和解とは、互いに争っている訴訟当事者が、裁判所が間に入った話し合いにより、互いに譲歩してその間に存在する紛争を解決する合意をし、この合意に基づいて、確定判決と同一の執行力などが与えられる裁判所の和解調書が作成されて訴訟が終了することである。このような訴訟上の和解は、主として当事者間の交渉により行われ、判決と比較して、紛争の一刀両断的な解決を回避でき、実定法の枠にとらわれない新たな救済方法を創造できるという紛争解決上の利点を有するなどといわれている。そうすると、訴訟上の和解の内容は、紛争の性質や内容に応じて多種多様であるということができる。また、普通地方公共団体が行う訴訟上の和解についてみても、当該和解が当該普通地方公共団体の利害及び権利義務関係に重大な影響を及ぼすか否かは、請求の当否に関する法的な見通しのほかに、行政の目的、現実の社会的要請等の諸要素を考慮せざるを得ないため、多岐にわたる事項についての複雑な判断によらざるを得ないものと考えられる。そうすると、どのような訴訟上の和解が法180条1項にいう軽易な事項に該当するか否かの判断は、第一次的には当該普通地方公共団体自身の意思、すなわち、住民の代表者で構成される議会の判断にゆだねられているものというべきである。しかし、法180条1項が、特に軽易な事項に限って長の専決処分にゆだねることができる旨を規定していることからすると、およそ訴訟上の和解のすべてを無制限に知事の専決処分とすることは法の許容するところではないというべきであり、このような議決がされた場合には、議会にゆだねられた裁量権の範囲を逸脱するものとして、違法との評価を受けるものというべきである。
○ そこで、本件議決が都議会にゆだねられた上記裁量権の範囲を逸脱するものであったか否かを検討することとする。
本件議決の内容からすれば、都議会は、都が提起する訴訟事件に係る和解と都が応訴する訴訟事件に係る和解とでは、その軽易の程度が異なるものと考え、都が提起する訴訟については、訴訟の目的の価額をその軽易の判断基準として、それが1000万円以下のものに限り知事の専決処分とすることとし、他方、都が応訴した訴訟事件に係る和解については、応訴事件であるがゆえにこれがすべて軽易なものであるとし、都議会にゆだねられた上記裁量権に基づいてこれを知事の専決処分としたようにうかがわれる。しかし、都が提起する訴訟事件が除外されているとはいえ、およそ都が応訴した訴訟事件に係る和解のすべてを知事の専決処分とすることは、あまりに広範囲の和解を知事の専決処分をにゆだねるものといわざるを得ない。応訴事件に係る和解のすべてが軽易な事項であるとすることは、「和解」を原則として議会の議決事件とした法96条1項12号及び議会の権限のうち特に「軽易な事項」に限って長の専決処分にゆだねることができる旨を規定している法180条1項の趣旨に反するものであって、本件議決は、都議会にゆだねられた上記裁量権の範囲を逸脱するものというべきである。
○ したがって、都が応訴した訴訟事件に係る和解のすべてを知事の専決処分とした本件議決は、法180条1項に違反する無効なものというほかない。
○ 上記のとおり本件議決は(地方自治)法180条1項に違反する無効なものであるから、被控訴人は都議会の議決を経た上で本件和解をすべきであったこととなる。しかし、普通地方公共団体においては、議会と知事がそれぞれ独立した役割を担い、独自の権限を有していることに照らすと、議会がした議決が違法であったことにより、これを執行した知事に直ちに損害賠償責任が発生するものと即断することはできない。そこで、違法な本件議決がされ、これに基づいて東京都が本件和解をしたことについて、知事である被控訴人に損害賠償の責任が発生するか否かを検討することとする。
○ 普通地方公共団体の長と議会は、それぞれが固有の権限を有する独立した機関であり、前記のとおり、和解に関する普通地方公共団体の意思を決定する権限は議会にあるので、議会が和解に関する議決をした場合は、執行機関である長には、この議決に従った和解をする権限が授与されるとともに、当該和解を行う義務をも負担することとなるが、他方、議会が本来は自らの権限に属する一定の範囲の和解についてこれを知事の専決処分とするとの議決をした場合には、知事としては、その議決が一義的明白に違法であるといえるような場合でない限り、この議決に従って専決処分としてこれを行うことを義務付けられるのであって、これを拒んだ上で、当該和解について、あえて法96条1項12号に基づく議会の議決を求めるようなことはできないものと解される。ただし、法176条4項は、議会の議決がその権限を超え又は法令若しくは会議規則に違反すると認めるときは、当該地方公共団体の長は、これを再議に付さなければならない旨を規定しており、議会の議決が違法であると認めるときは、これを再議に付することは長の義務でもあると解されているのであるから、議会の議決に基づく執行行為でさえあれば、長には常に損害賠償の責任が生じないと解するのは相当でなく、少なくとも、議会の議決が一義的明白に違法であるような場合には、そのような議決を執行した長にも損害賠償の責任が生ずるものというべきである。
○ ところで、前記のとおり、訴訟上の和解について、法180条1項にいう軽易な事項に該当するか否かを判断するには、多岐にわたる事項について複雑な判断によらざるを得ないものであるから、これが容易に判断できるものということはできないものであるところ、都議会は、この軽易な事項の解釈及び判断を誤り、都が応訴した訴訟事件に係る和解のすべてを無制限に知事の専決処分としてしまったのである。また、東京都では、本件議決を適法な議決として扱い、本件議決から本件和解までの約34年間にわたって、都が応訴する訴訟事件に係る和解を知事が専決処分としてきたものであるが、そのことにつき、都議会及び歴代知事などの執行機関はもとより、住民から疑義が出たことはうかがわれず、また、都が応訴する訴訟事件に係る和解を知事の専決処分にしたことで、住民に不利益を及ぼした形跡も存しないのである。
○ 上記の事実関係からすると、結果として、本件議決が法180条1項に違反することとなったものであるが、この議決が一義的明白に違法であるということは困難である。そうすると、知事の専決処分として本件和解がされたことについて、被控訴人には、その専決処分をゆだねた本件議決が違法であることを理由として、東京都に対して損害賠償義務を負担すべき責任は生じないものというべきである。
○ なお・・・本件和解については、平成10年11月19日の東京都の都市・環境委員会において、本件和解の内容について質疑応答がされ、さらに、平成10年12月に開催された都議会の平成10年の第2回定例会において、被控訴人から専決処分として報告され、これに対する質疑応答を経た上で都議会がこれを承認したことが認められる。上記事実関係からすれば、この都議会の承認は、本件和解についてあらかじめ承認の議決をしたのと同視し得るものと認められるので、都が応訴する訴訟事件に係る和解のすべてを知事の専決処分とした本件議決に瑕疵があったとしても、この瑕疵は、本件和解についてはこの都議会の承認により治癒されたものというべきである。
議会事務局職員が随行できる議員の行政視察は無制限に認められるわけではなく、それが認められるためには議員の行政視察、例えば姉妹都市、友好都市との交流活動等に公務性、必要性、相当性などの合理性があり、その際の事務局職員の随行について公務として随行する必要性、相当性などの合理性がなければならないとの前提のもと、本件議員の訪問は公務性があり、所定の手続きさえとれば公費支出も許されるものであって、単なる私的な私費旅行とはいえないものであり、市議会議長が決定した前記訪問への市議会事務局職員の随行決定それ自体にはその相当性、必要性の判断において裁量権を逸脱、濫用した違法があるということはできず、随行決定は適法であり、首長部局の総務課長のした支出命令も適法とした事例 神戸地判平13.9.12判例地方自治228.16
(市議会議員(日中友好議員連盟)の私的負担による海外視察につき議長は議会事務局職員を公費で随行させる決定をし、これら職員は随行した。公費は市長部局の総務課長が支出命令した)
○ 被告らは、議長の決定に伴う経費の支出について、普通地方公共団体の長(執行機関)と議会との関係から、その支出の決定権者は、議長の決定が一見明らかに不存在であるとか、これに重大かつ明白な瑕疵が存するものと認められる場合など特段の事由のない限り、その支出に応じなければならないというべきで、本件支出命令の違法判断については、その判断枠組みに応じて判断すべきである旨主張する。ところで、普通地方公共団体の長は、予算の執行権を有し(地方自治法149条2項)、当該普通地方公共団体に対して予算の適正執行を確保すべき義務を負っている。しかし、執行機関の長としての普通地方公共団体の長(同法148条)と議決機関としての議会(同法96条)は相互に独立し、執行機関の長としての普通地方公共団体の長は、議会を指揮監督する権限を有していない以上、普通地方公共団体の長ないしその権限の委任を受けて専決権者として支出決定権を持つ者は、議会ないし議長の支出を伴う決定については、被告らの主張する上記判断基準でなく、同決定が著しく合理性を欠き、そのため予算執行の適正を確保する趣旨から看過できない瑕疵が存する場合でない限り、同決定を尊重しその内容に応じた財務会計上の措置を採るべき義務があり、これを拒むことは許されないと解するのが相当である(最高裁判所第3小法廷平成4年12月15日判決・民集46巻9号2753頁)。
○ これを本件についてみるに、・・・によれば、以下の事実が認められる。
議会事務局には、事務局長、事務局次長のほか25名の職員がおかれており、議長の命を受け議会の庶務を処理している。その事務は、本会議や委員会等の議会自体の事務のみならず、議長、副議長の活動に伴う秘書業務や議員個人の調査活動等にまで広く議会及び議員に関する事務全般に及んでいる。たとえば、議員は、議員が行なう議員立法や立案に関する調査、情報収集、原案作成等について、議員としての職務に関する事項であるかぎり、事務局職員の補助を受けることができ、事務局職員は、これを職務として行なわなければならない。そして、日中友好議員連盟、日朝友好促進議員連盟、日韓親善議員連盟に関する事務も、議員としての職務に関するものとして、議会事務局の事務とされてきた。
○ 市議会ないし日中友好議員連盟による中国A市への議員の派遣は、昭和56年4月から本件訪中団まで7回(そのうち、日中友好議員連盟主催のものは2回、その他のものは市議会主催で、日中友好議員連盟主催のものは、いずれも議員の私費で賄われ、市議会主催のものは全て公費で賄われている。)行われてきたが、これまでも本件訪中団と同様、事務局職員が特に問題とされることもなくその随行をしてきた。なお、これまでの議員の訪中においても、友好都市である中国A市の他、北京市、上海市、蘇州、杭州市、桂林などを訪れている。
○ 市議会を代表して議会代表団が友好都市提携15周年を記念して平成9年10月に中国A市を訪れた際、中国A市長などから日中友好議員連盟として平成10年度に訪中をするよう強く要請された。日中友好議員連盟は、それに応じて、中国A市との友好を重ねるため訪中団を派遣することを決め、中国A市と連絡をとったところ、1998年(平成10年)8月19日付け書翰で、中国A市人民代表大会常務委員会主任及び中国A市長から、中国A市と市との友好都市提携15周年を記念して、同年10月上旬から7日間の友好訪問の招待を受けた。上記招待に応じて日中友好議員連盟に所属する議員らによって本件訪中団が結成され、本件訪中団の訪中が実施された。本件訪中旅行の日程(平成10年10月7日~12日まで)は、以下のとおりであった。(中略) 本件訪中団の活動には、その訪中の全期間、中国A市人民政府外事弁公室処長Xが、また、中国A市滞在中の4日間は、中国A市人民代表大会副主任のYがそれぞれ随行した。市議会議長、同事務局長は、被告Gらの本件訪中団への随行を復命するに当たっては、随行業務の他、市職員として国際的な視野を広げ、職務能力を高める海外研修としての趣旨をもつものとして、被告Gらに研修として北京市・西安市のまちづくりについて視察を行うことを復命している・・・。上記復命に当たって、研修の具体的視点として、今後の市のまちづくりに活かすため、a)歴史博物館の構想があるために兵馬俑博物館、故宮博物院、b)中国にちなんだ公園整備に活かすために華清地、c)国際的な視野を広めるために天安門広場の各視察を命じている・・・。被告Cらは、上記研修目的の復命に応じて、北京市、西安市においては上記のとおり兵馬俑博物館、故宮博物院、華清地、天安門広場の視察をそれぞれしている。日中友好議員連盟ないし被告Cらは、本件訪中団の西安市、北京市を含めた全日程について、西安市、北京市での視察した内容など、相当な程度に具体的な内容が記載された報告書を作成している・・・。
○ しかし、市では、本件訪中団の旅行が実施された当時、歴史博物館構想はあったものの何ら具体化していなかったし、また、友好都市がある中国にちなんだ公園整備については、その計画も具体化していなかった。また、被告Cらは、本件訪中旅行後、そこでの研修の成果が具体的な形で市の活動に活かされたとまでいうことができない。
○ 以上認定した事実を踏まえて、被告B(注:総務課長)の本件支出命令が違法かどうか判断することとする。
本件訪中団の中国A市滞在中の活動は、前記・・・で認定したとおり、中国A市の人民代表大会や人民政府、初級中学校などを公式に訪問したり、そこで、市長、市議会議長、市教育委員会委員長のメッセ-ジを伝達したりするなど中国A市や関係機関との友好を重ねるもので、議会ないし議員の活動として合理性が認められるものであった。もっとも、北京市や西安市での訪中団ないし被告Cらの行動は、中国A市での公的な活動を終えた後の行動であって、そこでは特に公式行事があったわけではなく、そこでの訪問先は主として観光地として有名な兵馬俑博物館、故宮博物院などの名所、旧跡であったことから、問題がないわけでない。しかし、そこでの本件訪中団の視察も友好都市である中国A市の職員が随行するものであり、両市での兵馬俑博物館、故宮博物院などの視察も、それを通して中国の風土、文化に対する理解を深め、国際交流を促進するという側面を一概に否定することができないものであった。そして、被告C、同Dらは、西安市、北京市での上記訪問に際しても本件訪中団とともに行動し、その随行業務を行なったもので、殊更、個人的に自由な行動をとったわけでなく、私的な観光、遊興目的で行動したものでもなかった。被告Cらは、西安市、北京市への訪問に当たって、本件訪中団に対する随行業務の外、研修目的として市議会議長や同事務局長から北京市、西安市のまちづくりについて視察を行うことの復命を受け、研修の具体的視点として、今後の市のまちづくりに活かすために、<ア>歴史博物館の構想があるために兵馬俑博物館、故宮博物院、<イ>中国にちなんだ公園整備に活かすために華清地、<ウ>国際的な視野を広めるために天安門広場の視察を命じられ、それに従って兵馬俑博物館、故宮博物院などを視察している。確かに、同随行の時点では、市では歴史博物館構想はあったものの何ら具体化していなかったし、また、友好都市がある中国にちなんだ公園整備についても計画が具体化していなかったし、本件訪中団の旅行に随行した後、同被告らの同研修の成果が具体的に市の活動に活かされたとまではいえない。しかし、西安市及び北京市への訪問を含めた本件訪中団の活動に関して、被告Cらによってその研修目的も踏まえて相当な程度具体的な内容記載のある報告書が作成されているうえ、同研修目的による視察によって、被告Cらは、本件訪中団に対する随行業務を行なう傍ら、市の職員として長期的にはその視野を広げるとともに国際感覚を身につけたということも可能であり、同人らの同視察を通して友好都市である中国A市との友好関係を促進したともいえる。
○ 本件随行決定は、これまで特に問題とされることなく行われてきた市議会ないし日中友好議員連盟による中国A市及びそれに付随する訪問先への議員の派遣と同様に、議会事務局職員にその随行を命ずるもので、中国A市などへの訪中内容もこれまでのものとそれほど差異なく、北京市、西安市への訪問には、上記のとおり随行目的だけでなく国際的な視野を広げ職務能力を高める趣旨としての職員研修目的も付加されていた。
○ ところで、普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の議決機関として、その裁量により同地方公共団体の費用で議員を国内や海外に派遣することができるが、上記裁量権の行使を逸脱又は濫用があるときは、議会による議員派遣の決定が違法となる(最高裁判所第1小法廷昭和63年3月10日判決・判時1270号73頁、同第3小法廷平成9年9月30日判決・判時1620号50頁参照)。
○ 本件訪中団の議員らの費用は、訪中議員個人及び中国A市当局が負担しており、市は負担していない。しかし、上記・・・の判断に照らせば、仮に、市議会が全額市の費用負担で本件訪中団の派遣を決定していたとしても、その決定に裁量権の行使を逸脱又は濫用した違法があるものとは認めらない。すなわち、本件訪中団の旅行には公務性があり、所定の手続きさえとれば公費支出も許されるものであって、単なる私的な私費旅行とはいえないものであった。
○ 結局、・・・で認定した市議会事務局職員の議会の庶務に関する職務内容の下で、・・・で検討した諸事情を踏まえると、市議会議長が決定した本件随行決定それ自体には、その相当性、必要性の判断において、裁量権を逸脱・乱用した違法があるということはできず、同随行決定は適法であるといわなければならない。
○ 被告B(総務課長)は、市議会議長がした費用支出を伴う本件随行決定が著しく合理性を欠き、そのため予算執行の適正を確保する趣旨から看過できない瑕疵が存する場合でない限り、同決定を尊重し、その内容に応じた財務会計上の措置を採るべき義務があり、これを拒むことは許されないところ、本件随行決定には、上記のとおり市議会議長にその裁量判断を逸脱・濫用した違法があると認めることができないことからすると、被告Bの本件支出命令は適法といわなければならない。
町の下水道計画は経費の無駄遣いで違法であり、先行する計画策定と後行の下水道関係工事請負契約等の財務会計行為はいずれも町長の権限であるので先行計画の違法性は後行財務会計行為に承継されるとする原告の主張について、当計画が条例審議会の審議を経ていること、下水道設置条例の制定などにより議会の承認も得られていること、法定め県知事の認可も受けていることからすれば、下水道計画が著しく合理性を欠き、そのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過できない瑕疵がある場合でなければ、下水道計画に基づく請負契約の締結等が違法となることはないとした事例 津地判平14.5.9
(町の下水道事業に関する工事請負契約締結および経費支出について、経費の無駄であるとして提起された住民訴訟。原告は、当地の地域実情からすれば安価な合併浄化槽方式でも効果が上がるのに巨費を投じて下水道を建設することは地方自治法2条14項に反するので下水道計画は違法でありよって上記財務会計行為は違法となると主張する)
○ 原告らは、「A町下水道計画が違法であるから、同計画に基づくC処理区下水道施設建設のための請負契約の締結、公金の支出もその違法性を承継する。原因行為の違法性と財務会計行為の違法性(及び義務違反)を別々に考える必要性があるのは独立の権限を有する行政執行機関の行った処分に関する執行行為を行う場合である。本件においては原因行為であるA町下水道計画はA町長が策定した計画であり、請負契約もA町長の専決行為であるから、違法性及び義務違反を別々に考える必要性はない。下水道計画を自ら策定した被告は下水道計画の違法性を十分知り得る立場にあり、下水道計画が違法であれば、その執行行為も違法であり、被告に義務違反があることは当然である。下水道事業に関する予算については、議会の決議を経ているが、その予算案は被告が提出したもので、その内容を最も知り得る立場にあり、この点でも執行行為たる請負契約などが原因行為の違法性を承継すること、A町長である被告の義務違反を問うことに何の問題もない。」旨主張する一方、被告は、「下水道計画の違法性がそのまま財務会計行為の違法性に承継されることはない。A町下水道計画は議会において予算決議されているのであるから、町長にはその執行義務があり、下水道計画を取消変更しうる権限など存しない。」旨主張する。
○ この点、一般的には、長その他の職員の公金の支出等は、一方において議会の予算の議決に基づくことを要するとともに、他面法令の規定に従わなければならず、議会の予算の議決があったからといって法令上違法な支出が適法な支出になることはないということはできる。
○ しかし、もともとA町長は、A町のし尿や生活排水をどのように処理するかについて広範な行政裁量を有している。また、A町下水道計画は、A町長が策定した計画ではあるものの、A町下水道事業審議会設置条例により設置されたA町下水道事業審議会の審議を経て、下水道法4条1項(改正前)に定める県知事の認可も受けていること、「A町下水道事業の設置等に関する条例」及び「A町下水道事業に地方公営企業法の一部を適用する条例」も制定されていることなどからして、下水道法に適合し、A町議会の承認も得られている事業計画であるといい得る。これらの事情からすれば、A町下水道計画が著しく合理性を欠き、そのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過できない瑕疵がある場合でなければ、A町下水道計画に基づくC処理区下水道施設建設のための請負契約の締結、公金の支出が違法となることはないというべきである。
【最高裁判例】 県議会議長がX年開催の全国都道府県議会議員軟式野球大会に参加する議員に対し発した旅行命令が違法である場合において,同命令を前提として知事の補助職員がした議員に対する旅費の支出負担行為及び支出命令は,同大会が,昭和24年以降,国民体育大会に協賛する趣旨で毎年その時期に合わせて開催され,同62年にはすべての都道府県議会が参加するようになったという歴史を有し,X年開催の国民体育大会に協賛するとともに,議員相互の親睦とスポーツ精神の高揚を図り,地方自治の発展に寄与する旨の目的の下に開催されたものであり,全国47都道府県議会から議員1400人余りがこれに参加したなど原判示の事実関係の下においては,財務会計法規上の義務に違反する違法なものということはできない 最判平15.1.17民集57.1.1
(事実関係の要旨は上記の通り。最高裁は、本件旅行命令は違法であるとの判断を示したうえで,旅費の支出負担行為・支出命令を行った上告人A3に対する請求について,次の通り判示)
○ (地方自治)法242条の2第1項4号に基づき当該職員に損害賠償責任を問うことができるのは,先行する原因行為に違法事由がある場合であっても,上記原因行為を前提にしてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られる(最高裁昭和61年(行ツ)第133号平成4年12月15日第三小法廷判決・民集46巻9号2753頁参照)。
○ ところで,議会がその裁量により議員を派遣することができることは前示のとおりであるところ,予算執行権を有する普通地方公共団体の長は,議会を指揮監督し,議会の自律的行為を是正する権限を有していないから,議会がした議員の派遣に関する決定については,これが著しく合理性を欠きそのために予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵がある場合でない限り,議会の決定を尊重しその内容に応じた財務会計上の措置を執る義務があり,これを拒むことは許されないものと解するのが相当である。
○ これを本件についてみると,県議会議長が行った議員に対する旅行命令は違法なものではあるが,・・・の事実関係及び原審の適法に確定した旅行命令の経緯等に関するその余の事実関係の下において,県議会議長が行った旅行命令が,著しく合理性を欠き,そのために予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵があるとまでいうことはできないから,知事としては,県議会議長が行った旅行命令を前提として,これに伴う所要の財務会計上の措置を執る義務があるものというべきである。そうすると,決裁規程…に基づき,知事に代わって専決の権限を有する上告人A3が議員に対する旅費についての支出負担行為及び支出命令をしたことが,財務会計法規上の義務に違反してされた違法なものであるということはできない。また,普通地方公共団体の支出負担行為及び支出命令をする権限を有する職員の損害賠償責任については,故意又は重大な過失により法令の規定に違反して当該行為をした場合に限り責任を負うものとされている(法243条の2第1項,9項)。そうすると,上告人A3が議員及び議会事務局職員に支給する旅費の支出負担行為及び支出命令をしたことにつき県に損害賠償責任を負うというためには,同上告人に故意又は重大な過失があることが確定されなければならない。ところが,原審は,上告人A3に重大な過失があることを確定しないで同上告人の損害賠償責任を肯定したものであるから,法243条の2の解釈適用を誤るものといわざるを得ない。そして,前記アで指摘した事実関係に加え,上告人A3は,専決を任された補助職員として,議会において本件野球大会に議員を派遣することが決定されたことを前提にして上記旅費の支出負担行為及び支出命令をしたものであることなど,原審の適法に確定したその余の事実を総合すれば,同上告人が上記旅費の支出負担行為及び支出命令を行ったことにつき故意又は重大な過失があったということはできない。この趣旨をいう論旨は理由がある。
○ 以上によれば,上告人A3の損害賠償責任を肯定した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,原判決中上記部分は破棄を免れない。そして,前記説示によれば,被上告人の上告人A3に対する請求は理由がないから,第1審判決中この請求を認容した部分を取り消し,同請求を棄却すべきである。
市が民事調停法17条決定に対し、議会の議決を得た上で、同決定に異議を申し立てず確定させ、決定内容に従い土地を買い受けて公金を支出した事例において、当該土地を取得する必要性に乏しいことや高額な買取価格の適正性について調査を尽くさなかったことからすれば本議決は著しく合理性を欠き自治体財政の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するところ、市長が議決事前に適正評価額の把握につとめず議会になすべき説明等も怠っていたことからすれば市長は本議決の存在で直ちに免責されるものではなく、また本件議決に上記瑕疵がある以上再議に付すべき義務があったのに市長はこれを怠ったものであり本件議決に市長が拘束されるものとはいえないとして、市長の損害賠償責任を認めた事例 大阪高判平15.2.6判例地方自治247.39
(一審被告Iらはゴルフ場開発のため山林を買収した。しかし住民の反対運動、隣接他市の議会の2度の反対決議、同市当局からの慎重対処を求める意見書提出等がなされるなどの経緯を経て市はゴルフ場開発不許可決定をしたところ、Iらは市へ80億円の損害賠償を求め民事調停を申し立てた。市は、賠償には応じられないが適正価格での土地買取に応ずる旨調停委員に伝えるとともに不動産鑑定を委託したところ約47億7千万円との評価額報告が市に提出され(調停手続には提出されていない)、市長Tはこの評価書に基づく金額を調停で提示する代金額とすることを決裁し、調停裁判所は上記山林を市議会承認を得ることを条件に市が約47億円で買い取ることを骨子とする民事調停法17条決定を行った。議会では価額が高額すぎるとの意見もあったが賛成多数で異議を申し立てない旨議決され、市長Tはこれを受け上記決定に異議を申し立てず、結果決定は確定し、市は決定の額を支出した。なおIによるゴルフ場事業計画書には用地買収費は約20億円と記載されており、原判決が認定した本件土地の適正価格は約21億4千万円である。当審もこの認定を維持した)
○ ・・・一審被告Tは、市長として市議会による本件議決に基づいて本件決定に対し異議を述べなかったものであるが、このように、市議会の議決に基づいて市長が行った行為について、地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づく代位請求に係る損害賠償請求を求めうるのは、上記行為自体が、市長が当該市に対して負う財務会計法規上の義務に違反するものであるときに限られると解すべきであるところ、このような財務会計法規上の義務違反が認められるのは、上記行為の前提である上記市議会の議決が著しく合理性を欠く違法なものであって、そのため同議決に地方自治体における地方財務行政の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存する場合に限られるというべきである(最高裁判所平成4年12月15日第3小法廷判決・民集46巻9号2753頁参照)。そして、本件では、最終的には、市長の市に対する財務会計法規上の義務違反が問題となるのであるから、同義務違反の存否の認定に当たっては、単に、当該地方議会での審議や議決の当否のみならず、当該議決に至るまでの議案提出や議決に至るまでに、市長が市議会に対して行った説明や具体的対応等をも十分考慮すべきである。
○ 以上に対し、一審被告Tらは、市議会の議決に明白かつ重大な瑕疵がある場合とか、市長自身が市議会に対し虚偽の説明を行い議決を誤らせた等の特段の事情がない限り、市長が市議会の議決に基づいて行った行為は違法とはなり得ないと主張する。しかしながら、上記の重大かつ明白な瑕疵という基準は、行政行為が無効となる場合についてのものであるところ、本件では、行政行為の有効性ではなく、地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づく損害賠償請求権の有無をめぐり、市長の地方公共団体に対する職務上の義務違反が問題となるのであるから、上記基準を採用する必然性はない。また、上記規定の趣旨に鑑みれば、前提となる議決に無効となるまでの瑕疵がない場合であっても、市長が財務会計法規に基づく職務上の義務に違反したことを理由として損害賠償責任を負うべき場合もある。したがって、一審被告Tらの主張する上記基準を本件で用いることは妥当ではないと解すべきである。
○ そこで、一審被告Tが、本件議決に従って本件決定に異議を述べなかった行為自体が財務会計法規上の義務に違反したものであったか否かの判断の前提となる、本件議決が著しく合理性を欠く違法なもので、そのためこれに地方自治体における財政の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存したといえるかを検討する。そもそも、地方公共団体における経費は、その目的を達成するための必要かつ最小の限度を超えて支出してはならないとされる(地方財政法4条1項)から、地方公共団体が土地を取得する場合も、できる限り適正かつ安価な代金で取得するよう最大限の努力をすべきことは当然であり、そうであれば、地方議会の行った適正価格を大幅に超える代金額で土地を取得する旨の議決が違法なものと評価される場合もあると解される。他方で、地方議会は、さまざまな公共目的を実現する見地から、必要な土地を適切かつ迅速に取得する権限が認められるべきであり、代金額を含めいかなる内容で当該土地を取得するかについて広範な裁量権を有すると解さなければならない。したがって、土地取得にかかる地方議会の議決の違法性の有無や程度は、単に取得価格が適正価格を上回ったか否かを事後的に判断するのみならず、上記取得価格の算定が手続的にも実体的にも適正に行われたか、当該土地を取得する具体的な行政目的や必要性がどの程度あったか等の諸事情を総合し、当該議決がなされた時点を基準として、地方議会に認められた裁量権の逸脱、濫用があったか否かという観点をも踏まえて判断するのが相当である。
○ そこで、以上を前提に市議会における本件議決の違法性の有無及びその程度について検討するに、引用にかかる原判決認定の各事実・・・によれば、以下の各事実を認定することができる。
(1) 本件土地の適正価格の評価について
〈1〉 H評価書について
前記認定のとおり、本件決定で示された本件土地の買取価格はH評価書の評価価格に基づくものであったが、H評価書については、前記のとおり、ゴルフ場開発予定地として買収されたH事例Bが取引事例として採用されていること、本件土地自体の従前の取引事例では買収総額が20億円とされているにもかかわらず、同事例が全く考慮されていないこと、H以外に複数鑑定を求めておらず、H評価書の評価の当否につき十分検証しうる資料に乏しかったことなど、市議会がその当時客観的に認識し得た事情に照らして合理性に疑問があったところ、市議会においても、市議会議員から上記問題点が具体的かつ明確に指摘されていたのであるから、市議会としては、問題を解明し検討すべく関係部署を通じて調査等すべきであったが、そのような対応は取られなかった。また、H評価書は市議会に開示されていた上、その評価価格の合理性について疑問が呈されていたものであり、市議会としては、前記のとおり、本件土地の傾斜度や、取引事例地の位置を誤認する等H評価書の記載内容の客観的な誤りについても当然認識し得たはずであるが、これを十分検討することを怠った。
〈2〉 評価委員会に対する諮問の必要性について
市公有財産規則は、市が土地を取得する場合、原則として評価委員会に土地価格について調査、審議、評定を諮問すべきことを定めているが、例外的に上記諮問を要しない場合を、市不動産評価事務取扱要綱15条が個別具体的に定めており、同条・・・では、調停等により当該土地の価格が確定した場合は上記諮問を要しない旨規定されている・・・。そして、本件では、市及び一審被告Iらが、調停に代わる決定である本件決定に異議を述べないことにより、本件決定と同内容の調停が成立したものとみなされるから、形式的には上記要綱15条が規定する例外事由に該当するかに見える。しかしながら、市公有財産規則は、市による財産の取得が適正になされることにより、市財政の健全化を図る趣旨と解され、上記要綱15条が、判決、和解、調停等で土地価格が確定した場合は評価委員会に対する諮問を要しないと規定したのは、上記場合は通常裁判所が紛争の実態や提出された関係資料を踏まえて適正な判断を行うことが期待できるからであると解される。ところが、本件は、原判決認定のとおり、調停裁判所に対しては、H評価書を含め本件土地の適正価格を算定するための資料は一切提出されておらず、同裁判所が市代理人の要望に基づいて本件決定を出したものであるから、上記要綱15条が想定する事例に該当するとはいえない。さらに、本件決定で示された本件土地の買取価格は40億円を超える高額なものであり、かつ、前記のとおり、市議会において上記買取価格やH評価書について批判がなされていたのであるから、市による財産取得の適正を図る趣旨から、評価委員会での慎重な審議を要する事案であったというべきである。したがって、本件が、上記要綱15条所定の事由に該当する事案であったとはいえず、評価委員会に諮問することなく本件議決を行ったことは、上記規則に違反するものであったといえる。
〈3〉 以上によれば、市議会は、本件決定に示された本件土地の買取価格が適正かについて、当然なすべき実体的な調査や審議を尽くさず、また、手続的にも内規に違反した上で、上記買取価格での買取を是認する旨の本件議決を行ったものであり、この点で違法があったというべきである。
(2) 市が本件土地を本件決定を確定させることによって取得する必要性について
一審被告Tらは、市による本件土地の取得は、①直接には、市が一審被告Iらから80億円の損害賠償を求める調停を申し立てられたため、その解決を図ることを目的とし、②最終的には、市民の健康につながる自然公園用地にあてるという行政目的に基づくものであり、③現に上記調停が申し立てられた状況下で、これを解決する必要があったから、差し迫った必要性がなかったとはいえないと主張する。しかしながら、一審被告Iらが上記調停で主張する市に対する80億円の損害賠償請求は、一審被告Iらが市担当者の行政指導に基づいてゴルフ場建設を計画し、また、建設用地として本件土地を取得することにつき国土法に基づく届出に対し市が不勧告通知をしたにもかかわらず、市は最終的に上記建設を不許可とする決定をしたことを理由とするものであるところ、調停申立書・・・の記載内容や判例(昭和56年1月27日第3小法廷判決・民集35巻1号35頁参照)に照らしても、本件調停が不成立となり一審被告Iらが上記損害賠償を請求する訴訟を提起したとしてもそれが認容される見込みが乏しいことは明らかであったし、市自身も、当初から一貫して上記損害賠償請求に応じないとの意向を明らかにしていたのであるから、市が本件調停事件を解決するために、高額な代金を支払ってまで、一審被告Iらから本件土地を購入する差し迫った必要性はなかったというべきである。なお、一審被告Tらは、一審被告Iらが市に対し行政処分の取消訴訟を提起した場合、市が敗訴する可能性がなくはなかったと主張するが、この点については、市議会の審議の際に議員等から何ら言及されておらず、本件議案と上記行政訴訟との関係が本件議決の際に考慮されていたとはいえない。また、一審被告Tらは、市が、本件土地を取得する目的として、自然環境を保全しながら自然とふれあう場を整備し、道路等の基盤整備その他の地域振興を図る必要があった点を指摘するが、上記目的自体極めて一般的かつ抽象的なものである上、本件議決がなされた当時、本件土地の具体的な利用計画はその概要さえ全く未定であった(なお、実際に本件土地一体を都市公園とすることが決定されたのは、本件議決から約4年後で、本訴提起後の平成8年である。)。したがって、市としては、本件議決当時、本件土地を取得する目的は余りに漠然としており、取得する現実的必要性も乏しいものであったといわざるを得ない。そして、一審被告Tらは、市と一審被告Iらとの紛争が長期化すれば、本件土地が転売される等して、将来的に、市が本件土地を取得することが困難になると主張するが、抽象的な可能性としてはともかく、近い将来、本件土地の転売がなされるおそれがあると認めうる的確な証拠はないから、上記主張は採用し難い。以上によれば、市としては本件土地を取得する必要性自体が乏しく、しかも、本件決定の異議申立期間という極めて限定された短期間の内に、前記のとおり本件決定における取得価格が適正であるか極めて疑問であったにもかかわらず、あえて本件決定を確定させることにより本件土地を取得する差し迫った必要性があったとは到底いえない。
○ 上記認定の各事実によれば、本件議決は、市が、本件決定に異議を申し立てないことにより、その当時も市として本件土地を緊急に取得する目的や必要性に乏しく、しかも、買取価格の適正さについて、極めて疑問な点が多々あったにもかかわらず十分な調査等もせず、また、価格の適正を担保するための内規にも違反した上、適正価格を20億円以上も超え経済的に見れば到底あり得ない高価格で本件土地を買い取るというものであったことが認められる。以上を総合すれば、本件議決が、地方議会に認められた裁量権を逸脱、濫用した違法なものであったことは明らかであり、さらに、同議決は、著しく合理性を欠き、そのためこれに地方自治体における財政の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものといわざるを得ない。
○ 一審被告Tの本件議決に至るまでの対応について
(1) 本件議案の提出に至るまで
引用にかかる原判決認定によれば以下のとおり認められる。一審被告Tは、本件調停申立にかかる紛争を一審被告Iらから本件土地を適正価格で買い取ることで解決しようとして、市代理人弁護士を通じて、平成4年4月15日の第1回調停期日に、調停裁判所に対し上記意向を伝えた上、同月20日、Hに対し本件土地について鑑定依頼を行い、その結果作成されたH評価書に基づいて、同年5月8日に、調停裁判所に対し、本件土地の買取希望価格(48億6963万円)を提示した。そして、同時点において、調停の進行状況如何では上記価格で本件土地を買い取る旨の調停が成立する可能性もあったと認められるから、少なくとも適正価格での買取の意向を明らかにした同年4月15日ころ、前記のとおり評価委員会に諮問するなどして適正価格の評価に努めるべきであったといえるのに、同一審被告はこれを怠ったものである。そうとすると、一審被告Tは、本件議案が提出される以前の段階で、本件土地の適正価格認定のために尽くすべき手段を講じなかったというべきである。さらに、一審被告Tから委任を受けた市代理人弁護士は、同年5月8日の第3回調停期日において、調停裁判所に対し、市が上記買取希望価格で本件土地を買い取る旨の調停に代わる決定(本件決定)を出すよう求め、同月13日に本件決定が出されたが、その結果、本件決定に対する2週間の異議申立期間内に、市は市議会において異議を申し立てるか否かの本件議案につき議決せざるを得なくなった。しかも、一審被告Tは、市議会に対し、本件議案を直ちに提出せず、市議会閉会間際の同月21日に至って本件議案を提出したため、本件議案について審議しうる期間が極めて短期間に限定されることになったものであり、かかる事態を招いた点について一審被告Tに責任があることは否定し難い。そうとすると、一審被告Tとしては、本件議案を提出した責任者であることやその審議期間が短期間となった経緯に鑑み、市議会が本件議案を審議するに際し、本件土地の適正価格について的確な判断ができるよう、議員から指摘された問題点を解明するために具体的な説明や資料の提出に努めるなど万全の配慮を尽くすべき義務を負っていたというべきである。
(2) 本件議決に至るまで
そこで、本件議案提出後、本件議決に至るまでの市議会における一審被告Tの答弁や説明等について検討するに、前記認定によれば、以下のとおり認められる。一審被告Tは、市議会においてH評価書の問題点が指摘されていたにもかかわらず、これを解決するため改めて検討、調査した上具体的な説明や答弁をすべきであったのに、H評価書を開示する等した以外は上記問題点について特段の調査や説明等をしなかった。また、一審被告Tは、調停裁判所が、H鑑定書等客観的な資料に基づいて本件決定を出したわけではなく、市側の提案した金額に専ら依拠して本件決定をしたのにその点に言及せず、本件決定で定められた土地価格は、調停裁判所が中立的かつ公正な立場から判断したものであるから信用しうる旨誤解を招くような答弁をしている・・・。そして、市議会の審議において、本件土地自体の過去の取引価格として、一審被告Iの国土法上の届出価格が指摘され、それと本件決定で定められた価格が大幅に異なる点が問題とされていたのに、国土法上の監督官庁としての守秘義務による限界があるとはいえ、市の担当者を通じて、本件決定で示された本件土地の価格が国土法の指導価格の範囲内であるとの抽象的な説明をするに留まり、市長としての国土法上の監督権限に基づいて、市議会が上記届出価格の適正さを検討するための指導価格の概算価格や算定根拠等、具体的客観的な資料を提出し得たにもかかわらずこれを怠ったものである。さらに、一審被告Tは、本件土地取得の必要性についても、損害賠償請求訴訟が提起された場合の敗訴可能性、本件決定に対し異議を申し立てた場合の本件調停手続やその後の予想される経緯等について具体的な説明を尽くしたかも証拠上疑問である。
(3) 以上によれば、一審被告Tは、市議会が、本件土地の適正価格や取得の必要性について審議するに際し、当然なすべき説明や資料の提出等を怠り、審議の充実を図るため万全の配慮を図るべき義務を怠ったというべきである。そして、このような場合、市長たる一審被告は、本件議決がなされたことを理由に、本件における責任が直ちに免ぜられると解することは相当ではない。
○ 以上検討したところを総合すれば、一審被告Tが、市長として、本件決議に従って本件決定に異議を申し立てなかった行為は、財務会計法規上の義務に違反する違法なものというべきである。しかしながら、他方で、一審被告Tが、法令上、本件議決に拘束され、そのため、本件決定に異議を申立てない以外の対応が取れないのであれば、その責任は問い得ないという余地もあるから、すすんで、本件議決が市長である一審被告Tに対していかなる効力を有し、また、その同効力を前提として、一審被告Tがいかなる職務を行うべきであったかを検討する。本件議決は地方自治法96条1項12号に基づくものであり、同項所定の各事項についてなされた議決は、予算に関するもの等は別として、当該地方公共団体の最終的な意思を決定するものであるから、市長等首長としては、特段の事情がない限り、上記議決の内容どおりにこれを執行すべき義務を負うものと解すべきところ、本件議決は、本件決定に対し異議を申し立てない旨の本件議案を受けて、市として本件決定に異議を申し立てないことを明確に議決したものであり、市議会における審議経過・・・に照らしても、市長に対し本件決定に異議を申し立てないよう義務付ける趣旨であり、異議を申し立てるか否かについての判断を市長の裁量に委ねる趣旨ではないとも見うる。しかしながら、前記のとおり、本件議決は、法的に無効とはいえないまでも著しく合理性を欠き、地方自治体における財政の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものであるから、上記特段の事情が認められるというべきである。そうとすると、本件議決が市長である一審被告Tに対して拘束力を有していたとは解し得ず、一審被告Tとしては、市に対して負っていた財務会計法規上の義務に基づき、本件決定に対し異議を申し立てるべきであったというべきである。なお、仮に、本件議決に拘束力があったとしても、地方公共団体の長は議会の議決が法令に違反すると認めるときは、これを再議に付する義務を負うところ(地方自治法176条4項)、前記のとおり、本件議決は違法であり、さらに著しく合理性を欠き、地方財政の適正確保の見地から看過し難い瑕疵が存するものであったと認められるから、市長としては、財務会計法規上の義務として、本件議決後直ちに再議に付する義務を負っていたというべきである。しかるに、一審被告Tは、上記再議に付する義務の履行を怠った上本件決定に異議を申し立てなかったものであり、違法な行為を行ったということができる。この点について、一審被告Tは、本件議案が審理された市議会は、審理のため会期を延長しており、本件議決後は閉会となり、本件決定に対する異議申立て期間内に再議に付することは事実上不可能であったと主張する。しかしながら、再議に付すべき議会の会期については、当該議決がなされた当該会期に限定されるべきではなく、市長は、再議に付すべき義務を負う場合、再議のため臨時会を招集する等できる限りの手段を講じなければならないというべきである。そして、原判決認定のとおり、上記異議申立て期間は平成4年5月27日までであり、本件議決がなされた同月26日を含めて2日間の期間が残されていたのであるから、上記期間中に臨時会を招集することも可能であったというべきであるから、一審被告Tが、本件議決後、直ちに、再議に付することは事実上不可能であったとはいい難い。また、そもそも、上記のように市議会における審議期間が限定されたものとなった点については、前記認定のとおり、一審被告Tに責任があったというべきであるから、審議期間が短期間となったため再議に付することに支障が生じたとしても、一審被告Tの責任が免責されるとは解し難い。したがって、一審被告Tらの上記主張は採用できない。
○ 一審被告Tらは、本件決定に対し異議を申し立てなかった行為が違法であったとしても、同行為に及んだ点について過失はなかったとしてるる主張するが、原判決認定の各事実及び前記認定の各事実を総合すれば過失があったことが認められ、上記主張は採用し難いというべきである。
○ 以上によれば、一審被告Tが本件決定に対し異議を申し立てなかった行為は違法であり、かつ、同行為は同被告の過失によるものと認められるから、これにより市が被った損害を賠償すべき義務を負うというべきである。
特別区が駅前再開発組合に参加して組合員協定に基づく負担金を支払い図書館用建物を取得した事案につき負担金が高額かつ手続にも瑕疵があるとする住民訴訟において、①組合員協定が無効でない場合区は契約上の支払義務があり、支出命令権者が違法事由を知りまたは知り得べきときは是正のための適宜の措置をとる義務を負うが本件では区が負担金減額を申し入れても実現する可能性はなかったことからすれば負担金支出命令が財務会計法規上違法なものとはいえない、②本来は議会の議決を得るべき財産取得を議会の議決を経ずに行っているが、当該事業を明示した予算議決がなされている場合は、議会としても財産取得のための協定の存在を認識しつつこれを是認していたと認めるのが相当であり、適法な議決がない財産取得に係る対価の支出命令は有効、とした事例 東京地判平15.3.26判例時報1836.62
(特別区が図書館用に取得した建物に時価と比較して異常に高額の代金を支払っておりその取得手続にも瑕疵があったとする住民訴訟。本件建物は、都市再開発法110条1項による駅前再開発事業につき区が再開発組合に組合員として参加して取得したもの(再開発ビルの一部)であり、建物取得に際し議会の議決を得ていない。区は参加組合員協定に基づき負担金を支払っている)
○ 原告らは、X+2年度分支出命令の違法事由として、〈1〉本件協定に基づく参加負担金は違法に高額なものであったから、これを是正すべく努力すべきであったのに、この努力義務を怠っている、〈2〉本件協定は、議会の議決等に基づいていないという点において違法であるから、このような違法な協定に基づく支出も違法であるという趣旨の主張をしているのに対し、被告は、「原告らは、同支出命令そのものの違法を主張しているのではなく、その原因行為である本件協定の違法を主張しているのにすぎないところ、このような事由は、同支出命令の違法事由たり得ない。」という趣旨の主張をしているので、まず、同支出命令の違法事由に関する基本的な考え方を検討しておくと、次のとおりである。
○ 地方自治法242条の2の規定に基づく住民訴訟は、普通地方公共団体の執行機関又は職員による同法242条1項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実の予防又は是正を裁判所に請求する権能を住民に与え、もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とするものである(最高裁昭和53年3月30日第1小法廷判決・民集32巻2号485頁参照)。そして、同法242条の2第1項4号の規定に基づく代位請求に係る当該職員に対する損害賠償請求訴訟は、このような住民訴訟の一類型として、財務会計上の行為を行う権限を有する当該職員に対し、職務上の義務に違反する財務会計上の行為による当該職員の個人としての損害賠償義務の履行を求めるものにほかならない。したがって、当該職員の財務会計上の行為をとらえて上記の規定に基づく損害賠償責任を問うことができるのは、たとえこれに先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、同原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解するのが相当である(最高裁平成4年12月15日第3小法廷判決・民集46巻9号2753頁)。そして、当該職員の行為の違法性は、当該職員が財務会計上の行為を行うに当たって負っている職務上の行為義務ないし行為規範についての違反の有無により定まり、その行為義務ないし行為規範の内容は、当該職員が財務会計上の行為をするに当たり、当該地方公共団体に対し、原因行為との関係でいかなることをすべき財務会計上の行為義務を負担しているかという観点から判断されるべきであって、先行する原因行為が契約であり、後行の財務会計行為が支出命令(地方自治法232条の4第1項)である場合には、原因行為も財務会計行為としての性質を有する支出負担行為(同法232条の3)であり、支出負担行為たる契約が違法かつ無効であれば、支出命令を担当する当該職員としては、職務上負担する財務会計法規上の義務として、無効な契約に基づく金銭の支出をしてはならないという義務を負っているということができ、当該契約に基づく支出命令をしてはならないこととなる。これに対し、原因行為たる契約が違法ではあっても私法上無効とはいえない場合には、地方公共団体は契約の相手方に対して当該契約に基づく債務を履行する義務を負うのであるから、同債務の履行として行われる行為自体はこれを違法ということはできず(最高裁昭和62年5月19日第3小法廷判決・民集41巻4号687頁参照)、支出命令を担当する当該職員は、契約の違法を知り又は知り得べきときはこれを是正するための適宜の措置を執る義務を負うということはできるが、その是正ができないものであれば支出命令を違法とすべき理由はないというほかない。そこで、以下においては、以上の基本的な考え方を踏まえ、原告らの前記主張〈1〉、〈2〉の当否について検討を加えることとする。(注:この判断枠組みに関しては最判平25.3.21民集67.3.375も参照)
○ ・・・契約内容の是正義務違反に関する主張について
本件においては、X+2年度分支出命令に先行する原因行為として本件協定があるところ、本件協定は、区と本件組合との間で締結された私法上の契約としての性質を有するものと考えられ、財務会計法規上は支出負担行為に当たるものである。したがって、本件協定が違法のみならず私法上無効である場合には、支出命令権者である被告は本件協定に基づく支出命令をしてはならないこととなり、この点は、原告らの前記主張〈2〉との関係で問題となる。しかしながら、原告らは、仮に本件協定が私法上有効であるとしても、協定の内容の是正を求めることなく支出命令をした場合には、当該支出命令は違法になるとの主張もしているので(原告らの前記主張〈1〉)、まず、この点について判断することとする。
○ ところで、本件協定が私法上は有効であることを前提とすると、仮に本件協定に違法事由があったとしても、区は、本件協定に従って本件組合に対し参加組合員負担金を支払う義務があることとなるから、支出命令権者であるAは、本件協定の違法事由を知り又は知り得べきときはこれを是正するため適宜の措置を執る義務を負うが、その是正ができないものであれば、X+2年度分支出命令をせざるを得ない立場にあったものであり、このような場合にまでX+2年度分支出命令をしたことについての責任を問うことはできないものと解すべきであり、このことは、Aの指揮監督権者である被告についても同様であると解される。そこで、本件協定に違法事由がある場合の是正の可能性について検討するに、本件協定は、区と本件組合との間で締結されたものであって、被告が同締結につき区を代表する立場にあっても、被告ないしは区の一存によりこれを変更することができないことはいうまでもない。本件協定においては、第3条2項において、本件協定締結後、参加組合員負担金確定の通知の日までに著しい経済変動、天災地変、その他不可抗力により本件組合が事業計画に定める事業費に著しい変動があった場合は、参加組合員負担金の額及び事業計画の内容について、必要があれば、本件組合と区が協議合意の上、見直すことができるものとする旨が定められており、区の参加組合員負担金の額を見直すことができる場合を天災地変等の不可抗力の場合に限定しており、本件ではこれに当たるような事情が生じていたことは認められない(上記条項中の「著しい経済変動」は「天災地変」と並んで不可抗力の一例としてあげられていることからすれば、いわゆるバブル経済の崩壊による一般的な地価の下落傾向が上記「著しい経済変動」に当たるものとは解されない上、上記条項は本件協定締結後の事情の変更について規定するものであるところ、本件協定が締結されたのはX+1年3月14日であって、既にバブル経済崩壊後相当の期間を経過した後であることは公知の事実であるから、本件において、本件協定締結後に「著しい経済変動」があったものとは認められないことは明らかである。)。なお、本件協定第6条3項には、同条1項に定める参加組合員負担金の納付時期及び納付額について、やむを得ず変更の必要が生じた場合は、本件組合と区が協議合意の上その変更を行うものとする旨が定められているが、これは、その文言上明らかなように、同条1項により本件協定別表のとおり3回に分割して支払うこととされた区の参加組合員負担金につき、その納付時期及び納付額を変更する場合のことを規定したものと解され、したがって、同条3項は、本件協定第2条により概算額が定められ、同第3条によりその確定方法が定められている参加組合員負担金の総額自体の変更について規定するものとは解されず、同総額の範囲内で、その分割支払の時期及びその時期に対応する各分割支払金額の変更をする場合の手続を定めたものと解すべきであるから、本件協定第6条3項に基づき区の参加組合員負担金の減額を申し入れることはできない。したがって、本件においては、仮に原告らが主張するように、本件建物の土地相当費が高額にすぎるものであったとしても、区には、本件協定に基づき、自らの参加組合員負担金の額を減額するよう申し入れる権利を有していたものとは認められず、被告が区を代表して本件組合に対し参加組合員負担金の減額を申し入れるとしても、それは、契約上の権利の行使ではなく、本件協定の内容を一部変更する新たな合意の申込みにすぎず、本件組合がこれに応ずる義務があるものではない。
○ また、本件事業は全員同意型の第一種市街地再開発事業であり、権利変換計画を変更するとすれば、全員の同意が必要となる点で、区の参加組合員負担金の減額を申し入れたとしても、その実現が容易ではないことが予想されるだけでなく、全員同意型の方式においては、都市再開発法の定める権利変換計画の基準規定の多くの適用が排除され(同法110条1項)、特に、従後資産と従前資産との間に著しい差額が生じないように定めなければならないという等価の原則を定めた同法77条2項や宅地棟の価額の算定基準及び評価時点について定めた同法80条、施設建築敷地の価額等の概算額の算定基準を定めた同法81条の規定の適用が排除されており、適用されるのは、同法82条の公共施設用地の帰属の基準のほか、同法74条の「権利変換計画は、災害を防止し、衛生を向上し、その他居住条件を改善するとともに、施設建築物及び施設建築敷地の合理的利用を図るように定めなければならない」(同条1項)、「権利変換計画は、関係権利者間の利害の公平に充分の考慮を払って定めなければならない。」(同条2項)という抽象的な基準だけであり、この点で、全員同意型の方式を採る場合には、権利変換計画の内容につき客観的な基準よりも関係者の同意に重点が置かれていると考えられる。しかも・・・関係権利者の従前の土地・建物価額の評価は、本件組合の依頼により不動産鑑定士による鑑定がされ、それに基づいて従前資産の評価がされ、同評価につき関係権利者全員の同意を得て行われ、これを基に権利変換計画が作成され、都市再開発法43条に基づき審査委員3名の同意がされたものであり、その中で本件建物の取得価格が決定されたものであることが認められるところ、そもそも市街地再開発事業は、全事業費を支払うに足りるだけの事業に伴う参加組合員負担金等の収入が確保されるときに初めて成立するものであって、本件の権利変換計画も区が支払を約した参加組合員負担金を不可欠の前提としているのであり、その支払がされず、他にそれを填補する途が得られなければ、権利変換計画自体の実現が困難となるものである上、区は、地域の街づくりにおいて主導的地位にあり、本件事業の基礎をなす権利変換計画自体が成り立たなくなるような行為は行い難い立場にあるものと認められる。さらに・・・本件においては、X+2年度支出命令についての減額を申し入れるべき義務の有無が問題となっているところ、同支出命令に係る支払のされたX+3年4月19日の1か月半ほど後である同年6月7日に・・・は竣工していることも認められる。したがって、区がその参加組合員負担金を本件組合に対して支払うことが本件事業全体の権利変換計画の中で占めていた重要性にかんがみれば、実際上、被告がX+2年度分支出命令をするか否かの検討に当たって、区の参加組合員負担金の見直しを求めることを期待するのは困難であり、また、仮に被告がその申入れをしたとしても、本件事業自体の実現を考えた場合、本件組合が区の参加組合員負担金を減額することについて同意をした可能性は皆無であったものと認められる。加えて、前記法令の定め及び前提事実によれば、区の参加組合員負担金の概算額を定めた本件協定締結後、その内容を含む権利変換計画が東京都知事により認可され、同認可が関係権利者に通知されることにより、行政処分として公定力を有するものと解される権利変換の処分がされていることが認められ、したがって、概算額とはいえ、本件事業につき区が本件建物の取得に対応して参加組合員負担金として支払うべきおおよその金額については、行政処分たる権利変換の処分により支払義務が確定されていて、同処分が取り消されたり当初から無効である旨の主張立証はない。
○ これらの事実からすれば、仮に、客観的には本件建物の取得価格が時価に比して高額なものであったとしても、被告において区の参加組合員負担金の減額の申入れを本件組合に対してすべき義務が生じていたものとは認め難く、むしろ、仮にそのような申入れをしていたとしても、本件組合及び関係権利者においてそれが受け入れられる可能性は皆無であったと認められるから、X+2年度分支出命令に関する指揮監督権者としての被告の立場において、同申入れをしないままX+2年度分支出命令がされることを許してしまったとしても、これが被告の財務会計法規上の行為義務に違反したものとして直ちに違法となるとは認められない。なお・・・本件事業の参加組合員である○株式会社及び○株式会社については、X+3年9月26日に、同各社の参加組合員負担金が減額されたことが認められるが、同各社と本件組合が締結した参加組合員契約書6条2項においては、参加組合員負担金の額の減額条件の一つとして「都営・・・線の・・・-・・・間の開業がX+1年度末より遅れた場合にまたは遅れることが明確になった場合」との定めがあり、実際にその開業が遅れたことから、この定めに基づいて、本件組合が減額につき鑑定を依頼し、その鑑定結果を基にして、審査委員の意見書においても減額をしなくてはならないとの意見が表明されたことから、区としても本件組合に対して同減額に同意し、減額要求額8億1899万7000円のうち、減額しても事業の成立が可能であると判断された5億2387万6000円の減額がされたことが認められる。これに対し、本件協定においてはこのような具体的かつ明確な定めはなく、本件協定において区の参加組合員負担金の額を見直すべき事由が生じたものとは認められないことは前記・・・のとおりであって、上記各社の場合のように当初から参加組合員負担金の額の見直しをすべき事態が具体的に想定されていた場合とは前提が異なるから、上記各社についての参加組合員負担金の減額がされた事実は、何ら前記判断を左右するものではない。
○ 以上によれば、区が、本件組合に対し、本件協定の内容を変更して参加組合員負担金の減額を求める法律上の根拠はなかったし、任意の交渉を通じてその実現を図ろうとすることも困難であったといわざるを得ないのであるから、参加組合員負担金額の減額を求めることのないまま本件支出命令をしたことが違法であったということはできず、したがって、被告に指揮監督義務違反があったということもできないのであって、原告らの前記〈1〉の主張は失当であるといわざるを得ない。
○ ・・・議会の議決の必要性に関する主張について
原告らは、本件協定の締結は、地方自治法96条1項6号の「財産を交換し、又は出資の目的」とする場合、又は同項8号の「財産の取得」に当たるものとして議会の議決を要すると主張するのに対し、被告は、「本件建物の取得は、参加組合員として本件事業により建設される再開発ビルの床を取得する方法によりされたもので、これは、権利変換処分という行政処分によって原始取得するものであるから、売買契約その他私法上の行為によって承継取得するものではなく、地方自治法96条1項により議会の議決を要する場合には当たらない。」と主張するところ、仮に本件協定の締結については、議会の議決が必要であるとすれば、その議決を欠いた契約は私法上無効というべきこととなるので、この点について判断する。
○ 本件協定は、形式的に見れば、「財産を交換し、又は出資の目的」とする場合には当たるものではないし、また、本件建物は、権利変換処分という行政処分によって区が原始的に取得するものであり、本件協定の効果として直ちに財産取得の効果が生じるものでもないのであるから、「財産の取得」にも当たらないものといわざるを得ない。しかしながら・・・においても指摘したとおり、本件事業のような全員同意型の第一種市街地再開発事業の場合には、権利変換計画の内容について、法律上の規制がほとんど働かず、参加組合員の合意によって決定されると言っても差し支えない状況にあるのであるから、区が本件協定を締結した場合には、協定に定められた内容に従って保留床を取得する一方、参加組合員負担金の支払義務を負うことが、ほぼ必然的な成り行きとなるものである。そして、このことからすると、本件協定を締結するということは、実質的にみれば、一定の対価(参加組合員負担金)を支払って保留床を取得する旨の合意をすることを意味するものといえるのであり、このような実質に着目し、かつ、地方自治法96条1項8号が、重要な財産の取得や処分といった普通地方公共団体の財政に影響を及ぼす可能性がある事項の決定は、執行機関の判断のみに委ねることなく、議会における審議を通じてその当否を判断する機会を与える必要があるとの観点から規定されたものであると解されることをも考慮すると、本件協定は、同号所定の「財産の取得」又はこれに準ずるものとして議会の議決を要するものと解すべきである。
○ もっとも・・・、土地改良法54条の2第5項に基づく土地の取得(いわゆる創設換地の取得)については、議会の議決を要しないとの行政実例が存在し・・・、また、「自治実務セミナー」という名称の雑誌や、地方公共団体公有財産管理事務質疑応答集という名称の書籍において、都市再開発法21条の参加組合員として建築物を取得する場合にも、議会の議決を要しないとの見解が示された例があること・・・が認められる。しかしながら、創設換地の取得の場合には、換地計画の内容に関する法令上の規制がそのまま適用されることとされており、法令上の規制の適用がほとんど排除され、参加組合員の合意によってほぼ権利変換計画の内容が決定される本件協定とは、その実質を大きく異にするのであるから、これを直ちに本件協定に適用することはできないものというべきであるし、また、上記各書籍に掲載された論稿は、それがどの程度権威のあるものとして扱われるべきであるかには疑問があるのみならず、その内容も、全員同意型の場合とそれ以外の場合とを区別した検討がされているものでもなく、そのまま本件協定に適用し得るものということはできないものというべきである(その上、自治実務セミナー掲載の論稿においては、参加組合員としての建築物の取得の「実質をみれば、100パーセント疑問なしというわけではないが」との留保が付されていることにも留意すべきである。)。したがって、上記の行政実例等は、上に示した結論を左右するものではない。
○ 以上のように、本件協定は議会の議決を欠いている点で私法上無効というべきであるから、本来ならば、これに基づく支出命令もまた違法無効なものというべきである。もっとも、本件協定の上記無効事由は、その態様からみて、本人から十分な授権を受けないでされた無権代理行為と同質のものであるところ、無権代理行為については本人が追認することによって有効なものとなるのであり、本人が無権代理行為の存在を知りつつ無効を主張せず、かえってその行為を是認する態度を採っている場合には、少なくとも本人は、その無効を主張し得なくなるものと解すべきである。
○ これを本件協定についてみると・・・、本件建物取得の対価とみるべき参加組合員負担金の支出については、X年度の補正予算議案において仮称○町図書館建設負担金と明示の上で平成X年度分の支出並びにX+1年度及びX+2年度における債務負担行為が議決されたのを初めてとして、各年度ごとに予算として議決され、しかも各年度の決算においても、費目を明示した上で認定がされているのである。このようにX+2年度分支出命令をすべき時点までには、既に2回の分割払がされており、そのいずれもが議会の議決を経た予算に基づいていて、決算についても議会の認定を受けているのである以上、議会としても本件協定の存在を認識しつつ、これを是認していたと認めるのが相当であり、X+2年度分支出命令もまた、議会が議決した同年度予算に基づくものであることからすると、本件協定については、もはや区の側からはその無効を主張し得ない状態にあったと認めるのが相当である。そうである以上、X+2年度分の参加組合員負担金の支出も私法上やむを得ないものであって、これについての支出命令も有効なものといわざるを得ない。
定年条例の要件を満たさない一律的な現業職員の勤務延長措置の実施に伴い給与を支出したことに対する住民訴訟において、首長部局のみならず教育委員会の職員に係る給与支出についても、これを違法とした事例 奈良地判平15.5.21判例地方自治253.46
(市は職員団体から、技能労務職員の給与水準が低く定年年齢も国家公務員や県内他市と比べ早いことから技能労務職員の定年引上げ要求を受けていたところ、市としては定年延長には難色を示しつつも要綱を定めて60歳の定年後の勤務延長を行うこととし、申出者のほぼ全員を勤務延長して給与を支出した。本判決は前提として、対象勤務延長について、定年条例所定の勤務延長要件(ひいては地方公務員法28条の3第1項所定の前提要件)に該当しない違法なものであると判断している)
○ 本件各職員についての本件勤務延長は、いずれも定年条例4条1項各号の要件をみたさない違法なものであるところ、原告らは、本件各支出命令が本件勤務延長を直接の原因とし、これと不可分一体のものであるから、本件勤務延長が違法である以上、本件各支出命令も違法であると主張する。しかし、当該職員の財務会計上の行為をとらえて地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づく損害賠償責任を問うことができるのは、これに先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、上記原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解するのが相当である(最高裁判所平成4年12月15日第三小法廷判決・民集46巻9号2753頁参照)。そこで、本件各支出命令について、それら自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるか否かについて検討する。
○ 本件各支出命令を行うにつき、市長は、支出命令について本来的な権限を有しており、その権限に基づき、適否を審査する義務も課されているというべきであるから、予算執行権限を有する市長としては、各支出命令の段階においてもこれを是正すべき財務会計法規上の行為規範が課されているというべきであり、そして、市長から上記予算執行権限を専決させられた職員に対しても、本来の権限者である市長と同様の行為規範が課されているというべきであるところ、前記のように本件勤務延長が違法であることから、被告○は、予算執行権限を有する市長として、そもそも勤務の延長の承認をせず、また、各支出命令の段階においてもこれを是正すべき財務会計法規上の行為規範が課されているというべきである。
○ なお、本件職員E、F、G、H、I及びJについては、本件勤務延長の発令が教育長により行われたことから、各支出命令が上記の観点から財務会計法規上の義務に違反し違法となるか否かが問題となる。地方教育行政法は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱その他地方公共団体における地方教育行政の組織及び運営の基本を定めるものであり(同法1条)、教育委員会の権限について、同法23条は、教育委員会が、学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止、教育財産の管理、教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事などを含む、地方公共団体が処理する教育に関する事務の主要なものを管理、執行する広範な権限を有するものと定めている。もっとも、同法は、地方公共団体が処理する事務のすべてを教育委員会の権限事項とはせず、同法24条において地方公共団体の長の権限に属する事務をも定めているが、その内容を、大学及び私立学校に関する事務(1、2号)を除いては、教育財産の取得及び処分(3号)、教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の締結(4号)並びに教育委員会の所掌に係る事項に関する予算の執行(5号)という、いずれも財務会計上の事務のみにとどめている。すなわち、同法は、地方公共団体の区域内における教育行政については、原則として、これを、地方公共団体の長から独立した機関である教育委員会の固有の権限とすることにより、教育の政治的中立と教育行政の安定の確保を図るとともに、他面、教育行政の運営のために必要な、財産の取得、処分、契約の締結その他の財務会計上の事務に限っては、これを地方公共団体の長の権限とすることにより、教育行政の財政的側面を地方公共団体の一般財政の一環として位置付け、地方公共団体の財政全般の総合的運営の中で、教育行政の財政的基盤の確立を期することとしたものと解される。上記のような教育委員会と地方公共団体の長との権限の配分関係にかんがみると、教育委員会がした学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関する処分については、地方公共団体の長は、上記処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合でない限り、上記処分を尊重しその内容に応じた財務会計上の措置をとるべき義務があり、これを拒むことは許されないと解するのが相当である。なぜなら、地方公共団体の長は、関係規定に基づき予算執行の適正を確保すべき責任を地方公共団体に対して負担するものであるが、反面、同法に基づく独立した機関としての教育委員会の有する固有の権限内容にまで介入し得るものでなく、このことから、地方公共団体の長の有する予算の執行機関としての職務権限には、自ずから制約が存するからである(前掲最高裁判所平成4年12月15日判決)。これを本件についてみると、本件各支出命令のうち、本件職員E、F、G、H、I及びJについての勤務延長は、いずれも定年条例4条の要件を欠くものであるところ、前記で認定した当時の市における定員配置の状況などからみて、本件職員E、F、G、H、I及びJがそれぞれの職場において果たしていた役割など被告らが主張する事情を考慮しても、これらの職員の勤務延長が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものというべきである。
○ そうすると、市長は、上記のとおり、支出命令について本来的な権限を有しており、その権限に基づき、適否を審査する義務も課されているというべきであるから、予算執行権限を有する市長としては、各支出命令の段階においてもこれを是正すべき財務会計法規上の行為規範が課されているというべきであり、そして、市長から上記予算執行権限を専決させられた職員に対しても、本来の権限者である市長と同様の行為規範が課されているというべきであるところ、前記のように本件勤務延長が違法であるのみならず、著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するものというべきであることから、被告○は、予算執行権限を有する市長として、そもそも勤務の延長の承認をせず、また、各支出命令の段階においてもこれを是正すべき財務会計法規上の行為規範が課されているというべきであり、市長から上記予算執行権限を専決させられた企画調整部長としても、市長と同様の行為規範が課されているというべきであった。そうすると、本件各支出命令は、企画調整部長が、上記行為規範に反して、何らの是正措置をとらずになしたものであるから、財務会計法規に反して違法なものであると解される。
町の公共施設建設に係る工事請負代金差止請求訴訟において、工事請負契約の違法性と先行する設計委託契約違法性の関連を否定した事例 名古屋地判平15.10.30判例地方自治257.16
(町は公共施設建設に際しS社に土地利用調査委託を行い、その後業者を指名し設計コンペを行ったが指名業社の中にS社が含まれており、実際に設計を行うこととなったのもS社であった。その後前記設計内容に基づく工事請負契約が建設会社等と締結された。本件はこの工事請負契約に基づく支出の差止めを求める住民訴訟であり、その論拠は設計での概算工事費が高額に過ぎるという点にあると解される)
○ 原告らは、本件支出(より具体的には、本件各請負契約(注:工事請負契約のこと)に基づく請負代金の支出を命ずる支出命令((地方自治)法232条の4第1項。以下「本件支出命令」という。)を指すものと解される。)の差止めを求める根拠として、当該支出命令そのものに内在する違法を主張するものではなく、専ら本件各請負契約の目的たる建設工事の指針である本件設計の形成過程において行われた本件設計競技及び本件設計契約並びに本件各工事入札の違法等を主張するので、まず、本件支出の適否に関する判断の枠組みを検討する。
○ この点、法242条の2の規定に基づく住民訴訟は、普通地方公共団体の執行機関又は職員による法242条1項所定の財務会計上の行為の違法な行為又は怠る事実の予防又は是正を裁判所に請求する権能を住民に与え、もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とするものであり、法242条の2第1項1号の規定に基づく当該執行機関又は職員に対する差止請求訴訟は、このような住民訴訟の1類型として、財務会計上の行為を行う権限を有する当該執行機関又は職員に対し、職務上の義務に違反する財務会計上の行為の差止めを求めるものにほかならないから、同規定に基づき、当該執行機関又は職員の財務会計上の行為の差止めを求めることができるのは、たとえこれに先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、その原因行為を前提としてする当該執行機関又は職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解するのが相当である(最高裁判所平成4年12月15日第三小法廷判決・民集46巻9号2753頁参照)。
○ 上記のとおり、本件において、原告らが被告に対して差止めを求める財務会計上の行為は、本件各請負代金に係る本件支出命令であるところ、このように、基礎となる支出負担行為が契約である場合に、当該契約が私法上当然に無効といえないときは、普通地方公共団体は契約の相手方に対して当該契約に基づく債務を履行すべき義務を負うのであるから、仮に当該契約に無効をもたらさない程度の違法が存在するとしても、同債務の履行上の手続として行われる支出命令自体は違法ということはできず、このような場合に住民が法242条の2第1項1号所定の住民訴訟の手段によって普通地方公共団体の執行機関又は職員に対し、その差止めを請求することは許されないものというべきである(最高裁判所昭和62年5月19日第三小法廷判決・民集41巻4号687頁参照)。そうすると、本件においては、原告らが主張する違法事由によって、本件支出命令に対応する支出負担行為としての本件各請負契約が私法上当然に無効を来すといえる場合に限って、本件支出命令自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものになると考えられる。以下、この見地に立って、原告らの主張につき検討する。
○ 原告らは、まず、本件設計競技が、被告の主張するように随意契約である本件設計契約の前置手続であることを否定した上で、一般競争入札とされるべきであるにもかかわらず、恣意的に選定された6社による指名競争入札として実施されたものであり、また最低価格入札者以外の者を落札者にする場合には、その決定基準を定め、公告すべきところ、これらが欠けている点が法234条2項に反し、さらに、そうした手続であるにもかかわらず、同競技において概算事業費の高額な案が選定された点が法2条14項に反するから、違法である旨主張する・・・。その趣旨は必ずしも明らかではないものの、本件事業施設の詳細な設計条件が本件設計競技実施要領により確定されている以上、その設計行為に創意工夫は必要のないはずであるから、本件設計契約は一般競争入札の方法によって締結されるべきであったとの主張を前提とした上、本件設計競技を本件設計契約の相手方を確定する指名競争入札手続ととらえ、この手続によってS社を相手方として選定した本件設計契約は違法であると主張しているものと解されるところ、なるほど、一般論としては、法234条2項、令167条の要件を欠き、一般競争入札以外の方法が許されないのに、指名競争入札(あるいは被告の主張する随意契約)の方法によって締結された契約は違法であり、更に契約締結の方法に制限を加える法令の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められれば、これが私法上も無効となる場合もあり得ると解される(前掲最高裁判所昭和62年5月19日第三小法廷判決参照)。しかしながら、本件において適否が問題とされているのは、先に指摘のとおり、本件各請負契約を支出負担行為とする本件各請負代金の支出命令(本件支出命令)であるところ、本件設計契約の内容は、委託を受けたS社が本件施設の設計を完成して設計図書を引き渡し、委託した町が委託代金を支払うものであるのに対し、本件各請負契約のそれは、請負人である建設会社等が建設等を完成して建築物等を引き渡し、注文者である町が請負代金を支払うものであって、法的には両者はそれぞれ目的、契約当事者、給付の内容を異にし、それぞれが完結した契約であるから、仮に本件設計契約に手続上の瑕疵が存したとしても、これに基づいて本件設計が完了し、その成果物である設計図書が町に引き渡されるなど、実体的に債務の本旨に従った履行がなされたことが客観的に明らかである以上、上記設計図書で定められた本件施設の建設を目的とする本件請負契約が無効となる余地は存在しないというべきである。このことは、請負契約の相手方が設計契約の相手方と異なる場合、設計契約の無効事由を知る由もなく、それにもかかわらず請負契約まで無効とされたのでは請負契約の相手方の地位が害されることからも裏付けられる。
○ そうすると、原告らが、本件設計競技ないし本件設計契約の違法をもって本件支出命令の違法原因として主張するのは、それ自体失当というほかない。
県のダム建設負担金支出を対象財務会計行為とする住民訴訟において、ダム建設の前提となる基本計画のダム負担金支出を対象財務会計行為とする住民訴訟において、需要水量の見積に過大の点はあるとしても将来的な当ダムの水需要が無しと断定することができず、また本支出は県がした費用負担同意を前提とし議会の議決も経ていることからすれば、負担金支出原因である納付通知が著しく合理性を欠き、そのためこれに県の健全な財政運営の見地から看過し得ない瑕疵が存するとも予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するとも認められないとした事例 岐阜地判平15.12.26判例時報1859.43
(内閣総理大臣の定める○水系水資源開発基本計画(フルプラン)により建設されたTダムにつき県は関係法に基づき費用負担を合意し、水資源開発公団(当時)の納付通知により負担金を支出しており、平成42年度まで負担金支出は継続する予定である)
○ 原告らは、新フルプランの平成12年度までの都市用水増加量予測約330立方メートル/日は著しく過大であり、平成12年度以降においてもTダムの水需要はないから、このように水需要予測を著しく誤った新フルプランは違法であり、その違法性がその後の事業実施計画の作成と認可、本件負担金の納付通知に承継されるところ、違法な納付通知には支払義務がないから、本件負担金の支出命令及び支出は違法であると主張する。
○ ところで、住民訴訟において、当該職員の財務会計上の行為をとらえて地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づき損害賠償責任を問うことができるのは、たとえこれに先行する原因行為に違法事由が存在する場合であっても、上記原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解するのが相当である(最高裁平成4年12月15日第三小法廷判決・民集46巻9号2753頁参照)。そして、この理は、地方自治法242条の2第1項1号の規定に基づく差止請求についても基本的に同様であるが、損害賠償請求と差止請求の性格の相違から、差止請求については、当該支出命令ないし支出が財務会計法規が要請する健全な財政運営に違反する違法なものであるときに限られると解するのが相当である。そして、本件のように、内閣総理大臣が閣議決定を経てフルプランを決定し、同決定に基づいて建設大臣が事業実施方針を策定してこれを(水資源開発)公団に指示し、同指示に基づいて公団が事業実施計画を策定して建設大臣の認可を受け、建設事業者の負担については県の同意を得た上で、公団が県に対して本件負担金の納付通知を発したという事案においては、上記納付通知が著しく合理性を欠き、そのためこれに県の健全な財政運営の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合に本件負担金の支出命令及び支出が違法となる、また、上記納付通知が著しく合理性を欠き、そのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合に被告県知事及び同県出納長は本件負担金を支出してはならない義務を負うと解するのが相当である。
○ 新フルプランの平成12年度までの都市用水増加量予測が現実の増加量に対比して過大であったことは原告ら主張のとおりであるが、水需要予測は多くの不確定要因に左右されざるを得ない性質のものである上、将来の長期間にわたってのものであることを考慮すると、今後もTダムの水需要はないと断定することはできないというべきである。また、本件負担金の支出は、県がなした本件費用負担同意(これが裁量権の範囲を逸脱するものでないことは後記のとおり。)を前提とし、県議会の予算承認議決を得ていることをも考慮すると、上記納付通知が著しく合理性を欠き、そのためこれに県の健全な財政運営の見地から看過し得ない瑕疵が存するとも、また、予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するとも認められないというべきである。
【最高裁判例】 県が職務専念義務の免除をするとともに勤務しないことの承認をして、いわゆる第3セクター方式により設立された株式会社に県職員を派遣しその給与を支出した場合において、上記派遣が、同社に事業収入がなく同社が十分な人材を確保していないことを考慮して行われたこと、同社の事業内容は遊園施設等の経営であったこと、派遣職員が従事した職務の内容は同社の業務全般に及んでいたこと、派遣人数は延べ13人、派遣期間は約7年間に及んだことなど判示の事実関係の下においては、上記給与支出は、違法である 最判平16.1.15民集58.1.156
(事実関係は概ね上記の通り)
○ 職務専念義務の免除及び勤務しないことについての承認について明示の要件が定められていない場合であっても,処分権者がこれを全く自由に行うことができるというものではなく,職務専念義務の免除が服務の根本基準を定める地方公務員法30条や職務に専念すべき義務を定める同法35条の趣旨に違反したり,勤務しないことについての承認が給与の根本基準を定める同法24条1項の趣旨に違反する場合には,これらは違法となると解すべきである(前掲第二小法廷判決参照(注:上掲最判平10.4.24集民188.275))。
○ そこで,これを本件についてみると,前記第1の事実関係によれば,1 本件職員派遣は,第1審被告会社との連絡調整の必要のみでなく,第1審被告会社が設立されたばかりで事業収入がなく,十分な人材を確保していないことを考慮して行われたものであった,2 第1審被告会社は営利を目的とする株式会社であり,その具体的な事業内容は遊園施設等の経営であった,3 本件派遣職員が従事した職務の内容は,第1審被告会社の組織体制の確立,社員教育,資金調達等,第1審被告会社の業務全般に及んでいた,4 第1審被告会社には,常時2人から6人の職員が派遣され,派遣人数は延べ13人,派遣期間は約7年間に及んだというのであるから,第1審被告会社が県の推進する○公園の建設,運営のために県等が出資して設立された株式会社であること等を考慮しても,本件職務専念義務の免除が本件免除規則2条2号所定の要件を満たすものであるということはできず,本件承認は,地方公務員法24条1項の趣旨に反する違法なものというべきである。 そうすると,本件承認を是正することなく,これを前提にして行われた本件派遣職員に対する給与支出は違法というべきであり,これと同旨の原審の判断は是認することができる。
【最高裁判例】 市長が市を代表するとともに相手方を代理し又は代表して契約を締結した場合において、議会が市長による上記行為を追認したときは、民法116条の類推適用により市に法律効果が帰属する 最判平16.7.13民集58.5.1368
(市の事業である博覧会の準備及び開催運営を行うことを唯一の目的として設立された財団法人が上記事務を行ったが博覧会の入場料収入等だけではその開催運営経費を賄いきれないことから、赤字回避目的で市と当該法人との間で博覧会の施設及び物品を買い受ける旨の契約を締結した。契約書の名義人は市、当該法人とも、各団体代表者としての1審被告A1(市長)名であった。なお当該団体は市長が会長(理事)、市助役が副会長(理事)、市収入役が監事、市幹部職員が専務・常務理事役職を占め、職員も市職員を中心に構成されており、財団寄附行為では会長が団体を代表し、重要事項は理事会で決するとされていた。契約の決裁は市、団体とも市長もしくは会長たるA1または規程上の所定の権限者が行なっている。議会は、契約、予決算についてこれを承認する内容の議決を行った)
○ 普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約締結行為であっても,長が相手方を代表又は代理することにより,私人間における双方代理行為等による契約と同様に,当該普通地方公共団体の利益が害されるおそれがある場合がある。そうすると,普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結には,民法108条が類推適用されると解するのが相当である。そして,普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表するとともに相手方を代理ないし代表して契約を締結した場合であっても同法116条が類推適用され,議会が長による上記双方代理行為を追認したときには,同条の類推適用により,議会の意思に沿って本人である普通地方公共団体に法律効果が帰属するものと解するのが相当である。
○ これを本件についてみると,前記第1の事実関係等によれば,本件各契約・・・中には,市において代決によって締結された契約や第1審被告協会において会長に代わって決裁することとされている者により締結された契約があるが,対外的にはいずれも第1審被告A1の名をもって行われたということができるから,本件各契約・・・は,第1審被告A1の双方代理行為により締結されたものであるというべきである。しかしながら,前記第1の事実関係等によれば,市議会は,第1審被告A1を会長とする第1審被告協会との間で本件各契約・・・が締結されたことを十分認識して,前記・・・のとおり審査や議決をしたものということができるから,本件各契約・・・を追認したというべきである。また・・・によれば,第1審被告協会においても同様に追認があったというべきである。
【最高裁判例】 町の財産の適正な対価によらない譲渡・貸付けにつき地方自治法237条2項の議会の議決があったというためには、議会において当該譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上当該譲渡等を行うことを認める趣旨の議決がされたことを要する 最判平17.11.17集民218.459
(町の財産を低廉に売却したとする住民訴訟。代金収入は事後提出の補正予算に計上され、単価の適正性について質問があったところ、執行部からは、近傍区域の類似の取引事例における単価を参考にして上記単価を決定したことなどの説明があり、補正予算は可決された)
○ 地方自治法237条2項は,条例又は議会の議決による場合でなければ,普通地方公共団体の財産を適正な対価なくして譲渡し,又は貸し付けてはならない旨規定している。一方,同法96条1項6号は,条例で定める場合を除くほか,財産を適正な対価なくして譲渡し,又は貸し付けることを議会の議決事項として定めている。これらの規定は,適正な対価によらずに普通地方公共団体の財産の譲渡等を行うことを無制限に許すとすると,当該普通地方公共団体に多大の損失が生ずるおそれがあるのみならず,特定の者の利益のために財政の運営がゆがめられるおそれもあるため,条例による場合のほかは,適正な対価によらずに財産の譲渡等を行う必要性と妥当性を議会において審議させ,当該譲渡等を行うかどうかを議会の判断にゆだねることとしたものである。このような同法237条2項等の規定の趣旨にかんがみれば,同項の議会の議決があったというためには,当該譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上当該譲渡等を行うことを認める趣旨の議決がされたことを要するというべきである。議会において当該譲渡等の対価の妥当性について審議がされた上当該譲渡等を行うことを認める趣旨の議決がされたというだけでは,当該譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上議決がされたということはできない。
○ これを本件についてみると,原審は,町議会が本件補正予算を可決するに当たり本件譲渡が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上その議決がされた事実を確定しておらず,原審が確定した事実関係の下においては,本件補正予算の可決をもって本件譲渡につき地方自治法237条2項の議会の議決があったということはできない。
首長は、財務会計行為を行うに当たりその原因となっている自己の権限に属する非財務会計行為に違法事由が存するか否かを審査、調査しなければならず、自己の権限に属する原因行為に違法事由があるのにもかかわらず、それに対する是正措置を執らずに財務会計行為に及んだ場合には、当該財務会計行為は、財務会計法規上の義務である誠実執行義務に違反し違法になると解すべきであり、この理は原因行為が不作為であったとしても異ならないとの前提のもと、違法な接待により減給処分を受けた教育長の教育委員会委員職の罷免措置を取らず給与を支給した首長の財務会計行為には違法がないとした事例 大阪地判平19.5.22判例地方自治299.74
(汚職事件に絡み接待を受けていた教育長A、教育監Bに教育委員会が減給処分をしたところ、懲戒免職処分ではなく減給処分として首長Cが給与を支給したことは違法な財務会計行為であるとする住民訴訟。下記は、本件判示事項のうち、首長の権限に属する教育長(たる教育委員会委員:旧地教行法による)の罷免権行使の当否およびその行使の有無を前提とした財務会計行為たる給与支出の当否判断に関する部分である)
○ 地教行法によれば、教育委員会は、教育長の任免権、懲戒処分権限を有する(同法16条2項、地方公務員法6条1項、地教行法23条3号、同法16条3項、地方公務員法29条)が、地方公共団体の長は、教育長の懲戒処分権限を有しない。もっとも、教育委員の中から任命された教育長が、その教育委員の職を罷免等された場合には、当然に、その職を失うことになり(地教行法16条2、4項)、地方公共団体の長は、当該地方公共団体の議会の同意を得て、教育委員を罷免することができる(地教行法7条1項)から、地方公共団体の長は、教育長を議会の同意を得て罷免する権限(正確には、教育長の身分のうち教育委員たる身分を罷免する権限をいう。)を有しているといえる。したがって、知事は、教育長であるAを罷免する権限と本件支出決定1(注:教育長Aに対する給与支給)をする権限とのいずれも有していたことになる。そして、地方公共団体の長は、財務会計行為を行うに当たり、その原因となっている自己の権限に属する非財務会計行為に違法事由が存するか否かを審査、調査しなければならず、自己の権限に属する原因行為に違法事由があるのにもかかわらず、それに対する是正措置を執らずに財務会計行為に及んだ場合には、当該財務会計行為は、財務会計法規上の義務である誠実執行義務に違反し、違法になると解すべきであり、この理は、原因行為が不作為であったとしても異ならないというべきである。したがって、本件支出決定1は、Aに対する本件減給処分1(注:教育長Aに対する減給処分)が著しく合理性を欠くにもかかわらず、Cが教育委員会に対し何らの働きかけも行わなかった場合・・・のほか、CのAに対する罷免権限の不行使が違法といえる場合にも、違法になると解すべきである。もっとも、地教行法7条1項は、同項所定の罷免事由について、概括的な定めをするに留めていることからすれば、地方公共団体の長は、罷免事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該教育委員の態度、処分歴、罷免することが他の公務員及び社会に与える影響等、諸般の事情を考慮し、地方公共団体の議会の同意を得て罷免すべきかどうかを決定する裁量権を付与されていると解すべきであり、罷免権者である地方公共団体の長の判断が違法となるのは、かかる裁量権の行使ないし不行使が社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権を付与した目的を逸脱し、これを濫用したと認められるような例外的な場合に限られるというべきである。
○ 以上を前提に本件についてみると、・・・Aは、平成16年2月に・・・関係者から料亭で飲食の接待を1回受けたことは認められるが、他方で、Aは、上記接待について2万円相当の品物を送付する形で費用負担をしていること、Aは、飲食の接待を受けた際に職務に関連して便宜供与を求められたり、また、便宜を図ったことはなかったこと、Aに対してされた減給3か月の処分は減給処分としては最も重い処分であることが認められる。そうすると、Aの上記行為は、教育行政のトップの地位にある者の行為として、(住民)の不信や疑惑を招く不適切なものではあったことは明らかであるが、Aの上記行為に対して教育委員会が行った本件減給処分1が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するとも、Cが議会の同意を得た上でAを罷免しなかったことが裁量権の逸脱、濫用にあたるともいえず、Cに財務会計法規上の義務違反があったとはいえない。
○ したがって、本件支出決定1が財務会計法規上の義務に違反してされた違法なものということはできないというべきである。
【最高裁判例】 自治体が土地開発公社との間で締結した土地の先行取得の委託契約に基づく義務の履行として,当該公社が取得した当該土地を買い取る売買契約を締結する場合であっても,次の(1)又は(2)のときには,当該売買契約の締結は違法となる
(1) 上記委託契約を締結した自治体の判断に裁量権の範囲の著しい逸脱又は濫用があり,当該委託契約を無効としなければ地方自治法2条14項,地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められるなど,上記委託契約が私法上無効であるとき
(2) 上記委託契約が私法上無効ではないものの,これが違法に締結されたものであって,自治体がその取消権又は解除権を有している場合や,当該委託契約が著しく合理性を欠きそのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存し,かつ,客観的にみて自治体が当該委託契約を解消することができる特殊な事情がある場合であるにもかかわらず,自治体の契約締結権者がこれらの事情を考慮することなく漫然と上記売買契約を締結したとき 最判平20.1.18民集62.1.1
(市は,X年12月19日,土地開発公社との間において,本件土地につき代金約3800万円で先行取得を行うことを公社に委託する旨の委託契約を締結した。委託契約において,市は,本件土地を本件公社から上記先行取得の代金の額にその調達のための借入れの利息等の額を加えた金額でX+6年3月31日までに買い取るべきこととされていた。公社は,X年12月24日,委託契約に基づき,本件土地を上記同額(約3800万円)で取得した。市は,X+6年3月18日,委託契約に基づき,本件公社との間において,本件土地を代金約4200万円で買い受ける旨の本件売買契約を締結し,同月29日,本件公社に対し,上記代金をすべて支払った。上記代金の額は,前記先行取得の代金の額に借入れの利息の額を加えた金額であった)
○ 地方自治法242条の2第1項4号の規定に基づく代位請求に係る当該職員に対する損害賠償請求訴訟は,財務会計上の行為を行う権限を有する当該職員に対し,職務上の義務に違反する財務会計上の行為による当該職員の個人としての損害賠償義務の履行を求めるものであるから,当該職員の財務会計上の行為がこれに先行する原因行為を前提として行われた場合であっても,当該職員の行為が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときは,上記の規定に基づく損害賠償責任を当該職員に問うことができると解するのが相当である(最高裁昭和61年(行ツ)第133号平成4年12月15日第三小法廷判決・民集46巻9号2753頁参照)。
○ 土地開発公社が普通地方公共団体との間の委託契約に基づいて先行取得を行った土地について,当該普通地方公共団体が当該土地開発公社とその買取りのための売買契約を締結する場合において,当該委託契約が私法上無効であるときには,当該普通地方公共団体の契約締結権者は,無効な委託契約に基づく義務の履行として買取りのための売買契約を締結してはならないという財務会計法規上の義務を負っていると解すべきであり,契約締結権者がその義務に違反して買取りのための売買契約を締結すれば,その締結は違法なものになるというべきである。
○ 本件において,仮に,本件土地につき代金(約3800万)円で先行取得を行うことを本件公社に委託した市の判断に裁量権の範囲の著しい逸脱又は濫用があり,本件委託契約を無効としなければ地方自治法2条14項,地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められるという場合には,本件委託契約は私法上無効になるのであって,前記・・・のように,本件土地を取得する必要性及びその取得価格の相当性の有無にかかわらず本件委託契約が私法上無効になるものではないとして本件売買契約の締結が違法となることはないとすることはできない。
○ また,先行取得の委託契約が私法上無効ではないものの,これが違法に締結されたものであって,当該普通地方公共団体がその取消権又は解除権を有しているときや,当該委託契約が著しく合理性を欠きそのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存し,かつ,客観的にみて当該普通地方公共団体が当該委託契約を解消することができる特殊な事情があるときにも,当該普通地方公共団体の契約締結権者は,これらの事情を考慮することなく,漫然と違法な委託契約に基づく義務の履行として買取りのための売買契約を締結してはならないという財務会計法規上の義務を負っていると解すべきであり,契約締結権者がその義務に違反して買取りのための売買契約を締結すれば,その締結は違法なものになるというべきである。
○ 本件において,仮に本件委託契約が私法上無効ではなかったとしても,上記のような場合には,本件売買契約の締結は財務会計法規上の義務に違反する違法なものになり得るのであって,前記・・・のように,市が本件委託契約上本件土地を買い取るべき義務を負っていたことから直ちに本件売買契約の締結が違法となることはないとすることもできない。
○ そうすると,本件委託契約が私法上無効であるかどうか等について審理判断することなく,本件売買契約の締結が本件委託契約に基づく義務の履行であることのみを理由として,市の契約締結権者が本件売買契約を締結してはならないという財務会計法規上の義務を負うことはないとすることはできないものというべきである。
市が市の出資会社が所有するビルの賃借にあたり適正賃料より高額な金額で賃貸借契約を締結し賃料を支出することに対する住民訴訟において、平成20年1月18日最判の判断枠組みに照らし、当該賃料の支出命令は違法ではないとした事例 大阪地判平20.6.26判例タイムズ1282.131
(市は市出資会社所有ビルの賃貸借契約を締結し賃料を支出したが、その賃料は適正賃料と鑑定された額の1.数倍であった。ただし当ビルの他の民間賃借人の賃料には相当のバラツキがあり、市の賃料がこれと比べ突出して高額とは認め難い事情が存在する)
○ ・・・本件で問題とされている支出命令は、W・・・契約及びA・・・契約の履行として、賃料等を支出する前提として行われる財務会計上の行為である。一般に、賃貸借契約を締結した賃借人は、当該賃貸借契約を締結した以上、その効力として、賃料の支払義務を免れないが、この点は、当該賃借人が地方公共団体であったとしても何ら変わるところはない。したがって、賃借人たる地方公共団体は、原則として、賃貸借契約に基づいて賃料の支出及びその前提としての支出命令をする義務を負う。しかし、当該賃貸借契約が私法上無効である場合、又は当該地方公共団体がその取消権又は解除権を有しているときや、当該賃貸借契約が著しく合理性を欠き、そのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存在し、かつ、客観的にみて当該地方公共団体が当該賃貸借契約を解消することができる特殊な事情にある場合には、支出命令権者は、当該賃貸借契約の効力を否定して賃料支払義務から脱却すべき義務を負っているというべきであり、そうであるにもかかわらず漫然と支出命令を行った場合には、当該支出命令は違法となるというべきである(最高裁平成20年1月18日第二小法廷判決・判例タイムズ1261号145頁参照)。
○ そこで、本件において、W・・・契約及びA・・・契約が私法上無効といえるか否か、仮に私法上無効ではないとしても、当該地方公共団体がその取消権又は解除権を有しているときや、当該賃貸借契約が著しく合理性を欠き、そのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存在し、かつ、客観的にみて当該地方公共団体が当該賃貸借契約を解消することができる特殊な事情にある場合といえるか否かについて検討する。
○ まず、原告らは、W・・・契約及びA・・・契約が、地方公共団体の経費はその目的を達成するための必要かつ最小の限度を超えて支出してはならないとの趣旨を定めた地方財政法4条1項及びこれと同趣旨の地方自治法2条14項に違反するため無効であると主張する。しかし、これらの規定は、地方公共団体の長その他の職員が、予算の執行として契約の締結その他の支出負担行為を行うに当たり、当該行為の具体的な事情に照らして、最も少ない額をもって目的を達成するように努める法的な義務を課したものと解されるから、より少ない金額で所期の目的を達成できることが明らかであるのにあえてそれを大きく超えた条件で支出負担行為をした場合のように、長その他の職員に与えられた裁量権の範囲の著しい逸脱又は濫用があり、当該行為を無効にしなければ地方自治法2条14項、地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、当該契約が私法上も無効となるというべきである。そこで、本件において、そのような特段の事情が認められるか否かを検討する。
○ ・・・W・・・契約及びA・・・契約の約定賃料等と本件鑑定に係る適正賃料等は、それぞれ・・・記載のとおりであり、そのすべての契約において、上記約定賃料等は、適正賃料等を上回っており、それを倍率として表すと、W・・・契約について、適正賃料等の1.57倍~1.61倍、A・・・契約について、適正賃料等の1.23倍~1.99倍である。しかし、本件鑑定において指摘されているとおり、W・・・ビル及びA・・・ビルにおける賃料等には、極めて大きなばらつきがあり(例えば、W・・・ビルにおける平成9年度の賃料単価には、約6倍の差がある。)、上記適正賃料等付近に集中する賃料分布になっていない。そして、W・・・契約及びA・・・契約における約定賃料等が他の民間賃借人の賃料等と比較して、突出して高いとまではいえず、他の民間の賃借人の賃料等の賃料分布内に収まるものである。すなわち・・・A・・・契約1の締結(平成5年10月1日)に近接した平成6年5月1日当時、A・・・ビルの民間の賃借人(本件補助金の利益を受けていない者に限る。以下、A・・・契約につき同じ。)70社のうち、A・・・契約1の賃料等(7108円/月・m2)と同程度の賃料等区分(7001円~7500円/月・m2)に属する賃借人が11社、それ以上の賃料等区分での賃借人は13社あったこと、A・・・契約2~4の締結(平成7年5月1日~平成8年5月20日)に近接した平成7年4月1日当時、A・・・ビルの民間の賃借人60社のうち、13社がA・・・契約2~4(6957円/月・m2)と同程度の賃料等区分(6501円~7000円/月・m2)に属し、18社がそれ以上での賃料等区分に属していたこと、平成8年4月1日当時、A・・・ビルの民間の賃借人51社のうち、10社が上記同程度の賃料等区分に属し、5社がそれ以上の賃料等区分に属していたこと、A・・・契約5及び6の締結(平成12年4月1日、同月13日)に近接した平成12年4月1日当時、A・・・ビルの民間の賃借人94社のうち、9社がA・・・契約5(6957円/月・m2)と同程度の賃料等区分に属し、4社がA・・・契約6(7108円/月・m2)と同程度の賃料等区分に属し、14社がそれ以上の賃料等区分に属していたこと、W・・・契約1の締結(平成10年8月1日~平成12年9月1日)に近接した平成10年当時、W・・・ビルの民間の賃借人(外郭団体を除く。以下、W・・・契約につき同じ。)47社のうち、8社がW・・・契約1(5110円/月・m2)と同額以上の賃料で入居していたこと(賃料だけでいえば、9社であるが、このうち1社は、共益費が無料のため、賃料と共益費の合計は、W・・・契約1を下回るので除外した。)、W・・・契約2~5の締結(平成12年11月1日~平成14年12月1日)に近接した平成12年当時、W・・・ビルの民間の賃借人35社のうち9社がW・・・契約2~5(5110円/月・m2)と同額以上の賃料で入居していたこと(賃料だけでいえば、10社であるが、このうち1社は共益費が無料で、賃料と共益費の合計は、W・・・契約2~5を下回るので除外した。)が認められる。そして、前記のとおり、本件鑑定人が、W・・・ビル及びA・・・ビルの賃貸市場では、その市場参加者の誰もが認識できる賃料水準が形成されていないため、その賃料分析だけでは、適正な賃料水準の把握はできないとして、市中心部の巨大ビルの賃料水準や神戸ファッションマート、オーク一番街などの賃料水準などの比較検討を併せて行い、これらを総合考慮して本件適正賃料等を算定したことからも明らかなとおり、本件適正賃料等の把握は、必ずしも容易なことではない。しかも、W・・・社及びA・・・社としては、供給に比べて有効需要が伸び悩む中、W・・・ビル及びA・・・ビルを、できるだけ高い賃料で賃貸したいと考えているわけであり(本件鑑定によっても、賃貸事業採算性に着目する積算賃料は、相当高額である。)、いくら借り手市場であるからといって、市がその賃料を一方的に決めることはできず、両社との交渉の結果決まることになる。また、市は、W・・・ビル及びA・・・ビルの賃借人であるとともに、W・・・ビルを所有するW・・・社、A・・・ビルを所有するA・・・社の大口株主でもあり、両ビルの公共性も含め、賃料の交渉において要する考慮は、単純ではない。これらのことに照らせば、W・・・契約及びA・・・契約に係る契約賃料等の額が適正賃料額等を超過していたことは、前記のとおりであり、事後的に見れば、W・・・社及びA・・・社に対し、より強い姿勢で交渉に望み、より低い賃料等で契約することは可能であったといえるものの、上記各契約の賃料等の定めが、公序良俗に違反する程度にまで高いものといえないことはもとより、市において、より少ない金額で所期の目的を達成できることが明らかであるのに、あえてそれを大きく超えた条件で上記各契約を締結したものともいえない。そして・・・市は、概ね・・・経緯ないし目的でW・・・契約及びA・・・契約を締結したことが認められ、上記各契約を締結する必要性が認められること(なお・・・によれば、上記各契約により市が使用している各室の中には、十分な有効活用がされていないと思われるものもあるが、それは活用の仕方の問題であり、市が上記各契約を締結した当時、賃借する必要性がなかったことを推認させるものではない。)も併せて考えれば、W・・・契約及びA・・・契約には、当該行為を無効にしなければ地方自治法2条14項、地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となるほどの著しい裁量権の逸脱又は濫用があったとはいえず、私法上無効であったとはいえない。
○ 次に、原告らは、W・・・契約及びA・・・契約が私法上無効ではないとしても、本件では、市がその取消権又は解除権を行使し、又はW・・・契約及びA・・・契約が著しく合理性を欠き、そのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存在し、かつ、客観的にみて市がW・・・契約及びA・・・契約を解消することができる特殊な事情にある場合にあると主張する。しかし、W・・・契約及びA・・・契約は契約期間の定めのある賃貸借契約であって、中途解約権の留保もされていたとは認めるに足りないから、賃借人として賃貸借契約を一方的に解除することはできないし(民法618条参照)、直ちに一方的に賃料を減額させることも困難である。確かに、市は、W・・・契約及びA・・・契約の期間満了に当たり、異議を述べて契約更新を拒絶することも契約上可能ではあった。しかし、前記のとおり、市は、平成16年4月分以降、W・・・契約及びA・・・契約における賃料等の減額を申し入れてその合意に達したのであるから、十分であったとはいえないまでも、適正賃料等の額との乖離は一定程度減少したといえるし、・・・によれば、W・・・契約及びA・・・契約に係る賃借部分が、現に、市の事務所、BPCネットワークセンター、輸入住宅促進センター等として、上記各契約を締結した当初の目的に沿って使用され、一定の効用を上げていることが認められる(もっとも、現時点において有効活用の程度に差があることは、前記のとおりである。)ことや、仮にW・・・契約及びA・・・契約を解消するとすれば、別途事務所スペース等の確保及び移転費用も必要となることにかんがみれば、客観的にみて、市がW・・・契約及びA・・・契約を解消することが期待できる特殊な事情にあったとまではいえないというべきである。
○ 以上のとおり、W・・・契約及びA・・・契約が私法上無効であるとも、これらに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存在し、かつ、客観的にみて当該地方公共団体が当該賃貸借契約を解消することができる特殊な事情にある場合にあるともいえないから、W・・・契約及びA・・・契約に基づく賃料等の支出命令は違法とはいえないというべきである。
【最高裁判例】 市が土地開発公社に対し土地の先行取得を委託する契約が,私法上無効とはいえず,また市にその取消権又は解除権があるとはいえないものの,著しく合理性を欠き,そのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存する場合であっても,次の(1),(2)など判示の事情の下では,客観的にみて市が上記委託契約を解消することができる特殊な事情があったとはいえず,市が上記公社の取得した上記土地を上記委託契約に基づく義務の履行として買い取る売買契約を締結したことは,違法とはいえない
(1) 市長は公社の理事長を兼務していたものの,理事長として上記委託契約の解消の申入れに応ずることは,公社に損害を与え,職務上の義務違反が問われかねない行為である上,市は公社の設立団体の一つにすぎず,出資割合も基本財産の約14%を占めるにとどまっていたことなどから,市長が理事長として上記解消につき他の設立団体や理事の同意を取り付けることは困難が予想された
(2) 上記土地を公社に売却した者が公社との間で契約の解消に応ずる見込みが大きいとか,公社がこれを第三者に上記売買契約の代金額相当額で売却することが可能であるなどの事情は認められない 最判平21.12.17集民232.707
(市と土地開発公社との間で,土地の先行取得の委託契約を締結し,これに基づいて公社が取得した同土地の買取りのための売買契約を締結した)
○ 前記事実関係等によれば,本件公社は市とは別の法人格を有する主体であるところ,本件委託契約及びその内容を定める業務方法書において,市が自己都合により同契約を一方的に解消することができることをうかがわせる条項は存在しない。したがって,市が本件公社に事実上の働きかけを真しに行えば,本件公社において本件委託契約の解消に応ずる蓋然性が大きかったというような事情が認められない限り,客観的にみて市が本件委託契約を解消することができる特殊な事情があったということはできないものと解される。確かに,本件委託契約は上告人が市及び本件公社の双方を代表して締結したものであり,上告人は本件売買契約締結当時も市長と本件公社の理事長とを兼務していた。しかしながら,本件公社は公拡法(注:公有地の拡大の推進に関する法律)に基づき設立された公共性の高い法人であるところ,仮に本件委託契約を解消して本件公社が本件土地を引き受けることとした場合には,本件公社がその取得金額と時価との差額を損害として被ることとなるのであるから,上告人が本件公社の理事長として本件委託契約解消の申入れに応ずることは,本件公社との関係では職務上の義務違反が問われかねない行為である。しかも,市は,本件公社の設立団体の一つにすぎず,出資割合も基本財産の約14%を占めるにとどまり,また,本件公社の運営上の重要事項は理事会が議決するものとされているのであるから,上告人が本件公社の理事長として上記解消につき他の設立団体や理事の同意を取り付けることは一層の困難が予想されるものというべきである。他方,Aが本件売買契約の解消に応ずる見込みが大きいとか,本件土地を第三者に本件売買契約の代金額相当額で売却することが可能であるなどの事情があれば,本件公社においても本件委託契約解消の申入れに応ずる蓋然性が大きいということもできるが,本件においてそのような事情が認められないことは,前記事実関係等からも明らかである。他に,本件公社が市からの本件委託契約解消の申入れに応ずる蓋然性が大きいと認めるに足りる事情は見いだし難い。
○ このように,本件において,客観的にみて市が本件委託契約を解消することができる特殊な事情があったとはいえないのであるから,上告人は,市長として,有効な本件委託契約に基づく義務の履行として本件土地を買い取るほかはなかったのであり,本件土地を買い取ってはならないという財務会計法規上の義務を負っていたということはできない。したがって,本件売買契約が上告人に課されている財務会計法規上の義務に違反して違法に締結されたということはできないものと解するのが相当である。
【最高裁判例】 市が賃借人として締結した土地賃貸借契約が,従前は市が所有し,賃貸人の要求に応じて賃貸人に譲渡した土地を対象とするものであり,また,賃借人の側から更新をすることができず,賃料の減額も制限されるなど,賃貸人に有利なものである場合であっても,次の(1)~(3)など判示の事情の下においては,当該契約に基づく市長による賃料の支出は,違法ではない。
(1) 上記土地は,市内のため池の一部を埋め立てて工場用地とすること等を内容とする開発事業の区域内にあった賃貸人の所有地の代替地として要求されたものであり,その要求に応じなければ,市に相当程度の税収入の増加と雇用の創出をもたらす上記開発事業を実施することができない状況にあった。
(2) 上記土地は,上記ため池の残部を含み,上記開発事業に係る土地利用計画に残存緑地として組み込まれており,その現状を維持し保全するために当該契約を締結することは,上記開発事業の円滑な継続のために必要であり,上記土地上に存在する特徴ある陸生植物種が植生する湿地環境の保全にも資するものである。
(3) 市が当該契約の締結に際して上記のような内容の約定に応じたのは,賃借人の側からの更新の約定を設けることに応じない賃貸人が自ら契約を更新する動機付けとなるに足りる金額の賃料を支払うことによって事実上その永続的な更新を確保する趣旨によるものであり,その賃料が特に高額であるともいえない 最判平23.12.2集民238.237
(入会集団が事実上所有する土地に工場を立地するにあたり、事業計画に難色を示す入会集団との間で町が締結した入会集団に有利な外観を呈する土地賃貸借契約について提起された1・4号訴訟)
○ 本件において,仮に,本件賃貸借契約を締結した市の判断に裁量権の範囲の著しい逸脱又はその濫用があり,かつ,これを無効としなければ地方自治法2条14項,地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められるという場合には,本件賃貸借契約は私法上無効になり,上告人は,これに基づく賃料としての公金の支出をしてはならないという財務会計法規上の義務を負うことになるものというべきである(最高裁平成17年(行ヒ)第304号同20年1月18日第二小法廷判決・民集62巻1号1頁参照)。そして,上告人は,本件賃貸借契約の締結は本件開発事業の実施や本件土地の環境保全のために必要不可欠であったとの趣旨をいうところ,本件開発事業によって得られる税収入や雇用の増加といったいわゆる開発利益を実現したり,本件開発事業によって影響を受ける自然環境を保全したりするためにどの程度の公費を支出するか,これらの相対立する利益をいかに調整するかといった事柄に関する判断に当たっては,住民の福祉の増進を図ることを基本として地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う地方公共団体(地方自治法1条の2第1項)である市に,政策的ないし技術的な見地からの裁量が認められるものというべきである。したがって,本件賃貸借契約を締結した市の判断については,それがこれらの見地から上記のような事柄に係る諸般の事情を総合的に勘案した裁量権の行使として合理性を有するか否かを検討するのが相当である。
○ …によれば,旧C町が本件開発事業の実施を確保するために本件○区所有地を任意に取得しようとしたところ,当初これに反対し売却を拒否していた○区は,その後の交渉の結果,代替地として本件土地を要求したものであり,旧C町がその要求に応じなければ本件開発事業は実施することができない状況にあったものといえるし,旧C町が上記要求に応じ,○区が本件土地を取得するに至った経緯に照らし,○区による本件土地の取得に何らかの無効原因が存在したことをうかがわせる事情もない。また,これにより実施が可能となった本件開発事業によって,現に相当程度の税収入の増加と雇用の創出が図られたというのである。
そして,前記事実関係等によれば,本件土地は,本件開発事業に係る土地利用計画において残存緑地として組み込まれていたのであり,公社の理事長としてのAがB県知事との間の自然環境保全協定に基づき本件開発事業の区域内において本件土地を含む緑地を確保すべき責務を負っていたことをも併せ考慮すれば,本件土地の現状を残存緑地として維持し保全することは,本件開発事業の円滑な継続のために必要であるとともに,本件土地上に存在する特徴ある陸生植物種が植生する湿地環境の保全にも資するものということができる。そうすると,上記のとおり本件土地を代替地として○区に提供せざるを得なかった以上,同区の所有に帰した本件土地の現状をできる限り維持し保全するために本件賃貸借契約を締結しその賃料として公費を支出することには,一定の公益性が認められるというべきである。もっとも,本件賃貸借契約は,存続期間を6年間とし,賃借人である市の側から更新をすることができず,存続期間中であっても賃貸人から解約の申出ができる内容となっており,本件土地の現状を長期にわたり残存緑地として保全する方策としては万全なものとはいい難い点があり,また,賃料の減額も制限されるなど,かなり○区に有利なものであった。しかしながら,本件賃貸借契約の締結に際して市がこれらの約定に応じたのは,賃借人の側からの更新の約定を設けることに応じない○区が自ら契約を更新する動機付けとなるに足りる金額の賃料を支払うことによって事実上その永続的な更新を確保する趣旨によるものと解され,本件土地の現状の維持及び保全という観点からは現実的でやむを得ないものであって,次善の策ともいえ,当該契約の目的に照らして不合理であるとはいえない。さらに,その賃料が特に高額であるといった事情があるともいえない。このほか,○区が本件ため池の管理を明治時代以前から行ってきた経緯に加え,公社が本件開発事業による本件ため池の環境への影響について継続的に事後調査を行っていることをも併せ考慮すると,本件賃貸借契約において本件ため池の管理が○区ないし○自治会に委ねられている点も特に不自然であるとまではいえない。
○ 以上によれば,本件土地の現状を残存緑地として維持し保全するために○区との間で本件賃貸借契約を締結した市の判断には,相応の合理性があるというべきであり,裁量権の範囲の著しい逸脱又はその濫用があるということはできず,本件賃貸借契約が私法上無効になるものとはいえない。
○ そして,前記事実関係等に照らせば,○区ないし○自治会が本件○区所有地の存在を奇貨として旧C町ないし市に対し権利の濫用に当たるような著しく不当な要求をしたなどの事情があるとはいえず,他に,本件賃貸借契約が違法に締結されたものであるとか,それが著しく合理性を欠くためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存するなどといった,本件賃貸借契約に基づく賃料としての公金の支出が違法なものになることをうかがわせる事情(前記第二小法廷判決参照)も存しない。
○ したがって,本件賃貸借契約に基づく市の義務の履行として,Aが○区に対する約定の賃料としての公金の支出命令をしたこと及び上告人が○区に対する上記賃料としての公金の支出をすることに,財務会計法規上の義務に違反する違法な点はないものというべきである。
【最高裁判例】 住民訴訟の対象とされている自治体の不当利得返還請求権を放棄する旨の議会の議決がされた場合において、請求権の発生原因である公金の支出等の財務会計行為等の性質、内容、原因、経緯及び影響(その違法事由の性格や当該支出等を受けた者の帰責性等を含む)、当該議決の趣旨及び経緯、当該請求権の放棄又は行使の影響、住民訴訟の係属の有無及び経緯、事後の状況その他の諸般の事情を総合考慮して、これを放棄することが普通地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする地方自治法の趣旨等に照らして不合理であってその裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められるときは、その議決は違法となり、当該放棄は無効となる (同旨:最判平24.4.23下掲) 最判平24.4.20民集66.6.2583
(市が派遣出向者に対する給与を委託料・補助金の形で支出していたのは、派遣法の潜脱行為であるとする住民訴訟。派遣者は市の業務に従事せず、また市の給与負担につき派遣法6条2項および市条例の規定による手続をおこなっていなかった。市は派遣先団体に委託料・補助金を支出し、その一部が派遣職員の給与費に充てられた。その後本訴訟一審で請求が一部認容され同市が当事者の同趣旨の別件訴訟二審でも請求一部認容判決がなされた後、控訴審の口頭弁論終結後に派遣条例が改正され、改正条例附則で、本件訴訟に係る市の各請求権を含め市から派遣先団体等への補助金等その他の支出に係る派遣先団体等又は職員に対する市の不当利得返還請求権および損害賠償請求権(遅延利息・遅延損害金含む)を放棄することが定められた。本件訴訟二審口頭弁論は市側が再開を申し立て、上記条例により請求権が消滅したことが主張された。二審判決は、上記改正条例附則に係る市議会の議決は市長が行った違法な財務会計行為を放置し損害の回復を含めてその是正の機会を放棄するに等しく、また本件の住民訴訟を無に帰せしめるものであって地方自治法に定める住民訴訟の制度を根底から否定するものといわざるを得ず、議決権の濫用に当たりその効力を有せず本件附則もその効力を生じない、として請求を一部認容する判決をした)
○ 地方自治法96条1項10号は,普通地方公共団体の議会の議決事項として,「法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか,権利を放棄すること」を定め,この「特別の定め」の例としては,普通地方公共団体の長はその債権に係る債務者が無資力又はこれに近い状態等にあるときはその議会の議決を経ることなくその債権の放棄としての債務の免除をすることができる旨の同法240条3項,地方自治法施行令171条の7の規定等がある。他方,普通地方公共団体の議会の議決を経た上でその長が債権の放棄をする場合におけるその放棄の実体的要件については,同法その他の法令においてこれを制限する規定は存しない。したがって,地方自治法においては,普通地方公共団体がその債権の放棄をするに当たって,その議会の議決及び長の執行行為(条例による場合は,その公布)という手続的要件を満たしている限り,その適否の実体的判断については,住民による直接の選挙を通じて選出された議員により構成される普通地方公共団体の議決機関である議会の裁量権に基本的に委ねられているものというべきである。もっとも,同法において,普通地方公共団体の執行機関又は職員による公金の支出等の財務会計行為又は怠る事実に係る違法事由の有無及びその是正の要否等につき住民の関与する裁判手続による審査等を目的として住民訴訟制度が設けられているところ,住民訴訟の対象とされている損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を放棄する旨の議決がされた場合についてみると,このような請求権が認められる場合は様々であり,個々の事案ごとに,当該請求権の発生原因である財務会計行為等の性質,内容,原因,経緯及び影響,当該議決の趣旨及び経緯,当該請求権の放棄又は行使の影響,住民訴訟の係属の有無及び経緯,事後の状況その他の諸般の事情を総合考慮して,これを放棄することが普通地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする同法の趣旨等に照らして不合理であって上記の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められるときは,その議決は違法となり,当該放棄は無効となるものと解するのが相当である。そして,当該公金の支出等の財務会計行為等の性質,内容等については,その違法事由の性格や当該職員又は当該支出等を受けた者の帰責性等が考慮の対象とされるべきものと解される。
○ 本件についてこれをみるに,まず,本件補助金等の支出の性質及び内容に関しては,本件補助金等は派遣職員等の給与等に充てられるものとして支出されたものであり,その違法事由は,派遣職員等の給与等に充てられる公金の支出の適否に関する派遣法の解釈に係るものであるところ,前記・・・において説示したところによれば,市長はもとより本件各団体においてもその支出の当時これが派遣法の規定又はその趣旨に違反するものであるとの認識に容易に至ることができる状況にはなかったというべきであって,市からその交付を受けて本件派遣職員等の給与等の人件費に充てた本件各団体の側に帰責性があるとは考え難い。次に,本件補助金等の支出の原因及び経緯に関しては,本件各団体が不法な利得を図るなどの目的によるものではなく,派遣職員等の給与等の支給方法について市の側が補助金等の支出という方法を選択したことによるものであって,本件各団体がその支給方法の選択に自ら関与したなどの事情もうかがわれない。また,本件補助金等の支出の影響に関しては,前記・・・のとおり,本件各団体は本件旧条例等において派遣対象団体又は特定法人とされ,その業務の全部又は一部が公益の増進に寄与するとともに市の事務又は事業と密接な関連を有し,その施策の推進を図るため人的援助が必要であるものに該当するところ,本件補助金等は,派遣職員等の給与等の人件費という必要経費に充てられており,これらの派遣職員等によって補強,拡充された本件各団体の活動を通じて医療,福祉,文化,産業振興,防災対策,住宅供給,都市環境整備,高齢者失業対策等の各種サービスの提供という形で住民に相応の利益が還元されているものと解され,本件各団体が不法な利益を得たものということはできない。
○ そして,以上を前提として,本件附則に係る議決の趣旨及び経緯についてみるに,前記・・・の一連の経過に照らせば,市議会の議決を経て成立した本件附則を含む本件改正条例全体の趣旨は,派遣職員の給与については,市が派遣先団体に支出する補助金等をこれに充てる方法を採らずに,派遣法6条2項を根拠に定める条例の規定に基づき市が派遣職員に直接支給する方法を採ることを明らかにしたものであり,前者の方法を違法とした第1審判決の判断を尊重し,派遣法の趣旨に沿った透明性の高い給与の支給方法を採択したものということができる。また,仮に,既に本件派遣職員等の給与等の人件費に充てられた本件補助金等を直ちに返還することを余儀なくされるとすれば,本件各団体の財政運営に支障が生じ得るところであり,前記・・・のとおり,市議会での審議の過程において,これにより公益的事業の利用者たる住民一般が被る不利益等を勘案した議論がされていること等に鑑みると,本件附則に係る議決は,公益の増進に寄与する派遣先団体等として住民に対する医療,福祉,文化,産業振興,防災対策,住宅供給,都市環境整備,高齢者 失業対策等の各種サービスの提供を行っている本件各団体についてそのような事態が生ずることを回避すべき要請も考慮してされたものであるということができる。 そして,本件補助金等に係る不当利得返還請求権の放棄又は行使の影響についてみるに,まず,本件改正条例によって,本件各団体のうち前記・・・団体を除く各団体については,派遣法所定の手続に従って市から派遣職員に直接給与が支給されるものとされており,これによれば,本件派遣職員等の給与の大半は,適法な手続を経た上で市の公金から支出されることがそもそも予定されていたものといえることからすると,上記請求権の放棄によって市の財政に及ぶ影響は限定的なものにとどまるということができる。また,既に本件派遣職員等の給与等の人件費に充てられた本件補助金等につき上記請求権の行使により直ちにその返還の徴求がされた場合,実際に本件各団体の財政運営に支障を来して上記の各種サービスの十分な提供が困難になるなどの市における不利益が生ずるおそれがあり,その返還義務につき上記の要請を考慮して議会の議決を経て免責がされることは,その給与等の大半については返還と再度の支給の手続を行ったものと実質的に同視し得るものともいえる上,そのような市における不利益を回避することに資するものということもできる。そうすると,上記の本件訴訟の経緯のみから直ちに本件附則に係る議決が本件各団体の債務を何ら合理的な理由なく免れさせたものということはできない。
○ なお,住民訴訟の係属の有無及び経緯に関しては,本件では,前記・・・のとおり,本件訴訟の係属中に,上告人の第1審での一部敗訴を経て原審の判決の言渡期日の直前に本件改正条例案が可決されており,このような現に係属する本件訴訟の経緯を踏まえ,本件附則に係る議決については,主として住民訴訟制度における当該財務会計行為等の審査を回避して制度の機能を否定する目的でされたなど,住民訴訟制度の趣旨を没却する濫用的なものに当たらないか否かという観点からみることとする。この点に関し,原審は,本件議決がされた時期と原審における住民訴訟の審理の状況との関係等をも理由として,市の本件各団体に対する不当利得返還請求権を放棄する旨の本件附則に係る市議会の議決は地方自治法の定める 住民訴訟制度を根本から否定するものである旨をいう。しかしながら,本件附則に係る議決の適法性に関しては,住民訴訟の経緯や当該議決の趣旨及び経緯等を含む諸般の事情を総合考慮する上記の判断枠組みの下で,裁判所がその審査及び判断を行うのであるから,上記請求権の放棄を内容とする上記議決をもって,住民訴訟制度を根底から否定するものであるということはできず,住民訴訟制度の趣旨を没却 する濫用的なものに当たるということはできない。
○ そして,本件補助金等の支出に係る事後の状況に関しては,前記・・・のとおり,本件訴訟等を契機に条例の改正が行われ,以後,市の派遣先団体等において市の補助金等を派遣職員等の給与等の人件費に充てることがなくなるという是正措置が既に採られている。 以上の諸般の事情を総合考慮すれば,市が本件各団体に対する上記不当利得返還請求権を放棄することが普通地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする地方自治法の趣旨等に照らして不合理であるとは認め難いというべきであり,その放棄を内容とする本件附則に係る市議会の議決がその裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとはいえず,その議決は適法であると解するのが相当である。
○ そして,上記不当利得返還請求権の放棄を内容とする本件附則を含む本件改正条例については,市議会による上記議決及び市長による公布を経て施行されているのであるから,本件附則に係る権利の放棄は有効であって,本件附則の施行により当該請求権は消滅したものというべきである。
【最高裁判例】 (最判平24.4.20同旨) 住民訴訟の対象とされている自治体の損害賠償請求権を放棄する旨の議会の議決がされた場合において、請求権の発生原因である公金の支出等の財務会計行為等の性質、内容、原因、経緯及び影響(その違法事由の性格や当該職員の帰責性等を含む)、当該議決の趣旨及び経緯、当該請求権の放棄又は行使の影響、住民訴訟の係属の有無及び経緯、事後の状況その他の諸般の事情を総合考慮して、これを放棄することが自治体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする地方自治法の趣旨等に照らして不合理であってその裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められるときは、その議決は違法となり、当該放棄は無効となる 最判平24.4.23民集66.6.2789
(町が浄水場用地として土地を購入したことについて、土地取得の必要性はなく代金額も適正価格よりも著しく高額なのに当該土地の売買契約を締結したことが違法とする住民訴訟。当該用地は競売の落札者から購入したが、購入額は不動産鑑定士の鑑定価格を基礎としたところ、この鑑定は町長の友人を介して依頼した不動産鑑定士が行なったものであったが、当該鑑定価格は落札者との当初折衝時の額より高額なものであったため、この鑑定価格について庁内・議会で意見を呈するものもあった。その後、本鑑定は極めて杜撰なものであるとして当該鑑定士は所属団体の会員権停止処分を受けた。本訴訟は一審で原告が勝訴したところ、二審の口頭弁論終結後、議会は当時の町長への損害賠償請求権を放棄する議決をした。そのため口頭弁論再開の申立てがなされ、議会の議決で請求権が消滅した旨の主張が被告側からなされた。二審判決は、裁判所が存在すると認定判断した損害賠償請求権についてこれが存在しないとの立場から裁判所の認定判断を覆しあるいは裁判所においてそのような判断がされるのを阻止するために当該請求権の放棄の議決をすることは、損害賠償請求権の存否について議会の判断を裁判所の判断に優先させようとするものであり、権利義務の存否について争いのある場合にその判断を裁判所に委ねるものとしている三権分立の趣旨に反し、議会の裁量権逸脱または濫用であるので放棄議決は違法無効であるとして、請求を認容する判決をした)
○ 地方自治法96条1項10号は,普通地方公共団体の議会の議決事項として,「法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか,権利を放棄すること」を定め,この「特別の定め」の例としては,普通地方公共団体の長はその債権に係る債務者が無資力又はこれに近い状態等にあるときはその議会の議決を経ることなくその債権の放棄としての債務の免除をすることができる旨の同法240条3項,地方自治法施行令171条の7の規定等がある。他方,普通地方公共団体の議会の議決を経た上でその長が債権の放棄をする場合におけるその放棄の実体的要件については,同法その他の法令においてこれを制限する規定は存しない。したがって,地方自治法においては,普通地方公共団体がその債権の放棄をするに当たって,その議会の議決及び長の執行行為(条例による場合は,その公布)という手続的要件を満たしている限り,その適否の実体的判断については,住民による直接の選挙を通じて選出された議員により構成される普通地方公共団体の議決機関である議会の裁量権に基本的に委ねられているものというべきである。もっとも,同法において,普通地方公共団体の執行機関又は職員による公金の支出等の財務会計行為又は怠る事実に係る違法事由の有無及びその是正の要否等につき住民の関与する裁判手続による審査等を目的として住民訴訟制度が設けられているところ,住民訴訟の対象とされている損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を放棄する旨の議決がされた場合についてみると,このような請求権が認められる場合は様々であり,個々の事案ごとに,当該請求権の発生原因である財務会計行為等の性質,内容,原因,経緯及び影響,当該議決の趣旨及び経緯,当該請求権の放棄又は行使の影響,住民訴訟の係属の有無及び経緯,事後の状況その他の諸般の事情を総合考慮して,これを放棄することが普通地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする同法の趣旨等に照らして不合理であって上記の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められるときは,その議決は違法となり,当該放棄は無効となるものと解するのが相当である。そして,当該公金の支出等の財務会計行為等の性質,内容等については,その違法事由の性格や当該職員又は当該支出等を受けた者の帰責性等が考慮の対象とされるべきものと解される。
○ 本件議決についてこれをみるに,まず,本件契約締結行為の性質及び内容に関しては,本件土地は,前記・・・のとおり,浄水場用地としての条件に適合しており,地権者も1名で交渉が容易であったことなどから,町においてこれを浄水場用地として取得する必要性が認められ,本件契約締結行為の違法事由は専ら代金額が高額に過ぎた点にあるところ(地方自治法2条14項,地方財政法4条1項),その当時,本件拡張計画に基づく用地取得の予定時期を数年過ぎても他に適当な候補地が見当たらない中で,水道事業の管理者としての町長は,用地取得の早急な実現に向けて努力すべき立場にあり,売買契約の代金額が売主との交渉によって決まるものである以上,その交渉の期間や内容等について相応の裁量も有していたものといえる。仮に,代金額に係る交渉を不調として本件土地の取得を断念するならば,用地取得の予定時期を既に数年過ぎて遅れていた浄水施設の設置など本件拡張計画の実現が更に遅れることになり,町及びその住民全体の利益に反する結果となる状況にあったともいえる。また,本件土地の売主である参加人Bが高額の代金額を要求した根拠は,町が依頼した不動産鑑定士による鑑定結果である本件鑑定であったところ,一般に不動産鑑定の適否の判定は中立的な専門家の関与なしには困難であることに照らせば,仮に町が依頼した他の不動産鑑定士によってより安価な鑑定評価額が出されたとしても,限られた期間内の当事者同士の交渉によって売主から代金額の大幅な引下げという譲歩を確実に引き出すことができたか否かは必ずしも明らかではない。そして,参加人Aと売主との間の交渉について,それが折衝としての実体を有しない態様のものであったことをうかがわせるような交渉の具体的な内容や状況等の事情は原審では明らかにされていない。次に,本件契約締結行為の原因及び経緯に関しては,上記の点のほか,少なくとも,参加人Aにおいて適正価格との差額から不法な利益を得て私利を図る目的があったなどの事情は証拠上うかがわれず,被上告人も主張していない。また,本件契約締結行為の影響に関しては,その代金額は,前記・・・のとおり,町議会の議決を得た3億円という用地購入費の予算の枠を5000万円下回るものであったのであり,本件売買により浄水場用地が確保され,浄水施設の設置など水道事業を拡充する本件拡張計画の早期の実現が図られることによって,町ないし市及びその住民全体に相応の利益が及んでいるものということもでき,参加人Aが本件売買によって不法な利益を得たなどの事情は証拠上うかがわれず,被上告人も主張していない。以上に鑑みると,本件鑑定の鑑定評価額に基づき高額に過ぎる代金額で売買契約を締結するに至ったことにつき,原審の認定した事情のみから直ちに参加人A(注:当時の町長)の帰責性が大きいと断ずることはできない。
○ そして,以上を前提として,本件議決の趣旨及び経緯についてみるに,前記・・・のとおり,本件議案の提案理由書には,本件訴訟の第1審における本件土地の適正価格の認定の基礎とされた被上告人鑑定書の内容を論難する記載がある一方で,当時の町長であった参加人Aにとって本件土地の取得は緊急を要しており水道の事業計画の推進のために水道事業の管理者として必然的な選択であったこと等が放棄の理由として記載されており,同議案に賛成した議員らの発言の中でも,浄水場の建設は緊急を要しており浄水場用地として本件土地を取得する必要性は高く地元住民の要望も強かったことが重視され,参加人Aが不法な利益を得たわけではないなどの指摘もされていることがうかがわれるところであり,このような市議会における審議を経た議決の経緯等に照らすと,本件議決について,上記提案理由書の一部に上記のような記載があるからといって直ちに本件訴訟の第1審判決の法的判断を否定する趣旨のものと断ずることは相当ではない。そして,市の参加人Aに対する損害賠償請求権の放棄又は行使の影響についてみるに,浄水場用地の取得は,町の水道事業に係る公益的な政策目的に沿って町の執行機関である長が本来の責務として行う職務の遂行であるといえ,また,本件売買の代金額は町議会の議決を得た用地購入費の予算の枠を下回るものであったところ,このような職務の遂行の過程における行為に関し,上記請求権の行使により直ちに1億数千万円の賠償責任の徴求がされた場合,執行機関の個人責任として著しく重い負担を負うことになり,以後,執行機関において,職務の遂行に伴い個人の資力を超える高額の賠償の負担を負う危険を踏まえ,長期的な観点からは一定の政策目的に沿ったこのような職務の遂行に萎縮的な影響を及ぼすなどの状況が生ずるおそれもあり,仮に上記の賠償責任につき一定の酌むべき事情が存するのであれば,その限りにおいて議会の議決を経て全部又は一部の免責がされることは,上記の観点からはそのような状況を回避することに資する面もあるということもできる。以上に鑑みると,本件議決については,本件鑑定評価額に基づき高額に過ぎる代金額で売買契約を締結するに至ったことにつき,参加人Aが,町に多額の損害を与えた一方で,水道事業の管理者として地元住民の要望も強く緊急に必要とされた浄水場用地を取得し,自らが不法な利益を得たわけではない等の指摘がされる中で行われたものであり,参加人Aの賠償責任を不当な目的で免れさせたことをうかがわせるような事情は原審では明らかにされていないといえるので,原審の認定した事情のみから直ちに本件議決が参加人Aの賠償責任を何ら合理的な理由なく免れさせたものと断ずることはできない。
○ なお,住民訴訟の係属の有無及び経緯に関しては,本件では,前記・・・のとおり,本件訴訟の係属中に,上告人の第1審での敗訴を経て原審の判決言渡期日の直前に本件議案が可決されており,このような現に係属する本件訴訟の経緯を踏まえ,本件議決については,主として住民訴訟制度における当該財務会計行為等の審査を回避して制度の機能を否定する目的でされたなど,住民訴訟制度の趣旨を没却する濫用的なものに当たらないか否かという観点からみることとする。この点に関し,原審は,本件議決がされた時期と原審における住民訴訟の審理の状況との関係等をも理由として,住民訴訟の対象とされている市の損害賠償請求権の放棄を内容とする本件議決は,議会の判断を裁判所の判断に優先させるもので三権分立の趣旨に反するものであるなどとして,これが市議会の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たる旨をいう。しかしながら,本件議決の適法性に関しては,住民訴訟の経緯や当該議決の趣旨及び経緯を含めた諸般の事情を総合考慮する上記の判断枠組みの下で,裁判所がその審査及び判断を行うのであるから,第1審判決の認容に係る上記請求権の放棄を内容とする本件議決をもって,議会の判断を裁判所の判断に優先させるもので三権分立の趣旨に反するものということはできず,住民訴訟制度の趣旨を没却する濫用的なものに当たるということはできない。
市の新庁舎建設の方針が変更されたため庁舎設計委託契約を解除し精算金を支払った事案において、当該精算金は損害賠償の性格を有しその支出には議会の議決を要するところ、この議決がない以上、本件支出負担行為は地方自治法96条に反する違法なものとして私法上無効であるとされた事例 東京高判平24.7.11判例地方自治371.29
(市は庁舎現在地の隣地に新庁舎を建てることとしたが、隣地所有者が買収に応じないため、隣地を賃借して建設することとして庁舎建設の設計委託をした。しかし議会で借地での庁舎建設に反対する趣旨の決議がなされたため、前記設計委託契約を解除することとし、業者が費やした人件費等につき709万円余の精算金を支払った。本件支払については議会の議決を経ていない。市は精算金は出来高部分相当額と業者と協議して定めたものであり解除に伴う原状回復として不当利得返還の性格を持つと主張したが、当審は委託契約約款の条項等からして本精算金は損害賠償の性質を有するものと認定した)
○ 地方自治法96条1項13号は、「法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること」について議会の議決を要するものとしている。これは、賠償額の決定は異例の財政支出を伴うことがあること、適正な賠償額の決定を図り、責任の所在を明確にすることなどをその趣旨とするものと解される。本件精算金は、本件契約が委託契約約款22条1項に基づいて解除されたために発生した損害賠償金の性質を有するものであるから、同号にいう「法律上その義務に属する損害賠償」に当たるものと解される。したがって、本件精算金の支出に当たっては、事前に市議会の議決を必要としたというべきである(・・・によれば、「法律上市の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が50万円以下のもの」については、市長の専決処分事項として指定されていることが認められるが、本件精算金の金額は、前記のとおり、709万0650円であり、50万円を大きく超えている。)。実質的にみても、本来、本件解除までにA設計事務所が費やした経費や人件費等は、可能な限り実額で計算された上で、本件解除に基づくA設計事務所の全損害が算定されるべきであったというべきであり、そのような算定をしないで、県算定基準に従って算定された出来高をもって賠償額とするのであれば、適正な賠償額の決定を図り、責任の所在を明確にするためにも市議会の議決が不可欠であったというべきである。
○ そして、本件支出は、前記のとおり、当時の市長であるYが、平成19年3月15日、本件精算金の支払は本件解除に基づく原状回復義務の履行であるとの前提で、市議会の議決を経ることなく、本件出来高認定に基づいて本件精算金の金額を709万0650円とする決裁をし、同日、A設計事務所から同金額の請求書が出され、本件精算金の支払について合意が成立し(本件支出負担行為)、支出命令について専決権限を有する当時の市助役(収入役を兼掌)であるBが、平成19年3月23日、709万0650円の支出命令を出し(本件支出命令)、同月28日、収入役として、A設計事務所に対し、同金額の本件精算金を支払った(本件支出をした)というものであるから、本件支出負担行為は、地方自治法96条1項13号に反する違法なものとして私法上無効であり、A設計事務所は本件精算金を取得する法律上の原因を欠いていたというべきである。
○ 被控訴人は、当審において、〈1〉本件精算金の支払については、平成19年6月12日、市議会において議員により質問があり、市議会の把握するところとなったが、その後、市議会が本件精算金の額を709万0650円とすることを否定する議決を行ったことはなく、Yに対する不信任決議を行ったこともないので、市議会においても本件精算金の確定について議会の議決が不要であることについて黙示に承認している、〈2〉本件精算金の支出は、一般会計からの支出であったところ、市議会は、平成18年度の一般会計の決算を不認定としたが、市庁舎建設に関しては、不認定に当たって議会から指摘・要望されたのは、(ア)市庁舎の早期建設のため、早急に取り組んでいただきたい、(イ)市庁舎の建設について用地買収ができない段階で基本設計が発注され、結果として709万円が無駄に支出されたが、今後このようなことが起きぬよう、議会と協議する等、適切な予算執行がなされるようにしていただきたいという2点であり、これは市議会の承認なく本件精算金の額を確定させたことを問題視するものではないから、市議会は、本件精算金の額が相当であったことを黙示的に表明したことにほかならず、本件精算金の額の確定については、市議会の黙示的な承認があったといえる、〈3〉仮に、額の確定についての市議会の黙示的承認が認められないとしても、市議会は、市議会の承認なく本件精算金の額を確定させたことを問題視することができたにもかかわらず、それを問題視していないから、市議会は、本件精算金の額の確定につき市議会の承認は不要だと判断したことにほかならず、この市議会の判断については、市議会が住民に選挙によって選ばれた議員によって構成されていることにかんがみれば、一見極めて明白に不合理である場合に限り、違法無効になると解すべきであるが、解除に伴う原状回復義務は講学上の損害賠償ではないから、一見極めて明白に不合理であるとはいえないなどと主張する。しかしながら、市議会において賠償額を定めることなく損害賠償の性質を有する本件精算金が支払われたことについて、市議会の追認がなされたというためには、本件精算金が損害賠償の性質を有することを市議会が十分に理解した上で、これを明確に追認することが必要であると解されるが、被控訴人の主張によっても、市議会がそのような理解をして明確な追認をしたものではないことが明らかであるから、被控訴人の上記主張はいずれも採用できない。
【最高裁判例】 自治体が締結した支出負担行為たる契約が違法に締結されたものであっても私法上無効ではない場合には,当該契約に基づく債務の履行として支出命令を行う権限を有する職員が当該契約の是正を行う職務上の権限を有していても,当該職員が上記債務の履行として行う支出命令は,次の(1)又は(2)のときでない限り,違法な契約に基づいて支出命令を行ってはならないという財務会計法規上の義務に違反する違法なものとなることはない
(1) 当該自治体が当該契約の取消権又は解除権を有しているとき
(2) 当該契約が著しく合理性を欠きそのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存し,かつ,当該自治体が当該契約の相手方に事実上の働きかけを真しに行えば相手方において当該契約の解消に応ずる蓋然性が大きかったというような,客観的にみて当該自治体が当該契約を解消することができる特殊な事情があるとき 最判平25.3.21民集67.3.375
(町有地上の建物が県道拡幅工事で取り壊しとなる際、この建物を事務局として無償で使用していた協議会に対し事務所移転のための移転補償費を町が支払った。原審は、移転補償契約は公序良俗に反し無効であるとはいえないが著しく不相当であって地方自治法2条14項、地方財政法4条1項に反し違法であるなどとした上で、支出の前提である契約(支出負担行為)が私法上無効とはいえないものの違法である場合において支出命令権者が支出負担行為を是正する権限を有するときは、支出命令権者は自治体に対して違法な支出負担行為に基づく支出命令を発すべきではないという財務会計法規上の不作為義務を負っており、これに違反して発せられた支出命令は違法であるとして、移転補償費支出を違法と判断した)
○ 地方自治法242条の2第1項4号に定める普通地方公共団体の職員に対する損害賠償の請求は,財務会計上の行為を行う権限を有する当該職員に対して職務上の義務に違反する財務会計上の行為による当該職員の個人としての損害賠償義務の履行を求めるものにほかならないから,当該職員の財務会計上の行為を捉えて上記損害賠償の請求をすることができるのは,たといこれに先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても,その原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解するのが相当である(最高裁昭和61年(行ツ)第133号平成4年12月15日第三小法廷判決・民集46巻9号2753頁参照)。
○ しかるところ,普通地方公共団体が締結した債務を負担する契約が違法に締結されたものであるとしても,それが私法上無効ではない場合には,当該普通地方公共団体はその相手方に対しそれに基づく債務を履行すべき義務を負うのであるから,その債務の履行としてされる財務会計上の行為を行う権限を有する職員は,当該普通地方公共団体において当該相手方に対する当該債務を解消することができるときでなければ,当該行為を行ってはならないという財務会計法規上の義務を負うものではないと解される。そして,当該行為が支出負担行為たる契約に基づく債務の履行としてされる支出命令である場合においても,支出負担行為と支出命令は公金を支出するために行われる一連の行為ではあるが互いに独立した財務会計上の行為というべきものであるから(最高裁平成11年(行ヒ)第131号同14年7月16日第三小法廷判決・民集56巻6号1339頁参照),以上の理は,同様に当てはまるものと解するのが相当である。
○ そうすると,普通地方公共団体が締結した支出負担行為たる契約が違法に締結されたものであるとしても,それが私法上無効ではない場合には,当該普通地方公共団体が当該契約の取消権又は解除権を有しているときや,当該契約が著しく合理性を欠きそのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存し,かつ,当該普通地方公共団体が当該契約の相手方に事実上の働きかけを真しに行えば相手方において当該契約の解消に応ずる蓋然性が大きかったというような,客観的にみて当該普通地方公共団体が当該契約を解消することができる特殊な事情があるときでない限り,当該契約に基づく債務の履行として支出命令を行う権限を有する職員は,当該契約の是正を行う職務上の権限を有していても,違法な契約に基づいて支出命令を行ってはならないという財務会計法規上の義務を負うものとはいえず,当該職員が上記債務の履行として行う支出命令がこのような財務会計法規上の義務に違反する違法なものとなることはないと解するのが相当である(最高裁平成17年(行ヒ)第304号同20年1月18日第二小法廷判決・民集62巻1号1頁,最高裁平成21年(行ヒ)第162号同年12月17日第一小法廷判決・裁判集民事232号707頁参照)。
○ これを本件についてみるに,前記事実関係等の下においては,本件移転補償契約は,違法に締結されたものであるとしても,公序良俗に反し私法上無効であるとはいえず,他にこれを私法上無効とみるべき事情もうかがわれないところ,町がその取消権又は解除権を有していたとはいえず,また,町がB協議会に事実上の働きかけを真しに行えばB協議会においてその解消に応ずる蓋然性が大きかったというような,客観的にみて町がこれを解消することができる特殊な事情があったともいえないから,Aが本件移転補償契約に基づいて支出命令を行ってはならないという財務会計法規上の義務を負っていたとはいえず,Aが当該契約に基づく債務の履行として行った本件支出命令がこのような財務会計法規上の義務に違反する違法なものであったということはできない。そうすると,Aは,本件支出命令につき,町に対して損害賠償責任を負うものではない。
(し尿処理等を業務とする広域連合において、各家庭からし尿等の積替え保管施設であるし尿中継槽までの運搬距離を平準化し各町のし尿くみ取り料金に格差が出ないようにするなどのため、各町にそれぞれ1か所ずつし尿中継槽が設けていたが、A町設置の中継槽に対する住民からの強い苦情があり、代替地を検討していたところ、関係業者からの賃借協議を行い、相当高額の賃料で賃貸借契約を締結した。なお原告は私的に不動産鑑定士による鑑定書を提出しており、本件賃料は鑑定書の適正賃料の7倍に及んだ)
○ 地方自治法242条の2第1項4号に基づく被上告人の請求は,本件各契約を締結した本件広域連合の長の判断が同法2条14項及び地方財政法4条1項に違反することを前提とするものであるところ,地方公共団体の長がその代表者として一定の額の賃料を支払うことを約して不動産を賃借する契約を締結すること及びその賃料の額を変更する契約を締結することは,当該不動産を賃借する目的やその必要性,契約の締結に至る経緯,契約の内容に影響を及ぼす社会的,経済的要因その他の諸般の事情を総合考慮した合理的な裁量に委ねられており,当該契約に定められた賃料の額が鑑定評価等において適正とされた賃料の額を超える場合であっても,上記のような諸般の事情を総合考慮した上でなお,地方公共団体の長の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものと評価されるときでなければ,当該契約に定められた賃料の額をもって直ちに当該契約の締結が地方自治法2条14項等に反し違法となるものではないと解するのが相当である。
○ 前記事実関係等によれば,旧○郡においては,各家庭から生ずるし尿の運搬距離を平準化し各町におけるし尿くみ取り料金に格差が出ないようにするなどのため,各町にし尿中継槽が設けられていたのであり,各町の合併後間もない本件賃貸借契約締結当時においても同様に,本件広域連合が旧○町の区域内にし尿中継槽を設置する必要性があったということができる。そして,本件広域連合としては,本件貯留槽は新たなし尿中継槽が完成するまでの期間に限定して借りたものであり,また,旧△町の区域内のし尿中継槽において同区域内から生ずるし尿等に加えて旧○町の区域内で生ずるし尿等の積替え及び保管を継続的に行うことは困難であったと考えられるから,旧し尿中継槽が閉鎖されてから2年以上経過した本件賃貸借契約締結当時において,速やかに新たなし尿中継槽の用地を確保する必要性があったというべきである。
○ そして,そもそも旧○町の区域内の旧し尿中継槽は周辺住民からの強い苦情を受けて廃止されたものであり,同区域内で新たなし尿中継槽の用地を確保することは相当困難であったと考えられるところ,他に具体的な候補地の存在もうかがわれない中で,本件広域連合がA協業組合から反対されて鑑定評価はしなかったものの前記…の相応の交渉を経て本件賃貸借契約を締結するに至った経緯それ自体が不当なものであったとはいえず,また,本件私的鑑定において適正とされた賃料の額は,上記のようなし尿中継槽の用地を確保するという本件土地を賃借する目的やその必要性等の事情を考慮して算出されたものでないことは明らかである。
○ そうすると,旧○町の区域内にし尿中継槽の用地を確保するという本件土地を賃借する目的やその必要性,契約の内容に影響を及ぼす社会的,経済的要因としての当該施設の性質に伴う用地確保の緊急性や困難性といった事情の有無にかかわらず,本件賃貸借契約において鑑定評価を経ずに定められた賃料の額及びこれを一部減額した本件変更契約所定の賃料の額が本件私的鑑定において適正とされた賃料の額と比較して高額であることをもって直ちに,本件各契約を締結した本件広域連合の長の判断がその裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものであったということはできない。
○ 次に,契約に基づく債務の履行として行われる公金の支出について地方自治法242条の2第1項1号に基づく差止めを請求することができるのは,当該契約が私法上無効である場合に限られるところ(最高裁昭和56年(行ツ)第144号同62年5月19日第三小法廷判決・民集41巻4号687頁参照),旧○町の区域内で新たにし尿中継槽の用地を確保するために本件土地を賃借する必要性,当該施設の性質に伴う用地確保の緊急性や困難性といった上記の諸事情に加え,本件賃貸借契約に定められた賃料の額が当事者間で相応の交渉を経た上で合意されたものであり,本件広域連合の議会においてその予算が承認されていたことなどからすると,本件私的鑑定において賃借の目的等を考慮することなく適正とされた賃料の額と単純に比較して,本件各契約の賃料の約定が公序良俗に反するものとはいえず,また,本件各契約を締結した本件広域連合の長の判断に裁量権の範囲の著しい逸脱又はその濫用があり,本件各契約を無効としなければ地方自治法2条14項,地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる(最高裁平成17年(行ヒ)第304号同20年1月18日第二小法廷判決・民集62巻1号1頁参照)と直ちにいうこともできないことは明らかである。
○ 以上によれば,前記…の事実関係等から直ちに,本件各契約が違法に締結されたものでありその賃料の約定が私法上無効であるとして,地方自治法242条の2第1項4号に基づく被上告人の請求の一部及び同項1号に基づく被上告人の請求を認容した原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
特定多目的ダム法7条1項により国土交通大臣が東京都に発した建設費負担金の納付通知による負担金支出について、納付通知に重大かつその外形上一見看取できるような明白な違法や瑕疵は認められず、都がダム使用権設定申請の取下げをなすべき義務も認められない以上、当該納付通知に基づく支出が財務会計法規上の義務に違反する違法なものとはいえないとされた事例 (同旨東京高判平26.10.7下掲も参照) 東京高判平25.3.29判例タイムズ1415.97
(東京都が設定の申請をしたYダムのダム使用権は都の水道事業に不要であり都がYダムにより治水上の利益を受けることもないなどとして東京都水道局長に対する特定多目的ダム法7条に基づく建設費負担金の支出差止め等を求める住民訴訟。同一ダムに関する同趣旨の事例につき下掲東京高判平26.10.7も参照)
○ 地方自治法242条の2の規定に基づく住民訴訟は、普通地方公共団体の執行機関又は職員(以下「職員等」という。)による同法242条1項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実の予防又は是正を裁判所に請求する権能を住民に与え、もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とするものであり、同法242条の2第1項1号の規定に基づく差止めの請求は、このような住民訴訟の一類型として、財務会計上の行為を行う職員等に対し、職務上の義務に違反する財務会計上の行為の差止めを求めるものであるから、同号により差止めを求めることができるのは、仮にこれに先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、当該職員等の財務会計上の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解するのが相当である(最高裁昭和61年(行ツ)第133号平成4年12月15日第三小法廷判決・民集46巻9号2753頁参照)。そして、職員等の財務会計上の行為が、これに先行する原因行為に基づく場合において、当該原因行為が行政組織上独立の権限を有する他の機関の権限に基づいてされた行為であるときは、職員等は、上記のような独立の権限を有する他の機関の固有の権限内容にまで介入し得るものではないことからすれば、法が特に職員等に対しその先行する原因行為の適法性を審査した上で、適法な場合に限り、その内容に応じた財務会計上の行為をすべき義務を課しているときを除き、当該原因行為について重大かつ明白な違法ないし瑕疵があるなど、当該原因行為が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正の見地から看過し得ない瑕疵があるときでない限り、これを尊重してその内容に応じた財務会計上の行為をすることが違法と認めることはできないと解するのが相当である。また、当該原因行為が契約である場合、職員等はその契約上の義務の履行のため必要な措置を執らなければならないのであるから、当該原因行為が無効であるとき、又は、当該原因行為が無効ではないものの違法であって、当該職員等が、当該原因行為について取消権・解除権を有しているとき、若しくは、当該原因行為が著しく合理性を欠き、そのために予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存在し、当該職員等に、当該原因行為を解消することができる特殊な事情が存在するときでない限り、上記原因行為を尊重してその内容に応じた財務会計上の措置を採るべき義務があり、これを拒むことは許されないものと解するのが相当であって、当該職員等が、上記原因行為に応じて行う支出行為が、財務会計法規上の義務に違反する違法なものになるものではないというべきである(前記最高裁平成4年12月15日第三小法廷判決、同平成17年(行ヒ)第304号同平成20年1月18日第二小法廷判決・民集62巻1号1頁、同平成21年(行ヒ)第162号同年12月17日第一小法廷判決・集民232号707頁参照)。
○ 被控訴人水道局長による建設費負担金の支出が、国土交通大臣による納付通知を原因とするものであることは前判示のとおりである。また、職員等の財務会計上の行為が、これに先行する原因行為に基づく場合において、当該原因行為が行政組織上独立の権限を有する他の機関の権限に基づいてされた行為であるときは、職員等は、上記のような独立の権限を有する他の機関の固有の権限内容にまで介入し得るものではないことからすれば、法が特に職員等に対しその先行する原因行為の適法性を審査した上で、適法な場合に限り、その内容に応じた財務会計上の行為をすべき義務を課しているときを除き、当該原因行為について重大かつ明白な違法ないし瑕疵があるなど、当該原因行為が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正の見地から看過し得ない瑕疵が存するときでない限り、これを尊重してその内容に応じた財務会計上の行為をすることが違法と認めることはできないと解するのが相当であることは前判示のとおりである。そして、特ダム法(注:特定多目的ダム法)7条1項が、ダム使用権設定予定者は、多目的ダムの建設に要する費用のうち、政令で定めるところにより算出した額の費用を「負担しなければならない」旨を定め、同法施行令9条1項は、上記負担金につき、毎年度、国土交通大臣が当該年度の事業計画に応じて定める額を、同大臣が当該年度の資金計画に基づいて定める期限までに納付する旨を、同法施行例11条の3は、国土交通大臣は、負担金を徴収しようとするときは、負担金の額を決定し、負担金の徴収を受ける者に通知する旨を、各定めており(前記法令の定め(1))、同法36条1項は、同法7条1項の負担金を納付しない者があるときは、国土交通大臣は、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない旨を、同条3項は、この督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、国土交通大臣は、国税滞納処分の例により、負担金等及び延滞金を徴収することができる旨を、各定めているのである。これらの各規定においても、被控訴人水道局長に対し、建設費負担金の支出について、原因行為である国土交通大臣による納付通知の適法性を審査した上で、これが適法な場合に限りその支出をすべき義務を課することをうかがわせる規定は存在しないことに加えて、これらの規定の定める、ダム使用権設定予定者に負担が義務付けられることなどの建設費負担金の性質、その額の決定及び督促・徴収の方法等における国土交通大臣とダム使用権設定予定者の権限の配分関係をも総合すれば、法が被控訴人水道局長に対し、建設費負担金の支出について原因行為たる国土交通大臣による建設費負担金の納付通知の適法性を審査した上で、これが適法な場合に限り上記建設費負担金の支出をすべき義務を課しているものとは認められず、国土交通大臣による上記納付通知について重大かつ明白な違法ないし瑕疵があるなど、当該納付通知が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正の見地から看過し得ない瑕疵があるときでない限り、これを尊重してその内容に応じてした被控訴人水道局長による建設費負担金の支出が違法であるということはできないと解するのが相当である。そして、その違法ないし瑕疵が明白であるというためには、行為の外形上違法ないし瑕疵が一見看取できるものでなければならないと解される(最高裁昭和41(行ツ)第52号同44年2月6日第一小法廷判決・集民94号233頁参照)。
○ 控訴人らは、Yダムにより貯留される予定の流水を東京都が利用する利水上の必要性は全くなく、東京都の利水のためにYダムについてダム使用権の設定を受ける必要はなく、東京都の水道事業を実施するために客観的必要のない水利権を確保するための費用を支出することは違法であると主張する。しかし、特ダム法7条1項は、ダム使用権設定予定者は、多目的ダムの建設に要する費用のうち、建設の目的である各用途について、多目的ダムの流水の貯留を利用して流水を当該用途に供することによって得られる効用から算定される推定の投資額及び当該用途のみに供される工作物でその効用と同等の効用を有するものの設置に要する推定の費用の額並びに多目的ダムの建設に要する費用の財源の一部に借入金が充てられる場合においては、支払うべき利息の額を勘案して、政令で定めるところにより算出した額の費用を負担しなければならない旨定め、同法施行令1条の2が、その算定方法について定めるところ・・・当初計画において、東京都(水道)の負担額が建設に要する費用の額に1000分の54を乗じて得た額と定められ、平成13年9月27日第1回計画変更・・・により完成予定時期を平成22年度とする変更が、平成16年9月28日第2回計画変更・・・により建設に要する費用の概算額を約4600億円、河川法59条、60条及び63条に基づく国等の負担額を建設に要する費用の額に1000分の546を乗じて得た額とするなどの変更がされ、国土交通大臣は、特ダム法施行令9条1項、11条の3に基づき、毎年度、当該年度の事業計画に応じて負担金の額を決定し、通知しているものであることが認められる。そして、特ダム法は、ダム使用権設定予定者が流水の貯留を利用して流水をその用に供する利水上の必要性があることを建設費負担金の負担の要件と規定するものではなく、東京都がダム使用権設定の申請をし、基本計画においてダム使用権設定予定者の地位にある以上、ダム使用権に基づいて東京都に本件ダムによる流水の貯留を利用することに利水上の必要性があるか否かに関わらず、建設費負担金を支払う義務を負うこととなるというべきである。したがって、東京都の水道事業を実施するためにYダムによる水利権について利水上の必要性があるか否かによって、上記納付通知が違法となり瑕疵があることとなるものではないというべきである。
○ 以上によれば、上記納付通知に、重大かつその外形上一見看取できるような明白な違法や瑕疵があるとは認められないばかりでなく、そもそもこれが違法であるとも認められないのである。
○ もっとも、特ダム法12条は、ダム使用権設定予定者のダム使用権の設定の申請が却下され、又は取り下げられたときは、その者がすでに納付した第7条1項の負担金を還付するものとする旨規定し、ダム使用権設定申請の取下げを特に制約する規定は置いていない。したがって、ダム使用権設定予定者は、ダム使用権の設定の申請を取り下げることにより、建設費負担金の負担義務を免れることができるものということができる。そうすると、被控訴人水道局長が、ダム使用権の設定申請をする行為が合理性を欠く場合には、その建設費負担金の支出について、被控訴人水道局長は、ダム使用権の設定申請を取り下げることによって、その負担義務を免れるよう務めるべき財務会計法規上の義務があると解する余地があるというべきであり、また、ダム使用権の設定申請には上記のような瑕疵がないとしても、その後の事情の変更により、ダム使用権設定予定者たる地位を維持することが、合理性を欠くと認められる場合においても同様であって、被控訴人水道局長は、ダム使用権の設定申請を取り下げることによって、建設費負担金の負担義務を免れるよう務めるべき財務会計法規上の義務を負うと解すべき余地があるということができる。そこで、Yダムに係るダム使用権の設定申請及びダム使用権設定予定者たる地位を維持することが、合理性を欠くと認められるか否かにつき、検討する。
○ 控訴人らは、東京都がYダムにおいて確保しようとしている水利権は、東京都の水道事業に必要のないものであって、被控訴人水道局長がYダムのダム使用権の設定申請をした昭和60年当時と比較して東京都の水道需要が減少傾向にあり、他方、東京都は十分な水源を保有しているのであるから、水需給計画を見直し、ダム使用権設定申請を取り下げる権利を行使することによって建設費負担金の支出を回避すべきであり、これを行わずに建設費負担金の支払を継続することは違法であると主張する。しかし、東京都の営む水道事業は、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とし(水道法1条)、東京都は、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことのできないものであり、かつ、水が貴重な資源であることにかんがみ、水源及び水道施設並びにこれらの周辺の清潔保持並びに水の適正かつ合理的な使用に関し必要な施策を講ずる義務を負い(同法2条1項)、地域の自然的社会的諸条件に応じて、水道の計画的整備に関する施策を策定し、これを実施しなければならず(同法2条の2第1項)、水道事業者として、事業計画に定める給水区域内の需用者から給水契約の申込みを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではならず(同法15条1項)、水道により給水を受ける者に対し、常時水を供給しなければならない義務を負い、渇水によって都民の生活が影響を受けないよう努力する責務を負っているというべきである。そして、Yダムに係るダム使用権の設定の申請も、このような責務を果たすために行われるものであり、上記の義務を全うし、将来の経済、社会の発展にも対応することができるよう、長期的な水道需要及び供給能力を合理的に予測し、その必要性を判断すべきものである。(認定部分略) 以上によれば、国土交通大臣による建設費負担金の納付通知が違法であるとは認められず、また、被控訴人水道局長がダム使用権設定の申請を行い、その設定の申請を取り下げないことについても、合理性を欠くものとは認められない。
○ したがって、被控訴人水道局長の、上記納付通知に応じて行う支出行為が、財務会計法規上の義務に違反する違法なものということはできない。
(東京高判平25.3.29同旨) 東京高判平26.10.7判例地方自治343.50
(事実関係は東京高判平25.3.29同内容(対象のダムも同一)で、別団体を当事者とするもの)
○ 地方自治法242条の2第1項4号に基づき当該職員に損害賠償の請求を求めることができるのは、先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、その原因行為を前提としてされた同職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解される(最高裁昭和61年(行ツ)第133号平成4年12月15日第三小法廷判決・民集46巻9号2753頁参照)。ところで、県が特ダム法負担金を支出する根拠すなわち原因行為は、国土交通大臣がする特ダム法負担金納付通知である。そして、特ダム法36条1項及び3項は、特ダム法負担金納付通知を受けても、特ダム法負担金を納付しない者があるときは、国土交通大臣は、督促状によって督促しなければならず、期限までに納付されないときは、国税滞納処分の例により負担金等を徴収することができる旨定めていることからすると、県は、国土交通大臣がする特ダム法負担金納付通知により、具体的な特ダム法負担金を納付すべき法的義務を負うことになると解すべきであり、そうであれば、被控訴人県公営企業管理者は、特ダム法負担金納付通知に重大かつ明白な瑕疵が存する場合でない限り、特ダム法負担金納付通知を尊重してその内容に応じた財務会計上の措置を採るべき義務があり、これを拒むことは許されないと解される。したがって、被控訴人県公営企業管理者がした特ダム法負担金の支出に関する行為は、上記のような瑕疵が存する場合でない限り、その職務上負担する財務会計法規上の義務に違反する違法なものということはできないと解すべきである。そして、地方自治法242条の2第1項1号に基づく差止請求についても、財務会計行為の違法性に関しては、これと同様に解すべきである。
○ もっとも、控訴人らは、特ダム法12条の予定しているダム使用権設定申請を取り下げる権限については、申請者がこれを自由に行使することができ、県側が、県にYダムによる利水上の利益がないにもかかわらず、上記申請を取り下げず、特ダム法負担金を支出することは、地方自治法2条14項等に違反した違法な公金支出になると主張する。確かに、特ダム法12条は、ダム使用権の設定予定者のダム使用権の設定の申請が取り下げられたときは、その者がすでに納付した特ダム法負担金を還付する旨定めており、このことからすると、ダム使用権の設定予定者がダム使用権の設定の申請を取り下げることは可能と解され、その場合、既に納付した特ダム法負担金の還付を受けられ得るとともに、同申請を取り下げれば、ダム使用権の設定予定者ではなくなるので、それ以降は、特ダム法負担金を負担する理由がなくなることになると解される。
○ ところで、県では、前記のとおり、被控訴人知事がダム使用権の設定の申請を取り下げる権限を有していると解されるところ、法令上、ダム使用権の設定の申請の取下げに関する要件や基準が定められているわけではない。そして、水道が国民の日常生活に直結し、その健康を守るために欠くことができないものであり、かつ、水が貴重な資源であり、清浄にして豊富低廉な水の供給が図られることが公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与すべきものであるところ(水道法1条、2条参照)、県は700万人を超える県民が生活しており・・・、このような多くの県民の生活基盤を支え、都市活動を維持していくためには、水道水を適切かつ安定的に供給する必要があること、そのためには、水の需要の予測や、供給能力及び水源の確保の評価が必要であり、これを踏まえて、利水上の必要性からYダムのような多目的ダムによって水源を確保するかどうかの判断がされるべきであること、上記予測や評価に当たっては、渇水の発生や予測を上回る給水人口の増加等の事態が発生しても水の安定的な供給を行えるよう、ある程度の余裕を見込みつつ、水の需要及び供給能力等の実績値の変化や傾向だけではなく、将来の人口、経済の状況、現有水源の状況、渇水発生の状況等といった専門技術的なものも含めて将来の予測困難な事情をも考慮する必要があること、Yダムのような多目的ダムの建設が計画から完成に至るまで長期間を要すること等からすると長期にわたる見通しをもって行う必要があること等にかんがみれば、被控訴人県知事が、Yダムに関し、既にしたダム使用権の設定の申請を取り下げるか否かは、県における水源確保という重要な施策の中で、上記のような様々な点を考慮して判断すべきことであり、その判断は、被控訴人県知事の裁量に委ねられていると解され、その判断について裁量権の範囲を逸脱し又はその濫用があるとはいえない限り、Yダムに係るダム使用権の設定申請を取り下げないことが違法であるとはいえないというべきである。
○ そこで、被控訴人県知事のYダムに係るダム使用権設定申請を取り下げないという判断が、その裁量権の範囲を逸脱し又はその濫用があり、違法といえるかについて検討する。・・・(中略)・・・
○ 以上によれば、前記平成15年予測及び平成19年予測では、いずれも、相応の合理的根拠に基づき、水需要予測並びに供給能力及び水源の確保の評価がされており、これを前提として、本件合理化事業に基づく各転用水利権による取水部分のうち非かんがい期について、安定的な水源を確保するため、Yダムへの参画を継続し、Yダムに係るダム使用権設定申請を取り下げないという被控訴人県知事の判断は、不合理とはいえず、また、被控訴人県知事は、国土交通大臣に対し、ダム使用権の設定予定者とされている県を代表して、Yダムの建設に関する基本計画の作成又は変更について異議がない旨又は意見を付して同意する旨等の意見を述べているところ、これは、特ダム法4条4項に基づくもので、同意見を述べることについての県議会の議決を経ていること・・・をも考慮すれば、被控訴人県知事の上記判断がその裁量権の範囲を逸脱し又はその濫用があるとはいえず、したがって、被控訴人県知事がYダムに係るダム使用権設定申請を取り下げないことが違法であるとはいえない。この点に関する控訴人らのその余の主張や当審で取り調べた証拠・・・を検討してみても、控訴人らのYダムに参画しなくても県としては水源を確保できるという主張はひとつの評価としてはあり得る指摘であるとしても、被控訴人県知事の上記判断に裁量権の逸脱又は濫用があるということはできない。
○ 前記事実関係等によれば,市は,本件公社に対し,本件事業の用に供する土地の先行取得を依頼し(本件依頼),本件土地を先行取得させるとともに,本件隣接地取得契約によりこれに隣接する本件隣接地を取得していたが,その後,図書館の建設事業を優先することになり,検討の結果,本件土地及び既に取得していた本件隣接地に図書館を建設することとしたため,これらを一体のものとして上記事業の用に供する目的で,本件売買契約により本件土地を買い取ったものである。
そして,市と本件公社との間で締結された本件売買契約における本件土地の取得価格6586万5900円についてみると,そもそも本件隣接地取得契約における本件隣接地の1㎡当たりの価格8万4700円が,前記…のとおり市において…の17筆の土地の分譲価格や本件隣接地の近隣2か所の県基準地の標準価格等を参考にして定められたものであり,相応の合理性を有するものであったところ,本件土地の1㎡当たりの価格7万2400円は,これを下回るものであったというのである。しかも,本件鑑定によれば,本件土地及び本件隣接地における平成16年12月7日から同19年8月14日までの間の地価変動率がマイナス10.7%とされており,本件隣接地の1㎡当たりの価格を上記地価変動率で本件売買契約の締結当時の価格に引き直すと約7万5600円となるところ,本件土地の1㎡当たりの価格は,これをも下回るものであったということができる。
そうすると,本件土地の取得価格は,上記に述べたところに照らし,特に高額であるとはいえない。
○ また,本件土地の取得価格は,本件土地の正常価格の約1.35倍であるが,そもそも当該正常価格は,本件土地を取得する目的や本件売買契約の締結に至る経緯等を考慮していないものであることが明らかである上,本件土地の取得価格と正常価格との較差(約1.35倍)自体についても,本件隣接地の取得価格と正常価格との較差(約1.27倍)と比較して,顕著な相違があるとはいえない。
○ もっとも,前市長は,本件公社との間で本件土地の売買契約を締結するに当たり,その取得価格につき,前記…のとおり本件公社が所有する保留地の簿価に基づいて算定された1㎡当たりの金額に本件土地の面積を乗じて決定したものであり,上記取得価格を決定するに当たり,不動産鑑定を実施したり,近隣の土地の分譲価格等と比較したりしていない点において,取引の実例価格等を必ずしも十分に考慮していない面があることは否定できない。しかし,上記取得価格を算定する際の基礎とされた上記簿価は,本件公社による本件土地を含む上記保留地の用地費(取得価格)に支払利息等(上記保留地の取得又は管理に要した経費や借入金に係る利子等)を加えたものであり,一定の算定根拠を有するものであったことに加え,その1㎡当たりの金額が,前記…で述べたとおり相応の合理性を有する本件隣接地取得契約における本件隣接地の1㎡当たりの価格や,これを本件売買契約の締結当時のものに引き直した価格を下回るものであったことからすると,前市長が上記簿価に基づいて本件土地の取得価格を決定したことが明らかに合理性を欠くものということはできない。
○ 以上によれば,本件公社との間で本件売買契約を締結した前市長の判断は,その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法となるということはできない。
【最高裁判例】 普通地方公共団体の財産の譲渡又は貸付けが適正な対価によるものであるとして議会に提出された議案を可決する議決がされた場合であっても,当該譲渡等の対価に加えてそれが適正であるか否かを判定するために参照すべき価格が提示され,両者の間に大きなかい離があることを踏まえつつ当該譲渡等を行う必要性と妥当性について審議がされた上でこれを認める議決がされるなど,審議の実態に即して,当該譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上これを認める趣旨の議決がされたと評価することができるときは,地方自治法237条2項の議会の議決があったというべきである 最判平30.11.6集民260.41
(市有地を開発して6.2万平米の団地を造成したが、3回の売却の試みは悉く不調であった。市は第三次の予定価格設定に際し、市不動産評価審議会が定めた4万平米に対する評価額5億円余に対し、本件土地が大規模であり近隣に類似する適切な取引事例が存在しないとして取引事例比較法による比準価格を採用せず、事業実施者が本件土地の造成及び販売に要する期間を考慮して5年後の価格を予測することとして、予定価格を4万平米に対し3億円弱(地区全体について4.6億円弱)としたことから、第四次の公募においても同様の理由により不動産鑑定評価額7.1億円余に対し3.4億円弱の予定価格を定めたところ、一者から3.5億円で応募があった。そこで市は同応募者と土地売却仮契約を締結し、市議会に対し、本件譲渡価格が地方自治法96条1項6号にいう適正な対価の範囲内であるという認識の下に、地方自治法96条1項8号及び受任条例(市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例)に基づき議案を提出し、同議案は可決された。この際、委員会では不動産鑑定価格7億円に対し予定価格3.4億円弱であったことの説明がなされ、本会議では出席した議員から本件土地の鑑定評価額は1坪当たり約3万8000円であるところ本件譲渡価格では1坪当たり約1万8000円で売却することになるなどの発言があった。翌年、当該年度土地造成特別会計決算に係る決算特別委員会は本件譲渡に関し、①本件土地の適正な対価は上記鑑定評価額(7.1億円)であるか否か、②本件譲渡が適正な対価なくしてされるものである場合に議会の議決があったか否か等について質疑及び討論を行い、決算不認定としたが、本会議では決算が認定された)
○ 地方自治法237条2項は,条例又は議会の議決による場合でなければ,普通地方公共団体の財産を適正な対価なくして譲渡し,又は貸し付けてはならない旨規定しているところ,同項の趣旨は,適正な対価によらずに普通地方公共団体の財産の譲渡又は貸付け(以下「譲渡等」という。)がされると,当該普通地方公共団体に多大の損失が生ずるおそれや特定の者の利益のために財政の運営がゆがめられるおそれがあるため,条例による場合のほかは,適正な対価によらずに財産の譲渡等を行う必要性と妥当性を議会において審議させ,当該譲渡等を行うかどうかを議会の判断に委ねることとした点にあると解される。そうすると,同項の議会の議決があったというためには,財産の譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上当該譲渡等を行うことを認める趣旨の議決がされたことを要するというべきである(最高裁平成15年(行ヒ)第231号同17年11月17日第一小法廷判決・裁判集民事218号459頁参照)。もっとも,当該譲渡等が適正な対価によるものであるか否かは評価に関わる事項であって見解が分かれることもあり得るところ,当該譲渡等が適正な対価によるものであるとして議案が提出された場合であっても,議会において,これが適正な対価によらないものであることを前提として審議した上これを認める趣旨で当該議案を可決することに制約が存するものではないから,そのように提出された議案を可決する議決であるからといって,直ちに同項の議会の議決でないということはできないし,また,当該譲渡等が適正な対価によらないものである旨の議会の認識を明らかにした上でされた議決でなければ,同項の議会の議決でないということもできない。そして,上記のような同項の趣旨に鑑みると,当該譲渡等が適正な対価によるものであるとして普通地方公共団体の議会に提出された議案を可決する議決がされた場合であっても,当該譲渡等の対価に加えてそれが適正であるか否かを判定するために参照すべき価格が提示され,両者の間に大きなかい離があることを踏まえつつ当該譲渡等を行う必要性と妥当性について審議がされた上でこれを認める議決がされるなど,審議の実態に即して,当該譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上これを認める趣旨の議決がされたと評価することができるときは,同項の議会の議決があったものというべきである。
○ これを本件についてみると,前記事実関係等によれば,市議会は,本件譲渡が適正な対価によるものであるとして提出された本件議案について,生活環境委員会において,本件土地の鑑定評価額が7億円であることや,本件予定価格が3億3777万8342円であることの説明を受け,本会議において,議員から平成23年鑑定評価額(注:上記7億円の鑑定額)と本件譲渡価格とでは坪単価が大きく異なることを指摘する趣旨の発言があった上で,本件譲渡議決をしたというのである。そうすると,市議会は,本件議案について,相応の根拠を有する平成23年鑑定評価額と本件譲渡価格との間に大きなかい離があることを踏まえて審議し,これを可決する議決をしたものということができる。さらに,市は,学校を統合してD地区に移転し,同地区に所在する本件土地を住宅地とする計画を表明しており,市議会においては,防犯や児童生徒の安全のため,同地区に小中学校が移転する平成25年4月までに本件土地が住宅地とされている必要がある旨の意見があったところ,本件土地については,2回一般競争入札に付されたが申込みはなく,その後に実施された公募においては大幅に減額された予定価格を下回る応募しかなかった上,その応募も撤回されたのであり,更にその後,本件公募によりEらが事業実施者として選定されたという経緯を経て本件仮契約の締結に至ったものである。そうすると,市議会においては,本件土地を譲渡して住宅地とする必要があったにもかかわらず,容易に本件土地を売り払うことができなかったという経緯を踏まえて本件議案の審議がされたものというべきであり,本件譲渡が適正な対価によらずにされたものであったとしてもこれを行う必要性や妥当性に係る事情が審議に表れているということができる。本件譲渡議決に係る審議の実態がこのようなものであったことは,本件決算を認定する本件決算議決がされたことに照らしても明らかである。以上の事情を総合的に考慮すれば,本件譲渡議決に関しては,市議会において,本件譲渡価格に加えて平成23年鑑定評価額を踏まえた上で,本件譲渡が適正な対価によらずにされたものであったとしてもこれを行う必要性と妥当性についても審議がされており,審議の実態に即して,本件譲渡が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上これを行うことを認める趣旨でされたものと評価することができるから,本件譲渡議決をもって,地方自治法237条2項の議会の議決があったということができる。
○ そして,本件譲渡の方式等についてみても,前記事実関係等に照らせば,プロポーザル方式により本件公募をし,Eらを選定した経緯等に関し,A市長が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したことをうかがわせる事情は存しない。したがって,本件譲渡に財務会計法規上の義務に違反する違法はなく,A市長は,本件譲渡に関して,市に対する損害賠償責任を負わないというべきである。
指名型プロポーザルを経て廃棄物処理業者と随意契約した事例について、プロポーザル通知以前から当該請負業者が契約の相手方として内定していたという事情が認定されていることを踏まえ、随意契約が許される場合に該当しないことについて請負業者は知っていたと推認できる事情のもとでは、当該契約は私法上無効であるとした事例 奈良地判平30.12.18判例時報2421.10
○ …補助参加人(注:請負業者たる本件契約の相手方)が本件契約の相手方に事前に内定していた状況で本件プロポーザルが行われたと認められること並びに本件契約の性質及び目的が競争入札に適さないものということができず、地方自治法234条2項、同法施行令167条の2第1項に違反することは前記3で判示したとおりである。そして、上記事情に照らすと、本件プロポーザルによっては、本件契約の相手方選定の公正を担保し得ず、随意契約の方法によることが許されないことは、契約の相手方である補助参加人においてもこれを知っていたものと推認することができ、これを覆すに足りる的確な証拠はない。
○ したがって、被告及び補助参加人の上記主張は採用することができず、本件契約は私法上無効であると認められる。そして、補助参加人は、本件契約に基づく支払が法律上の原因を欠くことについて悪意であると認められる。
保育所統廃合に伴う新用地買収において、市審議会で検討さていない用地で、かつ審議会で審議された所要面積より広大な敷地を正常価格より高額で購入する契約について、同売買契約締結に係る市長の判断には、裁量権の逸脱又は濫用があり、これが地方自治法2条14項、地方財政法4条1項に反し違法であることは明らかである上、その裁量権の逸脱又は濫用の程度は著しく、本件売買契約を無効としなければ地方自治法2条14項、地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情があるというべきであるから、本件売買契約は私法上無効であるとされた事例
甲府地判平31.4.9 (控訴審東京高判令2.1.23判例タイムズ1485.85原審)
(保育所統廃合による新保育所敷地について、用地買収の売買契約が締結されたが、市審議会では新保育所用地の所要面積を3千平米程度としていたのに対し、買収用地はこれまで審議会で検討されなかった用地であり、その広さは7千平米に及ぶものであった。また売買契約の相手方は、以前の市長選で市長と対立関係にあった前市長であり、市長が再選された場合には、市が対象土地を買い受ける意向があることが前市長に示され、選挙後、正常価格についての鑑定評価がされる前に、市長から前市長に対して購入見込額が直接伝えられたこと、市長は、この話合いによって前市長との関係が好転したという趣旨のことを述べていた。また購入価格は正常価格より相当高額であった。)
○ …A市においては、平成27年度の本件新保育所の新設を目指し、その用地の確保が求められていたが、旧病院用地に係る土地、ひいては本件買受地を本件新保育所用地とすることが適切であるのかについての実質的な議論がされた形跡がみられない状況において、Y市長により本件新保育所を建設するために旧病院用地に係る土地を買い受けるという判断がされたものであるところ、その他の…の経緯に鑑みると、本件審議会が平成23年○月○日にした答申に沿ってA地区に200名の定員規模の本件新保育所を設置するとしても、本件審議会においては3000㎡程度の面積が必要との説明がされていたことや、旧病院用地に係る土地が候補地として挙げられていたわけではないことなどからすれば、Y市長が7000㎡もの面積のある本件買受地を本件新保育所の適地と判断した理由は不分明である。そして、本件売買契約の相手方は、Y市長とは平成25年までの市長選挙では対立関係にあったB前市長であったところ、平成25年2月の市長選挙の前から、Y市長が再選された場合には、A市が旧病院用地に係る土地を買い受ける意向があることがB前市長に示され、選挙後の同年3月下旬頃、正常価格についての鑑定評価がされる前に、Y市長からB前市長に対して購入見込額が直接伝えられたこと、Y市長は、この話合いによってB前市長との関係が好転したという趣旨のことを述べていること、その後にB前市長の利便・利益に大きく配慮した分筆がされて本件売買契約に至ったこと、平成29年2月の市長選では、B前市長はY市長の支持に転じたことなどの事実からすれば、旧病院用地に係る土地を本件新保育所の用地としてA市が買い受けるとのB前市長の判断には、B前市長との関係を好転させ、政治的な協力を得たいというY市長の思惑も伏在していたものと考えざるを得ない。
○ …以上によれば、本件売買契約については、2億5200万円という代金が正常価格と評価できる1億5000万円を1億0200万円も上回っているというだけでなく、本件買受地の取得の経緯につき、A市が買い受ける土地について、鑑定評価が行われることが予定されているにもかかわらず、Y市長が、地権者であるB前市長に対して、鑑定評価が行われる前の時点で購入見込額を伝えるなど、適正手続の観点からの重大な問題があり、さらに、本件買受地が本件新保育所の用地として適地であると判断された理由が不分明である上、その目的には、Y市長において、それまでの市長選では対立関係にあったB前市長から政治的な協力を得たいという思惑も伏在していたとみられるのであって、これは、財政上必要最小限の支出を行うことを求める地方自治法2条14項、地方財政法4条1項に照らし、許容し難い他事考慮であるといわざるを得ない。
○ そうすると、本件売買契約締結に係るY市長の判断には、裁量権の逸脱又は濫用があり、これが地方自治法2条14項、地方財政法4条1項に反し違法であることは明らかである上、その裁量権の逸脱又は濫用の程度は著しく、本件売買契約を無効としなければ地方自治法2条14項、地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情があるというべきであるから、本件売買契約は私法上無効というべきである。
○ なお、仮に本件売買契約が私法上無効とまではいえないとしても、これまで述べてきた事情からすれば、本件売買契約の締結は、著しく合理性を欠きそのためその締結には予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存在するというべきであるし、本件売買契約においては、契約に疑義を生じたとき、又は契約に定めない事項については、被告及び売主が協議して定める旨(11条)の条項が置かれているところ…、本件売買契約の相手方は、A市長としてA市政に携わってきたB前市長とその親族であり…、こうした地位にある者に対して正常価格を著しく超える高額な売買代金額が提示されて本件売買契約が締結され、そのまま本件売買契約に基づく支出がされれば、A市に多大な損害が発生する事態が生じたのであるから、B前市長らに対して、本件売買契約の解消又は売買代金額の減額に向けた働きかけを真摯に行えば、B前市長らにおいて本件売買契約の有効性に固執することはその立場上困難であって、本件売買契約の解消又は売買代金額の減額に応ずる蓋然性が高かったと認められ、客観的にみてA市が本件売買契約の解消又は売買代金額の減額をすることができる特殊な事情があったともいい得る。
○ そうすると、副市長が行った本件支出命令及びA市会計課が行った本件支出行為は違法というべきであるし、これまで述べてきたところによれば、本件売買契約の締結は、Y市長が主導的に進めていたというべきであるから、Y市長において、本件支出命令及び本件支出行為を阻止すべき指揮監督上の義務に違反し、故意により本件支出命令を阻止しなかったと認められる。
○ したがって、被告は、Y市長に対し、不法行為に基づく損害を賠償するよう請求しなければならないというべきである。
事故繰越予算から支出命令を行ったことについて、事故繰越が違法であったとしても、委託契約について業務履行した契約相手方に対し、適法に計上された予算から支出命令をすること自体は免れることができず、損害を観念できない以上、当該支出命令権者が自治体に損害賠償を負うものではないとした事例 大阪地判令元.6.26判例地方自治465.88
○ 原告らは、本件事故繰越しの理由は、予算成立時に既に存在していた事情であり、「避けがたい事故」((地方自治)法220条3項ただし書)があるとはいえないから、本件事故繰越しは違法であり、事故繰越予算からの支出命令である本件支出命令2、3は違法であるから、これについてAは損害賠償責任を負う旨主張する。
○ (ア) そこで検討すると、普通地方公共団体の各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならず(法208条2項)、原則として、毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することはできない(法220条3項本文)。このように、一会計年度の収支は、他の年度にまたがってはならないが(会計年度独立の原則)、予算の効率的執行を図るため、繰越明許費(法213条)及び事故繰越し(法220条3項ただし書)等の例外が認められている。
ここで、繰越明許費は、予算の定めるところにより(予算を定めるには議会の議決を要する。法96条1項2号)繰越しが明許されるものであるのに対し、事故繰越しは、予算に定めることなく、予算の執行としてその支出の繰越しを認めるものであり、歳出予算の経費の金額のうち、既に支出負担行為が行われたもので、かつ、「避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったもの」についてのみ認められるものである。
このように、事故繰越しは、会計年度独立の原則の例外として、予算の効率的な執行の見地から、予算の執行の段階において、地方公共団体の長の判断で行うことができるものとされていることを勘案すると、前記の「避けがたい事故」(法220条3項ただし書)とは、支出負担行為の後で、かつ、当該会計年度中に発生したものである必要があると解するのが相当である。
○ (イ) 前記(ア)を前提として、本件において「避けがたい事故」があると認められるかについて検討すると、町が本件事故繰越しの原因としたのは「火葬場建設事業に係る事前協議等に時間を要したため、業務着手までに日程を費やしたことによる、事業進捗の遅れ」であり…、これは、支出負担行為である本件建築設計契約の締結(平成○年○月○日)後に発生した事情であるとはいい難い。また、被告は、本件訴訟において、本件事故繰越しの理由は、「…町火葬場建設事業建築基本・実施設計等業務委託の委託契約の変更について」と題する書面…に記載のとおりであると主張するが、その記載内容…も、本件建築設計契約の締結前に大阪府との協議が長引いたことをいうのみであって、支出負担行為後に発生した事情であるとは認められない。
その他、本件建築設計契約について、支出負担行為である本件建築設計契約締結後に「避けがたい事故」が発生したことを認めるに足りる証拠がないから、本件事故繰越しは、法220条3項ただし書の要件を満たさない違法なものであるといわざるを得ない。
○ しかしながら、本件支出命令2、3の当時、D社は本件建築設計業務の一部又は全部の履行を完了し、本件建築設計契約に基づき、能勢町に対する委託金額の請求権を有していたというべきである…。 すなわち、本件支出命令2、3の当時、町は、本件建築設計業務の一部又は全部を履行し、履行の確認等の所定の手続も履践したD社に対し、委託金額の支払義務を負っていたというべきであり…、法220条3項ただし書の要件を満たさないため、本件建築設計契約を支出負担行為とする支出について事故繰越しによることはできないとしても、D社に対して、所定の手続を経て適法に計上された予算から、本件支出命令2、3と同額の支払をすることは免れなかったものである。そして、本件支出命令が本件事故繰越しによって繰り越された予算からされたことにより、町に、本件支出命令2、3による出捐額を超えて、何らかの損害が発生したことを認めるに足りる証拠はない。
そうすると、本件事故繰越しが違法であるため本件支出命令2、3が違法であるとしても、Aが本件支出命令2、3を行ったことにより、町に何らかの損害が発生したということはできない。
○ したがって、Aが、事故繰越予算から本件支出命令2、3を行ったことについて、町に対する損害賠償義務を負うとは認められない。
前市長から保育所用地を買い受けて当該代金を支払った場合において、現市長が前市長から政治的協力を得たいという思惑も伏在していたと推認されることは地方自治法2条14項、地方財政法4条1項の趣旨に反するが、当該売買契約が私法上無効となるとは言えず、本件支出命令および支出は違法ではないとした事例 東京高判令2.1.23判例タイムズ1485.85
(事実関係は原審甲府地判平31.4.9参照。本件住民訴訟では契約締結部分は監査請求期間要件に抵触するため排斥され、支出命令・支出部分が本案審査された。なお本件売買契約前に執行され当該市長が再選された市長選では前市長は現市長の対立候補を支持していたが、契約後執行された次回市長選では現市長を支持したという)
○ 市長が、未だ部内検討中で庁内協議にも報告されていない段階で、前市長に対し、担当職員を通じ又は一人で面会して、旧病院用地を買い受ける意向を伝え、購入代金の見込額まで伝えたことは、適正手続の観点からすると問題があり、市長がこのような行動をとったのは、市長において、それまでの市長選では対立関係にあった前市長から政治的な協力を得たいという思惑が伏在していたものと推認される…ことは、地方自治法2条14項、地方財政法4条1項の趣旨に反するというべきである。
○ しかし、平成○年○月の市長と前市長との面談については、X市長は、購入代金を見込額として伝えたにとどまり…、市長も前市長も、市が旧病院用地を購入するに当たっては不動産鑑定の評価額によらなければならないことを知悉していたこと…、市長が本件新保育所の用地として本件買受地を取得したこと自体に、裁量権の逸脱又は濫用は認められないこと…、本件買受地の取得価格の根拠となったC鑑定は、前記のとおり疑問点があり、評価額は、やや高額ではないかと考えられるものの、不動産鑑定士としての裁量の範囲内に納まっていること…、市長や市の職員が、C鑑定士に対し、購入見込額を伝えるなど鑑定評価額について働きかけをしたとは認められないこと…、前市長宅に直結する道路部分を買い受けたこと及び本件覚書を交わしたことは違法とはいえず、その他B前市長に対し、違法な優遇措置がとられたとは認められないこと…を総合考慮すると、上記…の事実をもって、少なくとも、市長の裁量権の逸脱又は濫用が著しいものであり、本件売買契約を無効としなければ地方自治法2条14項、地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められ、本件売買契約が私法上無効となるとはいえず、かつ、上記〈ウ〉の特殊な事情(注:最判平20.1.18民集62.1.1、最判平25.3.21民集67.3.375にいう「特殊な事情」のこと)も認められない。
東京築地市場移転先用地を取得するため複数筆の土地を正常価格の目安となる価格の約1.37倍から約1.41倍の価格で買い取る各売買契約を締結した都財務局長の判断が裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法であるとはいえないとされた事例
東京地判令2.7.21判例タイムズ1502.158
○ 正常価格とは、市場性を有する不動産について、現実の社会経済情勢の下で合理的と考えられる条件を満たす市場で形成されるであろう市場価値を表示する適正な価格をいう(「不動産鑑定評価基準」…)。そして、地方公共団体が土地を正常価格に比して著しく高額な対価で取得することは、地方公共団体の財政の適正確保の見地から看過し得ないものとして地方自治法2条14項等の趣旨に照らし違法と評価される場合があるが、その取得価格が正常価格を超えるからといって、直ちに違法となるものではなく、取得価格と正常価格との差のほか、購入の必要性やその土地の代替可能性、交渉経過等をも考慮した上で、その適法性を判断すべきである(最高裁平成26年(行ヒ)第321号同28年6月27日第一小法廷判決・裁判集民事253号1頁参照)。したがって、地方公共団体による土地の取得に係る契約の締結については、上記の判断基準に照らして、当該取得価格により取得することが、当該地方公共団体において契約を締結する権限を有する者に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又は濫用するものと認められる場合に、違法となるものと解するのが相当である。
○ 不動産の正常価格の意義については、上記…のとおりであるところ、「不動産鑑定評価基準」において、不動産に個別性を生じさせ、その価格を個別的に形成する要因の一つとして、土壌汚染の有無及びその状態が挙げられていること…、「不動産鑑定評価基準運用上の留意事項」において、土地に関する個別的要因について、土壌汚染が存する場合には、当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置に要する費用の発生や土地利用上の制約により、価格形成に重大な影響を与えることがあるとされ、土壌汚染対策法に規定する土壌の特定有害物質による汚染に関して、同法に基づく手続に応じて留意事項が挙げられていること…からすれば、土壌汚染のある土地の正常価格については、原則として、土壌汚染を考慮しない土地の価格から、一般の市場参加者が求めると考えられる土壌汚染対策のための費用を控除したものをいうものと解すべきである。
原告らは、本件各土地の正常価格について、順次、正常価格〈3〉、〈2〉及び〈1〉のとおりであると主張しているので、以下検討する。
○ 正常価格〈3〉について
原告らの主張する正常価格〈3〉は、土壌汚染を考慮しない土地の価格578億1427万8000円から、本件訴え提起時点で東京都が締結済みの契約に係る土壌汚染対策費用541億7475万円全額を控除した結果である36億3952万8000円を、本件各土地の正常価格とするものである。
しかしながら、上記土壌汚染対策費用は、本件各土地以外の土地を含む豊洲新市場予定地の土壌汚染対策費用である。豊洲新市場予定地全体の面積は約37万3185㎡であるのに対し、本件各土地の合計面積は約10万7941㎡であり、豊洲新市場予定地全体の面積の約28.9%にすぎない(争いのない事実)。したがって、本件各土地の正常価格を算定するために、土壌汚染を考慮しない土地の価格から上記土壌汚染対策費用全額を控除するのは、不合理といわざるを得ない。
したがって、本件各土地の正常価格として、正常価格〈3〉を採用することはできない。
○ 正常価格〈2〉について
原告らの主張する正常価格〈2〉は、土壌汚染を考慮しない土地の価格578億1427万8000円から、平成25年決算時点での土壌汚染対策費用762億円…を豊洲新市場予定地における本件各土地の面積の割合(28.9%)で案分した220億2180万円を控除した結果である357億9247万8000円を、本件各土地の正常価格とするものである。
しかしながら、本件各契約が締結されたのは、平成23年3月から同年4月にかけてであるところ、この時点で判明していた土壌汚染対策費用は、前記…のとおり、技術会議での検討を経た586億円であり、762億円に上るということが判明したのは事後のことであって、本件各契約が締結された時点において、同額となることを想定することができたとする事情は見当たらない。本件各契約の締結時点で想定することができなかった土壌汚染費用額を当該時点での本件各土地の正常価格の算定において考慮するのは不合理といわざるを得ず、本件各土地の正常価格として、正常価格〈2〉を採用することはできない。
○ 正常価格〈1〉について
原告らの主張する正常価格〈1〉は、土壌汚染を考慮しない土地の価格578億1427万8000円から、本件訴え提起の時点で東京都が締結済みであった契約に係る土壌汚染対策費用541億7475万円を豊洲新市場予定地における本件各土地の面積の割合(28.9%)で案分した約156億5650万円を控除した結果である421億5777万8000円を、本件各土地の正常価格とするものである。
正常価格〈1〉については、本件各土地の価格から控除する土壌汚染対策費用を面積割合で案分したものとすることについては、一般に合理性が認められるものの、本件各土地を含む豊洲新市場予定地の土壌汚染の程度は必ずしも均一ではないこと…からすると、その相当性について疑問の余地がないとまではいえない。また、専門家会議の提言に基づいて東京都が行うとした、本件各土地を含む豊洲新市場予定地についての土壌汚染対策は、A等が14年合意等及び17年確認に基づき環境確保条例に従った土壌汚染対策を一応完了した後に実施する、土壌汚染防止法や環境確保条例等の法令により求められる土壌汚染対策の基準を上回るもので、食の安全・安心という観点も考慮して安全対策を行うものであった(なお、専門家会議の提言内容やその提言を実現するための技術会議の試算内容が、その提言や試算がされた当時、明らかに不合理であったといえる事情はない。)。
確かに、一般の市場参加者が土地を購入するに当たり、土壌汚染防止法、環境確保条例等の法令の限度内での土壌汚染対策がされればそれ以上は土壌汚染の対策を求めないとは考えにくく、ましてや本件各土地は、本件各契約の締結から半年余りで形質変更時要届出区域に指定される程度にまで土壌が汚染されていたことからすれば、本件各土地の正常価格を算定するに当たり、土壌汚染防止法、環境確保条例等の法令により求められる以上の土壌汚染対策費用を控除することについては、一応の合理性が認められるというべきである。しかしながら、上記東京都の土壌汚染対策は、一生涯豊洲の地に住んでも健康影響が生じることはないと説明されるほどの手厚いものであること…を考慮すると、正常価格の算定に当たって、東京都が行う上記土壌汚染対策に係る費用全額を控除することが必要であるとまでいい切るのは躊躇されるところである。
前記…のとおり、原告らの主張する正常価格〈1〉は、これをもって本件各土地の正常価格とすることになお疑問の余地がないとまではいえないものであるが、本件各土地の正常価格の目安として相応の合理性があることも否定し難いところであるから、以下、正常価格〈1〉が本件各土地の正常価格であることを前提として検討をする。なお、技術会議は、平成21年2月、専門家会議の提言を実現するための経費について、技術会議において策定した技術・工法を基に算定すると、586億円になると報告しているところ(前記前提事実(2)カ)、本件各土地の土壌汚染を考慮しない価格から、上記586億円を豊洲新市場予定地における本件各土地の面積割合(28.9%)で案分した169億3540万円を控除すると、408億7887万8000円となる。この金額についても、本件各土地の正常価格の目安として相応の合理性があるものと考えられるので、以下、正常価格〈1〉と併せて検討する(以下、この408億7887万8000円を「正常価格〈4〉」という。)。
○ 正常価格〈1〉が本件各土地の正常価格であるとすると、東京都の本件各土地の取得価格は578億1427万8000円であるから、その取得価格は正常価格を156億5650万円超えることになる。もっとも、較差にすると、取得価格は正常価格の約1.37倍にとどまる。次に、正常価格〈4〉が本件各土地の正常価格であるとすると、東京都の本件各土地の取得価格は正常価格を169億3540万円超えることになる。もっとも、較差にすると、取得価格は正常価格の約1.41倍にとどまる。そうすると、本件各土地の取得価格は正常価格より高額ではあるものの、その較差を考慮したときは、著しく高額とまでいうことには疑義がある。
○ 東京都による本件各土地の取得の必要性について
築地市場については、施設の狭隘・過密化・老朽化という問題が発生していたところ、東京都は、これに対処するため、平成13年12月に東京都卸売市場計画(第7次)を策定し、築地市場を豊洲地区へ移転する方針を決定し、その後、一貫して築地市場の豊洲地区への移転を目指していたのであり、築地市場の移転候補地として、本件各土地の所在する豊洲地区以外には見当たらない状態であったものである…。
もっとも、築地市場の上記…の問題への対処を巡っては、現在地再整備の方法も唱えられており、東京都議会においては、平成22年3月28日、「築地市場の老朽化を踏まえると、早期の新市場開場が必要であるが、これを実現するためには、なお解決すべき課題が多いことから、予算の執行に当たっては、以下の諸点に留意すること。〈1〉議会として現在地再整備の可能性について、大方の事業者の合意形成に向け検討し、一定期間内に検討結果をまとめるものとする。知事は議会における検討結果を尊重すること。(以下略)」とする付帯決議を付して平成22年度東京中央卸売市場会計予算が可決され、また、東京都議会の築地市場特別委員会は、同年10月5日、築地市場現在地再整備に関する四つの具体案を示した調査報告書を取りまとめていたにもかかわらず、参加人は、同月22日、築地市場の豊洲地区への移転を推進することを決断したことを明らかにし、東京都は、平成23年3月から4月にかけて本件各契約を締結したものである…。
しかしながら、築地市場現在地再整備は、東京都が委託した民間の設計事務所の試算結果によれば、整備期間が一番短いものでも、汚染対策や文化財及び埋蔵文化財の対策を除いて11年以上を要するとされていたのであり…、相当長期間を要するものであった。また、築地市場については、現在地における再整備が試みられたこともあったが、工期の遅れ、整備費の膨張、業界調整の難航という問題が発生し、平成7年に再整備工事は中断に追い込まれていた…。そうすると、築地市場特別委員会の取りまとめた築地市場現在地再整備に関する四つの具体案を採用せず、築地市場の豊洲地区への移転を推進するとしたことが、それ自体不合理であるとはいえない。
これに対し、原告らは、「市場問題プロジェクトチーム」の第一次報告書では、民間的手法を用いた場合には、営業しながらの改修で7年、一旦移転する方法では3年半の工期で築地市場現在地再整備が可能とされており、築地市場現在地再整備は不可能又は極めて困難ではなかったにもかかわらず、工期が長いのが致命的であるという誤った認識の下、築地市場の豊洲地区への移転が推進された旨主張する。しかしながら、上記「市場問題プロジェクトチーム」の第一次報告書が東京都知事に手交されたのは、平成29年6月13日であり…、本件各契約締結時点においては、築地市場現在地再整備が同報告書に記載された工期で可能と考えられることは明らかではなかったというべきである。そして、東京都は、上記のとおり民間の設計事務所に委託した結果、整備期間が一番短いものでも、汚染対策や文化財及び埋蔵文化財の対策を除いて11年以上を要するとの試算を得たものであり、その内容が不合理であったことをうかがわせる事情もないから、その整備期間を前提として築地市場の豊洲地区への移転を推進するという判断をし、本件各契約を締結したことが不合理であるとはいえない。さらに、本件各土地には相当程度の土壌汚染が存在したが、前記1(5)のとおり、多額の費用は要するものの、専門家会議の提言に盛り込まれた対策を行うことによって、一生涯豊洲の地に住んでも健康影響の生じることはないとされる程度に土壌汚染対策をすることが可能であったということができる。加えて、東京都は、本件各契約に先立ち、平成16年及び平成18年、豊洲新市場予定地の一部として、民間地権者から土地を既に取得し、保留地を買い受けており…、その活用も考慮する必要があったことは否定し難い。
○ 以上の諸事情を踏まえると、築地市場の豊洲地区への移転のため、本件各土地を取得する必要があると判断し、本件各契約を締結したこと自体が不合理であるということはできない。
○ A等の土壌汚染対策費用について
A等は、23年協定において、東京都が専門家会議の提言を受け、技術会議の検討も経て行おうとしていた土壌汚染対策の費用586億円のうち、78億円を負担することとなっており…、本件契約1及び2においては、代金の支払につき、当該78億円を控除した残額を支払うこととされている…。そうすると、A等による当該78億円の負担も、本件各土地の取得価格と正常価格との較差を検討する際に考慮されるべきであり、具体的には、当該78億円を豊洲新市場予定地における本件各土地の面積割合(28.9%)に応じて案分した22億5420万円を取得価格から控除すべきである。
本件各土地の売買代金額は578億1427万8000円であるところ、これから22億5420万円を控除すると、その取得価格は555億6007万8000円となる。そうすると、本件各土地の取得価格は、正常価格〈1〉(421億5777万8000円)を134億0230万円、正常価格〈4〉(408億7887万8000円)を146億8120万円それぞれ超えることになるが、較差にすると、それぞれ約1.32倍、約1.36倍にとどまるのであって、いずれにせよ、前記…より、価格差も較差も縮小する。
23年協定においては、A等の土壌汚染対策費用の負担額が78億円とされる一方、A等は、今後、豊洲新市場予定地等の土壌汚染に係る費用負担をしないこととされている…。この点について、原告らは、A等の責任を免除するような瑕疵担保責任免責条項を積極的に挿入し、A等に土壌汚染対策費用のうち僅か78億円のみを負担させるにとどめたことは明らかに不合理である旨主張する。そこで、23年協定の締結に至る経緯について検討する。
A等は、平成19年4月までに、約100億円を支出し、14年合意等及び17年確認に基づく土壌汚染対策を完了していた。しかし、専門家会議の調査により、新たに本件各土地を含む豊洲新市場予定地に土壌汚染が発見されたことから、東京都は、平成21年2月頃以降、技術会議の報告に基づく土壌汚染対策費用586億円の一部の負担を求めて交渉を開始したが、弁護士から、条例上の手続は済んでいるため法的責任について言及することはできないとの助言を受けていた。そして、A等は、将来の更なる追加負担の余地を残すことを拒絶し、負担額についても72億円とすることを提案するなどしていたが、交渉を重ねた結果、23年協定を締結するに至ったものである…。
A等が土壌汚染対策費用約100億円を既に支出していたことに加え、以上のような交渉経緯に鑑みれば、東京都がA等に対し、78億円以上の土壌汚染対策費用の負担を求めることや将来の更なる追加費用の負担の余地を残すことに固執した場合、A等の間で合意が成立せず、本件各土地の取得をすることが困難となっていた可能性も否定することができず、その結果、築地市場の狭隘・過密化・老朽化等の問題への対処が遅れたり、既に取得した豊洲地区の土地の活用といった問題が生じたりすることは否定し難い。このようなことからすれば、東京都がA等の土壌汚染対策費用の負担額を78億円とする一方、A等が今後対象用地の土壌汚染に係る費用負担をしないことを内容とする23年協定を締結したことが不合理であるということはできない。
○ 東京都財産価格審議会への付議について
東京都は、本件各土地の買収価格について、東京都財産価格審議会の議に付したが、その際、土地の土壌汚染については、処理費用の負担について、東京都と従前地権者との間で協議の上、別途取り扱うこととしていることから、評価に当たっては考慮外とするとの評価条件を付しているところ…、原告らは、この点について、土壌汚染の価格への影響について同審議会に諮らず、東京都公有財産規則を潜脱するものである旨主張する。
しかしながら、東京都財産価格審議会へ本件各土地の買収価格の付議においては、土地の土壌汚染の処理費用の負担を考慮外とする理由が明示されており、その上で、同審議会は、本件各土地の買収価格について、付された条件に異議をとどめず評定している…。したがって、同審議会への本件各土地の買収価格の付議において、土地の土壌汚染の処理費用の負担を考慮外とするとの条件を付したことは、東京都公有財産規則を潜脱するものとはいえない。
○ 以上のとおり、本件各土地の取得価格は、正常価格〈1〉及び〈4〉より高額ではあるものの、その較差でみると差が著しいものとまではいえず、A等による土壌汚染対策費用の負担額78億円を考慮すれば、較差は更に縮小する。その上、東京都が築地市場の豊洲地区への移転を推進するために本件各土地を取得することが不合理であったとはいえず、本件各土地の取得に際し、23年協定を締結し、A等に更に負担させる土壌汚染対策費用を78億円とし、今後、A等が土壌汚染対策費用を負担しないものとしたことも不合理であったとはいえないことなどからすれば、本件各契約を締結した財務局長の判断が、その裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用するものとして違法であるということはできない。
火葬場用地として産廃が存在する土地を産廃処理費を考慮せず高額で買収する違法な土地売買契約を締結しその土地での産廃撤去を含む工事請負契約を締結した事案における産廃撤去費を市が負担することが違法なので工事請負契約のうち産廃撤去部分も違法との主張につき、平成20年1月18日最判の契約無効に関する判断枠組みに照らし、違法無効となるものではないとした事例 奈良地判令2.7.21判例時報2488・2489.145
(市は火葬場の建設地としてAから用地買収を行うこととしたが、当該用地には撤去に1億円程度要する産業廃棄物が存在することが判明していた。また市が依頼した複数の不動産鑑定結果は、産廃を考慮しないとしてもAの想定(Aの父が当該地を競落した際の単価)より相当低額であった。そのため市とAの交渉は難航し、結局買収予定地に追加用地を含めた上で鑑定額より相当高額で買収し、かつ産廃撤去は市の負担で行うこととして売買契約が成立し、議会の議決も得た。そして市は産廃撤去を含む工事請負契約を事業者(Aではない)と締結した。当審は、土地売買契約締結について、当該土地は鑑定価格から産廃処理費を控除すれば実質的に無価値なのに鑑定額の3倍の価格で契約したこと、土地収用も可能なのに考慮されていないこと等を考慮し、市長の裁量権を逸脱する違法なものと判断した)
○ 契約に基づく債務の履行として行われる公金の支出について地方自治法242条の2第1項1号に基づく差止めを請求することができるのは、当該契約が私法上無効である場合に限られるところ(最高裁昭和56年(行ツ)第144号同62年5月19日第三小法廷判決・民集41巻4号687頁参照)、本件請負契約のうち産業廃棄物の撤去等に係る部分につき、裁量権の範囲の著しい逸脱又は濫用があり、同部分を無効としなければ地方自治法2条14項、地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合には、同部分は私法上無効になるというべきである(最高裁平成17年(行ヒ)第304号同20年1月18日第二小法廷判決・民集62巻1号1頁参照)。
○ 原告ら及び参加人らは、本件売買契約において、相手方D(注:市長)が、相手方Aらとの関係で産業廃棄物の撤去費用等をY市が負担することとしたことが違法であるから、本件請負契約のうちこれに関する部分についても違法である旨主張する。しかしながら、本件売買契約と本件請負契約は契約主体を異にしており、本件売買契約の違法によって直ちに本件請負契約のうち上記部分が相手方Dの裁量権の逸脱、濫用により違法無効になるものとはいえず、結局、上記の特段の事情があるとは認められないというべきである。
★同控訴審 大阪高裁令和3.2.26 ※当事者略号は引用ままであり、上記一審の記載略号との整合は考慮していない
※本件が上告不受理ののちの第2段訴訟で訴訟上の和解となったことについての住民訴訟については、下掲奈良地判令和7.5.22参照
○ …のとおり、Y市用地取得事務取扱要領において、同市の公共事業に必要な土地の取得に当たっては、その価格は、不動産鑑定士による不動産鑑定評価額を上限として算定し、一の土地につき複数の不動産鑑定評価を取得したときは、それらを平均した額を上限として土地の価格を算定するものと規定されているところ、これらの規定は公共用地の取得に関する市長の裁量を直ちに拘束するものではないものの、その趣旨に照らして、不動産鑑定士による不動産鑑定評価額は、価格決定に当たって重要な考慮要素とすべきものと定めたものといえ、…のとおり、相手方A(注:契約時のY市長)と相手方B(注:契約相手方。Dも同じ)らとは、平成27年7月30日、Y市は、本件買収地を鑑定評価等に基づく適正な価格で購入するものとし、最大限の努力をすることなどを内容とする本件覚書を取り交わしていたものである。そして、本件では、…のとおり、Y市は、本件買収地の近隣における取引事例が少ないことなどを考慮して、鑑定評価額の信頼性を担保するために、2社に対して不動産鑑定を依頼したところ、それらの不動産鑑定によって示された評価額の平均は463円/㎡((482円+445円)÷2。1円未満切り捨て)であり、これに本件買収地の面積(11万0780.88m2)を乗じた価格は5129万1547円(1円未満切り捨て)であったことが認められる。もっとも、…のとおり、本件買収地には産業廃棄物が投棄埋設されていることが判明していたが、本件鑑定は、いずれも、土壌汚染並びに地下埋設物の有無及びその状態について、価格形成要因から除外したものであったから、本件買収地に産業廃棄物が投棄埋設されていることを考慮した本件買収地の評価額は、上記金額を更に下回るものであったといえる。
そして、…のとおり、本件売買契約締結当時、本件買収地の取得目的である新斎苑整備事業を実施するためには、本件買収地に投棄埋設されている産業廃棄物を撤去する必要があり、その費用は1億円程度となる見込みであることが判明していた。その上、本件買収地は、現況が山林であって、標準的な画地よりも規模の大きい画地で、かつ、国定公園に指定され、一部保安林の指定があること等の公的諸規制を受けていた土地であり、利用用途及び需要者が限定されるなどの減価要因が存在する市場性の高くない土地であったもので、相手方Bらの父が昭和61年8月22日に競売による売却により取得して以降、長期間にわたり、現況の山林としての利用以外に特段の利用がされていたものとは認められない土地であったから、相手方Bらにおいて、本件買収地をY市等の地方公共団体などの限られた相手以外に処分することは困難な状況にあった(なお、相手方Bは、本件訴訟において、本件買収地には相続後に2、3回立ち入ったことがあるだけで、土地の中までは入れない状態であった旨の証言をしている。)。
そのような中にあって、…のとおり、相手方Aは、上記のように、5129万1547円を更に下回る価値しかなく、また、その取得に伴い1億円程度の産業廃棄物撤去費用を負担することが不可避となる本件買収地について、1億6772万2252円で購入する旨の本件売買契約を締結したのであり、このような本件買収地の取得価格は、土地の現況や評価額等に関する以上のような事情の下、通常の売買において想定される代金額と比べて、著しく不均衡な価格であったといわざるを得ない。
○ また、上記代金額で合意するに至った経過について検討してみると、…のとおり、Y市は、鑑定評価額が示される以前から、本件買収地の価格が4500円/㎡となることを想定して、新斎苑の用地取得費の枠として3億円程度を見込んでいたこと、…のとおり、Y市は、本件鑑定業者らから鑑定評価額が上記想定額よりも安価となる見込みであることを伝えられた際、相手方Bらから、本件買収地の購入費として6億円くらいはみてほしい、合併特例債を使えないようにしようと思えば、自分にはそのようにできる、鑑定評価額が低ければ本件買収地を売るつもりはないなどと言われていたこともあって、鑑定評価額を引き上げるため、本件鑑定業者らに対し、公共用地の取得事例を基礎に含めて鑑定するよう要請したこと、しかしながら、本件鑑定業者らから、そのような要請に応じることは困難であると伝えられたため、Y市は、F川ダム事例を含む4つの公共用地取得事例の全部又は一部を加味した14パターンもの価格を算出したにもかかわらず、相手方Bらとの交渉経過を踏まえて、最終的には、そのうち、その当時想定されていた本件撤去費用との合計額が3億円を超え、かつ、これに最も近いF川ダム事例のみを考慮した価格に決定したことが認められ、これらの事実からすれば、Y市は、新斎苑の建設には、合併特例債を活用して本件買収地に建設する以外には方法がないとの判断の下で、相手方Bらの代金額についての要求を受けて、必ずしも根拠の明らかでない3億円という当初予定した金額を念頭にして、本件鑑定の評価額を高く誘導しようとし、それができなかったため、鑑定評価額にY市が適当であると考える公共用地取得事例を加味して、独自の評価額を算定し、最終的にはこの評価額に基づく本件買収地の代金額と本件撤去費用との合計額が3億円程度となるように調整して本件買収地の代金額を決めたものと認められる。
○ さらに、本件買収地に追加買収地を含めることについても、…のとおり、Y市新斎苑基本計画や都市計画決定において追加買収地は含まれていなかったこと、…のとおり、相手方A及びG副市長が、平成29年11月15日、相手方Bらが追加買収地を売却しない意向であるならば、検討する旨述べていたこと、…のとおり、相手方A及びG副市長が、平成29年12月時点においても、追加買収地の活用計画の具体的な内容については今後詰めていく旨、その費用や財源については現時点では示すことができない旨、かえって、追加買収地をY市が取得した後に具体的な活用計画を議論すべきであると考えている旨を答弁したことからすれば、追加買収地については、本件売買契約締結時点において、具体的な活用方針が決定していたとはいえず、同時点での追加買収地の購入の必要性については、必要性が明確でない中で、相手方Bらの意向も踏まえて、追加買収地を本件買収地に含めることにしたことが推認できる。
○ 確かに、…のとおり、新斎苑の建設は、Y市における長年の懸案事項であった上、本件売買契約締結当時には、既存施設の老朽化や高齢化に伴う需要の拡大といった事情により、本件買収地を取得して新斎苑を建設する必要性は更に高まっていたものと認められる。しかしながら、上記…のとおり、本件売買契約は、5129万1547円を更に下回る価値しかなく、また、その取得に伴い1億円程度の産業廃棄物撤去費用を負担することが不可避となる本件買収地を、1億6772万2252円で購入したという著しく不均衡な価格によるものであり、しかも、上記…のとおり、その代金額は、相手方Bらの代金額についての過大な要求に少しでも応じるべく、必ずしも根拠の明らかでない3億円という当初予定した枠について、F川ダム事例を考慮するなどして後から説明を付けた数字にすぎないものといえるのであるから、上記必要性を踏まえても、そのような価格で本件買収地を取得することが正当化できるものとはいい難い。
○ また、…のとおり、平成30年改正前は、合併特例債を活用するためには平成32年度末までに新斎苑整備事業を竣工する必要があったところ、…のとおり、本件請負契約の工期はおよそ3年であったから、平成32年度末までに本件請負契約に係る工事を竣工するためには、工事の前提となる用地の取得を平成29年度末までに完了させる必要があったといえる。しかしながら、合併特例債を活用することができれば、対象事業費の大部分が地方交付税交付金として国から交付され、Y市の財政からの負担を填補することができることになるからといって、上記ア及びイのような価格で本件買収地を取得し、相手方Bらに不相当な利益を得させることになる結果が正当化されるものでないことは、上記…と同様である。また、…のとおり、そもそも、相手方Aは、平成29年8月には、合併特例債の再延長を求める首長会に参加し、合併特例債の発行期限が延長される可能性があることを認識していたにもかかわらず、…のとおり、同年11月19日、この点に関して何らの留保も付さずに、1億6772万2252円で本件買収地を購入することを相手方Bらと合意し、また、その後、合併特例債の発行期限を5年間再延長する旨の法改正がされることが確定的となっていく中で(なお、上記首長会に参加していた相手方Aは認定事実…の報道がされるよりも早い時点で、より正確な情報に接していたものと推認される。)、…のとおり、平成30年2月15日に本件売買契約を締結し、同年3月23日にY市議会による同意の議決を得たというのであるから、相手方Aは、合併特例債の起債期限が延長されることを認識してなお、本件売買契約の締結に踏み切ったものといわざるを得ず、このような観点からも、合併特例債の起債期限が迫っていたことは、相手方Aが、上記…のような価格で本件買収地を取得したことを正当化する事情とはならない。
○ 以上によれば、本件買収地取得の必要性や合併特例債の起債期限を考慮しても、相手方Aが合理性を有しない上記代金額で本件売買契約を締結したことは、地方自治法2条14項及び地方財政法4条1項の趣旨に照らし、同人に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用してしたものであるといわざるを得ない。
都市計画で決定された公園計画区域内に都市計画を変更しないまま一般廃棄物処理施設への廃棄物運搬車両専用道路を設置したことについての4号訴訟において、当該通行路設置は都市計画法上違法であり、前記通行路設置のための契約締結は地方自治法2条14項、地方財政法4条1項に違反することとなるから、市長がその職務上負担する財務会計法規上の義務に違反してされた違法なものと評価されるべきとして請求を認容した事例 東京地判令2.11.12判例時報2505.3
(事実関係は上記の通りであり、当審は、本件通行路設置は都市計画法上違法と評価すべきと判断した上で、次のとおり判示した)
○ …のとおり、本件都市計画を変更しないまま、本件都市計画と異なる都市施設である本件通行路をその計画区域に設置することは、都市計画法上違法と評価されるものであるところ、市長は、本件都市計画の変更をしないまま、本件通行路を設置するための本件各契約を締結したものである。
○ 市は、本件都市計画事業の施行者であるとともに、本件都市計画の変更に係る権限を有しており…、市長は、市の執行機関として、本件都市計画の変更の手続を行うことにより本件通行路の設置に係る都市計画法上の違法を是正する権限を有していた。それにもかかわらず、市長は、その権限を行使せず、上記の違法を是正しないまま、都市計画法上許されない本件通行路の設置をするため、債務負担行為である本件各契約の締結をしたものである。このような本件各契約の締結に係る市長の判断は、その裁量権の範囲の逸脱又はその濫用となるものであることが明らかであり、地方公共団体の事務につき不必要な経費を負担させるものとして地方自治法2条14項及び地方財政法4条1項に違反することとなるから、市長がその職務上負担する財務会計法規上の義務に違反してされた違法なものと評価されるべきである。
…
○ 以上によれば、本件各契約の締結は財務会計法規上違法であり、市長は、本件各契約の締結により市に生じた損害について損害賠償義務を負う。
庁舎解体工事入札において最低制限価格と同額の入札をした業者を落札者とした工事請負契約に基づく支出命令が違法と主張する4号訴訟において、予定価格や最低制限価格の推測は著しく困難ではなく最低制限価格と同額(ほぼ同額)の入札事例が多い等の事情を踏まえ、本件契約締結に際し同社が入札の公正な執行を妨げたとか公正な取引の秩序を見出すこととなる恐れがあって著しく不適法である(地方自治法施行令167条の4第2項2号、同令167条の10第1項)と認めることはできず、本件支出命令は違法ではないとした事例 大阪高判令2.12.3判例地方自治485.11
(事実関係は上記の通りであり、当審では、たしかに同市の入札では最低制限価格通りまたはほぼ同額での入札例が多く、最低制限価格が漏えいしていたとの疑念を生じさせる事情があったこと、市の課長が入札工事関係非公開情報を漏えいしていたといった事情があったが、予定価格や最低制限価格については工事内容に特殊性がない限り業者にとってこれを推測することは著しく困難ではなく、本件は特殊性のある工事ではないこと、同課長の漏えいは特定の者との個人的事情による影響が大きいことがうかがわれ、他に市の入札情報漏えいがあったことをうかがわせる事情は認められないことから、上記の事情により直ちに本件入札当時、庁舎解体工事に係る入札において、情報漏えいや職務の清廉性・入札の公平に強い疑念を抱かざるを得ない状況にあったとはいえない認定した)
○ 以上によれば、第1審原告らが指摘する上記事情から、直ちに、本件入札に際し、○建設が事前に本件最低制限価格等を知っていたと推認することはできない。そして、本件全証拠によっても、本件工事はもとより、○建設が関わった他の市の建築工事についても、市の担当者から○建設に対して入札に係る非公開情報が漏えいしたことを裏付ける具体的事情を認めることはできないのであって、○建設の本件入札への参加及び本件契約の締結に際し、全淡建設が入札の公正な執行を妨げた(地自令167条の4第2項2号)であるとか、○建設と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適法である(地自令167条の10第1項)と認めることはできない。
○ 第1審原告らは、上記…のとおり、〈1〉○建設の本件入札への参加及び本件契約の締結が、地自令167条の4第2項2号等に該当することを前提として、〈2〉市は本件特約条項※1項に基づく本件契約の解除権を有しており、(市長)は本件契約を解除する権限を有するとともに、本件契約を解除せずに本件支出命令2を行ってはならないという財務会計法規上の義務を負っていたことから、この義務に反してなされた本件支出命令2は違法であると主張する。
しかしながら、上記…のとおり、第1審原告らが指摘する上記事情から、直ちに、本件入札に際し、○建設が事前に本件最低制限価格等を知っていたと推認することはできず、○建設の本件入札への参加及び本件契約の締結が地自令167条の4第2項2号等に該当するということはできないから、(市長)において、本件契約を解除せずに本件支出命令2を行ってはならないという財務会計法規上の義務を負っていたということはできない。
○ 以上によれば、本件支出命令2が違法であることについての第1原告らの主張は、理由がない。
※ 本件契約には、市は、○建設が、本件契約の入札に関して、地方自治法施行令167条の4第2項2号に該当すると認めたときは、本件契約を解除できる、この場合においては、○建設は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として市の指定する期間内に払わなければならない、とする特定の違法行為に関する特約条項がある
和解にあたる協定を議会の議決を経ずに締結し事後的に追認議決したことは、事実関係に照らせば議会の裁量権の逸脱濫用には当たらず、同協定は追認議決により議決欠缺の瑕疵が治癒され有効となったとした事例 東京高判令3.3.25判例地方自治486.24
(市営サッカー場に隣接する私立学校の野球場から土砂が飛散堆積したため、市がX円を支払って除去し、市長が専決により、同校がX円の半額を負担するとの協定を締結したところ、残額について同校に市は損害賠償請求権を有しているのに市長がその行使を怠ることは違法な財務会計行為に当たるとする4号訴訟。本件一審判決において、同校は市に土砂除去費用相当額の損害賠償責任を負担した(民法198条)と認定の上、同協定は和解にあたり(民法695条参照)、よって地方自治法96条1項12号で議会の議決を要するところ、これを経ていない(金額が専決処分可能額(地方自治法180条1項による議会指定事項)を超えている上、歳入および歳出の財源内補正予算の議決はあったが同協定の説明をした形跡がないことから、議会は同議決で同協定を承認したとは認められず、事後的な議会の承認はないと判断)から同協定締結は違法な財務会計行為に当たると判断された(判決は請求認容)ことを受け、同判決後、市長は市と同校が土砂除去費用X円の半額ずつを負担するとの内容の和解をする議案を議会に提出し、同議案は可決された。当審では事後的追認議決の有効性が争点となったところ、最判平24.4.20民集66.6.2583、最判平24.4.23民集66.6.2789を引用の上、次の通り判示)
○ 上記の事実によれば、市が本件除去費用の支出を要することとなった原因は、主に学園による本件野球場の整備作業によって土砂の飛散が進んだことにあると考えられるものの、市の対応が後手に回ったことがその損害の発生・拡大に少なからず寄与していると考えられるから、市が学園との間で、本件除去費用の負担について、市と学園の双方が負担を分け合う形で合意による解決を図ることには、合理性があるといえる。また、本件除去費用の支出自体は、市長による専決処分とこれを承認する議会の議決を経て、適正に行われたものであり、その内容としても市民の利用に供されている市有財産の維持管理に用いられたものであるから、その一部を最終的に市の負担にとどめることとしても、不当な公金支出がされることにはならない。そして、市議会は、原審において本件協定の締結には議会の議決を欠くという手続的瑕疵があると指摘されたことから、その瑕疵を是正して違法な状態を解消するために本件追認議決を行ったものであって、本件追認議決が行われたことは住民訴訟の存在意義を無に帰するものではなく、むしろ、住民訴訟を通じて行政の適正化を実現するものであるといえる。
○ 以上によれば、市議会が本件協定の締結を追認する議決をしたことは、普通地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする地方自治法の趣旨等に照らして不合理であるとはいえず、議会の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるとは認められない。
○ そうすると、本件協定の締結は、本件追認議決が行われたことにより地方自治法96条1項12号違反の瑕疵が治癒され、有効となったというべきである。
○ したがって、控訴人が学園に対して本件除去費用の残額の支払を請求しないことが違法な財務会計行為であるということはできない。
大阪市が大阪府に市立高校等を一括移管することを計画し、当該高校等に係る不動産の行政財産の用途を廃止し当該不動産を契約で無償譲渡を予定した場合において、本件は、普通財産は公用又は公共用に供するため特に無償とする必要がある場合に限り国又は公法人にこれを譲与することができるとする大阪市条例の適用案件ではなく個別議決を要するものであるが、議会審議の内容から学校廃止にかかる条例案審議議決において個別議決に相当する議決がなされていることから地方自治法96条1項6号および237条2項に反するとの原告主張を排斥した事例 大阪地判令4.3.25判例時報2572.5
(事実関係は上記の通り。本件訴訟は種々の論点を含むが、そのうち、大阪市財産条例16条に普通財産は公用又は公共用に供するため特に必要がある場合に限り国又は公法人に譲与することができると定めており、本件譲与が地方自治法96条等の条例にあたり議会の議決を要しないか、そうでない場合は議会の議決の存否も争点となっている)
○(1) 本件譲与について(大阪市)財産条例16条が地方自治法96条1項6号及び237条2項にいう条例に当たり議会の議決が必要ではないといえるかについて検討する。
○ア 地方自治法96条1項6号及び237条2項にいう条例について
地方自治法96条1項6号及び237条2項の規定及び趣旨は、前記…のとおりである。
地方自治法96条1項6号は、条例で定める場合を除くほか、適正な対価なくして財産を譲渡し(譲与はこれに含まれる。)、又は貸し付けることを議会の議決事項とし、同法237条2項は、条例又は議会の議決による場合でなければ、適正な対価なくして財産を譲渡し、又は貸し付けることを禁止する。その趣旨は、適正な対価によらずに普通地方公共団体の財産の譲渡又は貸付け(以下「譲渡等」という。)がされると、当該普通地方公共団体に多大な損失が生ずるおそれや特定の者の利益のために財政の運営が歪められるおそれがあるからである。ただし、財産の譲渡等にも様々な類型があり、上記のようなおそれが乏しいということが類型的に判断することができる場合もあるのであるから、そのような類型的にみて、一般的取扱いになじむものについては、あらかじめ条例で基準を設けることにより、個別の議会の議決を要しないようにする趣旨であると解される。言い換えれば、条例では一般的に取扱いのできるものを定めるものとし、それにより難いものは、個別に議会の議決を求める趣旨であると解される。
現行の地方自治法96条1項6号及び237条2項の規定は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和38年法律第99号)により改正されたものであるところ、その当時、所管行政庁から、一般的基準を定める条例の一例として示されたのが、本件条例準則…であると解され、本件条例準則は、同法96条1項6号及び237条2項にいう条例の意味を解釈する手掛かりとなるものといえる。本件条例準則は、その3条において条例により普通財産の譲与又は減額譲渡をすることができる場合を1号から4号まで列挙している…。そして、上記各号の内容をみると、普通財産の譲与等のうち類型的に当該普通地方公共団体に対する財政の悪影響が小さいとみられるため、一般的に取り扱うことができる場合を条例に列挙して、当該類型に該当する事例では条例に基づき譲与等をすることを認め、それ以外の類型については、当該普通公共団体に対する財政への悪影響の有無及び程度等を精査して譲渡等の可否を議会の議決という形式で判断するというのが、地方自治法96条1項6号及び237条2項の趣旨であると解される。
○イ 本件譲与との関係での財産条例16条の地方自治法96条1項6号及び237条2項にいう条例該当性について
財産条例16条は、普通財産は、公用又は公共用に供するため特に無償とする必要がある場合に限り、国又は公法人にこれを譲与することができると規定するところ、その文言からすれば、同条が適用される譲与は、一定の要件を満たす必要があるとはいえ、相当広範なものが想定されており、本件譲与についても、財産条例16条を適用することができると解釈する余地はある。
しかし、本件譲与は、本件移管に伴って行われるものであるところ、本件移管は、大阪市立の高等学校22校全て及び中高一貫校の中学校2校全てを一括して大阪府に移管するという大規模なものであり…、本件譲与も、別紙財産目録一覧のとおり、21校の高等学校等の土地及び建物(本件不動産)の譲与という大規模なものである。また、本件不動産の価格は、令和2年4月1日現在の台帳価格で合計約1510億円であり…、高額である。さらに、他の普通地方公共団体を含め、これほどの規模の学校の一括移管は、大阪市から大阪府への特別支援学校の移管の事例(大阪市から大阪府に特別支援学校12校が移管され、この移管に伴い、平成28年4月1日現在の台帳価格で合計約345億円の土地及び建物が財産条例16条に基づき大阪市から大阪府に譲与された事例)があることを踏まえても、前例が見当たらない…。
そもそも本件不動産はいずれも行政財産であって、譲与するためには、大阪市教育委員会が本件不動産について行政財産の用途を廃止し、本件不動産を普通財産とする必要があるのであって、本件不動産はそのままでは譲与することが許されないものである。
地方自治法96条1項6号及び237条2項にいう条例は、前記アのとおり、一般的取扱いになじむものないし一般的に取扱いのできるものについて一般的基準を定めるものであると解されるから、普通財産の譲与又は減額譲渡のうち類型的に当該普通地方公共団体に対する財政の悪影響が小さいとみられるため、一般的に取り扱うことができる場合を条例に列挙している必要があると解される。もっとも、どのような場合であれば類型的に財政の悪影響が小さいとみられるかは、当該地方公共団体の規模や財産の価値等にも左右され得るので、列挙することが必要な事項を一義的に明らかにすることは困難である。少なくとも、上記のような本件譲与は、一般的取扱いになじむものないし一般的に取扱いのできるものとはいえないのであって、大阪市において普通財産の譲与について規定した財産条例16条があるからといって、本件譲与について、同法96条1項6号及び237条2項にいう条例があるとして、個別の議会の議決を要しないとはいうことはできない。
このように解することは、同法96条1項6号及び237条2項にいう条例の意味を解釈する手掛かりとなる本件条例準則に照らしても、妥当であると解される。すなわち、前記関係法令等の定め等…のとおり、本件条例準則において、普通財産の譲与又は減額譲渡について規定するのは、本件条例準則3条であるところ、同条は、行政財産の用途を廃止した場合において用途の廃止により生じた普通財産の譲与又は減額譲渡については、当該財産の維持及び保存の費用を負担した他の地方公共団体その他公共団体にその費用の額の範囲内において譲渡するとき(同条2号)、当該財産が寄附に係るものである場合にその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき(同条3号)及び代替となる他の財産の寄附を受けて用途を廃止した場合に寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき(同条4号)に限定しており、これらはいずれも当該行政財産の費用等を実質的に負担するなどの特別な関係のある者に対してのみ用途の廃止によって生じた普通財産の譲与又は減額譲渡を認める趣旨であると解される。ところが、本件譲与の相手は大阪府であるところ、大阪府は本件不動産と上記のような特別な関係にあるとは認められないので、本件条例準則が想定する条例を前提とすれば、本件譲与は、条例により行うことは許されないものと解される。
以上によれば、被告の主張を検討しても、本件譲与については、財産条例16条は、地方自治法96条1項6号及び237条2項にいう条例に当たるとはいうことはできず、財産条例16条があるからといって、個別の議会の議決を要しないということはできない。
○ウ したがって、本件譲与ないし本件無償譲渡契約の締結をするには、地方自治法96条1項6号及び237条2項の議会の議決が必要である。
○(2) そこで、本件譲与ないし本件無償譲渡契約の締結について地方自治法96条1項6号及び237条2項の議会の議決があったといえるかについて検討する。
ア 判断枠組み等
地方自治法96条1項6号は、条例で定める場合を除くほか、財産を適正な対価なくして譲渡し、又は貸し付けることを議会の議決事項として定め、同法237条2項は、条例又は議会の議決による場合でなければ、普通地方公共団体の財産を適正な対価なくして譲渡し、又は貸し付けてはならないと規定している。これらの規定の趣旨は、適正な対価によらずに普通地方公共団体の財産の譲渡又は貸付け(譲渡等)がされると、当該普通地方公共団体に多大の損失が生ずるおそれや特定の者の利益のために財政の運営がゆがめられるおそれがあるため、条例による場合のほかは、適正な対価によらずに財産の譲渡等を行う必要性と妥当性を議会において審議させ、当該譲渡等を行うかどうかを議会の判断に委ねることとした点にあると解される。このような同法96条1項6号及び237条2項の趣旨に鑑みれば、同法96条1項6号及び237条2項の議会の議決があったというためには、財産の譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上当該譲渡等を行うことを認める趣旨の議決がされたことを要するというべきである。(最高裁平成17年11月17日第一小法廷判決・裁判集民事218号459頁、最高裁平成30年11月6日第三小法廷判決・裁判集民事260号41頁参照)
同法96条1項6号及び237条2項の議会の議決があったというためには、適正な対価によらない財産の譲渡等について議決を求める個別の議案に対して議決がされることが本来的に予定されているといえる。しかしながら、同法96条1項6号及び237条2項の趣旨に鑑みれば、その形式いかんにかかわらず、議会においてその趣旨に沿った審議がされて議決がされることこそが必要であると解されるから、これらの条項によって求められる議決とは、上記のような個別の議案に対する議決に限定されないと解するのが相当である。上記のような個別の議案が提出されなくとも、当該財産の譲渡等に関連する議案が提出され、この議案を可決する議決がされる過程において、適正な対価によらずに当該財産の譲渡等を行う必要性と妥当性について審議がされた上で当該譲渡等を行うことを認める趣旨の議決がされるなど、審議の実態に即して、当該譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上で当該譲渡等を行うことを認める趣旨の議決がされたと評価することができるときは、同法96条1項6号及び237条2項の議会の議決があったと解するのが相当である。
○イ 検討
(ア) 前記前提事実(3)ウ及び前記認定事実(2)エのとおり、令和2年12月9日の市会本会議定例会において、議案第182号(本件条例案(注:大阪市立学校設置条例の一部を改正する条例案のこと。本件条例案は、大阪市立学校設置条例の一部を改正し、同条例に規定されている大阪市に設置する学校から、高等学校の全て並びに中学校のうち中高一貫校である大阪市立の2中学校を削ることを内容とするものである))が可決されており(本件議決)、本件議決をもって、地方自治法96条1項6号及び237条2項の議会の議決といえるかが問題となるので、本件条例案の審議及び議決について検討することとする。
(イ)a 前記認定事実(2)アのとおり、大阪市長は、同年11月27日の市会本会議定例会において、本件条例案について、本件移管に伴い、高等学校等24校を廃止するため、議会の議決を求めるものである旨説明しており、本件条例案が、本件移管に伴うものであることを明らかにしている。
b 前記認定事実(2)イのとおり、同年12月3日の教育こども委員会において、教育委員会教育長が、本件条例案について、本件移管をするため、大阪市立学校設置条例の一部を改正するものであることを明らかにした上で、移管計画案…及び譲渡財産の取扱いの基本的な考え方2…の書面を机上に配付した上で、移管に際しての方針及び譲渡財産の基本的な考え方は、移管計画案及び譲渡財産の取扱いの基本的な考え方2のとおりであると説明している。そうすると、本件条例案が本件移管を行うためのものであることが明らかにされており、また、上記書面のうち移管計画案には、本件移管の全体に関することが記載され、その中で、本件移管に係る「移管に関しての対応方針」の「財政」の「資産・負債」の項目に「土地、建物、工作物及び備品等については、大阪市より大阪府に対して無償譲渡する。」と記載され、譲渡財産の取扱いの基本的な考え方2には、本件移管に伴う譲渡財産の取扱いの考え方の全体が記載され、その中で、「財産は、無償で譲渡し、移管後の起債償還費については、大阪府において負担する。」と記載されているのであるから、本件移管の一内容として本件譲与(本件不動産の無償譲渡)が行われることが明記されているといえる。
また、…委員の質疑及びこれに対する答弁をみると、議案としては、大阪市立学校設置条例の改正を可決するかどうかであるが、移管計画案及び譲渡財産の取扱いの基本的な考え方2の内容を含め、本件移管について一体のものとして判断することが、教育こども委員会の審査の前提となっているといえる。
さらに、…委員の質疑及びこれに対する答弁をみると、同委員が、大阪市民の大切な財産である土地の無償譲渡は絶対に許されないなどと指摘した上で、無償譲渡の対象となる土地の価格等について質疑したのに対し、移管する予定の21校の土地の価格は、令和2年4月1日時点の公有財産台帳上の価格で約1275億円であること等の答弁がされ、また、高等学校の運営を大阪府に移管するとしても、土地及び建物(本件不動産)を無償譲渡とすることの必要性について、質疑及び答弁がされている。
そのほか、…委員の質疑において、本件移管の計画において、本件不動産を含む資産が無償で譲渡されることになっていることを前提として、高等学校等の資産を大阪府に譲渡することが目的ではないかという指摘があり、…委員の質疑及び答弁においては、本件不動産を含む資産が無償で譲渡されることを前提として、その後のチェック等について議論がされており、さらに、…委員の質疑において、1500億円ともいわれる財産を無償譲渡されることを前提として、府市間の覚書の効力に疑問を呈し、財政状況が厳しい大阪府に上記財産を譲渡してはならない旨の質疑がされている。
そうすると、同日の教育こども委員会において、本件不動産を含む資産が無償で譲渡されることを前提として、その是非等が議論されたといえる。
c 前記…のとおり、同月9日の教育こども委員会において、本件条例案について、本件附帯決議を付して原案を可決すべきものと決したところ、本件附帯決議は、本件移管に当たり、譲渡財産の取扱いの基本的な考え方2に基づき、財産が無償で譲渡されることを前提として、譲渡された財産が今後の府立高等学校の教育の充実に確実に活用されるための方策を提示する内容となっている。
d 前記…のとおり、同月9日の市会本会議定例会において、…教育こども委員長が、教育こども委員会に付託された議案第182号(本件条例案)について、同委員会では、本件附帯決議を付して原案を可決すべきものと決したと報告したところ、その中で、土地の無償譲渡について多くの委員から質疑があったことを報告した。また、本件条例案に反対の立場から討論をしたL議員は、反対する理由の一つとして土地の無償譲渡を挙げるとともに、土地の無償譲渡については、財産条例16条の要件を満たさないなどの法令上の問題点があることを主張した。本件条例案に賛成の立場から討論したae議員は、資産及び負債を含め、高等学校運営全体を大阪府が一体的に管理運営すること、すなわち、本件不動産を含む資産を大阪市から大阪府に無償で譲渡し、移管後の起債償還費を大阪府が負担することを前提とする主張をした。そして、議案第182号(本件条例案)は、前記cの内容の本件附帯決議を付して原案のとおり可決された。
このように、同日の市会本会議定例会における委員長報告、討論及び議決(本件議決)は、本件移管に伴い、高等学校等の本件不動産を含む資産が大阪市から大阪府に無償で譲渡されることを前提としてされたものといえる。
(ウ)a 本件条例案が議案として市会に提出される前の本件移管に係る検討状況等についてみるに、前記認定事実(1)アによれば、大阪市立の特別支援学校及び高等学校の大阪府への一元化に向けた検討が行われ、平成26年1月に旧基本的な考え方案…のとおり実施することが決定され、旧基本的な考え方案の中で、特別支援学校及び高等学校の土地、建物及び備品については、大阪市より大阪府に対して無償譲渡するとされていた。もっとも、この段階では、大都市制度ないし特別区設置(いわゆる大阪都構想)の実施を前提とするものであった。
b その後、前記…によれば、平成27年度に実施された特別区設置に係る住民投票が否決されるなどし、大阪市長や教育委員会等は、大都市制度ないし特別区設置とは切り離して本件移管を実施することを前提として、本件移管について、令和元年8月に基本的な考え方案を可決し、令和2年1月及び2月に中間報告素案及び中間報告案を作成し、同年8月に移管計画案を可決し、本件移管に伴う譲渡財産の取扱いについて、同年9月及び11月に譲渡財産の取扱いの基本的な考え方1及び2を決定し、これらは、中間報告素案を除き、書面及び口頭で、教育こども委員会で報告された。これらは、本件移管は、高等学校等を大阪市から大阪府に移管するものであるとし、本件移管について、財政、教育内容等及び組織・人員の点等を総合的に検討して方針等を形成するものであり、その中の財政の項目では、当初より、本件不動産等の資産については、大阪市より大阪府に対して無償譲渡することとする一方、移管後の起債償還費や施設整備費等の負債や経費については、大阪府が負担することとされてきた。したがって、これらについて報告を受けてきた教育こども委員会ないし市会において、本件条例案の審査及び審議より前の段階で、本件移管の内容が上記のようなものであることを十分に認識していたというべきである。
c また、前記…によれば、令和元年10月2日の教育こども委員会において、本件移管の内容が上記のようなものであることを前提として、本件移管の目的や本不動産の無償譲渡の理由等について質疑及び答弁がされ、同年11月7日の決算特別委員会において、…委員が土地の無償譲渡の必要性について質疑をし、これに対する答弁の中で、移管する予定の21校の土地及び建物の価格が、平成31年4月1日時点の公有財産台帳上の価格で、土地が約1193億円、建物が約216億円、合計が約1409億円であること、これに対する起債残高が平成30年度末時点で約134億円であること等の具体的な金額を提示した上で、その必要性があることの説明がされるなどした。令和2年2月17日の教育こども委員会において、中間報告案に関するものを含む大阪市立の高等学校等の大坂府への移管について質疑及び答弁が行われ、同年3月6日の財政総務委員会において、…委員が、本件不動産等の大阪市民の財産を無償譲渡することについて質疑し、これに対する答弁の中で、大阪市立高等学校について、平成31年4月1日時点の価格で、土地が約1193億円、建物が約216億円、合計が約1409億円であると説明されるなどし、令和2年3月18日の教育こども委員会において、本件移管に伴い本件不動産等の資産が無償で譲渡されることを前提として、移管後の土地等の取扱いについて、質疑及び答弁がされた。さらに、同年9月18日の教育こども委員会において、再編整備の対象となる工業系高等学校3校の土地の面積や価格について、質疑及び答弁がされた。
これらの審査ないし審議は、本件条例案が提出される前のものであるから、本件条例案の審査ないし審議そのものではないが、前記bの報告等を受けてされたものであり、本件条例案に係る教育こども委員会の審査並びに市会本会議の審議及び議決(本件議決)の前提となるものである。
(エ) 市会は、令和2年12月9日の市会本会議定例会において、議案第182号である本件条例案を可決する旨の議決(本件議決)をしたところ、前記(イ)及び(ウ)のような委員会の審査並びに市会本会議の審議及び議決の状況からすれば、本件議決は、単に大阪市立学校設置条例に規定されている大阪市に設置する学校から高等学校等24校を削るという内容の同条例の一部改正を認める趣旨の議決にとどまらない。本件条例案は、本件移管に伴い、高等学校等24校を廃止するためのものであり、その旨の説明もされている上、本件条例案の審査及び審議並びにその前提となる審査ないし審議の中で、本件移管の目的ないし趣旨及び本件不動産等の資産の無償譲渡の必要性ないし理由等について、前記のような説明、報告、質疑及び答弁がされるなどしてきたのであるから、本件議決は、本件移管を行うことの是非を決するための議決であり、本件議決はこれを肯定する旨の意思表示であるといえ、その中には、本件移管の一要素である本件不動産等の資産を無償譲渡することを肯定する旨の意思表示も含まれるといえる。そして、前記の委員会の審査及び市会本会議の審議の中において、本件譲与(本件不動産の無償譲渡)について、本件移管の中では、大阪府に新たな負担が生じるものもあるが、本件不動産そのものについては対価を受けることなく大阪市が無償で譲渡するものであること、本件譲与の相手方が大阪府であること、本件譲与の目的が本件移管を行うために行うものであること、本件譲与の対象である本件不動産が本件移管の対象となる高等学校等の土地及び建物であること、本件不動産の価格が、平成31年4月1日時点の公有財産台帳上の価格でいえば、合計約1409億円であり、千数百億円程度であること等が明らかになっていたのであるから、本件譲与について審査及び審議するのに必要な限度では、本件譲与の内容、相手方並びに対象財産の内容及び価格が特定されていたといえる。
そうすると、本件条例案が市会に提出される前の審査ないし審議を前提として、本件条例案について、教育こども委員会の審査を経て、市会本会議においてされた本件議決に関しては、本件譲与が本件不動産の無償譲渡であって適正な対価によらないものであることを踏まえつつ、本件譲与を行う必要性と妥当性についても審議がされるなどしており、審議の実態に即して、本件譲与が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上で本件譲与を行うことを認める趣旨の議決がされたと評価することができる。
したがって、本件譲与ないし本件無償譲渡契約の締結について地方自治法96条1項6号及び237条2項の議会の議決があったということができる。
○(3) 原告らの主張について
原告らは、議案第182号(本件条例案)に関する市会の審議及び委員会の審査は、地方自治法96条1項6号及び237条2項の議決又は処分行為の議決を行うためという目的が欠けており、その内容をみても本件譲与の必要性や妥当性を審議ないし審査したと評価できる事情は存せず、むしろ、議員は、本件譲与は財産条例16条に基づいて行われるため議決はしないという前提で上記議案の審議及び議決に臨んでおり、また、大阪市は、本件譲与を財産条例16条に基づき行うため議会の議決は不要であるという前提に立っていることなどからすれば、本件譲与について同法96条1項6号及び237条2項の議会の議決があったとはいえないと主張し、…・大阪市会議員もこれに沿う陳述をする…。
確かに、大阪市長は、市会に議案第182号(本件条例案)を提出したが、本件譲与について議決を求める個別の議案は提出していない。また、大阪市においては、本件譲与を財産条例16条に基づき行うこととし、本件譲与について同法96条1項6号及び237条2項の議会の議決は必要がないという見解が採られ、これに沿う対応が採られている。
しかし、前記(2)アのとおり、同法96条1項6号及び237条2項の趣旨に鑑みれば、同法96条1項6号及び237条2項の議会の議決があったというためには、適正な対価によらない財産の譲渡等について議決を求める個別の議案に対する議決に限定されず、審議の実態に即して、当該譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上で当該譲渡等を行うことを認める趣旨の議決がされたと評価することができるときは、同法96条1項6号及び237条2項の議会の議決があったと解するのが相当である。そして、前記(2)イで詳述したとおり、議案第182号の審査及び審議の前提となる本件移管に係る方針の決定等に係る事実経過及び委員会の審査ないし市会の審議の内容、議案第182号が市会に提出された後の教育こども委員会の審査及び市会の審議の内容並びに本件議決の内容等を子細に検討すれば、本件議決に関しては、審議の実態に即して、本件譲与を行うことを認める趣旨の議決がされたと評価することができるというべきである。
なお、前記(1)のとおり、本件譲与については、財産条例16条があるからといって、個別の議会の議決を要しないということはできないが、前記(1)イのとおり、同条の規定の文言からすれば、本件譲与についても、同条を適用することができると解釈する余地はあるので、大阪市において、本件譲与を同条に基づき行うこととし、同法96条1項6号及び237条2項の議会の議決は必要がないという見解が採られていても、この見解が一見して明らかに不合理であるとはいえず、大阪市長等の対応が著しく不合理であるとはいえない。また、大阪市において上記見解が採られていることと、審議の実態として、市会において本件譲与を行うことを認める趣旨の議決がされたと評価することができることとは、事実としては両立するものであり、現に両立している。したがって、大阪市において上記見解が採られていることは、直ちには同法96条1項6号及び237条2項の議会の議決があることを否定する事情とはならない。
○ 以上によれば、上記の原告らの主張は、採用することができず、原告らのその余の主張を検討しても、前記判断は左右されない。
○(4) まとめ
以上によれば、本件譲与ないし本件無償譲渡契約の締結が地方自治法96条1項6号及び237条2項に違反する違法な行為に当たるとはいえない。
なお、本件無償譲渡契約の締結が財産条例16条の要件を満たさず同条に違反するとしても、前記のとおり、本件無償譲渡契約の締結について地方自治法96条1項6号及び237条2項の議会の議決があったということができるので、本件無償譲渡契約の締結が同法96条1項6号及び237条2項に違反する違法な行為に当たることにはならないから、争点(4)(本件譲与ないし本件無償譲渡契約の締結は、財産条例16条に違反する違法な行為に当たるか(財産条例16条が地方自治法96条1項6号及び237条2項にいう条例に当たるとして、財産条例16条に違反し、ひいては同法96条1項6号及び237条2項に違反する違法な行為に当たるか))について判断する必要はない。
(市議会は防災情報発信システム構築業務委託のための予算(総額7億円弱)を議決した。予算審議の際、防災情報発信システム構築業務委託料として2か年度計7億円弱が計上されていたものの、システムの内容や契約の相手方に関する資料は配布されなかった。また市の担当者は、防災情報発信システム構築業務について、上記予算額を説明した上、委員からの質問に対して、全世帯の80%が戸別受信機を設置する前提で予算を計上していること、防災情報の発信方法は、市庁舎の放送室から、直接話して放送する又はパソコンに打ち込んで電子放送で戸別受信機に発信することを予定していること、緊急時であれば音量をゼロにしておいても最大音量で放送が流れること、町や区単位での放送又は各公民館からの放送が可能であることなどを説明した。また、市の担当者は、委員からの戸別受信機を2階に持ち運びできるかとの質問に対して、今後プロポーザル方式で業者を選定するため、戸別受信機の性能や通信方式(無線方式か有線方式か)はまだ決まっておらず、本件予算審議後に機種を選定して仮契約を行い、同年6月の議会で承認を得る予定であることなどを説明した。その後プロポーザル方式で選定した業務受託者と委託契約を締結し、最終的に約4億円強の委託料を支払ったが、契約にあたり議決は得ていない。なお、市は条例で地方自治法96条1項5、8号の事件につき地方自治法施行令の基準額と同額で議決事項を指定しており、本件契約は条例限度額を超えていた。本件は議決欠缺の違法契約を主張する4号訴訟であり、裁判所は、本件契約は地方自治法96条1項5、8号の工事請負、動産買入契約にあたると認定した上で、争点(本件予算議決により実質的に議会の議決を経たものといえるか)について次の通り判示)
○ …のとおり、(地方自治)法96条1項5号及び8号の趣旨は、契約の締結や財産の取得又は処分のうち、一定の重要な種類及び金額のものについては、普通地方公共団体にとって重要な経済行為に当たるものであるから、これに関しては住民の利益を保障するとともに、これらの事務の処理が住民の代表の意思に基づいて適正に行われることを期することにあるものと解される。
そして、政令等で定める契約の締結や財産の取得又は処分が、その性質としては予算の執行行為であるにもかかわらず、法96条1項2号に規定する予算の議決とは別に、同項5号又は8号において、議会の議決を要する事件として掲げられていることからすれば、法は、本来同項5号又は8号の規定に基づく議決は、予算の議決とは別個の議案について行われることを予定しているものと解され、そのような形で議決が行われることが望ましいというべきである。
○ しかしながら、独立した議案が提出・議決されない場合であっても、当該契約に係る歳出項目などが計上された予算の審議において、当該契約の締結の適否につき議決することが認識され、当該契約を締結する必要性及び妥当性についての審査を経て議決がされるのであれば、前記…の法の趣旨は満たされるということができる。
○ これを本件についてみると、前記のとおり、X年12月定例市議会以降、戸別受信機を市全戸に設置することが必要であるとの意見が述べられていたところ…、〈1〉 本件予算審議において、市の担当者は、防災情報発信システム構築業務について、業務委託料の予算額を説明した上、委員からの質問に対して、市内全世帯の80%が戸別受信機を設置する前提で予算を計上していることや、防災情報発信システムの概要を説明したにとどまり…、防災情報発信システムの無線方式及び有線方式のそれぞれの特徴についての説明はされなかったこと、〈2〉 市の担当者が、今後プロポーザル方式で業者を選定するため、戸別受信機の性能や通信方式(無線方式か有線方式か)はまだ決まっていない旨説明しているとおり…、通信方式も含めた契約の内容、契約金額、契約の相手方についても未定であったこと、〈3〉 市の担当者は、委員に対し、本件予算審議後に機種を選定して仮契約を行い、X+1年6月の議会で承認を得る予定であると説明していたこと…、以上の各事実からすれば、その場に出席した委員は、契約の具体的な内容は、X+1年6月の議会で議案として提出され、議論を経て議決されるものと認識していたものと認められる。
○ 以上によれば、本件予算審議は、X+1年6月の議会で議決を行うことを前提に、その準備として大枠の予算を通すために行われたものにすぎないというべきであり、本件予算審議において、本件契約の締結の適否につき議決することが認識されていたということはできない。
○ したがって、本件予算議決により、実質的に法96条1項5号及び8号の要求する議会の議決を経たということはできない。
市がケーブルテレビ会社と防災情報発信システム事業の契約を締結した際予算議決は経たものの地方自治法96条1項5号ないし8号の議決はなされなかった事案において、一審で議決欠缺により違法な契約と判断されたが、控訴審係属中に追認議決がなされたことにより議決欠缺の瑕疵は遡って治癒したとされた事例とした事例福岡高判令5.8.23判例地方自治511.92(上記令和4年佐賀地判の控訴審)
(事実関係は上記の通りであるが、当契約には内容として戸別受信機の購入や各戸におけるケーブルテレビ情報網と戸別受信機との配線工事等が含まれており、一審はこの契約は工事請負契約(地方自治法96条1項5号および地方自治法施行令121条の2(現2の2)第1項により個別議決事項とされるもの)等に該当し契約締結につき議決を要するものと判断した上で、本件の事実関係に照らし契約締結にかかる個別議決が欠けているとした)
○ 追認議決の存在は補正後の原判決「前提事実」のとおりであり、これにより、本件契約は遡って適法なものとされ、瑕疵は治癒されたと認められる。
○ 本件契約を追認しないと大規模な撤去工事が必要になること及び市議会がこのことを考慮してやむを得ず追認議決をしたことを認めるに足りる証拠はない。また、仮にそうであったとしても、市議会は、本件契約が無効とされた場合の撤去工事等による不利益と控訴人の責任を追及して得られる利益とを衡量した上で市の利益のために追認議決をしたものと推認することができ、その判断は尊重されるべきものであるから、このことを理由に追認議決の効力を否定することはできない。
○ 追認議決に当たり、市が市議会に有線方式と無線方式の優劣に関する説明をしなかったことを認めるに足りる証拠はなく、かえって、証拠…及び弁論の全趣旨によれば、市議会は、本件契約締結後の令和2年9月14日に全員協議会を開催して市担当者に有線方式と無線方式のメリット・デメリットについての説明をさせ、原判決言渡し後の令和4年12月22日から令和5年1月20日までの間の4回の特別委員会で、市担当者に有線方式を採用した理由を説明させた上で追認議決に至ったことが認められる。なお、前記証拠によれば、市議会は、有線方式と無線方式との優劣以外にも、付議なしに本件契約が締結された経緯等についても市担当者に説明をさせたことが認められ、本件契約の締結に関する問題点を把握した上でこれを追認したものということができる。
○ よって、被控訴人ら(一審原告)の請求は、その余の点について判断するまでもなく、理由がない。
4号訴訟で原告勝訴した後提起された地方自治法242条の3による第2段訴訟において、同訴訟の被告である市長等の損害賠償額を減額する和解案が示され議会が和解議案を可決し損害賠償請求権が一部放棄されたことに対し提起された3・4号訴訟において、第2段訴訟における請求権一部放棄の和解は許されないということはできず、また第2段訴訟での和解による請求権一部放棄についても上記平成24年最判の判断枠組みが妥当するとした上で、議決及び和解に違法はないとした事例 奈良地判令和7.5.22
(前記大阪高判令和3.2.26が最高裁の上告不受理決定で確定したところ、市長が市議会に請求権放棄議案を提出したが、議会がこれを否決したことを受け、市は地方自治法242条の3に基づくいわゆる第2段訴訟を市長等に提起した。同訴訟が係属する奈良地裁は、被告市長等への請求額を縮減し、市はその余の請求を放棄する等の条項を含む和解案を提示した。市長は同和解案について地方自治法96条1項10および12号に基づき、和解することについて議案を提出した。議会は地方自治法242条10項に基づき監査委員への意見聴取をしたところ、監査委員は原案同意の意見を提出した。議会はこれを受け審議採決の結果、可否同数により議長決定で議案を可決した。その結果、奈良地裁で上記訴訟上の和解が成立し、和解に基づく金員が市に支払われた。本件は、主位的に確定判決に係る損害賠償請求権の行使を怠る事実が違法であることの確認を求めるとともに、予備的に、第2段訴訟において市を代表した代表監査委員および市長が違法な和解をしたことにつき、市長、代表監査委員等に損害賠償請求をすることを求める3・4号訴訟)
○ …平成24年最高裁判決(注:最判平成24.4.20民集66.6.2583)は、普通地方公共団体の議会の議決を経た上でその長が債権の放棄をする場合には、地方自治法240条3項、地方自治法施行令171条の7の規定の適用がなく、この場合における放棄の実体的要件を制限する規定が存しないこと…を前提として、その放棄の適否の実体的要件については、住民による直接の選挙を通じて選出された議員により構成される普通地方公共団体の議決機関である議会の裁量権に基本的に委ねられていること…を示した上、議会の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるか否かの判断基準…を示したものである。そして、普通地方公共団体の議会の議決を経た上でその長が債権の放棄をする場合におけるその放棄の実体的要件を制限する規定が存しないことは、4号訴訟(第1段目の訴訟)係属中にその請求に係る損害賠償請求権を放棄する旨の議決がされる場合と、4号訴訟認容判決確定後の第2段目の訴訟において確定判決に係る損害賠償請求権の一部放棄を内容とする和解をする旨の議決がされる場合とで異ならないことからすると、後者の場合におけるその一部放棄の適否の実体的要件についても、住民による直接の選挙を通じて選出された議員により構成される普通地方公共団体の議決機関である議会の裁量権に基本的に委ねられているものというべきであり、平成24年最高裁判決の判断枠組みが妥当するものと解するのが相当である。
○ これに対し、原告らは、第2段目の訴訟は、第1段目の訴訟の確定判決における事実認定と法的判断を改めて争うことは許されず、第1段目の訴訟で確定した債権を粛々と実現するための手段という位置付けであり、第1段目の訴訟で確定した損害賠償請求権を第2段目の訴訟における和解により減額(一部放棄)することは想定されていない旨主張する。
○ そこで検討すると、平成14年改正後の新4号訴訟においては、第1段目の訴訟において当該職員又は相手方に対して訴訟告知がされ(地方自治法242条の2第7項)、その判決の効力が第2段目の訴訟の当事者間に及ぶものとされていることから(同法242条の3第4項)、4号訴訟認容判決確定後の第2段目の訴訟は、確定判決に係る損害賠償請求権の存在及び額を前提として審理及び裁判がされるべきことになるものと解される。しかしながら、4号訴訟の確定判決の効力が第2段目の訴訟の当事者間に及ぶことから直ちに第2段目の訴訟において和解をすることが法律上禁止されるわけではない。また、平成14年改正の立法過程をみると、改正案の問題点の一つとして「住民は第一次訴訟には参加できるものの、第二次訴訟手続には参加できず、第二次訴訟手続では地方公共団体とその職員が当事者となるから、馴れ合い訴訟の危険がある。例えば第二次訴訟手続で低額の和解をする等である。」(…日本弁護士連合会の平成13年5月9日付け意見書)との指摘がされていたものであり、この問題点の指摘に関しては、第153回国会平成13年12月4日衆議院総務委員会において政府参考人(総務省自治行政局長)が「今御指摘がありました、第一番目の訴訟の結果、第二番目の方に訴訟効力があるということで、今、仮に万が一の訴訟が起こった場合に、追及としては、首長さんが職員の方に同じ額を請求するということで訴訟が起こる。それで、和解はないと思います。これは、いずれにせよ、その額を請求せよということですから、その金額について争うんですけれども、先ほど来言っていますように、効力は及んでいるものですから、その判決は直ちに終わる、口頭弁論は終結を見るということでございまして、ほとんどの場合そういうことはあり得ないというぐあいに思っております。」、「仮定のお話でちょっと御答弁しにくいですが、和解というのは、議会の議決、九十六条で、どういう事由でございましょうか、議会にお諮りをして議決をすればあり得るわけです。あり得るわけでございますが、それは、住民の皆さん、議会の皆さん、みんなが見ている中での議決でございますので、どういう理由でございましょうか、和解の議決はほとんど想定されないなということを申し上げました。」と答弁しているところである…。この答弁は、第2段目の訴訟における和解が想定し難い旨述べるものであるが、地方自治法96条の議会の議決を経た上で和解をすることが法的には可能であることを前提とするものと解される。
○ このような平成14年改正の立法過程に照らしても、4号訴訟認容判決確定後の第2段目の訴訟における和解が許されないということはできない。そして、和解による請求権の一部放棄の適否の実体的要件については、これを制限する規定が存しないから、住民による直接の選挙を通じて選出された議員により構成される普通地方公共団体の議決機関である議会の裁量権に基本的に委ねられているものというべきであり、平成24年最高裁判決の判断枠組みが妥当するものと解するのが相当である。
本件和解の違法性について
○ 市が本件第2段目訴訟においてAとの間及びBらとの間でした本件和解は、地方自治法96条1項10号及び12号に基づく議会の議決としての本件議決並びにこれに先立つ同法242条10項に基づく監査委員への意見聴取…を経たものであり、和解による確定判決に係る損害賠償請求権の一部放棄をするための手続的要件を満たしている。そして、その一部放棄の適否の実体的要件については、前記…のとおり、住民による直接の選挙を通じて選出された議員により構成される普通地方公共団体の議決機関である議会の裁量権に基本的に委ねられているものというべきであり、平成24年最高裁判決の判断枠組みが妥当するものと解するのが相当である。
○ そこで、平成24年最高裁判決の判断枠組みを参照の上、本件和解により確定判決に係る損害賠償請求権の一部放棄をすることが普通地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする地方自治法の趣旨等に照らして不合理であり、市議会の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるものとして本件議決が違法となるか否かを検討する。
○ まず、本件売買契約の締結行為の性質及び内容についてみると、確定判決が認定した本件売買契約の締結行為の違法事由は、代金額が高額に過ぎた点にある(地方自治法2条14項、地方財政法4条1項)。もっとも、確定判決も説示するとおり、新たな火葬場の建設は市の長年の課題であり、早期に本件買収地を取得して新斎苑の建設を実現する必要性は高かったものといえる。また、(平成30年改正法による再延長前の)合併特例債の発行期限が平成32年度末に迫り、3年の工期を前提とすると、平成29年度末までに地権者であるBらとの売買契約の締結及びこれを前提とする請負事業者との請負契約の締結に至る必要がある状況の中で、Aは市長として用地取得に係る交渉の期間や内容等につき相応の裁量を有していたといえる。仮に平成29年11月に行われたBらとの代金額の交渉を不調として任意買収による本件買収地の取得を断念し、土地収用手続に切り替えたとするならば、その当時は合併特例債の発行期限の再延長が不確実であったことからすると、合併特例債の活用による財政負担の軽減を図ることができず、市の利益に反する結果となるおそれもあったといえる。この点につき、確定判決は、合併特例債の活用による財政負担の軽減は本件売買契約の価格の違法性を正当化する事情とはならない旨などの説示をしているが、その法的判断を前提としても、合併特例債の発行期限が迫っていたことを帰責性の程度に関する事情として考慮することは妨げられないというべきである。以上の事情のほか、市において本件買収地の代金額を決めるに当たり、何ら根拠なく本件鑑定の評価額と異なる代金額を算定したのではなく、本件鑑定の評価額に加え、近傍における公共事業の用地取得事例である岩井川ダム事例を併せ考慮したものであり、その代金額の算定には相応の根拠があったとみる余地もあること、市議会において必要な議決を得るなどの所要の手続が履践されていたことも考慮すると、本件売買契約の締結行為が市長に与えられた裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たることがその態様等に照らして明らかな状況であったとまではいい難い。この点については、確定判決も、Aに「故意又は少なくとも過失」が認められると説示するにとどまるところである。そうすると、Aにおいて本件売買契約の締結行為が違法であることを容易に認識し得る状況にあったとはいえず、Aの帰責性が大きいということはできない。
○ 他方、Bらについては、確定判決は、代金額の交渉におけるBらの行動が社会通念上許される範囲を逸脱し、不法行為法上違法である旨説示するが、その法的判断を前提としても、Bらは、本件売買契約の締結行為の適否を判断する立場になく、交渉を経て市との間で代金額の合意に至ったことから私法上有効な本件売買契約を締結し、これに基づいて代金を受領したにすぎないものである。本件売買契約の締結行為が市長に与えられた裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たることが明らかな状況であったとまではいい難いことは上記のとおりであるから、Bらが受領した代金が高額であることを考慮しても、Bらの帰責性が大きいということはできない。
○ 次に、本件売買契約の締結行為の原因及び経緯に関しては、上記の点のほか、少なくともAは、本件買収地の適正価格との差額から不法な利益を得て私利を図ろうとしたものでないことは明らかである。そして、本件売買契約の締結行為の影響に関しては、前記…のとおり、市が本件売買契約に基づいて本件買収地を取得し、本件請負契約に基づく新斎苑の建設工事が行われた結果、令和4年4月1日の新斎苑の供用開始により、火葬場の使用料収入が前年度と比較して大幅に増加するとともに、市外施設の利用による市民の負担が大幅に減少するに至ったものであって、早期に新斎苑の建設を実現したことにより市及び市民全体に相応の利益が及んでいるものということができる。
○ 以上を前提として、本件議決の趣旨及び経緯についてみると、本件和解案の補足説明…及び本件議案の和解の理由…等に照らせば、本件議決は、本件売買契約の締結行為が違法であるとの確定判決が示した法的判断を前提とした上で、市が本件買収地を早期に取得したことにより、合併特例債に係る交付税措置を最終事業年度まで確実に受けることができ、市の財政負担を軽減することができたこと、早期の供用開始により、使用料収入の増加や市外施設の利用による市民の負担の減少などの経済的利益や便益が市及び市民に生じていること等を考慮した上でされたものであるとみることができ、A及びBらの支払義務を不当な目的で免れさせたものということはできない。
○ これに対し、原告らは、本件和解案は確定判決に反する内容であり、本件和解案において考慮された資力等の事情は当事者の主張を鵜呑みにしたものにすぎないとした上、市議会は令和3年11月にAに対する請求権放棄の議案を否決し、AとBらの責任軽減に厳しい態度を示していたが、そのような市議会が可否同数とはいえ可決に至ったのは、裁判所による和解案が判決に準ずる妥当性を有するとの考えが投票行動に影響を及ぼしたものである旨主張する。しかしながら、本件和解案は、飽くまでも確定判決に係る損害賠償請求権の存在及び額を前提とした上、和解によりA及びBらが支払う額をその元本の5割程度の6000万円とし、AとBらの負担割合を半分ずつとする内容の和解を提案するものであり、損害賠償請求権の存在及び額に係る確定判決の効力に矛盾抵触するものとは解されない。その補足説明の具体的な記載についてみると、合併特例債の活用による財政負担の軽減に係る記載…は、「和解限りで考慮することとしました」とあるとおり、本件売買契約の締結行為は違法であり、合併特例債の発行期限が迫っていたことがその違法性を正当化する事情とはならない旨の確定判決の判断…を前提とした上、和解による支払額を確定判決に係る損害賠償請求権の元本の5割程度とするに当たって考慮した事情を示したものと解される。早期の供用開始により生じた便益に係る記載…についても同様であり、市全体の便益が「本件売買契約によって直接もたらされたわけではなく」、市の「損害と相殺され得る利益ともいえないが」と留保されていることに照らしても、本件第2段目訴訟において判決をする場合に当該便益を損害額から控除し得るとの判断の見通しを示したものとは解されない。Bらの行為が「一面において合理的な経済活動の範囲内とみる余地」もあるとの記載…についても、Bらにも不法行為が成立する旨の確定判決の判断…を前提とした上、和解におけるAとBらの負担割合の考慮要素となる帰責性の大小を評価したものにすぎず、確定判決の法的判断を否定する趣旨とは解されない。また、本件和解案の補足説明には、和解による支払額を6000万円とするに当たり考慮した事情の一つとして「支払能力や回収可能性等をも踏まえると」との記載…があるところ、その記載が飽くまでも和解において考慮した事情を示したものにすぎず、判決に準ずる裁判所の判断を示したものでないことは文脈上明らかである。そして、市議会においては、本件議案に反対する立場の議員から、A及びBらに支払能力がないとは思われず、約8600万円の債権の放棄につき市民の理解が得られない旨などの意見表明が行われた上で採決に至ったという審議の経過に照らしても、本件和解案の補足説明の記載が市議会議員の投票行動に不当な影響を及ぼしたということはできない。
○ また、原告らは、市議会におけるD副市長の答弁は、①第2段目の訴訟の判決が和解額未満となる場合も十分に想定される旨、②香芝市の事例を引用して本件においてもどのような判決が言い渡されるかは全く不明とする旨及び③判例に示されている損益相殺的な考え方に立った旨をいう点において明らかなミスリードであり、議会の審議が誤った方向へと導かれたという疑念を払拭することができない旨主張する。そこで検討すると、確かに、D副市長の上記①~③の答弁は、その内容に正確性を欠いた点があることを否定し難いところであるが、前記…のとおり、第2段目の訴訟の位置付けについても香芝市の事例についても、本件議案に反対する立場の議員から反対の意見表明が行われた上で本件議決に至ったという審議の経過からすれば、上記の点が市議会議員の投票行動に重大な影響を及ぼしたということはできない。
○ さらに、請求権の放棄又は行使の影響についてみると、確定判決に係る損害賠償請求権の額は1億1643万0705円及びこれに対する平成30年4月10日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金であり、本件和解は、上記元本の5割程度に相当する6000万円をA及びBらが3000万円ずつ支払い、市がその余の請求権を放棄することを内容とするものである。上記損害賠償請求権の全額についてAが個人責任を負うことは、本件売買契約によって何らの利得も得ていないAにとっては極めて重い負担となるものであり、長期的な観点からは一定の政策目的に沿った市長の職務の遂行に萎縮的な影響を及ぼすおそれもある。他方、任意の履行により合計6000万円を早期かつ円満に回収することは市にとって相応の利益となる上、市の規模等に鑑みれば、その余の請求権を放棄することによってその財政に多大な影響を及ぼすとはうかがわれない。
○ なお、本件議決は、住民訴訟(4号訴訟)の判決確定後の第2段目の訴訟において損害賠償請求権の一部放棄を内容とする和解をするものであるところ、これが確定判決における法的判断を前提とするものであることは前記のとおりであるから、住民訴訟制度の趣旨を没却する濫用的なものに当たるということはできない。
○ 以上の諸般の事情を総合考慮すると、市が本件和解により確定判決に係る損害賠償請求権の一部放棄をすることが普通地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする地方自治法の趣旨等に照らして不合理であるとは認め難いというべきであり、本件議決が市議会の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たるということはできない。
○ したがって、本件議決が違法であるとは認められないから、市が本件議決を経てAとの間及びBらとの間で本件和解をしたことが違法であるとも認められないことになる。

熱海MOA美術館から熱海の街。熱海の塩っぽい温泉はなかなかよく温まりました。それにしてもここ、バスがすごいところを上るものだと。