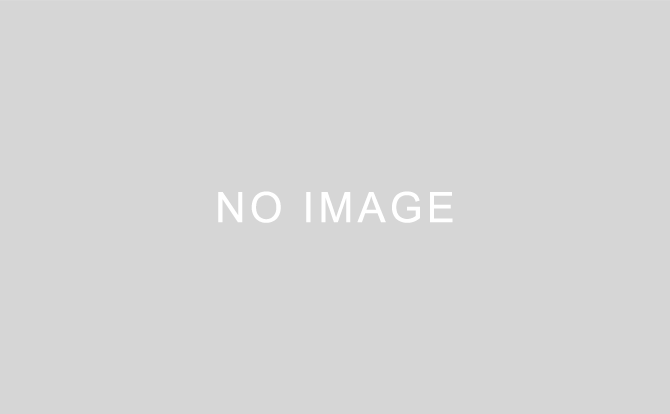本ページの一番下に、本ページのPDF版リンクを設けています。
最終改訂 2025.8.2 改訂内容は改訂履歴ページを参照
上記の通り、この問題は請求要件の問題ではなく、いわば「本案」の問題(直截な言い方をすれば、請求対象の財務会計行為が違法かどうか)となります。
1 「違法性の承継」問題とは
(1) 前提
住民監査請求(住民訴訟)においての、いわゆる「違法性の承継」問題とは、請求の直接の対象となっている財務会計行為には直接的な違法性がないにも関わらず、その財務会計行為※1に先行する自治体の行為等(財務会計行為に限らない)※2が違法であるために、対象財務会計行為が住民監査請求・住民訴訟において違法の評価を受けることがあるのか、あるとすればどのような局面か、というものです※3、※4。
| ※1 怠る事実についての原因先行行為も当然観念可能ですが、以下に掲げる諸判例の内容等を踏まえ、本項目での、監査対象事項を指すものの記述は「財務会計行為」とします。「等」は省いているが、怠る事実についてまったくこれを排除する趣意ではありません。財務会計行為に先行する原因が怠る事実のときもあり得るでしょうが、同様としておきます。 |
| ※2 先行行為は通常、住民監査請求・住民訴訟で直接対象となる財務会計行為とは別の行為と観念されるもの(人事上の処分と給与の支給、計画の策定と計画に基づく事業契約の締結・支出、設計契約と施工契約など)となるのが通常ですが、住民監査請求・住民訴訟においては、支出負担行為と支出命令(および現実の支出)はそれぞれ別の財務会計行為とされるため(最判平14.7.16民集56.6.1339)、ある契約の締結(支出負担行為)を先行行為とし、契約の履行である公金の支出(支出命令)を後行する対象財務会計行為とする、という関係も成り立ちます。参照:最判平25.3.21民集67.3.375 |
| ※3 住民訴訟における違法性承継問題とは何かについて、この問題のリーディングケースである最判平4.12.15民集46.9.2753の調査官解説(平4年度p.536(福岡右武))では「講学上、これまで行政行為の違法性の承継の問題として論じられてきたのは、複数の処分が相連続して行われ、これらが一連の手続を構成する場合に、先行行為(例えば、土地収用における事業認定等)が違法であるときは、これに続く後行行為(例えば、収用裁決等)には固有の違法事由がないにもかかわらず、先行行為の違法性を引き継いで、これもまた違法となるのか、ということに関してである…。これに対し、住民訴訟における「違法性の承継」の問題は、(地方自治法)242条の2第1項4号に基づく当該職員に対する損害賠償代位請求訴訟(注:本件当時の法規定による)についていえば、当該職員個人の損害賠償責任を基礎付ける当該財務会計上の行為の違法性の評価に当たって、これと一連の手続を構成するわけではない原因行為の違法がどのように影響するのかという、損害賠償責任の評価の一場面に関するものであるから、従来における講学上の違法性の承継の問題とは区別されるものである」とする。5.2 財務会計行為1年経過後の請求についての正当な理由の2※3も参照。 |
| ※4 なお上記※2のように、行政法学における講学上の概念としての「違法性の承継」(公定力に関する問題として通常論じられている)と、住民監査請求・住民訴訟において「違法性の承継」と呼ばれる問題は、問題の内容や判断の法的枠組みが異なるものであるため、住民監査請求・住民訴訟の問題において「違法性の承継」の用語を使用することに批判的な見解もあります(参照:実務住民訴訟p.171)が、本稿では、一般的な用例(なお参考:上記※2掲出の最判平4調査官解説p.532は「…住民訴訟の対象の問題と区分されるものとして、財務会計上の行為に先行する原因行為の違法が主張される場合に、このような違法事由の主張の法的な位置付けをどのように考えるべきかという問題があり、これは、一般に、住民訴訟における「違法性の承継」の問題といわれているものである」としている)も考慮して、混乱を避けるため、「違法性の承継」の用語を使用することを回避してはいません。 |
ところでこの「違法性の承継」問題は、本質的に住民監査請求・住民訴訟の審査の枠組みに依拠する問題であるため、地方自治法242条・242条の2の規定において、そうした問題についてどのような枠組みが用意されているのかにより結論が導かれる問題ですが、実際は同条にはこれら問題に関する何らの具体的な規定はないため、判例等に基づく解釈論により、考え方を整理していく必要があります。
| 【参考】 この「違法性の承継」問題が住民訴訟のどの訴訟類型(地方自治法242条の2第1項各号)で問題になるかは、論点の理解のためにも重要です。 通常「違法性の承継」問題は、もっぱら4号(損害賠償等請求)で、そして場合により1号(差止め請求)訴訟で問題となります※4。つまり、住民監査請求・住民訴訟における違法性の承継という問題は、主に財務会計職員などの損害賠償責任(違法な財務会計行為により自治体に与えた損害の賠償責任、またはその前提となる財務会計行為の違法性)に、財務会計行為の原因となった先行行為がどのように影響しているのか、という場面で問題になる、ということです。 なお住民監査請求では、請求の類型が定められておらず、監査委員も請求内容に拘束されない判断ができるので、請求内容を類型化してどうした場合には「違法性の承継」を考慮する必要があるのか、といったことを意識する必要は、さほどはないものと考えますが、財務会計職員の損害賠償責任判断の局面があれば、この論点は意識すべきものといえましょう。 |
| ※※4 2号訴訟の場合は、行政処分における違法性承継の問題となります(上記の通り、住民監査請求・住民訴訟における違法性承継問題とは完全にパラレルなものではありません)。3号訴訟の場合は、先行行為が観念されることはあまりないものと思われます(3号訴訟の場合でも、先行行為の違法性に伴う後行財務会計行為の作為義務違反、というケースが生ずるのかもしれません)。 |
(2) 「違法性」とは
ところで、ここでいう「違法性」とはどのような概念でしょうか。よく考えてみれば、地方行政実務者的には迷子になりやすいところがあります。なぜならそもそも違法性の承継は、多くの場合損害賠償請求事案(住民訴訟における4号訴訟)で問題となるのですが、(不法行為法の制度趣旨等に照らして事案を検討する際に「違法性」の概念をどのように組み込んで考慮するのかは別として)民法709条には「違法」の文言はなく、また近年では不法行為の要件として「違法性」の概念を独立して持ち出すことも基本ないため、一般の不法行為の損害賠償責任の成否判断において「違法性」を観念することはまずなく、よってたとえば先行行為が行政行為の場合、その「違法性」の観念は容易であったとしても、それでは損害賠償請求の直接原因行為である後行財務会計行為での違法性とは何か、ということになってしまうからです(行政行為の効力論(特に公定力)における違法性の承継論は、先行・後行行為いずれも行政行為であり、行政法総論の教科書をみればわかるとおり、「違法な行政行為」は普通に観念できるので、そのようなことで悩む必要はありません。なお上記(1)※2参照)。なお国家賠償法1条1項には民法と異なり「違法」要件が(民法709条の権利侵害要件のかわりに)掲げられていますが、これは国家賠償法制定当時の不法行為法の学説のトレンドが反映されたためとされているのであって※1、国家賠償法の賠償責任要件が民法のそれと大きく異なるものとは解されていませんし※2、それ以前に、住民監査請求・住民訴訟で財務会計職員に問責される損害賠償の根拠法は、国家賠償法ではありません(国家賠償法は自治体が賠償責任の主体となる場合の適用法であり、賠償される側の場合には適用されないことは当然である。なお財務会計職員の賠償責任の根拠法である民法・地方自治法(243条の2の8)にも「違法」要件は明記されていない)。
とすれば、何の違法性がどのような形で承継されるのでしょうか。
| ※1 民法709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」としており、この条文によれば、不法行為の成立要件は、主観要件としての故意過失と、客観要件としての権利利益侵害(および損害の発生)ということになります。かって、この権利利益侵害(以前の条文では「他人ノ権利ヲ侵害」)を違法性の概念を用いて説明するのが有力な学説とされていました。なお国家賠償法1条1項は「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる」としており、上記の客観要件が権利利益侵害から違法性にかわっています。これは国賠法制定当時、上記の学説が有力であったという趨勢が影響しているとされています。この点下記※2部分参照。 |
| ※2 たとえば内田貴「民法Ⅱ(第3版)」東京大学出版会(2011年)p.499、潮見佳男「基本講義 債権各論Ⅱ不法行為法(第3版)」新世社(2017年)p.18。また内田前掲p.358以下、潮見「民法(全)(第3版)」有斐閣(2022年)p.505。 |
この点、やや大雑把ですが概念理解のためとして先行説明として申し上げれば、訴訟における違法性の承継問題のリーディングケースとして下記に紹介する一日校長事件最判平4.12.15民集46.9.2753において、この違法性の承継問題に関する最も基本的となる判断の枠組みとして「当該職員の財務会計上の行為をとらえて右の規定に基づく損害賠償責任を問うことができるのは、たといこれに先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、右原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られる」と示しています。とすれば、まず後行財務会計行為について、それが行政法規である財務会計法規の上で違法となる(これとても財務会計法規の定義がかなり広範(言い様によっては曖昧)なところがある、という問題があるのですが、すくなくとも「財務会計法規」とここで称されるものが自治体の執行機関の財務会計に関する行動を規制する行政法規であることには違いないでしょう)、という意味で、行政法規上の違法性が観念でき、さらに、先行行為の違法が後行財務会計行為の行政法規(財務会計法規)上の違法に帰結するかどうかが違法性の承継の問題である、ととりあえずは観念できそうです。
そして、これを起点として考えれば、前段の記述とはいささか矛盾するようではありますが、国家賠償法における「違法性」の概念※3が参考になるものと考えます。つまり、職員(先行行為は「当該」財務会計職員が行なったとは限らない)が何らかの行為をした場合、その行為に関する法令上のルールに反していること※4が、ここでの「違法性」を指す、と考えることが適当であり、その違法性が後行の財務会計行為を財務会計法規上の違法性(財務会計法規上の義務違反)をもたらすことを違法性の承継と考えることが理解しやすいと思われます。
| ※3 国家賠償法1条1項の解釈において、「違法性」と「故意過失」を一元的に判断するか(判例の主要な事案における立場・職務行為基準説)、二元的(学説において有力なもの・公権力発動要件欠如説)に判断するか、という議論がありますが、本稿のこの部分では二元論における対象行為の違法性の概念(先行行為が根拠法令に違反している)を参考としています。なお参照:塩野Ⅱp.332以下。 |
| ※4 塩野Ⅱp.339は、国家賠償法上の違法性について、権力的法的行為形式としての行政行為について生じた損害賠償事件につき、賠償請求権の成立は当該行為の取消訴訟上の違法が必要条件となる、という。なお同書は、国家賠償法1条1項の「違法性」について、公権力発動要件欠如説に立つものと解される。 |
たとえば自治体の機関が公権力の行使により住民の権利を適法に制限した(法律に定める要件に基づき、適法に営業許可の取消し処分や営業許可の申請拒否決定をするなど)としても、それにより住民がこうむった損害を賠償する国家賠償法上の責任は生じません。このようなケースで国家賠償法上の責任が生ずるのは、上記の営業許可取消し処分や申請拒否決定が根拠法令に反する、つまり行政法規上違法である場合となります(判例は、行政法規違反イコール国賠法上の違法の定式をとるわけではないが、いずれにせよすくなくとも行政法規違反は賠償要件の必要条件とはいえる。国賠法事案でのたとえば最判昭61.2.27民集40.1.124、最判平5.3.11民集47.4.2863、また住民訴訟(よって国賠法事案ではない)においての下掲茅ヶ崎市職員派遣事件の差戻後上告審最判平16.3.2集民213.613のロジックなどが参考になると考える)。これを、国家賠償法適用事案ではないものの先行行為の違法性と賠償責任(財務会計法規上違法な財務会計行為をなしたことによる賠償責任)の関係性という点から、上にあげた一日校長事件の事例(詳細は下記3(1))に引き直せば、先行する教育委員会の人事措置(昇格昇給措置)が地方公務員法や地教行法、地方自治法等の法令に照らして適法なものであれば、そもそもそれに基づきなされた首長の財務会計行為(昇格昇給後の給料月額に基づく退職手当の支給)が違法の評価を受けることはなく(なおここでも財務会計職員は財務会計法規に照らしてどのような場合はどのようなことをしてはならないという義務設定がされているという前提があり、この義務に反すれば、法令の適合性の点から「違法」と評価されることとなる※5。上記一日校長事件の判旨はそのように考えればよい)、逆に、教育委員会の人事措置が何からの点で法令違反があった場合に、はじめて4号訴訟での首長の賠償責任が問われ得ることとなるのであり、その人事措置の違法が4号訴訟(住民監査請求)での首長の責任判断にどのように影響するか、つまりは人事措置の違法がどのような経路で首長の賠償責任をもたらすのか、というのが、住民監査請求・住民訴訟における違法性の承継の問題の根幹である、ということになります。
| ※5 つまり住民監査請求・住民訴訟(損害賠償請求事案)においては、対象財務会計行為(怠る事実を含む)は、「その財務会計行為等が違法かどうか」という評価をなすことが必然、ということになります。 なおたとえば公立学校の行事で生徒が怪我をした場合の国家賠償請求では、学校(自治体)側には上記のような行政法規上の義務設定がそもそも存在せず(そもそも他人の権利利益の侵害行為であり、私立学校の職員と同様に、民法(不法行為法)上問題となる権利利益侵害(こうしたケースでは権利利益侵害は自明なのであまり表面上問題として騒がれることはないだけで、権利利益侵害要件は満たしていることになる)および結果回避義務違反なのかどうかの判断があるか以上に「違法性」が持ち出される場面がない)、国家賠償請求でも違法性の問題を論ずることは通常は考えづらいところです。これを住民監査請求のシーンであり得る事例に引き直した場合、たとえば職員が過失で自家用車を庁舎にぶつけたのにその者への賠償請求を怠る場合において、その賠償請求を怠る事実を住民監査請求の対象とした場合、職員であろうが無関係の第三者であろうが車を庁舎にぶつけた場合の自治体への損害賠償義務の発生に行政法規上の行為義務違反の問題を論じられることはありませんが(民事上の結果回避義務違反の問題)、その損害賠償請求権の行使を怠っているという直接の住民監査請求・住民訴訟での問題においては、自治体(財務会計職員)側の財務会計法規上の行為義務違反、つまり行政法規上の違法性の有無が問題となっています。 |
また財務会計行為の差止め請求(住民訴訟における1号訴訟)における違法性の承継についても、先行行為における上記のような意味での違法性が、後行財務会計行為をしてはならないという財務会計法規上の義務の成立にどのように影響するのか、という問題である、ということになります。
2 「違法性の承継」が抱える前提問題
「違法性の承継」については、住民監査請求・住民訴訟の制度設計に由来する内在的な問題が前提として存在します。
本Webサイト各ページで説明の通り、住民監査請求・住民訴訟制度では、請求対象が財務会計行為(またはそれを怠る事実)に限定されています(参照:最判昭53.3.30民集32.2.485、最判昭51.3.30集民117.337、最判平2.4.12民集44.3.431)。
ところで、「違法性の承継」が問題となるケースでは、住民監査請求等の直接の対象行為は財務会計行為そのものであっても、その財務会計行為に先行する行為の違法が、対象財務会計行為を違法とし、これを前提として是正措置要求(住民訴訟であれば損害賠償の請求等)がなされる、というパターンとなるのですが、この先行行為は財務会計行為とは限りません。
そうなると、違法性の承継を無限定、または幅広に容認すると、住民監査請求・住民訴訟の枠組みを利用して、非財務会計行為の違法性を問うことが可能となります。
しかし既に別稿(0.1住民監査請求の制度設計の考え方など)で説明の通り、住民監査請求・住民訴訟制度は、対象を財務会計行為等に限って住民が提起すること認められた特別の争訟制度です。そして、行政作用のほぼすべての局面で予算執行、つまり財務会計行為が発生することや、訴訟要件の厳しい抗告訴訟と比べ、住民訴訟は比較的訴訟要件が緩やかである(特に原告適格)ことからすれば、そのような抜け穴的運用、つまり住民監査請求・住民訴訟制度の枠組みを利用して、非財務会計行為である行政処分等の効力を実質的に問うような事態が生ずることは容易に想定されますが、そうした仕組みを認めることが、住民監査請求・住民訴訟の制度設計の点から見て適切でないことはいうまでもないでしょう※1。
| ※1 こうした事態について、碓井p.147は、「抗告訴訟の代替的機能」を果たすようになることを問題視している。藤田p.332 は、住民訴訟が抗告訴訟の補完機能(抗告訴訟より使いやすいことからくる住民訴訟の多発)、そして住民訴訟の運用をめぐり多くの解決すべき問題が登場し、その一つとして住民訴訟における違法性審査の範囲(違法性の承継)の問題が論じられたことを指摘する。 |
しかし一方で、財務運営の適正化をその制度趣旨とする住民監査請求・住民訴訟において、上記のような問題の存在から問題となっている財務会計行為の違法性判断に際し先行行為の影響を何でもかんでも遮断することが、果たして適切なのか、という疑問も生じます。住民監査請求・住民訴訟において問われる問題の本質は、請求人・原告が摘示した対象財務会計行為が、財務会計法規に違反した違法なものかどうか、という点なのであり、それを通して自治体財務運営の適正化を図るという制度の目的を考えれば、先行行為との関係をドラスティックに割り切ることが果たして適切なのか、という疑問が生じることは、容易に想像がつくことであり、われわれは、これら両論のディレンマに直面することとなります。
上記1の通り、住民監査請求・住民訴訟における「違法性の承継」の問題は、最高裁判例の積み重ねにより実務的な解釈論が形成されていますが、この問題においては、ここで取り上げた両論のバランスが意識された判断が積み上がっていることを、念頭に置く必要があります※2。
| ※2 上記1(1)※2掲出の最判平4.12.15民集46.9.2753の調査官解説p.532では「…住民訴訟において「違法性の承継」の問題が近年特に論じられているのは、このような原因行為の違法がすべて後行する財務会計上の行為の違法につながるとすると、普通地方公共団体の行う行為の多くは何らかの形で予算の支出を伴うものであるから、それらがすべて住民訴訟における審査の対象となるのと同一に帰することとなり、それでは、財務会計上の違法な行為又は怠る事実に限ってその予防又は是正を請求し得るものとされる住民訴訟制度の建て前にそぐわない結果となるのではないかという問題意識に由来するものと思われる。他面、財務会計上の行為の違法性の審査に当たって先行する原因行為の違法がしんしゃくされることを一般的に排除してしまうような考え方は、地方財務行政の適正な運営を確保するという目的を持つ住民訴訟…を余りに狭い範囲に限定し、住民訴訟の制度目的に反する結果となるものというべきであって、この問題についてどのような判断枠組みを採るべきかは、住民訴訟における極めて難しい解釈問題の一つということができる」という。また参考として塩野Ⅱp.290以下。 |
またこれとは別に、監査請求期間(違法な行政処分に対する出訴期間制限)と関連する問題についても、考慮しておくことが望ましいものです。別稿「5.2 財務会計行為1年経過後の請求についての正当な理由」の2※3参照。
3 「違法性の承継」に関する基本的な判例法理
上記の通り、住民監査請求・住民訴訟における「違法性の承継」問題は、最高裁判例により解釈論が積み上がっているので、まずは、基本的な最高裁判例の内容について観察します。
(1) 一日校長事件
いわゆる「一日校長事件」と呼ばれる最判平4.12.15民集46.9.2753は、住民訴訟の相当部分を占める4号訴訟における基本的な判断枠組みを示す、いわゆるリーディングケースとされています※1。
| ※1 本判決は違法性の承継論における最重要判例であることには違いがありませんし、違法性の承継が問題となる事案の多くが4号訴訟類型の問題ではありますが、それはさておき本判決の論旨の1号訴訟への適用については慎重にあるべきとの論があります。たとえば藤田p.336など。 |
本件は、教育委員会が、退職勧奨に応じた教頭に対し、退職期日となる3月31日付けで校長に昇任させた(この場合、給料表上の昇格がなされ、後記の昇給がなくともそれだけで給料月額が上がったものと思われる。原告の請求は、教頭としての退職手当額と校長としての退職手当額の差額を損害としている)上で、勧奨退職に応じた勤続15年以上の者への特別昇給の制度を適用してこれらの者を2号給特別昇給とし、教育委員会関係の予算執行権限を有する首長が、この特別昇給後の給料月額を基礎として退職手当の支給をしたことについて、住民が首長に旧4号訴訟により損害賠償請求をした、という事案です。
上記の事実関係の内容を踏まえれば、本件の主要な争点は、財務会計行為を行う機関(首長)とは権限的に独立した執行機関(教育委員会)の措置を前提とする財務会計行為の違法性であり、本判決は、①先行行為と後行財務会計行為の関係が財務会計行為の違法性判断で問題になる場合の住民訴訟における基礎的な判断方法 ②先行する行政委員会の行為が違法である場合に後行する首長の財務会計行為に及ぼす影響の射程 の2点について判断を示しています。違法性の承継という問題を表面的にとらえれば、②の論点がこの問題への正面の解ともとれますが、①が、実際は違法性の承継問題における基礎的な論点となっています。
まず上記①の論点について、同判決は次の通り判示しています。
| 地方自治法242条の2の規定に基づく住民訴訟は、普通地方公共団体の執行機関又は職員による同法242条1項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実の予防又は是正を裁判所に請求する権能を住民に与え、もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とするものである(最高裁昭和51年(行ツ)第120号同53年3月30日第一小法廷判決・民集32巻2号485頁参照)。そして、同法242条の2第1項4号の規定に基づく代位請求に係る当該職員に対する損害賠償請求訴訟は、このような住民訴訟の一類型として、財務会計上の行為を行う権限を有する当該職員に対し、職務上の義務に違反する財務会計上の行為による当該職員の個人としての損害賠償義務の履行を求めるものにほかならない。したがって、当該職員の財務会計上の行為をとらえて右の規定に基づく損害賠償責任を問うことができるのは、たといこれに先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、右原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解するのが相当である。 |
ここでの最大のポイントは、4号訴訟(損害賠償請求)において、財務会計行為の先行行為の違法性が問題とされている場合であっても、4号訴訟において判断すべきは、対象財務会計行為が財務会計法規に違反する違法なものかどうか、つまり判断の直接の変数は対象財務会計行為が財務会計法規に違反するかどうかであって、先行行為の違法性は、この判断の主変数にはならない、ということです。
これは、本件のような4号訴訟の場合、住民訴訟制度設計の当然の帰結として請求の趣旨が対象財務会計行為に起因する当該職員等に対する損害賠償請求となる、つまり中心となる論点が、対象財務会計行為についての当該財務会計職員の損害賠償責任の追及である以上、直接問題とされるべきは、当該財務会計職員の行なった対象財務会計行為が損害賠償責任を発生させるものなのか、つまり対象財務会計行為を行うにあたり、当該財務会計職員はどのような財務会計法規上の義務があり、その義務に違反する(地方自治法242条1項でいう)違法な財務会計行為を行ったのか、ということになるべきだからです。
そして、違法性の承継の問題の点からこの義務を観察した場合、原因行為との関係で、当該財務会計職員が負う財務会計法規上の義務の内容はどのようなものか、ということになる、また原因先行行為の違法性が、この損害賠償責任の判断において、問題となっている対象財務会計行為の財務会計法規上の義務の審査を飛び越えて問題とされるものではない、ということになるのです※2。
| ※2 参考:上記1(1)※2掲出の最判平4.12.15民集46.9.2753の調査官解説p.542では、概要このように述べた上で「当該職員が財務会計上の行為をするに当たり…(財務会計法規上)の義務を尽くしたといえるかということが、「違法性の承継」の問題として問われるべきものの核心であり、原因行為の違法性それ自体でいわば無媒介に財務会計上の行為の違法をもたらすという関係にあるのではない…」という。 |
そしてその上で、②の論点について、次の通り判示しています。
| ところで、地方教育行政の組織及び運営に関する法律は、教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱いその他地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めるものであるところ(1条)、教育委員会の権限について同法の規定するところをみると、同法23条は、教育委員会が、学校その他の教育機関の設置、管理及び廃止、教育財産の管理、教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事などを含む、地方公共団体が処理する教育に関する事務の主要なものを管理、執行する広範な権限を有するものと定めている。もっとも、同法は、地方公共団体が処理する教育に関する事務のすべてを教育委員会の権限事項とはせず、同法24条において地方公共団体の長の権限に属する事務をも定めているが、その内容を、大学及び私立学校に関する事務(1、2号)を除いては、教育財産の取得及び処分(3号)、教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の締結(4号)並びに教育委員会の所掌に係る事項に関する予算の執行(5号)という、いずれも財務会計上の事務のみにとどめている。すなわち、同法は、地方公共団体の区域内における教育行政については、原則として、これを、地方公共団体の長から独立した機関である教育委員会の固有の権限とすることにより、教育の政治的中立と教育行政の安定の確保を図るとともに、他面、教育行政の運営のために必要な、財産の取得、処分、契約の締結その他の財務会計上の事務に限っては、これを地方公共団体の長の権限とすることにより、教育行政の財政的側面を地方公共団体の一般財政の一環として位置付け、地方公共団体の財政全般の総合的運営の中で、教育行政の財政的基盤の確立を期することとしたものと解される。 右のような教育委員会と地方公共団体の長との権限の配分関係にかんがみると、教育委員会がした学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関する処分(地方教育行政の組織及び運営に関する法律23条3号)については、地方公共団体の長は、右処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合でない限り、右処分を尊重しその内容に応じた財務会計上の措置を採るべき義務があり、これを拒むことは許されないものと解するのが相当である。けだし、地方公共団体の長は、関係規定に基づき予算執行の適正を確保すべき責任を地方公共団体に対して負担するものであるが、反面、同法に基づく独立した機関としての教育委員会の有する固有の権限内容にまで介入し得るものではなく、このことから、地方公共団体の長の有する予算の執行機関としての職務権限には、おのずから制約が存するものというべきであるからである。 |
つまり、先行行為が財務会計職員である首長から独立した執行機関である教育委員会の権限でなされている以上、首長が行う財務会計行為は、教育委員会の先行行為に原則として拘束される、ということになります。
具体的には、本件のように先行の原因行為を行う権限主体と後行の対象財務会計行為を行う権限主体が異なり、後行財務会計行為を行う者が先行原因行為を行う権限主体に対する指揮監督権を有しないなど、原因行為に対しての組織法的なコントロール権限がない場合は、後行財務会計行為を行う財務会計職員は原因行為を行う権限主体の判断を尊重せざるを得ず、よって、「(原因行為たる)処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合※3、※4でない限り、右処分を尊重しその内容に応じた財務会計上の措置を採るべき義務があ」る、ということになるのです。
| ※3 本判決が、先行原因行為について瑕疵の重大明白性を要件とせず、「著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵の存する場合」とする点について、本判決調査官解説p.546では、一つは瑕疵の重大明白性要件は行政処分の無効原因に関して論じられた考え方であるところ、住民監査請求・住民訴訟における違法性の承継問題においては、先行原因行為が行政処分とは限られず、行政処分以外の原因行為もカバーする行為義務の基準を示す必要があったこと、また原因行為が行政処分の場合でも、重大明白基準より若干広がるニュアンスが込められており、首長は教育委員会の行為について重大明白な違法がなければ安んじて予算措置をとればよいというものではなく、そのような場合でも首長はなお、その処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が認められるときは、首長は予算執行機関として予算執行の適性確保を図るべき立場から、教育委員会の独立した権限を侵さない範囲で、教育委員会に協議を求める等をして、処分の瑕疵の解消に努めるべき行為義務を負うことがあり得ることを認めていると解する余地があると思われるとの説明をなしている。 |
| ※4 参考:実務住民訴訟p.185は、「著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵」を、財務会計職員側から見た(つまり、後行財務会計行為を行う上で看過することができない)瑕疵、「重大かつ明白な瑕疵」を先行行為自体に存する瑕疵であり、前者については、財務会計職員は、原因(先行)行為者と協議等して瑕疵の解消に努めなければならない(努めてもなお原因行為者がこれに応じない場合は、当該財務会計行為は適法になる)、と説明しています。「著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵」が財務会計職員の財務会計法規上の義務に直結する瑕疵、という観点からの説明として、理解に資するものと考えます。 |
以上について本件にそくしていえば、退職手当支給にあたって、首長は、先行行為である教育委員会の人事処分である昇任・特別昇給措置に「著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵」があるかどうかをまず判断する義務を負いますが、その要件に該当しない場合は、教育委員会の人事措置判断に基づく財務会計行為の実行を拒むことはできないのだから、首長は教育委員会の人事措置の違法を理由として首長がなす財務会計行為(退職手当支出)について損害賠償責任を問われることはなく、仮に損害賠償責任が発生するとすれば、当該財務会計行為に固有の(教育委員会の人事措置とは別の)財務会計法規上の義務違反による、ということになります。このように、ここでは先行する教育委員会の人事処分の違法性の有無およびその内容は、財務会計職員の賠償責任の根拠には直結されていないのです。この論法は、まさしく上記①の論点から演繹されている、といえます※5。
| ※5 なお上記※3・4のように、逆に「著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵」がある場合でも、本件のように先行原因行為と後行財務会計行為の権限機関が相互独立する場合、後行財務会計行為を担当する財務会計職員は、先行行為を是正する組織法上の権限を有しない以上は、先行行為の違法性是正に係る財務会計職員としての財務会計法規上の義務は努力義務を超えないと解し得ることとなる。最判平20.1.18民集62.1.1、最判平25.3.21民集67.3.375に係る下記4(1)イ(b)、また先行行為と後行財務会計行為の権限機関が相互独立しない場合については、下記(2)イや4(1)イ参照。 |
(2) 一日校長事件判決に先行する最高裁判例と一日校長事件判決の関係
ところで、一日校長事件判決以前にも先行行為と後行財務会計行為の関係が争点となった重要な最高裁判決があるところ、これら先行判例と一日校長事件判決がどのように関係しているか(とりわけ一日校長事件で示された、後行財務会計行為の違法性判断における先行行為の影響の射程判断に関する各判断との関係)を把握することは、「違法性の承継」問題の理解において重要であるため、本項はこの点について整理します※。
| ※ 本項の内容は、概ね上記の一日校長事件(平4最判)調査官解説の解説を参考としています。 |
ア 最判昭52.7.13民集31.4.533(いわゆる津地鎮祭事件)
本件は、市主催の市立体育館起工式を神社神職を招聘して神式で行ったところ、これに要する費用の支出は違憲違法と主張し市長個人等に対して市の損害補てんを代位請求する住民訴訟であり、原審が、本件起工式は憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当し許されないものであり、従ってこれに基づき市長としてなした公金支出は、憲法89条の適用をまつまでもなく、基本となる権利義務関係が法律上許されない以上、違法な支出たるを免れないと判断したことについて、最高裁は「公金の支出が違法となるのは単にその支出自体が憲法89条に違反する場合だけではなく、その支出の原因となる行為が憲法20条3項に違反し許されない場合の支出もまた、違法となることが明らかである」と判示し、上記原審判断を是認しました。
これを見る限り、公金支出の前提(原因)である市主催式典が憲法違反(市による宗教的活動の実施)であることが直接財務会計行為を違法としている、つまり原因たる先行行為の違法性が「無媒介」で後行財務会計行為の違法性に直結されている論法にも見えなくありません。憲法89条が財務会計法規の内容であるのに対し、憲法20条3項違反というのは、地方自治体が神事の実施に直接コミットする(式典主催者として神事を実施するに等しい)ことへの法的評価であり、外形的には、財務会計行為をその法的評価の射程にとらえているわけではないともいえるからです。
この点について本判決の上記説示は、原審の判示事項に対し上告人(市長)が、本件は4号訴訟であり、裁判所の判断の対象は市長の公金支出の違法性、つまり(財務会計法規である)憲法89条違反かどうかが審理判断の中心となるべきものであり、式典が憲法20条3項違反かどうかは正面から採り上げられるべき論点ではないと主張していることに対する説示であることを考慮する必要がありますが、その上で一日校長事件判示事項との関連について整理すれば、本件の支出の原因行為は市と神社の神事挙行に関する有償の契約関係であり、それに基づき支出がなされているということができますが、原因行為である契約が憲法20条3項に違反するものであれば、その契約は公序に反する私法上無効なものであり(民法90条、また同91条参照:政教分離原則は憲法的基本秩序事項というべきであり、憲法98条1項に照らしても自治体が一方当事者として締結するそのような契約は当然に公序違反であると解される)、支出を担当する財務会計職員は無効な契約に基づく支出をしてはならないという財務会計法規上の義務を負う、というものであると理解すべきこととなります※。
なおこうした原因行為としての契約とそれに基づく住民監査請求・住民訴訟の直接の対象財務会計行為である契約履行行為としての支出の関係を、一日校長事件判決を踏まえてより精緻に論旨展開したものが、後述の最判平20.1.18民集62.1.1、最判平25.3.21民集67.3.375になります。
| ※ したがって本判決は、先行原因行為が憲法違反という公序違反(違法)のものだから、それを原因行為とする後行支出行為も違法、という説示ではなく、またそのようなロジックで理解すべきものでもないことになります。 |
イ 最判昭60.9.12集民145.357(いわゆる川崎市分限免職事件)
本件は、収賄容疑で逮捕された職員を市長が分限免職処分として退職手当を支給したところ、本来懲戒免職処分とすべき事案であり退職手当支給は違法であるとする4号住民訴訟ですが、最高裁は上記ア津地鎮祭事件判決の判旨を引用のうえ、「(市の退職手当)条例の下においては、分限免職処分がなされれば当然に所定額の退職手当が支給されることとなっており、本件分限免職処分は本件退職手当の支給の直接の原因をなすものというべきであるから、前者が違法であれば後者も当然に違法となるものと解するのが相当である」と判示しました。
よってこの内容を見る限りは、一日校長事件判決との関係においては、上記ア津地鎮祭事件判旨と同じ疑問が生ずることとなります。
この点について整理してみると、まず本件の特徴として、退職手当支給の原因行為は任命権者の人事上の処分であり、この処分権限と退職手当の支給権限はいずれも市長に属しています。そして、判決文にもある通り分限免職処分は退職手当の支給に直結するものとなっています。
こうした事案の特徴を踏まえ、本件について一日校長事件の判旨との関係で内容を整理すると、市長がその所属する自治体の事務を誠実に執行する義務を負っている(地方自治法138条の2)※1以上、原因行政処分が違法である場合は処分権者たる市長においてこれを取り消すべきものであり(特段の法的制約を受けることなく取り消し得る処分であることが前提であり、そうでない場合は、上記ア掲出の平成20年、25年最判の趣旨が参照されることとなる)、またこの誠実執行義務が財務会計法規上の義務としての性格も有するのだから、市長が原因行為である分限免職処分が違法であるにもかかわらずこれを取り消さず、この分限免職処分に直結する後行行為として退職手当を支給することは、財務会計法規上の義務違反(誠実執行義務違反)となることになります※2。
| ※1 この誠実執行義務は、結局、法律による行政の原理への忠実要求が法文化されたものとここでは見ればよいでしょう。 |
| ※2 なお同様の事例(首長部局職員の非違行為について任命権者である首長が辞職申出を承認して退職手当を支給)につき大阪高判平10.12.11判例地方自治199.22は、一日校長事件判決を引用のうえ、首長は当該自治体に対しその事務を誠実に執行すべき職務上の義務を負っており(地方自治法138条の2)、この誠実執行義務もまた財務会計法規上の義務の一内容を成すものなので、原因行為である行政処分について、首長がこれを取り消しうる権限を有している場合には、原因行為が違法なものであれば、首長はこれを取り消すべきものであり、これをしないで財務会計行為を行ったときには、この財務会計行為は違法となる、と判示。 本件は一日校長事件判決後のものであり、同判決の趣旨も考慮して論旨展開されていることや、本項掲出の川崎市事件判決では直接的には言及されていない首長の誠実執行義務と財務会計法規上との関係(上述)について述べている点、参考となる事例と考えます。 |
要すれば、本件の最高裁の判示内容は、本件の特質(原因行為としての処分と財務会計行為が同一者たる市長の権限であり、違法な原因処分を市長が取り消すことに特段の支障がないこと、原因行為としての分限免職処分が退職手当の支給に直結していること)を踏まえたものであり、本判決の判示内容をもって、先行原因行為の違法性が後行財務会計行為の違法に直結するという一般論を示したものと解すべきではない、ということになります。
ウ 最判昭62.5.19民集41.4.687
一日校長事件は、4号訴訟(損害賠償請求)の事案ですが、上記1で述べた通り違法性の承継はときに1号訴訟(差止め請求)でも問題となることあり、本件はその差止め請求についての最高裁判決の事例です。その意味で、ここでは上記ア、イのような(いわゆる)典型的な違法性の承継問題に関する一日校長事件判決前の最高裁判例(と一日校長事件判決の関係の問題)、というよりは、1号訴訟において違法性の承継の問題をどのように考えるのかという参考事例として捉えることとします※1、※2。
| ※1 なお本判決は、契約の締結を先行原因行為、履行を後行する対象財務会計行為とする事案であり、同判決の(違法性の承継にかかる)射程は、あくまでも契約の締結と履行の前後関係に限定されることに留意が必要です。本項はそのことを前提とした上での説明となります。 |
| ※2 いうまでもなく、差止め訴訟である1号訴訟と損害賠償請求訴訟である4号訴訟の勝訴要件は同一ではありません。なお参考:碓井p.148は、松山地判昭63.11.2判例時報1295.27において、1号訴訟と4号訴訟では、請求を認めるにあたっての対象財務会計行為と先行原因行為(非財務会計行為)の関係を論じるにあたり、考慮すべき要素が同一でなければならない必然はないとの判示事項を引用しています。 |
事案は、随意契約規定に反する随意契約での土地売却の差し止めを求めるものであり、最高裁は「・・・契約が仮に随意契約の制限に関する法令に違反して締結された点において違法であるとしても、それが私法上当然無効とはいえない場合には、普通地方公共団体は契約の相手方に対して当該契約に基づく債務を履行すべき義務を負うのであるから、右債務の履行として行われる行為自体はこれを違法ということはできず、このような場合に住民が法242条の2第1項1号所定の住民訴訟の手段によって普通地方公共団体の執行機関又は職員に対し右債務の履行として行われる行為の差止めを請求することは、許されない・・・」と判示しました。
本判決は、上記の通り一日校長事件以前のものであり、また平成16年行訴法改正により差止め訴訟が抗告訴訟の一類型として法定される以前のものでもありますが、①差止め認容の判断は、直接的には対象となる財務会計行為の法的評価によりなされること(先行原因行為の違法性が無媒介に判断の変数となることはない)、②差止めの認容は、対象財務会計行為をなすべきではないという覊束性※3の存否により判断される、という点で、一日校長事件の判旨とも、現行行訴法37条の4第5項の規定とも平仄が合うもので、結局1号訴訟において違法性の承継が問題になる場合も、一日校長事件の判旨と整合的な考えにより判断がなされるものということができます※4(②部分は差止め訴訟自体の勝訴要件であり、違法性の承継の問題ではない)。
| ※3 現行訴法37条の4第5項、また塩野Ⅱp.262参照。 |
| ※4 ここでの説明は対象財務会計行為に関わる財務会計法規上の義務の面から、一日校長事件が示した判旨の考え方の適応について述べていますが、4号訴訟(一日校長事件)と1号訴訟(差止め訴訟)で適用される法理の相違を指摘する学説もあります。上記※2参照。またこの点については、「集約版」で若干の説明を加えています。 |
ところで住民訴訟は司法権による行政上の行為への法的関与制度なので、裁判所は、法的義務のない行為(不作為)への関与的命令や、違法ではない不当にとどまる行為への判決による関与はできませんが、住民監査請求を扱う監査委員は、財務会計行為を行った自治体の内部行政組織であり、地方自治法は監査委員に対し自治体内部の他の機関の不当な行為に対する関与的な勧告権を認めていることから、監査委員は、当然に適法性のみならず当・不当、つまり妥当性の点からの判断ができます。
とすれば差止め請求は、住民訴訟においては対象財務会計行為に法令上の不作為義務が存在することが勝訴要件となる一方、住民監査請求においては、法律上の不作為義務の存否だけではなく政策的な適正性・適切性の点から差止めを認める余地があるため、監査委員は法律上の不作為義務の存否に関わらず差止め請求を認める(勧告する)、ということできそうです。
ただし、先行原因行為が契約であって、これが私法上無効ではなく、差止め請求の対象となる財務会計行為の実行についての自治体側の法律上の義務が解除できない場合、不当性を理由とする後行財務会計行為の差止めを勧告は、担当執行機関・職員に対する努力義務を設けるに過ぎないものであることに注意が必要です(ただし、監査委員の勧告は、たとえば人事上の処分に対する人事(公平)委員会の不服申立て裁決のような判断代置的決定ではなく、行為義務を設定するものでもない、という性格のものではあるので、その点で監査委員の政策判断的な自由度は高いとも考えられます※5)。
| ※5 その意味でいけば、損害賠償や不当利得返還の請求権は法定債権であり、財務会計行為等が違法ではなく不当にとどまる限り、こうした債権が成立するものではないので、財務会計職員等に対する請求権の存否判断は、住民監査請求と住民訴訟とでは変わらないこととなります。 ただし、実際の住民監査請求事案では、対象財務会計行為等に一定の不当性が窺われれば、具体的な措置内容を明示せずに適切な措置を講ずるよう求める勧告をすることはあり得ることですし、法定債権の成立に疑問があるとしても、監査委員が政策的な観点から自治体の損害の補てんに向け関係者に対して折衝を求める等の努力義務を設ける勧告をなすこともあり得ることでしょう。 その意味から言えば、差止め請求についても、対象財務会計行為の法律上不作為義務の存在が明らかとは言えない場合であっても、努力義務的な措置を求める勧告を行うことは、十分にあり得ることです。 |
エ まとめ
一日校長事件に先行する最高裁判例には、違法性の承継に関し、一日校長事件の判示内容、つまり違法性の承継が問題となる事案においても直接的に問われるべきは、対象財務会計行為が財務会計法規に違反するものかどうか、という内容と文面上必ずしも整合しないようにとらえ得るものもありますが、上記の通りこれら判例の判示事項は一日校長事件の判旨と齟齬をきたしているわけではない(事案の特性や一日校長事件での判断枠組みをトータルに考慮して読み込むべきもの)、ということになります。
4 一日校長事件判決の敷衍
(1) 関連・派生する判例法理
本項では、一日校長事件の判例法理に関連する、またはこの判旨から派生する判例法理について説明します。
ア 違法性の承継が問題とならないケース
対象財務会計行為に関連するなんらかの財務会計行為とは独立した先行行為がある場合に、その先行行為が対象財務会計行為を行う動機ではあっても、後行財務会計行為を行う要件(前提条件)とはいえない場合は、先行行為と後行財務会計行為の間に原因結果関係があるとはいえないのであり、このような場合には、そもそも違法性の承継の問題は発生しません※。
| 最判昭59.11.6集民143.145
道路の路線認定に関する議会の議決、路線の認定および道路の区域の決定を経ずに道路用地を買収して公金支出したのは違法とする4号訴訟において、最高裁は「(道路法の定める路線認定等の)手続は、道路法上の道路を成立させるための要件であるにとどまり、当該道路開設のためにその用地に対する権原を任意に取得するについての要件をなすものではないから、被上告人(首長)の前記土地買収が、本件計画道路に係る路線の認定に関する区議会の議決、路線の認定及び道路の区域の決定を経ずに行われたことをもって、これを違法ということはできない。また、本件計画道路の開設が前記土地買収の動機目的をなすものではあっても、前記土地買収は、本件計画道路を開設する行為そのものとは区別され、それとは独立して、区に対し当該土地に係る権原を取得させ、その代金の支払債務を負担させるという効果を発生させるにとどまるものであるから、仮に本件計画道路を開設することに所論のような違法事由が存するとしても、そのことにより前記土地買収が違法となるものではない」と判示。 |
| ※ 本件は、対象財務会計行為である用地買収行為が汎用的な性格、つまり買収した用地は理念的には道路用地以外の用途にも使用できるものであり、それだけ単独行為としての独立性が強い、という点に特徴があります。それゆえに「土地買収は、本件計画道路を開設する行為そのものとは区別され、それとは独立して、区に対し当該土地に係る権原を取得させ、その代金の支払債務を負担させるという効果を発生させるにとどまるもの」という結論を導きやすいものであると考えます。 |
イ 先行原因行為と後行財務会計行為が同一者の権限に属するなど、組織法的権限上、財務会計職員による先行行為の違法性是正が困難とは言いがたいケース
一日校長事件は、先行原因行為が教育委員会の権限(昇格昇給という任用行為)、後行対象財務会計行為の権限が首長(公金支出)と相互独立した異なる執行機関に属するケースであり、同判決ではこのような場合、後行財務会計行為を行う機関は先行原因行為を行う機関の権限行使に対して謙抑的な姿勢をとらざるを得ないことを前提とした論旨が展開されています。
一方で、先行原因行為と後行財務会計行為の権限が同一の者に属するなど、組織法的権限からみるだけなら、後行財務会計行為の権限者(財務会計職員)が先行行為の違法性を是正することが必ずしも困難とは言いがたいケースも多々(というより、通常そちらの方が多い※)と考えられます。
このような場合に上記の論旨をストレートに適用するわけにいかないのは当然であるところ、こうした場合については、次のような判例法理が展開されています。
| ※ 特に契約の締結(支出負担行為)と履行としての公金支出(支出命令)は、本来的にはどちらも首長の権限であり、現実的な決裁権の配分も同一の権限ライン上の職員(機関)に配分されている例が多いものと思われますが、住民監査請求・住民訴訟の枠組みでは別の財務会計行為とされており(最判平14.7.16民集56.6.1339)、その意味では、違法な契約に基づく契約履行(公金支出)の当否、という先行後行関係(違法性の承継)問題は、理念的には極めて多数発生し得るものといえます。 |
(a) 先行原因行為の内容変更が容易なケース
先行原因行為に違法性がある場合、この内容の変更が容易であり、変更することによって後行財務会計行為に違法の影響を及ぼさないようになし得るのであれば、下記の通り、判例では、違法な先行原因行為をそのままに後行財務会計行為が行われた際の後行財務会計行為の財務会計法規上の義務違反を比較的緩やかに認める傾向が看取されます。
| 最判昭60.9.12集民145.357(川崎市職員分限免職事件)
収賄で逮捕された市長部局職員を市長が分限免職処分として退職手当を支給したのは違法とする4号訴訟において、最高裁は津地鎮祭事件判決を引用の上で、「…(市の退職手当)条例の下においては、分限免職処分がなされれば当然に所定額の退職手当が支給されることとなっており、本件分限免職処分は本件退職手当の支給の直接の原因をなすものというべきであるから、前者が違法であれば後者も当然に違法となるものと解するのが相当である」と判示。(ただし請求は棄却) |
| 最判平10.4.24集民188.275(茅ヶ崎市職員商工会議所派遣事件)
派遣法制定前において、市長が、市長部局職員に市商工会議所専務理事職への派遣を発令し、商工会議所での業務に専任従事する(派遣中の当該職員の市業務への関与は数度の市の政策会議に出席した程度)同職員に対して市条例に基づき職務専念義務免除をした上で、派遣期間中の給与を市が負担したのは違法とする4号訴訟において、最高裁は「本件免除条例・・・及び本件給与条例・・・は、職務専念義務の免除や勤務しないことについての承認について明示の要件を定めていないが、処分権者がこれを全く自由に行うことができるというものではなく、職務専念義務の免除が服務の根本基準を定める地方公務員法30条や職務に専念すべき義務を定める同法35条の趣旨に違反したり、勤務しないことについての承認が給与の根本基準を定める同法24条1項の趣旨に違反する場合には、これらは違法になると解すべきである。そして、本件においては、本件派遣の目的、被上告人会議所の性格及び具体的な事業内容並びに派遣職員が従事する職務の内容のほか、派遣期間、派遣人数等諸般の事情を総合考慮した上、本件職務専念義務の免除については、本件派遣のため本件派遣職員を市の事務に従事させないことが、また、本件承認※については、これに加えて、市で勤務しない時間につき給与を支給することが、右各条項の趣旨に反しないものといえるかどうかを慎重に検討するのが相当である」と判示。 ※ 「本件承認」とは、市給与条例において「職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合…を除く外、その勤務しない1時間につき、…に規定する勤務1時間当りの給与額を減額して給与を支給する」と規定するところ、この任命権者の承認のことを指している。つまり、派遣職員が市において勤務せずして給与を支給する前提としての任命権者の承認、ということになる。 【注】 本件判決は、地方公務員派遣法制定のきっかけとなった事案として著名なものである。なお本件原審は、商工会議所の高度に公共的な性格や派遣目的の市の施策との関連性から派遣発令に特段の問題はなく、派遣職員の身分処遇保障の観点から、職専免措置は市長の裁量権を逸脱濫用したものではないとした上で、市給与条例に定める任命権者の承認(上記※の「本件承認」のこと。ここでは違法とはいえない職専免措置)があるのだから、本件給与支給は違法ではないと判断したが、最高裁は本件判決でこの判断を是認せず破棄差戻しとした。そして差戻し後上告審で最終的に本件給与支給を違法と判断した(ただし派遣当時の派遣出向者への給与支給が多くの自治体で行われており、派遣法制も整備されておらず、当論点に関する定説が定まっていなかったことを踏まえ、本件給与支出に関する市長の故意過失を否定し(つまり給与支給違法性とは別の理由付けで)請求を棄却)。 |
| 最判平16.1.15民集58.1.156(岡山県職員倉敷チボリ公園派遣事件)
県が職務専念義務の免除をするとともに勤務しないことの承認をして、いわゆる第3セクター方式により設立された株式会社に県職員を派遣しその給与を支出したことを違法として知事および3セクに損害賠償・不当利得返還を求める4号訴訟において、最高裁は上記茅ヶ崎市職員商工会議所派遣事件判決を引用の上で、「…前記第1の事実関係によれば,1 本件職員派遣は,第1審被告会社との連絡調整の必要のみでなく,第1審被告会社が設立されたばかりで事業収入がなく,十分な人材を確保していないことを考慮して行われたものであった,2 第1審被告会社は営利を目的とする株式会社であり,その具体的な事業内容は遊園施設等の経営であった,3 本件派遣職員が従事した職務の内容は,第1審被告会社の組織体制の確立,社員教育,資金調達等,第1審被告会社の業務全般に及んでいた,4 第1審被告会社には,常時2人から6人の職員が派遣され,派遣人数は延べ13人,派遣期間は約7年間に及んだというのであるから,第1審被告会社が県の推進する…公園の建設,運営のために県等が出資して設立された株式会社であること等を考慮しても,本件職務専念義務の免除が本件免除規則2条2号所定の要件を満たすものであるということはできず,本件承認(注:上記茅ヶ崎市事件の「本件承認」と同種のもの。本判決は、派遣職員について職務専念義務特例条例による職務専念義務免除がされ、黙示的に給与条例に基づく「本件承認」がなされたと認定)は,地方公務員法24条1項の趣旨に反する違法なものというべきである。そうすると,本件承認を是正することなく,これを前提にして行われた本件派遣職員に対する給与支出は違法というべきであり,これと同旨の原審の判断は是認することができる」と判示。 |
上記判例はいずれも、首長が任命権者として行った人事上の処分(発令)に基づき、やはり首長が行なった財務会計行為(給与支出)について、先行原因行為(人事上の発令処分)が違法であることにより、後行財務会計行為が違法であるという結論を比較的容易に導出しています(茅ヶ崎市職員派遣事件判決は、先行派遣発令と後行給与支給の法的評価がほぼ一体化してなされています)。
この点について、これらの事案は、先行原因行為が違法である場合、権限者(先行原因行為・後行財務会計行為いずれにも権限をもつ機関・職員)は、先行原因行為の取消権(自庁取消権)をもち(そして法律による行政の原則からすれば、取消権を行使すべき)、かつ取消権の行使に特段の障碍がない事例であり、さらに先行原因行為がなければ(適法な形に是正されれば)後行財務会計行為を行う必要はないのですから、先行原因行為を取消し(是正)することは、違法な財務会計行為を行ってはならないという財務会計法規上の義務にしたがうこととなる、ということとなります。
これを言い換えれば、先行原因行為に違法があり、原因行為の取消権および後行財務会計行為の権限がある者が、先行原因行為を取り消さずに後行財務会計行為を行った場合は、財務会計法規上の義務に違反し、財務会計職員としての賠償責任を生じる、ということであり、上記例示の判例では明示的ではありませんが、こうした事例でも一日校長事件の法理が貫徹されているとともに、前記の通り、違法性の承継(先行原因行為の違法にもとづく後行財務会計行為の義務違反)は、比較的緩やかに解される傾向がある、ということになります※、※※、※※※。
| ※ ただし、これはあくまでも違法性が承継されるについて緩やかな枠組みを認めているという意味であり、だからと言って4号訴訟における請求認容に直ちに結びついている、というものではない(上記各事例参照)ことに注意が必要です。 |
| ※※ 先行原因行為に違法があり、かつ後行財務会計行為と行為者が同一であるケースでの裁判例として、東京地判令2.11.12判例時報2505.3(都市計画法を変更しないまま設置した産廃運搬車専用の通行路について、これが都市計画法上違法であり、道路設置のため市長がした契約締結が地方自治法2条14項、地方財政法4条1項に違反するとして、市長の損害賠償責任を認めた事例)。上記川崎市分限免職事件と類似するものであり、厳密には財務会計行為の先行原因行為ではない都市計画決定(実際は変更すべきものを変更しなかった)権限と財務会計行為権限が同一の機関(市長)に属することから、市長は都市計画法の違反を是正すべき立場にあり、前記川崎市分限免職事件の判旨にしたがって対象財務会計行為の財務会計法規上の義務違反を認める、というロジックで見るとわかりやすいものと考えます。 |
| ※※※ ただし、首長部局内の出張(県総務部長の出張について財政課係長が支出命令)に係る旅行命令と旅費支出命令の関係について、最判平17.3.10集民216.357のような事例があるので注意。本件については宇賀自治法p.411もご覧ください。なお本例に関しては、県警本部長が違法な管下警察官県外派遣を行い給与支出したことについて県警本部長の賠償責任を認容した名古屋高判令3.10.7 のような例もあります。 |
(b) 先行原因行為の内容変更が容易でないケース
たとえば先行原因行為が契約の場合、契約には相手方があり、かつ相手方との契約上の約定を遵守すべき法律関係が発生するので、契約が違法だからといって自治体側が勝手に一方的な契約の破棄や内容変更をすることは、通常はできません。
といっても、違法な契約に基づき契約の履行として自治体側が公金の支出をした場合、その公金の支出も違法でなるのではないかとの疑念が、当然生じるところです。
このような場合の財務会計職員の損害賠償責任については、一日校長事件の法理を敷衍する形で、次の判例法理が展開されています。
| 最判平20.1.18民集62.1.1
市が土地開発公社にある土地の先行取得を委託し、公社が当該土地を取得の上、市と公社の間で前記委託契約に基づき当該土地の売買契約を締結したことに対し、上記委託契約は地方財政法等に違反して締結されたものであり、これに基づいてされた上記売買契約の締結も違法であると主張して市長に損害賠償を求める4号訴訟事案において、最高裁は一日校長事件判決を引用の上、次の通り判示。 「土地開発公社が普通地方公共団体との間の委託契約に基づいて先行取得を行った土地について,当該普通地方公共団体が当該土地開発公社とその買取りのための売買契約を締結する場合において,当該委託契約が私法上無効であるときには,当該普通地方公共団体の契約締結権者は,無効な委託契約に基づく義務の履行として買取りのための売買契約を締結してはならないという財務会計法規上の義務を負っていると解すべきであり,契約締結権者がその義務に違反して買取りのための売買契約を締結すれば,その締結は違法なものになるというべきである」 「本件において,仮に,本件土地につき代金・・・円で先行取得を行うことを本件公社に委託した市の判断に裁量権の範囲の著しい逸脱又は濫用があり,本件委託契約を無効としなければ地方自治法2条14項,地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められるという場合には,本件委託契約は私法上無効になるのであって,前記・・・のように,本件土地を取得する必要性及びその取得価格の相当性の有無にかかわらず本件委託契約が私法上無効になるものではないとして本件売買契約の締結が違法となることはないとすることはできない」 「また,先行取得の委託契約が私法上無効ではないものの,これが違法に締結されたものであって,当該普通地方公共団体がその取消権又は解除権を有しているときや,当該委託契約が著しく合理性を欠きそのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存し,かつ,客観的にみて当該普通地方公共団体が当該委託契約を解消することができる特殊な事情があるときにも,当該普通地方公共団体の契約締結権者は,これらの事情を考慮することなく,漫然と違法な委託契約に基づく義務の履行として買取りのための売買契約を締結してはならないという財務会計法規上の義務を負っていると解すべきであり,契約締結権者がその義務に違反して買取りのための売買契約を締結すれば,その締結は違法なものになるというべきである」 「本件において,仮に本件委託契約が私法上無効ではなかったとしても,上記のような場合には,本件売買契約の締結は財務会計法規上の義務に違反する違法なものになり得るのであって,前記・・・のように,市が本件委託契約上本件土地を買い取るべき義務を負っていたことから直ちに本件売買契約の締結が違法となることはないとすることもできない」 「そうすると,本件委託契約が私法上無効であるかどうか等について審理判断することなく,本件売買契約の締結が本件委託契約に基づく義務の履行であることのみを理由として,市の契約締結権者が本件売買契約を締結してはならないという財務会計法規上の義務を負うことはないとすることはできないものというべきである」 |
| 最判平25.3.21民集67.3.375
町有地上の建物が県道拡幅で取り壊しとなるため、町長が町を代表してこの建物を無償で使用する団体との間で移転補償費を支払う契約を締結し、同契約に基づき町長が支出命令を発して移転補償費を支払ったことに対し、上記契約は公序良俗に反し無効であるかまたは地方自治法2条14項、地方財政法4条1項に反して違法なので移転補償費の支出命令も違法であり、それにより町が損害を受けたとする4号訴訟事案において、最高裁は一日校長事件判決、上記平成20年最判等を引用の上、次の通り判示。 「・・・普通地方公共団体が締結した支出負担行為たる契約が違法に締結されたものであるとしても,それが私法上無効ではない場合には,当該普通地方公共団体が当該契約の取消権又は解除権を有しているときや,当該契約が著しく合理性を欠きそのためその締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存し,かつ,当該普通地方公共団体が当該契約の相手方に事実上の働きかけを真しに行えば相手方において当該契約の解消に応ずる蓋然性が大きかったというような,客観的にみて当該普通地方公共団体が当該契約を解消することができる特殊な事情があるときでない限り,当該契約に基づく債務の履行として支出命令を行う権限を有する職員は,当該契約の是正を行う職務上の権限を有していても,違法な契約に基づいて支出命令を行ってはならないという財務会計法規上の義務を負うものとはいえず,当該職員が上記債務の履行として行う支出命令がこのような財務会計法規上の義務に違反する違法なものとなることはないと解するのが相当である」(本件は、契約は私法上無効とはいえず、上記のような特殊な事情もないとして、原告の請求を棄却) |
以上の各事件はいずれも財務会計職員は違法な先行行為の是正にコミットすることについては、組織法的な権限上の障碍(例:一日校長事件参照)が特段あるとはみえないものの、上記(a)と異なり、先行原因行為が第三者との契約等、つまり先行原因行為を権限者が独自に取消・是正することが容易でない(契約等には当該第三者との間での法律上の拘束力が生じるため)、という特性があります(なお平成25年事件は、先行、後行財務会計行為とも町長が実行)。
たとえば先行原因行為である契約に行政法規上の違法原因があったとしても、契約が公序良俗違反(民法90条)、強行法規違反(同91条)その他の無効原因がない限り直ちにその契約が私法上無効となるとは限らず(民法上も無効な法律行為と取り消し得べき法律行為は分けられていますし、違法な行政行為もすべてが無効になるわけではありません)、だからと言って無効でない契約には外形上の効力があるのですから、その契約の違法性を回避するには契約を解除するか契約変更をするしかありませんが、これらの行為を自治体が自由に行うことができるわけではありません(一般には契約を締結した以上は契約相手方の信頼や利益を保護する必要はありますし、財務会計法規に違反する違法性の瑕疵ある契約だからといって自治体側が任意に解除、変更すること(自庁取消権)を認める法律上の規定もありません。契約に違法の瑕疵があると自治体が主張して、かってに契約の効力を無視することもできません)。これはとりもなおさず、先行原因行為に違法の瑕疵があっても私法上無効とはいえない場合、先行原因行為の権限者は、後行財務会計行為を行わざるを得なくなる、ということを意味することとなります※1。そしてその場合には、どこまで先行原因行為の違法性を理由として住民監査請求・住民訴訟の直接の対象である後行財務会計行為についての財務会計法規上の義務違反を認めるのか(=財務会計職員の損害賠償責任が生じるのか)、という問題が生じます。
| ※1 この点については、損害賠償請求の4号訴訟ではなく差止め請求訴訟ですが、最高裁は最判昭62.5.19民集41.4.687において「(先行原因行為たる)契約が仮に随意契約の制限に関する法令に違反して締結された点において違法であるとしても、それが私法上当然無効とはいえない場合には、普通地方公共団体は契約の相手方に対して当該契約に基づく債務を履行すべき義務を負うのであるから、右債務の履行として行われる行為自体はこれを違法ということはでき」ない(ので、上記契約の履行として行われる財務会計行為の差止めは認められない)と判示しています。つまり、先行行為による私法上の義務(契約に基づく債務履行義務)と財務会計法規上の義務(違法な先行行為に基づく後行財務会計行為を行うべきではない)が衝突した場合に、後者の義務が前者の義務に当然に優越する、ということではない、ことを意味します。 |
ところで上記平成20年・25年判決はいずれも、そのようなケースにおいて、次のような場合でない限り、先行原因行為が違法であるがために後行財務会計行為の違法(財務会計法規上の義務違反)は生じるものではない(裏を返せば、次の事情がある場合に先行原因行為に基づき後行財務会計行為をそのまま行った場合は、財務会計法規上の義務違反に問われ得る)、という判断枠組みを示しています。いずれにしても、先行原因行為に違法の瑕疵があることが前提となります(つまり、先行原因行為が違法かどうかの判断が必ず先行し、そのうえで下記のいずれにあたるかが問題となる)。
| ① 先行原因行為が私法上無効である場合 ② 先行原因行為が違法ではあるが私法上無効ではない場合で、自治体側に解除(取消)権がある場合 ③ 先行原因行為が違法ではあるが私法上無効ではなく、明示的な解除(取消)権もない場合で、同行為について著しく合理性を欠きそのため予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵があり、かつ、客観的にみて原因行為を解消できる特殊な事情がある場合 |
【①の場合】
①の場合は、先行原因行為が私法上無効であるときには、財務会計職員は、無効な先行行為に基づく義務の履行としての後行財務会計行為を行ってはならないという財務会計法規上の義務を負っているので、それにもかかわらず財務会計職員が後行財務会計行為を行った場合は、財務会計法規上の義務違反が当然問題となります。
| ★先行原因行為(契約)が私法上無効となる場合★
平成20年判決は、私法上無効の原因として「公社に委託した市の判断に裁量権の範囲の著しい逸脱又は濫用があり、本件委託契約を無効としなければ地方自治法2条14項、地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる」場合としています。 一般的に、自治体が当事者となる法律行為が私法上無効となるというと、上記の通り、強行法規違反(民法91条)や公序違反(民法90条)が考えられます(ただし強行法規の解釈や、国家社会の秩序に関わる法制の解釈が容易でないことはあり得ることです。たとえば政教分離に関わる問題など)。また地方自治法238条の4第6項該当行為は私法上無効であることが明確に法律上定められており、これによる無効もあり得るものでしょう。 では、これらのほか上記平成20年最判の判示事項のような無効原因とはどのようなものでしょうか?
そこで、本判決に先行する判例などから、このようなケースで問題となり得る、先行原因行為が私法上無効と評価され得る枠組みについての情報を整理します。 ① 最判昭62.5.19民集41.4.687 ② 最判平16.1.15民集58.1.156 ③ 最判平25.3.28集民243.241 なおこのほか、最判平23.12.2集民238.237も参照 以上からすれば、対象財務会計行為に先行する原因行為が違法である場合に、さらにこれを私法上無効であると評価すべき、となり得るのは、その原因行為が、当該原因行為の法的評価に関わる関連法規で強行法規性をもたない(強行法規違反が無効なのはあきらかなので)ものの場合においては、次のケースの場合、ということができます※3。 a) 先行原因行為について、裁量権の範囲の著しい逸脱又は濫用があり、当該行為を無効としなければ地方自治法2条14項、地方財政法4条1項の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合 なおb) については、昭和62年、平成16年最判をみる限り、平たくいえば契約の相手方も契約法規に違背することを認識しており(認識可能であり)、結果においても契約法規が求める競争原理を働かせることができたにも関わらずそれより相当に高額な契約となっており競争原理を無意味にした、地方公務員法の職務給与の基本原則を無意味にした=法の趣旨を没却する結果となる特段の事情、という枠組みと考えれば分かりやすいのではないでしょうか。
なお参考までに、地方自治法2条16項は「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない」と、そして17項は「前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする」と定めるところ、違法な財務会計行為の私法上の効力についていえば、法令違反の財務会計行為はいかなるもの(たとえば些細な違法なもの)であっても、地方自治法2条17項によってその効力をすべからく否定される、とは解されていないので、留意が必要です※4。
|
【②③の場合】
②③の場合は、先行原因行為が違法ではあるが法律上の効力が存在する場合(原始的に無効ではない)となりますが、その場合であっても、法律上(②のケース)または事実上(③のケース)、先行行為を解消することができる場合※1、※2、自治体は一方的に違法な先行行為を解消できるのですから、先行行為を解消することによって、後行財務会計行為をしてはならないという財務会計法規上の義務を負う、と解すべきことになります。
| ※1 「最高裁 時の判例Ⅷ」有斐閣(2018年)p.100(平成25年最判調査官解説:中山雅之) |
| ※2 平成20年、25年最判ともに、事実上解消できる場合が「客観的に見て」とされているところ、これは当事者の判断ではなく、裁判所が事案を見てどう判断するか、ということになる(住民監査請求段階では、監査委員が見て、となる)。 |
ちなみに②の場合は、自治体側に先行行為の違法性を是正する法律上の権能があるのですから、自庁取消権のあるケースとしての上記川崎市分限免職事件と類似の構造となり、したがってこの違法性を放置して後行財務会計行為を行うべきでは(通常は)ない、というのが当然の帰結となろうと考えます。
一方で③の場合は、「著しく合理性を欠きそのため・・・予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵」という、上記一日校長事件判決と同じ措辞となっています。結局③の場合は、一日校長事件同様、先行原因行為が後行財務会計行為の実行を拘束する(一日校長事件の場合は、執行機関間の権限並立の観点から、本件平成20・25年最判の場合は、契約の拘束力から)、という事情が共通しているのであり、そうなると、先行行為に「著しく合理性を欠きそのため・・・予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵」がない限り、後行財務会計行為を行ってはならないという財務会計法規上の義務は生じないこととなり、先行行為に「著しく合理性を欠きそのため・・・予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵」がある場合にはじめて、後行財務会計行為について財務会計職員にはこれを行ってはならないという財務会計法規上の義務が生じ得ることとなります。
しかし、このような瑕疵がある場合でも②と異なり、財務会計職員には先行行為の法律上の拘束力を任意に解消する法律上の権能はないのですから(一日校長事件と同じ)、当然に先行行為の違法性を財務会計職員が解消することはできません。
この場合において最高裁は、平成20・25年最判において、「客観的にみて原因行為を解消できる特殊な事情がある場合」は、これらの事情を考慮することなく、漫然と違法な先行行為に基づく義務の履行として後行財務会計行為をしてはならないという財務会計法規上の義務を負っているとの判断枠組みを示しています。つまり「客観的にみて」(=裁判所(や監査委員)からみてであり、財務会計職員の判断ではない)&「先行行為の違法性を解消できる特殊な事情」(=当然に違法性解消ができる権能が後行財務会計行為の担当財務会計職員にない以上、これを解消できるのは「特殊な事情」というべきである)という条件が重畳的に(=and条件として)存在する場合は、後行財務会計行為を担当する財務会計職員には、その財務会計行為をなすべきではないという財務会計法規上の義務が生じ、そうでない場合は、後行財務会計行為を行わざるを得ない(行っても、財務会計法規上の義務違反から解放される)、ということになります※3。
| ※3 なお平成25年最判には「当該普通地方公共団体が当該契約の相手方に事実上の働きかけを真しに行えば相手方において当該契約の解消に応ずる蓋然性が大きかったというような,客観的にみて当該普通地方公共団体が当該契約を解消することができる特殊な事情があるとき」との説示があるところ、この下線部部分が平成20年最判でいう先行行為を解消できる特殊な事情の例示であり、よって「当該契約を解消することができる特殊な事情」の範疇にこの例示ケースが含まれることは明らかです。 なおこの説示は、同判決の先行事例である平成20年最判にはありませんが、その趣旨からして、先行・後行行為が別契約である平成20年最判と一の契約の支出負担行為と支出命令である平成25年最判で異なるべきものではなく、よって平成20年最判で示された判断枠組みに適用される内容であると考えます。 |
そして③の場合、後行財務会計行為担当の財務会計職員には、法律上当然に先行行為の違法性を解消できる権能がないのだから、上記の財務会計法規上の義務は努力義務、つまり先行行為の違法性を解消する努力義務を負うが、その努力を尽くしてもなお先行行為の違法性を解消できない場合、先行行為に基づき後行財務会計行為を行っても、後行財務会計行為について、その財務会計職員は、財務会計法規上の義務違反には問われない、ということになります※5、※6。
ただし、原因行為を解消できる特殊な事情があるということは、原因行為の解消権、たとえば契約の解除権を有するのと同様なのであり、すくなくとも財務会計職員は、こうした特殊な事情があることを考慮することなく、漫然と違法な先行原因行為に基づく義務の履行として後行財務会計行為を行ってはならない、という財務会計法規上の義務を負うことになるとも考えることができるので、その点を留意すべきです。
| ※4 上記3(1)※5参照。 |
| ※5 参考:判例行政法p.32では、違法性承継に関する判例として平成20年最判を紹介するなかで、②③について、②を財務会計職員が原因行為の是正権限を有する場合(川崎市分限免職事件の類型)、③を是正権限を有しない場合(一日校長事件の類型)と区分しています(なお①は津地鎮祭事件の類型)。 |
| ※6 なお、平成25年最判において原判決を破棄するに当たり、先行原因行為たる契約締結に予算執行の適正確保の見地から看過し得ない瑕疵が存しないことを理由として説示していないのは、本件のように先行行為である違法な契約とその後行行為である財務会計行為の主体が同一でありそれらが公金を支出するための一連の行為である事案においては、両行為の主体が異なる事案や平成20年最判事案のように先行行為が当該財務会計行為とは別個の行為である事案と比較して、「看過し得ない瑕疵」の要件は必ずしもこれらと同程度に限定的にとらえられ作用するものではなく、実質的には「特殊な事情」要件を満たすか否かが主たる判断の対象となる場合が多いことを踏まえたものである、としています(平成25年最判調査官解説p.98(注10))。このように、③の事例であっても、その態様によって後行財務会計行為に係る財務会計職員の負う財務会計法規上の義務は、限定的にも(たとえば1日校長事件のように先行原因行為と後行財務会計行為の権限者が異なり指揮監督系統も異なる場合)、幅広にも(たとえば平成25年最判のように先行原因行為と後行財務会計行為が権限上同一系統にあり、かつ先行行為と後行行為が一連性(支出負担行為と支出命令のように)がある場合)解され得ることとなるべき点に注意が必要です。 |
【まとめ】
以上の平成20・25年最判の判断枠組みは、多くの住民監査請求事案で問題となるものと思われます。なぜならば、とりわけ契約を締結し、その履行として公金の支出をする、というのは、日常的に多数行われており、住民監査請求・住民訴訟の領域では、契約の締結(支出負担行為)と、契約履行としての支出(支出命令、現実の支出)は別の財務会計行為とされるため、契約内容が違法であるために契約履行としての公金支出を違法と主張するケースが普通に想定されるからです。
(2) 参考となる下級審裁判例
本項では、違法性の承継について参考となる裁判例について見ていきます。
ア 一日校長事件と判示内容が類似する先行裁判例
一日校長事件に先行する裁判例で、違法性の承継の判断枠組み自体を検討した裁判例として次のようなものがあり、参考となるものと考えます。
○ 仙台地判昭62.9.30判例時報1287.47
○ 秋田地判平3.3.22判例時報1427.46
○ 水戸地判平3.9.17行裁例集42.8・9.1503
これらの裁判例は一日校長事件に先行したものであり、これら裁判例においては、住民監査請求・住民訴訟の立法趣旨(財務会計行為等に対象を限定する民衆争訟)であることを考慮しての判断枠組みが検討され、その結果として、違法性の承継を認める判断指標として、先行行為と後行財務会計行為の関係(密接性、一体性)が考慮されています。こうした視点は、一日超事件で違法性の承継について、まずは対象財務会計行為の財務会計法規違反性を問擬するという一般法理が示された今日においては、違法性の承継における汎用的な原則というよりは、後行財務会計行為に財務会計法規違反性をもたらす関係性の具体例として見ることが適当でしょう※1。
また秋田地判では先行行為に重大明白な瑕疵がある場合は、後行財務会計行為は違法となるとの前提に立っていますが、一日校長事件判決では先行原因行為の違法性について重大明白要件を採用していない点、同判決のほか、上記(1)イ(b)の平成20年、25年最判や下記平成25年東京高判の内容に留意すべきです※2。
| ※1 富山地判平10.6.10判例地方自治186.94は、一日校長事件判決後のものですが、同判決の判旨を引用しておらず、上記各従前裁判例と同様の論旨(密接一体的関係の有無を違法性承継の成立要件とする)を展開しています。 この富山地判は、参考事例としては上記の先行裁判例同様、先行原因行為と後行財務会計行為の密接一体性は違法性の承継を認める一般的要件ではなく条件が成立する態様の具体例と見るべきと考えます。 なお本判決は住民監査請求・住民訴訟制度が財務会計行為等に対象を限定するという制度構成を前提として上記の論旨を導出していますが(上記3裁判例いずれも同じであり、一日校長事件においても同様)、要すれば、違法性の承継の問題は、結局住民監査請求・住民訴訟の対象の射程はどの範囲までなのかということが問題の根本であるとの意識からの論旨構成なのでしょう。たとえば同判決での「(本件の住民監査請求・住民訴訟の対象となる)財務会計上の行為の違法事由として、その原因ないし前提となった非財務会計上の行為の違法性を主張できるのは」とあるのは、直接の住民訴訟の対象である財務会計行為から先行非財務会計行為を、つまり後行財務会計行為から先行原因行為をスコープしての措辞であり、その意味では先行行為→後行行為の影響を論ずる違法性の承継に関する枠組みというよりは、非財務会計行為は住民監査請求・住民訴訟の対象となり得ないという制度設計の中で、どこまでを住民監査請求・住民訴訟の対象として観察し得るのかという論旨のように思われます。 |
| ※2 一日校長事件における重大明白性要件の扱いについては、上記3(1)※3参照。 |
イ 先行原因行為と後行財務会計行為の権限機関が異なる場合の判断例(一日校長事件判決後のもの)
先行原因行為と後行財務会計行為の権限機関(職員)が異なる場合の関係性について、一日校長事件同様に、先行原因行為を行った機関判断が後行財務会計行為の実行を強く拘束するケースとしては、次の裁判例が参考となるものと考えます。
○ 横浜地判平7.3.6判例時報1574.62(国税の更正処分による地方税の更正処分)※
○ 神戸地判平13.9.12判例地方自治228.16(議長決定の海外出張命令と旅費支出)
○ 東京高判平25.3.29判例タイムズ1415.97、東京高判平26.10.7
最後の2件の東京高判は、いずれも国の事業である八ッ場ダムの県負担金関係事案であり、一日校長事件判決の趣旨が前提とされているものです。そして事案の内容としても、先行原因行為の権限機関と後行財務会計行為の権限機関が異なる点、一日校長事件と類似するものです。
その上で本裁判例は、一日校長事件で示された、他機関の行う先行原因行為に対する後行財務会計行為の担当職員が負うべき財務会計法規上の審査義務について、一日校長事件判旨をブレイク・ダウンして示しており、とりわけ参考となるものと考えます。
また本件は、県負担金の負担義務の性格という正面からの問題だけではなく、ダム使用権申請取下げ義務の存否という面からの財務会計法規違反性を検討しており、そうした点からも参考となると考えます。
一方で、先行原因行為と後行財務会計行為の権限機関(職員)が異なる場合であっても、先行原因行為を行った機関判断の拘束力が弱いケースとしては、次の裁判例が参考となるものと考えます。
○ 大阪高判平15.2.6判例地方自治247.39(議決承認を経た民事調停による支出)
○ 奈良地判平15.5.21判例地方自治253.46
大阪高判の事例は、議決が先行するケースですが、違法な議決があったと認めるときは、首長は再議に付する義務があり(地方自治法176条4項)、これを怠って議決に基づく財務会計行為を行った場合、財務会計法規上の義務違反と評価され得ることに注意が必要です。その点では上記最判平25.3.21民集67.3.375のように、先行行為が後行財務会計行為をなすべきことを強く拘束するような効力を、議決に認めることは、難しいというべきです。
また奈良地判の事例は、一日校長事件同様、教育委員会の人事措置に伴う給与支出の事案ですが、本件は教育委員会職員に限定・固有の事案ではなく、全市的な人事措置(技能労務職員の勤務延長。当審では条例違反と判断されている)に伴うものであり、先行原因行為と後行財務会計行為の実質的な権限の遮断がないといえるため、違法性の承継を認めやすい事案であると考えます。
| ※ 名古屋地判平13.3.2判例地方自治217.29は、本件同様国の行為を先行原因行為とするものですが(その点は上記東京高判八ッ場ダム訴訟も同じ)、本判決で「原告らが同計画は違法であり、本件貸付けもその違法性を承継しているから違法であるとして本件貸付けの適法性を争うことは、実質的にみて、住民訴訟である本件訴訟において内閣総理大臣が行った本件基本計画の計画決定を争うものであって、明らかに住民訴訟の目的を逸脱するものであるといわざるを得ない」とするのは疑問というほかないと考えます。そもそも、違法性の承継が問題となる事案であっても、判断の対象となるのがあくまでも対象財務会計行為の財務会計法規上の違法性の存否となることは、一日校長事件判旨から明らかです。また先行原因行為者が国であることが問題であれば、行政委員会の行う先行原因行為と首長の財務会計行為の関係も同じく問題とせざるを得なくなりますが、一日校長事件判決は先行原因行為が行政委員会のなしたものであるがために首長の行う財務会計行為への影響を全く遮断する判断をしているのではないことは明白であり、その内容と矛盾することとなります。そのため上記横浜地判や掲示の八ッ場ダム事件判決など多くの国の行為を先行原因行為とする裁判例で上記のように先行原因行為が国の行為であることを理由として違法性の承継を遮断するという論理をとってはいません。また「仮に、原因行為の違法が財務会計行為の違法につながる余地があるとしても、原因行為である非財務会計行為が国の行政機関や当該普通地方公共団体における行政組織上独立の権限を有する機関により、その権限に基づいてなされた行政処分その他の行為である場合には、一定の要件を満たした場合にのみ当該行為の効力を争うことを認めている抗告訴訟制度(行政事件訴訟法3条)に抵触することになるだけでなく、住民訴訟という枠の中で国の行政活動一般をも対象とすることになるものであって、住民訴訟の目的を著しく逸脱する」との論旨も、住民監査請求・住民訴訟制度においては先行原因行為の違法性は後行財務会計行為の財務会計法規上の違法性(それが住民監査請求・住民訴訟において争われるべき本質的な内容です)をもたらす影響変数問題であり、先行原因行為の違法性を訴訟物としているわけではない以上、違法性の承継の枠組み検討において抗告訴訟の枠組みを持ち出すのは不適切ではないかとの疑いが拭いきれません。 とすれば、類似案件の検討において本判決を参考とするのは問題なしとすることはできず、八ッ場ダム事件に係る東京高判等を参照することが適当であると考えます。 |
また、一日校長事件同様、行政委員会の人事権限と首長の財務会計行為権限(退職手当支給)のバッティング事例ですが、やや権限関係が特殊なものとして、次の事例が参考となります。
○ 大阪地判平19.5.22判例地方自治299.74
本件は教育長に非違行為があり減給処分とされ、これに基づく給与支給を首長がしたところ、本来免職相当でありその給与支給を違法とする住民訴訟です。
財務会計職員である首長は教育長の懲戒処分を行う権限はなく、その点一日校長事件同様に、先行原因行為と後行財務会計行為の処分権限の分離が見られる事例ですが、本件は対象者が教育委員会委員である教育長であり、財務会計職員である首長は教育委員会委員の罷免権がある(その場合自動的に教育長職からも解任される)という特殊性があることを考慮し、本判決は、罷免権行使の不作為が財務会計法規上の義務違反に当たるかどうかにつき、首長に自庁取消権がある事例と同様の判断枠組みを採用しています(なお本件は、旧地教行法下の事件であり、現在とは教育長の組織法上の位置付けが異なることに注意)。
ウ 先行原因行為(非財務会計行為)と後行財務会計行為の権限機関が同じ場合の判断例(上記4(1)イ)
非財務会計行為である先行原因行為と後行財務会計行為の権限機関(職員)が同じ場合について参考となる下級審裁判例としては、次のものがあります。
○ 大阪高判平10.12.11判例地方自治199.22(上記3(2)イ※)
先行原因行為が人事上の処分であるケース。川崎市分限免職事件と類似する事案。
○ 津地判平14.5.9
先行する原因行為が下水道計画であるところ、これが違法であり、これに基づく下水道工事請負契約を違法と主張する事例。下水道計画が著しく合理性を欠き、そのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過できない瑕疵がある場合でなければ、下水道計画に基づく下水道施設建設のための請負契約の締結、公金の支出が違法となることはないというべき、とする。つまり、契約のように、後行財務会計行為(契約の履行たる支出)の実行を法律上拘束するわけではない行政計画についても、先行行為に「著しく合理性を欠き、そのためこれに予算執行の適正確保の見地から看過できない瑕疵がある」という要件を違法性承継の要件と判断した事例。
ただしこの後に最判平20.1.18民集62.1.1が示されており、本件のような事例においては、本件津地判の判旨もさりながら、上記平成20年最判の判旨により、客観的にみて権限者に先行行為を解消することができる事情があるか、つまり先行原因行為である行政計画が、後行財務会計行為の実行をどの程度拘束するのか、計画の内容修正等を行う余地があるのか、の点を考慮すべきものと考えます。
先行原因行為が財務会計行為である場合で後行財務会計行為の権限機関(職員)が同じ場合について参考となる下級審裁判例としては、次のものがあります。
○ 東京地判平15.3.26判例時報1836.62
再開発ビルの組合員協定に基づく負担金支出を問題とする事案。先行原因行為を契約締結行為とする最判平25.3.21民集67.3.375が示される前の事例であり、事案の枠組みも類似するところ、同最判の判旨をブレイク・ダウンした内容として参考となると考えます。
○ 大阪地判平20.6.26判例タイムズ1282.131
先行原因行為が契約締結、対象財務会計行為が契約履行の支出であり、最判平20.1.18民集62.1.1が示された後、先行原因行為を契約締結行為とする最判平25.3.21民集67.3.375が示される前の事例です。平成20年最判の判旨にもとづく判断事例となっていますが、検討に当たってはあわせて平成25年最判の判旨も参照することが望ましいものです。
○ 奈良地判令2.7.21判例時報2488・2489.145
独立する前後財務会計行為間の問題という点で前記平成20年最判事例と類似性がある事例(ただし1号訴訟(差止め請求))。
○ 東京地判令2.11.12判例時報2505.3
都市計画を変更せず道路工事契約を行ったことを問題とする事案。
5 議会の議決と後行財務会計行為の関係
財務会計行為を行うにあたり、財務会計行為の実行要件として議決を必要とする等、議会の個別の議決(予算等の一般的な議決ではなく特定の財務会計行為を行う前提としての議決)が先行しているケースが多いところ、こうした議決に違法性がある場合、後行する財務会計行為にどのような影響があるのかは、当然問題となり得るところです。本項では、議決が財務会計行為に先行すべき場合の財務会計行為の違法性の問題について説明します。
(1) 所要の議決が存在する場合
まず議決の効力の一般論について、最判昭37.3.7民集16.3.445は、公金の支出等は、一方において議会の議決に基づくことを要するとともに、他面法令の規定に従わなければならないのは勿論であり、議会の議決があったからといって、法令上違法な支出が適法な支出となる理由はなく、監査委員は、議会の議決があった場合にも、長に対し、その執行につき妥当な措置を要求することができないわけではないし、ことに訴訟においては、議決に基づくものでも執行の禁止、制限等を求めることができる、としています。
また、議決については、議会に広範な裁量権が認められるが、裁量権の逸脱・濫用により議決が違法・無効となることはあり得ます(最判平24.4.20民集66.6.2583、最判平24.4.23民集66.6.2789)※1。
次に、先行する議決に違法の瑕疵がある場合の財務会計行為への影響について、そのような場合は適法な議決があったということはできないとする最高裁判例があります(最判平17.11.17集民218.459※2)。法令により財務会計行為の前提として議決を要するとする以上、当然の結論です(なお参考:最判平30.11.6集民260.41)。
| ※1 同最判は、権利放棄議決については、放棄の実体要件についてこれを制限する法令は存在しないので、放棄適否の実体的判断については、住民による直接の選挙を通じて選出された議員により構成される自治体の議決機関である議会の裁量権に基本的に委ねられている(つまり、議会の裁量権は広範である)としたうえで、住民訴訟の対象とされている損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を放棄する旨の議決がされた場合についてみると、このような請求権が認められる場合は様々であり、個々の事案ごとに、当該請求権の発生原因である財務会計行為等の性質、内容、原因、経緯及び影響、当該議の趣旨及び経緯、当該請求権の放棄又は行使の影響、住民訴訟の係属の有無及び経緯、事後の状況その他の諸般の事情を総合考慮して、これを放棄することが普通地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする同法の趣旨等に照らして不合理であって上記の裁量権の範囲の逸脱又はその濫用に当たると認められるときは、その議決は違法となり、当該放棄は無効となるものと解するのが相当、とします。 本件は、地方自治法96条1項10号の議決事件に関するものですが、住民監査請求で問題になるであろう5、6、9号議決についても、その実体的要件について地方自治法その他の法令に制限する規定は見当たらない点で本最判の前提条件は同様であることなどを踏まえれば、これら行為に対する議決に係る議会の裁量権およびその裁量の限界については、本最判の判断枠組みに準じるものと考えます。 |
| ※2 本判決は、財産の適正な対価によらない譲渡又は貸付けにつき地方自治法237条2項の議会の議決があったというためには,議会において当該譲渡等が適正な対価によらないものであることを前提として審議がされた上当該譲渡等を行うことを認める趣旨の議決がされたことを要するとし、その点を判断せずに請求を棄却した原判決について、原判決が確定した事実関係の下においては,本議決により対象財産譲渡につき地方自治法237条2項の議会の議決があったということはできないとして、差し戻したものである。 |
なお、次の裁判例も参考となるものと考えます。
| ○盛岡地判昭46.12.28判例時報655.20 宗教法人への町有地の廉価な土地売却において、町長の提案による議案につき議会の議決を経ていたが、そもそも本売却は憲法89条および当時の地方自治法212条に明白に違反する無効なものであり、当該議決によりその売却行為の違法性が治癒されるものではない(上記昭和37年最判参照)とした事例※2○京都地判昭59.9.18行裁例集35.9.1366 補正予算提出にあたり真の目的を秘匿してこれと異なる目的の説明を行い、結果成立した予算を真の目的のために契約締結・支出したことは脱法行為であり、適法な財務会計行為とはいえないとした事例○金沢地判昭62.11.27行裁例集38.11.1665 契約の締結につき議会の議決を得ている場合であっても、首長が裁量権を濫用もしくは逸脱し、著しく高額な価格で財産を取得する契約を締結し自治体に債務を負担させた場合には、当該行為は違法と評価され、民法上の不法行為の要件に従って長は地方公共団体に対し住民訴訟による代位行使の対象となる損害賠償責任を負うとの判断枠組みを示した事例。要議決事案についての議会への案件内容の十分な説明義務についても言及している※2。○大阪高判平4.3.24行裁例集43.3.492 首長は、少なくとも条例(特別職の期末手当に係る条例)の違法性が重大かつ明白な場合においては当該条例を執行すべき拘束を受けないものと解するのが相当であり、首長がそのような条例の規定に基づいて公金の支出をしたときは、それに固有の違法が認められない場合であっても条例の違法性を承継し、違法な公金の支出となるとした事例※3○東京高判平13.8.27判例時報764.56 議会の議決が違法のときは、首長は再議に付する義務があり(地方自治法176条4項)、議会の議決に基づく執行行為でさえあれば、首長には常に損害賠償責任が生じないと解するのは相当でなく、少なくとも、議会の議決が一義的明白に違法であるような場合には、そのような議決を執行した首長にも損害賠償の責任が生ずるとした事例 ○最判平24.4.20民集66.6.2583、最判平24.4.23民集66.6.2789 ○奈良地判令和7.5.22 |
| ※2 参考:碓井p.155は、この2判決を参照して、議会の議決があったからといって、法令上違法な支出が適法な支出になるものではないとする事例が見られることにつき、議案提案者が首長(つまり財務会計行為の権限者)であることが多いことを指摘する。そしてその点につき執行機関は議決に強く拘束され、違法な議決であっても、その違法が重大明白で議決が無効である場合を除き議決に従った執行機関の執行行為は違法とならないとする東京地判昭62.10.27行裁例集38.10.1573の判示内容を疑問視している。 |
| ※3 重大明白性要件については、一日校長事件に係る上記3(1)※3参照。ただし条例は先行行為とはいえず、かつ議会の議決を経た点で一定の適法性推定も働くと見るべきなので、条例については(平成4年調査官解説でいうところの「より狭い要件」である)重大明白性要件で考えるのは合理性があるのではないか。 |
(2) 所要の議決が存在しない場合
そもそも、議決の存在を前提とする財務会計行為について議決が欠ける場合、当該財務会計行為の行為者(執行機関・職員)に代表権限が設定されていないため、無権限の行為として無効となると通常考えられるところです(参照:最判昭35.7.1民集14.9.1615、最判昭44.9.11集民96.489)。
ところで議決が欠けるという瑕疵については一般に、事後的に議決で追認される場合は、その瑕疵は治癒される(違法性が遡及的に消滅する)、とされます(個別行為に係る議案ではなく条例措置(条例のない給与支給)の事案であるが参考例として最判平5.5.27集民169.87)。財務会計行為をするにあたり議会の議決を要するというのは、財務会計行為を行うにあたっての政策判断を議会に委ねる趣旨であり、事後ではあれ議会がそれを追認すれば、議決の存在という条件は充足されるという考えに立つものと解されます※1。
| ※1 そもそも私法上無効な行為は、追認によっても有効になることはありませんが(民法119条参照)、上記昭和44年最判の趣旨を勘案すれば、議決欠缺の無効とは原始的無効(たとえば公序良俗違反等)ではなく、無権代理的な意味で効力を生じない、ということとなり、したがって追認によって有効となり得る(参照:民法113条1項、116条)ものとなります。参照:下記平成15年東京地判。 |
ただしこの追認的措置については、議決にあたって対象財務会計行為が特定されており、法令が議決を要するとする当該財務会計行為の内容を議会が理解した上でなされることを要するものとされます。参照:最判平17.11.17集民218.459※2、※3。また、事後の議決により治癒されるのは議決の欠缺であり、それ以外の違法性があったとしても、議決により治癒の効果が出ることがないのは、当然の帰結です(上記(1)昭和37年最判の趣旨も参照)。さらに、前記⑴掲出の、最判平24.4.20民集66.6.2583、最判平24.4.23民集66.6.2789の判旨は、これらが追認事件に係るものではないとはいえ、議決事件につき議決を求める法の趣旨等を勘案すれば、追認議決においても妥当するものと考えます。
| ※2 平成17年最判の内容は上記(1)※参照。この判決事例の場合は、地方自治法237条2項に言うところの、適正な対価によらない財産の譲渡であることを前提とした審議が行われること、ということになる。 |
| ※3 判例行政法p.26は、「最高裁は、議会の議決を欠く瑕疵の治癒が認められるためには、事後的な議決の形式は問わない反面、その議決が実質的に追認の趣旨でなされていることを要するとしているものと解される」とする。 |
また、次の裁判例も参考となるものと考えます。
| ○松山地判昭48.3.29判例時報706.18 予算外の町長交際費支出につき後年度の補正予算措置によって予算外支出の違法が治癒されるものではないとした事例。追認的議決は適法なものでなければならない(この場合は、会計年度独立原則(地方自治法施行令148条)に反することとなり、そのような議決で過去の議決の欠缺という瑕疵は治癒されない)という当然の事理によるもの。○水戸地判昭48.8.23行裁例集24.8・9.828 予算成立前になされた工事請負契約について無予算の瑕疵を追認的行為で治癒するためには、その違法な行為の内容が事後的に明確に承認されることが必要であるとした事例。事後的な議決欠缺の瑕疵を治癒させるためには、形式面だけではなく、議決対象事項の内容面まで踏み込んだレベルでの議決の適切性(議決議案と現実の整合性)が確保されていなければならない、ということ。○大阪高判昭53.10.27行裁例集29.10.1895 予算措置はあったが高額契約締結に関する所要の単行議決がなかったケースにおいて、後補的に追認議決した場合に、議決欠缺の瑕疵が治癒されたとした事例○名古屋高判昭55.9.16行裁例集31.9.1825(注:取消訴訟) ○大阪地判昭56.11.24行裁例集32.11.2070 名古屋高判、大阪地判ともに違法な専決処分の瑕疵が、追認議決により治癒するとした事例○奈良地判昭57.3.31行裁例集33.4.785 条例根拠のない給与支給について、事後に措置された条例に遡及適用条項がある場合、条例欠缺の瑕疵は治癒されるとした事例。下記事例および上記最判平5.5.27集民169.87も参照。○京都地判昭59.9.18行裁例集35.9.1366 議決欠缺の事例ではないが、議決の際の議案内容説明粒度に関するもの。上記(1)参照、また最判平17.11.17集民218.459も参照。 ○東京高判平3.10.15行裁例集42.10.1627 ○奈良地判平6.3.30判例地方自治129.40 ○奈良地判平7.7.19判例地方自治145.11 ○東京地判平15.3.26判例時報1836.62 ○東京高判平24.7.11判例地方自治371.29 ○東京高判令3.3.25判例地方自治486.24 ○福岡高判令5.8.23 |

宇奈月温泉。世間的には黒部トロッコ列車の起点として有名なところですが、法律学勉強した人間にとっては、なんといっても宇奈月温泉事件でお馴染みですね。これって民法判例百選のアタマに載っているので有名なんだ説もありますが、でも憲法、刑法百選の一番めなど覚えてはいないわけで、やはりこの事件、大概の判例は事実関係読むだけでゲンナリするのに、当事件は事実関係がシンプルなおかつその中身の見るからに越後屋対水戸黄門的構図がインパクトあり過ぎるからでしょう。なお宇奈月温泉に行くにあたり家人がお宿探しにWebで宇奈月温泉検索したら「宇奈月温泉事件」が検索候補の冒頭に上がり、なんか当地で、船越英一郎がテレビドラマで崖のキワに佇むような話のたぐいの「事件」でもあったのかとビビっておりました。