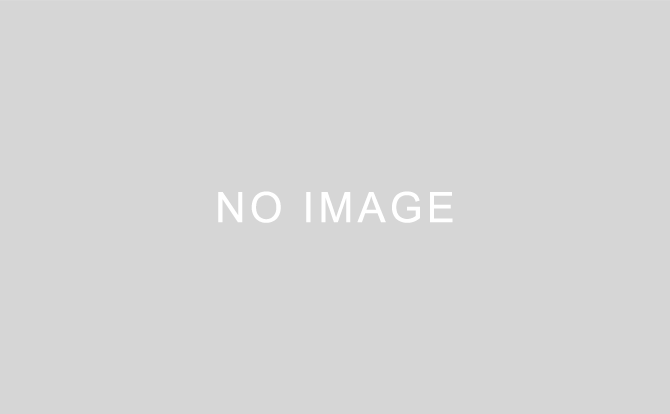本ページの一番下に、本ページのPDF版リンクを設けています。
最終改訂 2024.5.7 改訂内容は改訂履歴ページを参照
住民監査請求を提起する際には、請求書等を所定の方式により提出しなければならない等の形式的要件が存在します。
1 住民監査請求提起の際の形式的要件の概要
地方自治法施行令172条1項は、地方自治法242条1項の規定による必要な措置の請求は、その要旨を記載した文書をもってこれをしなければならないとしており、住民監査請求の提起は文書によることを義務付けています(口頭による提起は不可)。
なお請求書については、地方自治法施行令172条2項および地方自治法施行規則13条により、次の事項の記載が求められています。
・ 地方自治法242条1項による措置請求である旨
・ 請求の要旨
・ 請求者※の住所氏名(氏名は自署/盲人は点字可)
・ 請求日
・ 宛先の監査委員
また、地方自治法242条1項は、監査対象財務会計行為等について「これらを証する書面を添え」監査委員に監査を求めることとされており、いわゆる事実証明書の提出があわせて必要です。
| ※ 地方自治法242条は「請求人」と表記しますが、地方自治法施行規則様式では「請求者」となっています。 |
以上の内容をもつ文書を提出することが、住民監査請求を提起する際の形式的要件となります。
なお、住民監査請求提起時の要件審査(形式的要件)においては、内容に踏む込む必要はなく、求められる書面がそろっており、かつ必要な事項が記載されているかを審査すればよく、実質的・内容的な部分(たとえば監査対象事項が特定摘示されているか等)は、監査(準備)を進める過程で追って審査し、必要に応じて補正要求、請求人への照会調査等で整理することとなります。
2 請求書
(1) 全般的事項
ア 請求書の目的
請求書は、請求人が、どのような財務会計行為等について監査を求めるのか(また、どのような措置を求めるのか。要するに地方自治法施行令172条1項にいう「請求の趣旨」)についての意思表示を行う文書であり、上記の通り住民監査請求の提起は文書主義をとること、請求書が意思表示の本体部分を構成することから、請求書は住民監査請求提起時における必須の文書ということができます。
請求人が請求において明らかにすべきことは、請求人が誰か(住民かどうか:地方自治法242条1項)、監査対象の財務会計行為等は何か(請求人がこれを特定摘示しなければならない:最判平2.6.5民集44.4.719)、そしてこ(れら)の財務会計行為等について必要な措置を求める意思を表示することですので、その内容について住民監査請求を提起するという明確な意思表示を請求書でなすことが求められます(地方自治法242条1項をみる限り、要求する措置内容も請求において明らかにすべき事項とも取れるが、監査委員は請求人の要求措置内容に拘束されず、実際にはこうした内容は書いていても参考事項にしかならない(最判平10.7.3集民189.1)。つまり措置要求の具体内容は任意的な記載事項であり、この内容がどうであろうと請求の形式要件審査には影響しない。それよりは、摘示する財務会計行為等について請求人が違法不当と認める理由を明らかにすることが、効率的な監査実行のためには重要である(「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」4(3)ウ参照))。
なお以上の内容は、請求書でその内容が網羅されている必要はなく、あわせて提出される事実証明書などの資料等の内容を総合して明らかになれば差し支えありません(なお参考:最判平16.11.25民集58.8.2297)。
イ 様式等
請求書は、地方自治法施行規則の様式に沿って、上記1所定項目についての必要な内容が記載されていれば(記載順序等が地方自治法施行規則の様式所定通りとなっていなくとも)、いかなる書式等であっても、形式要件審査上の不備の問題にはなりません。たとえば請求書の標題が「職員措置請求書」(地方自治法施行規則の様式による)でなくとも、内容から住民監査請求提起の意思が判明し、上記の内容が備わっていれば構わないのです。
ウ 請求日の取扱い
住民監査請求の実務においては、いつ請求がなされたかは、とりわけ、住民監査請求の適法要件である、監査請求期間内に請求がなされたかどうかの判断において重要な要素となります(なお、地方自治法242条6項、242条の2第2項3号所定の60日期限の起算日にもなります)。
そして、請求書を提出することが、請求人が住民監査請求を提起するという意思表示となることは、地方自治法施行規則所定の様式に、請求提起の文言があることからも明らかです。
したがって、請求書が提出された場合、仮に補正事項(内容や添付書面の不備等)があったとしても、請求書中に、請求人の人定事項が明瞭に記載され、一定の範囲の監査対象事項が明示されていれば※1、民法97条1項の原則により、その請求書が自治体に到達した日※2、※3が請求のなされた日となります※4。
なお実務的には、請求書が提出された後、監査委員が請求人に発出する文書(陳述日指定通知や補正要求通知等)において、いつ請求書が到達したかを明記することが適当です(単なる受取通知のみの文書や、文書収受日を記載した(押印等)控え請求書の返戻でも、実務上の意味があるものと考えます)。
| ※1 監査請求期間内請求かどうかの判断をしようとすると、①請求人は誰で(特段の事情の判断に必要) ②監査対象とされる財務会計行為等は何か(当然必要な事項) が判断に必要な事項となります。ということは、たとえば請求内容に補正が必要な場合で、後補の結果、請求対象の財務会計行為等が、最初の請求書の内容とまったく異なるものとなるのであれば、それは新たな請求の提起として扱うべきであり、最初の請求書提出の時点で請求があったものとみなすべきではありません。無論、最初の請求書における監査対象事項が不定、未定、またはあまりにも漠然としており、後補による対象事項の摘示事項との連続性が確保できないような場合も同じです。 |
| ※2 住民監査請求については、行政不服審査法18条3項(隔地から郵送等で発信する審査請求書に係る発信主義規定)に相当する条項はなく、地方自治法258条でみられるような行政不服審査法の準用も行われていないことからすれば、民法上の到達主義の原則が適用されることとなります。参照:実務住民訴訟p.57、奥田p.71。 |
| ※3 到達日は、たとえば郵送等された文書を最初に文書担当課で受け取り、それから庁内各部へ配送するような場合は、監査委員事務局に文書が配付された日ではなく、文書担当課で受け取った日と解されるので、注意が必要です。参照:最判昭36.4.20民集15.4.774。 |
| ※4 なお、補正の途上で、当初の請求内容とは異なる財務会計行為等が請求対象としてあげられた場合や、後補により異なる財務会計行為等が請求対象として追加された場合は、その部分については、追加後補された日を請求日とすべきです。監査請求期間内に請求の意思表示を完了するため、とりあえず適当な内容で請求書を提出し、後付けで請求対象を特定するというのであれば、監査請求期間制限の潜脱行為に他ならないし、期間制限の潜脱を目的としない場合であっても、このような場合にまで、変更内容を通常の補正同様に扱い、変更部分の請求日を当初請求日とする理由がないからです。 |
(2) 請求の要旨
地方自治法施行令172条1項により請求書の必要的記載事項とされるところ、ここで、請求人は、監査対象とする財務会計行為等を特定摘示するとともに、その財務会計行為等について住民監査請求を求める理由を示す必要があります。したがって、請求の趣旨の記述内容により、上記の点が明らかにされていなければなりません。
ア 財務会計行為等の特定摘示
監査対象とする財務会計行為等の特定摘示については、最判平2.6.5民集44.4.719で示される通り、請求人の請求時の義務となっています。
したがって、請求書が請求人の住民監査請求提起の意思表示の根幹部分を構成するものとなるため、請求書の請求の趣旨においては(作文技術等の関係ですべてを記述できなくとも)どういった請求対象事項について(たとえば作文例としては、別紙に掲げる財務会計行為について、等により)監査を求めるのかについての記述がなされるべきものと考えます。
ただし、実務的には請求における監査対象事項の特定摘示をどのような方式で行うかについて、最判平16.11.25民集58.8.2297の趣旨を踏まえれば、請求書の内容および事実証明書や添付参考書類等の、請求人が提出する資料等の全体(請求人が提出しないものの、請求人が提示する情報に明示される、監査委員が容易に入手可能な資料等を含む)からその監査対象事項が確定すればよく、また、上記の趣旨からすれば、初期段階で情報が確定していなくとも、監査開始前までに後補されても問題ありません。逆に、それをもってしてもなお請求における対象事項が特定されないのであれば、不適法な請求となります。
イ 理由
理由の記述は、「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」4(3)ウの通り、濫訴を防ぐことや、監査を適切効率的に行うために求めるものです。そして、その内容についてどのような作文、提示方式、粒度を求めるのかについては、特段の規定があるものでもありません。
したがって、請求人の理由に関する意図・問題意識がわかる程度のものであれば、とくに初期段階の要件審査において問題となるものではなく、それ以上に追い込み整理をかける必要はないと考えます。請求人の意図や問題意識等は、追っての調査や陳述時等に確認してもよいことです。
(3) 住所氏名
住所氏名は、請求人を特定することと、請求人が住民であることをその記載内容から確認するために用いるものです。また、氏名に自署を求めるのは、請求が請求人の意思によることを明確にするための手段とされています(盲人は点字でも可)。
したがってその記載内容は、住民要件を確認できるもの、実務的には住民票情報等との照合が可能な内容であることが必要です。
したがって、個人の請求人においてはフルネーム、法人等の請求人においては法人等団体の正式名称とその団体を代表して請求を行う者のフルネームの記載が必要とすべきものです。
なお、個人の請求における氏名への通称記載については、「○○こと▲▲」といったように、本名が併記されていれば、本人の意思表示であることや人定確認が可能であることから、通称利用をもって不適法な請求とする理由はありませんが(参考:東京地判平12.3.23判例地方自治213.33)、通称のみであれば、住民要件の確認が確実に行えない以上、不適法な記載とすべきものです。
住所についても、同姓同名の請求人ではない等、請求人の同定を監査委員において確実とするために、所番地までの記載が必要とすべきです。
(4) 日付
上記(1)イの通り、請求の意思表示が自治体に到達した時点で、請求の提起としての効力を生じる以上、請求書の日付はそれ自体が請求の効力を左右するものとはなりません。
しかし、請求日付について最判平14.9.12民集56.7.1481のような事案も生じ得る以上、総合的な判断材料の一つとして記載されていることが望ましいのですが、ないからといって、請求を不適法とすべき絶対的な理由はないものと考えます。
(5) 宛先
誰に対する意思表示かを請求書中で明確にするためのものですが、請求書全体の趣旨から、当該自治体の監査委員に対する請求の意思が判明すれば、宛先監査委員名がないことをもって請求が不適法とすべき理由はないものと考えます。
3 事実を証する書面
(1) 事実証明書の機能・これを求める趣旨
請求人は監査対象財務会計行為等を特定摘示する義務がある以上、事実証明書がその機能を果たす文書と考えるのが当然です。一方で、弁論主義を採用しない住民監査請求では請求人が主張責任を負うことはないことも踏まえ※、事実証明書の提出を求める目的を、濫訴防止のためとする裁判例があります(名古屋高(金沢支)判昭44.12.22行裁例集20.12.1726※※)。
| ※ 弁論主義とは、民事訴訟(住民訴訟にも適用がある)で採用される原則であり、裁判に必要な事実に関する資料の収集は当事者の権能かつ責任であるとする原則(「法律学小辞典」p.1182)です。主張責任とは、弁論主義がとられる帰結として、ある事実が主張されないとその事実が考慮されず、その結果一方の当事者が不利な判決を受けることになるその不利益のことをいいます(同p.624)。たとえば不法行為での損害賠償請求訴訟(住民訴訟であれば、財務会計職員の違法な財務会計行為による自治体の損害責任追及などで現れるものです)では、法律上の損害賠償責任を発生させる事実(行為者の故意過失、自治体の権利・法益の侵害、損害の発生、因果関係)は、原告が主張しなければ、裁判所はそれに関する事実を認定して判決をすることはできません。 住民監査請求では、下記※※※の通り、弁論主義ではなく職権探知主義が採用されるので、請求人は、監査対象財務会計行為等を特定摘示する以上の主張責任を負わず、監査委員は請求人が提出した資料や自らが職権で収集した情報をもとに、自らの判断で各種の事実の認定を行うことができます。 |
| ※※ 同判決は「(地方自治法242)条が監査請求に当って、右の如き違法又は不当な公金の支出等の事実を証する書面を添えることを要求しているのは、事実に基かない単なる憶測や主観だけで監査を求めることの幣害を防止するにあると解され」る、とする。請求人の監査対象財務会計行為等の特定摘示義務を考慮すれば、妥当な見解と考えます。 |
ただいずれにしても、事実証明書は、監査請求書や他の提出資料と総合して、監査対象財務会計行為等を特定するため重要な資料であり、本質的には監査対象とする財務会計行為等の存在に関する事実の証明を行う機能を有するものです※※※。
| ※※※ 上記のように、事実証明書を求める法の趣旨がいわゆる濫訴の防止にあること、住民監査請求は住民訴訟と異なり弁論主義の適用はないこと(自治体内に分立する執行機関の一つとして、監査委員が(住民による請求を契機として)自治体財務運営適正化のため自浄的な内部的権限を行使するのが、住民監査請求による監査機能の本質であり、本質的に職権探知による監査が前提とされることになる)、監査委員は請求人の措置要求内容に拘束されないことなどを踏まえれば、①事実証明書は、請求人に(民事訴訟のような)主張責任を負わせる趣旨ではない ②事実証明書は、監査対象財務会計行為等の事実を証明するものであり、違法不当性を証明するものである必要はない(参考:大阪高判平17.5.12は「(地方自治)法242条1項が、監査請求について、違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実を証する書面を添えることを求めている趣旨は、事実に基づかない単なる憶測や主観だけで監査を請求することの弊害を防止しようとするところにあるから、「証する書面」については、当該行為が違法等であることを証明するに足りる証拠である必要はなく、監査を求めている根拠として一定の事実があることを示す書面であれば足りると解される」とする)、ということになります。 |
(2) 事実証明書の要求形式・内容の水準
この事実証明書は、その内容に具体性があれば、いかなるもの(手書きメモ、新聞切り抜き、自作資料(参考:新聞切り抜きにつき富山地判平12.11.15、自作資料につき大阪高判平元.1.27行裁例集40.1・2.50))でもよく(参照:行実昭23.10.12※)、結局は、請求書と事実証明書等の資料(請求人が提出しないものの、請求人が提示する情報に明示される、監査委員が容易に入手可能な資料等を含む)により、請求内容としての監査対象財務会計行為等が特定できればよいのです。
またその内容の真実性は、監査により明らかになる事項であるため、要件審査の段階でその点を問う必要はありません(参照:行実昭23.10.30※)。
| ※ 上記行実昭23.10.12は、地方自治法242条1項に該当すべき事実を具体的に指摘すればよく、別段の形式を要しないこと、内容が抽象的であるものは不可とすることを示しています(「抽象的」とは、対象財務会計行為等が特定適示されていないことをいう)。また行実昭23.10.30は、一定の事実証明の形式を備えておれば書類を受け付けるべきであり、内容の真実性については、監査により明らかになるので、それ以前に事実証明書でないと拒絶することは法の趣旨ではないとしています。 なお最高裁判決(最判平2.6.5民集44.4.719等)において示される事実証明書の機能・要求水準も、こうした見解と平仄が合うものです。また、「公財政の管理・運営の民主的コントロールをその狙いとしている住民監査請求制度の趣旨並びに監査委員は財務会計の専門スタッフを擁し調査権限を有することに鑑みると、事実を証する書面添付の要件はこれをいたずらに厳しく解釈すべきものではなく、右要件不備による却下は事実を証する書面が全く添付されていない場合その他これと同視しうる場合など必要最小限にとどめるべきものと解するのが相当である。しかして、前記事実を証する書面は、請求人に対して監査請求にあたって要求されている証拠資料であるから、その性質上、証明に対比して要証事実の真実性につき低度の蓋然性をもって足る疎明資料でよく、その形式を問わないものである」とする裁判例(神戸地判昭62.10.2判例タイムズ671.193)があり、参考となると考えます。 |
また事実証明書が上記の通り、請求対象事項の特定のための資料として機能するのであれば、他の資料によって財務会計行為の存在が明らかとされ、かつ特定もされているのに、さらに関連書類(たとえば支出関連帳票など)を文書公開請求の上で提出するように求める等は必須とは言えないこととなります(そもそも、自治体内部で保管される稟議書等の証拠書類は、監査委員が職権で入手可能です)。
(3) 事実証明書の提出がない場合※
地方自治法242条1項では事実証明書は請求時の必須書類と読め、このことから、事実証明書の提出を当然に請求人の義務とするのが原則なのは明らかですが、一方で事実証明書の機能や要求水準に関する上記の趣旨からすれば、例外的なケースですが、請求書の記載事項のみで請求内容たる監査対象財務会計行為等の存在および特定が可能な場合は※※、事実証明書がないことをもって請求不適法とすることは行き過ぎであると考えます(参考:京都地判昭63.11.9判例タイムズ697.205)。
| ※ 事実証明書が、他の文書から独立した文書である必要はありません。参考:請求書と事実証明書が一体化した文書を適法とした事例として神戸地判平3.11.25判例時報1442.88。 |
| ※※ 典型的な想定例として、たとえば請求書において、○年条例○号改正による給与条例改正により○手当の支給に関する規定が新設され、○年○月から○の職員に対して支給されているが、同規定は、地方自治法204条2項に根拠のない違法無効なものであるので、既に支給された○手当に係る公金の支出について、然るべき措置を求める、との記載がある場合、条例の新設は監査委員にとっては明白(いわゆる顕著な事実)であり、また条例の規定内容をみれば、通常、いつからどの範囲の職員に支給されているのか明らかとなるので、追ってさらに事実証明書を求めなければならない理由は、それだけでは明らかではないものとなります。上記京都地判の事例も同様のものです(自治体三役の退職手当に関する事案において「本件監査請求に地方自治法242条1項所定の書面の添付がないので不適法である旨主張するが、原告は前示のとおり一定の期間内に京都府がその知事、副知事、出納長に支給した退職手当金が無効な退職手当条例・・・に基づくもので法律上の原因を欠く旨を主張して監査請求をしているものであって、右書面の添付がなくとも監査委員ないし京都府において右支出は会計帳簿上自ら特定しこれを明確にし得る性質のものであり、右退職手当条例、地方自治法の条項を知り得ることはいうまでもない。したがって、監査請求の対象を特定させ、濫用を防止するために必要とされる右書面の添付は、前示のとおりとくに書面を必要としない特段の事情がある本件においては、右書面の添付がないからといって、本件監査請求が不適法であるとはいえない」とする)。 |
4 その他の文書等
地方自治法には規定がありませんが、住民監査請求の提起に際し請求人に対し資格証明文書を求めるべき場合があり得ます(参照:奥田p.9、78)。具体的には、請求人の請求資格を証明する文書で、公用請求(住民票の写し、登記事項証明等)では入手できず、請求人に提出させなければ、監査委員が職権でその文書を入手することができないものです。
これらの文書が不備であることは、そのことによってただちに住民監査請求の不適法を帰結するものではありません(請求要件確認のための補完情報となるため)ので、厳密には形式的要件を構成する文書とはいえません。
しかし、請求人が請求資格(要すれば住民要件、団体での請求の場合の団体の代表資格、代理請求の場合の代理権)を有することは、請求の適法要件そのものであるため、こうした文書の提出不備等で要件審査の過程で請求人の請求資格存在の確認ができない(心証を得ることができない)こととなった場合は、所要の追加資料提出を求め、請求人の請求資格存否について判断を行うことが、結局は必要です。
なお、こうした資格証明文書の例としては、次のものが考えられます。
○ 請求人に代理がある場合の、代理権を証明する書類(委任状等)
○ 個人の請求人で、住民票上の住所が提起先自治体を住所としない場合に、提起先自治体の住民たる実質を有することを証明する資料等(到着郵便物や公共料金支払明細等などが考えられる)
○ 法人格のない団体が請求人となる場合に、住民要件や代表者資格を確認するための、規約その他主たる事務所の所在地や代表役員の範囲を示す文書、団体の代表として請求書に表示される個人が団体の代表権を有することを示す文書(代表役員選任総会議事録等)
| 【注】 多くの概説書では、住民監査請求提起の際の請求書等の受付と受理を概念的に分けて説明しています(一般に、受付は文書の収受、受理は形式要件審査が完了して監査委員として請求を受け取るという趣意とされているようです。民事訴訟法における裁判長の訴状審査(同法137条)のようなものを想定しているとも思われます)。 本稿では、意思表示の到達の意味での文書収受概念は考慮していますが、受理概念については考慮していません。 |

足立美術館の庭。足立美術館といえば、タイカンだギョクドーだカンセツだショーエンだロサンジンだとなんでも鑑定団状態のところとして有名ですが、いわゆる童画のコレクションも良いものがあり、昔ここを訪れた際、また娘が赤ん坊頃だったので、林義雄のいかにも愛らしい絵の印刷物を買って、心根の優しいよい子に育つようにとパネルに入れて飾っていたのですが、まあ結果は想像の通りであり・・・(無論それは絵の責任ではなく・・・