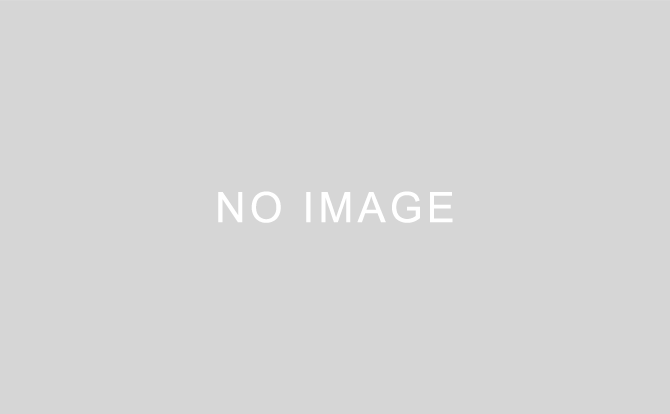本ページの一番下に、本ページのPDF版リンクを設けています。
最終改訂 2024.5.3 改訂内容は改訂履歴ページを参照
このページは、監査請求期間経過後の請求に係る正当な理由に関する裁判例を紹介するページです。
(監査請求期間に関する説明は こちら 、正当な理由に関する説明は こちら。また監査請求期間の裁判例については こちら に別掲)。
正当理由に関する判断は、いくつかの最高裁判例を起点に、経験則の積み上げによる理論的精緻化が図られているため、ここでは最高裁判例・下級審裁判例を、原則としてすべて経年順で並べています。
【注】 参考事例の判決文は、必ずしも原文通りではなく、項目の表記にあうように若干の修正をしていることがあります。
町長が自己の違法行為を隠蔽するため虚偽の内容の町広報を制作しその経費を支出したところ、支出から1年以上経過したものの、住民が同広報の虚偽を確知した翌月に住民監査請求をした場合において、監査請求期間を経過したことに正当な理由があると認めた事例 釧路地判昭47.3.28行裁例集23.3.193
(町長が自己の違法行為を隠蔽するため虚偽の内容の町広報を制作しその経費を支出したところ、その1年10が月後に住民監査請求がなされた)
○ 本件広報発行費がX年3月12日ころ支出されたことは当事者間に争いがないから、本件監査請求(注:X+2年1月26日)は右支出行為のあった日から1年経過後になされたことは明らかであるが・・・認定のようなA駅前通りの改良工事に際して、A町長であった被告がとった措置に関し、原告は当初から疑惑をいだき、原告の発行する「○新聞」紙上でとりあげ、右被告の行為について監査請求をしたこともあること、それに対し被告においても本件広報特集号を発行したが、原告は当時その内容が事実に反する点があるのではないかと考えていたものの、その確信をいだくまでにはいたっていなかったこと、さらに被告は原告を相手として、X年に前記新聞記事によって名誉を毀損されたという理由で損害賠償請求の訴を提起し、右訴については、X+1年1月23日被告は後記工事に伴う潰地およびその代替地に関し、従来町長としてとった手続が土地区画整理法に則ってなされた正式なものでないことを認め今後正式な手続によって処理するよう努力すること等を内容とする裁判上の和解が成立したこと、しかし右努力がなされずにX+1年12月24日の同町議会によって、X+1年度A都市計画中部土地区画整理事業特別会計補正予算が議決されたが、後記認定の潰地補償費について前記特集号にあるような特別会計を設けて事業費に充てられることなく、その一部が被告に還付されることとなり、ここに原告は前記特集号に虚偽の記載があることを確知したことが認められ、右のような経過および本件事案の性質からして本件特集号の内容が虚偽であり、被告が自己の利益のために発行したものであることは一般住民がたやすくこれを知り得なかったことは明らかであるから、本件支出行為があった日から1年を経過した後のX+2年1月26日に監査請求をしたことについて原告に地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるというべきである。
内密の予算外の交際費支出について、支出1年以上経過後にその事実が発覚し、それから1年以内(5か月経過後)に監査請求したことにつき、監査請求期間経過後の請求に正当な理由があるとされた事例 松山地判昭48.3.29行裁例集24.3.290
(事実関係及び経過は下記参照)
○ A町は昭和32年度から昭和38年度まで累積赤字解消のため地方財政再建促進特別措置法の適用を受け、予算につき国および県の行政指導を受ける立場にあったのであるが、被告は本件予算外支出につき国および県あるいはA町議会に報告せず、町執行部以外の者に明らかにしなかったので、予算外支出行為は何ら問題にされることなく、A町議会も昭和32年度から昭和38年度の歳入歳出予算および決算を認めてきたこと、しかるに昭和39年9月の町長選挙のころから同年末にかけて町長選挙に立候補し当選したC町長が以前(昭和32年から昭和34年まで)町長をしていた時代に予算の使い込みをやったとの噂が流れ出したので、町議会の有力議員が調査したところ、被告が町長在任中(昭和35年9月から昭和39年9月まで)に交際費として予算外支出を行っていたことが判明し、一部町会議員も右事実を知るに至ったこと、原告らは同年末にH町会議員からC町長および被告町長の在任中合計800万円余りの予算外支出の交際費があったことを聞き、監査請求しようとしたが、地方自治法を調査した結果監査請求をするには事実証明が必要であることが判明したので、是非公けに出来る資料が欲しいと思っていたところ、昭和40年2月18日同町のI宅でC町長とJ町会議員と原告らが集まった際原告らの質問に対し被告が町長在任中502万7307円の予算外支出の交際費があったことをJ議員が認めたので、原告らは同年5月30日右事実を書面にして本件監査請求に及んだものであること、が認められ、右認定に反する証拠はない。
○ 右認定事実および当事者間に争いのない事実によれば、被告の本件予算外支出(交際費)は極めて内密に行われ、その最終行為が終わって1年以上も経過した昭和39年12月頃にA町の有力町会議員によって予算外支出の具体的な事実が発覚し、原告らもその頃右予算外支出の話を聞き、それから1年以内である昭和40年5月30日に監査請求をしたのであるから、被告が予算外支出をした時から1年以内に監査請求できなかった「正当な理由」があるものと認めるべきである。
浄水場落成式の際招待客から受領した祝い金を約5年水道事業会計に計上せず議会にも報告しなかった件について、議員が異常な雑収益額に気付き質問したことから上記事実が明らかになり、その数日後に、祝い金の費消有無等を調べ費消ある場合はその補填させる措置を求める住民監査請求をした場合において、監査請求期間経過後の請求に正当な理由があるとされた事例 浦和地判昭53.3.6行裁例集29.3.205
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 市長でありかつ同市水道企業管理者であった被告は、X年度の決算等においては本件のいわゆる祝い金の額、保管方法、使途等についてはもちろん、これを水道企業が受けとったこと自体をも市議会に報告しなかったので、当時は祝い金やこれからの支出について市議会で問題となることもなかったこと、そして、X+5年6月に至って右祝い金の残額及び銀行預金の利子の合計33万3086円を水道企業の雑収益として会計に組み入れたこと、市議会議員である原告は、同年9月の定例市議会において事前に配布された資料である水道部事業試算表中の同年6月30日までの雑収益が、通常は2、3万円であるのに、90万円余と異常に多額になっていたことから、これに疑問をもって質問をしたところ、被告らの答弁があいまいであったため、更に質問をするうち、水道企業がX年11月11日○○浄水場落成式当日に招待客から多額の祝い金を受けとっていながら、X+5年6月までこれを会計に計上しなかった事実が明らかになったこと、そこで、原告は同年9月18日監査委員に対し、受けとった祝い金の総額、計上の遅れた理由、費消の事実の有無を調べて、費消の事実がある場合にはその補填をさせる等の措置を求めて監査請求をしたものであること、なお、原告は右落成式には出席したが、これにひき続いて行なわれた「○○亭」での宴会には招待されず、出席しなかったこと、当日水道企業が祝い金を受けとったことに気づかなかったことが認められ、右認定に反する証拠はない。
○ 右認定事実によれば、被告による後記認定の本件予算外支出は当時はごく一部の市の関係者以外には知られておらず、X+5年9月になってはじめて祝い金を受けとったことが明らかにされたが、原告はその数日後に被告の予算外支出があったのではないかとの疑念を抱いて監査請求をし、その結果、本件予算外支出の事実が明らかになったのであって、原告としてはできうる限りすみやかに監査請求をしたものと認められるから、被告の本件予算外支出の時から1年以内に監査請求ができなかったことについては正当な理由があるものというべきである。
町会議員が支出から1年経過後に住民監査請求をした場合において、当該支出が議会の議決を経ているという事情を踏まえれば、監査請求期間経過後の請求に正当な理由が存しなかったとされた事例 大阪地判昭54.2.28判例時報930.63
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 本件の公金支出がなされたのはX年5月14日であることが認められ、他方、原告らが本件公金の支出について地方自治法242条1項による監査請求をなしたのがX+1年6月9日であることは原告らの自認するところであるから、右監査請求が同条2項本文に定める1年の期間経過後になされたことは明らかである。
○ そこで、進んで右1年の期間内に監査請求がなされなかったことについて同条2項但書に定める正当な理由が存したか否かについてみるに、右正当な理由が存したと認めるに足りる証拠はなく、かえって・・・によれば、本件公金の支出がA町の町議会の議決を経てなされていること、原告○が当時A町の町会議員をしていたことが認められ、右事実によれば、原告らが右1年の期間内に本件公金の支出に関し監査請求をしなかったことについて正当な理由が存しなかったことが窺われる。
○ したがって、原告らの本訴請求は、適法な監査請求の前置を欠いた不適法なものといわざるをえない。
一部事務組合がした公金の支出に関する住民監査請求が地方自治法242条2項本文所定の監査請求期間を経過した後にされた場合につき,組合が決算認定手続の段階において公金の具体的支出先,支出年月日及び支出目的を明示しなかったため,原告らにおいてこれを知ることができなかったという事情があるだけでは,同項ただし書にいう「正当な理由があるとき」に当たらないとした事例 岐阜地判昭58.11.14判例時報1107.54
(事実関係及び経過は下記参照)
○ ・・・各支出に関してその支払完了の日から1年以内に監査請求をしなかったことについて、原告らに(地方自治)法242条2項但書所定の「正当な理由」があったか否かの点について検討することとする。・・・なるほど、(一)原告らは・・・日ころ、初めて、訴外組合の公金が上級行政機関の公務員に対する接待のために支出されていることを知るに至ったこと、(二)訴外組合の議会で行われた決算認定手続の全過程においても、公金の支払先、支払年月日、支払目的等に関する具体的な説明がなく、わずかに予算科目に対応する収支の報告がされるにすぎないような状況であったこと、以上の事実を肯認することができる。しかしながら、右(二)のごとき状況は、決算認定手続として通常かつ標準的なあり方であるというを妨げず、本件においては、被告を含む訴外組合の関係者が前記各金員支出の事実をことさらに隠蔽したというがごとき特段の事情の存在を窺わせるに足りるような証跡は毫もこれを見いだし得ない。そして、以上説示のような諸事情をいわゆる監査請求期間を公金支出等の行為の終わった日から1年と定め、そのことによって地方公共団体の行政運営の安定性を図ることを所期しているものと解せられる法の趣旨と対比しながら合理的かつ利益衡量的に考察すると、単に決算認定手続の段階で公金の具体的支出先、支出目的が明らかにされず、そのために原告らにおいてこれを知り得なかったという事情が存在するにすぎない本件については、原告らにその主張のごとき法242条2項但書所定の「正当な理由」があったことを是認することは、とうてい不可能であるというのほかはない。
請求人が対象支出から11か月後には当該支出を知っていたという事情下において、当該支出から1年4か月後になされた住民監査請求には、監査請求期間経過後の請求に正当な理由は存しないとされた事例 富山地判昭59.2.3判例地方自治2.42
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 本件公金の支出がX年12月24日になされ、本件監査請求が、本件公金の支出の日から1年を経過した後であるX+2年3月23日になされたことは当事者間に争いがない。
○ 地方自治法242条2項但書は1年の期間を徒過した場合にも、「正当な理由があるとき」は、住民監査請求をなし得る旨規定しているところ、ここに「正当な理由」とは監査請求の対象となる当該行為を知ること、監査請求をなすことにつき、客観的障害がある場合、即ち当該行為がきわめて秘密裡に行われ、1年を経過した後初めて明るみになったとか、天災、地変等で交通杜絶になり請求期間を徒過した場合などを指し、監査請求当事者に関する主観的事情を含まないと解すべきである。そして本件公金の支出は、その議案がA町議会においての審議、議決を経てなされたものであることは当事者間に争いがなく、右議案につき具体的説明がなされなかったからといって本件公金の支出が秘密裡に行われたものとはいえず、その他本件全証拠によっても本件公金の支出が秘密裡に行われたとの事実は認められない。又原告主張のその余の事由は右「正当な理由」には該当せず、かつ本件全証拠によるも、他に原告に右の客観的障害による前同条項所定の「正当な理由」が存在するとの事実を認めるに足りない。
○ かえって、原告がX+1年11月24日A町決算審査特別委員会において本件公金の支出を知ったことは原告の自認するところであり、したがって、本件公金の支出がなされたX年12月24日から1年以内であるX+1年12月24日までに監査請求が可能であったことが認められ、原告に前示「正当な理由」が存しないことは明らかである。
架空接待が疑われる支出が議会で取り上げられ、翌日新聞報道もされた事案について、監査請求期間経過後の、上記報道の5か月後に監査請求したところ、新聞報道があった日以後監査請求期間が経過するまでの任意の時期に新聞記事を事実を証する書面として添付の上監査請求手続をとることが可能であったのだから、監査請求期間経過後の請求に正当な理由がないとされた事例 大阪地判昭61.8.7判例タイムズ618.54
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 大阪府水道部は、地方公営企業法に基づき大阪府が設置、経営する水道事業及び工業用水道事業に関し、水道企業管理者の権限に属する事務を処理するために設けられた内部組織であるところ、本件会計年度当時同部の事業遂行上必要な関係諸機関等との会議に要する経費は、一般の営業費用である総経費中の会議費、第7次拡張事業費の事務費中の会議費のほかに、第7次拡張事業費の工事費中の工事諸費ないしそのうちの会議費から支出できることになっており、特に右工事諸費は第7次拡張事業の進行に附随して必要となる地元折衝や関係先との調整等にあてるための費用として認められたもので、2487万余円の多額に達していた。同水道部が右会議に要する経費を支弁する際は、総務課長の統轄のもと、当該会議の主管課長において会議開催に先立ち、会議の目的、日時場所、出席者名、債権者名(支出先)、経費支出予定額等を記載した経費支出伺を作成して、所定の決裁を受けることになっており、その支出手続は、同部会計規程に従い、会議開催後債権者からの請求に基づき会議の主管課長において事実の確認を行った上、所定の決裁を受け、支出伝票に経費支出伺、債権者の請求書を添付して総務課長経由で金銭出納員に送付し、金銭出納員がこれを審査し、支出決定をして小切手を振出すこととされていた。しかしながら、本件(一)の支出のうち別表(一)の支出や本件(二)の支出については、支出伝票発行に際し請求書と経費支出伺との形式的な照合が行われたに過ぎず、会議が経費支出伺の記載どおり現実に行われたか否かの確認がされていなかったことから、経費支出伺の記載内容(別表(一)、(二)記載の日時場所、出席者名が記載されていたものと推測される。)自体にも疑惑を生じさせるものがあった。しかるところ、何らかの経路で別表(一)記載の支出につき経費支出伺の記載内容を知るに至った一府会議員がX年11月18日及び同月24日に開催された大阪府議会決算特別委員会において右疑惑を取上げて質疑を行い、各会議に出席したとされている他の公共団体職員中には現実に出席していない者がいる事実を指摘し、右支出が架空名義接待による違法支出であり、ひいては第7次拡張事業費の工事費中、工事諸費ないしそのうちの会議費から支出された総額2487万余円の使途も不明確であるとして、水道部当局者を追及した。これに対し当局側は、別表(一)記載の日時場所での会議につき債権者に同表記載の金額を支払ったことは認めたが、出席者の氏名は事柄の性質上答弁を差控えたいとして明らかにせず(暗に架空接待の事実を認めたものと解される。)、右2487万余円は第7次拡張事業にかかる工事の執行に必要な地元折衝あるいは関係先との調整のための会議開催にあてたものであるとの抽象的な答弁を繰返すに止まった。右決算委員会の模様は、同月19日及び25日付の読売、朝日、毎日の各新聞に「水道部カラ接待」、「府水道部がぶ飲み」、「多過すぎる会議接待費」(以上19日付)、「架空接待相次ぎ8件」「工事費名目で飲み食い」、「水道部のカラ出張(接待の誤記)追及」(以上25日付)等の見出しをつけて大々的に報道された。右記事の中には、会議に出席したとされている他の公共団体職員の一人が接待を受けたことを否定している談話や、水道企業管理者の会議費の使途は公表できないが今後はできるだけ節減に努め、批判を招かないようにしたいとの談話も掲載されている。
○ 原告らはいずれも、市民の立場に立って政治、行政を監視し、不正、不当な政治、行政を是正することを目的として、近畿各地に居住する趣旨賛同者により○年12月に設立された「市民オンブズマン」の会員であるが、同会はX+1年4月の大阪府知事選挙に際し、活動の一環として本件(一)の支出問題を取り上げることとし、水道部職員や大阪府会議員等との接触によって、別表(一)の会議に出席したとされる者の名簿や前記決算特別委員会の速記録の手書き原稿等を入手し、事案の内容を検討した結果、大阪府下に居住する原告らが弁護士1名と共に同月28日本件(一)の支出につき監査請求をした。なお、監査請求書に添付すべき事実を証する書面としては、右名簿や速記録原稿の提供者が公表を望まなかったために添付せず、前記新聞記事のうち主要なもの3つのコピーを添付するに止めた。
○ 次いで同年10月6日に開催された大阪府議会本会議で一府会議員が新たな資料に基づき、本件(二)の支出につき前同様架空接待の疑いがあるとの質疑をしたが、水道部当局者は会議接待費は機密的な要素を含んでおり、内容の公開は差控えたい旨答弁した。この模様は翌7日付の読売新聞に「架空接待また発覚、大阪府水道部が128万円」との見出しで報道された。そこで、原告らは何らかの経路で右支出にかかる会議に出席したとされる者の名簿を入手し、前同様の動機から同年11月6日右支出についても監査請求をしたが、監査請求書には右新聞記事のみを事実を証する書面として添付した。
○ ところで、(地方自治)法242条2項本文が、住民監査請求は当該行為のあった日又は終った日から1年を経過したときは、これをすることができないと定めているのは、監査請求の対象となる行為の法的効果を早期に確定させることにより、地方公共団体の行財政運営の安定を図ろうとする趣旨に出たものと解される(右期間の始期が客観的に定められており、請求者の知、不知を問わないこととしているのもそのためである。)。そして、同項ただし書において、正当な理由があるときはこの限りでないとして、右期間制限の排除を定めているのは、交通途絶等による客観的障害が存する場合のほか、当該行為の種類、性質、態様、行為後の事情その他諸般の事情により、注意深い住民が相当の方法により調査しても当該行為の存在を知ることができなかったために、住民監査請求を認めなければ著しく正義に反することとなる場合には、地方財務会計についての民主的コントロールを十全ならしめるべく、法的安定性を犠牲にしても期間経過後の監査請求を許容しようとする趣旨であると解され、従って正当な理由があるときとは、右に述べたような例外的な場合に限られるというべきである。
○ 本件についてこれを見るに、前記認定のとおり、本件(一)の支出に関し大阪府議会決算特別委員会でなされた質疑応答に基づき、右支出のうち別表(一)記載の合計134万90円の支出については架空接待の疑いがあることが大々的に新聞報道されたのであるから、地方財政につき多少とも関心のある注意深い住民にとっては、右新聞記事によって架空接待にかかる右支出の適法性につき疑問を抱くのは勿論のこと、偶々判明した氷山の一角に過ぎない右134万90円だけでなく更には工事諸費の総額2487万円の支出についてもその使途に問題があることを容易に認識することができたものと判断される。従って、「市民オンブズマン」なる民間の行政監視組織の会員である原告らとしては、右新聞報道があったX年11月下旬以後、監査請求期間が経過するまでの任意の時期に、右新聞記事を事実を証する書面として添付の上、本件(一)の支出につき監査請求手続をとることが可能であったものであり、その他前記例外的な場合に当る事情は本件全証拠によっても窺えないから、結局原告らには本件(一)の支出についての監査請求の期間徒過につき正当な理由は存しないというべきである。
○ なお、原告らが新聞報道のみでは本件(一)の支出の違法不当性を立証できないと判断したとしても、かかる主観的事情によって、正当な理由ありとすることができないことは前記説示からして明らかである。また、本件(二)の支出については、これに関する府議会本会議での質疑応答と新聞報道がなされたのは監査請求期間の経過後のことであり、新聞記事には右支出の支出科目まで明記されなかったが、原告らが把握した支出の内容は別表(二)記載のとおりであって、本件(一)の支出のうち別表(一)記載の支出と全く同じ態様のものであるから、水道部所管の第7次拡張事業費に関連して架空接待の疑いがある支出として、本件(一)の支出に包含され、その一部をなす別表(一)記載の支出のいわば追加分に相当することが自ら明らかである。従って、既に本件(一)の支出につき監査請求をしていた原告らにつき前記のとおり右監査請求期間の徒過に正当な理由がない以上、本件(二)の支出についての監査請求も、右期間徒過に正当な理由がないというべきである。
架空接待に関する住民監査請求について、違法な支出の疑いを報じる新聞報道から約1か月後になされた請求は、財務会計行為1年経過後の請求についての正当な理由があるとされた事例 大阪地判昭63.2.26判例タイムズ675.140
(事実関係及び経過の詳細は省略)
○ ・・・X年11月の府議会の決算特別委員会でも、翌日の新聞報道でも、事務費中の会議費の総額が770万余円であることは明らかにされたが、その支出の具体的内容に触れる質疑応答、報道は一切なく、したがって、また、架空名義接待による違法支出の有無などについての質疑応答、報道もなかったのであって、控訴人らは、X+1年10月の府議会本会議の質疑応答の内容を伝える翌日の新聞報道などにより、初めて、・・・支出の具体的内容及びそれが架空名義接待であり、実際にはこれと別の内容の違法な支出が存在する疑いがあることを知ったということができ、注意深い住民が、X年11月の府議会での質疑応答の内容を伝える新聞報道によって・・・支出の具体的内容を知り、架空接待の疑いを抱いたことから、・・・支出の具体的内容を知り又は知ることができたとか、それにつき架空接待の疑いを抱き又は抱くことができたとか、実際の支出の有無を知ることができたとはいえず、これは、控訴人らが「市民オンブズマン」なる民間の行政監視組織の会員であることを考慮しても同様である。そして、前記のとおり、実際の支出が外部に全く明らかにされず秘密裡になされ、支出関係の書類の閲覧が認められず、注意深い住民を基準に考えても前記の事情を知りえなかった状況において、控訴人らが右新聞報道から約1カ月後に監査請求をしたことに照らせば、期間徒過に法所定の正当な理由があるということができる。
【最高裁判例】 地方自治法242条2項の「正当な理由」の有無は、住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたかどうか、また、当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断する 最判昭63.4.22集民154.57
(秘密裡の予算外支出が4年後の議会質問で突如発覚し4か月後に自治体広報誌に掲載された。請求人はこれを見て真相の解明がされると期待していたが、その約3か月後の新聞報道ではじめて上記支出の概要を知り、結局請求人は広報誌配布の4か月後に住民監査請求を行った)
○ 地方自治法…242条2項本文は、普通地方公共団体の執行機関・職員の財務会計上の行為は、たとえそれが違法・不当なものであったとしても、いつまでも監査請求ないし住民訴訟の対象となり得るとしておくことが法的安定性を損ない好ましくないとして、監査請求の期間を定めた。しかし、当該行為が普通地方公共団体の住民に隠れて秘密裡にされ、1年を経過してからはじめて明らかになった場合等にも右の趣旨を貫くことが相当でないことはいうまでもない。そこで、同項但書は、「正当な理由」があるときは、例外として、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過した後であっても、普通地方公共団体の住民が監査請求をすることができるとしたのである。したがって、右のように当該行為が秘密裡にされた場合、同項但書にいう「正当な理由」の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたかどうか、また、当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものといわなければならない。
○ 町の住民にとって、遅くとも「町議会だより第○号」が配布されたX年10月中旬までには、町長である上告人が…事業の用地買収の補償金として町の公金○円を違法又は不当に支出したことが明らかになった筈であり、被上告人ら町の住民がこの時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって法242条2項但書にいう「正当な理由」の有無を判断すべきところ、被上告人は右の時から4か月余を経過したX+1年3月8日になってはじめて本件監査請求をしたのであるから、本件監査請求が本件支出のあった日から1年を経過した後にされたことについて同項但書にいう「正当な理由」があるということはできない。
○ なお、町議会が法100条に基づく調査を行うため…特別委員会を設置し、同委員会が本件支出の調査を進めていたとしても、そのことは監査請求ないし住民訴訟の提起とはなんらかかわりがないから、被上告人が同委員会の調査の動向を見守っていた故をもって、本件監査請求について法242条2項但書にいう「正当な理由」があるということはできない。また、町監査委員が本件監査請求について誤って法242条2項但書にいう「正当な理由」があるとしてこれを受理し、監査を行ったとしても、そのことによって、監査請求の期間を徒過した本件監査請求ひいては本件訴えが適法となるものではないことも当然である。
○ 以上によれば、本件訴えは、適法な監査請求を経ていないから、不適法な訴えとして、これを却下すべきものである。
都道府県の三役の退職金支給に対する監査請求期間経過後の住民監査請求について、三役の退職金支給はことさらに隠蔽されたものではなく、退職事実も新聞報道されている等の事情からすれば、請求期間経過後の請求について正当な事由があるとはいえないとされた事例 京都地判昭63.11.9判例時報1309.79
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 被告らのうち支給日の最も遅い被告Aに対する退職金を支給したX年1月29日から数えても・・・原告の本件監査請求が提出され受付られたと認められるX+1年4月15日までに既に地方自治法242条2項本文所定の「当該行為のあった日又は終った日から1年」を経過していることが明らかであり、同条項但書の「正当な理由」がない限り、適法な監査請求とはいえない。
○ 原告は右の「正当な理由」があると主張するけれども、同条項の「正当な理由」とは、注意深い住民が相当の方法により探索しても客観的に当該行為の探知が不可能であった場合を指し、本件退職金の支給はこれがことさらに隠蔽されたものでなく、府において予算に計上したうえ、被告らのいわゆる三役に対して本件退職金が支給されたもので、被告らが退職したことは新聞報道もなされていたこと、そして、被告らに対する退職金の支給の存在自体を知りうべきものであったことは、その旨の被告らの主張を原告において何らの反論もしないことなど弁論の全趣旨に照らし明らかであるから、原告に「正当な理由」があるとはいえず、他にこれを認めるに足る的確な証拠がない(最判昭和63年4月22日判例時報1280号63頁参照)。なお、原告は本件退職手当条例7条の無効につき、住民、法曹も無関心で、これが公的に無効と判断されていない以上、原告がこれに気付くのが遅れたことに「正当な理由」がある旨をも主張するが、法令の違法、無効の判断の難易をもってここにいう「正当な理由」を判断することはできない。
ヤミ給与支給に対する住民監査請求について、請求人が当該自治体の議員であり、議員として相当の注意力をもって調査等をしたら、条例で定める以上の一時金支払いの予算上の措置がどうなっているのか、ひいてはA市が条例に違反する手当又は給与の支払いをしたかは、監査請求期間終了の相当以前の段階で容易に知ることができたので、監査請求期間徒過について正当な理由はないとされた事例 大阪高判平成元.1.27行裁例集40.1・2.50
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 「正当な理由」の有無は、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査した時に客観的にみて当該行為を知ることができたかどうか、また、当該行為を知ることができたと解される時から相当の期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものであるが(最高裁判所昭和62年(行ツ)第76号損害賠償請求事件・昭和63年4月22日第二小法廷判決参照)、本件にあっては、被控訴人はA市議会議員の公職にあったばかりか、昭和51年度支出の予算及び決算に関する審議と議決に加わったものであるから、かかる特段の事情を前提として、被控訴人がA市議会議員として、相当の注意力をもって調査した時に客観的にみて当該行為を知ることができたかどうか、また、当該行為を知ることができたと解される時から相当の期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきである。
○ 確かに、右各審議と議決の際、A市当局が書面や口頭により本件支出の内容、目的及び相手方等について具体的な説明はしなかったものであるから、審議や議決に加わったことの故に、直ちに本件支出の実質を知ることができたと解することは困難である。しかしながら、被控訴人は、一般住民と異なり、(地方自治)法98条ないし100条に規定する各種権限を有する普通地方公共団体の議会の議員であり、補助参加人発行の「A町職ニユース」等を読むことにより、補助参加人がA市当局に対し、条例で定める以上の一時金(手当又は給与)の支払いを要求し、A市がこれに応じて条例で定める以上の一時金を支払っていたことを認識していたものであるから、市議会議員として相当の注意力をもって調査等をしたならば、条例で定める以上の一時金支払いの予算上の措置がどうなっているのか、ひいてはA市が条例に違反する手当又は給与の支払いをなし、本件支出の予算上の根拠が款項目各19節「負担金補助及び交付金」であったことなどを、遅くとも昭和51年度支出の終了後法242条2項所定の1年を経過したX年4月19日の相当以前の段階において容易に知ることができたと解されるから、右「正当な理由」があるとは解し難い。
○ 加えて、被控訴人は、X年3月7日B収入役からの説明やメモ・・・の手交を受けたことにより、本件支出の実質を知ったものであり、また、同月30日A市議会で当局者から答弁を受けた時点からでも、直ちに手続をすれば、右所定の期間内に監査請求をなしえたというべきである。被控訴人は、法242条1項所定の「証する書面」として添付する定例会会議録の完成を待っていたと主張するけれども、右「証する書面」は、特段の要件や形式を要求されているものではなく、当該行為を具体的に記載しているものである限り、被控訴人作成の文書で足るし、メモ・・・が存在したことからすれば、右所定の期間内に監査請求することを妨げる事情は存在せず、この観点からも「正当な理由」の存在は認め難い。
職員の勤務時間が条例所定のものより短縮されていたのに給与の減額がなされていなかったことに対しての住民監査請求について、市広報で市役所の執務時間が短縮されたとの広報があったとはいえ、執務時間の短縮が職員の勤務時間の短縮につながるものかどうかは職員の勤務状態についての正確な実態の把握なしには軽々に判断し難い事柄であるので、仮に市民が執務時間の短縮を知り又は知り得たものとしても、それだけのことから直ちに勤務時間の短縮を知り又は知り得たことにはならず、監査請求期間以後になされたことに正当な理由があるとされた事例 東京高判平成元.4.18判例地方自治57.10
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 本件監査請求は、右のとおり被控訴人らのした違法な給与支給行為をその対象とするものであるが、控訴人はX年3月以降違法な給与支給が継続して行われているとして、右支給された給与につき損害賠償を求めているのであるから、右のうち監査請求のあったX+4年9月13日(この事実は当事者間に争いがない。)から遡る1年前の日以降に支給された給与に関する損害賠償請求部分は法定期間内にされ、したがって監査請求を前置したものとして適法であるが、それ以前に支給された給与に関する損害賠償請求部分、すなわち被控訴人Aに対する請求についてその全部、被控訴人Bに対する請求について同被控訴人が市長に就任したX+2年12月25日から監査請求1年前の前日であるX+3年9月12日までの間に支給された給与に関する損害賠償請求部分は、いずれも法定期間を徒過するについて正当な理由がない限り、適法な監査を経ないものとして訴訟要件を欠くに至るものとなる。そこで、正当な理由の有無について検討する。
○ X+4年6月頃某市で職員に対し条例に基づかない給与の支給をしたこと(いわゆる闇支給)が発覚し、これが発端となって各地方公共団体でも取沙汰されるようになった。控訴人は、当時市の主権者の会の代表をしていた関係から、この問題を取り上げ、その頃から市職員の勤務条件についての実態調査を始めた。控訴人は、右調査の過程で市の例規集にあたって職員の勤務時間を調べてみたところ、条例の定める勤務時間と実態との間に食い違いのあることに気付いた。
○ そこで、控訴人はX+4年8月頃市の助役、人事課長等に面談して、右の点の疑義を質したところ、市長決裁により職員の執務時間を短縮したもので問題はないとの説明を受けた。控訴人は、右の際に人事課長から「現行勤務時間の取扱について」と標題のある市長決裁文書の写しの交付を受けたが、右の標題等から市長が条例の定める勤務時間を市長決裁により違法に短縮したものと理解し、さらに調査をすすめ、勤務時間の違法短縮後、本来減額の措置がとられるべきものであると考えるのに、減額されないまま正規の勤務時間どおりの給与支給が継続している実情を知り、右の非違を正すべく監査請求をするに至った。
○ 控訴人は、X-1年当時市内の町内会「○自治会」の会長をつとめていた。市の広報紙のX-1年11月1日号に「市役所の執務時間がX-1年11月11日からは午前9時から午後5時までとなる」旨の記事が掲記され、その頃右広報紙が各自治会長を通じて各家庭に配布された。X-1年11月頃市庶務課で右広報紙の記事と同内容のポスターが作成され、各自治会長の手を経て町内会の掲示板に掲示された。X-1年11月20日付市公報第○号には、市達第2号として市長名で同年11月11日から執務時間の開始を午前9時からと変更する旨公告された。
○ しかしながら、これら広報紙にせよ、ポスターにせよ、いずれも従来から行われていたいわゆる冬時間帯(後記のとおり)がX-1年11月から実施されることを市民に知らせたものにすぎないし、かつ、それらは土曜日の執務時間の終了時刻には触れていないのであるから、これらがX年3月以降執務時間を1年を通じて短縮する旨公示したものではなく、したがって、控訴人を含む市民がこれらの文書から執務時間の短縮を知り又は知り得たものということはできない。また、右決裁により執務時間が短縮された結果、X年3月以降も冬時間帯が解除されることなく、午前9時の執務開始が継続されたのであるから、市民はまもなく市役所の執務時間が1年を通して短縮されたことを知り又は知り得たとみる余地がある。しかし、後記のとおり勤務時間と執務時間とは本来異なる概念であり、両者は相互に全く無関係ではないが、その関係はそれほど明確なものではないから、執務時間が短縮されたとしても、それが勤務時間の短縮につながるものかどうかは職員の勤務状態についての正確な実態の把握なしには軽々に判断し難い事柄である。したがって、仮に市民が執務時間の短縮を知り又は知り得たものとしても、それだけのことから直ちに勤務時間の短縮を知り又は知り得たことにはならない。
○ 右のとおりであるから、控訴人が監査請求期間を経過させたことについては、正当な理由があるものと認めるのが相当である。
公然となされた支出であっても、職員が金銭を騙取する目的でこれをなし、違法・不正な支出である事実がことさら隠蔽されている場合にあっては、一般住民において、当該支出がなされた事実に基づいて或いはこれを端緒として、右支出が違法・不正なものであることを知ることは、特段の事情がない限り不可能であるといわざるを得ず、新聞報道後1か月強でなされた住民監査請求には、監査請求期間後の請求についての正当な理由があるとされた事例 大阪高判平成3.5.23行裁例集42.5.667
(事実関係及び経過は下記参照)
○ ・・・によると、右各支出は、市の行う土地建物の買収に関して、補償金として支出する理由がなかったのに、右買収事務を担当していた市の職員においで、架空の人物であるKなる者が当該建物において中華そば店を経営している旨の・・・、或いは、既に買収済の土地について借地権者との間で補償契約が締結された事実がなく借地権者に支払う意思もなかったのに、右契約が締結された旨の・・・、それぞれ虚偽の事実を記載した書面を作成して補償金支払の必要があるかのように装い、支出を担当する同市職員をしてその旨誤信させて、支出決定、支出命令をさせたうえ、通常の財務会計上の行為として支出された(なお、その審議に際して、右各支出命令は市議会の委員会に提示されたが、右各支出決定の提示はなかった。)ことが認められる。
○ よって、検討するに、公然と行われた予算内の支出行為について、それが違法或いは不正な支出であることを主張して住民が監査請求をする場合は、通常は当該行為後直ちにこれをすることが可能であるから、同条2項本文所定の期間の制限に服すべきことはいうまでもない。しかしながら、本件の場合のように、形式的には公然となされた予算内の支出行為ではあっても、それが単なる予算項目の流用等財務・会計法規違反の支出行為にとどまらず、その実質は職員において内容虚偽の文書を作成して地方公共団体から金員を騙取する詐欺行為に当たるなど刑事上の処分の対象になる場合のようにその違法性が著しく、違法・不正な支出である事実がことさら隠蔽されている場合にあっては、通常の予算内の支出行為とは事情を異にし、一般住民において、当該支出がなされた事実に基づいて或いはこれを端緒として、右支出が違法・不正なものであることを知ることは、特段の事情がない限り不可能であるといわざるを得ない。けだし、右のような著しく違法な方法により支出行為がなされる場合には、外観上は通常正規の財務会計上の支出行為の形式を採り、地方公共団体の内部においても特定の職員を除きそれが実質的に違法のものと知ることはできないのが通常であり、いわんや一般住民において当該行為について監査請求の権利を行使することを期侍することは不可能もしくは著しく困難といわざるを得ないからである。
○ したがって、このような場合にあっては、当該支出が違法・不正なものであることがことさらに隠蔽されているのであるから、右支出は秘密裡になされた場合に該当するものとして、特段の事情がない限り、住民の監査請求が同条2項本文所定の期間を徒過してなされても、直ちにこれを不適法ということはできず、住民が相当の注意力をもって調査したときに、客観的にみて、当該行為が違法或いは不正であることを知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求がなされていれば、同条2項但書所定の「正当な理由」があるときに該当し適法なものと解すべきである。
○ ・・・によると、本件各支出行為は、その形式の上においては、正当な支出と同様に、所定の支出命令、支出決定を経て、通常の財務行為の外観を装ってなされたものであって、当該支出決定、支出命令をした市の担当職員でさえこれが違法、不正な支出であることを知らなかったものと認められるから、一般住民において、右各支出行為自体に基づいて或いはこれを端緒としてこれらが違法・不正なものであることを知ることは、いかに注意力を尽くしたとしても不可能であったというべきである。そして・・・によると、控訴人らは、いずれも新聞報道によって、請求原因・・・の行為についてはX年5月30日に、請求原因・・・の行為については同年6月5日に、それぞれ違法な支出がなされたことをはじめで知ったものと認められるところ、市の一般住民において相当の注意力をもって調査した場合、本件各行為が違法、不正な支出であることを右各期日よりも前に知ることが可能であったと認めるべき証拠はない。そうすると、右各期日から41日或いは35日後である同年7月10日になされた本件監査請求は、所定の期間を徒過したことについて正当な理由があったとみるべきであって、適法なものと認められる。
収入役当時の現金忘失について賠償命令を受けていた者が新町長となり、自己に対する右賠償命令に関する事項について引継を拒否した場合においては、当該拒否がなされるまでは住民が監査請求する客観的必要性がなく、そのような特段の事情の存在が認められる以上、監査請求経過後の請求に係る正当な理由があるとされた事例 那覇地判平成4.3.3行裁例集43.3.287
(事実関係及び経過は上記参照)
○ (地方自治)法242条2項但書にいう「正当な理由」の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである。本件についてこれをみるに、原告らの主張する被告による本件亡失行為については、亡失金の存在自体当時公表される財政に関する情報のみでは住民らが知り得る性質のものではなく、更にこれが被告の行為によるものであるかどうかは○年2月16日になされた知事の前記裁決により初めて問題となったもので、原告ら住民においてもその時点で初めて知り得たことということができる。
○ ところで、前述のとおり、右裁決後町長Aは監査委員に監査を求め、現実に、被告に対し法243条の2第3項による賠償命令を出していたのであり、本件訴訟が町に代位して被告に対し損害賠償を求めるものであり、本件監査請求も右損害の補填に必要な措置を講ずべきことを求めるものであることからすれば、法的には賠償命令とは別個に原告らによる監査請求及び住民訴訟が可能であったとしても、新町長となった被告が○年5月15日に自己に対する右賠償命令に関する事項について引継を拒否するまで、原告らにおいて監査請求をする客観的必要性はなかったものというべく、本件の場合、かかる特段の事情が存在したものと認められる以上、同年6月24日に初めて本件監査請求をなしたことには「正当な理由」があるというべきである。
監査委員事務局の誤った指導に基づき、公然となされた議会海外視察旅行経費支出に対する監査請求期間を経過した後になされた住民監査請求について、監査請求経過後の請求に係る正当な理由があるとされた事例 浦和地判平成4.3.30判例時報1455.88
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 本件公金支出がされたのはX年10月16日であり、原告らが監査請求の申立てをしたのはX+1年11月1日であること、本件公金支出は概算払の方法でされたことは弁論の全趣旨に照らして明らかであるところ、原告らは右監査請求の期間は概算払の精算手続が終了したX+1年11月19日の翌日から起算すべきであると主張する。
○ 思うに、地方自治法第242条の2に規定する住民訴訟を提起するためには適法な監査請求を経ることが必要であるが、同法第242条第2項が監査請求につき「前項による請求は、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることはできない。ただし、正当な理由があるときは、この限りではない。」と規定して期間制限を付しているのは、監査請求の対象が普通地方公共団体の機関、職員の行為である以上、いつまでも争いうる状態にしておくことは法的安定性の見地からみて好ましくないので、なるべく早期に確定させようとの趣旨からであり、右期間の起算点を「当該行為のあった日又は終わった日」と規定したのは、その時点から、監査の対象が特定し確定されることによりその違法性・不当性を監査し判断できるようになり、住民の具体的・主観的事情はさておき客観的には監査請求をすることができる状態になるからであると解される。
○ これを本件についてみるのに、地方自治法第232条の5は「普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によってこれをすることができる。」と規定しており、概算払は地方自治法上公金の支出の一形態とされているところ、・・・によれば、本件公金支出については概算払の時点でその目的、支出金額及びその計算根拠が明確にされていることが認められ、その違法性・不当性は他の支払方法による場合と同様清算手続の終了を待つまでもなく判断できるから、監査請求の期間の起算日との関係では概算払のあった時点をもって「当該行為のあった日」と解するのが相当である。
○ ・・・によれば、本件公金支出は、議会運営委員会でX年度予算に計上することが決定され、議会の議決を経て予算化され、さらに各会派代表者会議で行政事情視察を行うことを確認のうえ派遣議員を選定し、これを受けて被告において市費用弁償及び旅費支給条例に基づき実施されたことが認められる。これによれば、本件公金支出は極めて秘密裡に行われたというようなこともなく、正規の手続に従ってされたものであるということができる。しかしながら・・・によれば、原告らはX+1年9月21日、市監査委員に対し、市のヨーロッパ行政視察旅行を中止することを求める監査請求書を提出し同日受け付けられたが、同年10月29日、さらに視察旅行費500万円の返還を求める請求を追加しようとして右書面にその旨を書き加えさせてほしい旨の申出をしたところ、監査委員事務局は、既に右書面による監査請求について回答文書の作成段階に入っていたことから、一旦、請求を取り下げて、請求書を出し直してほしい旨の回答をしたこと、その際原告らから監査請求期間についての疑問が出されたが、事務局は、視察旅行の最終日から1年以内なら監査請求は可能である旨の指導をし、原告らはこの指導に基づいて同年11月1日、先の監査請求の取下書とともに、改めて別の監査請求書を提出したこと、この点について監査委員の監査報告書には、「一 請求の取扱い」の項において「本請求は、所定の法定要件を具備しているものと認められたので、X+1年11月1日付で、これを受理した。」と、「四 監査の対象期間及び除斥」の項において「請求人は、三請求の要旨一でヨーロッパ行政視察の中止及び当該旅費の取消しと返還請求について、地方自治法第242条第2項の規定により、○年度以降実施された7回のヨーロッパ行政視察の監査を求めているが、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したものについて、特に請求を認めるだけの正当な理由がないので、X年度のみについて監査を実施した。」とそれぞれ記載されていることが認められ、これによれば、当時、市監査委員及び同事務局はいずれも、右後者の監査請求についてはその請求期間は視察旅行が終了したX年11月4日から1年間であると判断しており、監査もこれを前提として実施されたことが明らかである。以上のような事実関係の下では通常人において「当該行為」が客観的にされた時点を認識していたとしても、到底期間内に監査請求をすることは期待できないし、原告らは監査委員事務局の指導のとおり少なくともX+1年11月4日以前に監査請求をしているのであるから、原告らの請求が期間を徒過したことについて「正当の理由」があるというべきであり、本件訴えは、適法な監査請求を経ているというべきである。
公然行われた契約を対象とする住民監査請求について、請求人固有の事情によって監査請求期間経過後請求となったことについての正当理由の主張を排斥した事例 京都地判平成4.10.19判例タイムズ815.189
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 地方自治法242条2項本文は、同条1項の規定による監査請求が、当該行為のあった日または終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない旨を定めている。これは、普通地方公共団体の執行機関・職員の財務会計上の行為は、いつまでも監査請求ないし住民訴訟の対象となり得るのは法的安定性を損なうとして監査請求の期間を定めたものである。しかし、同項但書は、「正当な理由」があるときは、この例外として当該行為のあった日から1年を経過した後でも、住民が監査請求をすることができるとしている。したがって、この「正当な理由」があるときとは、当該行為が犯罪行為の介在などにより住民に隠れて秘密裏に行なわれ、1年を経過してから初めて明らかになった場合などのように、住民が相当の注意力をもって相当な方法により探索しても客観的に当該行為の探知が不可能であった場合を指す。当該行為の存在は明らかであり、かつ住民が相当の注意力をもって調査をすれば、その行為の存在自体からその違法性を発見することが可能である場合には、正当理由があるとはいえない(最判昭63・4・22判時1280号63頁参照)。
○ 弁論の全趣旨によれば、被告と市との間の本件交換契約は、所定の手続を経て、公然と行なわれたものと認められる。本件全証拠によるも、これが、犯罪行為の介在などにより住民に隠れて秘密裏に行なわれたとの事実を認めることができない。また、仮に、本件交換契約が違法、不当なものであったとしても、本件全証拠によるも、違法、不当な点が殊更に隠蔽、仮装してなされた等の事情を認めることができない。したがって、右交換契約締結日ないし本件土地の所有権移転登記日から1年以上経過した後に原告らの監査請求がなされた点につき、正当な理由を認めることができない。
○ これに関し、原告らは、このように主張する。 ①本件交換契約後も、本件土地は依然として人々の通行の用に供されていた。 ②X年4月13日に至って初めて新聞紙上でこの問題が採り上げられた。 ③それまで、原告らには本件交換契約締結の事実を知るすべもなかった。 ④たとえ右契約締結が公然と行なわれたものであるとしても、本件交換契約の問題点を知ることができなかった。したがって、監査請求期間経過につき正当な理由がある。というのである。
○ しかしながら、弁論の全趣旨により、本件土地の道路廃止処分はX-3年10月13日に市公報により告示され、これに基づき本件交換契約も所定の手続にしたがい公然となされた事実が認められる。そうすると、右交換契約は秘密裏に行なわれたものでないから、住民が相当の注意力をもって調査すれば、その契約の存在及びその存在自体からその違法性を調査発見し得る性質のものである。したがって、原告らが監査請求の期間を徒過したことにつき、正当な理由があるとは認められない。とすれば、たとえ原告ら主張の右①、②の事実があるとしても、同③、④のように原告らが本件交換契約の存在、その問題点ないし違法性を知りえなかったとはいえないのであって、原告らに右正当な理由を認めることができない。この他、正当な理由となる事情について、原告らにおいて主張がないし、これを認めるに足る的確な証拠もない。
○ したがって、原告らの監査請求は、地方自治法242条2項の要件を欠くものである。
公然行われた支出を対象とする住民監査請求について、請求人固有の事情によって監査請求期間経過後請求となったことについての正当理由の主張を排斥した事例 静岡地判平5.7.15行裁例集44.6・7.582
(事実関係及び経過は下記参照)
○ ・・・認定のとおり、本件補助金を含む被告土地改良区に対する補助金は、X年度の市一般会計予算に計上され、これに基づいて公然と支出されたものであり、また、被告土地改良区からC事務局長に対する給与等の支出も同被告の一般会計予算に計上されて支出されているものであって、いずれについても支給の過程においてことさら不正な処理をしてこれを隠蔽した等の特段の事情の存在を認めることはできない。そうすると、市はもとより、被告土地改良区においても、補助金の交付の事実が特に秘密とされていたことはないから、市議会の審議を傍聴し、前記一般会計予算の農業総務費中第19節負担金補助及び交付金の詳細と交付先を担当部局に尋ねるなどして、補助金の交付の事実及びその中に事務局長の人件費分の補助が含まれることは、容易に判明すると解される。
○ 原告は、市の予算の執行状況について一般の住民に先立ってその内容を知り得る公職にはないこと、予算上は細目の全く分からない費目毎の合計が示されるだけであること、被告土地改良区の事業執行やC事務局長の選挙戦での支出ぶり、日頃の生活態度から疑問を感じ、X+2年始めに市役所内の被告土地改良区の事務所に資料の提出を求めたり、被告土地改良区の理事長に事務局長の給与額を尋ねたり、市林政土地改良課に補助金の内訳を尋ねたりしたが、いずれも回答を拒否されたこと、そのため、被告土地改良区に交付された補助金の内、いくらが事務局長の人件費分に該当するのかの資料を収集することが困難であったなどと縷縷主張する。しかし・・・によれば、原告は、本件監査請求に際して、(地方自治)法242条1項の違法等の事実を証する書面として、X年度被告土地改良区一般会計予算(写)、被告土地改良区に対する補助金額の推移等の資料を添付していること、右監査請求においては、第一次的に、C事務局長による私物化のため、被告土地改良区の事業に公益性がなく、これに対するX年度における4732万4000円の補助金交付は全て違法であると主張し、第二次的に、C事務局長の職務専念義務違反を理由に、被告土地改良区の事務局長を含む2名の常勤職員に対するX年度の給与支給額が654万6000円であるところ、市の被告土地改良区に対する人件費を含む事務費に対する補助金の額は634万円で、その大部分が給与に充てられていると指摘し、C事務局長の給与相当額は返還を求めるべきであると主張するに止まり、特にC事務局長の人件費分の金額を特定して本件補助金の交付の違法を主張していたわけではないこと、X+2年4月30日に提出した追加申立書においても、X+1年度分の被告土地改良区に対する補助金支出についての措置請求を追加したに止まり、事務局長の人件費分の金額を特定した主張はされていないことの各事実が認められる。してみると、原告は、その主張する調査によって初めて知ったとする本件補助金の額を本件監査請求の理由において主張していないのであり、原告が本件補助金の額を知らなかったことをもって本件監査請求が請求期間を徒過したことの必然的な理由となるものではないといわざるを得ない。むしろ、右に認定した本件監査請求の経過によれば、原告は、市及び被告土地改良区の一般会計上明らかにされている事実から、本件監査請求をなしえたことがうかがわれる。
○ 以上によれば、本件監査請求においてその請求期間を遵守できなかったことについて、正当な理由があるとの原告の主張は採用できない。
通常の手続をふんで公然行われた土地買収支出を対象とする住民監査請求について、支出の違法不当性を判断するに当たっては土地の形状、面積、接道の有無、買収までの土地使用の経過、態様、近隣の同種土地の標準的土地価額、買収手続きの経過等を調査して事実を確認したうえ総合的に判断しなければならない点で一般住民にとっては相当大きな困難性があること、議会での指摘や報道等もなされておらず、秘密裡の支出と異ならないの正当理由の主張が排斥された事例 東京高判平5.9.27判例地方自治122.20
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 地方自治法242条2項が「当該行為のあった日又は終わった日から1年」の期間内に監査請求をすることを要件とした趣旨は、監査請求の対象となる行為の多くは私法上の行為であるけれども、普通地方公共団体の機関、職員の行為である以上、いつまでも争い得る状態にしておくことは法的安定性の見地から見て好ましくないため、なるべく早く右行為の効力を確定させる必要があるという点にある。したがって、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとされるためには、例えば、当該行為が極めて秘密裡に行われ、1年を経過した後始めて明るみに出たような場合又は天災地変等による交通途絶により監査請求ができなかった場合等、特に期間徒過後の請求を認めるだけの相当な理由がある場合をいうと解される。
○ そこで、本件についてこれを見るに・・・、A・B間の売買及び本件売買とも価格決定に当たって市財産価格審査会の審査を経るなど、通常の手続きを履んで公然と行われたもので、関係者がこれを隠蔽しようとした事実はないこと、第1売買の代金に係るX年度中の賦払金は、X年9月18日に市議会において議決されたX年度補正予算案に「目5児童遊園費、節17公有財産購入費」として753万7000円が計上され、その審議に際して同市議会に提出された予算案の事項別明細書において、右児童遊園費が、「児童遊園整備事業に要する経費」であり、「用地買収(市土地開発公社取得用地)」に要する費用であることが明確にされていたこと、同年度の決算書にも、第1、第2売買の代金に係る同年度中の賦払金として、「公有財産購入費、○児童遊園用地購入費割賦金(市土地開発公社に対する支払)」名目で822万5032円が支払われた事実が明記されていたこと、X+1年度予算の審議の際、本件第1、第2売買について市議会で質疑がされていること、右X年度補正予算案、予算案の事項別明細書及び同年度の決算書などは、その性質上市の住民がこれを入手し又は閲覧することが可能であること、以上の事実が認められ、右事実によれば、市の住民が、通常の方法による調査等によって、本件各支出命令中最初の支出命令が出されたX年9月下旬から1年以内に、第1売買及び第2売買の存在及びこれに基づいて支出命令がされていることを了知して監査請求すること、更に、これを端緒として第3売買の存在及びこれに基づく支出命令がされていることを知り、右支出命令から1年以内に監査請求をすることが、いずれも可能であったと認められる。
○ 控訴人らは、「本件における各支出行為は、秘密裡にされたものではないが、支出行為の違法又は不当性を判断するに当たっては、本件土地の形状、面積、接道の有無、買収までの土地使用の経過、態様、近隣の同種土地の標準的土地価額、買収手続きの経過等を調査して事実を確認したうえ、総合的に判断しなければならない点で一般住民にとっては相当大きな困難性があり、しかも、本件監査請求前に本件における各支出行為の問題点が議会で指摘されたり、報道されたりしたことはなく、市の予算、決算関係書類を調査しても本訴で取り上げた問題点に気付くことは不可能に近かったことを考慮すると、本件は、支出行為の違法又は不当性を知ることの困難という点では支出行為が秘密裡にされた場合と異ならないというべきである。」旨主張する。しかし、本件売買及び本件各支出命令をその支出命令がされた日から1年以内に知ることは必ずしも困難でないことは・・・で認定したとおりであり、「本件土地の形状、面積、接道の有無、買収までの土地使用の経過、態様、近隣の同種土地の標準的土地価額」等の調査は、通常の不動産の価格調査や売買契約の調査とさほど変わるものではなく、短期間にその調査を終えることができると認められるし、「買収手続きの経過等」についても、本件売買契約書を閲覧することなどにより、さほど期間をかけずに調査可能であるから、本件を、支出行為が秘密裡にされた場合と同視することはできない。現に、控訴人らは、匿名の電話通報を端緒として1、2か月程度で調査を終え、本件監査請求をしている(控訴人らの主張自体から明らかである。)。したがって、控訴人らの右主張は採用しない。そして、他に前記認定を左右するに足りる証拠はない。
漁業補償交渉過程での過大な経費を伴う会食経費の支出事案について、予決算等は通常の手続でなされており殊更に隠蔽されたものではないが、住民の入手可能な資料では食糧費の具体的使徒等は明らかでなく、住民が相当の注意力で調査しても本件支出は知り得なかったものというべきなので、請求人がこの支出を知り得た時から1か月以内になされた住民監査請求について正当な理由があるとされた事例 広島地判平7.3.16判例地方自治142.18
(県が港湾埋立等事業を行うにあたり、漁業補償を進めるため、県職員と漁協関係者が頻回会食をしたが、その額は県の内規を大幅に超過し、支出稟議も不適切なものがあった。また当該経費の予決算は正規の手続で承認されていたが、食糧費の詳細事項は明らかにされていなかった(法定の公表義務がない)。しかし支出の数年後、噂を聞きつけた某県議の調査やマスコミ報道でこれらの疑惑が明るみになり、県議会でも取り上げられるに至り、その約1ヶ月後に本件監査請求がなされた)
○ 本件監査請求は、当該行為たる本件支出から1年以上を経過してなされたものであることが明らかであるが、予算書や決算書等、住民が入手可能な資料には、食糧費の具体的使途はもちろん、金額やひいてはその存在すら明らかでなく、議会審議の過程でも特に取り上げられなかったのであるから、本件支出がすべて予算内の支出であり、住民に対しことさら隠蔽されたものでないとしても、なお秘密裡になされたものとみて差し支えなく、住民が相当の注意力で調査しても客観的にみて本件支出を知り得なかったものというべきである。そして、原告らが本件支出を知ることができたのは、X年11月9日及び10日開催の決算特別委員会の審査を通じて得た資料によるものというべきであるから、それから1か月以内になされた本件監査請求は、法242条2項に定める期間を徒過したことにつき「正当な理由」があるものというべきである。
高速道路の経済効果について商工会議所に調査委託したことに対する住民監査請求について、請求人らがかねて当該高速道路の調査等に関心を寄せており、上記委託契約の存在を知って約2か月後に文書公開請求によりその詳細を把握するなど情報を収集していたこと等を考慮すれば、契約の存在や内容を把握して直ちにまたは遅くとも1か月以内には監査請求をすることができたというべきであるのに、実際の監査請求は事実を知って約2か月後であり、相当の期間内に請求がされたとはいえず、監査請求期間徒過についての正当な理由はないとされた事例 横浜地判平7.12.20判例地方自治150.11
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 本件委託契約については、X年9月13日に市道路局において、・・・環状道路が整備されたときの経済効果のうち、特に業務目的に着目した効果に関する調査を・・・商工会議所に随意契約で委託することについての起案がされ、これが同年9月20日に決裁され、同年10月3日に本件委託契約が締結されたうえ、同年12月28日に・・・商工会議所から高速・・・環状道路整備効果調査報告書が同局に提出された。なお、本件委託契約は、市の刊行する予算書等には掲載されていない。
○ 原告・・・らは、高速・・・環状道路の建設に反対していたが、市道路局に対し、X年8月9日付けで、・・・環状道路の計画の概要を知るためには何を読めばよいのか、またその決定のために、現況調査、高速道路を作った場合の経済効果又は排気ガス及び騒音等の予測報告書が作成されたか、作成された場合にはその名称、またそれが公開されているかどうかなどについて、教えてくれるよう要請した「・・・環状道路問題等についての再要請書」と題する文書・・・を提出したところ、市道路局長・・・は、同年10月31日付け回答書において、本件委託契約にかかる調査について触れることなく、「今後計画の具体化にあわせて調査を行っていく予定である」と回答した。
○ X年12月13日、同月15日の新聞には、・・・商工会議所のほか、市の経済団体36団体で組織する「・・・市幹線道路網建設促進協議会」が・・・環状道路の建設を促進するために活動していること、右協議会の会長は・・・商工会議所の会頭である・・・が就任していることがそれぞれ報道された。
○ 原告・・・らは、市議会に対し、X+1年9月9日付けで、・・・環状道路北側区間建設に伴う経済・社会影響調査の実施についての陳情書を提出した。これに対し市当局は、同月13日、市議会に対し、・・・環状道路の整備効果の調査については、市域の一体化など定量的な把握に適さない項目もあり、定性的な取りまとめを行い、パンフレット等で公表している、また・・・環状道路が地域に与える経済的効果等については、今後関係機関を含め検討していきたいと考えている、昭和62年度及び昭和63年度に実施した「開発効果調査(アンケート調査)」については、・・・環状道路全体の必要性や効果等を広く一般市民に理解してもらうため、市内の商工業者への意識調査やポスターの作成等を実施したものであり、既に公表しているが、北側区間についても検討していきたいなどと説明したが、本件委託契約が既に締結されていることについては説明しなかった。
○ 原告・・・らは、X+1年9月26日、市を訪れ、・・・環状道路に関する各種調査報告書等の公文書公開について、これを担当している市道路局総務課庶務係の・・・と話し合ったところ、本件委託契約が存在することを知り、その内容を知るため原告・・・において、同日、市に対し、高速・・・環状道路整備効果検討調査報告書及びこれに関する執行伺、委託契約書等について公文書公開条例による文書の公開請求をした。そして、市は、同原告に対し、同年10月9日、右公文書公開決定期間延長通知をしたうえ、同年11月11日に右公文書について一部公開決定し、同月19日付けで一部公開決定通知書を送付し、同月22日に同原告は右公文書(写し)を受領した。
○ ところで、市は、X+1年11月18日に、本件委託契約による前記報告書に関し、民間研究機関に調査を委託した結果、・・・環状道路による直接、間接の経済波及効果は約1030億円に上るなどと整備効果調査の効果を公表し、これが同月19日の新聞に報道された。
○ その後、X+1年12月5日、原告・・・が代表をしている高速・・・環状道路に反対する住民の団体は、市が・・・商工会議所との間において本件委託契約を締結したのは、不当で、公正で客観的な結果が出てくるはずがないとして、調査のやり直しを求める陳情書を市議会議長宛に提出した。
○ 右認定に係る事実によれば、原告らにおいて、本件委託契約の存在について、X+1年9月26日まではこれを知ることができなかったものであり、同日の市の担当職員による説明により初めて市が・・・環状道路整備効果検討の調査を委託し、その報告書が存在することを知り得たものと認められる。そして、原告らにおいて、本件委託契約の存在のみならず、その具体的内容、受託者及び費用等について知らなければ、その契約の締結等が違法なものであるかどうかについて判断できないと解されるから、本件では、前記認定のように原告・・・において、X+1年9月26日に本件委託契約の存在を知った後、公文書公開条例による文書の公開請求をし、これが同年11月11日に一部公開決定されたうえ、同月22日にその写しを受領したことにより、その具体的内容、受託者、費用等についてこれを知った時点で、原告らにおいて、本件監査請求の対象となる本件委託契約の存在を知り得たことになるというべきである。なお、・・・本件委託契約の締結のための起案、決裁、契約等の事務は、それ自体、特別秘密裡にされたものではないこと、本件委託契約の締結等を知る手掛かりとして、市の「決裁供覧文書整理簿」の公文書公開請求をする方法があり得ることが認められる。しかし、前記認定の原告らの要望等に対する市当局側の態度は、本件委託契約にかかる調査ないしその報告を殊更、秘匿しようとしていたものとしか考えられないこと・・・、「決裁供覧文書整理簿」から知りたい文書を特定し、その公開請求手続きをとることには、相当の困難が伴うことが認められる。・・・
○ ところで、X+1年11月22日の時点では、本件に関する住民監査請求の期間は徒過しているところ、前記認定のとおり、原告らは、元来、高速・・・環状道路に関する各種調査に強い関心を持っていたこと、そして、本件委託契約の存在自体については、同年9月26日にこれを知ったこと、しかも、原告らは、同年11月22日までに、市に対して・・・環状道路に関する公文書開等を求めるなど、種々の情報を収集していたこと、また、前記認定の事実によれば、原告らは・・・商工会議所が・・・環状道路の建設を促進するために活動している「・・・市幹線道路網建設促進協議会」に加盟していて、その会頭である・・・が、右協議会の会長をしていることを従前から知っていたか、少なくとも知り得たと認められること、原告らは、市議会議長に対し、X+1年12月5日、・・・商工会議所が本件調査をしたのは公正ではないなど本件におけるとほぼ同様の理由で、調査のやり直しを求める陳情書を提出していることなどからすれば、本件において、原告らが本件委託契約の締結等が違法であるとして、それについて地方自治法242条の是正措置を求めようとするならば、前記時点で直ちに、遅くともそれから1か月以内には監査請求をすることができたというべきである。
○ ところが、原告らが、本件監査請求をしたのは、翌年のX+2年1月21日であり、右の事実を知ってから既に約2か月を経過しているから、「当該行為を知ることができたと解されるときから相当期間内に監査請求した」とはいえないと解される(なお、右「相当期間」を常に約2か月と解すべき根拠はない。)。
○ そうすると、結局、本件監査請求が期間を徒過してされたことに「正当な理由」があるということはできない。
都市計画道路建設のPR用パンフレットの一部に道路構造の記載誤りがあり、かかるパンフレットを製作配布し無駄な費用を費消したとする住民監査請求について、住民が当該道路構造の正確な情報を得ることができた時点から約1か月後に提起された請求は、財務会計行為1年経過後の請求についての正当な理由があるとされた事例 横浜地判平8.10.28判例地方自治166.39
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 市道路局は、X-2年ころ以降、建設省や道路公団等とも協議調整を重ねた上、高速・・・線の都市計画原案の策定作業を進め、X年夏ころ、その都市計画原案を策定した。この都市計画原案において、本件区間は地表式とされていた。
○ 市は、この都市計画原案を住民に周知するため、X年8月20日から同年9月26日までの間、2区7会場で合計14回、事前説明会を開催し、同年11月6日から同月9日までの間、2区2会場で合計3回、第1回相談コーナーを設け、X年12月12日から同月18日にかけて、3区7会場で合計7回にわたり、都市計画原案の説明会を開催し、同月14日から同月28日までの間、市役所において本件都市計画原案を任意縦覧に供し、同月15日から平成3年1月26日までの間、3区3会場で、区役所での原案の図面掲示を行った。また、市は、平成3年1月12日から同月19日まで、2区2会場で合計3回、第2回相談コーナーを設け、さらに、同年5月22日から同月25日までの間、2区2会場で合計3回、第3回相談コーナーを設けた。このうち、X年8月ないし9月開催の事前説明会は非公式のものであったし、同年12月開催の都市計画原案の説明会は公式のものであったが、ほとんどが計画に反対する住民の強い抵抗により、事実上、流会ないし開催不能という結果に終わった。このような説明会等においては、会場に、縮尺2500分の1の計画平面図と縮尺1000分の1の計画平面図が掲示された。このうち、非公式の事前説明会と第一回相談コーナーの会場において掲示された計画平面図(縮尺2500分の1)には、本件区間は「平面」と記載されていた。また、任意縦覧に供された計画平面図(縮尺2500分の1)には、本件区間の道路構造を示す記載はなかった。そして、都市計画原案の説明会、都市計画原案の任意縦覧、都市計画原案の図面掲示、第2、3回相談コーナーの会場において掲示された計画平面図(縮尺1000分の1)には、他の区間で記載されている地下式等の道路構造の表示(いわゆる旗上げ)が本件区間では記載されていなかった。また、前記の説明会等において、住民に配布されたパンフレット等のうち、X年12月配布の小冊子「・・・建設計画道路 高速・・・線」(市、建設省及び日本道路公団の共同発行・・・には、Kジャンクションの平面図が記載され、そこには本件区間の道路構造が「地表式」と表示され、また、これとは別に、Kジャンクションの完成予想図が絵図で記載されていた。
しかし、X年8月配布の「首都圏中央連絡自動車道」と題するパンフレット(市、建設省及び日本道路公団の共同発行・・・)、同年12月配布の「高速・・・線」と題するパンフレット・・・、X+1年8月配布の「人にやさしく、街に調和する、高速・・・線」と題するパンフレット・・・には、高速・・・線の縦断図が記載されたが、そこには、本件区間を含めて、KジャンクションからK橋交差点までの区間が「地下式」と表示されていた。その後、市は、前記のとおり、都市計画原案を住民に周知するため、新聞折込の方法で、X+1年5月に本件パンフレット1を、同年9月に本件パンフレット2を配布したが、両パンフレットには、高速・・・線の道路縦断図が記載され、そこには本件区間を含めてKジャンクションからK橋交差点までの区間が「地下式」と表示されていたほか、本件パンフレット1には、道路構造を併記した高速・・・線の平面図が記載され、そこには、本件区間を含むKジャンクションからK橋交差点までの区間が「地下式」と表示され、また、本件パンフレット2には、道路予定地の航空写真図が掲載され、そこには、右と同様、本件区間を含むKジャンクションからK橋交差点までの区間が「地下式」と表示された。
ところで、X+2年6月7日から同月13日にかけて、3区5会場で開催された県主催の環境アセスメント説明会で配布された「環境影響評価の概要」(県作成・・・)においては、本件各パンフレットと同様の道路縦断図のほか、道路構造を併記した道路平面図が記載され、その平面図に本件区間が「地表式」と表示されていた。このため、6月13日の説明会において、出席していた一部住民から、本件区間は地表式と地下式のいずれであるかという質問が出て、主催者側が地表式であると答える場面があった。原告らは、このような質疑応答から、本件区間が地表式として計画されていることを知り、同年7月22日、市監査委員に対し、被告らが本件各パンフレットに高速・・・線の道路構造に関し事実と異なる内容を記載して配布し、無駄な費用を支出したとして、その費用の賠償等を求める本件監査請求を行うに至った。以上のとおり認められ、これを覆すに足りる証拠はない。
○ 右認定の事実によれば、原告ら住民は、公式な説明会において、本件都市計画原案の内容を知る機会が事実上なかったといえる上、都市計画原案の任意縦覧の際にも、本件区間の道路構造を正確に知ることができなかったことに加えて、市から、本件区間も含めたKジャンクションからK橋交差点までを「地下式」と表示した、前記パンフレットや本件各パンフレットの配布を受けていたのであるから、X+2年6月の県主催の環境アセスメント説明会で配布されたパンフレット(「環境影響評価の概要」)に接するまでは、相当の注意力をもってしても、本件区間が実際は地表式として計画されていること、したがって、本件パンフレット1には、本件区間を「地表式」と表示すべきところを、これを含めたKジャンクションからK橋交差点までを一括して「地下式」と表示した誤りのあることを知り得なかったものというべきである。そして、原告らは、それに気付いた約1か月後に、本件監査請求をしているのであるから、原告らには、本件パンフレット1に関する監査請求期間を徒過したことについて、地自法242条2項但書にいう「正当な理由」があったものというべきである。
○ 被告らは、原告ら住民は説明会等の会場で掲示された図面で本件区間が地表式であることを知り得たはずであると主張し、なるほど、前記のとおり、X年8月ないし9月開催の事前説明会及び同年11月開催の第1回相談コーナーにおいて、会場内に掲示された計画平面図(2500分の1)には、本件区間が「平面」と表示され、また、同年12月開催の説明会では、本件区間を「地表式」と表示した平面図と、Kジャンクションの完成予想図を絵図で記載した小冊子(「・・・建設計画道路 高速・・・線」)が配布されていることなどが認められるけれども、事前説明会は非公式なものであったし、また、相談コーナーも一部住民に対するものであった上、X年12月に開催された公式の説明会は、そのほとんどが住民の反対により事実上流会に終わっていることなどからすると、原告らが相当の注意力をもってすれば、これらの図面ないしは小冊子などによって、本件区間の道路構造を知り得たということはできない。また、本件区間はKジャンクションの一部であるが、ジャンクションであるからといって地表式とは限らないから、このことから原告ら住民が本件区間を地表式と認識し得たということもできない。
町職員に対する土地売却についての住民監査請求において、当該売買契約は議会で審議され、その事実や内容も秘密裡にされたとは認められないことからすれば、議会での議論がなされた時点で町民は当該契約の内容を知り得るものというべきところ、本件監査請求はその1年4か月後になされたものであり、請求の1か月前にあった匿名投書によって事実を承知したとの原告の主張を排斥して、監査期間経過後の請求につき正当な理由がないとした事例 静岡地判平10.1.29判例タイムズ980.144
(事実関係及び経過は下記参照)
○ ・・・本件売買契約については、X年12月開催の被告町議会の総務常任委員会において契約内容の説明がなされたうえ、正式な審議を経て代金額が改訂され、契約書も作り直され、X+1年9月に開かれた決算特別委員会の総務常任委員会の席上でも話題となり、事実上の話し合いが行われ、更に、議会の決算特別委員会において審議され、同月21日、決算認定を受けているうえ、その際、本件売買契約が記載された関係書類が議員に配布されており、契約書も被告町の町役場内部で回覧されているのであり、右契約につき、被告町の議会及び町役場において秘密裡の処理がなされたものとは認められず、また、本件土地上の被告Aの建物建築は、近隣住民が参加して上棟式が行われたほか、完成までの約6か月間公然と行われているうえ、右土地については、X+1年7月7日、被告町から被告Aへ売買を原因とする所有権移転登記がなされていたから、被告Aが被告町から本件土地を購入したことは、不動産登記簿を閲覧する等の方法により、容易に知りうるところであった。更に、X+1年8月ころ以降、被告町議会の全議員宛に本件売買契約に問題があるとして、調査を促す匿名の投書が相次いでおり、これら投書が、特定の町民からなされたものか否かは不明であるが、少なくともこの時期、一部町民の間では、本件売買契約の内容が知りうるところとなり、その売買価格等が問題とされていた事実が明らかである。
○ 以上の事実を総合すれば、本件売買契約が秘密裡になされたとか、関係者がその内容や手続を秘匿しようとした事実は認められず、被告町の住民が、被告町の行政や議会審議に関心を持ち、相当の注意力をもって調査をすれば、遅くともX+1年9月ころまでには、本件売買契約につき監査請求が可能な程度の事実(被告Aが被告町から本件土地を購入したことや本件土地の売買代金額等)を知ることができたというべきである。ましてや、前記認定の原告の被告町における議員等の経歴、政治活動の内容及び実績等(注:対象財務会計行為の約5年前まで24年近く町議をつとめ、その後も元町議ら政治団体を結成し、政治活動を活発に行なっている)からすれば、原告は、町議会議員等を通じて本件売買契約に関する議会での審議状況、関係資料の存在及びその内容等を知りうる立場にあったと認められ、原告が遅くともX+1年9月ころまでに右事実を知ることはなおさら容易であったというべきである。
○ 然るに、原告は、右の時から約1年4か月を経過したX+3年1月26日になってはじめて本件監査請求を行ったのであるから、相当な期間内に監査請求をしたとはいえず、本件監査請求が本件売買契約締結の日から1年を経過した後になされたことについて、地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるということはできない。
○ なお、原告は、本件売買契約については、被告町が被告Aの代替地として訴外Bから本件土地を購入する際、同土地を公民館駐車場用地として利用する予定がないのに、公民館駐車場用地という虚偽の名目で農地法5条の転用許可を得たり、被告Aが、本件国道工事に伴い代替地の提供を受けた他の住民と比べて、様々な点において優遇されるなど、その経緯も含めて、極めて不自然な処理がなされた旨主張するが、右事実の存否は、本件の「正当な理由」の有無についての前記判断を妨げるものではない。更に、原告は、原告が本件売買契約について知ったのは、X+2年12月中旬ころに受け取った匿名の投書による旨主張し、本人尋問において、これに沿う供述をするが・・・などに照らすと、原告の右供述によって右投書が存在したことを認めるには足りず、その他これを認めるに足りる証拠はない。
自治功労者が叙勲等された際の記念品料支給に対する住民監査請求において、予算決算手続や支出手続は通常に行われ、これら支出がことさらに隠蔽されていた事情が窺えない以上、外部から容易に知ることができたとはいえないが、秘密裡に支出が行われたものではなく、監査請求期間経過後の請求に正当な理由はないとした事例 名古屋地判平10.3.27判例時報1672.54
(事実関係及び経過は下記参照)
○ (地方自治)法は、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは住民監査請求をすることができないとしている(法242条第2項本文)が、これは、財務会計行為が違法又は不当なものであったとしても、いつまでも住民監査請求や住民訴訟の対象となり得るのでは、法的安定を損なうので、行為の時から1年間を経過した後は、住民の知不知にかかわらず、住民監査請求をすることができないこととしたものである。このような監査請求期間が定められている趣旨に鑑みると、右「正当な理由」があるということができるためには、単に住民が当該行為を知らなかった又は知り得なかったというだけでは足りず、当該行為が秘密裡にされたために住民がその行為を知り得なかったという事情がなければならないというべきである。そこで・・・記載の15件のうちX年度からX+2年度までの間にされたもの・・・が秘密裡に行われたかどうかについて判断する。
○ 本件X年度ないしX+2年度支給は、「(款)総務費、(項)総務管理費、(目)一般管理費、(節)報償費」として、各年度の議会において定められた予算に含まれていたものであり、また、各年度の議会において認定された決算にも含まれていたものである・・・。本件X年度ないしX+2年度支給は、通常の手続に従い、支出負担行為、支出命令及び支出の各手続を経て支給されたものである・・・。
○ 本件支給基準は、自治功労者に対して支給する記念品料等の支給に関して必要な事項を定めた、いわゆる内規であり、自治功労者が、地方自治功労表彰を受章したとき、叙勲を受章したとき、国家褒章を受章したとき、死亡したときのいずれかに該当することとなった場合は、記念品料を支給することができること、その支給基準額は、自治功労表彰を受けた場合は記念品料15万円以上、叙勲又は国家褒章を受けた場合は記念品料20万円以内、弔慰金は50万円であることが定められている。本件X年度ないしX+2年度支給のうちには、本件支給基準に則って支給されたものがある。
○ 県の住民は、公文書公開請求をすることによって、本件X年度ないしX+2年度支給に係る支出金調書について、特定の個人が識別される部分及び口座番号を除いて、閲覧するとともに、写しの交付を受けることができた・・・。また、県の住民は、本件支給基準について、公文書公開請求をすることによって、閲覧するとともに、写しの交付を受けることができた・・・。
○ ・・・認定の事実によると、本件X年度ないしX+2年度支給がことさら隠蔽されていたなどのこれらの行為が秘密裡にされたというべき事情は認められず、他にそのような事情を認めるに足りる証拠もないから、本件X年度ないしX+2年度支給が秘密裡にされたとは認められない。
○ ・・・によると、予算、決算の書類や支出金調書の右公開部分のみでは、自治功労表彰を受章した議員、叙勲を受けたり国家褒章を受章した議員、議長や副議長を退任した議員に対して現金が支給されていたことは分からず、本件支給基準の存在も一般には知られていなかったものと認められるから、右支給の事実は外部から容易に知ることができたとはいえないが、そうであるからといって、隠蔽行為等が認められない本件においては、本件X年度ないしX+2年度支給が秘密裡にされたということはできない。
○ したがって、右「正当な理由」は認められない。
固定資産税減免を対象とする住民監査請求において、議会での答弁や予算書によれば、減免が秘匿されたとはうかがわれず、監査請求期間経過後になされた請求には正当な理由はないとした事例 宇都宮地判平10.5.14判例時報1670.12
(事実関係及び経過は下記参照)
○ X年第2回町議会定例会において、本件賃貸借契約締結前である同年3月10日に、企画財政課長が、X年度一般会計予算のうち町民ホールについての説明欄の「土地賃借料等」という記載の「等」に何を含むかについての質問に答えて、町は土地1に関し、1平方メートル当たり月額54円の賃料の他に固定資産税相当分の1万9900円を支出すること、固定資産税相当分は、一旦町から賃貸人に支払い、同人から町に支払ってもらうことで話を進めてきたが、税を減免することを検討中であることを説明した。X+1年第1回町議会定例会において、同年3月17日に可決されたX+1年度一般会計予算のうち町民ホールについての説明欄には、X年度と異なり「土地賃借料」とのみ記載され、固定資産税相当額の支出を表す「等」の記載はなかった。前記認定の事実に照らせば、町において、免除の存在及び内容が秘匿されたような事情は全く窺われない。
○ 免除に先立って、免除の可能性を示唆する発言が議会でされていることに加えて、X+1年度一般会計予算では固定資産税相当額の支出が計上されていないことを併せ考えれば、住民にとっても、その間に免除がされたことは容易に推察し得るのであり、住民が相当の注意力をもって調査したときには、遅くともX+1年3月には免除の存在及び内容を知ることができたというべきであるが、本件監査請求は、X+4年3月14日までなされなかったのであるから、監査請求期間徒過について正当な理由があるということはできない。
監査委員と知事の会見(意見交換等)においてホテルのフルコースフランス料理の昼食を利用したのは違法とする住民監査請求において、監査委員が謝罪会見するまでは公文書開示請求をしても重要な情報が非開示とされる条件下では、同謝罪会見までは秘匿されていたというほかなく、それから1か月以内に提起された住民監査請求は、対象財務会計行為1年経過後の請求についての正当な理由があるとされた事例 東京地判平10.6.19判例地方自治182.19
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 原告はX年3月8日、監査委員に対して、X-1年4月1日からX年1月31日までの間の会議、懇親会等の会合に係る支出命令書、起案文書、領収書等の公文書の開示請求をしたが、監査委員は、X年5月8日、全部非開示とする旨の決定を行ったため、原告は、同月18日、右公文書非開示決定の取消しを求めて提訴した。
知事は、X年10月13日、開示基準を定め、事業に関連する随時の協議、打合せの際の飲食に要する経費については、実施年月日、支出金額、支出内訳、出席者数については開示し、会議等の名称、会議開催の目的、都の出席者については原則開示するが、相手方の肩書・氏名、会議等の場所、債権者名、債権者の口座、権者の印影については非開示とすることとし、会議費について、過去に全面非開示決定としたもののうち、現に争訟中のものについて、開示基準により開示できる部分については開示することとした。
監査委員は、X年12月25日、前記・・・の訴訟の対象に含まれる別件知事会見に係る公文書の一部を開示したが、会議等の名称、開催の目的、開催場所、会議の内容及び出席者名を非開示とした。
別件知事会見は本件知事会見と同様、本件ホテルにおいて開催されたものであるが、別件知事会見については34万7468円、本件知事会見については31万2488円の支出がされ、これに合致する会計書類が作成されていたものの、実際の支払額は、別件知事会見については28万5001円、本件知事会見については27万9811円であり、その差額は、X+1年2月14日に返還された。
監査委員は、X+1年2月15日、監査事務局が行ったX-1年度の会議費の支出につき不正経理、過大支出があったとして、謝罪会見を行い、その中で、別件知事会見の内容が明らかにされ、同月23日、別件知事会見の会議件名、開催場所を開示した。
○ 右のとおり、本件知事会見は別件知事会見と会議の名称、目的及び開催場所のみならず、会計処理に係る支出が現実の支払額を超えていたためその差額返還が行われた点でも共通するところ、X年10月13日以降においても、開示基準によれば、会議等の場所、債権者名は非開示とされ、別件知事会見については、右事項に加えて、X+1年2月15日の謝罪会見までの間は、開示基準において原則開示とされている会議等の名称、開催の目的、都の出席者についても非開示としていたのであるから、仮に、原告が、本件知事会見につき公文書開示請求をしたとしても、監査委員は、X+1年2月15日の謝罪会見までの間は、会議等の場所、債権者名はもちろんのこと、本件知事会見の名称、開催の目的、出席者についても非開示としたものと推認することができる。
○ ところで、地方自治法242条2項本文は、監査請求の期間を同条1項に現定する財務会計行為のあった日又は終わった日から1年と規定する。しかし、当該財務会計行為の存在及び内容が地方公共団体の住民に秘匿され、監査請求期間内に監査請求することができない場合等にまで、右の規定を適用することは相当でない。そこで、同項ただし書は、「正当な理由」があるときに、その例外を認めたものである。したがって、右にいう「正当な理由」の有無は、特段の事情のない限り、地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該財務会計行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から監査請求をするために必要とされる相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断されるべきである。そこで、この点を本件について検討するに、X年10月13日からX+1年2月15日までは、本件知事会見の開催日、これに係る支出内訳、出席者等を知ることは可能であったとしても、会議等の名称、開催の目的、開催場所を含む支出の内容の開示は拒絶されたであろうと推認されることは前記のとおりであり、これらが明らかにされたのはX+1年2月15日というのである。そうすると、財務会計行為は日時と支出金額のみならず、使途との関係においてその当否、適否の判断が可能となるものであることからすれば、本件知事会見に係る支出負担行為、支出命令はX+1年2月15日まで秘匿されていたものというほかなく、前記のとおり、原告は、その1か月以内である同年3月13日に本件監査請求をしているのであるから、本件監査請求が本件知事会見開催から1年経過後になされたことについて正当な理由が存するものということができる。
いわゆる組合専従職員に対する違法な給与等支給に関する住民監査請求について、市の広報誌または一般地方紙に掲載された本件に関する市長の議会答弁により住民が相当の注意力をもって調査すれば欠勤中の本件職員についての負担金及び給与の支出行為を知ることができたものであり、それから2ヶ月程度後になされた住民監査請求について、対象財務会計行為1年経過後の請求についての正当な理由があるとされた事例 札幌地判平10.7.17判例地方自治186.10
(事実関係及び経過は下記参照)
○ ・・・各証拠によると、以下の各事実が認められる。
本件市長部局職員についての負担金及び給与は、市の予算に計上された上、通常の支出手続によって支出されていた。
X-2年7月ころ、月刊誌であるD誌に「・・・市政の暗部?・・・市労連書記長の特権」と題する記事が掲載され、右見出しを含む右雑誌の広告がH新聞に3日間に渡り掲載された。右記事は、リード部分において「市労働組合連合会などの同市の労組役員3人が、長期間にわたって『欠勤』のまま組合活動に専従している。」と記載し、市総務局職員部勤労課長は、「円滑な労使関係を保つために、行政の裁量権の中で取った『特例措置』です。」「確かに、法が求める趣旨とはズレがありますが、『欠勤扱い』ということで市は給料を払っていないし問題はないと思います」と説明したと記載している。
X年2月28日、市議会本会議において、被告は市長として、M議員の質問に対し、組合専従役員について地方公務員法の定める在籍専従期間を超えて許可をしたことはなく、必要があってさらに組合業務に従事する場合は欠勤によって対応しており、給与上は無給であること、右は安定的かつ円滑な労使関係を維持する必要からされたものであって無断欠勤の場合と同様に扱うことはできないとの趣旨の答弁をした。(こ)の答弁については、市の広報誌である「広報・・・」X年4月号に記事として掲載された。
X年3月10日、市議会第一部予算特別委員会において、被告は市長として、M委員の質問に対し、欠勤職員の扱いについて同趣旨の答弁をした。(こ)の答弁については、X年3月11日付のH新聞・・市内版に記事として掲載された。
○ 右の事実関係の下で、欠勤中の本件市長部局職員についての負担金の支出行為に関して、原告のような一般の市住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみてどの時点で当該行為を知ることができたと解すべきか検討する。この点、被告は、本件市長部局職員についての負担金及び給与は、予算に計上された上で適正な手続によって支出されているから、市住民が問題の支出行為を知ることについて客観的障害があったとはいえない旨主張する。しかしながら、本件市長部局職員についての負担金及び給与が予算に計上されているとはいえ、予算には負担金及び給与の各総額が計上されるに過ぎず、欠勤職員が存在することは予算からは認識することができないから、これをもって市住民が欠勤職員の存在や、欠勤中の本件市長部局職員についての負担金及び給与の支出行為を知ることができたとはいえない。また、被告は、X-2年7月ころに市における欠勤職員の存在が広く報道されたから、市住民は遅くとも同年8月ないし9月ころには欠勤職員についての負担金及び給与の支出行為を知ることが可能であった旨主張する。しかしながら、前記認定によれば、右報道にかかる雑誌の新聞広告のみからでは当該記事が欠勤職員の存在を指摘するものであると認識することは不可能であり、また、D誌に掲載されたことのみをもってしては欠勤職員の存在が広く報道されたとはいえず、他にそのころ欠勤職員の存在が広く報道されたことを認めるに足りる証拠はないから、結局、X-2年7月ころに欠勤職員の存在についてD誌に記事として掲載されたことをもって、市住民が欠勤中の本件市長部局職員についての負担金の支出行為を知ることができたとはいえない。
○ 他方、・・・事実関係の下では・・・X年2月28日の市議会本会議における市長の答弁が、市の広報誌である「広報・・・」X年4月号に記事として掲載されてこれが各戸に配布された時点(右時点は必ずしも明確ではないが、他の記事の内容からして同年3月中旬以降と認められる。)又は・・・X年3月10日の市議会第一部予算特別委員会における被告の答弁が、H新聞平成9年3月11日付・・・市内版に記事として掲載されてこれが各戸に配布された時点においては、これらの答弁が、給与上は無給であることを指摘するものであることを考慮しても、市住民が相当の注意力をもって調査すれば欠勤中の本件市長部局職員についての負担金及び給与の支出行為を知ることができたと解される。
○ 原告は、X年5月8日に欠勤職員についての負担金及び給与の支出について監査請求をしているところ、右請求は前記・・・で判示したとおり、市住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて欠勤中の本件市長部局職員についての負担金及び給与の支出行為を知ることができた時点から約2か月を経過したに過ぎないから、相当な期間内にしたものというべきである。
○ よって、原告には、X-1年5月7日までに行われた欠勤中の本件市長部局職員についての負担金及び給与の支出行為について、X年5月8日に至るまで監査請求をしなかったことについて正当な理由があり、これについても適法な監査請求を経ているものというべきであるから、本件訴えのうち、X-1年5月7日までに支出された本件市長部局職員についての負担金及び給与相当額及びこれらに対する遅延損害金の損害賠償を求める部分は、監査請求がX年5月8日にされたことをもって不適法ということはできない。
いわゆる官官接待事案について、予算自体は計上されており支出の秘匿、書類の改ざん等も認められないことからすれば、秘密裡に行われたとはいえないこと、予算の内容から個々の支出の具体的内容が明らかになっているわけではないが、接待のための食料費支出は国民の間で問題視されていることに照らせば、その一一事をもって秘密裡になされたと見ることはできないこと、公開資料があればただちに監査請求可能であるにも関わらず資料公開から86日後に請求をなしていることからすれば相当期間内に請求したとはいえない、とした事例 大津地判平10.9.21判例タイムズ1038.188
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 地方自治法242条2項本文は、普通地方公共団体の長その他財務会計職員の財務会計上の行為について、当該行為が違法・不当であるとして監査請求できるのは、当該行為のあった日又は終わった日から1年以内である旨規定している。右規定は、たとえ違法・不当な財務会計上の行為であったとしても、普通地方公共団体の機関や職員の行為であるから、いつまでも住民が争い得る状態のままにしておくのは、法的安定性を損ない好ましくないとの趣旨に基づくものである。しかしながら、当該行為が住民に秘密裡になされ、1年を経過してから明らかになった場合等にまで、右趣旨を貫徹することは妥当ではない。そこで、同項但書は、「正当な理由」があれば、当該行為があった日又は終わった日から1年を経過した後でも監査請求ができる旨の例外規定を設けたのである。とすれば、当該行為が秘密裡になされた場合、同項但書にいう「正当の理由」の有無は、特段の事情がない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為の存在を知り得たかどうか、また、当該行為を知り得たと解される時点から監査請求をするのに必要と認められる相当期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものというべきである。
○ 右を本件にあてはめてみると、別表1の各支出を含む本件各支出は、いずれもX年度県一般会計予算に計上されており、各支出自体も殊更秘匿されていたものではない。また、関係書類への虚偽記載や改ざん等が行われたという事実も見当たらない(以上の事実は当事者間に争いがない)。
○ 右事実を前提とすると、別表1の各支出については、そもそも当該行為が秘密裡になされたものとは解されない。したがって、別表1の各支出につき、監査請求期間を徒過したことに「正当な理由」はないというべきであって、この点に関する原告らの主張は採用できず、右支出にかかる請求は、不適法なものとして却下を免れない。
○ もっとも、この点、原告らは、関係資料公開の結果によってしか別表1の各支出を知り得なかったとして、「正当な理由」があった旨主張する。確かに、予算の議決や決算の認定手続きに際し、別表1の各支出を含む本件各支出の個々具体的な内容が明らかにされていたわけではない。しかしながら、いわゆる接待のために支出される「食糧費」の存在自体、本件各支出当時以前から国民の間で問題視されていたことに照らせば、手続上、個々の支出の具体的内容が明らかにされていなかったという事実のみをもって、別表1の各支出が秘密裡になされたと認めることはできない。また、仮に別表1の各支出の秘密裡性が認められたとしても、原告らの行った本件監査請求の理由・・・に照らすと、公開を受けた資料さえあれば直ちに監査請求をすることが可能であるにもかかわらず、最終の資料公開日から86日もの期間経過後にはじめて本件監査請求が行われているのであって、監査請求をするのに必要と認められる相当期間内の監査請求であったと評価することはできない。したがって、原告らの右主張は採用できない。
記者クラブとの飲食を伴う会合が架空会議とする住民監査請求において、その会議に近接する年度に行われた飲食を伴う会合に関する契約・会計事務について多くの不適正処理がされたとする報告書が公表されていること、また本件会合での単価が会合場所の料金表単価より著しく高額であることという事情があることを踏まえれば、公文書公開により本件会合の件名、支出先が公開されてから監査請求までにさほどの準備を要するとは思われず、また本件会合から4年以上経過していることも合わせると、前記文書公開から3か月余を経過してなされた住民監査請求は相当期間内に請求したとはいえないとした事例 東京地判平10.11.12判例地方自治190.32
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 普通地方公共団体の住民が適法に住民訴訟を提起するためには、当該住民訴訟の対象とする財務会計上の行為又は怠る事実について監査請求を経ているだけではなく、その監査請求が適法なものであることをも要するところ、原告が本訴において違法な財務会計上の行為として問題としている本件各会議に係る支出負担行為は、いずれもX年度中にされたものであり、他方、本件監査請求はX+5年9月1日にされたものであるので、本件監査請求が(地方自治)法242条2項本文の定める監査請求期間経過後にされたものであることは明らかである。したがって、本件訴えが適法な監査請求を経たものといえるか否かについては、原告が監査請求期間経過後に監査請求をしたことについて「正当な理由」(同項ただし書)があるか否かによって決せられることになる。
○ この点につき、原告は、東京都が本件各会議の件名や経費の支出先である債権者名を非公開にしていた以上、原告は被告らの不正・違法行為を知ることができなかったものであり、原告は、右の情報が公開されたX+5年5月24日から4か月以内という相当な期間内に本件監査請求を行っているのであるから、本件各会議に係る支出負担行為については、監査請求期間経過後に監査請求をすることにつき正当な理由がある旨主張する。
○ しかしながら、原告の右主張は採用することができない。その理由は次のとおりである。
法242条2項本文は、監査請求について、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができないと規定しているところ、法が監査請求についてこのような期間制限を設けたのは、普通地方公共団体の執行機関又は職員の財務会計上の行為がたとえ違法・不当な場合であっても、いつまでもこれを監査請求ないしは住民訴訟の対象となり得るものとしておくことは、法的安定性を損ない好ましくないとの理由によるものである。しかし、普通地方公共団体の執行機関又は職員により当該行為の存在自体が秘匿され、あるいは当該行為自体は公然とされたものであってもその内容を偽るなど当該行為について仮装、隠ぺい行為が行われ、右仮装、隠ぺい行為の存在が当該行為があった日又は終わった日から1年を経過した後に初めて明らかになった場合などにおいても、右の趣旨を貫くことは相当でないことから、法242条2項ただし書は、「正当な理由」があるときは、例外として、当該行為があった日又は終わった日から1年を経過した後であっても、住民において監査請求をすることができるものとしたのである。したがって、普通地方公共団体の執行機関又は職員が行った財務会計上の行為について、前示のような仮装、隠ぺい行為が行われた場合には、法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるかどうかは、特段の事情がない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて隠ぺいされた当該行為を知ることができ、又は当該行為について仮装行為が行われたことを疑うべき相当な事情があることを知ることができたかどうか、また、当該行為の存在を知ることができ、又は右仮装行為が行われたことを疑うべき相当な事情があることを知ることができたと認められる時から相当な期間内に監査請求がされたかどうかによって判断すべきものというべきである。
他方、普通地方公共団体の執行機関又は職員が行う財務会計上の行為には、内部的にされるものが多くあり、このような行為については、当該普通地方公共団体の住民がその存在及び内容を知らないことが通常であり、これらのすべてについて単に住民が当該行為の存在及び内容を知り得なかったということのみで、監査請求期間経過後に監査請求をすることにつき「正当な理由」があるとすることは、法が監査請求について期間制限を設けた趣旨を没却することになるのであって、法が監査請求について期間制限を設けた趣旨や監査請求期間の始期を「当該行為のあった日又は終わった日」とし、これを住民が当該行為のあったことを知ったか否か又は知ることができたか否かにかからしめていないことに照らしてみれば、普通地方公共団体の執行機関又は職員が行った財務会計上の行為について前示のような仮装、隠ぺい行為が行われていない場合において、監査請求期間経過後に監査請求をすることにつき「正当な理由」があるというためには、単に当該普通地方公共団体の住民が当該行為の存在及び内容を知り得なかったということのみでは足りず、天災地変等による交通途絶のため監査請求期間を経過したなど、他に監査請求期間経過後においても監査請求を認めることを相当とする特別の事情が存することを要するものと解するのが相当である。・・・
○ ・・・原告は、本件会議〈6〉は架空会議である旨主張しているところ、証拠・・・及び弁論の全趣旨によれば、被告Nは、報道部総務課長として、都庁記者クラブの一つであるKクラブとの懇談会(本件会議〈6〉)をX+1年1月11日午後6時30分からS社が経営する牡丹という宴会場において開催することを決定し、同社との間で右懇談会における料理等の提供に係る契約を締結したこと、X+1年2月12日、S社からの請求に基づき、本件会議〈6〉に係る料理等の代金として同社に対し5万8308円を口座振込の方法により支払う旨の本件支出命令書が発出され、これに従い同月24日に口座振込の手続がとられ、同月26日に同社の当座預金口座に右振込による入金があったこと、本件支出命令書に添付されたS社作成名義の本件請求書には、酒類の単価として、ビール800円、酒900円、ウイスキー1万円との記載があり、また、サービス料として、料理等の代金の10パーセントに当たる4万8740円を請求する旨の記載があること、X+5年1月の時点での牡丹における料理等の料金やサービス内容等を記載した「牡丹の御案内」には、酒類の単価として、ビール(大瓶)330円、酒(銚子一本)310円、ウイスキー(ボトル一本)4500円又は5000円と記載されており、また、牡丹においては、客4、5名に対し1名の割合で接待係がサービスをし、サービス料は、接待係1名につき15分間825円(一時間3300円)で計算する旨記載されていること、東京都は、東京都が行う「飲食を件う随時の会議」(個々の事業の円滑な推進を図るために、必要に応じ、各局の判断で様々な関係者と随時に懇談を行い飲食を提供するものであり、本件各会議もこれに分類されるものである。)に係る支出に関し、不正支出があるのではないかとの疑惑が持たれてきたことから、都監査委員に対しX+3年度の「飲食を伴う随時の会議」に係る支出について調査を依頼したところ、X+4年11月8日、都監査委員から、「飲食を伴う随時の会議」に係る契約・会計事務について重大な不適正処理の事例が多数があるとの監査結果が報告されたこと、そのため、東京都においては、X+1年度及びX+2年度の「飲食を伴う随時の会議」に係る支出についてもその実態を調査し、再発防止策と支出された会議費のうち不適正の度合が重大であるものの返還方法等について検討するため、同日、総務局を所管する副知事を長とする改善検討委員会を設置したこと、改善検討委員会は、同月20日、委員会報告書を発表したところ、同報告書によれば、同委員会の調査において、X+1年度からX+3年度までの「飲食を伴う随時の会議」に係る契約・会計事務について、契約金額でみて全体の約7割に「つけ払い」(委員会報告書に記載された「つけ払い」の概要は、別紙記載のとおりである。)などの重大な不適正処理があったことが確認されていることが認められる。
○ 右認定のとおり、東京都におけるX+1年度からX+3年度までの「飲食を伴う随時の会議」に係る契約・会計事務については、契約全額でみて全体の約7割に「つけ払い」などの重大な不適正処理があったことが確認されているところであり、本件会議〈6〉はX年度に開催されたとされるものであるが、X年度とX+1年度ないしX+3年度において、「飲食を伴う随時の会議」に係る契約・会計事務の処理状況に大きな変化があったことをうかがわせる事情は認められないから、本件会議〈6〉についても、何らかの不適正な処理が行われた可能性を否定できないのみならず、本件請求書に記載された酒類の単価等と「牡丹の御案内」に記載された酒類の単価等を比較すると、両者の間には食い違うところがあるのであって、このことは、本件会議〈6〉に係る支出負担行為において、その内容を偽るなどの仮装行為が行われたのではないかという疑いを抱かせるものである(なお、前記認定のとおり、「牡丹の御案内」に記載された料理等の料金やサービス料の計算方法は、X+5年1月時点のものであり、本件会議〈6〉が開催されたとされるX+1年1月当時の牡丹における料理等の料金やサービス料の計算方法が、右の「牡丹の御案内」に記載されたとおりの内容であるとの立証はないが、酒類の単価についていえば、X+5年1月においてビール(大瓶)330円とされているのに、本件会議〈6〉が開催されたとされるX+1年1月におけるビールの単価が800円であったとは通常考え難いところである。)。
○ しかしながら、仮に本件会議〈6〉に係る支出負担行為にその内容を偽るなどの仮装行為が行われたものとしても、X+4年11月20日に委員会報告書が発表され、X+1年度からX+3年度までの「飲食を伴う随時の会議」に係る契約・会計事務について、契約金額でみて全体の約7割に「つけ払い」などの重大な不適正処理があったことが明らかになっていたのであるから、X年度に開催されたとされる本件会議〈6〉についても何らかの不適正な処理が行われたのではないかと疑われる状況にあった上、原告の主張によれば、X+5年5月24日には、公文書公開条例により、本件会議〈6〉の件名及び経費の支出先である債権者名が開示されたというのであるから、これを前提とすれば、少なくとも、原告としては、本件会議〈6〉の件名及び経費の支出先である債権者名が開示されたX+5年5月24日の時点において、本件請求書に記載された酒類の単価等と本件会議〈6〉が開催されたとされるX+1年1月当時の牡丹における酒類の単価等を比較することにより、本件会議〈6〉に係る支出負担行為について仮装行為が行われたことを相当の根拠をもって疑うことができたものということができる。したがって、少なくとも、原告としては、本件会議〈6〉に係る支出負担行為について監査請求をする場合には、本件会議〈6〉の件名及び経費の支出先である債権者名が開示されたX+5年5月24日の時点から相当な期間内に監査請求をする必要があるところ、本件請求書に記載された酒類の単価等と本件会議〈6〉が開催されたとされるX+1年1月当時の牡丹における酒類の単価等が異なるか否かということは比較的容易に調査することができることであり、本件会議〈6〉に係る支出負担行為について監査請求をするためにさほど準備期間を要するとは思われないこと、本件会議〈6〉の件名及び経費の支出先である債権者名が開示された時点において、本件会議〈6〉に係る支出負担行為が行われたとされる時から既に4年3か月以上が経過しており、法的安定性の確保という観点からすれば、右支出負担行為に対する監査請求は可及的速やかにされるべきものであることなどを考慮すると、本件会議〈6〉の件名及び経費の支出先である債権者名が開示された時点から3か月以上経過した後にされた本件監査請求は、仮装行為が行われたことを疑うべき相当な事情があることを知ることができたと認められる時から相当な期間内にされたものと認めることはできない。そして、他に本件会議〈6〉に係る支出負担行為について右の相当期間経過後においても監査請求を認めることを相当とする特別の事情が存するものとは認められないから、右支出負担行為については、法242条2項ただし書にいう、監査請求期間経過後に監査請求をすることについての「正当な理由」があるものと認めることはできない。
○ そうすると、本件監査請求は、本件各会議に係る支出負担行為のいずれとの関係でも、法242条2項の定める監査請求期間を徒過した不適法なものというべきであるから、本件訴えは、適法な監査請求を経ていない不適法な訴えというべきである。
多数の所有者から購入した土地のうち1件のみ代金が著しく高額であることに対する住民監査請求について、土地価格の適正性判断には現地調査が必要な事案であり、請求人が実際にこれを為した時点ではじめて当該土地単価の適正性が判明するものであるとして、監査期間経過後の請求についての正当な理由があり、かつ調査から1か月後になされたことについて相当期間内に請求がなされたとした事例 東京高判平11.9.21判例時報1704.47
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 監査請求は、違法又は不当な契約の締結等の行為のあった日から1年以内にしなければならないが、正当な理由があるときは、1年経過後であっても、することができる(地方自治法242条2項)。そして、地方公共団体が故なく情報の提供を拒む等の事情により当該行為が1年を経過してから明らかになった場合には、住民が当該行為の存在を知ることができた時から相当な期間内に監査請求をしたときは、正当な理由があるものというべきである。
○ 区は、X-1年7月からX年3月にかけて、本件施設用地として、本件土地を含む・・・地域の土地(土地登記簿上の面積合計12万1546・16平方メートル)を29名の所有者から総額10億7888万0408円で購入した。これらの土地の実測はせず、売買代金は、原則として、登記簿上の面積を基準に定められた。すなわち、本件土地の所有者宗教法人A寺以外の28名との売買契約においては、登記簿上の面積を基準として、平米単価7562円で代金が決められた。しかし、X年3月16日に締結された本件土地の売買契約の代金は、2億3525万8851円であり、登記簿上の面積を基準とすると平米単価2万3580円である。その理由について、区は、本件土地4筆のうち原判決別紙物件目録記載4の山林は、登記簿上の面積9917平米に対し、公図上はもっと大きく記載されており、業者に依頼して公図から面積を測定させたら5万2063.41平米もあったためであると説明している。ただし、A寺との売買代金が他と算定基準を異にし、登記簿上の面積による平米単価が約3倍にのぼることは、当時は明らかにされず、控訴人がこれらの事情を知ったのは、後のことである・・・。控訴人は、X+1年5月ころ、本件施設用地の取得問題を審議した区議会において、これらの土地には暴力団が関係している疑いがある旨の指摘があったことを知った。そこで、控訴人は、右用地取得に疑問を抱き、自分で調べてみることにした。控訴人は、X+1年7月16日、区長に対し、本件施設用地の売主、平米単価及び購入面積を明らかにすることを求める情報公開を請求した。区長は、X+1年7月29日、所有者別の土地の登記簿上の面積、買収金額等を明らかにしたが、土地の地番と所有者名(売主)については非公開とした。控訴人は、これにより、29名の所有者のうち、1名だけ平米単価が高いことを知ったが、その所有者が誰なのか不明であり、また、その土地の地番も明らかでなかったので、一部非公開としたことに対して異議申立てをした。控訴人の異議申立ては、区情報公開審査会に諮問された。区長は、X+1年10月28日、同審査会に対し、区政情報一部公開理由説明書を提出した。区長は、この説明書の中で、本件土地の登記簿上の面積は約1万平米であるが、公図上の面積を算定すると約5万2000平米となり、大きな隔たりがあるため、所有者と交渉した結果、平米単価が異なることになった、しかし、実際の面積に近い公図上の面積で計算すると、平米単価4519円となる旨説明している。そして、右理由説明書は、平X+1年11月2日ころ、控訴人に送付された。区長は、X+2年10月13日、本件土地の売買契約書・・・を公開すべきであるとの区情報公開審査会の答申に従い・・・売買契約書を公開する旨決定した。そして、控訴人は、X+2年10月15日、売買契約書を見て、本件土地の地番と売主がA寺であることを知った。その後、控訴人は、X+2年10月29日、土地購入代金の領収書等の情報公開を請求し、X+2年11月13日ころ、A寺への振込依頼書の写しを入手して、区が本件土地の売買代金を間違いなく支払っていることを確認した。控訴人は、本件土地の売買代金が他より高くても、本件土地が他の土地と比べて価値があるものであれば、違法・不当であると指摘することは難しいので、現地に行って本件土地の現況を確認する必要があると考えた。そこで、控訴人は、X+2年12月1日ころ・・・に行ったが、本件土地がどこにあるかわからなかった。控訴人は、X+3年1月22日ころ、現地の町役場に行って本件土地の場所を問い合わせ、おおよその位置を把握した。控訴人は、X+3年2月14日、再度現地に赴き、本件施設用地を見たところ、本件土地は、周囲の他の土地と何ら変わりのない、草の生えた荒地であることを知り、本件土地を他の土地の3倍の価格で購入する理由はないと考えるに至った。そこで、控訴人は、X+3年3月26日、本件土地の売買代金は高額にすぎることを理由とする本件監査請求を行った。
○ 本件監査請求は、本件土地の売買契約が締結されたX年3月16日から1年を経過した後にされたものである。そこで、本件監査請求が1年経過後にされたことについて、正当な理由があるかどうかを検討する。
○ ・・・認定事実によれば、控訴人は、X+1年7月29日、登記簿上の面積を基準とした平米単価が本件土地だけ高額であることを知ったが、区長が本件土地の所有者と地番を非公開としたため、本件土地の場所を知ることはできなかったこと、控訴人が区長の理由説明書・・・を入手したX+1年11月2日においても、このことに変わりはなかったこと、控訴人が本件土地の地番を知ったのは、区長が区情報公開審査会の答申に従い情報公開をしたX+2年10月15日であること、その後、控訴人は、本件土地の場所を調査した上で、X+3年2月14日に本件土地を検分することができたことが認められる。控訴人は、区が本件土地を不当に高額の代金で購入したことを問題としているものである。そして、土地の価値は、その所在、面積、形状その他の現況により左右されるものであるから、その価格の適否を判断するには、実際に現地を検分することが不可欠である。また、公図は、一般には土地の面積を知るための資料とはされていないことが認められる。そうすると、区が公図上の面積を参考としたことの当否を検討するため、控訴人が現地に出向いてその面積その他の現況を見るのは、当然の行動といわねばならない(なお、山林の売買において現地を測量することは一般に行われており、山林の価格は一般に低いものであることに照らすと、その測量の費用が被控訴人のいうような高額なものであるとは認められない。)。ところが・・・によれば、控訴人は、当初、本件土地の地番を知らされなかったため、現地を検分することができなかったものであり、本件土地を検分するのに不可欠な本件土地の地番を知ったのは、X+2年10月15日になってからである。そして、控訴人は、X+3年2月14日に本件土地を検分して、本件土地の購入が違法であると考えるに至ったものである。そうすると、控訴人が、本件土地の売買契約に控訴人が違法と主張する事由が存在することを知ったのは、X+3年2月14日になってからであったものと認められ、この認定を左右すべき証拠はない。なお、控訴人が本件土地の地番を知ってから本件土地を検分するまでに4か月かかっているが、控訴人は、会社員であり、会社勤めの合間に独力で調査したものであること、控訴人の住所と本件土地とは相当距離が離れていること、本件土地が広大な山林、原野の中の一画に存在する土地であること、一般に山林等の所在は、宅地や農地の場合と異なり、公図等を見ても直ちに現地にあてはめて確認することが困難なものであるのが通常であること(裁判官の経験に照らして顕著である。)に照らすと、4か月という調査準備期間が不相当に長期間であるとは認められない。
○ 被控訴人は、控訴人が本件監査請求で違法事由として主張しているのは、本件土地の売買代金が登記簿上の面積ではなく公図面積を基準にして定められたことであるが、控訴人はX+1年11月2日にはこの点を知っていた旨主張する。控訴人がX+1年11月2日ころに右の点を知ったことは、前記・・・認定のとおりである。また、控訴人が提出した本件監査請求書・・・には、本件土地の売買代金を公図面積を基準にして定めたことは不当である旨の記載がある。しかし、前記・・・事実によれば、控訴人は、本件土地を不当に高額な代金で購入したこと自体を問題にしているものである。このことは、控訴人が監査請求書の冒頭に、他の土地の平米単価は7562円であるのに、本件土地だけ2万3560円であり、その結果、本件土地の購入代金は約1億6000万円余分に支払われたものである旨記載していることからも明らかである。控訴人は、監査請求書において、この記載に続けて、公図面積を基準とすることの不当性を指摘しているが、これは、控訴人の問題提起に対し、区当局が本件土地の売買代金は公図面積を基準にして決定した旨の説明をしたから、これに対する控訴人の反論を記載したにすぎないものと認められる。被控訴人の右主張は、採用することができない。また、被控訴人は、控訴人は原審でX+2年11月13日にA寺に対する違法支出を知った旨認めていると主張する。しかし、控訴人は、訴状において、区長がX+2年10月13日に本件土地の所有者を公開する決定をしたことにより本件土地の売主がA寺であることを知り、X+2年11月13日、A寺に対する代金支払に関する情報公開により、代金支払を確認したと主張している。したがって、控訴人の主張全体からみると、被控訴人指摘の部分は、控訴人がX+2年11月13日にA寺に対する代金支払の事実を知ったという趣旨にすぎず、その時に違法事由の存在まで知ったという趣旨ではないものと認められる。なお、控訴人がその主張の違法事由を知ったのはX+3年2月14日であることは・・・のとおりである。この点に関する被控訴人の主張も採用することができない。
○ 以上のとおりであるから、控訴人は、本件土地の売買契約に控訴人主張の違法事由が存在することを知ったX+3年2月14日から相当な期間内(約1か月後)のX+3年3月26日に本件監査請求をしたものである。そうすると、控訴人の本件監査請求は、本件土地の売買契約から1年経過後にされたことにつき正当な理由があるから、適法な監査請求であると認められる。
公園用地買収価格が高額であるとする住民監査請求において、買収自体は正規の手続を経て行われており、秘密裡になされたものではないが、売買価格不適正価格の事実があるとするならば、売買価格の相当性に関する点が隠蔽されていた、つまりその行為自体が秘密裡になされた場合と同様にその違法性、不当性を判断する上で極めて重要な前提事実が隠されており、その結果として、行為が秘密裡になされたと同様に住民が相当の注意力をもって調査したとしても、監査請求の対象とすることができない状態にあったものというべきであるので、当該「正当な理由」の有無は、住民が相当の注意力をもって調査したときに、客観的にみて、売買価格の相当性に関する点が隠蔽されているのではないかとの合理的な疑いを持つことができた時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものであるところ、本件は本件契約の疑義について議会質問があった時を上記合理的疑いを持つことができた時とすべきであり、それから約2か月後の監査請求は、その間の文書公開請求等の調査に期間を要したことを考慮すれば、相当期間内になされたものとした事例 仙台高判平12.11.24判例地方自治214.86
【本件上告審 最判平14.9.17集民207.111 (下掲)で、監査対象財務会計行為について住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて監査請求をするに足りる程度にその存在及び内容を知ることができた時期についての判断に関し異なる判断を示したうえで本判決を破棄しているので注意】
(事実関係及び経過は下記参照)
○ (地方自治)法242条2項本文は、普通地方公共団体の執行機関・職員の財務会計上の行為は、たとえそれが違法・不当なものであったとしても、いつまでも監査請求ないし住民訴訟の対象となり得るとしておくことが法的安定性を損ない好ましくないとして、監査請求をなしうる期間を当該行為のあった日又は終わった日から1年内に制限したものである。しかし、事案によっては、右の趣旨を貫くことが相当でない場合もあるので、同項ただし書は、「正当な理由」があるときは、例外として、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過した後であっても、住民が監査請求をすることができると定めたものである。そして、右のとおり、法が、住民において当該行為があったことを知っていたか否かを問わず、監査請求をなしうる期間を1年という短期間に限定することによって、早期に財務会計上の行為の法的安定性を図ろうとしている趣旨に照らせば、当該行為が秘密裡に行われたため、請求期間経過後初めてその存在が明るみにでた場合のように、期間経過後においても、なお住民の監査請求を認むべき特別の事情がある場合でなければ「正当な理由」があるとすることはできない。
○ そこで、検討するに・・・によれば、次の事実が認められる。
控訴人らは、市で弁護士、税理士等の職業を有する市民であり、市の予算の執行状況について一般の住民に先んじてその内容を知りうる公職にある者ではない。
市は、昭和45年ころから、史跡景勝の丘陵地帯であるa山を公園として整備する計画を有し、当初はa山公園計画の実現のために公園予定地全部を取得するとの方針を決定していた。そして、昭和63年11月11日には、地権者を対象とする右計画についての説明会が開催され、その後も数回にわたり地権者に対する説明会が開催された。その後、市は、平成2年11月16日、a山公園について公園区域面積を変更する旨を決定・告示するとともに、買収予定区域を明示した都市計画案を縦覧に供し、同年12月14日にはa山公園整備事業の認可を得た。
市は、市公有財産価格審査委員会の審査を経て購入価格を決定した上、a山公園整備事業の公園用地として、平成3年3月13日、本件土地1について、被控訴人Wらの各持分を1平方メートル当たり17万円で買い受ける旨の契約を締結した(本件契約1)。なお、売買価格は、被控訴人Wの持分につき5億4259万0888円、同Xの持分につき3億2555万4533円、同Y建設の持分につき1億0851万8177円であった。そして、本件土地1について、平成3年3月26日、市に対し、同月13日売買を原因とする共有者全員持分全部移転の登記がなされ、さらに、同月29日、被控訴人Wらに対し右売買代金が全額支払われた。本件土地1は、同月30日、市土地台帳に記載された。また、市は、平成3年12月2日、本件土地2について、被控訴人Wらの各持分を1平方メートル当たり18万0700円で買い受ける旨の契約を締結した(本件契約2)。なお、売買価格は、被控訴人Wの持分につき7778万1311円、同Xの持分につき4666万8786円、同Y建設の持分につき1555万6262円であった。そして、本件土地二について、平成3年12月9日、市に対し、平成3年12月2日売買を原因とする共有者全員持分全部移転の登記がなされ、同月25日、被控訴人Wらに対し右売買代金が全額支払われた。本件土地2は、平成4年9月30日、市土地台帳に記載された。なお、市は、不動産鑑定士による鑑定評価額を資料として本件契約1及び2の売買価格を決定したが、本件契約1による購入価格は、平成3年3月1日時点での正常価格のおよそ3倍から4.7倍にも達し、また、本件契約2による購入価格は、平成3年11月1日時点での正常価格のおよそ4.9倍に達するものであった。
市財産条例では、1万平方メートル以上の土地の取引については市議会の議決に付す旨定められている・・・が、本件土地1及び2の購入については1万平方メートル未満の土地の取引であったため、個別案件として市議会の議決に付されることはなかった。なお、a山公園整備事業については、市の平成2年度予算説明書において、その一般会計の歳出の部で、土木費の公園造成費の対象事業として、単独事業欄に「風致公園」として「a山公園」と記載され、同年度の決算説明書において、その一般会計の歳出の部で、土木費の公園造成費の対象事業として、補助事業及び単独事業の各欄に「風致公園」として「a山公園」と記載され、さらに、公共用地先行取得事業会計の歳出の部で、公共用地先行取得事業の事業費として「a山公園5294.1平方メートル、900,000千円」と記載されているほか、さらに、平成3年度の予算説明書において、その一般会計の歳出の部で、土木費の公園造成費の対象事業として、補助事業欄に「特殊公園」として「a山公園」と記載され、同年度の決算説明書において、その一般会計の歳出の部で、土木費の公園造成費の対象事業として、補助事業及び単独事業の各欄に「特殊公園」として「a山公園」と記載され、公共用地先行取得事業会計の歳出の部には、公共用地先行取得事業の事業費としてa山公園についての歳出の記載はないが、一部別会計に移された分について歳入の部に記載されている。そして、これら予算及び決算説明書は一般の閲覧に供された。以上の事実が認められる。
○ このように、本件契約1及び2は、都市計画変更決定・告示及び地権者に対する説明会を経たa山公園整備計画の一環として、公衆の縦覧に供されている買収予定区域を明示した都市計画案に基づいて締結されたものであること、本件契約1及び2における売買価格は市公有財産価格審査委員会の審査を経て決定されていること、また、a山公園用地を取得するための事業費は、概括的ではあるが当該年度の予算に計上されて議会の議決を受けて支出されているほか、決算に計上されて議会の承認を受けており、さらに、これら審議の対象となった当該年度の予算及び決算説明書は一般の閲覧に供されていること、市が取得した本件土地1及び2は登記簿及び公有財産台帳に記載されており、これら台帳等は閲覧が可能であったことなどの事実によれば、本件契約1及び2は、その締結から代金の支払に至るまで、所定の手続に従って行われたことが明らかであって、秘密裡になされたものとすることはできない。しかしながら、控訴人らは、市と被控訴人Wらは、その売買価格が適正な価格をはるかに超える違法若しくは不当なものであることを隠蔽して本件契約1及び2を締結したと主張するものであるが、もし、そのような事実があるとするならば、本件契約1及び2には、売買価格の相当性に関する点が隠蔽されていたということができよう。そして、そのような場合には、本件契約1及び2には、その行為自体が秘密裡になされた場合と同様にその違法性、不当性を判断する上で極めて重要な前提事実が隠されており、その結果として、行為が秘密裡になされたと同様に住民が相当の注意力をもって調査したとしても、監査請求の対象とすることができない状態にあったものというべきである。したがって、本件契約1及び2に右のような事情が認められる場合には、「正当な理由」の有無の判断においては、本件契約1及び2が秘密裡になされた場合と同様に取り扱うべきであり、「正当な理由」の有無は、住民が相当の注意力をもって調査したときに、客観的にみて、売買価格の相当性に関する点が隠蔽されているのではないかとの合理的な疑いを持つことができた時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきである。
○ そこで、控訴人らは、どの時点で、本件契約1及び2における売買価格の相当性に関する点が隠蔽されているのではないかとの合理的な疑いを持つことができたかについて検討する。・・・によれば、次の事実が認められる。
市議会議員Dは、別件の用地買収について調査していた際に、a山公園の用地買収について問題があるとの情報を得て、市から各年度毎の各購入土地の所在、地積、単価等に関する資料の提出を受けて調査したところ、本件契約1及び2の買収価格の相当性が問題と思われたので、平成5年9月20日、市議会の一般質問において、市長に対し、a山公園における調整区域内の用地買収について、平成2年度及び平成3年度の買収価格が平成4年度のそれの4倍に近い異常な高値であったことを質したところ、市は、平成2年度及び平成3年度のa山公園用地の買収価格には疑問があり、現在調査中であることを明らかにした。
同月21日、市議会における右質疑の内容が新聞で報道されたが、その内容は、市は、a山公園の用地として市○区○○の土地を買収したが、平成2年度においては約9400平方メートルを1平方メートル当たり平均17万円で、平成3年度においては約1万2900平方メートルを1平方メートル当たり平均18万円で購入していたこと、ところが、平成5年3月、これまでの不動産鑑定士2人に代わって、別の不動産鑑定士に改めて土地の評価をしてもらったところ、平成4年度には約1万平方メートルの土地が1平方メートル当たり4万7747円で購入できたこと、市では価格が4倍も違うのはおかしいとして当時の不動産鑑定士などから鑑定の内容や購入に至ったいきさつなどを調査している、というものであった。
市長は、自ら、市監査委員に対し、平成5年10月6日、平成2年度及び平成3年度に市及び後記の土地開発公社が取得したa山公園整備事業用地の買取価格が不当に高額なものであるか否か等を監査対象事項とする監査請求を行った。
控訴人らは、前記新聞報道により、a山公園用地の取得価格に疑いを抱いて、平成5年10月8日、市に対し、市情報公開条例によりa山公園用地の売買契約書等の開示請求を行ない、同月22日に開示決定を受けたが、土地の所在、地番、地積、代金額は、右条例の非開示規定に基づき開示されなかった。そこで、控訴人らは、同年11月10日ころまでに、a山の公図、登記簿等を閲覧するなどして疑義のある売買契約がなされた土地の地番などを特定する作業を行った。
○ 控訴人F、同Gらは、市監査委員に対し、同年11月25日、平成2年度と同3年度におけるa山公園の用地買収につき監査請求を行った(なお、控訴人Fの監査請求書・・・では、監査の対象として、本件土地1及び2の地番、地積、買取価格等が個別的かつ具体的に特定されている。)ところ、市監査委員は、平成6年1月20日、本件土地1及び2の買取価格が不当に高額であるおそれも有すると判断するが、その立証・確定はなしえないので措置の勧告(地方自治法242条3項)をするまでには至らず、これに代えて市長に対し監査結果に基づく意見(地方自治法199条10項)を提出した旨を通知した。以上の事実が認められる。
○ 以上認定した事実、特に、平成5年9月の市議会においてa山公園用地の買収価格を問題にしたD議員においても、別件の用地買収の調査過程で得た情報を契機に、市から本件契約1及び2の資料を取り寄せ、その具体的な内容を検討して初めて、本件契約1及び2が不当に高額であるとの疑いが持たれる価格で締結され履行されていた事実を知ることができたというのであり、また、市においても、そのころから平成2年度及び平成3年度のa山公園用地の買収価格には問題があるとして調査を進め、平成5年10月6日に、市長自ら、市監査委員に対し、平成2年度及び平成3年度に市及び後記の土地開発公社が取得したa山公園整備事業用地の買取価格が不当に高額なものであるか否か等を対象として監査請求を行っていることに鑑みると、平成5年9月の市議会において、a山公園用地の買収価格の相当性に関する疑いが表面化するまでは、住民らが本件契約1及び2の売買価格の相当性に関する点が隠蔽されているのではないかとの合理的な疑いを持つことは著しく困難であったというべきである。なるほど、本件契約1及び2は、市公有財産価格審査委員会の審査を経て買収価格が決定されているほか、売買代金は概括的にではあるが市議会の議決を経て支出されるなど、所定の手続に従い公然と行われたものではあるものの、住民において、このような手続の流れの中では売買価格の相当性について疑いを差しはさむ余地はなかったものというべきであり、その一方、本件土地1及び2の購入については個別案件として市議会の議決に付されることがなかった関係上、市議会では本件契約1及び2について具体的に審議されたものではないから、住民らが市議会の審議の経過から本件契約1及び2の買取価格の相当性に疑いを抱くことは不可能に近かったものといわざるをえない。また、平成2年度及び同3年度の予算及び決算説明書にはa山公園整備事業に関する記載があり、いずれも住民の閲覧に供されてはいるけれども、それぞれの予算及び決算における事業や事業費の内容等の記載はいずれも概括的なものにすぎず、住民がa山公園の用地取得につき、その買取価格の相当性の点に疑いを抱く端緒となりうる資料としては十分なものとはいえない。なお、平成2年度の決算説明書には、公共用地先行取得事業会計の歳出の部に、公共用地先行取得事業の事業費として「a山公園5294.1平方メートル、900,000千円」との記載があるが、土地の取引価格は、その所在、地番、地積、形状、現況等により左右されるものであることに鑑みると、住民において、右の記載をもとに単純に取得金額を取得面積で除する方法によって、取引価格の相当性に関する点に疑いを抱く端緒となし得たとするのも適切でないというべきである。
○ 以上によれば、住民らが、相当の注意力をもって調査すれば、平成5年9月20日に市議会においてa山公園用地の売買価格の相当性に関する疑義が取り上げられ、これが翌日新聞報道された時点において、客観的にみて、本件契約1及び2の売買価格の相当性に関する点が隠蔽されているのではないかとの合理的な疑いを持つことができたものというべきである。
○ そこで、進んで、控訴人らが、右の時点から相当の期間内に本件監査請求をしたといえるかについて検討する。住民監査請求をするには、その対象となる本件契約1及び2を特定する必要があるが、前記の市議会での質疑及び新聞報道の内容などからだけでは、本件契約1及び2を特定し、その違法若しくは不当な事由を知ることは困難であったというべきである。ところで、法242条2項ただし書の趣旨に鑑みると、控訴人らは、本件契約1及び2の買収価格の相当性に関する疑いを抱くことができたと認められる時から速やかに監査請求をなすべきものであるが、事案の性格からみて、住民が、財務会計上の当該行為を特定し、その違法若しくは不当な事由を調査するための作業には相当の困難を伴うことが考えられ、その作業内容に照らせば、監査請求をするまでにある程度の期間を要することにも無理からぬものがあると認められる場合には、なお相当な期間内になされたものと解することができる。
○ 前記認定のとおり、控訴人らは、少なくとも平成5年9月21日の新聞報道により、a山公園用地の買収価格の相当性につき疑いを抱き、同年10月8日、市情報公開条例に基づきa山公園用地の売買契約書等の開示請求を行ない、同月22日に開示決定を受けたが、土地の所在、地番、地積、代金額は開示されなかったため、公図、登記簿等を閲覧するなどしてa山公園用地の所在、地番等を特定する作業を行い、同年11月10日ころ、ようやく、市が本件土地1及び2を不当ではないかと疑われる高額の代金で購入した事実を確認した上、同月25日に監査請求をしたものである。このように、控訴人らは、本件契約1及び2の買収価格の相当性に関する点が隠蔽されているのではないかとの合理的な疑いを持つことができた時から2か月余り経過して監査請求を行ったのであるが、本件事案の性格と控訴人らの調査のためにとった作業の内容からすれば、控訴人らが監査請求をするまでに2か月余りの期間を要したとしても無理からぬものがあるというべきである。
○ そうすると、控訴人らによる本件監査請求は、本件契約1及び2による売買代金の支払日から起算して1年経過後になされたことにつき正当な理由があることになるから、適法な監査請求であるというべきである。
当初から失敗必至であるテーマパーク事業への補助金支出は何らの公共性も公益性も認められないと主張する住民監査請求について、同違法事由を前提とすると、客観的にみてどの時点で監査請求をすべきか否かを検討し得る程度に具体的な内容を知ることができたか否かについては、事業化を厳しいと判断するコンサル報告書内容等が報道された時点であり、それから約4か月後になされた請求は相当期間内になされたものとはいえないとした事例 福岡地判平14.3.25判例地方自治233.12
(事実関係及び経過は下記参照)
○ (地方自治)法242条2項本文は、普通地方公共団体の執行機関、職員の財務会計上の行為は、たとえそれが違法・不当なものであったとしても、いつまでも監査請求ないし住民訴訟の対象となり得るとしておくことが法的安定性を損ない好ましくないとして、監査請求期間を定めたものである。他方、同項ただし書は、「正当な理由」があるときは、例外として、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過した後であっても、普通地方公共団体の住民が監査請求をすることができるとしているが、その「正当な理由」とは、前記242条2項本文の趣旨にかんがみ、特段の事情のない限り、①普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたかどうか、また、②当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものと解される(最高裁昭和63年4月22日第二小法廷判決・裁集民154号57頁参照)。また、前記「正当な理由」が本案前の監査請求期間の徒過が許されるか否かの場面で問題となることにかんがみれば、前記①の「当該行為を知ることができた」とは、普通地方公共団体の住民をして、当該行為について監査請求をすべきか否かを検討し得る程度に具体的な内容を知ることができたか否かを問題にすべきものと理解すべきである。
○ ・・・によれば、本件各支出については、それぞれB市の一般会計予算案(当初予算案、補正予算案)に計上され、本件会社に対する出資金又は補助金である旨の説明を経た上で、別紙「B市の本件会社に対する支出一覧表」中の「市議会議決」欄の日に市議会の議決を経て、支出命令機関であるB市長の命令に基づき出納機関である収入役により支出されたものであり、予算内支出として必要な手続を経た上で支出されているとともに、その後同市議会において決算認定を経ているものと認められる。他方・・・各年度の予算議決の概要が議決後約2か月後に市広報紙「広報B」により広報されるとともに、本件テーマパーク事業の概要も同広報紙にて広報されていることが認められる。よって、本件各支出の事実及びその内容は、各支出行為後間もない時期において、B市民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたものというべきである。次に・・・によれば、第9号事件(注:本件住民訴訟のうち市長に対する損害賠償代位請求部分)原告らが第9号事件監査請求において主張した本件各支出についての違法事由は、本件各支出が法232条の2「公益上必要がある場合」に当たらないことであり、具体的には、B市の財政状況からみると、P1(注:市が本事業の実現可能性評価を委託したコンサル会社。なおP1社は、投資予定額,入込客見込み等に基づく事業計画では事業化は極めて困難で,事業計画の変更(用地変更を含む)を要する旨の内容で,「テーマパークとして適正度に欠ける敷地で,今後競合が激化する九州の中にあって立地ハンディを負いながら,かつ,財務的にも極めて厳しいことが予測される状況で,あえて事業化を図る価値があるか甚だ疑問である」とする中間報告を提出した。なお市は他のコンサルにも事業計画案提示等を委託した)から本件会社に対し経営の失敗を予測した報告書が提出されて、当初から失敗必至であった本件テーマパーク事業へ支出することは、何らの公共性も公益性も認められないという点にあるものと認められる。
○ ここで、第9号事件原告らの主張する前記違法事由を前提として、客観的にみてどの時点において当該行為について監査請求をすべきか否かを検討し得る程度に具体的な内容を知ることができたか否かを検討するに、①・・・本件テーマパーク事業については、前記・・・「広報B」のほか、企画当初の構想、本件会社に対するB市の出資・支援態勢、用地変更、基本構想の変更、事業計画概要(収支見込みを含む。)、関連事業(アクセス道路等)、経営状況、本件経営再生計画(要旨)などについてB市議会において議論された概要が「B市議会報」により広報されていることが認められるとともに・・・によれば、地元新聞紙であるU新報やほかの新聞においても、本件テーマパーク事業に係るB市議会における議論の前記概要のほか、同市議会全員協議会における同事業に関する協議内容、本件会社の設立から本件テーマパーク閉園に至るまでの事実経過(事業計画の進捗状況、開園時の状況、開園後の経営状況、本件各損失補償契約の概要等)がその都度報道されていると認められること、②・・・本件各支出の公益性の有無の判断は、当該補助金の交付の目的、趣旨及び経緯、補助の対象となる事業の目的、性質及び状況、当該地方公共団体の財政状況、議会の対応等諸般の事情を総合的に判断して決せられるべきものであるところ、第9号事件原告ら指摘に係るP1の報告書は、本件各支出の違法性を判断するための一判断要素ではあるが、その性質上本件各支出の違法性を直ちに基礎づける根拠資料とはいい難いこと、③・・・によれば、平成9年12月16日開催のB市議会12月定例会の本会議において、B市長が本件テーマパーク事業について「当初計画の見通しに甘さがあったと言わざるを得ない」旨答弁した事実が同月17日のU新報において報道されたことが認められ、この時点において、当時の本件テーマパークの経営不振につき、計画段階での経営の見通しに要因があったことがB市民に対して表明されていたといえること、④・・・によれば、平成10年12月2日のU新報において、P1作成に係る中間報告書の存在及びその内容が「財務的に非常に厳しく、あえて事業化を図る価値があるのか疑問…」というものであったこと並びに上記中間報告書を受けて本件会社の取締役総務部長が同社長に「P1が結論を出しました。テーマパーク事業を方向転換するか、あるいは会社を解散するか。いまなら出資者に資金は全額返せる。これまでに使った分は資本金の定期預金金利で大半がまかなえます…」と迫ったことが明らかにされた報道がなされていたこと、⑤第9号事件原告らのうち原告Nは、昭和42年4月から平成2年1月4日までの間(昭和50年から54年までは除く。)、B市市議会議員の職にあり・・・本件テーマパーク事業が本格的に開始した平成元年当時には、B市議会内において本件テーマパーク事業に関し審議を行っていた総務委員会に同委員として継続的に参加していた者であると認められ、本件テーマパーク事業ないし本件各支出の問題点について一般住民よりは容易に知り得る立場にあったと認められること、以上の各事実からすれば、第9号事件原告ら主張に係る前記違法事由の根拠事実は遅くとも平成10年12月2日の時点においては第9号事件原告らに対して明らかになっており、客観的にみて、当該時点においては本件各支出について監査請求をすべきか否かを検討し得る程度に具体的な内容を知ることができたものというべきである。
○ この点、第9号事件原告らは、平成10年12月2日におけるU新報の前記報道においては、各コンサルタント会社の報告書の内容のごく一部が開示されたにすぎない旨主張する。しかしながら・・・によれば、U新報の前記④の報道が、原告Nが本件各支出に違法性があると判断した直接の要因であったことが認められ、また・・・現に第9号事件原告らは前記④の報道に基づいて監査請求をなし得ているものと認められるから、前記程度の報道であっても第9号事件監査請求をすべきか否かを検討し得る資料になり得たものというべきであって、第9号事件原告らの前記主張には理由がない。
○ そして、第9号事件監査請求は、平成10年12月2日から4か月弱を経た平成11年3月31日になされており、本件全証拠によっても前記・・・の報道後監査請求をするまでに4か月間弱を要すべき事情は認められないから、当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたものとはいえず、第9号事件監査請求が本件監査請求期間外支出から1年を経過した後にされたことについて法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるということはできない。よって、第9号事件原告らの訴えのうち、本件監査請求期間外支出に係る財務会計行為が違法であるとして損害賠償を請求する部分は、適法な住民監査請求を経ていないから、法242条の2第1項の要件を欠く不適法なものである。
警察本部の食糧費支出に対する住民監査請求について、本件支出は秘密裡になされたものではないが、支出関連書類について裁判により一部が開示されたことにより、その違法不当性を判断するための必要な事実が住民に明かされたのであり、違法性・不当性を判断する上で必要な事実が隠されていた場合に該当し、監査請求期間後の請求について正当な理由が認められること、文書開示から49日後にした請求は相当期間内になされたものとした事例 仙台地判平14.3.25判例地方自治238.105
(事実関係及び経過は下記参照)
○ (地方自治)法242条2項本文は、住民監査請求について、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができないと規定しているところ、同法が住民監査請求についてこのような期間制限を設けたのは、普通地方公共団体の執行機関又は職員の財務会計上の行為がたとえ違法・不当な場合であっても、いつまでもこれを住民監査請求ないしは住民訴訟の対象となり得るものとしておくことは、法的安定性を損ない好ましくないという理由によるものである。しかし、普通地方公共団体の執行機関又は職員により当該行為の存在自体が秘匿され、あるいは当該行為自体が公然とされたものであっても、当該行為の違法性・不当性を判断する上で必要な事実が隠され、この違法性・不当性を判断する上で必要な事実が当該行為があった日又は終わった日から1年を経過した後に初めて明らかになった場合などにおいても、この趣旨を貫くことは相当でないことから、同項但書は、「正当な理由」があるときは、例外として、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過した後にあっても、その住民において監査請求をすることができるものとしたのである。したがって、このように当該行為が秘密裡にされた場合、ないし当該行為の違法性・不当性を判断する上で必要な事実が隠されていたような場合、同項但書にいう「正当な理由」があるかどうかは、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民・・・が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為の違法性・不当性を判断する上で必要な事実を知ることができたかどうか、また、その事実を知ることができた時から相当な期間内に住民監査請求がされたかどうかによって判断すべきである。
○ これを本件についてみるに、本件支出は、いずれも予算に基づき支出決定、支出命令などの正規の手続きを経てなされたもの(当事者間に争いがない。)であり、その支出自体が秘密裡になされたものではない。しかしながら、・・・本件各文書は、○市民オンブズマンが、平成8年10月15日、県知事に対し本件開示請求を行い、同知事が決議書等について非開示決定処分を行ったことなどを不服として、同年12月26日、文書開示拒否処分取消請求訴訟・・・を提起し、平成12年4月25日、一部を除き非開示処分の取消しを命じる判決が言い渡されたことに基づいて、同年5月31日、○市民オンブズマンに開示された結果明らかにされたものである。そして、弁論の全趣旨によれば、本件各文書が開示される以前に、具体的に本件支出がなされたことを住民側が認識する機会は存在しなかったことが認められ、本件各文書の開示によって、本件支出の具体的な日時、金額、内容等などの本件支出を特定するに足る事項やこれを証する書面が住民に明らかにされたものということができる。したがって、本件支出の違法性・不当性の有無を判断する上で必要な事実についても、本件各文書の開示によって初めて住民に明らかにされたものというべきであり、本件支出については、その違法性・不当性を判断する上で必要な事実が隠されていた場合に該当すると認めるのが相当である。
○ したがって、本件において、法242条2項但書にいう「正当な理由」があるかどうかは、特段の事情がない限り、住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為の違法性・不当性を判断する上で必要な事実を知ることができたかどうか、また、その事実を知ることができた時から相当な期間内に住民監査請求がされたかどうかによって判断すべきである。本件においては、○市民オンブズマンは、本件支出がなされて1年を経過した後の平成8年10月15日に本件開示請求を行っており、この時点ですでに法242条2項本文の1年の監査請求期間を徒過しているところ、住民に対し探索的に情報公開請求を行うことを強いるのは相当でない反面、本件のように当該行為の違法性・不当性を判断する上で必要な事実を情報公開請求により知ることが可能な場合には、かかる情報公開請求を行うことが合理的にみて可能となった時点から速やかにその請求を行ったものでなければ、住民が相当の注意力をもって調査したということはできないものと解すべきである。
○ そこで、本件において、いつの時点で原告らにおいて本件開示請求が合理的にみて可能となったかについて検討する。
原告らが構成員となっている○市民オンブズマンは、県知事に対し、平成5年度の県財政課の食糧費関係文書の開示請求を行い、平成7年1月20日、同文書は懇談会の出席者・懇談場所・懇談目的を非開示とされた上、開示された。○市民オンブズマンは、開示された同文書から、カラ飲食の疑いがあることを発見し、また同年2月20日、このことが地元紙・・・の社会面のトップで報道され、県財政課の「カラ飲食」疑惑が一般社会にも表面化するに至った。○市民オンブズマンは、平成7年3月3日、上記の懇談内容を明らかにするために上記の非開示処分の取消しを求める訴えを仙台地方裁判所に提起した・・・。同年4月25日には、全国の市民オンブズマンが、平成5年度の各都道府県及び政令指定都市の秘書課、財政課、東京事務所の食糧費に関する一切の資料の公文書開示請求を行い、その結果、道府県の食糧費総額は約27億8000万円、10政令指定都市のそれは約1億7000円であり、その約80パーセントが接待・懇談費として支出されていたことが判明した・・・。○市民オンブズマンも、県議会及び県警を除く県庁の100近くの全ての部署の食糧費の調査を続け、その結果、同年6月7日には、平成5年度の県の食糧費総額が約8億8900万円にのぼっていることが判明した・・・。その後、○市民オンブズマンは、同年10月2日、県議会事務局の食糧費支出に関する一切の資料(平成4年4月から平成7年9月)について公文書開示請求を行い、さらに同年12月14日、上記請求に対する県知事の非開示処分に対し、行政不服審査法に基づく異議申立てを行った。さらに、○市民オンブズマンは、平成8年6月24日、県警本部総務室総務課職員の出張に関する一切の資料(平成6年、7年度)や県議会(議員及び職員)の出張に関する一切の資料(平成6年、7年度)などについての公文書開示請求を行い、さらに同年7月23日、県知事が行った同開示請求についての不受理通知(請求にかかる文書が公文書としては存在しないことを理由とする。)に対し、文書開示拒否処分取消請求訴訟を提起した。
平成8年7月29日、上記・・・文書開示拒否処分取消請求事件につき、出席者名簿、懇談場所、懇談目的の全面開示を命ずる判決が言い渡され・・・、これに基づいて、同年9月20日、平成5年度の県財政課を含む県の11課2出先機関の食糧費関係文書が全面的に開示された・・・。その結果、開示された懇談会2574件のうち、実際に懇談会の開催が確認されたのは1332件(52パーセント)であり、残りの48パーセントの懇談会が架空もしくは実施不明の懇談会であることが判明した(但し、県知事は、この時点では、不正な懇談会であることを否定していた。)。
その結果、○市民オンブズマンは、県警本部についても、情報公開請求により懇談会の実態を明らかにする必要があると考え、同年10月15日、県警本部総務室の食糧費にかかる本件開示請求を行った。なお、本件支出がなされた平成7年ないし同8年当時、本件条例は存在していたが、情報公開の対象となる実施機関には、公安委員会や県議会は除外されていた・・・。
○ 以上に認定した事実をもとに検討すると、平成7、8年当時の本件条例においては、公安委員会や県議会が実施機関から除外されており、現に、○市民オンブズマンが県警や県議会が所持する文書について情報公開請求を行っても、実施機関である県知事により、公文書性に欠けるとの不受理通知、ないしは非開示決定の処分がなされ、さらには、本件各文書にかかる文書開示拒否処分取消請求訴訟・・・は、訴え提起から第1審の一部認容判決がなされるまで約3年4か月の期間を要したことなどからすれば、住民が県警の所持する文書について開示請求を行っても、これらの文書の開示を受けることは直ちには期待しがたい状況にあったものということができる。また、平成7年2月20日に新聞報道がなされて以来、官官接待や「カラ飲食」の疑惑が度々報道され、さらに○市民オンブズマンの調査により、県の財政課をはじめ県の行政機関において、このような飲食がなされている疑いが表面化したことは認められるが、そのことから必然的に県警本部においても、このような飲食がなされていると疑うことが容易であったとは考えにくく、むしろ、平成8年9月20日、県の財政課等の11課2出先機関の食糧費関係文書が全面的に開示されたことに伴い、県の行政機関の多くの部署において架空もしくは実施不明の懇談会の存在が濃厚となった時点において、これらの部署において違法・不正な懇談会が実施されていることが蓋然性をもって明らかになったということができ、さらには原告らが主張するように県警本部においても、このような懇談会が実施されている可能性があると考えられるに至ったものと捉えるのが相当である。
○ そうすると、この時点に至ってはじめて、住民にとって、県警本部の食糧費関係文書にかかる本件開示請求が合理的にみて可能となったと解すべきであり、○市民オンブズマンが、平成8年10月15日に本件開示請求を行ったことは、本件開示請求が合理的にみて可能となった時点から速やかにその請求を行ったということができる。したがって、当該情報が開示されたと合理的に認められる時点というのも、現実に本件各文書が部分的に開示された平成12年5月31日の時点と捉えるのが相当である。
○ これに対し、被告らは、原告らを構成員とする○市民オンブズマンの県の情報公開請求に関する平成7年、8年当時の活動状況、すなわち、平成7年10月には県議会事務局に関する文書について、平成8年6月には県警本部総務室総務課の文書についてそれぞれ公文書開示請求を行い、これに対する県知事の処分に対しては行政不服審査法に基づく異議申立て、文書開示拒否処分取消請求訴訟を提起して争っていたことからすれば、本件支出後の1年の期間内において、本件開示請求を行うことは十分に可能であり、本件支出から1年の期間内に本件開示請求を行わなかったことについて、相当の注意力をもって調査を行ったとはいえないと主張する。しかしながら・・・県の行政機関において違法・不当な懇談会が実施されていることが蓋然性をもって明らかとなったのは、平成8年9月20日に県の財政課等の11課2出先機関の食糧費関係文書が全面的に開示されてからであり、それ以前に、住民が県警本部についても同じ様な違法・不当な懇談会が実施されていることを予見した上で、情報公開請求を行うなどの調査をすることは相当な注意力をもってしても困難であったというべきである。また、○市民オンブズマンは・・・平成7年から同8年にかけて、県議会や県警本部に関する公文書の開示請求を行っている(県議会については食糧費及び出張費、県警本部については出張費)が、県議会や県警本部に対し、このような情報公開請求を行っていることをもって本件開示請求を行うことが合理的にみて可能であったと考えるのは相当ではなく(このように考えなければ、住民は探索的に情報公開請求を行うことを強いられることになりかねない。)、情報公開請求をすることが合理的にみて可能となったときから本件開示請求を行ったことをもって、住民が相当の注意力をもって調査したものということができると解すべきである。したがって、被告らの主張を採用することはできない。
○ 原告らは、本件文書が部分的に開示された平成12年5月31日から49日後である同年7月19日に本件監査請求を行っているところ、開示された文書に照らすと、平成7年度の県警本部総務室の食糧費支出に関する資料(本件各文書)を整理分析し、本件支出の違法性・不当性を根拠づけるとする事実を発見するには、この程度の日数は必要であると認められることから、相当な期間内に住民監査請求がなされたというべきである。
○ 以上からすれば、原告らにおいて、本件監査請求につき監査請求期間を徒過したことについて、法242条2項但書の「正当な理由」があるというべきである。
空港予定地のオオタカ保護対策調査委託業務に関する住民監査請求について、本件に関する議会質疑があり、その内容を知り得た時点で、相当の注意力をもって調査すれば監査請求が可能な程度の事実を知ることができ、監査請求期間経過後の請求に正当な理由はないとした事例 静岡地判平14.3.28判例地方自治232.84
(事実関係及び経過は下記参照)
○ ・・・委託料は、「款企画費、項 企画費、目 空港対策費、節 委託料」から支出されたものであり、X年度についてはX年度9月補正予算に、X+1年度及びX+2年度についてはそれぞれ当初予算に計上の空港整備計画推進事業費として執行され、支出後には議会にも報告されている。また、監視機構の設置等の経過等は・・・のとおりであるところ、その運営経費は、「款 企画費、項 企画費、目 空港対策費、節 その他の報償費、その他の旅費並びに使用料及び賃借料」から支出されたものでありもX+1年度及びX+2年度については、それぞれ当初予算計上の空港整備計画推進事業費として執行され、支出後には議会にも報告されている。
○ 本件各契約及び監視機構に係る報道、県議会審議の経過は次のとおりである。
X年8月1日付け読売新聞、日経新聞、静岡新聞に、県が検討委員会を設置し、○空港予定地と周辺のオオタカの調査、保護対策の検討に入ることとなった旨の報道がされた。
X年9月4日付け静岡新聞に、県が検討委員会を設置し、その委員長がSである旨の報道がされた。
X+1年5月17日付け読売新聞、静岡新聞に、○空港自然環境保全対策調査委員会(委員長はS)の報告書公表に関連して、県がオオタカについてはX+2年度まで継続調査をし、そのうえで保全対策を検討している旨の報道がされた。
X+1年9月10日付け静岡新聞(夕刊)及び同月11日付け朝日新聞、読売新聞、産経新聞、中日新聞に、監視機構が初会合を開き、委員長にSが選出されたこと及びオオタカはX+3年7月まで生態生息調査を実施するなどの内容の環境監視計画案を県が監視機構に提出したことが報道された。
X+1年11月6日付け読売新聞、日経新聞、静岡新聞に、県が示した○空港の環境監視計画案を監視機構が了承した旨の報道がされた。
X+1年11月18日付け日経新聞に、県が市民団体の請求していたオオタカの生息調査に関する業務委託契約書などを開示した旨の報道がされた。
県議会のX+2年6月定例会の本会議(公開)において、同年7月23日、当時県議会議員であった原告Hは県がX-1年度からX+3年度までS研究所に随意契約で調査委託しているのは問題である旨の質問をし、さらに、同年7月31日に同旨及び検討委員会の委員長と監視機構の委員長が同一人物であり、かつ、監視機構の有力メンバーの1人が事実上、検討委員会の責任者であるのは問題である旨の討論をした。そして、これらの質問、討論は会議録に登載されて、X+2年9月下旬には一般県民の閲覧に供された。
○ ところで、普通地方公共団体の執行機関・職員の財務会計上の行為について住民訴訟を提起するには、適法な住民監査請求を経なければならないところ、(地方自治)法242条2項本文は、法的安定性の見地からその期間を当該行為のあった日又は終わった日から1年と定めている。しかし、当該行為が普通地方公共団体の住民に隠れて秘密裡にされ、1年を経過してからはじめて明らかになった場合等にも上記の画一的な扱いをすることは相当でない。そこで、同項但書は、「正当な理由」があるときは、例外として、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過した後であっても、住民が監査請求をすることができるとしている。したがって、上記のように当該行為が秘密裡にされた場合、同項但書にいう「正当な理由」の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたかどうか、また、当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきである(前掲の最高裁昭和63年4月22日第2小法廷判決)。
○ これを本件についてみると・・・、X年度契約、X+1年度契約及びX+2年度契約は公然と予算内の支出負担行為としてなされ、また、X+1年度支出及びX+2年度支出も公然と予算内の支出としてなされたものであって、秘密裡になされたものではないことは明らかである。そして、原告Hについては、遅くとも・・・質問及び討論を行ったX+2年7月31日ころまでには、また、その余の原告らも遅くとも・・・会議録が一般県民の閲覧に供された同年9月下旬ころまでには、相当の注意力をもって調査すれば、上記各契約、上記各公金支出につき監査請求が可能な程度の事実(本件各契約が随意契約により締結されていること及びS・・・が検討委員会の委員(長)と監視機構の委員(長)を兼任していること)を知ることができたというべきである。そうすると、本件各監査請求は、上記時期(原告HについてはX+2年7月31日、その余の原告らについてはX+2年9月下旬)から1年以上を経過して行われたことになるが、この期間超過については正当な理由があるとはいえないことは明らかである(なお、X+2年度支出のうち同年6月29日の支出以外の支出は、上記時期にはまだなされていなかったが、支出の問題点を知ることができたのであるから、監査請求が支出(当該行為)から1年を経過したことに正当理由がないことは明らかである)。
○ したがって、原告らが、X年度契約、X+1年度契約、X+2年度契約、X+1年度支出及びX+2年度支出に関し、監査請求期間を徒過したことに正当な理由があるとはいえない。
【最高裁判例】 自治体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知ることができなかった場合には,地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由の有無は,特段の事情のない限り,当該自治体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきである 最判平14.9.12民集56.7.1481
(事実関係(時的経過)については上記リンク先を参照されたい)
○ 法242条2項本文は,普通地方公共団体の執行機関,職員の財務会計上の行為は,たとえそれが違法,不当なものであったとしても,いつまでも監査請求ないし住民訴訟の対象となり得るものとしておくことが法的安定性を損ない好ましくないとして,監査請求の期間を定めている。しかし,当該行為が普通地方公共団体の住民に隠れて秘密裡にされ,1年を経過してから初めて明らかになった場合等にもその趣旨を貫くのが相当でないことから,同項ただし書は,「正当な理由」があるときは,例外として,当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過した後であっても,普通地方公共団体の住民が監査請求をすることができるようにしているのである。したがって,上記のように当該行為が秘密裡にされた場合には,同項ただし書にいう「正当な理由」の有無は,特段の事情のない限り,普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたかどうか,また,当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである(最高裁昭和62年(行ツ)第76号同63年4月22日第二小法廷判決・裁判集民事154号57頁参照)。そして,このことは,当該行為が秘密裡にされた場合に限らず,普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができなかった場合にも同様であると解すべきである。したがって,そのような場合には,上記正当な理由の有無は,特段の事情のない限り,普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである。
○ 前記事実関係によれば,支出金ア及び支出金イに係る各支出は,支出決定書及び支出命令書において種別,科目及び支出理由を明らかにしてされたものではあるが,その具体的な使途については,(担当室長)が持っていた領収書と会計規則に準じて作成した金銭出納帳に記載されていたというのである。そして,記録によれば,① X+1年12月12日,F新聞及びG新聞は,同月11日開催の市議会普通決算特別委員会において,X年度中に報償費名目で(担当)室長あてに3回に分けてされた計340万円の各支出は領収書等がなく使途を明らかにしないまま行われた不明朗な支出である旨が指摘された事実を報道したこと,② 同月13日,E新聞は,同月12日開催の市議会厚生委員会において,市のX年度決算の中に報償費名目で(担当)室長あてにされた計340万円の各支出は領収書等がないまま行われた不明朗な支出である旨が指摘された事実を報道したことが明らかである。
○ そうすると,遅くともX+1年12月13日ころには,市の一般住民において相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて監査請求をするに足りる程度に本件各財務会計行為の存在及び内容を知ることができたというべきであり,第1審原告らが同日ころから相当な期間内に監査請求をしなかった場合には,法242条2項ただし書にいう正当な理由がないものというべきである。
○ 本件各財務会計行為についての上記各新聞報道に基づき,監査請求の対象を特定してその違法事由を監査請求書に摘示することは,十分可能であったところ,記録によれば,本件監査請求に関し,第1審原告AについてはX+2年1月20日付けで,その余の第1審原告らについては同年2月17日付けで,それぞれ自己名義の監査請求書が作成され,同日付けで第1審原告ら代理人名義の事実調査報告書が作成されていることが明らかであるから,第1審原告らがこれらの文書を作成していたにもかかわらず,本件監査請求のあった同年3月7日に初めて監査請求をしたものであるとすれば,上記の相当な期間内に監査請求をしたものということはできない。
○ しかし,第1審原告らの主張するところによると,第1審原告らは,同年2月17日に上記各監査請求書及び事実調査報告書を提出しようとしたが,受理されなかったために,同年3月7日に配達証明付き書留郵便でこれらの書類を送付して本件監査請求をしたというのである。仮にそのような事実があるとすれば,X+1年12月13日を基準とする限り,相当な期間内に監査請求がされたものということができる。
【最高裁判例】 上記仙台高判平12.11.24上告審
市が公園用地とするために買い受けた土地の売買契約の締結及び売買代金の支出について住民監査請求がされた場合において,買収予定区域を明示した都市計画案の縦覧並びに市への所有権移転登記及び市土地台帳への登録がされ,市の決算説明書の記載から1㎡当たりの売買価格の平均値が明らかとなっていたなどの事実関係の下においては,上記決算説明書が一般の閲覧に供されて市の住民がその内容を了知することができるようになったころには,市の住民が相当の注意力をもって上記各書類を調査すれば客観的にみて上記売買契約の締結又は売買代金の支出について監査請求をするに足りる程度にその存在及び内容を知ることができたというべきである 最判平14.9.17集民207.111
○ 原審の確定した事実関係等の概要は,以下のとおりである。
市は,昭和45年ころ,史跡景勝の丘陵地帯であるa山を公園として整備するa山公園計画を有していた。市は,同63年11月11日以降数回にわたり,公園予定地の地権者を対象とした同計画の説明会を開催し,平成2年11月16日,a山公園について公園区域面積を変更する旨を決定して告示するとともに,本件各土地を含む買収予定区域を明示した都市計画案を縦覧に供し,同年12月14日,a山公園整備事業の認可を受けた。
市は,不動産鑑定士による鑑定評価及び仙台市公有財産価格審査委員会の審査を経て売買価格を決定した上,平成3年3月13日,上告人らから,a山公園整備事業の公園用地として,本件土地1を1㎡当たり17万円の価格で買い受ける旨の本件契約1を締結した。本件土地1について,同月26日,本件契約1を原因とする上告人らから市への共有者全員持分全部移転の登記がされ,同月30日,閲覧が可能であった市土地台帳にも登録された。市は,同月29日,上告人らに対し,平成2年度予算の執行としてその売買代金を支払った。 また,市は,同様の手続を経た上,平成3年12月2日,上告人らから,a山公園整備事業の公園用地として,本件土地2を1㎡当たり18万0700円の価格で買い受ける旨の本件契約2を締結した。本件土地2について,同月9日,本件契約2を原因とする上告人らから市への共有者全員持分全部移転の登記がされ,同4年9月30日,市土地台帳にも登録された。市は,同3年12月25日,上告人らに対し,平成3年度予算の執行としてその売買代金を支払った。 本件土地1の上記売買価格は,同年3月1日時点における正常価格の約3倍から4.7倍であり,本件土地2の上記売買価格は,同年11月1日時点における正常価格の約4.9倍であった。
a山公園整備事業については,市の平成2年度予算説明書には,一般会計の歳出の部の土木費(款),公園造成費(項)の「説明」欄に「単独事業,風致公園,a山公園」との記載がある。同年度決算説明書には,一般会計の歳出の部の土木費(款),公園造成費(項)の「説明」欄に「補助事業,風致公園,a山公園」との,公共用地先行取得事業会計の歳出の部の公共用地先行取得事業の「事業費」欄に「a山公園5294.1㎡,900,000千円」との記載がある。同3年度予算説明書には,一般会計の歳出の部の土木費(款),公園造成費(項)の「説明」欄に「補助事業,特殊公園,a山公園」との記載がある。同年度決算説明書には,一般会計の歳出の部の土木費(款),公園造成費(項)の「説明」欄に「補助事業,特殊公園,a山公園」との記載があり,a山公園に係る歳出に関して一部別会計に移された分につき,公共用地先行取得事業会計の歳入の部に記載がある。上記各予算説明書及び決算説明書は,いずれも一般の閲覧に供されていた。
市議会議員Dは,市が行った別の用地取得について調査をしていた際,a山公園用地の買収について問題があるとの情報を得,市から各年度ごとの各購入土地の所在,地積,単価等に関する資料の提出を受けて調査したところ,本件各契約の売買価格に問題があると考え,平成5年9月20日に開かれた市議会の一般質問において,a山公園に係る平成2年度及び同3年度の取得用地の売買価格が同4年度のそれの4倍に近い異常な高値であったことについて質問をした。市は,上記売買価格に疑問を持ち,調査中であることを明らかにした。翌21日,上記質疑の内容が新聞で報道された。その新聞記事には,市は,同2年度においてa山公園用地として・・・の土地約9400㎡を1㎡当たり平均17万円で購入し,同3年度において同様に同所の土地約1万2900㎡を1㎡当たり平均18万円で購入したこと,市は,平成5年3月,それまで依頼していた不動産鑑定士とは別の不動産鑑定士に依頼して改めて取得予定地の鑑定評価をし,平成4年度において約1万㎡の土地を1㎡当たり4万7747円で購入したこと,市は,同2年度及び同3年度当時の鑑定内容や購入に至ったいきさつなどを調査していることなどが記載されていた。
被上告人らは,平成5年10月8日,市情報公開条例に基づき,a山公園用地の売買契約書等の開示請求を行い,同月22日,請求に係る文書のうち土地の所在,地番,地積及び代金額部分が非開示とされ,その余の部分が開示された。被上告人らは,同年11月10日ころまで,公図,登記簿謄本等を閲覧するなどして,疑義のある売買契約がされた土地の地番等を特定する作業を行い,同月25日,本件各土地の取得に関し,代金額を正当な価額に是正し,市の被った損害を賠償させる等の適切な措置を講ずることを求める監査請求(以下「本件監査請求」という。)をした。監査委員は,同6年1月20日,被上告人らに対し,本件各契約における売買価格が不当に高額であるおそれがあるものの,その立証,確定をし得ないので措置の勧告をするまでには至らず,これに代えて,市長に対し監査結果に基づく意見を提出した旨を通知した。
記録によれば,上記平成3年度決算説明書中のa山公園に係る歳出に関して公共用地先行取得事業会計の歳入の部に移された分は,同会計の歳入の部の公共用地先行取得事業収入(款),財産収入(項),財産売払収入(目),土地建物(節)に「a山公園1435.6㎡,249,208千円」と記載されたものであることが明らかである。
○ 第1審は,本件監査請求は(地方自治)法242条2項本文の監査請求期間を経過した後にされたものであって,被上告人らの本件訴えは,適法な監査請求を経ていない不適法なものであるとして,これを却下すべきものとしたが,原審は,上記事実関係等に基づき,次のとおり判示して,本件監査請求について同項ただし書にいう正当な理由を認め,第1審判決を取り消して,本件を第1審裁判所に差し戻した。
法242条2項本文の趣旨に照らせば,財務会計上の行為が秘密裡に行われたため,監査請求期間経過後初めてその存在が明るみに出た場合のように,その経過後においてもなお住民の監査請求を認めるべき特別の事情がある場合でなければ,同項ただし書にいう正当な理由があるとすることはできない。
本件各契約は秘密裡にされたものではないところ,本件監査請求は,本件各契約の各売買代金支払時から起算しても,同項本文に定める1年の監査請求期間を経過している。しかしながら,被上告人らは,売買価格が適正な価格をはるかに超える違法又は不当なものであることを隠ぺいして本件各契約が締結されたと主張するものであるところ,そのような事実がある場合には,当該行為の違法,不当を判断する上で極めて重要な前提事実が隠されており,その結果として,住民が相当の注意力をもって調査したとしても監査請求の対象とすることができない状態にあったものというべきである。この場合には,本件各契約が秘密裡にされたと同様に取り扱うべきであり,同項ただし書にいう正当な理由の有無は,住民が相当の注意力をもって調査したときに,客観的にみて,売買価格の相当性に関する点が隠ぺいされているのではないかとの合理的な疑いを持つことができた時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきである。
本件各契約は所定の手続に従い公然と行われたものではあるが,住民においてその手続の中で売買価格の相当性につき疑いを差し挟む余地はなかったというべきである。また,平成2年度及び同3年度の各予算説明書及び決算説明書にはa山公園整備事業に関する記載があり,いずれも住民の閲覧に供されているが,その記載内容は概括的なものにすぎず,住民が売買価格の相当性の点に疑いを抱く端緒となり得る資料としては十分でない。結局,平成5年9月20日の市議会においてa山公園用地の売買価格の相当性に関する質疑がされ,その翌日にその内容が新聞で報道されるまでは,住民らが本件各土地の売買価格の相当性に関する点が隠ぺいされているのではないかとの合理的な疑いを持つことは著しく困難であったというべきである。そして,被上告人らは,上記の新聞報道により合理的な疑いを持つことができた時から2箇月余りを経過して本件監査請求をしているところ,事案の性格と被上告人らの調査のための作業内容からすれば,当該期間を要したことは無理からぬものがある。
以上によれば,本件監査請求は,法242条2項本文の監査請求期間経過後にされたものであるが,これにつき同項ただし書にいう正当な理由があるから,適法な監査請求であるというべきである。
○ しかしながら,原審の上記判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
(地方自治)法242条2項本文は,普通地方公共団体の執行機関,職員の財務会計上の行為は,たとえそれが違法,不当なものであったとしても,いつまでも監査請求ないし住民訴訟の対象となり得るものとしておくことが法的安定性を損ない好ましくないとして,監査請求の期間を定めている。しかし,当該行為が普通地方公共団体の住民に隠れて秘密裡にされ,1年を経過してから初めて明らかになった場合等にもその趣旨を貫くのは相当でないことから,同項ただし書は,「正当な理由」があるときは,例外として,当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過した後であっても,普通地方公共団体の住民が監査請求をすることができるようにしているのである。したがって,上記のように当該行為が秘密裡にされた場合には,同項ただし書にいう正当な理由の有無は,特段の事情のない限り,普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたかどうか,また,当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである(最高裁昭和62年(行ツ)第76号同63年4月22日第二小法廷判決・裁判集民事154号57頁参照)。そして,当該行為が秘密裡にされた場合に限らず,普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができなかった場合には,上記の趣旨を貫くのは相当でないというべきである。したがって,そのような場合には,上記正当な理由の有無は,特段の事情のない限り,普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである。
○ 本件監査請求は,本件各土地の売買価格が不当に高額であるとしてされたものであるところ,前記事実関係等によれば,本件各契約に関しては,a山公園整備事業都市計画案の縦覧並びに本件各土地につき市への所有権移転登記及び市土地台帳への登録が前記各日にそれぞれされており,平成2年度及び同3年度の各予算説明書及び決算説明書にa山公園用地取得のための事業費に関する記載があるというのである。そして,上記各決算説明書の記載によれば,a山公園用地の各年度の売買価格の平均値が1㎡当たり約17万円であったことが明らかとなっていたというべきである。そうすると,上記各決算説明書が一般の閲覧に供されて市の住民がその内容を了知することができるようになったころには,市の住民が上記各書類を相当の注意力をもって調査するならば,客観的にみて本件各契約の締結又は代金の支出について監査請求をするに足りる程度にその存在及び内容を知ることができたというべきである。ところが,上記各決算説明書が一般の閲覧に供されて市の住民がその内容を了知することができるようになった時期は,原審の確定するところではなく,記録上も明らかではないから,本件監査請求がその時から相当の期間内に行われたものであるか否かを判断することはできないといわざるを得ない。
【最高裁判例】 市有地の賃貸借契約の締結について住民監査請求がされた場合において,その締結に至る事実経過が逐一新聞報道され,同監査請求の請求人が,その入手した市の内部資料により上記契約における権利金及び賃料の算定根拠を知ることができ,これに基づいて自ら不動産鑑定士として監査請求の64日前に上記権利金及び賃料が適正な額より低いとする旨の意見書を作成したなどの事実関係の下においては,監査請求が上記契約の締結の日から1年を経過した後にされたことについて地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるとはいえない 最判平14.10.15集民208.157
(事実関係(時的経過)については上記リンク先を参照されたい)
○ 普通地方公共団体の執行機関,職員の財務会計上の行為が秘密裡にされた場合に限らず,普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができなかった場合には,(地方自治)法242条2項ただし書にいう正当な理由の有無は,特段の事情のない限り,普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである(最高裁平成10年(行ツ)第69号,第70号同14年9月12日第一小法廷判決・民集56巻7号1481頁,最高裁平成13年(行ツ)第38号,同年(行ヒ)第36号同14年9月17日第三小法廷判決・裁判集(民事)207号111頁参照)。もっとも,当該普通地方公共団体の一般住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて上記の程度に当該行為の存在又は内容を知ることができなくても,監査請求をした者が上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される場合には,上記正当な理由の有無は,そのように解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである。
○ 原審の適法に確定した事実関係によれば,本件賃貸借契約の締結に至る事実経過については逐一新聞報道されていたというのであるから,本件賃貸借契約が締結されたこと自体については,これに近接する時点において,市の一般住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみてこれを知ることができたということができる。そして,記録によれば,① 本件監査請求の代理人である弁護士は,X+1年11月10日ころ,市の内部資料を入手したが,その中には,本件賃貸借契約において定められた権利金及び賃料の算定根拠に用いられた本件土地の更地価格が1㎡当たり57万4750円であることを示す資料のほかに,X年4月1日時点の本件土地の1㎡当たりの更地価格を71万5000円とする鑑定評価書,これを64万9000円とする鑑定評価書が含まれていたこと,② 上告人は,X+1年11月17日付けで自ら不動産鑑定士として本件賃貸借契約における権利金及び賃料の額の適否について意見書を作成したが,その内容は,上記の権利金及び賃料の算定根拠となった本件土地の1㎡当たりの更地価格57万4750円は,類似地域の公示価格により算定される契約時点における1㎡当たりの更地価格74万4000円と比べて20%程度低くなっており,権利金及び賃料を総合すると,対象不動産の価値に比して低いと考えると結論付けたものであることが認められる。そうすると,上告人は,市の内部資料により本件賃貸借契約における権利金及び賃料の算定根拠を知ることができたのであり,これに基づいて,遅くともX+1年11月17日ころまでには,上記権利金及び賃料が適正な額より低いとする旨の不動産鑑定士としての意見を明らかにすることができたのであるから,そのころには既に本件賃貸借契約の締結について直ちに監査請求をするに足りる程度にその内容を認識していたというべきである。このような上告人の認識に基づいて考えると,X+2年1月20日にされた本件監査請求は前記の相当な期間内にされたものということができず,本件監査請求に法242条2項ただし書にいう正当な理由があるということはできない。
議員の海外視察旅行を対象とする住民監査請求について、報告書が公表されホームページで旅行の概要および報告書の閲覧方法が掲載された時点で、参加した市会議員、訪問先等の概要のほか日程の詳細を知ることが可能であり、これらを知り得た以上、その時点で、監査請求をするに足りる程度には、視察旅行について公金が支出されていること及びその内容を知ることができたというべきところ、その10か月後になされた監査請求は監査請求期間後の請求についての正当な理由がないとした事例 京都地判平16.9.22
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 市会事務局は、X年8月7日、同日の市会運営委員会でヨーロッパ視察を実施することが決定された旨の広報発表をし、それが、同月8日のA新聞の朝刊で報道された。また、同年9月5日発行の「市会旬報」にも、上記市会運営委員会でヨーロッパ視察について承認された旨及びヨーロッパ視察の結果の概要の報告が掲載されている。なお、「市会旬報」は、市会図書室において、市民等の閲覧に供されている。そして、これらの広報発表、記事には、いずれも、ヨーロッパ視察の期間、団員、出張目的、訪問都市及び主な視察項目が明らかにされていた。
市会事務局は、X年10月11日、第1アメリカ視察を実施する旨の広報発表をし、同月12日のB新聞の朝刊で報道されている。また、同年11月6日発行の「市会旬報」には、第1アメリカ視察の結果の概要の報告が掲載されている。これの発表、記事には、第1アメリカ視察の期間、団員、出張目的、訪問都市及び主な視察項目が具体的に記載されるか、その概要が記載されている。
ヨーロッパ視察及び第1アメリカ視察の結果は、その参加者によって、「X年市会欧州行政調査報告書」及び「X年市会米国行政調査報告書」という冊子にまとめて報告され、これら冊子は、X+1年2月ころ及び同年3月ころに、市会情報公開コーナーにおいて一般市民の閲覧の用に供されるなどした。これらの冊子には、ヨーロッパ視察及び第1アメリカ視察の詳細な行程も含まれている。X+1年4月2日から公開された市会のホームページには、ヨーロッパ視察及び第1アメリカ視察の概要及びその報告書の閲覧方法が掲載されている。
○ 以上の認定事実によると、市の一般住民は、相当な注意力をもってすれば、上記の新聞報道、市会旬報、調査報告書、市会のホームページなどにより、遅くともX+1年4月ころまでには、ヨーロッパ視察及び第1アメリカ視察について、参加した市会議員、訪問先等の概要のほか日程の詳細を知ることが可能であったというべきである。そして、これらを知り得た以上、その時点で、監査請求をするに足りる程度には、ヨーロッパ視察及び第1アメリカ視察について公金が支出されていること及びその内容を知ることができたというべきである。ところが、原告らが監査請求をしたのは、X+2年2月1日及び同年5月27日であって、X+1年4月から相当な期間内に監査請求をしたといえないから、公金の支出から1年以内に監査請求ができなかったことにつき正当な理由があるということはできない。
○ この点、原告らは、X+1年12月5日、本件各海外視察に関する支出命令等につき情報公開請求に基づき、支出命令書及びそれに添付された旅費明細、旅費法による旅費計算、旅程表などを入手して、初めて本件各海外視察が観光目的中心である疑いを持ったと主張する。しかし、上記のとおり、市の一般住民が相当な注意力をもってすれば、X+1年4月ころまでには詳しい旅行日程を知ることができ、同様の疑いを持つことは可能であったから、原告らは、同年12月5日に初めて上記の疑いを持ったとしても、そのことは・・・認定判断に影響するものではない(なお、旅費明細、旅費法による旅費計算を知らなくても、ヨーロッパ視察及び第1アメリカ視察が観光目的中心である疑いを持つ妨げとはならない。)。
○ したがって、原告らのヨーロッパ視察及び第1アメリカ視察に係る公金支出についての訴え・・・は、いずれも適法な監査請求を経ていないから、不適法である。
公用車運転手に対する賃金支払に関する住民監査請求について、請求人は町議会議員であり、本件支出の前提となる補正予算に関し質問を当局の答弁を得た経緯を踏まえれば、同補正予算成立時点で直ちに監査請求をするに足りる程度に本件支出命令の存在及び内容を認識することができたというべきところ、その10か月後になされた監査請求は相当期間内になされたものとはいえないとした事例 大分地判平16.9.27
(事実関係及び経過は下記参照)
○ ・・・によれば、本件監査請求(X+1年10月29日)が、X年7月5日の本件支出命令・・・から1年を経過した後にされたものであることは明らかである。そこで、期間経過につき、法242条2項ただし書にいう「正当な理由」が認められるかを検討する。
○ (地方自治)法242条2項本文は、普通地方公共団体の執行機関、職員の財務会計上の行為は、たとえそれが違法、不当なものであったとしても、いつまでも監査請求ないし住民訴訟の対象となり得るものとしておくことが法的安定性を損ない好ましくないとして、監査請求の期間を定めている。しかし、当該行為が普通地方公共団体の住民に隠れて秘密裡にされ、1年を経過してから初めて明らかになった場合等にもその趣旨を貫くのは相当でないことから、同項ただし書は、「正当な理由」があるときは、例外として、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過した後であっても、普通地方公共団体の住民が監査請求をすることができるようにしているのである。したがって、上記のように当該行為が秘密裡にされた場合には、同項ただし書にいう「正当な理由」の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたかどうか、また、当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである(最高裁昭和63年4月22日第二小法廷判決・裁判集民事154号57頁)。そして、このことは、当該行為が秘密裡にされた場合に限らず、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができなかった場合にも同様であると解すべきである。したがって、そのような場合には、上記正当な理由の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである(最高裁平成14年9月12日第一小法廷判決・民集56巻7号1481頁)。もっとも、普通地方公共団体の一般住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができなくても、監査請求をした者が上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される場合には、上記正当な理由の有無は、そのように解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである(最高裁平成14年10月15日第三小法廷判決・判例時報1807号79頁)。
○ X年6月15日、同年第2回町議会定例会において、公用車運転手賃金について210万円の増額を計上した同年度一般会計補正予算案(以下、単に「補正予算案」という。)が第49号議案として提出され、同議案は、審議の上、可決された。また、同年12月12日、同年第4回町議会定例会において、本件支出命令・・・に係る公用車運転手賃金について、37万2000円の増額を計上した同年度一般会計補正予算案(以下、「追加補正予算案」という。)が第72号議案として提出され、同議案は、審議の上、同月21日可決された。そして、上記補正予算の執行状況については、X+1年9月18日、町長から、X年度町一般会計歳入歳出決算が、同年第3回町議会定例会に提出され、同決算書には、歳出第2款第1項第1目第7節賃金の項目に「公用車運転手賃金」として244万8167円(不用額2万3833円)が計上された。
○ 原告は、X-8年2月以降、町議会議員の地位にあり、上記各定例会に出席し、補正予算案の審議、議決等に加わっていた。補正予算案について、原告は、X年6月の定例会において、既に4月から採用した公用車運転手・・・に対する給与が支払われていることを指摘し、予算の事前執行であって許されない旨の意見を述べた。また、追加補正予算案について、原告は、同年12月18日に開催された定例会の審議において、公用車運転手賃金の増額が計上されている理由について質問をし、D総務課長が、上記質問に対し、増額の理由として、同年4月に、退職した職員を公用車運転手として採用し、同人との間で、同年6月及び12月に賞与を支払う旨の嘱託契約を締結していたが、賞与分については、同年6月に提出した補正予算案に計上していなかったため、追加補正予算案に計上したこと、上記各賞与の支給については、既に執行済みであることを回答した。
○ ・・・の認定事実によれば、本件支出命令・・・が秘密裡にされたということはできず、原告は、遅くともX年12月18日には、町が、同年4月、Cとの間で嘱託契約を締結し、Cを公用車運転手として雇用したこと、Cに対し、同年6月及び12月に賞与が支給されたこと、Cに対する給料は補正予算案に計上され、その額は210万円であること、上記各賞与が追加補正予算案に計上され、その額は37万2000円であること等について、追加補正予算案の審議を通して認識していたということができる。そして、原告は、法98条ないし100条に規定する各権限を有する普通地方公共団体の議会の議員であって、上記認識に基づいて、町議会議員として相当の注意力をもって調査等をしたならば、本件各契約の内容等についても知ることが可能であったというべきであって、遅くとも、追加補正予算案が可決された同月21日には、直ちに監査請求をするに足りる程度に、本件支出命令・・・の存在及び内容を認識することができたというべきである。
○ このような原告の認識や地位等に基づいて考えると、同日から10か月以上を経過したX+2年10月29日になされた本件監査請求は、前記相当な期間内にされたものということはできず、本件監査請求に法242条2項ただし書にいう正当な理由があるということはできない。
福祉センター等の設計委託料を支出した後、財政難により着工延期としたところ、同委託料支出を違法とする住民監査請求について、住民が相当の注意力をもって調査すれば監査請求するに足る程度に対象行為の内容を知ることができたのは、財政難を理由に着工を延期したことを住民が知り得る状態になった時点であり、それから1年余の後になされた監査請求には監査請求期間後の請求についての正当な理由がないとした事例 神戸地判平16.11.9判例地方自治270.19
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 市長は、X年7月11日の市議会全員協議会において、財政難を理由に、複合福祉センターの建設着工の延期を表明し、同センターの建設着工が延期されることとなった。市議会全員協議会は、会議ごとに議場に諮って傍聴を認める旨決議するのが通例となっており、上記全員協議会についても、冒頭に傍聴を許可する旨決議しており、市の住民は傍聴することが可能な状態にあった・・・。また、上記市長の延期表明は、全員協議会の会議録に記録化されており、市の住民は、X+1年5月28日の時点では、同市の情報公開条例に基づき、同会議録を閲覧ないし謄写することが可能な状態にあった・・・。
上記の複合福祉センターの建設着工延期表明は、X年7月12日付けのA新聞朝刊により報道された・・・。また、その後も、X年8月9日付けA新聞朝刊、同年11月27日付けA新聞朝刊、翌X+1年2月26日付けB新聞朝刊においても、複合福祉センター建設着工延期に関する記事が掲載された・・・。
市長は、X年11月26日の市議会全員協議会において、すでに着工延期に追い込まれている複合福祉センターの建設を、図書館建設より優先させる旨の答弁を行い、また、同年12月21日の市議会定例会においても、財政難を理由に、X+1年度中に図書館の建設に着工することは無理である旨答弁し、計画通りに図書館の建設に着工することが事実上困難であることを表明していた。そして、市長は、X+1年5月27日の市議会定例会において、図書館の建設については、PFI手法(民間資金主導で事業推進を行う手法)の導入を検討する旨発言し(換言すれば、市の主導により、図書館建設事業を進めることはしない旨発言したこととなる。)、公式に図書館の建設着工の延期を表明した・・・。X年11月26日の市議会全員協議会についても、冒頭に傍聴を許可する旨決議しており、市の住民は傍聴することが可能な状態にあった・・・。そして、上記市長の市議会全員協議会での発言も、全員協議会の会議録に記録化されており、市の住民は、X+1年3月4日の時点では、同市の情報公開条例に基づき、同会議録の閲覧ないし謄写をすることが可能な状態にあった・・・。また、市議会定例会は、(地方自治)法115条1項本文により、原則として公開することとされており、X年12月21日の市議会定例会も、同項ただし書きに定める秘密会とはされておらず、市の住民であれば誰でも傍聴できる状態にあった・・・。そして、上記市長のX年12月21日の市議会定例会での発言は、定例会の会議録に記録化されており、市の住民は、X+1年2月7日の時点では、同市の情報公開条例に基づき、同会議録の閲覧ないし謄写をすることが可能な状態にあった・・・。
上記のX年12月21日の市議会定例会での市長の答弁は、同月22日付けA新聞朝刊により報道された。
市の市民団体である「○の図書館を考える会」は、X年11月下旬から翌12月上旬にかけて、図書館建設工事の早期着工に関する陳情書及び要望書を提出した。
原告は、X+1年11月25日付けで、市長に対し、図書館建設の中断の理由等に関する質問書を提出し、市長は、X+1年12月10日付けで、原告に対し、上記質問書に対する回答書を交付した・・・。
○ (地方自治)法242条2項本文は、普通地方公共団体の執行機関、職員の財務会計上の行為が、たとえ違法、不当なものであったとしても、いつまでも監査請求ないし住民訴訟の対象となりうるものとしておくことは、法的安定性を損ない好ましくないとして、監査請求の期間を1年と定めたものである。しかし、当該行為が普通地方公共団体の住民に隠れて秘密裡になされ、1年を経過してから初めて明らかになった場合等にもその趣旨を貫くのは相当でないことから、法242条2項ただし書きは、「正当な理由」があるときは、例外として、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過した後であっても、普通地方公共団体の住民が監査請求をすることができるものとしている。したがって、当該行為が普通地方公共団体の住民に隠れて秘密裡になされた場合には、法242条2項ただし書きにいう「正当な理由」の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたかどうか、また、当該行為を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきであると解するのが相当である(最高裁昭和63年4月22日第二小法廷判決・集民154号57ページ参照)。また、上記のように当該行為が秘密裡になされた場合に限らず、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても、客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができなかった場合には、上記の趣旨を貫くのは相当でないから、そのような場合にも、上記「正当な理由」の有無は、特段の事情のない限り、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査をすれば、客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求を行ったかどうかによって判断すべきであると解するのが相当である(最高裁平成14年9月12日第一小法廷判決・民集56巻7号1481ページ、最高裁平成14年9月17日第三小法廷判決・判例時報1807号72ページ参照)。
○ そして、上記各最高裁判決が、「通常の注意力」ではなく、「相当の注意力」による調査を必要としている趣旨にかんがみれば、マスコミ報道や広報誌等によって受動的に知り得る情報等だけに注意を払っていれば足りるものではなく、住民なら誰でもいつでも閲覧できる情報等(市議会の会議録等)については、それが閲覧等できる状態に置かれれば、そのころには住民が相当の注意力をもって調査すれば知ることができるものと評価するのが相当である。すなわち、住民がなすべき「相当の注意力」をもってする調査は、住民であれば誰でもいつでも閲覧等できる情報等については、住民の方で積極的に調査することを当然の前提としているものと解すべきである。
○ また、上記最高裁平成14年9月12日判決が、住民が知ることができた時(具体的には、報道がなされた時)から66日後に監査請求がなされたのであれば、「相当な期間」内に監査請求がなされたといえ、84日後になされたものであれば、「相当な期間」内に監査請求がなされたとはいえない旨判示していることにかんがみれば、「相当な期間」とは、特段の事情のない限り、概ね2か月半程度の期間をいうものと解するのが相当である。・・・
○ 市の住民は、たとえ本件各施設の各設計業務委託契約の締結、各設計業務委託代金の支出命令及び各狭義の支出の存在を知ったとしても、本件各行為が違法であったことまでは認識し得ず、本件各行為が、財源の確保がなされないまま行われた可能性があるということを知って初めて、監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができたといえる。そして、本件各施設の建設は・・・財政難を理由に着工が延期されたというのであるから、原告を含む市の住民は、建設の着工延期を知ったか、もしくは知り得る状態となった時点で、本件各施設の建設事業の担当者等が、いかなる財政計画を立てていたのか、建設財源の確保につき楽観的な見通しを立てていなかったかなどの調査をすることが可能であり、調査の結果、建設財源の確保の確認を怠った可能性があることを知り得ることができたといえる。そして、市の住民は、財政難を理由に本件各施設の建設着工が延期されたことを認識できる状態になれば、本件各施設の建設着工が延期されれば、既に支出済みの複合福祉センター設計業務委託費、図書館設計業務委託費の少なくとも一部は無駄になり(将来、本件各施設の建設着工の時点で、大なり小なりの再度の設計業務委託費が必要となる。)、市に損害が発生するおそれがあることをも認識できるといえるから、監査請求を行うことが可能であるといえる。それゆえ、本件各施設の建設着工が延期されたことを認識できる状態になれば、現実に市に損害が発生しているか否かが不明であるとはいえず、損害が発生しているとしてもその損害額がいくらかであるか不明であるなどという事情は、監査請求期間の始期に影響を与えるものではないというべきである。したがって、原告を含む市の住民は、本件各施設の建設着工延期を知り得る状態となってから相当期間(概ね2か月半程度)内には、本件監査請求をすることが可能であったものと認めるのが相当である。
○ 複合福祉センターについては、X年7月11日の市議会全員協議会において建設着工延期の表明がなされており、翌12日には上記着工延期表明の新聞報道がなされ、それに引き続いて、X年8月9日、同年11月27日、翌X+1年2月26日にも、複合福祉センター建設着工延期に関する新聞報道がなされている。また、市全員協議会の会議録についても、X+1年5月28日には閲覧可能な状態となっている。上記の複合福祉センターの建設着工延期の広報状況等にかんがみれば、建設着工延期の表明がなされてから約1年9か月経過後に本件監査請求がなされたことにつき、法242条2項ただし書きの「正当な理由」があるとは到底認められない。
○ 市長は、X年11月26日の市全員協議会において、すでに着工延期に追い込まれている複合福祉センターの建設を、図書館建設より優先させる旨の答弁を行い、同年12月21日の市定例会においても、平成14年度の建設着工が無理である旨の答弁をしており、翌22日には、図書館建設の困難性に関する新聞報道がなされている。また、X年11月下旬から翌12月上旬にかけて、「○の図書館を考える会」から、図書館建設の早期着工に関する陳情書及び要望書が提出されている。上記の各事情にかんがみれば、X年12月の時点では、図書館建設の着工は、事実上の延期状態にあり、多数の住民も、このことを知り得る状態にあったものと認められる。したがって、原告を含む市の住民は、X年12月の時点で、図書館の建設財源確保の確認を怠った可能性につき、調査を行うことが可能であったと認められ、同時点から相当期間(概ね2か月半)内には、本件監査請求を行うことが可能であったと認められる。よって、本件監査請求が、図書館の建設着工が事実上の延期状態となったことを多数の住民が知り得たX年12月から約1年4か月も経過した後になされたことにつき、法242条2項ただし書きの「正当な理由」があるとは認められない。
○ また、仮に、事実上の着工延期を知り得る状態となったのみでは調査の開始が困難であったとしても・・・市長は、X+1年5月27日には、公式に、図書館の建設着工の延期表明を行い、原告自身も、同年11月25日付けで、市長に対し、図書館建設の中断の理由等に関する質問書を提出し、X+1年12月10日ころには、市長からの上記質問書に対する回答書を受領しているのであるから、原告は、どんなに遅くとも、X+1年12月10日ころの時点においては、図書館の建設着工延期の理由等につき、詳細に知るところとなっているものと認められ、同時点から、相当期間(概ね2か月半)内には、本件監査請求を行うことが可能であったと認められる。ところが、図書館の建設着工延期の理由を原告が詳細に知るところとなったX+1年12月10日の時点を基準としても、本件監査請求は、上記時点から、約4か月経過した後になされていることとなる。
○ したがって、いずれにせよ、図書館の設計業務委託に関する財務会計上の行為(図書館設計業務委託代金残額の支出を除く。)に関する監査請求が、法242条2項所定の監査請求期間を経過してなされたことにつき、同項ただし書きの「正当な理由」があるとは認められない。
【最高裁判例】 食糧費各支出の日から1年を経過した後に住民監査請求がされた場合において,住民団体が情報公開条例に基づく公開請求をした結果,上記監査請求の約4か月弱前には,上記各支出を含む1年度分の食糧費支出に関し個別の支出の日,金額,その内訳及び債権者名並びに支出に係る会合の場所,出席人数及び市側の出席者が明らかとなる文書の写しの交付を受けたこと,上記文書の件数は1422件であったが,上記団体はその交付を受けた日から約3か月後には会合出席者1人当たりの金額が6000円を超えるものが230件程度あるなどの分析結果の集約を終えることができたのにかかわらず,その分析結果を新聞紙上に発表して監査請求人を公募し,その約25日後に上記団体の構成員及び上記公募に応じた者が上記監査請求をしたことなどの事実関係の下では,同請求の約4か月弱前ころには,市の一般住民においても同様の情報公開請求手続を採るなど相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記各支出について監査請求をするに足りる程度にその存在及び内容を知ることができたというべきであり,上記監査請求はその時から相当な期間内にされたということはできず,同請求が上記各支出の日から1年を経過した後にされたことについて地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるとはいえない 最判平17.12.15集民218.1151
(事実関係(時的経過)については上記リンク先を参照されたい)
○ 普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在又は内容を知ることができなかった場合には,(地方自治)法242条2項ただし書にいう正当な理由の有無は,特段の事情のない限り,当該普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきである(最高裁平成10年(行ツ)第69号,第70号同14年9月12日第一小法廷判決・民集56巻7号1481頁参照)。前記事実関係等によれば,本件団体は,X年7月3日,市のX-1年度の食糧費の支出に関する文書について本件情報公開請求をしたが,食糧費の支出の内容を知るに足りる文書の公開を受けることができなかったところ,X+1年8月19日,本件情報公開請求に係る一般支出決議書等の文書を交付され,それにより,個別の食糧費の支出の日,金額,その内訳及び債権者名並びに食糧費の支出に係る会合の場所,出席人数及び市側の出席者が明らかになったのであるから,支出の件数が多数に及ぶものであったとしても,本件団体の構成員は,同日において,監査請求をするに足りる程度に本件各支出の存在及び内容を知ることができたというべきである。また,同日ころには,市の一般住民においても,同様の手続を採るなど相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて本件各支出について監査請求をするに足りる程度にその存在及び内容を知ることができたというべきである。そうすると,そのころから約4か月弱の期間が経過した同年12月15日にされた本件監査請求は,前記の相当な期間内にされたものということはできない。
○ 本件各支出の件数は220件を超えるものであるが,現に文書の公開を受けた本件団体の構成員において,その約3か月後には前記のとおりの分析を終えることができたのにかかわらず,それから更に約25日を経過した後に本件監査請求をしたというのであるから,支出の件数が多数であることなどによって,前記の相当な期間についての判断が左右されるものではない。したがって,本件監査請求に法242条2項ただし書にいう正当な理由があるということはできないと解すべきである。
【最高裁判例】 市が,勧奨により退職した職員が市のあっせんにより再就職した場合には再就職先での給与額を一定の期間退職時の給与月額と同額とする旨の内部基準に基づき,退職した職員の再就職先の団体に対し給与の差額分を業務委託費の名目で支出したが,支出の外形からは市の一般住民においてその実質的な内容を知ることができなかった場合において,地方有力紙が上記基準の内容とそれに基づく支出が市議会議員らから問題視されている状況を報道し,記事の中で既に上記基準により上記支出の年度に再就職した職員がいたことに触れていたにもかかわらず,上記報道の約6か月後に上記支出について住民監査請求がされたなどの事実関係の下では,同住民監査請求が上記支出の日から1年を経過した後にされたことについて,地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるとはいえない 最判平18.6.1集民220.353
(事実関係(時的経過)については上記リンク先を参照されたい)
○ 普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知ることができなかった場合には,地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由の有無は,特段の事情のない限り,当該普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきである(最高裁平成10年(行ツ)第69号,第70号同14年9月12日第一小法廷判決・民集56巻7号1481頁参照)。
前記事実関係等によれば,本件支出は,…管理運営業務の費用の名目でされたものであり,その外形からは,市の一般住民においてその実質的な内容を知ることはできない。しかしながら,X+1年4月28日付けの○○新聞は,前記・・・のとおり,市は職員が勧奨に応じて市の外郭団体に再就職した場合には退職時の給与月額を保証する制度を実施し,当該外郭団体に対し再就職した者の人件費の差額を補助していること,この制度によりX年度において○協会に再就職した者がいることを報道していたところ,同新聞は…県の有力紙であるから,この報道は市の一般住民において容易に閲読することができたものであることを勘案すると,当該報道がされた日ころには,市の一般住民において相当の注意力をもって調査すれば客観的に見て監査請求をするに足りる程度にその対象とする財務会計上の行為の存在及び内容を知ることができたというべきである。ところが,本件監査請求は,そのころから約6か月後である同年10月27日にされたというのであるから,上告人が上記の相当な期間内に監査請求をしたものということはできないことは明らかである。したがって,本件監査請求に地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるということはできないと解すべきである。
○ 上記の報道と同時期に同旨の報道をした全国紙があったが,その内容の一部に誤りがあったという事情や,市の担当職員が市議会において本件支出が本件要領等に基づき支払われる人件費の差額分に相当する旨の具体的な説明をしたのが同年9月8日であったという事情などがあったとしても,前記の判断が左右されるものではない。
ごみ焼却工場の運転管理業務を巨額の特命随意契約で外部委託していた件について、相当以前に市助役が議会で随意契約として説明し議事録が公開されていること、やはり公開されている各年度予算書において当該契約が連年外部委託されていることを承知できること、特命随意契約は例外的な場合にのみできるにもかかわらず本件契約が巨額であることからすれば、当該年度の契約について当該年度の6月末には市の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしたとすれば、当該年度契約が随意契約で締結されたとの事実を知ることができたと認めることができ、このような巨額の契約につき随意契約の方式をとったということ自体、住民監査請求をするに足りる程度の重要な事実ということができるから、市の住民は、遅くとも上記時点までには、当該年度委託契約の締結につき住民監査請求をするに足りる程度にその存在及び内容を知ることができたと認められ、かつ当該契約の監査請求期間は翌年度4月1日までなのに、それから10か月を経過してなされた住民監査請求について監査請求期間徒過の正当な理由はないとした事例 東京地判平18.11.29判例時報1958.42
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 正当な理由があるか否かを検討するに当たっては、普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知ることができなかった否かをまず判断すべきである。住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても上記の程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知ることができなかった場合には、正当な理由の有無は、特段の事情のない限り、相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきものである(以上につき、最高裁判所第一小法廷平成14年9月12日判決・民集56巻7号1481頁参照)。以下、この観点から検討する。
○ 証拠(掲記のもの)及び弁論の全趣旨を総合すれば、以下の事実を認めることができる。
本件ごみ焼却施設の運転管理業務は、平成4年度までは市の職員のみがこれに当たっていたが、平成5年度に入って、夜間及び休日の業務を外部に委託する(部分委託)という方針が採用され、同年6月30日、市と補助参加人との間において、同年7月1日以降、本件ごみ焼却施設の運転管理業務のうち夜間及び休日の業務を補助参加人に委託するとの内容の委託契約が、特命随意契約の方式により締結された…。契約内容は平成9年度から平成13年度までの本件各委託契約の内容と同様である。以後、本件平成9年度委託契約が締結されるまで、市は、補助参加人に対し、特命随意契約の方式により部分委託を続けてきた。すなわち、平成5年7月1日以降、平成14年3月31日まで、同様の方式により、補助参加人との間で随意契約が行われてきた。
平成5年度以降平成14年度まで、市の毎年度の予算書には「ごみ焼却施設運転管理業務委託料」として予算額が計上され、また、市の毎年度の「主要な施策の成果の概要」と題する書面(決算書の付属書類)には、「ごみ焼却施設運転管理業務委託料」として事業費が記載されており…、市の住民は、市立図書館においてこれらを閲覧すれば、本件ごみ焼却施設の運転管理業務が外部に委託されていることを知ることができた。
平成9年度から平成13年度までの本件各委託契約に関し、各年度ごとの具体的な閲覧可能日は次のとおりである…。
(ア) 平成9年度
予算書 平成 9年 3月21日
決算書 平成10年12月16日
決算付属書類 平成11年 3月25日
(イ) 平成10年度
予算書 平成10年 3月19日
決算書及びその付属書類 平成11年12月 4日
(ウ) 平成11年度
予算書 平成11年 3月25日
決算書及びその付属書類 平成12年12月 6日
(エ) 平成12年度
予算書 平成12年 3月29日
決算書 平成13年12月25日
決算付属書類 平成13年12月26日
(オ) 平成13年度
予算書 平成13年 3月29日
決算書及びその付属書類 平成14年12月11日
平成5年9月24日に開催された市議会9月定例会において、市の助役は、本件ごみ焼却施設の運 転管理業務のうち夜間及び休日の業務を外部に委託することにしたこと、自治法234条2項及び施行令167条の2第1項2号の規定により補助参加人との間で随意契約の方式により委託契約を締結したこと、その契約内容等について説明をした…。
本件ごみ焼却施設の運転管理業務を外部に委託していることについては、平成6年3月25日開催の市議会3月定例会、同年12月8日開催の市議会12月定例会、平成7年3月20日開催の市議会3月定例会においても説明が行われた…。
市議会の会議録は、議会終了後8か月以内に市議会事務局又は市立図書館で閲覧することが可能となり、上記各議会の会議録についても同様であった。
市議会議員であった原告Eは、平成11年11月4日開催の決算審査特別委員会、同月9日開催の同特別委員会、平成12年11月6日開催の決算特別委員会、平成14年3月14日開催の同特別委員会、同年11月1日開催の同特別委員会に委員として出席しているが、これらの場においても、本件ごみ焼却施設の運転管理業務を外部に委託していることの説明が行われている…。また、このうち平成14年3月14日開催の予算特別委員会においては、原告は、本件ごみ焼却施設運転管理業務委託料が増額となった経緯について質問をしている…。
平成14年11月27日、讀賣新聞及び毎日新聞は、○市長が、同市と補助参加人との間で随意契約の方式により締結されたごみ焼却施設運転管理業務委託契約を巡り、補助参加人の前社長から賄賂を受け取ったとの容疑で逮捕される見込みであるとの報道をした。同月28日には、両紙とも、○市長が上記収賄容疑で、補助参加人の前社長等が贈賄容疑で、それぞれ逮捕されたとの報道をした。…
原告Eは、平成14年11月28日の讀賣新聞の…記事を読むなどして、補助参加人が市との間で締結している本件ごみ焼却施設運転管理業務委託契約についても徹底して調査をしなければならないと考えるに至り、同年12月6日、平成5年度から平成14年度までの本件ごみ焼却施設運転管理業務委託契約に係るすべての文書につき、市の情報公開条例に基づく公文書公開請求をし、同月20日、その開示を受けた…。そして、同じく上記…の記事を読むなどしてこの問題について関心を持つに至ったその余の原告らとともに、平成15年2月3日、連名で、上記開示を受けた文書の中の一部を証拠書面として添付して、本件監査請求をした…。
原告Eが上記カにおいて開示を受けた文書の中には、本件平成10年度委託契約及び本件平成12年度委託契約の各締結に先立ち市内部で作成された起案書(契約用)が含まれており、ここには、平成5年7月1日以降特命随意契約の方式により補助参加人に対して本件ごみ焼却施設運転管理業務を委託している経緯とその理由が記載されている…。
市の情報公開条例は平成11年7月1日に施行されている…。
○ 前記前提事実…に基づき判断する。…
市と補助参加人との間の本件ごみ焼却施設運転管理業務委託契約は、平成5年7月1日以降継続している。本件ごみ焼却施設の運転管理業務が外部に委託されていることは、毎年度の予算書及び決算付属書類を閲覧すれば知ることができた。そして、当初の平成5年の時点におけるこの契約の締結が特命随意契約の方式によって補助参加人との間で行われたことは、平成5年9月24日に開催された市議会9月定例会における助役の説明によって明らかになっており、この議会の議事録は、議会終了後8か月以内に閲覧可能となるであるから、遅くとも平成6年5月末ころには、上記助役の説明があった議会の議事録も閲覧可能となったと認められる。さらに、平成11年7月1日に市の情報公開条例が施行されており、市の住民は、同日以降、本件各委託契約にかかわる文書につき、この条例に基づく公開請求をすることができた。上記…の事実に照らすと、公開請求をしてから実際に開示されるまでの期間も、長くても1か月はかかるものではないといえるし、開示がされれば、随意契約で契約を締結するに至った経緯とその理由を知ることができたといえる。
以上の事実を前提に、本争点…において検討すべき本件各委託契約のうち最も遅い本件平成13年度委託契約の締結につき、市の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて監査請求をするに足りる程度にその存在及び内容を知ることができた時点を確定することとする。まず、平成13年度の予算書は平成13年3月29日に閲覧が可能であるから、これを見ることにより、本件ごみ焼却施設運転管理業務が外部に委託されていることを知ることができる。契約の相手方及び契約締結方法に関しては、平成5年9月24日に開催された市議会9月定例会の会議録は既にその時点で閲覧可能であるから、これを見ることにより、平成5年当時本件ごみ焼却施設の運転管理業務の委託を受けたのは補助参加人であること及び契約締結が随意契約の方式によるものであることを知ることができる。この事実は、平成13年度における委託契約も随意契約によるものではないかとの疑問を生じさせるものであるということができるから、次に、市の情報公開条例に基づく公文書公開請求をすることにより、平成13年度における委託契約の相手方及びその内容、随意契約であるか否かを知ることができる。この点について、市の担当職員は、本件平成13年度委託契約の締結が同年4月1日であったことからすれば、事務処理の都合上、この契約書類の公開は同年6月1日ころになるとしている…。以上の点を踏まえると、市の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしたとすれば、本件平成13年度委託契約が補助参加人との間で随意契約の方式により締結されたとの事実は、遅くとも同年6月中には知ることができたと認めることができる。そして、本件平成13年度委託契約の委託料は1億円を超える巨額のものである。(地方)自治法234条2項及び施行令167条の2第1項2号により、委託契約につき随意契約を締結することができるのは例外的な場合であるとされていることからすると、このような巨額の契約につき随意契約の方式をとったということ自体、監査請求をするに足りる程度の重要な事実ということができる。したがって、市の住民は、遅くとも平成13年6月末までには、本件平成13年度委託契約の締結につき監査請求をするに足りる程度にその存在及び内容を知ることができたと認められる。
○ 以上の次第で、市の住民である原告らは、相当の注意力をもって調査をすれば、遅くとも平成13年6月末には、本件平成13年度委託契約の締結につき監査請求をするに足りる程度にその存在及び内容を知ることができたと認められる。一方、期間制限規定の定める期間の終期は平成14年4月1日であるから、約9か月もの時間的余裕があり、この期間内に監査請求をすることを要求しても不当とはいえない。そうすると、期間制限規定の制限を及ぼすことに問題はなく、この契約の締結を対象とする監査請求が平成15年2月3日であって期間制限規定の定める期間を経過していることにつき、正当な理由を肯定することはできないというべきである。
○ このように、本件平成13年度委託契約の締結についてすら正当な理由はないのであるから、それ以前の平成9年度から平成12年度までの本件各委託契約の締結に関して監査請求期間を経過したことにつき正当な理由がないことは明らかである。なお、原告Eは、平成11年5月以降市議会議員であり、一般の住民と比較すればより容易に調査を行うことができる立場にあったといえるが、一般の住民について上記のことがいえる以上、原告Eについて取り立てて検討を加える必要はない。
知事の海外出張に対する住民監査請求について、知事の海外出張に関する動向等は詳細に一般紙等で報道されており、これに基づき文書開示請求をしたところ開示文書に財務会計上の行為の内容が記載されておりこれに関係法令や条件を適用することにより当該行為の適否を知ることが可能となる場合は、当該公文書が開示されると、住民は、監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在及び内容を知ることができるものと考えられ、当該公文書が作成され開示可能となったと推認できる時期から2年6か月以上経過して請求がなされた本件請求は、監査請求期間後の請求についての正当な理由はないとした事例 東京高判平19.2.14判例タイムズ1265.204
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 地方自治法242条2項本文が、監査請求の期間を当該行為のあった日等から1年間と定めた趣旨は、普通地方公共団体の執行機関・職員の財務会計上の行為は、たとえそれが違法・不当なものであったとしても、いつまでも住民が争いうる状態にしておくことが、法的安定性を損ない好ましくないので、速やかにこれを確定させようとすることにあり(最高裁判所昭和63年4月22日第二小法廷判決・判例時報1280号63頁等参照)、その目的のため、同項本文は監査請求期間の始期を画一的に定めているが、他方で、その趣旨を貫くのが住民監査請求や住民訴訟制度の趣旨とする法適合性確保の要請からして相当でないこともあり、同項ただし書で正当な理由があるときは例外的に監査請求ができるとしている。したがって、その正当な理由の解釈に当たっては、例外的な場合であると規定されていることに留意して解釈すべきであり、その一方で、財務会計上の行為の法的安定性の要請とその法適合性の確保の要請との調和を図る趣旨に沿って検討されることも必要とする。
○ 普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在又は内容を知ることができなかった場合には、地方自治法242条2項ただし書の適用が問題となり、この場合における同ただし書にいう正当な理由の有無は、特段の事情のない限り、当該普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきである(最高裁判所平成14年9月12日第一小法廷判決・民集56巻7号1481頁参照)。そして、通常の注意力でなく相当の注意力をもってする調査を正当な理由の有無の判断基準としていることの趣旨を考慮すると、住民が相当の注意力をもってする調査については、マスコミ報道や広報誌等によって受動的に知った情報だけに注意を払っていれば足りるものではなく、住民であれば誰でもいつでも閲覧できる情報等については、それが閲覧等をすることができる状態に置かれれば、そのころには住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて知ることができるものというべきである(最高裁判所平成14年9月17日第三小法廷判決(判例時報1807号72頁参照)は、平成3年3月になされたS市による・・・公園用地取得時土地売買に関し、同市の住民が、売買代金が異常に高額であると市議会で質疑があった旨の平成5年9月の新聞記事を読み、同年10月に売買契約等の開示請求を行った後に同年11月に監査請求をした事案に関し、原審が新聞報道があるまでは売買価格の相当性に合理的な疑いを持つことが困難であったとして正当な理由があるとしたのに対し、新聞報道の点に言及することなく、「上記各決算説明書の記載によれば、・・・公園用地の各年度の売買価格の平均値が1平方メートル当たり約17万円であったことが明らかとなったというべきである。そうすると、上記各決算説明書が一般の閲覧に供されて市の住民がその内容を了知することができるようになったころには、市の住民が上記各書類を相当の注意力をもって調査するならば、客観的にみて本件各契約の締結又は代金の支出について監査請求をするに足りる程度にその存在及び内容を知ることができたというべきである。」と判示しており、同判例は、マスコミ報道等を待つまでもなく、住民なら誰でもいつでも閲覧等できる情報等については、それが閲覧等できる状態に置かれれば、そのころには住民が相当の注意力をもって調査すれば知ることができるものと判示したことは明らかである。)。
そこで、上記でいう閲覧できる情報等について検討するに、東京都の住民は、東京都情報公開条例に基づき、実施機関に対し、財務会計上の行為の完了の日と近接した日から、当該行為に関する公文書の開示請求をすることができ、実施機関は、非開示事由に該当しない限り、当該公文書を開示すべきものであるから、当該公文書に財務会計上の行為の内容が記載されており、これに関係法令や条件を適用することにより当該行為の適否を知ることが可能となる場合は、当該公文書が開示されると、住民は、監査請求をするに足りる程度に財務会計上の行為の存在及び内容を知ることができるものと考えられる。そうすると、当該住民は、財務会計上の行為について監査請求をする前提として、同条例に基づく開示請求をすることで相当の注意力をもって調査したことになり、逆に開示請求をしないままでいる場合には相当の注意力をもって調査したとはいえないと解するのが相当である。
○ これに対して、一審原告は、東京都情報公開条例に基づく開示請求は、①開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項を明らかにして開示請求をしなければならない(同条例6条1項3号)、②実施機関が公文書の開示を行うときは開示手数料を徴収する(同条例17条、別表)旨規定してるから、開示請求をするのが相当であると考えるべき事情、又は開示請求をする端緒となり得る事情がなくても、監査請求の前提として条例に基づく開示請求をしていなければ、当該住民が相当の注意力をもって調査したとはいえないと解すると、住民に過度の要求をすることになり、財務会計上の行為につき法適合性確保の要請を害することになると主張する。そして・・・A開示文書2についてA記者がアメリカ出張に係る文書の開示請求をする際に要した手数料は2380円(その内訳は資料114枚×写しの交付料20円/枚+閲覧料100円である。)であることが認められる。しかしながら、情報公開制度が普通地方公共団体に設けられており(東京都においては東京都情報公開条例に基づく開示制度)、その情報公開制度の趣旨は、住民の主権の理念に則って行政機関の保有するすべての情報を対象とし、住民一人一人がそれらの情報を開示請求できる権利に基づきこれを利用した上、行政機関の諸活動の遂行状況に的確な理解と批判をすることで公正かつ民主的な行政の推進に資することにあるのであり、その制度趣旨からすると、住民は、この情報公開制度が利用できる以上、開示請求が自己の権利であるとともに情報を得ることにより積極的に上記役割を果たすことも期待されているものというべきである。一審原告の主張する上記①の点については、通常の住民が開示請求のための公文書を特定することが困難な場合、あるいは提供された文書では財務会計上の行為の具体的内容を把握できないような場合には、さらに正当の理由について特別の考慮を払えば足りるし、②の点についても、その負担内容に照らして住民に過度の負担であるとまでは認められない。一審原告の上記主張は採用できない。また、このように解した場合、情報公開制度により住民監査請求の期間が短縮され、監査請求に支障を来たすとの批判がありうる。しかし、監査請求期間は、そもそも法的安定のため1年と定められており、正当な理由がある場合はあくまでその例外であること、開示請求をすることで相当の注意力をもって調査したことになるとすると、普通地方公共団体は文書につき財務会計上の行為の完了後速やかに作成して閲覧に供するなど情報公開制度を充実させ機能させることが求められ、その一方で、住民も必要な情報を得るべく関心を持ち積極的に情報公開制度を利用することが求められる結果、情報公開による文書の開示がすすむ利点もあること、これらの財務会計上の行為の法的安定性の要請とその法適合性確保の要請とのバランスを考えるとその批判は当を得ない。
○ 本件では、前認定のとおり、A記者が東京都情報公開条例に基づきX年11月14日に開示請求を行い、一審被告から同年12月4日に本件海外出張に係る文書の開示及び交付を受けたところ、当該文書であるガラパゴス出張にかかるA開示文書1は平成13年6月28日に作成されたものであり、アメリカ出張にかかるA開示文書2は同年9月4日に作成されたものであること、Bが東京都情報公開条例に基づき平成16年2月10日に開示請求を行い、一審被告から同月24日に本件海外出張に係る文書の開示及び交付を受けたところ、当該文書であるガラパゴス出張にかかるB開示文書1の1及び2は平成13年5月18日に作成されたものであり、アメリカ出張に係るB開示文書2は同年9月3日に作成されたものであることからすると、上記各当該文書については、本件海外出張の旅費が支給された日と近接した日ころには閲覧等をすることができる状態に置かれて開示請求をすることができたと推認しうるし、前認定の上記各当該文書の内容からして、開示の対象となった本件海外出張に係る公文書により客観的にみて監査請求をするに足りる程度に本件海外出張に係る財務会計上の行為の存在及び内容を知ることができたというべきである。そうすると、上記開示請求ができたとする時点から相当期間が経過すれば、正当な理由はないことになる。
○ したがって、本件海外出張に係る本件監査請求は、開示請求をすることができた時点から約2年6か月以上の期間が経過した後であり、相当な期間内にされたものではないから、これを適法な監査請求ということはできない。
○ なお、住民が財務会計上の行為について監査請求をする前提として、開示請求をすれば公文書が開示される状態にあった時点で、常に住民に当該文書につき開示請求することを求めるのは相当の注意力をもって調査する範囲として酷となる場合もあり得る。そのような場合でも、住民にとって財務会計上の行為の存在を知り得る報道がなされる等、開示請求をする何らかの手がかりとなる事情があれば、その時点で既に公文書が開示される状態となっているときは、住民は公文書の開示請求をすることができるのであり、また、その時点以降に公文書が開示される状態となったときは、その時点以降では開示請求をすることが可能となるのであるから、報道等の手がかりがあるときは、住民にとって相当の注意力をもって調査する範囲内として開示請求をすることが酷とはいえない。そこで、本件について、この点からも検討しておくこととする。
○ ガラパゴス出張について、前認定のとおり、①平成13年5月26日、全国的な一般紙である・・・新聞は、知事が、記者会見において、同年6月11日から11日間の日程でガラパゴス諸島を視察すると発表した事実を報道したこと、②同年6月11日、・・・新聞は、7段組みの囲み記事で、「知事、都議選を回避?」、「21日まで南米視察旅行」などの見出しの下に、知事が同日ガラパゴス諸島へ視察に出かけるため日本を出発し、帰国は同月21日の予定であること、一行は総勢8人で交通費だけでも1000万円程度かかるとされていること、視察先には知事が趣味としているダイビングスポットもあり、憶測を呼んでいること、「遊びに行くなら理屈をつけずに行けばいい。物事をはっきり言う知事らしくない。」と皮肉を言う都議会議員がいたことなどの事実を報道したものである。
そうすると、遅くとも平成13年6月11日ころには、東京都の住民は、新聞(全国紙で一般紙)の報道内容により知事らのガラパゴス出張に係る財務会計上の行為の存在を認識し、開示請求をする手がかりとなる情報を得たものであるから、この時点以降、住民が相当の注意力をもってする調査の範囲内として開示請求をすることは可能になるのであり、住民にとって監査請求をする前提として開示請求をすることが酷とはいえない。したがって、一審原告が、上記報道された日ころより後でかつ開示請求をすれば公文書が開示される状態にあった時点以降では、開示請求することは可能であり、ガラパゴス出張に係る本件監査請求は、開示請求をすることができた時点から約2年9か月以上の期間が経過した後になされたものであり、相当な期間内にされたものとはいえないから、これを適法な監査請求ということはできない。
○ アメリカ出張について・・・、①平成13年9月8日、・・・新聞は、知事がアメリカ合衆国に向け同日出発し、ワシントンDCの・・・などで日米関係について講演をするほか、現地要人と会談する予定であるという事実を報道したこと、②同月9日、・・・新聞は、知事がアメリカ合衆国のワシントンDCに同月8日に到着したこと、また、・・・において日米関係について講演をするほかアメリカ合衆国政府関係者らと会談し、同月15日に帰国する予定であるという事実を報道したこと、③同月11日、・・・新聞は、知事が同日アメリカ合衆国の国防副長官と会談し、・・・主催の講演会で講演した事実を報道したこと、④同月12日、・・・新聞は、知事が、アメリカ合衆国の国防副長官との会談等を行い、また、テロ事件発生時、ワシントンDCのホテルに滞在していたが無事であったという事実を報道したこと、⑤同月12日、・・・新聞は、知事が、テロ事件発生時にワシントンDCのホテルに滞在していたが無事であり、また、アメリカ合衆国訪問には、○秘書やCら8人が同行しているという事実を報道したこと、⑥同日、Eは、知事が、テロ事件発生時、ワシントンDCの・・・ホテルに宿泊していたが無事であったという事実を報道したこと、⑦同月15日、・・・新聞は、知事が、同月14日、アメリカ合衆国から帰国し、記者会見を行ったという事実を報道したものである。そうすると、遅くとも平成13年9月中ころには、東京都の住民は、上記新聞(全国紙の一般紙又はスポーツ紙)の報道内容により知事らのアメリカ出張及びCのアメリカ出張への同行に係る財務会計上の行為の存在を認識し、開示請求をする手がかりとなる情報を得たものであるから、この時点以降、住民が相当の注意力をもってする調査の範囲内として開示請求をすることは可能になるのであり、住民にとって監査請求をする前提として開示請求をすることが酷とはいえない。したがって、一審原告が、上記報道された日ころより後でかつ開示請求をすれば公文書が開示される状態にあった時点以降では、開示請求することは可能であり、アメリカ出張に係る本件監査請求は、開示請求をすることができた時点から約2年6か月以上の期間が経過した後になされたものであり、相当な期間内にされたものとはいえないから、これを適法な監査請求ということはできない。
○ なお、一審原告は、これらの報道では、人事委員会との協議を経ないで旅費が増額されたとの違法事由を知ることができないので、これらの報道があったからといって、客観的にみて本件各旅費について監査請求をするに足りる程度にその存在及び内容を知ることができたということができないと主張する。しかしながら、これらの報道を端緒として情報公開により支払われた旅費を調査し、旅費に関する東京都の条例と照らし合わせば、増額手続の必要性及びその実施の有無も判明するのであるから(これらは、上記説示にかかる最高裁判所判例にいう相当の注意力をもってする調査の範囲内である。)、この主張にも理由がない。
○ 以上のとおり、本件訴えは、適法な監査請求前置の要件を欠くものであるから、いずれも不適法である。
住民がある財務会計上の行為について情報公開条例に基づく開示請求をするのが相当であると考えるべき、あるいはそう考える端緒となり得べき事情が存在しないにもかかわらず、当該財務会計上の行為について監査請求をする前提として、同条例に基づく開示請求をしていなければ、相当の注意力をもって調査したとはいえないというのは、住民に過度の要求をすることになるから妥当ではなく、マスコミ報道等によって知った情報を含めて、情報公開条例に基づく開示請求をするのが相当であると考える端緒となるべき事情が存在する場合に初めて、開示請求をすることも相当の注意力をもってする調査の範囲に含まれると解するのが相当との前提のもとに、市民病院の国立大臨床医局への寄附支出に対する住民監査請求について、関連報道中に本件寄附を推認させる内容はなく、客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該支出の存在及び内容を知り得たとはいえないとした事例 仙台高判平19.4.20
(M市立病院が国立大学医学部臨床系医局に寄附金支出したことが、当時の地方財政再建促進特別措置法24条2項(地方公共団体は、当分の間、国・・・に対し、寄附金、法律又は政令の規定に基づかない負担金その他これらに類するもの(これに相当する物品等を含む。以下「寄附金等」という。)を支出してはならない。ただし、地方公共団体がその施設を国、独立行政法人若しくは国立大学法人等又は会社等に移管しようとする場合その他やむを得ないと認められる政令で定める場合における国、独立行政法人若しくは国立大学法人等又は会社等と当該地方公共団体との協議に基づいて支出する寄附金等で、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得たものについては、この限りでない、と規定)に反するとする住民監査請求・住民訴訟)
○ 本件記事(X年9月22日付けの、M市立病院がO財団に対し10万円の寄附をしているとの記事)は、M市立病院がO財団に対し10万円の寄附をしたことを報じたにすぎないから、これから市の一般住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて同病院から医局に対する本件支出について監査請求をするに足りる程度に当該支出の存在及び内容を知ることができたということはできない。・・・によれば、これに先立つX年9月11日及び同月13日付けNはP市民病院が医局(教授)とO財団の双方に寄附を行っていたことを報じていたけれども、これらを含めて本件記事に至るまでの新聞報道によっても、東北地方の同病院以外の自治体病院からの寄附先はO財団にとどまるものであったことが認められ、本件記事に係るM市立病院の寄附は10万円にすぎず、外に寄附先があることをうかがわせるような金額ともいえないことを考え併せれば、P市民病院に関する上記記事からM市立病院についてもO財団と医局の双方に寄附がなされている可能性が大きいことを知り得たということはできない。
○ 控訴人は、市情報公開条例が施行されたX-4年1月1日以降はM市立病院の会計文書等を入手すれば本件支出を知ることができた旨主張する。しかしながら、単に情報公開制度の下で請求によって当該情報に接することができる機会を与えられているとの一事をもってしては、各支出のころに住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて各支出の存在及び内容を知ることができたと解することは相当でない。確かに、市民が、積極的に情報公開条例を利用し同病院の会計処理等に関する情報を収集調査すれば、その時点から相当期間内に本件支出の存在と内容を知ることができた可能性が高いことは否定できない。しかしながら、市の住民が、ある財務会計上の行為について同条例に基づく開示請求をするのが相当であると考えるべき、あるいはそう考える端緒となり得べき事情が存在しないにもかかわらず、当該財務会計上の行為について監査請求をする前提として、同条例に基づく開示請求をしていなければ、相当の注意力をもって調査したとはいえないというのは、住民に過度の要求をすることになるから妥当ではなく、マスコミ報道等によって知った情報を含めて、情報公開条例に基づく開示請求をするのが相当であると考える端緒となるべき事情が存在する場合に初めて、開示請求をすることも相当の注意力をもってする調査の範囲に含まれると解するのが相当である。
○ 控訴人は、相当の注意力を持った住民は、本件記事を手がかりとして、情報公開請求をすることにより、市において通常情報公開がなされる期間である13日間を経過したX年10月5日ころには、本件支出の存在及び内容を知ることができた旨主張する。しかしながら、地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附をすることができるのであって(地方自治法232条の2)、私的財団に対する寄附が一般的に違法不当とされているわけではないから、被控訴人がM市立病院からO財団への寄附金支出を知ったからといって、そこから直接医局への本件支出がなされている可能性を疑って情報公開請求をすることを一般市民に期待するのは無理があり、本件記事が情報公開条例に基づく開示請求をするのが相当であると考える端緒になるとはいえない。してみれば、控訴人の主張は採用できない。
○ 控訴人は、遅くともQが(近隣他)市で監査請求をした同月22日ころには、被控訴人は、本件支出の存在及び内容を知ることができた旨主張するけれども、Qが◎市に対してS市立病院のO財団に対する寄附につき監査請求をしたからといって、これから直ちに一般市民である被控訴人がM市立病院から医局に対する寄附につき客観的にみて監査請求をするに足りる程度に当該支出の存在及び内容を知り得た根拠となるものとはいえないから、控訴人の主張は採用できない。
町議会議員である請求人は、一般住民より早い時点で客観的にみて監査請求をするに足りる程度に本件滞納債権の徴収を怠る事実の存在及び内容を知り得たとした事例 大阪地判平19.7.27判例地方自治299.56
(事実関係及び経過は下記参照)
○ 前記認定事実によれば、X年5月2日、旧A町が特定の住民から約20年間にわたって国民健康保険料と税金を徴収せず、しかも住民甲と旧A町職員幹部との間にカラオケ店で飲食するなどの癒着があったなどという住民甲の高額滞納問題が新聞各紙によって報道され、それを契機として、同年7月25日、旧A町における不納欠損処理の状況及び時効中断措置を始めとする滞納処理の状況についての本件特別監査が旧A町監査委員によって実施され、その結果を受けて、同年9月11日付けで、旧A町における一般的な町税及び国民健康保険料等について、消滅時効の完成に係るものについて適宜必要に応じて不納欠損処理を行う、各事案を見直す期間を設定し消滅している債権と消滅していない債権を明確化する、消滅債権を出さないよう時効中断措置を講じ徴収事務の整理を行う、などの具体的な消滅時効の完成等に係る徴収事務の整理の在り方等が示された本件改善策が旧A町長から提出され、それが告示をもって一般住民にも公表されたことが認められる。したがって、旧A町の一般住民は、本件改善策が公表されたX年9月11日以降は、相当の注意力をもって調査すれば、住民甲の高額滞納問題以外にも、旧A町の町税及び国民健康保険料について、その徴収権が消滅時効期間の経過等により消滅していた事実が存在し又は存在する可能性があり、旧A町において本件改善策に従った徴収事務の整理が進められることにより、X年度の決算において徴収権の消滅が確認された町税又は国民健康保険料に係る債権について不納欠損処理が行われる可能性が高い事実を認識することができたというべきである。しかるところ、普通地方公共団体の町税及び国民健康保険料の徴収権が消滅時効期間の経過等により消滅することは、当該普通地方公共団体の通常の業務過程において頻繁に起こり得るものとして当然に法が許容している事態であるとはいい難いのであるから、当該普通地方公共団体の職員が上記徴収権を消滅させたことは特段の事情のない限り違法又は不当な所為であると評価、判断することにも、相当の合理的な理由があるということができ、そうであるとすれば、当該普通地方公共団体の町税及び国民健康保険料の徴収権の消滅の事実を知り得たことそれ自体をもって、当該町税及び国民健康保険料につき違法又は不当にその徴収を怠る事実が存在したと疑うことが可能であったと解しても、何ら不合理ではないというべきである。
○ 以上のとおり、旧A町の一般住民は、本件改善策が公表されたX年9月11日以降は、相当の注意力をもって調査すれば、旧A町の町税及び国民健康保険料について、違法又は不当にその徴収を怠る事実が存在する可能性があり、X年度の決算において徴収権の消滅が確認された町税又は国民健康保険料に係る債権について不納欠損処理が行われる可能性が高い事実を認識することができたというべきである。
○ そうすると、本件不納欠損処理に係る町税及び国民健康保険料の合計金額及びその件数等が具体的に記載された本件各決裁文書(町税についてはX+1年3月31日付け、国民健康保険料については同年2月10日付け及び同年3月31日付け)が完成してA町情報公開条例に基づく開示請求の対象となり・・・、しかも、・・・上記各文書には納付義務者(滞納者)の個人に関する情報・・・及び法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報・・・を除いて不開示情報が記録されているとは認められないから、旧A町の一般住民は、上記各文書が存在することを知り得たのであれば、上記条例に基づいてそれらの開示請求をすることによって、少なくとも本件各決裁文書に記録された不納欠損処理に係る町税又は国民健康保険料の対象件数及び総額に関する情報を入手することができ、監査請求をするに足りる程度に本件不納欠損処理に係る町税及び国民健康保険料の徴収を怠る事実の存在及び内容を知り得たものということができる(前記・・・で説示したとおり、本件においては、少なくとも本件不納欠損処理に係る町税及び国民健康保険料の合計金額及び件数が明らかにされれば、当該町税及び国民健康保険料の徴収を怠る事実に係る監査請求の対象の特定を欠くものではない。)。しかしながら・・・、本件各決裁文書は、旧A町の通常の業務過程において作成されたものではなく、住民甲の高額滞納問題を契機として実施された本件特別監査の結果を受けて旧A町長が提出した本件改善策に従って、徴収事務の整理を進め、徴収権が消滅した多額の町税及び国民健康保険料について不納欠損処理を実施するために、対策本部の設置など通常の業務とは異なる手続過程を経て作成された文書であると認められるのであって、X年11月26日付けで設置された対策本部の設置の事実ないしその活動状況等が一般に報道ないし公表されていたことを認めるに足りる証拠がこれまでの審理経過にかんがみても存在しないことに照らすと、旧A町の一般住民は、本件改善策の存在及びその内容等から法令の規定に基づく決算の調製とは別にその議会への提出に先立って不納欠損処理に関しA町情報公開条例による公開の対象となるような文書が作成されるものと思い至ることは困難というべきであり、相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて、本件不納欠損処理の実施の事実及びその内容が新聞報道によって明らかにされたX+1年9月3日以前において、本件不納欠損処理に係る町税及び国民健康保険料の合計金額及び件数等を記載した本件各決裁文書が作成され存在していることを知ることができたとは解し難い。
○ これに対し、決算書は毎年一定の時期に作成される・・・から、旧A町の一般住民は、X年度決算書(X+1年7月12日付け)の存在そのもの及びそのおおよその作成時期は知り得るのであり、A町情報公開条例に基づいてそれらの開示請求をし、それらの開示を受けることができたのであれば、同決算書に記載されている本件不納欠損処理に係る滞納債権の合計金額を知ることができたから、監査請求をするに足りる程度に本件不納欠損処理に係る町税及び国民健康保険料の徴収を怠る事実の存在を知り得たものという余地がある。しかしながら、X年度決算書は、A町情報公開条例に基づく開示請求の対象にはなり得る・・・ものの、それらは旧A町監査委員による審査に付した上で旧A町議会に提出されるものであって・・・、少なくとも監査委員による審査の手続が完了して旧A町長により議会の認定に付することができる状態になるまでは、同決算書に記載された情報は同条例7条(2)の不開示情報(いわゆる内部情報)又は同条(3)の不開示情報(いわゆる事務事業情報)に該当すると解されることからすれば、X年度決算書が旧A町議会に提出されたX+1年9月3日以前においては、旧A町の一般住民は、同決算書の存在及び作成時期を知り得たとしても、同決算書の内容を知ることは事実上不可能であったということができ、したがって、監査請求をするに足りる程度に本件不納欠損処理に係る滞納債権の徴収を怠る事実の存在を知ることは不可能であったといわざるを得ない。
○ 以上のとおりであるから、X年度決算書が旧A町議会に提出され、本件不納欠損処理の実施の事実及びその内容が新聞報道により明らかにされたX+1年9月3日以前においては、旧A町の一般住民は、相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に本件不納欠損処理に係る町税及び国民健康保険料の徴収を怠る事実の存在又は内容を知ることは不可能であったというべきである。
○ そこで、・・・本件監査請求〈1〉をした甲事件原告(原告B)及び乙事件原告ら(原告C、原告D、原告E)が、X+1年9月3日以前において、客観的にみて監査請求をするに足りる程度に本件不納欠損処理に係る滞納債権の徴収を怠る事実の存在及び内容を知ることができたか否かについて検討することとする。
○ まず・・・のとおり、旧A町の一般住民は、本件改善策が公表されたX年9月11日以降は、相当の注意力をもって調査すれば、住民甲の高額滞納問題以外にも、旧A町の町税及び国民健康保険料について、その徴収権が消滅時効期間の経過等により消滅していた事実が存在し又は存在する可能性があり、したがって、当該町税及び国民健康保険料につき違法又は不当にその徴収を怠る事実が存在した可能性があり、X年度の決算において徴収権の消滅が確認された町税又は国民健康保険料に係る債権について不納欠損処理が行われる可能性が高い事実を認識することが可能であったから、本件監査請求〈1〉及び〈3〉をした甲事件原告及び乙事件原告らにおいても、上記の各事実を認識することが可能であったことは明らかである。のみならず、前記前提となる事実等及び前記認定事実によれば、甲事件原告(原告B)は、X-2年9月頃から旧A町会議員として活動していたところ、X年5月に住民甲の高額滞納問題が新聞により報道されると、旧A町税務課及び保険課から情報提供として50万円以上の高額滞納者のリスト(本件滞納町税一覧表〈1〉、本件滞納保険料一覧表。前記のとおり滞納者ごとに当該町税の賦課年度ないし当該保険料の発生年度が記載されている。)を入手し、その直後に開催された上記問題の対策を検討する旧A町議会の会議に参加して同町職員からの説明を聞いており、同月7月24日には自ら上記問題に関し当該高額滞納者(住民甲)に対する町税債権及び国民健康保険料債権を時効により消滅させたことについての旧A町長及び担当職員の責任を問う住民監査請求をするだけではなく、同年9月11日付けで旧A町における一般的な町税及び国民健康保険料等について消滅時効の完成等に係る徴収事務の整理の在り方等を提示した本件改善策が公表された後は、同月18日の旧A町決算特別委員会においてX-1年度決算における不納欠損の要因等について税務課長に質問し、同課長から不納欠損処理の根拠となる法令の規定・・・の内容の説明やX-1年度決算における不納欠損額及びその内訳についての説明等を受けたり、同委員会に先立って同課長から本件改善策に沿った同課の事務遂行の状況や滞納繰越分の見直し等について説明を受けるとともに、X-1年度決算における不納欠損処理の内訳(件数)等が記載された資料の交付を受けるなどし、また、X+1年1月には本件改善策に従ってX年11月26日付けで設置された対策本部の活動状況及び組織構成等について同課長に質問をし、さらに、X+1年3月初めころには税務課及び保険課に差押え等の滞納処分の状況等をも記載したより詳細な50万円以上の高額滞納者に係る情報の提供を依頼し、これを受けた税務課から上記事項を記載した滞納者のリスト・・・を入手するとともに、税務課長から全面的な滞納繰越分の見直し及び精査は大体終了した旨の説明を受けているのであって、しかも、同一覧表に記載されている滞納債権のうち約17.6%については、本件不納欠損処理の対象とされており、同一覧表中に時効消滅により不納欠損処理の対象とされるべき債権が含まれていることは、原告BがX年5月の時点で入手していた本件滞納町税一覧表〈1〉と対照することにより容易に認識することができたことが認められるのである。
○ 以上の事実によれば、本件監査請求〈1〉及び〈3〉を共同請求人として)した原告Bは、遅くともX+1年3月初めころに本件滞納町税一覧表・・・を受領して以降は、住民甲に対する町税及び国民健康保険料以外にも、旧A町の町税及び国民健康保険料について、その徴収権が消滅時効期間の経過等により消滅していたものがある事実を認識しており、これらの町税及び国民健康保険料につき違法又は不当にその徴収を怠る事実が存在した可能性があり、X年度決算において徴収権の消滅が確認された町税又は国民健康保険料に係る債権について不納欠損処理を行うことを前提にその対象となる事案の調査(滞納繰越分の見直し及び精査)が進められ、少なくとも町税についてはX+1年3月初めころには当該調査はほぼ終了していた事実をも認識していたものというべきである。
○ 以上のとおり、本件監査請求〈1〉を(共同請求人として)した甲事件原告(原告B)は、旧A町のX年度の決算において徴収権の消滅が確認された町税又は国民健康保険料に係る債権について不納欠損処理を行うことを前提にその対象となる事案の調査(滞納繰越分の見直し及び精査)が進められ、少なくとも町税についてはX+1年3月初めころには当該調査がほぼ終了していた事実を認識していたところ・・・、A町財務規則36条1項は、「歳入徴収者は、すでに調定した歳入について、その徴収の権利が消滅しているものがあるとき…は、不納欠損処理簿・・・により不納欠損として処理しなければならない。」と、同規則36条2項は、「前項に定めるもののほか、不納欠損として整理すべきものがあるときは、歳入徴収者は、次に掲げる事項を、町長に報告し、指示を受けて処理しなければならない。(1) 不納欠損の科目及び金額、(2) 納入義務者の住所、氏名その他必要な事項」と、同規則36条3項は、「前2項の規定により不納欠損の処理をしたときは、歳入徴収者は、出納機関に通知するとともに、関係帳簿を整理しなければならない。」とそれぞれ規定していることをも考慮すれば、原告Bは、上記不納欠損処理の対象となる事案の調査の終了後、当該会計年度の終了時(X+1年3月末)ないしその直後ころ(遅くともその翌月中)までには、本件不納欠損処理に係る町税及び国民健康保険料の金額及び件数等が具体的に記載された不納欠損処理簿に準じる文書ないし帳簿が作成されることになる事実を知り得たものというべきである。そして、原告Bにおいて、同年4月以降、A町情報公開条例に基づき、請求に係る行政文書を町税及び国民健康保険料に係るX年度不納欠損処理に関する不納欠損処理簿、関係帳簿ないしこれに準ずる文書などとして開示請求をすれば、本件不納欠損処理に係る町税及び国民健康保険料の合計金額及び件数等が記載された本件各決裁文書(町税についてはX+1年3月31日付け、国民健康保険料については同年2月10日付け及び同年3月31日付け。これらの文書が同条例に基つく開示請求の対象となり、しかも、納付義務者(滞納者)の個人に関する情報及び法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を除いて不開示情報が記載されているとは認められないことは、前記・・・のとおりである。)の開示を受けることにより、少なくとも本件各決裁文書に記録された不納欠損処理に係る町税又は国民健康保険料の対象件数及び総額に関する情報を入手することができ、住民監査請求をするに足りる程度に本件不納欠損処理に係る町税及び国民健康保険料の徴収を怠る事実の存在及び内容を知り得たものというべきである。のみならず、前記認定のとおり、原告Bは当時旧A町議会議員の職にあり、旧A町の行政当局(税務課及び保険課)は、同原告の要求にほぼ沿う形で本件滞納町税一覧表〈1〉、本件滞納保険料一覧表、本件滞納町税一覧表・・・を提供し、また、X-1年度決算における不納欠損処理の内訳(件数)等が記載された資料をも交付するなど、可能な限りの情報提供を行ってきた経過が明らかであり、このような経過にかんがみると、少なくとも本件各決裁文書が完成した後は、原告Bは、本件不納欠損処理に係る町税及び国民健康保険料の対象件数及び総額等に関する情報提供を要求すれば、A町情報公開条例に基づく行政文書開示手続を経ることなく本件各決裁文書に記録された不開示情報を除く情報の提供を任意に受けることができたものと認められるから、これによって、同原告は、住民監査請求をするに足りる程度に本件不納欠損処理に係る町税及び国民健康保険料の徴収を怠る事実の存在及び内容を知り得たものというべきである。
○ 以上によれば、本件監査請求〈1〉をした原告Bは、遅くともX+1年4月末ころまでには、客観的にみて監査請求をするに足りる程度に本件不納欠損処理に係る滞納債権(町税及び国民健康保険料)の徴収を怠る事実の存在及び内容を知り得たものというべきである。
【最高裁判例】 県警察本部の県外出張に係る旅費の支出について住民監査請求がされた場合において,当該住民が県の情報公開条例に基づき上記出張に関する資料の開示を求めたところ,当初は,上記出張の旅行期間,目的地,用務等の事項が開示されず,その部分開示決定に対する異議申立ての結果,初めてこれらの事項が開示されるに至り,その1か月後に上記監査請求がされたなどの事実関係の下では,上記監査請求が上記支出のあった日から1年を経過した後にされたことについて地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由がある 最判平20.3.17集民227.551
(事実関係(時的経過)については上記リンク先を参照されたい)
○ 前記事実関係等によれば,本件各出張に関しては,(X+6年5月31日の)第1次開示において,支出負担行為兼支出命令決議書につき支出負担行為日,支出命令日,支払日,旅費額等が,旅行命令(依頼)票につき旅行命令日,旅行者氏名,旅行期間,旅行内容,目的地,旅費の支給額及び受領月日等が,復命書につき作成日付,出張者の職及び氏名,用務,用務先,旅行期間等が,それぞれ墨塗りされて開示されず,X+8年5月24日の第2次開示において初めてこれらの事項が開示されたというのである。そうすると,第2次開示によって本件各出張ないし本件各出張に係る旅費の支出について具体的な内容が明らかにされる以前の段階では,上告人において,本件各出張が架空のものであるかどうか,また,業務上必要のないものであるかどうかを判断することは困難であったものというべきである。この段階において原審が掲げる諸事実を根拠として本件各出張が架空のものであるなどと主張したとしても,その主張は単なる憶測の域を出ないものとならざるを得ない。
○ そうであるとすれば,第2次開示によって本件各出張ないし本件各出張に係る旅費の支出について具体的な内容が明らかにされる以前の段階では,上告人において本件各出張に係る旅費の支出に違法又は不当な点があると考えて監査請求をするに足りる程度にその存在及び内容を知ることができたと解することはできず,第2次開示において本件各出張の旅行期間,目的地,用務等に関する情報が記録された部分が開示されてから1か月後に,本件各出張に係る旅費の支出につき本件監査請求がされたことについては,地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるというべきである。
住民が相当な注意力を持ってする調査の内容として、特段の事情もないのに情報公開請求をしなければならないと解するのは相当ではなく情報公開請求をすれば知り得る情報を前提に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時点を判断すべきではないとの前提のもとで、本件監査対象について違法不当をうかがわせる事情についての報道等もなく、市議が組合活動への問題意識から行なった情報公開請求に基づき開示された情報をもとに、開示後約1か月後に行なった監査請求について、監査請求期間経過後の請求の正当な理由があると認めた事例 大阪地判平25.4.24
(市営バスの職員が勤務時間中に労働組合のための活動を行うことを理由として他の職員にバス乗務勤務を行わせ、代走が行われた勤務時間についても組合活動を行っていた職員が勤務したこととして取り扱われ当該職員に対し代走が行われた勤務時間に対応する給与等が減額されることなく支給されたことが違法である等とする住民監査請求・住民訴訟。請求人は市議であり、労組と自治体の癒着についてかねてから問題意識を持ち、その一環で市に有給職免や代走等の情報公開請求をしたところ、本件監査請求に至ったものであり、端緒となる報道等が情報公開請求や監査請求に先行したものではない)
○ 普通地方公共団体において違法に財産の管理を怠る事実があるとして住民監査請求があった場合に、当該監査請求が、当該普通地方公共団体の長その他の財務会計職員の特定の財務会計上の行為を違法であるとし、当該行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実としているものであるときは、当該監査請求については、当該怠る事実に係る請求権の発生原因たる当該行為のあった日又は終わった日を基準として地方自治法242条2項の規定を適用すべきものと解するのが相当である(最判昭和62年2月20日・民集41巻1号122頁参照)。
○ 本件において、原告は、代走、有給職免及び優遇ダイヤに基づく給与等の支払が違法であることに基づいて発生する不当利得返還請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権の管理を怠る事実としているから、監査請求の期間は、当該行為のあった日を基準とすべきである。そうすると、監査請求のあったX年10月4日の1年以上前に給与等の支払行為が行われた部分については、監査請求期間を徒過したものというべきである。(中略)
○ 原告は、X年8月13日、市に対し、有給職免に関する情報公開請求を行い、同月27日及び31日に有給職免のほか、代走及び優遇ダイヤに関する文書の開示を受けた・・・。前提となる事実記載の代走、有給職免及び優遇ダイヤ(注:組合幹部に優遇的な仕業割当を行ったこと。優遇ダイヤで生じた空き時間に給与減額なく組合活動に従事することを容認したことが本件監査請求の内容に含まれる)の内容からすると、このような行為が行われていることについて、違法ないし不当を主張できる程度に内容を知るためには、情報公開請求等によって資料を入手することが不可欠であると認められる。そして、原告が市議会議員であることを考慮しても、X年8月13日に情報公開請求をする前の時点で、代走、有給職免及び優遇ダイヤについて、これらの具体的な内容を知る契機があったことはうかがわれない。そして、情報公開請求によって資料の開示を受けた後も、その資料を分析して違法行為の内容を知るためには一定の時間を要すると認められることからすると、監査請求をしたのが資料の開示を受けた34日後となったことは、やむを得ないといえ、正当な理由があるというべきである。
○ これに対し、被告らは、情報公開制度を利用すれば、代走、有給職免及び優遇ダイヤの存在並びにこれらの内容を知ることができたから、正当な理由がないと主張する。しかし、正当な理由の有無は、当該普通地方公共団体の住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて上記の程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断すべきである(最判平成14年9月12日・民集56巻7号1481頁参照)ところ、住民が相当な注意力を持ってする調査の内容として、特段の事情もないのに情報公開請求をしなければならないと解するのは相当ではないから、情報公開請求をすれば知り得る情報を前提に、当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時点を判断すべきではない。そして、市の住民において、情報公開請求をする契機があったことについて、特段の事情があったことをうかがわせる証拠はない。
府本庁舎の耐震性等の問題から高層ビルを買い取り一部部局を移転させたものの東日本大震災で損壊が発生し防災拠点としての使用をしないこととした事案において、東日本大震災前に同ビルの耐震性に関する設計報告書が公表されてはいたがこれは高度に専門的な内容を含むため、これによってビル購入契約等の違法不当性を原告が判断することは困難であること、震災後に公表された専門家会議の検証結果が公表されて初めてビルの耐震性に問題があることを原告は知ることができ、本件購入契約の締結及び本件購入費用の支出につき違法又は不当な点があるか否かを原告ら自ら判断することが困難ではない程度に対象財務会計行為の具体的な内容を知ることができたというべきであるところ、同検証結果も高度な専門的内容を含むことを考慮すると、同結果公表から70日後になされた住民監査請求について監査請求期間経過後の請求の正当な理由があると認めた事例 大阪地判平29.12.7判例タイムズ1448.128
(府庁舎は大正年間の建築で耐震性等の問題があったことから、Aビルを購入し府の一部部局を移転させたところ、2011(平成23)年3月11日の東北地方太平洋沖地震で損壊が生じ(注:震源域は非常に遠隔であったが気象庁の記録では当地の震度は3を記録しており、報道によれば同ビルは長周期振動で大きく揺れたという)、府は専門家が参加した会議結果等を踏まえ同ビルを防災拠点として使用しないことを決定した。原告は上記会議結果の公表から約2ヶ月後に住民監査請求を提起した。当審は下記判断にあたり、最判平14.9.12民集56.7.1481および最判平20.3.17集民227.551を引用する)
○ これを本件についてみると、確かに、証拠…及び弁論の全趣旨によれば、府は、平成21年1月頃にN設計報告書を受領し、同年2月頃には上記報告書の内容やこれを踏まえた必要な措置について大議会に対して説明するとともに、上記報告書の概要…を府のホームページにおいて公表したことが認められる。
○ しかし、公表された上記概要においては、Aビルの耐震性に特段の問題はない旨の結論が示されたにとどまり、その結論に問題があるか否かを検討するためには、N設計報告書(概要を含む。)を入手して検討する必要がある。そして、仮に同報告書が公開されていたとしても、その内容は、長周期地震動の高層ビルへの影響等に関する高度に専門的な内容を含むことが明らかである。そうすると、上記の点につき相当高度な専門的知見を有する者でない限り、N設計報告書の内容及び結論に疑いを差し挟むことは事実上不可能というべきであって、本件購入契約の締結及び本件購入費用の支出につき違法又は不当な点があるか否かを、原告ら自ら判断することは困難であったといわざるを得ない(なお、原告らが上記の相当高度な専門的知見を有していたと認めるべき証拠はない。)。そうすると、上記概要が府のホームページに公表された時点や、同報告書に基づく説明により府議会がAビルの購入に係る議決を行った時点(平成22年5月28日)において、原告らが、相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて本件監査請求をするに足りる程度に本件購入契約の締結及び本件購入費用の支出の内容を知ることができたとはいえない。
○ そして、平成23年8月9日に公表された専門家会議検証結果…には、研究者が公表していた模擬地震波を用いてAビルの構造安全性を検討すると、外装材等に影響が出る可能性がある値が出た旨の記載があり、Aビルの耐震性に問題がうかがわれることは、専門家会議検証結果の公表によって初めて明らかになったものといえる。
○ 以上によれば、原告らは、専門家会議検証結果が公表されて初めて、Aビルの耐震性に問題があることを知ることができ、本件購入契約の締結及び本件購入費用の支出につき違法又は不当な点があるか否かを原告ら自ら判断することが困難ではない程度に、上記各財務会計行為の具体的な内容を知ることができたというべきである。そうすると、原告らは、専門家会議検証結果が公表された平成23年8月9日において、上記検証結果を入手して相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて本件監査請求をするに足りる程度に本件購入契約の締結及び本件購入費用の支出の内容を知ることができたといえるところ、原告らは、同日から70日後の同年10月19日に本件監査請求をしたのであるから…、専門家会議検証結果もまた高度に専門的な内容を含むものであることも考慮すると、その公表の時点から相当な期間内に本件監査請求をしたものというべきであり、本件監査請求が監査請求期間を超えてされたことについては、地方自治法242条2項ただし書にいう「正当な理由」があるというべきである。
○ よって、本件監査請求は監査請求期間の制限を遵守した適法なものであるから、本件訴えは適法である。
小学校の校舎の耐震補強工事に係る公金の支出から1年を経過して住民監査請求がされたことについて、補強設計が困難である旨指摘を受けていたにもかかわらず工事を行ったことについては、特段の情報や契機もないのにそのような特殊な事情を考慮に入れて住民が調査をするのは困難であるが、その後保護者説明会や議会説明、第三者委員会が設置されたことを踏まえれば、同委員会設置要綱公表後5か月を経過してなされた住民監査請求について地方自治法242条2項ただし書にいう正当な理由があるということはできないとされた事例 大阪地判平30.7.26
(設計業者から補強設計をすることが困難である旨の指摘を受けていたにもかかわらず小学校の校舎の耐震補強工事が行われたことについて(府から市に対し、本件校舎はコンクリート強度が公的基準に達していないため、このままでは耐震補強を実施したと判断することはできないとの指摘があり、市は本件校舎を閉鎖した)、工事に係る公金の支出から1年以上を経過して住民監査請求が提起された。なおコンクリートの最低強度が耐震診断基準に記載された最低強度を下回ることを前提に耐震補強工事が行われたものであるとの事情について当該小学校において保護者説明会が実施されたほか、市議会において詳細な説明がされ、さらに同工事について検証等を行う第三者委員会の設置要綱が公表されていた。当審は最判平14.9.12民集56.7.1481を前提に次の通り判示)
○ 上記認定事実によれば,本件工事は一定の規模を有する公共施設に対する耐震補強工事であり,その工期も約5か月に及んでいたことなどからすると,本件工事が行われていたこと自体は,その当時から,地域住民にとって,客観的・外形的に明らかであったということができる。 そうすると,本件工事が行われていることが客観的・外形的に明らかになった時点において,本件工事の請負契約(本件請負契約)のみならず,本件工事を施工するために当然に必要となる設計契約(本件業務委託契約)についても,契約の締結その他の財務会計上の行為の存在自体は,○小学校周辺の地域住民にとっては明らかであったということができる。そして,市が本件校舎を含む市内3校4棟の耐震補強工事を実施していたことのほか,市の規模等に鑑みれば,○小学校の周辺住民に限らず,市の住民が,相当の注意力をもって調査すれば,本件工事に係る公金の支出の存在を知ることができたことは明らかというべきである。
○ また,上記認定事実によれば,本件工事に係る公金の支出に関しては,□報告書及び本件覚書を含む本件各公文書が作成ないし取得され,その作成・取得の時点以降,市の住民であれば誰でも,公開請求により,その内容を了知することができたというのであるから,本件各公文書につき上記請求をすれば,本件各契約の内容等の形式的事情のみならず,本件工事がFから本件校舎の補強設計をすることは困難である旨の指摘を受けた後にコンクリート強度が弱いこと等を前提に施工されたとの事情(本件事情)を知ることもできたと考えられる。
○ もっとも,本件監査請求は,補強設計をすることが困難である旨の指摘を受けていたにもかかわらず本件工事が行われたことを問題とするものであるところ,このような事情(本件事情)は,本件各契約に係る契約書や支出命令書のみを調査しただけでは判明しないものであって,更に□報告書や本件覚書の公開請求をするなどして,その詳細な経緯まで調査しなければ,本件監査請求をするに足りる程度に当該行為の内容を知ることはできなかったものというべきである。そして,特段の情報や契機もないのに,上記のような特殊な事情があることを考慮に入れて調査をすることは相当に困難であると考えられ,本件各契約に係る契約書や支出命令書を調査することについては,住民による合理的な調査として一般的に期待することができるとしても,それを超えて詳細な経緯を調査することまで住民に期待するのは酷な面があるといわざるを得ない(公開請求に係る情報を「本件工事に係る情報一切」などとして公開請求をすれば,□報告書や本件覚書も公開されたと考えられるものの,特段の情報もないのに,このような包括的・網羅的な公開請求をすることまでを期待するのが相当であるとはいい難い。) 。そうすると,被告の内部において本件各公文書が作成ないし取得されたとしても,本件事情は,市の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても知ることが困難であったものということができる。
○ 以上によれば,本件工事に係る公金の支出について,被告の内部における本件各公文書の作成ないし取得の時点において,市の住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても客観的にみて本件監査請求をするに足りる程度にその内容を知ることができたと解することはできない。
○ しかしながら,上記認定事実によれば,X年8月には○小学校において保護者説明会が実施されたほか,同年9月14日には市議会定例会において教育部長から本件事情等についての詳細な説明がされ,さらに,同年11月7日には本件委員会の設置要綱が施行されて公表されたというのである。
○ これらの経緯に照らせば,遅くとも,本件委員会(注:上記事実関係掲出の第三者委員会)の設置要綱が公表された同年11月7日頃には,市の住民が相当の注意力をもって調査すれば本件事情を知ることができたと解するのが相当である。
○ しかるに,上記認定事実によれば,原告が本件監査請求をしたのは上記の時から5か月以上が経過したX+1年5月1日であるから,原告が上記の時から相当の期間内に監査請求をしたとは到底いえない。
※対象となる公金の支出はX-6年中、府の指摘で校舎を閉鎖したのはX年10月

比叡山の山上から琵琶湖坂本方面。向こうのほうが何だか若干ヨコヤマタイカンの風情。