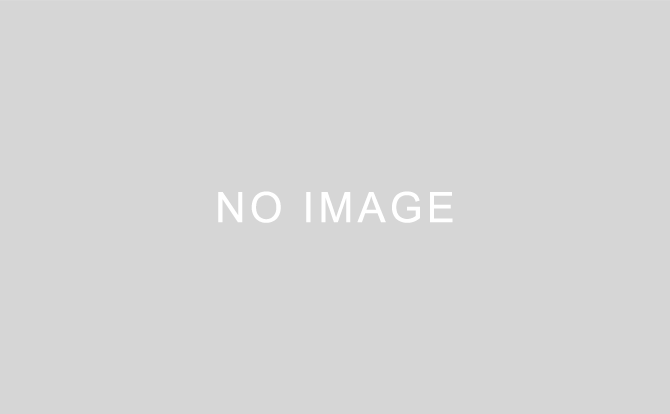本ページの一番下に、本ページのPDF版リンクを設けています。
最終改訂 2024.5.3 改訂内容は改訂履歴ページ参照
このページは、監査請求期間に関する裁判例を紹介するページです。
(監査請求期間に関する説明は こちら 。また「正当理由」の裁判例については こちら に別掲)。
また、監査請求期間に関する判断は、いくつかの最高裁判例を起点に、経験則の積み上げによる理論的精緻化が図られているため、ここでは最高裁判例・下級審裁判例を、原則としてすべて経年順で並べています。
【注】 参考事例の判決文は、必ずしも原文通りではなく、項目の表記にあうように若干の修正をしていることがあります。
監査請求期間の起算日は、監査請求をする住民が当該行為をいつ知ったかに関わりなく、客観的に「当該行為のあった日又は終わった日」を監査請求のできる期間の起算日とするとした事例 大阪高判昭46.8.31判例タイムズ271.199
○ 控訴人は、昭和41年10月5日付新聞記事によりはじめて事実を知ったと主張するけれども、地方自治法242条2条は、監査請求のできる期間の起算日を「当該行為のあった日又は終わった日」と規定しているのであって、「当該行為を知った日」としておらず、このことは、監査請求が普通地方公共団体の住民に一般的に与えられている権利であり、しかも監査請求の対象となる行為が行われたことについて個々の住民に個別的に告知されるわけのものではないことから、その起算日を個々の住民の個別的な知不知にかからせると、個々の住民の主観的事情によって起算日が区々となり、いつまでも法律関係が不安定な状態にとどまるおそれがあるため、法が、住民の個別的事情の考慮よりも、法律関係の画一的安定を優先させることとし、監査請求をする住民が当該行為をいつ知ったかにかかわりなく、客観的に、「当該行為のあった日又は終わった日」を起算日としたものと解するのが相当であるから、控訴人が昭和41年10月5日付A新聞の記事によってはじめて本件売渡処分の事実ないしはその違法不当性を知ったとしても、そのことの故に右起算日が左右されるものではないし、従ってまた、そのことのみによって当然には、右期間を遵守できなかつた「正当な理由」があったとすることもできない。
【最高裁判例】 怠る事実に係る住民監査請求には、地方自治法242条2項の規定の適用はない 最判昭53.6.23集民124.145
(町収入役が、町長印を勝手に使用して金融機関から金銭を借り入れ、これを第三者に貸し付けたが、回収不能となり、町は金融機関との訴訟に敗訴してその負担で金融機関に返済せざるを得なくなった。本件は、被告である町長が、収入役と共謀して、又は監督怠慢により、町に損害を与えたと主張する4号訴訟)
○ 本件監査請求は、上告人は不法行為により訴外○町に対し損害を被らせ同町に対し損害賠償義務を負うところ同町はその請求をすることを怠っているから損害賠償請求等適当な措置を求める、というのであり、これによってみれば、被上告人らの監査請求は、地方自治法242条1項所定の不当又は違法に財産の管理を怠る事実を改めるために必要な措置を講ずべきことを求めていたものというべきである。そうすると、右規定による怠る事実に係る請求については同条2項の適用はないと解すべきものであるから、被上告人らの本件監査請求については所論の期間徒過の違法はない。
工事監理委託契約の締結が違法であることを理由とする住民監査請求の請求期間は、契約の履行の時期にかかわらず、「当該行為のあった日」である契約締結の日から起算されるとした事例 松山地判昭55.11.17行裁例集31.11.2402
○ 当該行為の「あった日」が一時的行為のあった日を意味するのに対し、当該行為の「終わった日」とは、その文理上、継続的行為について、その行為が終わった日を意味するものと解される。したがって、契約締結行為に違法があることを理由とする監査請求は、契約の締結された日から1年内にしなければならないものというべきである。(なお、原告において、本件契約に基づく代金の支払等の各履行行為又は代金支払のための公金の支出行為に違法な点があるというのであれば、それぞれの行為を対象に当該各行為のあった日又は終わった日から1年内に監査請求をすべきであった。)
代金等の分割支払を内容とする契約等の是正を求める住民監査請求において、監査請求期間は分割金の支払が終了する日を起算日とするとされた事例 秋田地判昭56.5.25判例時報1036.62
(町が土地開発公社に一の委託契約をもって土地買収を委託し、10年の割賦で代金を支払うこととした)
○ 地方自治法242条1項の住民監査請求は、同条2項により「当該行為のあった日又は終わった日」から1年以内になされなければならないところ、本件契約のように、地方公共団体が売買代金などの割賦金として公金を数年に亘って支出する場合、右規定の適用にあたっては、その支出を一体のものとみて、その支出の原因である契約が締結された日や個々の支出が行われた日ではなく、右支出が終了する日をもって「当該行為の終わった日」と解し、その日から監査請求期間を起算するのが相当である。
★本裁判例に関する留意事項については「5.1監査請求期間」2(2)イ④参照
売買契約の締結、同契約による公金の支出、財産の取得が違法であるとしてなされた住民監査請求においては、売買契約の締結については契約の締結日から、公金の支出については各支出日から、財産の取得については当該財産を取得した日からそれぞれ監査請求期間を起算すベきとされた事例 東京地判昭57.7.14行裁例集33.7.1502
○ (地方自治)法242条1項、242条の2第1項は住民監査請求及び住民訴訟の対象となる財務会計上の行為を個別的に限定列挙しているから、それぞれが独立して監査請求及び住民訴訟の対象となりうる適格を有しているとみられること、同法242条2項が監査請求に期間制限を設けているのは地方公共団体の機関又は職員の行為をいつまでも争いうる状態にしておくことが法的安定の見地からみて妥当でないとの趣旨にでたものであることにかんがみると、同項の監査請求期間遵守の有無も監査請求の対象とされる各個の財務会計上の行為ごとに判断すべきものと解される。
○ 本件においては、売買契約の締結が違法であり、したがつて右契約に基づく公金の支出及び財産の取得が違法であるとして監査請求がされているというのであるから、売買契約の締結については契約の締結日から、公金の支出については各支出日から、財産の取得については当該財産を取得した日からそれぞれ監査請求期間を起算すベきである。
○ これに対し原告らは、契約の締結、公金の支出、財産の取得を一連の行為とみて最終的に残代金が支払われ、引渡しを了して履行が完了した日が当該行為の終わった日であると主張する。しかし、前記のように同法242条1項は、契約の締結、公金の支出、財産の取得を別個の財務会計上の行為として各別に監査請求、住民訴訟の対象として規定しており、数回の公金の支出もそれぞれ別個の財務会計上の行為として把握することができ、当該行為の違法性、損害の有無についても各別に問題としうる以上、監査請求期間も個々の財務会計上の行為ごとに判断すべきである。のみならず、原告らのような見解をとると、公金の支出が長期間にわたるときは長期間契約締結の違法を主張して監査請求をすることができることとなって、監査請求に期間制限を設けた前記の趣旨が没却されることとなる。したがつて、原告らの右主張は採用することができない。
○ これを本件についてみると、被告A区が昭和51年8月20日被告Bらとの間で本件土地につき請求原因・・・記載のとおりの本件売買契約を締結し、同日本件土地の所有権を取得したこと、同年9月3日被告B及び同Eに対し、本件土地代金の一部としてそれぞれ2億882万5121円及び3379万4624円を、昭和52年4月5日に残代金としてそれぞれ900万円及び100万円を支払ったこと、同53年3月14日原告らが本件売買契約、公金の支出、財産の取得が違法であるとしてA区監査委員に対して本件監査請求をしたことはいずれも各当事者間に争いがない。
○ 以上によれば、被告A区は昭和51年8月20日本件売買契約の締結とともに本件土地の所有権を取得したものであるから、本件監査請求のうち違法な契約の締結及び財産取得を理由とする部分は監査請求期間を徒過した違法があり、また、公金支出の違法を理由とする部分のうち同年9月3日の支出分については、同様監査請求期間を徒過した違法があるといわなければならない。
【最高裁判例】 首長その他の財務会計職員の財務会計上の行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実とする住民監査請求については、右財務会計上の行為のあった日又は終わった日を基準として地方自治法242条2項の規定を適用すべきである 最判昭62.2.20民集41.1.122
(町有地を第三者に随意契約で売却したことについて、複数回の住民監査請求がなされ、うち3回目は首長に損害賠償請求を、売却先に不当利得返還請求等をなすことを怠っているとするものであった。この3回目の監査請求は上記売却から1年を経過した後に行われた)
○ 普通地方公共団体において違法に財産の管理を怠る事実があるとして法242条1項の規定による住民監査請求があった場合に、右監査請求が、当該普通地方公共団体の長その他の財務会計職員の特定の財務会計上の行為を違法であるとし、当該行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実としているものであるときは、当該監査請求については、右怠る事実に係る請求権の発生原因たる当該行為のあった日又は終わった日を基準として同条2項の規定を適用すべきものと解するのが相当である。けだし、法242条2項の規定により、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過した後にされた監査請求は不適法とされ、当該行為の違法是正等の措置を請求することができないものとしているにもかかわらず、監査請求の対象を当該行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使という怠る事実として構成することにより同項の定める監査請求期間の制限を受けずに当該行為の違法是正等の措置を請求し得るものとすれば、法が同項の規定により監査請求に期間制限を設けた趣旨が没却されるものといわざるを得ないからである。
○ 右と同旨の見解に立ち、上告人…の第3回監査請求及び上告人…の監査請求は法242条2項所定の請求期間を徒過したものとして不適法であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。
怠る事実が終了した後に、当該怠る事実によって生じた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを求める監査請求は、怠る事実が終了した日から1年以内に提起すべきものとした事例 長野地判平2.10.25行裁例集41.10.1652
○ 地方自治法242条1項の「怠る事実」を対象とする住民監査請求については、賦課徴収すべき租税の賦課徴収を怠っているなどの事実が現に継続している以上(怠る事実が時々刻々発生し、かつ終了しているとも観念しうる。)、何時でもその事実の是正を求めうるとするのが当然であるから、同条2項の監査請求期間(1年)の制限には服しないというべきであるが、怠る事実が終了した後に当該怠る事実によって被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求する監査請求は、右怠る事実が終了した日から相当の期間の制限に服すべく、その期間は、「当該行為」の場合との均衡上及び怠る事実の終わった日を「当該行為」の終わった日と同視しうることに照らし、1年と解するのが相当である(中略)。けだし、地方公共団体が当該職員に対して損害賠償請求等適当な措置をなしうる期間とは無関係に、住民が住民自治の一手段としての監査請求をすべき期間を短期1年に制限している趣旨(法的安定、早期確定等)は、監査請求の対象が、「当該行為」である場合も、「当該行為」が違法、無効であることに基づいて発生した損害賠償請求権等である場合も、「怠る事実の終了」がある事案において当該違法な怠る事実に基づいて発生した損害賠償請求権等である場合も異なることはなく、怠る事実が終了した場合には、怠る事実が継続する場合のような期間制限を設けがたい性質上の特殊性はないからである。
○ しかして、被告は、本件土地について昭和58年度固定資産税の賦課徴収を怠ったものであるが、右怠る事実は、課税期間の経過により終了し、その時点において、損害賠償請求に必要な他の要件の具備を別にすれば、A村に固定資産税額相当の損害が発生したことになる。そして、固定資産税にかかる賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して5年(これは除斥期間である。)を経過した日以後においてはすることができない(地方税法17条の5、3項)。地方税法第1章総則の各条に規定する「法定納期限」とは、同法または同法に基づく条例の規定により地方税を納付し、または納入すべき期限をいい、納期を分けている地方税の第2期以降の分については、その第1期の納期限をいい(同法11条の4、1項)、固定資産税の納期は原則的には同法362条に定めるとおりであるが、A村は、A村村税条例67条1項で固定資産税の納期について6月から毎月末日までに納付すべきものとし、6月期分(第1期)から10回徴収とすると定めているから、昭和58年度固定資産税の法定納期限は、昭和58年6月30日である。
○ したがって、被告の怠る事実は、昭和58年6月30日の翌日から5年を経過した昭和63年6月30日に終了しているものというべきである。そして、原告の本件監査請求は、被告の怠る事実の終了した日から1年以上経過した後の平成元年12月12日になされているから不適法というべきである。
当初契約と変更契約の監査請求期間の起算日は、それぞれ各別に開始し、また監査の対象が契約締結行為である以上、契約履行行為が継続しているからといって起算日が移動するものではないとした事例 大阪地判平3.4.24判例タイムズ771.121
○ 契約締結行為に違法があることを理由とする監査請求にあっては、(地方自治)法242条2項の当該行為のあった日又は終わった日とは、当該契約が成立した日、すなわち、契約の締結された日と解すべきところ、これを本件についてみるに・・・本件においては、被告がA市長として本件各売買契約を締結することにつき決裁をし、A市が、売買契約書(被告の決裁したもの、A市側の署名・押印はされていない。)をB社とC社に交付し、B社は第一契約につき、昭和61年3月8日に、C社は第二契約につき、昭和60年12月27日にそれぞれ契約書に署名・押印したうえでこれをA市に交付し、その後、A市都市整備局長が、本件各売買契約の契約書に署名・押印し、これをB社とC社に交付したことが認められる。
○ 右事実によれば、本件においては、売主であるA市が、売買契約書(被告の決裁したもの、A市側の署名・押印はまだない。)をB社とC社に交付することが契約の申込みであり、B社とC社が、右契約書に署名・押印したものをA市に交付する行為が承諾と解されるから、諾成契約である第一及び第二契約の各締結日は、第一契約については昭和61年3月8日であり、第二契約については昭和60年12月27日であることが明らかである。なお・・・当初の本件各売買契約成立後、第一契約については建築施設の部分の譲渡契約に関する覚書(昭和61年4月10日付)、B´社への譲渡契約承継願(昭和61年11月11日付)、B´社との建築施設の部分の譲渡契約に関する覚書(昭和62年5月28日付)があり、第二契約については建築施設の部分の譲渡契約に関する覚書(昭和60年12月27日付)・・・建築施設の部分の譲渡契約を変更する契約書(昭和61年1月14日付)・・・建築施設の部分の譲渡代金の支払に関する覚書(昭和61年2月28日付)、建築施設の部分の譲渡契約に関する覚書(昭和62年5月28日付)が作成されていること、及び右覚書は、いずれも当初の本件各売買契約の内容の変更を目的としてなされた新たな合意であることが認められる。
○ 右事実によれば、右各覚書は、本件各売買契約の内容の変更を目的とした当初の契約とは独立した契約であり、したがって、元の契約と覚書による変更契約は、独立した財務会計上の行為であるから、それぞれが別個に監査請求の対象になるのであって、変更契約がなされたからといって、元の契約の成立の日までもが変更契約の成立の日までずれるわけではなく、元の契約に対する監査請求の期間はあくまでも、元の契約の成立の日から1年間となるのである。
○ したがって、覚書の交付を基準に本件各契約の成立の日とする原告らの主張は採用できない。右によれば、契約締結の違法に関して是正を求める本件監査請求は、本件各売買契約締結日、すなわち、行為のあった日又は終わった日から1年を経過した後になされたものといわざるを得ない。
○ 次に原告らは、本件監査請求が第一契約、第二契約の契約成立の日から1年を経過した後になされたものとしても、本件監査請求は、本件各売買契約の契約の履行をもその対象としており、しかもその履行のあった日から1年以内になされているから、本件監査請求のうち、契約の履行を対象とした部分は、適法である旨主張するので、この点について検討する。
○ ・・・本件監査請求の申立書には、「以上により、A市長のなした右売買契約は、A市の取得した財産を処分するための契約としては違法であるから、すみやかに右契約を解約するか、時価を基準とした適正価額まで増額するなどの適切な措置をとり、かつ、今後、施設建築物の建築工事の完了公告をしても、右売買契約を履行して本件施設建築物の一部等を処分しないよう求めて本住民監査請求に及んだ。」との記載があることが認められるが、右記載から本件監査請求が第一契約、第二契約の契約の履行を対象としているものと解することは困難である。仮に、右本件監査請求の申立書の「今後、施設建築物の建築工事の完了公告をしても、右売買契約を履行して本件施設建築物の一部等を処分しないよう求めて本住民監査請求に及んだ。」との記載部分から、本件監査請求が第一契約、第二契約の契約の履行を対象としているものと考える余地があるとしても、本件監査請求は、契約の締結の違法とは無関係に契約の履行について固有の違法事由を主張しているわけではなく、単に契約の締結が違法であるからそのような違法な契約の履行もまた違法であるということを前提に、これに対する是正措置を求めているにすぎない。
○ このような場合、法242条2項の適用に当たっては、当該行為のあった日または終わった日とは、売買契約締結の日を言うものと解するのが相当である。けだし、法242条2項の規定により、違法な契約締結行為の日から1年経過後になされた監査請求は不適法とされ、契約締結行為の違法是正等の措置を請求できないとしているにもかかわらず、契約の履行行為が続いている限り、履行行為そのものに何らの違法事由がなくても、契約締結行為の違法を契約の履行の違法として監査請求の対象とすることにより、監査請求期間の制限を受けずに、契約締結行為の違法是正等の措置を請求し得るものとすれば監査請求で実質的に契約内容の違法をいつまでも争えることになり、住民監査請求に期間を設けた趣旨を没却することになるからである。
○ したがって、原告ら主張の契約の履行に関する監査請求も当該行為のあった日又は終わった日から1年経過後になされたものといわざるを得ない。
概算払委託料の精算を誤ったため生じた精算残額の精算・徴収を怠る事実を対象とする住民監査請求において、監査請求期間規定の適用はないとした事例 東京地判平6.5.24判例タイムズ860.148
○ ・・・そうすると、右監査請求の対象とされている怠る事実とは、・・・区が被告A会に対して有するとされる精算残金に係る債権を、被告・・・(区長および収入役)が右監査請求の時点において行使しないことを指すものとみることができる。概算払と精算手続とはこれらが相まって支出を構成するものではあるが、精算については、客観的に未精算の部分が残っているときはこれが終了したとされたからといってその部分に係る権利義務が消滅するものでないことは前記のとおりであり、精算残金があるのであれば、その請求権は、これを行使することができる状態で存続しているものであるから、区において、更に精算を求めないことは、この精算残金の請求権の行使すなわち債権である財産の管理を怠っている状態であると解し得る。
○ そして、そのような怠る事実に係る監査請求については地方自治法242条2項は適用されないと解すべきであるから、当該請求権が行使されない間は右怠る事実に係る監査請求はいつでもできるものと解すべきである。
【最高裁判例】 概算払による公金の支出についての住民監査請求は、右公金の支出がされた日から1年を経過したときはすることができない 最判平7.2.21集民174.285
(補助金の概算払日から1年以上経過後に、住民監査請求がなされた。ただし、住民監査請求をした日は、補助金の確定があった日からは1年を経過していない)
○ 概算払は、地方自治法が普通地方公共団体の支出の一方法として認めているものであるから(232条の5第2項)、支出金額を確定する精算手続の完了を待つまでもなく、住民監査請求の対象となる財務会計上の行為としての公金の支出に当たるものというべきである。そして、概算払による公金の支出に違法又は不当の点がある場合は、債務が確定していないからといって、これについて監査請求をすることが妨げられる理由はない。債務が確定した段階で精算手続として行われる財務会計上の行為に違法又は不当の点があるならば、これについては、別途監査請求をすることができるものというべきである。そうすると、概算払による公金の支出についての監査請求は、当該公金の支出がされた日から1年を経過したときは、これをすることができないものと解するのが相当であって…
不当利得の元本の返還を受けたが利息の返還請求を怠っていることが違法とする住民監査請求は、特定の財務会計行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産管理を怠る事実としているものであるから、当該請求権の発生原因たる財務会計行為のあった日又は終わった日を基準として、地方自治法242条2項の監査請求期間の規定を適用すべきものであるとした事例 大津地判平8.10.28判例タイムズ944.131
(宮家名を冠する公営競輪競技につき主催自治体が宮家に公金を支出していたが、皇室経済法に定める手続を経ておらず違法であることが判明し授受金額(元本額)が返還されたところ、利息相当額の返還請求を怠る事実について住民監査請求がなされた)
○ 原告らは、被告市長の本件市各公金支出、被告知事の本件県公金支出いずれの関係の監査請求(以下「本件各監査請求」という。)においても、被告両名がA宮家に対して公金を支出したことは違法、無効であって、市及び県がA宮家に対し、民法704条に基づく不当利得返還請求権として交付した金員及びそこから生じた利息の返還請求権を有しているにもかかわらず、被告両名が、A宮家に対し右利息等の返還を求めないことは地方自治法242条の違法又は不当に公金の徴収を怠る場合に該当するとして、被告両名に対し、市あるいは県に生じた損害を回復する措置を求めていたことが認められるのであって、本件各監査請求は、いずれも被告市長又は被告知事の財務会計上の行為である公金支出を違法であるとし、公金支出行為が違法、無効であることに基づいて発生する不当利得請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実とするものにほかならない。よって、本件においては、原告らが違法であると主張している各公金支出行為のあった日又は終わった日を基準として、同条2項の規定する期間内に本件各監査請求が行われているか否かを検討すべきである。
○ なお、原告らは、利息の額は元本が返還されるまでは確定しないから、元本の返還請求を怠る事実を監査の対象とするのではなく、利息を返還しないことを「怠る事実」とする本件各監査請求においては、監査請求期間の制限を受けないと主張している。しかし、本件において原告らが主張している利息返還請求権も、A宮家に対する各公金支出が違法、無効であることを前提として発生するものであり、利息額が確定していなくとも元本とともに元本支払い済みまでの利息の返還を求めることは可能であるから、本件各公金支出の終了した時点から直ちに、被告市長や被告知事に対しA宮家に支払った金員の元本とともに利息の返還請求を行う等の措置をするよう求める監査請求をすることは可能である。したがって、支出された公金の元本の返還を請求する場合と利息の返還を請求する場合とで監査請求期間の制限の点で別異に扱うべき理由はなく、原告らの主張は採用できない。
【最高裁判例】 財務会計上の行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実とする住民監査請求において、右請求権が右財務会計上の行為のされた時点ではいまだ発生しておらず、又はこれを行使することができない場合には、右実体法上の請求権が発生し、これを行使することができることになった日を基準として地方自治法242条2項の規定を適用すべきである 最判平9.1.28民集51.1.287
(国鉄が市に多目的ホール敷地等のための用地として土地を売却。契約上、所定期間内に第三者に譲渡した場合の違約金条項があったが、本件土地は、国鉄の承諾を得ないまま所定の期間内に第三者に売り渡された。国鉄清算事業団は、市に対し、売買契約特約に違反して土地が転売されたことを理由に、契約を解除する旨の意思表示し、5千万円弱の違約金支払を催告したが、市はこれを争ったため清算事業団が市を提訴。市は請求棄却を求める答弁をしたが、その後、市が清算事業団に約1500万円を支払う裁判上の和解が成立し、市は同額を支払った。これに対し住民が、市長を被告として前記和解金を市の損害とする4号訴訟を提起。なお、住民訴訟に先立つ住民監査請求は、本件土地の第三者への転売日からは1年以上を経過していたが、前記和解成立、和解金支払日いずれの日からも1年以内になされたもの)
○ 前記事実関係によれば、本件売買契約における特約に違反して本件土地の転売がされたとしても、それだけで当然に違約金請求権が発生するものではないとされているから、右転売行為の時点において直ちに市が違約金相当の損害を被ったという余地はない。そうすると、右時点においては、転売行為が違法であることに基づく市の被上告人(市長)に対する損害賠償請求権はいまだ発生していないことになるから、監査請求の対象となるべき右損害賠償請求権の行使を怠る事実も存在しないというほかはない。それにもかかわらず、当該怠る事実を対象とする監査請求につき、転売行為の日を基準として地方自治法242条2項の規定を適用し、同項本文の期間が進行するものと解することはできない。前示第二小法廷判決(注:昭和62年2月20日・民集41.1.122)の判旨は、右のような場合にまでそのまま妥当するものではなく、財務会計上の行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実とする住民監査請求において、右請求権が右財務会計上の行為のされた時点においてはいまだ発生しておらず、又はこれを行使することができない場合には、右実体法上の請求権が発生し、これを行使することができることになった日を基準として同項の規定を適用すべきものと解するのが相当である。
○ 本件においては、上告人らの主張するように被上告人が本件転売行為をし、これが違法であったとすると、国鉄清算事業団が本件売買契約の解除をしたことにより、契約条項の上では市の同事業団に対する売買代金の1割相当の違約金債務が発生したことになるが、前記の事実関係によれば、地方公共団体である同市が同じく公的団体である同事業団の請求に対して右債務の存在を否定する対応をし、同事業団の提訴に対しても転売禁止の特約の有効性自体を否定する答弁をして応訴し、その後2年8箇月余にわたってこの争いが続行した結果、最終的に裁判上の和解による解決をみたのであって、その間、同市は、右債務負担を否定し続けていたというのであるから、他方で被上告人に対して右債務負担によって損害を被ったと主張して損害賠償請求をすることはできない立場にあったものというべきである。そうだとするなら、右主張の下においては、前記和解により右違約金の一部に相当するとみられる和解金の支払が約され、市の債務負担が確定した時点において、初めて市の被上告人に対する損害賠償請求権を行使することができることとなったというのが相当であるから、右和解の日を基準として地方自治法242条2項の規定を適用すべきである。
○ 以上によれば、右和解が成立した平成…日から1年が経過する以前にされた本件監査請求は、同項の期間を遵守したものとして適法であり…
最判平9.1.28民集51.1.287にいう「財務会計上の行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実とする住民監査請求において、当該請求権が当該財務会計上の行為のされた時点ではいまだ発生しておらず、又はこれを行使することができない場合」とは、財務会計上の行為がなされた時点で請求権自体が法律上発生していない場合、又は、請求権自体は既に発生しているが、それを行使するについて法律上の障害若しくはこれと同視しうるような客観的な障害のある場合をいうとした事例 【上告審で破棄差戻しされているので注意】 名古屋高(金沢支)判平10.4.22判例時報1671.50
(談合入札について落札業者を相手方とする損害賠償請求を怠る事実に係る住民訴訟)
○ 平成9年判決(最判平9.1.28民集51.1.287)は、前記昭和62年判決(最判昭62.2.20民集41.1.122)の法理に例外のあることを認め、「財務会計上の行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実とする住民監査請求において、右請求権が右財務会計上の行為がなされた時点ではいまだ発生しておらず、又はこれを行使することができない場合には、右実体法上の請求権が発生し、これを行使することができることになった日を基準として(地方自治)法242条2項の規定を適用すべきである」旨判示している。右平成9年判決の法理による法242条2項の期間制限の規定の適用に当たっても、同項本文の本来の規定が財務会計上の行為についての住民の知、不知にかかわらず財務会計上の行為の時点から1年以内に監査請求期間を制限することにより、地方財政の健全化と財務会計上の行為の法的安定性との調和を図っていることからして、その起算点は、地方公共団体の財務会計担当者の主観的事情に左右されずにできるだけ客観的に定められるべきであるから、右判決にいう「(財務会計上の行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の)請求権が右財務会計上の行為がなされた時点ではいまだ発生しておらず、又はこれを行使することができない場合」とは、財務会計上の行為がなされた時点で右請求権自体が法律上発生していない場合、又は、請求権自体は既に発生しているが、それを行使するについて法律上の障害若しくはこれと同視しうるような客観的な障害のある場合をいうと解するのが相当であって、財務会計上の行為がなされた時点で請求権自体は既に発生しているのに、地方公共団体の財務会計担当者が当該財務会計上の行為が違法であることを知らなかったために事実上右請求権の行使ができなかったにすぎない場合は含まれないと解するのが相当である。
○ これを本件についてみるに、控訴人らの主張を前提とすれば、財務会計上の行為である本件各契約が締結された時点では、県の被控訴人らに対する損害賠償請求権が既に発生していることになる(控訴人らの主張に係る被控訴人らの不法行為(違法な談合行為)は完了し、契約当事者である県の損害が具体化している。)のに対し、控訴人らが県が公正取引委員会による課徴金納付命令が公表された平成7年8月9日までは右請求権の行使をすることができなかった理由として挙げるところは、それまでは県においても被控訴人らの談合を知りえなかったこと、すなわち財務会計上の行為である本件各契約の締結が違法であることを知らなかったというにすぎないことになる。そうしてみると、先に説示したところに照らしても、本件は平成9年判決が適用される事案ではなく、原則どおり昭和62年判決の法理を適用すべき事案であるというべきである。そう解したとしても、法242条2項ただし書の「正当な理由」の有無についての判断によって具体的妥当性をはかることが可能であるから、住民の権利行使を不当に制限するものではない。
○ なお、平成9年判決の事案は、「市が国鉄から転売禁止特約付きで買い受けた土地を特約に違反して転売したとして、国鉄を承継した国鉄清算事業団から、右土地の売買契約を解除された上、解除により発生すると定められた違約金の支払を請求され、その請求訴訟における裁判上の和解に基づき違約金の一部に相当するとみられる和解金を支払ったため、右和解金相当額の損害を被ったのに、右の違法な転売行為をした市長個人に対して取得した損害賠償請求権の行使を怠っていると主張された住民監査請求について、右訴訟において市が右特約の有効性を争い違約金債務の負担を否定し続けていたなど判示の事実関係の下においては、右和解の日を基準として地方自治法242条2項の規定を適用すべきである。」とされたものであって、右和解の日までは市の被った損害自体が具体化していない事案であるから、本件各契約の時点で既に県の損害が具体化していた本件とは事案を異にすることは明らかである。
【注】本件については、上告審において、いわゆる真正怠る事実の事案であり監査請求期間の制限を受けないとして破棄され、その上で一審判決を取り消して一審に差し戻した。同上告審判例は、次を参照。
【最高裁判例】 実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象としてされた住民監査請求において,監査委員が当該怠る事実の監査を遂げるためには,特定の財務会計上の行為の存否,内容等について検討しなければならないとしても,当該行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはない場合には,当該監査請求に地方自治法242条2項の規定は適用されない 最判平14.7.2民集56.6.1049
○ 本件は,県の住民である上告人らが,平成3年5月21日にW川について,同5年6月30日にK川について,いずれも県と被上告人B電機株式会社・・・との間で締結された水道管理所の監視制御装置更新工事の請負契約(以下「本件各契約」という。)は,被上告人らが談合をした結果に基づき受注予定者とされた被上告人B電機において県の実施した指名競争入札に応札して落札の上締結されたものであり,県は,これにより談合がなければ形成されたであろう代金額と契約代金額との差額相当の損害を被ったから,被上告人らに対し,不法行為等による損害賠償請求権を有しているにもかかわらず,その行使を違法に怠っているとして,地方自治法(以下「法」という。)242条の2第1項4号に基づき,県に代位して,怠る事実に係る相手方である被上告人らに対し,損害賠償を求める事案である。 記録によれば,上告人らは,平成7年11月27日,県の監査委員に対し,被上告人らは上記談合という共同不法行為により本件各契約の契約金額を不当につり上げて県に上記差額相当の損害を与えたのであるから,県の地方公営企業の管理者は,損害賠償請求権を行使して県の被った損害を補てんする措置を講ずべきであるのに,これを怠っているとして,措置を講ずべきことを勧告することを求める監査請求をしたというのである。
○ 原審は,次のとおり判断して,本件訴えを不適法として却下した第1審判決を是認し,上告人らの控訴を棄却した。
業者が談合したことのみによって,地方公共団体に損害が発生し,地方公共団体が業者に対して不法行為による損害賠償請求権を取得するものではない。業者の談合に基づき不正な入札価格が形成され,その価格で落札した業者が地方公共団体から工事を受注することにより,地方公共団体に損害が発生するのである。そして,業者と地方公共団体との間の請負契約の締結は,当該地方公共団体の財務会計上の行為にほかならず,その違法性は客観的に判断すべきものである。
上告人らの主張を前提とすれば,本件談合は違法であるから,これに基づき落札した被上告人B電機との間で県がした本件各契約の締結行為も,客観的に違法というべきである。したがって,本件監査請求は,財務会計職員の特定の財務会計上の行為の違法を問題としていることに帰する。そうすると,上告人らのした本件監査請求は,財務会計上の行為が違法であることに基づき発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実に係るものであるから,最高裁昭和57年(行ツ)第164号同62年2月20日第二小法廷判決・民集41巻1号122頁の示した法理に従い,法242条2項の規定が適用されるというべきである。
上記法理が適用される監査請求というべきかどうかは,監査請求人の法律構成によるのではなく,客観的に判断すべきものである。そして,被上告人らの談合による不法行為は本件各契約締結によって初めて損害が具体化するものであるから,県の被上告人らに対する損害賠償請求権が成立し,その行使を怠っているとするには,その前提として本件契約の締結が必要であり,談合による不法行為と本件契約締結行為とは必然的に結び付いている関係にある。
以上によれば,本件監査請求は,財務会計上の行為である本件各契約締結の日から法242条2項本文の規定(以下「本件規定」という。)が定める1年の監査請求期間を経過した後にされたものであって,不適法であり,本件訴えも不適法である。
○ しかしながら,本件監査請求に本件規定が適用されるとした原審の判断は,是認することができない。その理由は,次のとおりである。
法242条1項は,普通地方公共団体の住民が当該普通地方公共団体の違法,不当な財務会計上の行為又は怠る事実につき監査請求をすることができるものと規定しているところ,本件規定は,上記の監査請求の対象事項のうち行為については,これがあった日又は終わった日から1年を経過したときは監査請求をすることができないものと規定している。これは,財務会計上の行為は,たとえそれが財務会計法規に違反して違法であるか,又は財務会計法規に照らして不当なものであるとしても,いつまでも監査請求ないし住民訴訟の対象となり得るとしておくことは,法的安定性を損ない好ましくないことから,監査請求をすることができる期間を行為が完了した日から1年間に限ることとするものである。これに対し,上記の対象事項のうち怠る事実についてはこのような期間制限は規定されておらず,住民は怠る事実が現に存する限りいつでも監査請求をすることができるものと解される。これは,本件規定が,継続的行為について,それが存続する限りは監査請求期間を制限しないこととしているのと同様に,怠る事実が存在する限りはこれを制限しないこととするものと解される。
○ しかしながら,いかなる場合にも上記の原則を貫かなければならないと解すべきものではなく,本件規定の法意に照らして,その例外を認めるべき場合もあると考えられる。すなわち,監査請求が実質的には財務会計上の行為を違法,不当と主張してその是正等を求める趣旨のものにほかならないと解されるにもかかわらず,請求人において怠る事実を対象として監査請求をする形式を採りさえすれば,上記の期間制限が及ばないことになるとすると,本件規定の趣旨を没却することになるものといわざるを得ない。そして,監査請求の対象として何を取り上げるかは,基本的には請求をする住民の選択に係るものであるが,具体的な監査請求の対象は,当該監査請求において請求人が何を対象として取り上げたのかを,請求書の記載内容,添付書面等に照らして客観的,実質的に判断すべきものである。
○ このような観点からすると,怠る事実を対象としてされた監査請求であっても,特定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法であるか又はこれが違法であって無効であるからこそ発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象とするものである場合には,当該行為が違法とされて初めて当該請求権が発生するのであるから,監査委員は当該行為が違法であるか否かを判断しなければ当該怠る事実の監査を遂げることができないという関係にあり,これを客観的,実質的にみれば,当該行為を対象とする監査を求める趣旨を含むものとみざるを得ず,当該行為のあった日又は終わった日を基準として本件規定を適用すべきものである(前掲最高裁昭和62年2月20日第二小法廷判決参照)。しかし,怠る事実については監査請求期間の制限がないのが原則であり,上記のようにその制限が及ぶというべき場合はその例外に当たることにかんがみれば,監査委員が怠る事実の監査を遂げるためには,特定の財務会計上の行為の存否,内容等について検討しなければならないとしても,当該行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはない場合には,これをしなければならない関係にあった上記第二小法廷判決の場合と異なり,当該怠る事実を対象としてされた監査請求は,本件規定の趣旨を没却するものとはいえず,これに本件規定を適用すべきものではない。
○ 本件監査請求の対象事項は,県が被上告人らに対して有する損害賠償請求権の行使を怠る事実とされているところ,当該損害賠償請求権は,被上告人らが談合をした結果に基づいて被上告人B電機において県の実施した指名競争入札に応札して落札の上県と不当に高額の代金で請負契約を締結して県に損害を与える不法行為により発生したというのである。これによれば,本件監査請求を遂げるためには,監査委員は,県が同被上告人と請負契約を締結したことやその代金額が不当に高いものであったか否かを検討せざるを得ないのであるが,県の同契約締結やその代金額の決定が財務会計法規に違反する違法なものであったとされて初めて県の被上告人らに対する損害賠償請求権が発生するものではなく,被上告人らの談合,これに基づく被上告人B電機の入札及び県との契約締結が不法行為法上違法の評価を受けるものであること,これにより県に損害が発生したことなどを確定しさえすれば足りるのであるから,本件監査請求は県の契約締結を対象とする監査請求を含むものとみざるを得ないものではない。したがって,これを認めても,本件規定の趣旨が没却されるものではなく,本件監査請求には本件規定の適用がないものと解するのが相当である。前掲第二小法廷判決の示した法理は,本件に及ぶものではない。
固定資産税を課税した後これを免除したことに対し、公金の賦課徴収を怠る事実としてなされた住民監査請求は、課税免除の日を基準として監査請求期間の適用を受けるとした事例 宇都宮地判平10.5.14判例時報1670.12
(いったん賦課した固定資産税について、税額更正により課税を免除したことについて、公金の賦課徴収を怠るとして首長への損害賠償および怠る事実の違法確認を求める3・4号訴訟)
○ 被告町長の免除は、一括して平成5年度より固定資産税を免除することとしているが、平成5年度については、すでに賦課されていたのであるから、一旦発生し、確定した具体的租税債権を放棄する意味の免除でしかあり得ないのに対し、平成6年度以降は、賦課もしないこととしたのであるから、平成5年度と平成6年度以降については、異なる性質の免除がされたものと解さざるを得ない。すなわち、平成5年度については、地方税法367条に基づく免除がされ、平成6年度以降については、同法6条1項に基づく課税免除がされたというべきである。ただし、町においては、実際のところ、課税免除も減免も、その区別を認識することなく、税金を徴収しないという程度の認識で徴税事務処理が行われてきたことは、証人○の証言するところである。
○ そこで、平成5年度の免除について検討するに、原告らも町税条例○条が減免について定めていることは争っておらず、前記認定の免除前後の経緯に照らしても、被告町長の免除が単なる行政内部の措置にとどまるものと解することはできない。してみると、右免除は、一旦発生し、確定した具体的租税債権という地方公共団体の「財産」を放棄することで「処分」したものというべきであるから、地方自治法242条にいう財務会計行為に該当する。
○ なるほど原告ら主張の徴収を怠る事実は、右免除自体から直接に発生する請求権について管理の懈怠を問題としている訳ではないが、すでに具体的租税債権が発生している状況において、右免除が違法無効である場合には、右債権が存続することになるから、怠る事実の存否はすべからく前提となっている免除という財務会計行為の違法の有無に帰着し、その意味で右免除から直接に発生する請求権の管理の懈怠の場合と何ら異なるところはなく、いずれの場合においても、もともと前提として存在する財務会計行為たる免除を争うことが可能であり、また、それにより目的を達することができるものである。
○ したがって、・・・本件の場合においても、前提たる財務会計行為の免除を基準として期間制限を適用するのが相当であり、前記認定の事実からすれば、本件の監査請求が監査請求期間を徒過していることは明白である。
・・・・・・
○ 平成6年度ないし平成8年度の課税免除は、そもそも賦課しないこととしたものであるから、地方公共団体の「財産」といい得る具体的租税債権が成立しておらず、地方自治法242条1項に定める財務会計行為には該当しないこととなり、賦課及び徴収の懈怠は、怠る事実としてのみ争い得ることになる。 したがって、監査請求期間の適用はないことが明らかである。
市民税の徴収をせず時効消滅させたことについての公金賦課徴収を怠る事実を対象とする住民監査請求は監査請求期間制限の適用があり、その起算日は催告書が滞納者に到達して6か月を経過した日とした事例 浦和地判平12.4.24判例地方自治210.35
○ 原告等は、本件徴収権を時効によって消滅させたことが違法であることに基づいて発生した実体法上の損害賠償請求権を行使しないことが、財産の管理を怠る事実に該当するというが、前記監査請求において、右事由を理由とする監査請求を含むと解しても、この場合であっても、当該監査請求期間は、右怠る事実にかかる損害賠償請求権の発生原因となった当該行為のあった日又は終わった日を基準として、地方自治法242条2項の規定を適用すると解するのが相当である。けだし、本件徴収権を時効によって消滅させたことが違法であるとして、当該職員に発生した実体法上の損害賠償請求権の不行使が怠る事実に該当するとしても、実質上問題となるのは、本件滞納者に対する徴収権を時効によって消滅させたことの適否であり、しかも、求める是正措置も同じであることにかんがみれば、監査請求の期間制限を受けずに当該行為の違法是正等の措置を請求し得るとすれば、同条により監査請求の期間制限を受けた趣旨が没却され、著しく不合理な結果となるので、原告等の右主張は、採用できない。
○ 原告等は、予備的主張として、○年度分の市民税の徴収を怠る事実が終了した日とは、消滅時効が完成する直前に発せられた催告書が本件滞納者に到達してから6か月が経過した時点であるところ、本件監査請求は、いずれも右6か月が経過する前にされているから、適法であると主張する。
○ 前記認定した事実によると、本件補助職員は、平成8年11月28日、○年度分の市民税について民法153条に基づいて催告書を発したことが認められるが、被告は、右催告書が本件滞納者に到達してから6か月を経過するまでに、同条所定の措置を講じることによって、○年度の市民税の徴収権の消滅時効を中断することができるので、右時点まで、すなわち平成9年5月28日ころまでは、○年度分の市民税につき民法153条に定める措置を執って消滅時効を中断し、右市民税を徴収する義務を負っていたと認めるのが相当である。そうすると、○年度分の市民税の徴収を怠る事実が終了した日とは、平成8年11月28日に発した催告書が本件滞納者に到達してから6か月を経過した日(平成9年5月28日ころ)と解すべきであるところ、本件監査請求のうち、○年度の市民税の徴収を怠ったことに関する部分は、平成9年5月28日ころから1年経過する前にされている・・・ので、地方自治法242条2項の要件を充たし、適法な監査請求であることが認められる。
単純労務職員の定年後も勤務延長措置をとり例月の給与を支給した場合、監査請求期間の起算日はそれぞれの支出命令日から起算されるのであり、これら支出を一体としてとらえ、最終の財務会計行為の日から起算すべきものではないとした事例 大阪地判平12.4.28
○ 地方自治法242条2項は、監査請求は、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができない旨規定している。ここにいう当該行為とは、同条1項に列挙されている事項であるが、同項がまず、財務会計上の行為を行う主体として長、委員会、委員又は職員を列挙した後で、財務会計上の行為として契約の締結、公金の支出、財産の取得等を列挙していること、そして、通常は各個別の財務会計上の行為についてそれぞれ独立してその違法性、不当性を問題とし得ること、さらに、法は地方公共団体の機関又は職員の行為をいつまでも争い得る状態にしておくことが法的安定性の観点から妥当ではないので監査請求期間を1年と限定して法的な安定性を確保したと解されることからすると、監査請求期間も個々の財務会計行為ごとに判断すべきである。
○ しかしながら、各別の財務会計上の行為が観念できる場合であっても、それぞれが相互に密接に関連し不可分一体となり、全体としてみなければその違法性あるいは不当性を判断することができないような特段の事情がある場合には、これを一体としてとらえ、最終的な財務会計上の行為が行われた日をもって当該行為の終わった日と解すべきである。
○ これを本件についてみると、本件各支出命令は、本件勤務延長を前提とするものではあるが、それぞれ個別の根拠に基づき発せられ、それぞれ個別の財務会計法規がこれを規律しているものであり、これを一体としてとらえるべき特段の事情は認められないというべきである。
町有温泉給湯契約のような継続的契約であっても、契約の履行行為について固有の違法事由を主張しているとはいえない住民監査請求については、契約締結日を起算とする監査請求期間に監査請求を行うべきであるとした事例 盛岡地判平12.6.16
(町有温泉につき、議会の議決を経ずに、また町条例に定める審議会に付議せずに、温泉湯を無償で供給する契約を締結したことに対する住民監査請求・住民訴訟)
○ 原告らは、本件契約のような継続的契約については、地方自治法242条2項にいう「終わった日」とは契約関係が終了した日を指すものと解すべきであるとし、本件契約については、未だ監査請求期間を徒過していない旨主張する。しかしながら、地方自治法242条2項本文が監査請求に期間制限を設けたのは、地方公共団体の執行機関・職員の財務会計上の行為は、たとえそれが違法・不当なものであったとしても、いつまでも監査請求ないし住民訴訟の対象となり得るとしておくことが法的安定性を損ない好ましくないとの趣旨にでたものであると解されるところ(最高裁判所昭和63年4月22日第二小法廷判決・裁判集民事第154号57頁参照)、本件契約のような継続的契約については、長期間にわたってその締結の違法を主張することができるとすると、監査請求に期間制限を設けた法の趣旨が没却されることとなり、相当ではない。したがって、地方自治法242条2項にいう「当該行為の・・・終わった日」とは、行為自体が継続して行われる場合において、その終わった日を意味するものと解すべきである。
○ 本件監査請求の対象とされている財務会計行為は、契約の締結という一時的な行為であるから、右「終わった日」とは、同条にいう「当該行為のあった日」即ち右契約の締結日というべきである。そうすると、右監査請求の期間は、右契約の締結日から起算するものと解するのが相当である。・・・
○ また、原告らは、本件監査請求は、本件契約の締結行為のみならず、その履行行為をも監査の対象としたものである旨主張する。しかしながら・・・、本件監査請求にかかる「・・・町職員措置請求書」の記載内容は、専ら本件契約の締結が違法ないし不当であることを主張しているものと解されるのであって、これを契約の締結行為のみならず、あえてその履行行為をも監査の対象としたものと見ることには無理がある。仮に、本件監査請求が契約の締結行為のみならず、その履行行為をも監査の対象としたものであると解する余地があるとしても、右監査請求は、契約の締結行為の違法とは無関係に契約の履行行為について固有の違法事由を主張しているとは到底見ることができないから、この点は監査請求期間を本件契約締結日から起算すべきであるとの結論を左右するものではないと解すべきである。けだし、契約の履行行為が続いている限り、履行行為そのものに何ら固有の違法事由がなくても、契約締結行為の違法を契約の履行行為の違法として監査請求の対象とすることにより、監査請求期間の制限を受けないこととなるとすれば、実質的に契約内容の違法をいつまでも争い得ることとなり、前記2のような監査請求期間を設けた趣旨が没却されることとなるからである。
契約締結からは1年以上経過したが公金支出からは1年を経過しない時点でなされた住民監査請求については、契約締結という財務会計行為部分については監査請求期間を経過したものであり、契約に基づく公金支出である以上公金支出終了日を監査請求期間の起算日とすべきとする原告の主張を排斥した事例 静岡地判平成14.3.28判例地方自治232.84
(事実関係略)
○ (地方自治)法242条第2項が監査請求の請求期間を制限した趣旨は、普通地方公共団体の職員等の当該行為の適法性あるいは相当性をいつまでも争うことができる状態にしておくことは法的安定性の見地から望ましくないため、なるべく早期にこれを確定させようとした点にあると考えられる。そこで、本件各監査請求の起算点は、当該行為のあった日、すなわち、本件各契約の締結行為がなされた日(契約締結時)と解するのが相当である。しかも、本件各監査請求は、随意契約の要件を満たさないことや財務規則に違反したことなど契約締結行為(契約の方法)に違法があることを理由とするものであるところ、法の同条1項が財務会計行為について「契約の締結」と「公金の支出」を分けて規定していることから考えると、契約の締結があり、その後同契約に基づいて公金の支出がされた場合であっても、契約締結の不当を主張する監査請求の起算点を、後者の公金支出の時点であるとすることはできないというべきである。原告らの主張のように起算点を公金支出の終了時点であるとすると、本件のように契約の締結と委託料の支出という2つの財務会計行為が存在する場合、契約の締結という基本的事実から1年が経過し、これについてその違法性が争えないことになるはずであるのに、契約の履行に過ぎない委託料の支出という付随的事実に着目すれば、再び契約の締結自体についても監査請求が可能ということになり、早期に法的安定性を確保しようとする法の趣旨に反することになる。よって、この原告らの主張は採用できない。・・・
○ なお、県監査委員が、本件各監査請求のうち、平成10年度契約に関するものについて、委託料支出時から1年以内になされていることを理由に、適法な住民監査請求であると判断し、監査を行ったとしても、そのことによって、監査請求の期間を徒過した、平成10年度契約に関する本件各監査請求ひいては本件訴えが適法となるものではないことも当然である。
カラ出張旅費の財源の一部に国庫補助金が含まれ国から返還命令を受けたことに伴い提起された、損害賠償請求権行使を怠る事実を監査対象とする住民監査請求において、本件は国庫精算返還金支出による損害賠償請求権行使を怠る事実を監査対象とするものであり、旅費支出の違法に伴う請求権不行使を怠る事実と構成するものではない以上、国庫返還の補正予算成立ないし実際の返還支出から1年以内になされた住民監査請求は、監査請求期間内になされたものとした事例 名古屋高(金沢支)判平14.4.15
(職員のカラ出張による旅費財源の一部に国庫補助金が充当されていたため国から返還命令を受けたことに伴い、首長に対し旅費支出専決権者に対する損害賠償請求権を行使しないことが違法であることの確認を、首長個人に自治体に代位しての損害賠償を請求する住民訴訟。原審は、控訴人らが首長が行使を怠っていると主張する損害賠償請求権は、旅費支出が違法又は無効であることに基づいて発生したものであり、首長その他の職員の特定の財務会計上の行為が違法無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって、違法に財産の管理を怠る事実と構成している場合には、この監査請求期間は、その怠る事実に係る請求権の発生原因たる当該行為のあった日又は終わった日から起算すべきであるところ、本件監査請求は、最後の旅費支出からでも約2年経過しており、監査請求期間徒過・正当理由不在により訴えを却下)
○ 住民監査請求及びこれに引き続き提起される住民訴訟において、その対象となる財務会計上の行為又は怠る事実は、当該住民が定めるべきものであるから、監査請求書及びその添付書類並びに訴状などを総合的に判断し、当該住民の主張が監査請求書などに記載された事実に反する場合には、もとよりその主張を認めることはできないが、そうでなければ、その法律構成が監査請求期間を潜脱するためのものであるなどの許容できない特段の事情のない限り、判断の対象となる財務会計上の行為又は怠る事実は、当該住民の主張に拘束されるというべきである。そこで、控訴人らの上記主張の当否について検討する。
○ ・・・によれば、控訴人らは、平成11年8月24日、県監査委員に対し、職員措置請求書・・・及び事実証明書・・・を提出して、本件監査請求を行ったが、同請求書には、県が本件旅費支出に係る国庫返還精算金を国に返還するために一般会計補正予算を組み、県議会でこれを可決したことに関して、〈1〉国庫精算返還金の支出を差し止めること、〈2〉既に支出された分については、県が被った損害を填補するための必要な措置を採ること、〈3〉国庫精算返還金の支出に見合う収入を県知事及び県管理職から追徴すべきこと等を求める旨の記載のあることが認められる。もっとも、事実証明書・・・には、本件国庫精算返還金の内訳明細として、<イ>平成11年7月30日返還分合計1419万8419円、<ロ>平成11年8月13日返還分合計2億7458万4013円、並びに<ハ>平成11年8月20日返還分合計4383万1953円(上記の金額はいずれも加算金等を含んだ金額)のみが明示されているが、職員措置請求書・・・によれば、「県議会は、カラ出張に係る国庫精算返還金5億5000万円を支出する旨の平成11年度県一般会計補正予算を議決し」との記載がある他、控訴人らは国庫精算返還金の将来的な支出の差し止めも求めており、上記の事実証明書・・・にも、「県は総務庁以下9庁に対し、215百万円(内加算金54百万円 加算金の返還金に占める割合は25.12%)の返還を予定しており」との記述があることも併せて勘案すると、控訴人らは、上記<イ>、<ロ>、<ハ>の国庫精算返還金の支出のみならず、その後に支出されたものも含めた本件国庫精算返還金合計5億4555万0930円の全体について、監査請求を行ったものと認めるのが相当である。そして、本件訴訟の被控訴人知事に対する請求の趣旨は、「被控訴人知事が平成6年度ないし平成9年度の間の事務処理上不適切な旅費支出によって生じた損害金5億4555万0930円について、別紙『氏名』欄各記載の旅費支出専決権者に対して、別紙『返還額』欄各記載の金額の損害賠償請求をしないことが違法であるを確認する。」というものであり、その請求原因でも、県が本件国庫精算返還金の支出によって損害を受けたと主張しているのであるから、控訴人らが本件監査請求において求めたのは、本件国庫精算返還金の支出によって県に生じた損害の回復・是正であり、また、本件訴訟においては、その回復・是正をしないことの違法確認であると認められる。
○ 以上のことからすると、控訴人らが本訴において求めているのは、本件国庫精算返還金の支出に基づいて発生したと主張する本件損害賠償請求権を被控訴人知事が行使しないことの違法確認であり、本件監査請求も、同旨の趣旨を含むものと認めるのが相当であり、これを敢えて、本件旅費支出が違法無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって、怠る事実と構成しているとみなす合理的根拠はない。そうすると、引用した原判決の前提事実記載のとおり、本件国庫精算返還金の国庫に対する返還に関する補正予算の県議会の議決がなされたのは、平成11年7月14日であり、これを受けて被控訴人知事が本件国庫精算返還金を国庫に返還したのは、同年7月30日から同年9月30日までであるのに対し、控訴人らの本件監査請求が県監査委員になされたのは、同年8月24日であるから、本件監査請求は、地方自治法242条2項本文に定める期間(1年間)内になされたものと認められる。
【最高裁判例】 公金の支出を構成する支出負担行為,支出命令及び支出については,地方自治法242条2項本文所定の監査請求期間は,それぞれの行為のあった日から各別に計算すべきである 最判平14.7.16民集56.6.1339
(X年8月21日から9月9日までの日程で実施された議会欧州行政視察旅行は,その実体は単なる観光旅行であって,その旅費等の支出は地方財政法4条1項等に違反する違法なものであるとして,住民が県に代位して,議員の旅費等の支出負担行為兼支出命令をしたA1及び随行員の旅費等の支出負担行為兼支出命令をしたA2に対し,各旅費等相当額の損害の賠償を請求する4号訴訟。本件の各支出負担行為兼支出命令をしたのはX年8月9日であり,原告がこれらにつき監査請求をしたのはX+1年8月13日)
○ 住民監査請求は,財務会計上の行為又は怠る事実を対象として行われるものであるところ,行為についての監査請求は,当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは,これをすることができないものとされている(地方自治法242条2項本文)。そして,ここにいう当該行為とは,具体的な個々の財務会計上の行為をいうものと解される。
○ 公金の支出は,具体的には,支出負担行為(支出の原因となるべき契約その他の行為)及び支出命令がされた上で,支出(狭義の支出)がされることによって行われるものである(地方自治法232条の3,232条の4第1項)。これらのうち支出負担行為及び支出命令は当該地方公共団体の長の権限に属するのに対し,支出は出納長又は収入役の権限に属するのであり,そのいずれについてもこれらの者から他の職員に委任等により各別に権限が委譲されることがある。また,これらの行為に適用される実体上,手続上の財務会計法規の内容も同一ではない。このように,これらは,公金を支出するために行われる一連の行為ではあるが,互いに独立した財務会計上の行為というべきものである。そして,公金の支出の違法又は不当を問題とする監査請求においては,これらの行為のいずれを対象とするのかにより,監査すべき内容が異なることになるのであるから,これらの行為がそれぞれ監査請求の対象事項となるものである。もっとも,公金の支出を構成するこれらの行為を併せて監査請求の対象とすることも許され,これらを明確に区別しないでされた監査請求が対象事項の特定を欠き不適法となるものではないが,これらにつき各別に監査請求をすることができることはいうまでもないところである。
○ 以上によれば,支出負担行為,支出命令及び支出については,地方自治法242条2項本文所定の監査請求期間は,それぞれの行為のあった日から各別に計算すべきものである。
○ 本件は前記旅費等につき支出負担行為兼支出命令をした職員である上告人らに対し損害賠償請求をする住民訴訟であるから,これに前置すべき監査請求は各支出負担行為兼支出命令のあった日から1年以内にこれをしなければならないところ,前記のとおり,被上告人は,その日から1年を経過した後に監査請求をしたというのである。そうすると,本件の監査請求は,請求期間を経過した後にされたものというほかはない。そして,被上告人はX+1年2月13日には上記旅費等の存在及び内容を知ったというのであるから,その日を基準にしても6箇月経過後にされた上記監査請求には,地方自治法242条2項ただし書所定の正当な理由もないことが明らかである。
○ 以上のとおりであるから,本件訴えは,適法な監査請求を経たものとはいえず,不適法というべきであり…
【最高裁判例】 監査請求期間の起算日である「当該行為があった日」「終わった日」の意義およびこれら起算日の客観性 最判平14.9.12民集56.7.1481
(事実関係略)
○ (地方自治)法242条2項本文は,財務会計上の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは監査請求をすることができない旨を定めるところ,上記行為のあった日とは一時的行為のあった日を,上記行為の終わった日とは継続的行為についてその行為が終わった日を,それぞれ意味するものと解するのが相当であり,当該行為が外部に対して認識可能となるか否かは,同項本文所定の監査請求期間の起算日の決定に何ら影響を及ぼさないというべきである。
【最高裁判例】
①財務会計職員が行った財務会計上の行為の準備行為が違法であることに基づいて発生する当該職員に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象としてされた住民監査請求については,上記違法が財務会計上の行為の違法を構成する関係にある場合には,財務会計上の行為のあった日又は終わった日を基準として地方自治法242条2項の規定が適用される
②財務会計職員の補助職員が行った財務会計上の行為の補助行為が違法であることに基づいて発生する当該補助職員に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象としてされた住民監査請求については,上記違法が財務会計上の行為の違法を構成する関係にある場合には,財務会計上の行為のあった日又は終わった日を基準として地方自治法242条2項の規定が適用される 最判平14.10.3民集56.8.1611
(県が発注した公共施設建設工事の増額変更契約を行い,この金額を支払ったことについて,共同企業体各企業に対しては,本変更契約は,元来の請負契約では認められないJV赤字補填のため,工事単価水増し等がなされており,違法無効な変更契約で不当利得を得たことについて,知事,建築部担当副知事,建築部・総務部の幹部職員等に対しては,被告県議の働きかけにより,これが違法無効の契約と知り,または知ることができたのに,追加変更予算を作成し,議会に事実を隠蔽して予算を成立させ,違法に増額分の公金を支出したことは,県への共同不法行為であるとして,損害賠償を求めるもの)
○ 本件規定(地方自治法242条2項本文)は,監査請求の対象事項のうち財務会計上の行為については,当該行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは監査請求をすることができないものと規定しているが,上記の対象事項のうち法242条1項にいう怠る事実については,このような期間制限は規定されておらず,怠る事実が存在する限りはこれを制限しないこととするものと解される。もっとも,特定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法であるか又はこれが違法であって無効であるからこそ発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象として監査請求がされた場合には,これについて上記の期間制限が及ばないとすれば,本件規定の趣旨を没却することとなる。したがって,このような場合には,当該行為のあった日又は終わった日を基準として本件規定を適用すべきものである(前掲第二小法廷判決参照(注:昭和62年02月20日 民集41.1.122))。しかし,怠る事実については監査請求期間の制限がないのが原則であることにかんがみれば,監査委員が怠る事実の監査をするに当たり,当該行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にない場合には,当該怠る事実を対象としてされた監査請求に上記の期間制限が及ばないものとすべきであり,そのように解しても,本件規定の趣旨を没却することにはならない(最高裁平成10年(行ヒ)第51号同14年7月2日第三小法廷判決・民集56巻6号1049頁参照)。
○ 記録によれば,本件監査請求は,県建築部及び総務部の幹部が,被上告会社9社の要請を受け,本件工事に関し,単価の水増し等の操作により設計変更予算案を違法に作成し,県議会に対してその事実を隠ぺいしたため,増額変更予算の執行議案が原案どおり可決承認され,29億円余を不当に追加する本件変更契約が締結されたとして,財務会計職員その他の職員等による本件変更契約の締結その他これにかかわる行為等を対象としているが,そのほか,被上告会社9社が,県に対し,本件工事に関し不当に水増し請求をするなどし,県に本来支払う義務のない工事代金29億円余を余分に支払わせたとし,県は,被上告会社9社に対しこの不法行為により受けた損害である上記金員相当額を賠償させるべきであるのに,当該請求権の行使を怠っているという事実を対象に含んでいることが明らかである。本件監査請求中上記怠る事実について監査を遂げるためには,監査委員は,被上告会社9社について上記行為が認められ,それが不法行為法上違法の評価を受けるものであるかどうか,これにより県に損害が発生したといえるかどうかなどを確定しさえすれば足りる。本件監査請求には,財務会計職員その他の職員が被上告会社9社の要請を受けて本件変更契約の締結その他これにかかわる行為を行ったなどとする部分が含まれているが,このことによって上述したことは左右されない。県の被上告会社9社に対する損害賠償請求権は,本件変更契約が違法,無効であるからこそ発生するものではない。したがって,上記監査請求について本件規定の適用がないものと認めても,本件規定の趣旨が没却されるものではなく,監査請求期間の制限が及ばないものと解するのが相当である。そうすると,本件監査請求中,本件工事に関し,前記不法行為により,県に本来支払う義務のない工事代金を余分に支払わせた被上告会社9社に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分は,監査請求期間を徒過した不適法なものということはできない。
(以下、職権による検討)
1 被上告人B10(注:副知事)に対する請求
(1) 「当該職員」に対するものとしてされた損害賠償請求
記録によれば,被上告人B10は,本件変更契約締結当時副知事であったところ,本件変更契約締結につき法令上本来的権限を有する知事から委任を受け,又は専決する権限を付与されていたものと認めることはできない。したがって,本件訴えのうち上告人らの被上告人B10に対する上記請求に係る部分は,不適法として却下すべきである…。
(2) 怠る事実に係る相手方に対するものとしてされた損害賠償請求
記録によれば,本件監査請求は,本件工事に関し,被上告人B10が,被上告会社9社による前記不法行為に違法に荷担したとし,県が被上告人B10に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠っているという事実を対象に含むものということができる。本件監査請求中上記怠る事実について監査を遂げるためには,監査委員は,被上告人B10について上記行為が認められ,それが不法行為法上違法の評価を受けるものであるかどうか,これにより県に損害が発生したといえるかどうかなどを確定しさえすれば足りる。県の被上告人B10に対する損害賠償請求権は,本件変更契約が違法,無効であるからこそ発生するものではない。したがって,上記監査請求については本件規定による監査請求期間の制限が及ばないものと解するのが相当である。そうすると,本件監査請求中被上告人B10に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分は,監査請求期間を徒過した不適法なものということはできない…。
3 被上告人B15(注:前建築部長)に対する請求
(1) 「当該職員」に対するものとしてされた損害賠償請求
記録によれば,被上告人B15は,本件変更契約締結前の…から…まで県建築部長であったところ,…の本件変更契約締結の時点では既に同部長の職にはなく,本件変更契約につき,その時点で,法令上本来的権限を有する知事から委任を受け,又は専決する権限を付与されていたものと認めることはできない。したがって,本件訴えのうち上告人らの被上告人B15に対する上記請求に関する部分は,不適法として却下すべきである…。
(2) 怠る事実に係る相手方に対するものとしてされた損害賠償請求
記録によれば,本件監査請求は,本件工事に関し,被上告人B15が,X年2月ころ,本件変更契約につき専決権限を有する県建築部長として単価の水増し等の操作による違法な設計変更予算案の作成等の本件変更契約締結の準備行為をし,その結果,同年7月,29億円余を不当に追加する本件変更契約が締結されたとして,県が被上告人B15に対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠っているという事実を対象に含むものということができる。特定の財務会計上の行為が行われた場合において,これにつき権限を有する職員又はその前任者が行ったその準備行為は,財務会計上の行為と一体としてとらえられるべきものであり,準備行為の違法が財務会計上の行為の違法を構成する関係にあるときは,準備行為が違法であるとし,これに基づいて発生する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象としてされた監査請求は,実質的には財務会計上の行為を違法と主張してその是正を求める趣旨のものにほかならないと解される。したがって,上記のような監査請求が本件規定の定める監査請求期間の制限を受けないとすれば,法が本件規定により監査請求に期間制限を設けた趣旨が没却されるといわざるを得ないから,上記監査請求には当該財務会計上の行為のあった日又は終わった日を基準として本件規定を適用すべき【要旨①】である。 上記事実によれば,被上告人B15は,本件変更契約締結当時の県建築部長の前任者と認められるところ,本件監査請求において被上告人B15のした本件変更契約締結の準備行為で違法とされているものは,本件変更契約の違法を構成する関係にあるから,本件監査請求中,上記準備行為の違法を理由とする損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分については,本件変更契約の締結日を基準として本件規定を適用すべきである。…
4 被上告人B16(注:建築部技監),同B17(注:建築部営繕課長),同B12(注:総務部次長)及び同B18(注:建築部建設専門監)に対する請求
(1) 記録によれば,本件監査請求は,本件工事に関し,同被上告人らが,X年2月ころ,単価の水増し等の操作による違法な設計変更予算案の作成等の本件変更契約締結の補助行為をし,その結果,同年7月,29億円余を不当に追加する本件変更契約が締結されたとして,県が同被上告人らに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠っているという事実を対象に含むものであるところ,同年2月当時,被上告人B16は県建築部技監,同B17は県建築部営繕課長,同B12は県総務部次長,同B18は県建築部建設専門監であり,いずれも本件変更契約締結の権限を有する財務会計職員ではなかったことが認められる。特定の財務会計上の行為が行われた場合において,これにつき権限を有する職員を補助する職員が行ったその補助行為は,財務会計上の行為と一体としてとらえられるべきものであり,補助行為の違法が財務会計上の行為の違法を構成する関係にあるときは,補助行為が違法であるとし,これに基づいて発生する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象としてされた監査請求は,実質的には財務会計上の行為を違法と主張してその是正を求める趣旨のものにほかならないと解される。したがって,上記のような監査請求が本件規定の定める監査請求期間の制限を受けないとすれば,法が本件規定により監査請求に期間制限を設けた趣旨が没却されるといわざるを得ないから,上記監査請求には当該財務会計上の行為のあった日又は終わった日を基準として本件規定を適用すべき【要旨②】である。
(2) 上記事実によれば,被上告人B16,同B17及び同B18は,県建築部長を補助する職員と認められるところ,本件監査請求において上記3名のした本件変更契約締結に関する事務の補助行為で違法とされているものは,本件変更契約の違法を構成する関係にあるから,本件監査請求中,上記補助行為の違法を理由とする損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分については,本件変更契約の締結日を基準として本件規定を適用すべきである。…
(3) これに対し,被上告人B12は,職制上,県建築部長を補助する職員ではなく,その行為が本件変更契約締結に関する事務を補助する行為に当たると認めるべき特段の事情もいまだ確定されていないから,本件監査請求中,被上告人B12の行為の違法を理由とする損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分については,本件規定は直ちには適用されないものというべきである。そうすると,上記監査請求は,前記1(2)と同様に,監査請求期間を徒過した不適法なものと断ずることはできず,これと異なる判断の下に,本件訴えのうち被上告人B12に対する請求に関する部分を不適法として却下すべきものとした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があり,同部分につき原判決は破棄を免れない。…
公の施設の不法占拠者(1年以上前に退去済み)に対し損害賠償・不当利得返還請求を怠る事実を対象とする住民監査請求については、監査請求期間の制限を受けないとした事例 東京地判平14.10.11判例地方自治242.36
○ 被告A及び被告Bは、本案前の主張として、被告Aが、遅くとも平成10年9月28日までには、○福祉会館からの退去を完了させ、また、被告Bが、遅くとも同月30日までには、区からの受託業務以外での同会館の利用を中止したことから、原告らの主張する公の施設の違法な管理は、遅くともこれらの日までに終了したものであるところ、本件監査請求は、1年以上を経過した平成12年3月28日に行われたものであるから、監査請求期間を徒渦した不適法なものであり、原告らの被告A及び被告Bに対する訴えは、適法な監査請求を経ていないものとして却下されるべきであると主張する。
○ しかしながら、・・・原告らは、被告A及び被告Bに対しては、○福祉会館の不法占拠による損害賠償請求を区長に勧告することを求めて、本件監査請求を行ったことが認められ、本件監査請求は、被告A及び被告Bとの関係においては、区長が○福祉会館の不法占拠を理由とする損害賠償請求権の行使を怠る事実が、地方自治法242条1項の「財産の管理を怠る事実」に該当するものとして、当該損害賠償請求権の行使を求めたものと解することができる。そして、原告らは、本件訴えにおいて、被告A及び被告Bに対する損害賠償請求権及び住民監査請求の観点からこれと実質的同一性を有すると認められる不当利得返還請求権について、区の職員による○福祉会館の違法な管理という財務会計上の行為又は同会館の管理を怠る事実に基づいて発生したものと主張するのではなく、被告A及び被告Bによる所有権の事実的侵害に基づいて発生したものと主張して、その代位行使を求めているものである。
○ そうすると、原告らは、財務会計上の行為の違法等に基づいて発生した実体法上の請求権の不行使をもって「財産の管理を怠る事実」とするものでなく、当該地方公共団体の職員以外の第三者による財産権侵害による不法行為及び不当利得に基づく実体法上の請求権の不行使をもって「財産の管理を怠る事実」とするものであって、このような請求権の行使を怠ることを主張して行う監査請求については、地方自治法242条2項に規定する監査請求期間の制限を受けないものというべきである。
消防団に支出された助成金の目的外使用に対し損害賠償・不当利得返還請求を怠る事実を対象とする住民監査請求については、監査請求期間の制限を受けないとした事例 東京地判平14.10.11判例地方自治242.36
(消防団に対する助成金が、目的外経費である飲食費に費消されていたことについて、消防団長に対する損害賠償請求を怠る事実を対象とする住民監査請求・住民訴訟)
○ 原告が行った本件監査請求の内容は、本件助成金の使途のうち、本件大会に参加した○分団以外の団員の慰労費、昼食、飲物等名下での81万2929円、及び、第一分団の費用とされた100万円から激励会名下の飲食費として11万0243円、飲物代26万0820円、氷代3万2000円、弁当代1万7610円、夕食代補助22万2500円、祝勝会費19万8975円を問題とし、これらは、本来個人で負担すべき飲食費を公費で賄うもので、助成事業の対象として不法なものが圧倒的であると主張した上、このような違法な公金支出を決裁し実行した市長(被告A)と消防団長(被告B)らに対し、損害賠償金ないし不当利得金を市に返還、補てんさせるなどの措置を求めるものと認められる。この事実からすれば、原告が本件監査請求の対象としたのは、本件助成金の支出額が確定した段階で、精算手続として行われる財務会計上の行為の違法又は不当、あるいは、本件助成金の交付を受けた消防団の団長である被告Bに対する損害賠償請求権の行使を怠る事実であると解される。
○ ところで、(地方自治)法242条2項本文は、怠る事実については監査請求期間の制限を規定していないのであって、これは、継続的行為について、それが存続する限りは監査請求期間を制限しないこととしているのと同様に、怠る事実が存在する限りはこれを制限しないこととするものと解され、ただ、怠る事実を対象としてされた監査請求であっても、特定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法であるか又はこれが違法であって無効であるからこそ発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象とするものである場合には、例外的に、当該行為のあった日又は終わった日を基準として同条項を適用すべきものと解される(最高裁判所昭和62年2月20日第二小法廷判決、民集41巻1号122頁参照)。したがって、監査委員が怠る事実の監査を遂げるためには、特定の財務会計上の行為の存否、内容等について検討しなければならないとしても、当該行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはない場合には、当該怠る事実を対象としてされた監査請求は、上記制限規定の趣旨を没却するものとはいえず、これに同制限規定を適用すべきものではないと解するのが相当である(最高裁判所平成14年7月2日第三小法廷判決、裁判所時報1218号1頁参照)。
○ 上記のとおり、本件監査請求の対象事項は、本件助成金の支出額が確定した段階で精算手続として行われる財務会計上の行為の違法又は不当、あるいは、本件助成金の交付を受けた消防団長である被告Bに対する損害賠償請求権の行使を怠る事実であると解される。市が被告らに対して有する損害賠償請求権の行使を怠る事実については、原告の主張するところによれば、被告Bが消防団に交付された本件助成金をその目的外に支出した不法行為により発生した損害賠償請求権についてのものということになる。そうすると、本件監査請求を遂げるためには、監査委員は、消防団における本件助成金からの個々の支出の当否について検討しなければならないけれども(市長による本件助成金の支出やその精算手続による支出額の確定が財務会計法規に違反する違法なものであったとされて初めて市の被告らに対する損害賠償請求権が発生するものではなく)、消防団による本件助成金の使途が不法行為法上違法の評価を受けるものであること、これにより市に損害が発生したことなどを確定しさえすれば足りるのであるから、本件監査請求の対象は、それは財務会計上の行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権とはいえない。したがって、本件は、上記例外的に、監査請求権期間の制限規定が適用される場合に当たらないというべきである。
【最高裁判例】 賃貸借契約の締結を対象とする住民監査請求においては,契約締結の日を基準として地方自治法242条2項本文の規定を適用すべきである 最判平14.10.15集民208.157
(自治体と被告企業等の間で締結した土地賃貸借契約が無効であるとして,住民が自治体に代位して,本件土地の賃貸借契約に基づき土地上の建物を所有し土地を占有等する各被告に,所有権に基づき,建物収去・土地明渡し等を求めるとともに,土地の無権原占有を理由とする不法行為等に基づく,上記各被告及び首長への賠償請求等を求めるもの及び市の土地賃貸借契約条項にある借地権第三者譲渡の際の承諾料支払を求めるもの。監査請求は賃貸借契約締結から1年以上経過後に提起)
○ (地方自治法242条2)項本文にいう当該行為のあった日とは一時的行為のあった日を,当該行為の終わった日とは継続的行為についてその行為が終わった日を,それぞれ意味するものと解するのが相当である。前記事実関係によれば,本件監査請求においては,本件賃貸借契約の締結がその対象となる行為とされているところ,契約の締結行為は一時的行為であるから,これを対象とする監査請求においては契約締結の日を基準として同項本文の規定を適用すべきである。これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。
(本件原審:仙台高判平9.11.26判例タイムズ982.123)
○ 控訴人らは、賃貸借契約のようにその効力が相当期間継続する契約の締結の場合には、契約が終了した日が「当該行為の……終わった日」として監査請求期間の起算点となると主張するが、「当該行為のあった日」が一時的行為のあった日を意味するのに対し、「当該行為の……終わった日」とは、行為自体が継続して行われる場合において、その終わった日を意味するものと解すべきであるし、契約の効力がその終了・消滅事由が発生するまで継続することは、何も賃貸借契約に限られるものではなく、すべての契約に当てはまるものであるから、控訴人ら主張のように解することはできない。(地方自治)法242条2項本文が監査請求に期間制限を設けたのは、地方公共団体の執行機関又は職員の財務会計上の行為をいつまでも争い得る状態にしておくことが法的安定の見地からみて妥当でないとの趣旨にでたものであるところ、控訴人ら主張の見解をとると、賃貸借契約についてのみ他の売買契約等と異なり、長期間契約締結の違法を主張して監査請求をすることができることとなって、監査請求に期間制限を設けた右の趣旨が没却されることとなり、相当でない。
○ また、控訴人らは、その監査請求は契約締結行為とともにその履行を継続していることも対象としていたもので、賃貸借契約における履行としての「土地の賃貸」という財務会計上の行為は現在も継続しているから、監査請求の期間制限は問題とならないと主張する。しかしながら、契約の締結行為とその履行行為とは、財務会計上の行為として別個のものであり、それぞれが独立して監査請求及び住民訴訟の対象となり得るものと解すべきであるところ、第一事件の対象とされる財務会計上の行為が本件賃貸借契約の締結行為であることは、前記のとおりであり、控訴人らは、その後の本件賃貸借契約の履行行為について、契約締結行為とは別個の違法事由があるとして、これを本件住民訴訟の対象としているものではなく、かつ、本件賃貸借契約締結行為自体を違法・不当な財務会計上の行為として監査請求の対象としているもので、その履行行為を右締結行為とは別個の対象として監査請求していないから、控訴人らの右主張は失当である。
市が三セク会社に駐車場の管理業務を委託し各月委託料を支出した場合、監査請求期間の起算日はそれぞれの支出命令日から起算されるのであり、これら支出を一体としてとらえ、最終の財務会計行為の日から起算すべきものではないとした事例 大阪地判平15.10.30判例地方自治258.49
○ 住民監査請求は、財務会計上の行為又は怠る事実を対象として行われるものであるところ、行為についての監査請求は、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは、これをすることができないものとされている((地方自治)法242条2項本文)。ここにいう当該行為とは、同条1項に列挙されている行為であるが、〈1〉同項が財務会計上の行為として契約の締結、公金の支出、財産の取得等を個別に列挙していること、〈2〉通常は、各個別の財務会計上の行為についてそれぞれ独立してその違法性、不当性を問題とし得ること、〈3〉同条2項は、地方公共団体の機関又は職員の行為をいつまでも争い得る状態にしておくことが法的安定性の観点から妥当ではないため、監査請求期間を1年と限定して法的安定性を確保したものと解されることからすると、監査請求期間も個々の財務会計行為ごとに判断すべきである。ただし、各別の財務会計上の行為が観念できる場合であっても、それぞれが相互に関連していて、全体としてみなければその違法性、不当性を判断することができないような特段の事情がある場合には、これを一体として捉え、最終的な財務会計上の行為が行われた日をもって当該行為の終わった日と解すべきである。
○ 上記に説示したところからして、本件各契約の締結については、契約締結行為の時点から監査請求期間を起算すべきである。甲契約は平成11年4月1日に締結されているところ、甲事件原告らは平成12年5月29日に甲契約に関する監査請求を行っており、また、乙契約は平成12年4月1日に締結されているところ、乙事件原告らは平成13年7月27日に乙契約に関する監査請求を行っており、本件各契約の締結については、いずれも監査請求期間を徒過していることは明らかである。
○ 本件各支出命令及び本件各支出は、本件各契約に基づき行われたものではあるが、それらは各月の管理委託業務の委託料の支払のためにされたものであり、各支出命令及び各支出自体に相互に関連性はなく、これを一体として捉えるべき特段の事情は認められない。そうすると、本件においては、原則どおり、各月ごとの支出命令及び支出行為の日から監査請求期間を起算すべきであり、平成11年5月29日以前に行われた甲契約に関する各支出命令及び各支出並びに平成12年7月27日以前に行われた乙事件に関する各支出命令及び各支出については、監査請求期間を徒過したものであるというべきである。
公共事業財源を資金運用部等から借り入れるにあたり虚偽の申請があったため利子を付して繰上償還を求められたことについて、首長に損害賠償請求しないのは違法に財産管理を怠る事実であるとして行った住民監査請求は、繰上償還要求等がなされた日から起算しての監査請求期間の制限が適用されるとした事例 甲府地判平16.4.13判例地方自治263.65
(農道建設資金を資金運用部等から当該年度及び明許繰越が可能な翌年度に支出しなかった金額を隠し口座に預金していたため、利子を付して分割繰上償還をすることを要求されるとともに、交付税算定において錯誤措置を受けたため受けた自治体の損害について首長に損害賠償請求を怠っているとする4号訴訟)
○ 原告らは・・・、本件各借入行為が違法な財務会計上の行為であるとして、これに基づいて発生する損害賠償請求権の不行使をもって、財産の管理を怠る事実としているところ、一般に、改正前(地方自治)法242条1項所定の怠る事実に係る監査請求については同条2項の適用がない(最高裁判所昭和53年6月23日第3小法廷判決・最高裁判所裁判集民事124号145頁)が、普通地方公共団体において違法に財産の管理を怠る事実があるとしてされた改正前法242条1項の住民監査請求が、特定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法であるか又はこれが違法であって無効であるからこそ発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象とするものである場合には、当該行為が違法とされて初めて当該請求権が発生するのであるから、監査委員は、当該行為が違法であるか否かを判断しなければ当該怠る事実の監査を遂げることができないという関係にあり、これを客観的、実質的にみれば、当該行為を対象とする監査を求める趣旨を含むものとみざるを得ず、当該行為のあった日又は終わった日を基準として改正前法242条2項を適用すべきである(最高裁判所昭和62年2月20日第2小法廷判決・民集41巻1号122頁参照)。
○ 本件各借入行為及び本件隠し口座への預金が違法であることに基づいて発生する損害賠償請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実とするものであるところ、これらが違法であるか否かは、もっぱら、これらが財務会計法規に違反するか否かにかかっているのであるから、改正前法242条2項が適用される場合に当たり、本件各借入行為ないし本件隠し口座への預金のあった日を起算日として改正前法242条2項の規定を適用するのが本則である。それゆえ、平成12年4月28日付けで行われた本件監査請求は、監査請求期間を徒過して行われたものであるように見える。
○ しかし、一方で、財務会計上の行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実とする住民監査請求において、その請求権がその財務会計上の行為のされた時点においてはいまだ発生しておらず、又はこれを行使することができない場合には、その実体法上の請求権が発生し、これを行使することができることになった日を基準として、改正前法242条2項の規定を適用すべきものと解するのが相当である(最高裁判所平成9年1月28日第3小法廷判決・民集51巻1号287頁参照)。
○ 原告らは・・・、本件各借入行為及び本件隠し口座への預金が違法な財務会計上の行為であるとして、これに基づいて発生する損害賠償請求権の不行使をもって、財産の管理を怠る事実としているところ、繰上償還をさせるか否かを決定するのは各貸主の側であるとされているから、本件各借入行為が行われた時点では各貸主に対する虚偽内容の申請が行われたに過ぎず、本件各借入行為が行われたことによって、当然に繰上償還措置を取られる関係にはない。また、地方交付税の錯誤措置についても、「自治大臣は・・・・・・することができる」と規定されているのであり(平成11年法律第160号による改正前の地方交付税法19条1項)、本件隠し口座への預金が行われたからといって、当然に錯誤措置を取られる関係にはない。したがって、本件各借入行為、本件隠し口座への預金が行われた時点において、原告らの主張する損害の発生は認められない。その後、平成11年5月25日付けで、大蔵省資金運用部地方資金を所管する関東財務局長から、同年6月8日付けで、公営企業金融公庫から、それぞれ一括繰上償還の要求がされ、さらに、平成12年7月に地方交付税の錯誤措置を受けたことによって、原告らの主張する損害賠償請求権が発生するに至ったものと認められる。
○ したがって・・・原告らの主張する損害賠償請求権は、早くても、平成11年5月25日までは発生していないのであるから、改正前法242条2項の定める監査請求期間の起算日は、この時点より以前にさかのぼることはない。本件監査請求が行われたのは、平成12年4月28日であり、上記起算日から1年以内の日であるから・・・原告らの請求は適法な監査請求を前置している。
契約締結およびその履行としての公金支出は一連のものであり、違法性承継理論により監査請求期間は現実の支出の日から起算されるべきとの原告の主張を排斥し、先行する契約締結(支出負担行為)や支出命令に違法ありとしても、支出負担行為、支出命令、現実の支出は独立した財務会計行為であり、監査請求期間の起算日はそれぞれの財務会計行為のなされた各別の日となるとした事例 神戸地判平16.11.9判例地方自治270.19
(公共施設の設計業務委託契約を締結して代金を支出した後、財政難のため建設事業を中止したところ、本件代金の支出は違法であるとする住民監査請求が、一部を除いて各財務会計行為がなされた日から1年以上経過してからなされた)
※最判平14.7.16民集56.6.1339判示事項を前提とする
○ 本件においては・・・、本件各施設の設計業務委託に係るすべての財務会計上の行為に関する監査請求が、平成15年4月15日になされているところ、・・・図書館設計業務委託代金残額の支出を除く本件各行為は、平成15年4月15日の1年以上前になされている。
○ この点、原告は、本件各行為は一連の行為として扱うべきであること、及び先行行為の違法は後行行為に引き継がれるといういわゆる違法性の承継の理論により、監査請求期間は、最終の財務会計上の行為である狭義の支出の終了時から起算すべきである旨主張する。
○ しかし、支出負担行為及び支出命令は当該地方公共団体の長の権限に属するのに対し、狭義の支出は出納長又は収入役の権限に属し、各行為の権限者が異なること、いずれの行為についても、委任等により他の職員に権限が委譲される場合には、それぞれの行為ごとに各別に委譲されることとなること、これらの行為に適用される実体上、手続上の財務会計法規の内容も同一ではないことなどの諸点にかんがみれば、上記アのとおり、支出負担行為、支出命令及び狭義の支出は、互いに独立した財務会計行為であり、監査請求期間はそれぞれの行為があった日から起算されるものと考えるべきである。 したがって、この点に関する原告の主張は採用できない。
○ 支出負担行為、支出命令及び狭義の支出は、互いに独立した財務会計上の行為であることは、上記で判断したとおりであるところ、仮に、本件において、先行行為たる設計業務委託契約の締結行為ないしはその決裁行為、及び支出命令の実行ないしはその決裁行為が違法であり、その違法性が後行の狭義の支出に引き継がれるとしても、それぞれの行為が、互いに独立した財務会計上の行為であることに変わりはなく、それぞれの行為が、個別に監査請求の対象となり、監査請求期間もそれぞれの行為があった日から起算すべきものであることに変わりはない。したがって、この点に関する原告の主張も採用できない。
町長や担当職員が関与する官製談合(町長による本命割付での談合)において、職員に対する賠償請求を怠る事実を対象とする住民監査請求につき、監査請求期間の制限は適用されないとした事例 函館地判平17.6.16
(町長があらかじめ落札業者を指定する、いわゆる本命割付を行い、助役や担当課長もこれに関与した上で談合入札が行われた。被告は、町長(死亡により訴え取下げ)、助役や担当課長は財務会計行為の権限者もしくは専決権・代決権を有し本件財務会計行為の補助者であり、これらの者に対する損害賠償請求を怠る事実は不真正怠る事実として監査請求期間制限が適用されると主張。一方原告は、町長らによる「本命割付」は、本命業者に対して予定価格を漏示しかつ指名競争入札を実施するに際し本命業者及び他の適当な業者を指名するというものであり、いずれも財務会計行為ではなく、ただ、特定の業者が本命業者となることができる条件を整えることによって業者間の談合という犯罪を助長するという「不法行為法上違法の評価を受ける」行為にすぎないと主張)
○ (地方自治)法242条2項本文は、監査請求の対象事項のうち財務会計上の行為については、当該行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは監査請求をすることができないものと規定しているが、上記の対象事項のうち怠る事実については、このような期間制限は規定されておらず、怠る事実が存在する限りはこれを制限しないこととするものと解される。もっとも、特定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法であるか又はこれが違法であって無効であるからこそ発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象として監査請求がされた場合には、当該行為が違法とされて初めて当該請求権が発生したと認められるのであるから、これについて上記の期間制限が及ばないとすれば、上記規定の趣旨を没却することとなる。したがって、このような場合には、当該行為のあった日又は終わった日を基準として上記規定を適用すべきものである。しかし、怠る事実については監査請求期間の制限がないのが原則であることにかんがみれば、監査委員が怠る事実の監査をするに当たり、当該行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にない場合には、当該怠る事実を対象としてされた監査請求に上記の期間制限が及ばないものと解するのが相当である(最高裁平成10年(行ヒ)第51号同14年7月2日第三小法廷判決・民集56巻6号1049頁参照)。
○ 本件監査請求の対象事項は、町が本件債務者らに対して有する損害賠償請求権の行使を怠る事実であるが、当該損害賠償請求権は、町が発注した本件各工事等について、町長による本命割付及び指名業者間の談合により、公正な競争により形成されたであろう契約代金額との差額相当の損害を町に与えたという不法行為により発生したというものである。
○ そうすると、本件監査請求について監査を遂げるためには、監査委員は、町が本件各入札の落札業者との間で各請負契約等を締結したことやその代金額が不当に高いものであったか否かを検討せざるを得ないが、町の上記各契約締結やその代金額の決定が財務会計法規に違反する違法なものであったとされて初めて町の本件債務者らに対する損害賠償請求権が発生するものではなく、町長による本命割付、指名業者間の談合行為、これに基づく落札業者の入札及び町との契約締結が不法行為法上違法の評価を受けるものであること、これにより町に損害が発生したことなどを確定しさえすれば足りるのであるから、本件監査請求について監査委員が怠る事実の監査をするに当たり、当該行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはないということができる。
○ したがって、本件監査請求については、法242条本文の規定による監査請求期間の制限が及ばないものと解するのが相当である。
補助金の支出を違法とする住民監査請求において、最初から当該事業が年度内に終わる見込みがなかったことが明らかなのにかかわらず補助交付決定(補助金交付)後の事情により年度内完了が不能な補助事業につき返還請求を怠ると構成した住民監査請求については、監査請求期間の制限が適用されるとした事例 福岡高判平18.10.31判例タイムズ1254.126
(町が公共事業につき地権者の同意を得るため交付した植栽補助金に対する住民監査請求について、補助金の交付(決定)自体ではなく、補助金交付(決定)後の事由により年度内に完成見込みがないにも関わらず返還請求を怠ると構成して行った。なお原告は、本補助金が実際は地権者の同意を得るための解決金的性格のものであることを知っていた)
○ 監査委員において、町が同条に基づいてAに対し本件補助金(の全部又は一部)の返還を命じないことについて監査を遂げるためには、本件補助金交付決定の存否及び内容等について検討しなければならないのは当然としても、同決定自体が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはないので、その点において最高裁第三小法廷平成14年7月2日判決(民集56巻6号1049頁)の場合と類似するということができなくもない。
○ しかしながら、本件補助金交付決定に至る経緯は・・・本件道路の開設・維持について、その原状回復を主張するAとの交渉において、町が同人に対し150万円を支払うとの合意が成立したこと、町長は同金額を損害賠償金として支払うとの内容の議案をX年第1回町議会定例会に提案したが、一部議員の強硬な反対を受けて、撤回を余儀なくされたこと、しかし、町長が同議会に提案した補正予算案の中にはAに対する150万円の支払いが計上されており、同補正予算案は可決されたこと、その直後に、Aから本件申請がなされたのを受けて本件補助金交付決定がなされ、150万円が同人に交付されたこと、以上の事実が認められる。
○ そうであれば、本件補助金は予めAとの間で合意された150万円の支払いを「補助金」の名目で支出したにすぎないものであり、その本質は、同人に対する損害賠償金ないしは本件道路部分を原状に復しないこととするについて同人に異議を言わせないための解決金であると見るべきである。そのことは、本件補助金交付決定がなされたのがX年3月29日、これについての支出命令は同月31日、150万円が同人に交付されたのは同年5月2日であって、そもそも平成X-1年度内に本件申請にかかる事業計画に従ったすももの植栽事業を完成させることなどできる筈がなかったことからも裏付けられる。
○ そして、以上の事情は、一審原告らにおいても十分認識していることである。すなわち、一審原告らは、そのような認識を前提にして上記の主張をし、当審においても、本件補助金は本件道路の存続についてAの同意を得るための便法として支出したものにほかならないから、本件補助金の一部ではなくその全額を返還させるべきである旨主張しているところである。
○ そうすると、上記の主張は、一審原告らが、第1回及び第2回の各監査請求が却下されたこと、就中、第2回監査請求が請求期間徒過を理由に却下されたことを踏まえて、請求期間の制限を回避するために、怠る事実の違法確認という構成をとるべく、本件補助金交付決定の本来の意図からは外れることを十分認識しつつ、それが「補助金」の名目で交付されていることを捉えて、本件規則11条を援用することを考え出したものと見ることができ、このことは、第3回監査請求の請求書の末尾に、「本件は、町長の本件補助金支出について、支出決定の取消を怠ること、及び補助金返還請求権の行使を怠ることが違法であることを確認する請求である。このような「怠る事実の違法確認」に関しては、支出後1年以内という監査請求の期間制限はない」旨の「補足」がわざわざ付記されていること、その他弁論の全趣旨からして明白である。
○ そうであれば、Aの植栽事業がX-1年度内に完成する見込みがないことは、本件補助金交付決定当時既に明白なことであったにもかかわらず、敢えて同決定の違法・無効を前提とせず、本件規則11条に基づき同決定の取消(変更)や本件補助金(の全部又は一部)の返還を請求しないことを怠る事実として構成し、改めて監査請求をするという一審原告らの第3回監査請求は、専ら監査請求期間の制限を免れるための技巧的な構成であり、いかにも事の本質から外れたものというほかないから、このような監査請求を敢えて許さなければならない理由はない。また、実質的な見地からしても、Aの植栽事業がX-1年度内に完成する見込みがないことは明らかであるにもかかわらず、何故本件補助金交付決定がなされるに至ったのかについて踏み込まない以上、真の意味で本質に迫った監査はできないから、本件補助金交付決定自体が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはないといって済ませられるかどうかも、大いに疑問であるものといわなければならない。
○ 以上によれば、上記についても地方自治法242条2項の期間制限を免れることはできないものというべきである。
相当過去に締結された損失補償協定(契約)に基づく三セク破綻時の損失補償の実行(監査請求約2か月前の支出命令、支出による)に対する住民監査請求につき、もっぱら支出負担行為(損失補償契約)の違法を理由とする請求であり監査請求期間の起算日を損失補償契約日とすべきとの被告の主張および損害の発生を契約実行(公金支出)の停止条件とする損失補償契約を対象とする監査請求においては契約日ではなく損失補償の支出日を起算日とすべきとの原告の主張を排斥した事例 横浜地判平18.11.15判例タイムズ1239.177
(市が三セク会社への金融機関融資に係る金融機関との損失補償協定を締結の10年以上後に三セク破産により協定に基づく和解契約で市が金融機関に公金を支出したが、その支出命令・支出の2か月後に住民監査請求が提起された)
○ 本件損失補償金については、本件協定の締結(支出負担行為)が平成6年5月10日、本件和解契約の締結が平成16年12月27日、支出命令が平成17年1月7日、支出(狭義の支出)が同月14日に行われている。そして、前記のとおり、本件監査請求は同年3月7日にされている。
○ 支出負担行為、支出命令及び支出は、特定の支出するために行われる一連の行為ではあるが、互いに独立した財務会計上の行為であって、地方自治法242条2項本文所定の監査請求期間は、それぞれの行為のあった日から各別に計算すべきものである(最高裁判所平成14年7月16日第三小法廷判決・民集56巻6号1339頁参照)。したがって、上記によれば、本件における支出命令及び支出についての監査請求は、それぞれの行為がされた日から地方自治法242条2項本文所定の期間内にされたものといえる。
○ 被告は、上記監査請求は、専ら支出負担行為(本件協定の締結)の違法を理由とするものであり、このように契約の締結が違法、不当であることを専らの理由としてその履行行為について監査請求をする場合には、その監査請求期間は支出負担行為たる契約がされた日を起算点とすべきである旨主張する。しかしながら、上記のとおり、地方自治法では特定の支出を行うについて、それが適切に行われるように支出負担行為、支出命令及び支出という一連の段階的な手続を要求しており、それぞれが独立した行為と解される以上は、それぞれの行為についての監査請求期間はそれぞれの行為のあった日又は終わった日を基準として算定すべきものと解するのがもっとも自然な解釈であり、被告がいうように、当該監査請求においてどのような行為が違法、不当な事由として主張されているかによって監査請求期間の起算点を異にすると解すべき根拠はないものというべきである。
○ 被告は、上記のような場合には、監査請求期間の起算点を支出負担行為の時点としないと、支出負担行為の監査請求期間の起算点を実質的に支出の日とすることになり、期間制限を設けた法の趣旨に反することになると主張する。しかし、上記のとおり、支出負担行為、支出命令及び支出はそれぞれ独立した財務会計上の行為と解されるから、支出命令及び支出についての監査請求は直接的にはこれら各行為の違法、不当を問題としているのであって、これらの各行為を違法、不当ならしめる事由として支出負担行為の違法、不当が主張されているとしても、この点に変わりはない。ただ、支出命令及び支出が違法、不当であるかどうかということと、それに先行する支出負担行為の違法性とは無関係ではないし、支出負担行為が違法である場合に後行の支出命令及び支出がいわばその違法性を承継して違法になるという場合もあり得ることから、そのような場合には上記の審査において支出負担行為について違法性が審査されるにすぎない。被告の主張は、上記のように先行する支出負担行為の違法が後行の支出命令及び支出の違法、不当に一定の影響を与えることを前提として、その一方で、そのような主張が可能となるのは支出負担行為についての監査請求期間内に支出命令及び支出についての監査請求がされた場合に限定されるというに等しいものである。しかしながら、再三述べるように、支出負担行為、支出命令及び支出をそれぞれ独立した財務会計上の行為とし、支出負担行為の違法は支出命令及び支出を違法、不当ならしめる事情として主張されているものと理解する以上は、その監査請求期間もそれぞれの行為ごとに起算されると解するのが筋であって、被告が指摘するような問題点は、先行する支出負担行為の違法が後行の支出命令及び支出にどのような場合に、どのような影響を与えるかという問題として検討されるべきことと思われる。支出負担行為についての監査請求期間は経過しているにもかかわらず、その違法性について蒸し返し的に争われる余地があるとしても、それを理由として支出命令及び支出の監査請求期間の起算点を支出負担行為時と解すべき必然性はないし、そのように解しなければ期間制限を設けた法の趣旨に反するとまでは解し得ない。
【注】 支出負担行為の違法性の支出行為への継承については、最判25.3.21民集67.3.375参照
○ 以上のとおり、支出命令及び支出に係る本件監査請求は、監査請求期間内にされたものとして適法というべきである。
○ 支出負担行為(本件協定の締結)についての監査請求について、本件協定の締結は平成6年5月10日にされているから、この締結日を起算点とすれば、本件監査請求は監査請求期間を経過した後にされたものというべきであるが、原告は、支出がされた日(平成17年1月14日)を起算点とすべき旨主張する。
○ そこで検討すると、住民監査請求は、財務会計上の行為又は怠る事実を対象として行われるものであるところ、当該行為についての監査請求は、当該行為のあった日又は終わったから1年を経過したときは、これをすることができないものとされている(地方自治法242条2項本文)。そして、ここにいう当該行為のあった日とは一時的な行為のあった日を、当該行為の終わった日とは継続的な行為についてその行為が終わった日を、それぞれ意味するものと解される。本件監査請求においては、本件協定の締結がその対象となる行為とされており、同契約の締結行為は一時的行為というべきであるから、これを対象とする監査請求は契約締結の日を基準として同項本文の規定を適用すべきである(最高裁判所平成14年10月15日第三小法廷判決・判例時報1807号79頁参照)。
○ 原告の上記主張は、財務会計上の行為がされても損害が発生していなければ、監査請求において損害を補てんするため必要な措置を講じることを請求したり、その後の住民訴訟において当該職員に対して損害賠償の請求(又は賠償命令)をすることを求めることができないという点を根拠としている。しかし、監査請求においては、その対象である財務会計上の行為又は怠る事実を特定して、必要な措置を講ずべきことを請求すれば足り、措置の内容等を具体的に明示することは必須ではなく、仮に、執るべき措置内容等が具体的に明示されている場合でも、監査委員は監査請求に理由があると認めるときは、明示された措置内容に拘束されずに必要な措置を講ずることができる(最高裁判所平成10年7月3日第二小法廷判決・裁判集民事189号1頁参照)。すなわち、監査請求は、財務会計上の行為又は怠る事実を対象としてされるものであって、監査委員に求める措置が、当該行為の防止、是正、怠る事実を改めること及び損害のてん補のいずれであるかによって、監査請求の対象が異なるというわけではない。また、監査請求を前置してされる住民訴訟についてみても、その対象とする財務会計上の行為又は怠る事実について監査請求を経ていると認められる限り、監査請求において求めていた具体的措置とは異なる内容の請求をすることも許されると解されるから、この点からも監査請求の期間を住民訴訟で求める請求の内容ごとに考える必要があるとは解されない。
○ 原告は、支出負担行為がされた時期を基準にすると、当該職員に損害賠償請求(賠償命令)することを求めることができず、そのような請求をする機会が保障される必要がある旨を主張する。しかしながら、住民訴訟制度の目的は、住民が納税者としての立場から、地方公共団体が違法な財務会計上の行為によって損害を被ることを防止し、あるいは被った損害を回復する手段を設け、これによって地方公共団体が適正な財務会計処理を行うことを保障する点にある(監査請求制度も、その対象が不当な財務会計上の行為を含む点を除けば、同趣旨の制度であるということができる。)。このような制度趣旨からすると、監査請求及び住民訴訟において、契約の締結行為の当否、適否を争うことができるとされているのも、その後に予定された契約の履行により地方公共団体が損害を被ることを防止したり、あるいは被った損害を回復するためであって、契約の締結時において、履行行為の差止めや法律関係の不存在確認(旧法下)を求めることができれば、契約が締結された結果として発生した損害について当該職員に対する損害賠償請求等を求める機会が保障されることが必須の要請とまでは解されない。もとより、監査請求の可否とは関わりなく、当該地方公共団体は当該契約に起因して損害が発生すれば、当該職員に対して損害賠償等の請求をなし得るわけであるし、その請求が行われないときには当該請求を怠る事実についての監査請求や住民訴訟の提起も可能なのであるから、上記のように解することによって特段の不都合があるとも認められない。
○ また、原告は、平成9年最判(最高裁判所平成9年1月28日第三小法廷判決・民集51巻1号287頁)を上記主張の根拠として指摘している。しかしながら、上記最高裁判決は、財務会計上の行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実とする監査請求について、上記請求権が財務会計上の行為がされた時点においてはいまだ発生しておらず、又はこれを行使することができない場合には、実体法上の請求権が発生し、これを行使することができることになった日を基準として地方自治法242条2項の規定を適用すべき旨を判示したものである。すなわち、上記判決は怠る事実に係る監査請求について同条項の適用関係を明らかにしたものであり、本件のように、本件協定の締結という財務会計上の行為(当該行為)が監査請求の対象とされた場合について判断したものではない。原告は、同判決は、怠る事実に固有のものではないと主張するが、同判決は、上記のとおり、怠る事実に係る請求権が発生しておらず、又は行使することができない場合には、監査請求の対象となる怠る事実が存在しないため、その監査請求期間については上記判示のとおりに解すべきであると判示しているのであって、財務会計上の行為(当該行為)を対象とする監査請求の場合には、当該行為は既に存在しており、監査請求の対象とし得るのであるから、この二つの場合を同一に論じることはできない。そして、原告の主張によった場合、原告が主張するように、地方自治法242条2項にいう「当該行為のあった日」とは、当該行為によって直ちに損害が発生するという関係が存在しない場合は損害の発生時点をいうと解するか、一つの契約締結行為について、求める措置の内容に応じて、契約締結日から1年間と、当該職員に対する損害賠償請求権が発生した日から1年間という二つの監査請求期間があると解するほかはないように思われるが、このような解釈は同条項の「当該行為のあった日から1年」との文言と大きく乖離することになり、困難というべきである。なお、上記のことを本件についてみると、本件協定が締結された時点では、現実に市が本件各金融機関に損失補償することになるかどうか、また、いつの時点でいかなる金額を支出することになるのかは未確定であったが、住民としては、旧法下においても、その履行の差止めや契約の相手方に対する法律関係の不存在確認を求めて監査請求ないし住民訴訟をすることが可能であったものと考えられる。この点、差止めの訴えについては、その時点での訴外会社の経営状況等にもよるが、既に本件協定が締結されており、その補償限度額が9億円という高額であることからすれば一応適法な訴えと解されるし、法律関係不存在確認の訴えについては、これができないとする理由はないものと思われる(この点、原告は回復困難な損害が生ずるおそれがある場合にのみ同訴えが許されると主張するが、そのように解すべき根拠はない。)。
○ 以上のとおり、本件協定の締結を対象とした監査請求は、その締結日である平成6年5月10日から1年以内にすべきであって、本件監査請求は期間を徒過してされたものである。
【最高裁判例】
①財産の管理を怠る事実に係る実体法上の請求権が除斥期間の経過により消滅するなどして怠る事実が終わった場合には,当該怠る事実の終わった日から1年を経過したときはこれを対象とする住民監査請求をすることができない
②財産の管理を怠る事実(第1の怠る事実)に係る実体法上の請求権が除斥期間の経過により消滅するなどして怠る事実が終わった場合において,上記請求権の行使を怠り,同請求権を除斥期間の経過により消滅させるなどしたことが違法であるとし,第1の怠る事実が違法であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実(第2の怠る事実)とした上で,第2の怠る事実を対象とする住民監査請求がされたときは,当該監査請求は,第1の怠る事実の終わった日を基準として1年の監査請求期間の制限に服する 最判平19.4.24民集61.3.1153
(町道改良工事請負業者への瑕疵修補に代わる損害賠償請求権の行使を怠り,約款所定の除斥期間経過で,請求権を消滅させ,町に損害をこうむらせたとする,町長に対する4号訴訟。事実経過は上記リンク先を参照)
○ 地方自治法242条2項本文の規定(以下「本件規定」という。)は,同条1項の規定による住民監査請求のうち財務会計上の行為を対象とするものは,当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは,これをすることができない旨定めている。これは,財務会計上の行為は,たとえそれが財務会計法規に違反して違法であるか,又は財務会計法規に照らして不当なものであるとしても,いつまでも監査請求ないし住民訴訟の対象となり得るものとしておくことは,法的安定性を損ない好ましくないことから,監査請求期間を,非継続的な財務会計上の行為については当該行為のあった日から,継続的な財務会計上の行為については当該行為の終わった日から,それぞれ1年間に限ることとしたものである(最高裁平成10年(行ヒ)第51号同14年7月2日第三小法廷判決・民集56巻6号1049頁参照)。このような本件規定の趣旨からすれば,財産の管理を怠る事実に係る実体法上の請求権が除斥期間の経過により消滅するなどして怠る事実が終わった場合には,継続的な財務会計上の行為の終わった日から1年を経過したときはこれを対象とする監査請求をすることができないのと同様に,怠る事実の終わった日から1年を経過したときはこれを対象とする監査請求をすることができない【要旨①】ものと解するのが相当である。また,上記の場合において,上記請求権の行使を怠り,同請求権を除斥期間の経過により消滅させるなどしたことが違法であるとし,当該怠る事実(以下「第1の怠る事実」という。)が違法であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実(以下「第2の怠る事実」という。)とした上で,第2の怠る事実を対象とする監査請求がされたときは,当該監査請求については,第1の怠る事実の終わった日を基準として1年の監査請求期間の制限に服する【要旨②】ものと解するのが相当である。なぜなら,前記のとおり,第1の怠る事実を対象とする監査請求は,第1の怠る事実の終わった日から1年を経過したときはこれをすることができないにもかかわらず,監査請求の対象を第1の怠る事実が違法であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使という第2の怠る事実として構成することにより,監査請求期間の制限を受けずに実質的に第1の怠る事実を対象とする監査を求めることができるものとすれば,本件規定が監査請求期間を制限した前記趣旨が没却されるといわざるを得ないからである。
○ これを本件についてみると,原審の適法に確定した事実関係によれば,上告人らの監査請求は,A(注:町長)が,町のB(注:工請業者)に対する瑕疵の修補に代わる損害賠償請求権の行使を怠り,同請求権を除斥期間の経過により消滅させたことを違法であるとし,当該怠る事実が違法であることに基づいて発生する実体法上の請求権である町のAに対する損害賠償請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実としているものである。そして,上告人らの監査請求は,Bに対する上記損害賠償請求権が除斥期間の経過により消滅したとされる日から1年を経過した後にされたものであるというのである。そうすると,上告人らの監査請求は,Bに対する上記損害賠償請求権の行使を怠る事実の終わった日から1年を経過した後にされた不適法なものというべきであって,本件訴えは,適法な監査請求の前置を欠く不適法な訴えとして却下を免れない。
工事請負契約締結に係る官製談合に関与した町長と助役に対する損害賠償請求を怠る事実を対象とする住民監査請求において、財務会計職員である町長への請求には監査請求期間の制限が適用されるが、財務会計職員ではない助役には適用されないとした事例 大津地判平22.7.1判例タイムズ1342.142
○ 原告らは、Aに対する損害賠償請求権の根拠として、談合を知りながらこれを助長させたこと、あるいは、談合を知り得たのに、町長としての職務義務に違反して、これを防止する措置を採らなかったことを不法行為として主張するところ、本件監査請求は、上記主張に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実をも監査の対象として含むものということができる。
○ ところで、町長は・・・、本件各契約の締結につき、法令上本来的権限を有する財務会計職員であり、財務会計法規上の義務として、談合をして不当に高い金額で落札した業者との間で請負契約を締結することを回避すべき義務があるところ、原告らが主張するAの行為で違法とされているものは、結局、Aがした本件各契約の締結の違法を構成する関係にあり、当該財務会計上の行為である本件各契約の締結が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にあるといわざるを得ない。したがって、Aに対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする監査請求については、本件各契約の締結日を基準として本件規定が適用されることとなる。
○ Bは・・・、助役として、町長の補佐及び代理を務める一般的権限のほか、審査会の会長として、建設工事請負契約の指名競争入札に係る業者の格付け、資格要件及び指名選定に関する具体的な権限を有していたものの、後者の具体的な権限は、指名競争入札を行う前提条件を整えるものにすぎず、Bが、本件各契約の締結につき、法令上本来的権限を有する町長から委任を受け、又は専決する権限を付与されていたなどの事情は認められない。したがって、Bは、Aとは異なり、本件各契約の締結につき、権限を有する財務会計職員ではない。
○ そして、本件監査請求は、Bが本件談合という不法行為に関与したとし、町がBに対する不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠っているという事実を対象とするものであるところ、これについて監査を遂げるためには、監査委員は、Bについて上記行為が認められ、それが不法行為法上違法の評価を受けるものであるかどうか、これにより町に損害が発生したといえるかどうかなどを確定しさえすれば足りる。Bに対する上記損害賠償請求権は、本件各契約の締結が財務会計法規に違反する違法なものであったとされて初めて発生するという関係にはなく、その財務会計行為の違法を判断しなければならない関係にはないから、Bに対する請求について、本件規定を適用すべきものとはいえない。このことは、本件業者らに対する請求についても同様である。
移転補償として複数回にわけて支払われた金員交付に対する住民監査請求については、各支出別に監査請求期間が進行するとした事例 福岡地判平23.4.19判例地方自治357.33
(道路拡幅工事に伴い集会所を収去することとされたことに伴い、集会所の一部を事務所として使用していた団体に対して町が団体と締結した一の移転補償合意に基づき(同一会計年度内の)複数回に分けて補償金を支払った(支出命令日は異なる3日、支出命令の名目は4つ、支出命令件数は5件で各命令は異なる)。支払いの総額は、移転補償合意での合意額と同一である。原告は、○円を交付するという町と団体の協定に基づいて交付されたものである以上、この金員交付が何回かに分けてなされたとしても、これを相互に無関係な別個独立のものと解するのは妥当でなく、本件公金支出は一体のものと考えられるのであって、監査請求期間の起算日について、各内金の交付日ごとに個別に進行すると解するのは相当でなく、最終の交付日から全体についての監査請求期間が進行するものと考えるべき、と主張。なお判決理由において、本件は移転補償費につき、町長として支出負担行為及び支出命令を行った被告に対し損害賠償請求するよう求める住民訴訟であって、原告らは、町長の支出命令の違法を問題とすることを明らかにしている、とする)
○ 本件では、A団体に対する移転補償費につき、町長として支出負担行為及び支出命令を行ったBに対し損害賠償請求するよう求める住民訴訟であって、原告らは、B町長の支出命令の違法を問題とすることを明らかにしているから、その監査請求期間も、B町長による個々の支出命令があった日から各別に計算すべきであることとなる。そして、前記前提事実によれば、B町長は、X1日、X2日及びX3日の3回に分けて、本件支出命令を行ったことが認められる。そうすると、上記支出命令ごとに、各別に監査請求期間を計算すべきである。
○ なお、この点について原告らは、B町長によるA団体に対する移転補償は、本件移転補償合意に基づいて交付されたものである以上、この金員交付が何回かに分けてなされたとしても、これを相互に無関係な別個独立のものと解するのは妥当でなく、起算点も一体として考えるべきである旨主張する。
○ 確かに、本件の場合、本件移転補償合意の違法を根拠として本件訴訟を提起するのであれば、原告らの主張するように、本件公金支出全体を一体のものと見る余地があるように思われる。しかし、前記のとおり、原告らは、B町長の本件支出命令の違法を問題として本件訴訟を提起しているのであるから、各支出について各別の支出命令がなされている以上、個別の支出命令ごとに監査請求期間を計算するのが相当である。この点に関する原告らの主張は採用できない。
学校法人に対する私立学校経常費補助金の年度内複数回の支出はそれぞれ独立した財務会計行為であり、各別に監査請求期間が進行するとした事例 横浜地判平23.5.25判例地方自治359.67
(市は学校法人に対してX年度市立学校経常費補助金を3回支出したが、それぞれについて執行伺票および支出命令票が起票されていた)
○ 第1回補助金交付ないし第3回補助金交付が、それぞれの支出ごとに執行伺票及び支出命令票が作成された上で行われる、互いに独立した会計行為であることが認められる。そうすると、上記1年の監査請求期間の起算日は、それぞれ、上記各補助金の交付日と解されるべきであるところ、第1回補助金交付がX年6月30日であったことは・・・のとおりであるのに対し、第1回監査請求がX+1年9月8日付けでされたことは・・・のとおりである。したがって、第1回補助金交付に係る第1回監査請求は、上記期間の経過後にされた不適法なものであると解される。よって、本件訴えのうち、第1回補助金交付に係る請求は、適法な住民監査請求を前置しないものであって、不適法といわねばならない。
○ 本件請求…に係る訴えは、市が○不動産鑑定所に対して有する本件各業務委託契約の債務不履行に基づく損害賠償請求権の行使を違法に怠る事実があるとして、被告にその行使を求めるものである。
○ 怠る事実を対象とする監査請求であっても、特定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法であるか又はこれが違法であって無効であるからこそ発生する実体法上の請求権の行使を怠る事実を対象とするものである場合には、当該財務会計上の行為のあった日又は終わった日を基準として地方自治法242条2項本文を適用すべきものである(最高裁昭和62年2月20日第2小法廷判決・民集41巻1号122頁参照)。しかし、怠る事実があると原告が主張する損害賠償請求権は、○不動産鑑定所による本件各業務委託契約の債務不履行(…の適正な賃料を調査、判断して報告すべき義務の違反)によって発生したというのであって、監査委員が、これについて監査を遂げるためには、○不動産鑑定所が本件各業務委託契約により負担する義務の内容及びその違反の有無、これにより市に損害が発生したことなどを確定しさえすれば足り、本件各業務委託契約の締結が違法か否かはもちろん、本件賃貸借契約の締結が違法か否かも判断をする必要はないから、本件賃貸借契約の締結があった日(X年3月31日)を基準として同項本文を適用する余地はないというべきである。
○ そうすると、本件請求…のうち本件業務委託契約…の債務不履行に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実について、本件監査請求は、同項本文の監査請求期間を徒過してされた不適法なものであるとする被告の主張は採用することができない。
工事請負契約の違法に関する4号訴訟において、請負業者に対する損害賠償請求を怠る事実を申請怠る事実、自治体関係職員に対する損害賠償請求を怠る事実を不真正怠る事実とした事例 大阪地判平29.5.19判例地方自治428.42
(国庫補助事業について入札差金が生じ補助事業期限である年度末も迫ったので、庁舎の太陽光発電設備設置を実施することとし、緊急随意契約により工事請負契約を締結したことについて、市の関係職員および請負業者を対象としてなされた4号訴訟)
○補助参加人(請負業者)を相手方とする請求について
…のとおり,本件監査請求は,本件各財務会計職員及び補助参加人に対する共同不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象に含んでいると認められるところ,本件監査請求書の記載内容…等に照らせば,原告が主張するところの被告が補助参加人に対して有する損害賠償請求権は,補助参加人が本件工事を受注する合理的な理由もないのに不当に高額で本件工事の請負契約を締結して○市から請負代金の支払を受けて○市に損害を被らせたことにより発生したものであると認められる。そうすると,上記の損害賠償請求権の行使を怠る事実について監査を遂げるためには,監査委員は,補助参加人について上記行為が認められ,それが不法行為法上違法の評価を受けるものであるかどうか,これにより○市に損害が発生したといえるかどうかなどを確定しさえすれば足りるのであって,本件請負契約の締結やこれに基づく代金の支払が財務会計法規に違反する違法なものであったとされて初めて○市の補助参加人に対する損害賠償請求権が発生するものではない。したがって,上記怠る事実を対象としてされた本件監査請求は,本件各財務会計行為を対象とする監査を求める趣旨を含むものとみざるを得ないものではない。そうすると,上記監査請求について法242条2項の規定の適用がないものと認めても,同項が期間制限を設けた趣旨が没却されるものではないから,上記監査請求に同項の規定は適用されないものと解するのが相当である。
○本件各財務会計職員を相手方とする請求について…のとおり,本件監査請求は,本件各財務会計職員及び補助参加人に対する共同不法行為に基づく損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象に含むものと認められるところ,本件監査請求書の記載内容…等に照らせば,原告が主張するところの被告が本件各財務会計職員に対して有する共同不法行為に基づく損害賠償請求権は,本件各財務会計職員が本件各財務会計行為又はこれらに関与する行為が違法であることにより発生するものであると認められる。もっとも,本件監査請求書…の内容等に照らせば,原告らは,本件各財務会計職員の共同不法行為を基礎づける違法として本件各財務会計行為が財務会計法規に違反して違法である旨を主張し,財務会計法規違反とは別の違法事由を主張しておらず,本件各財務会計行為に関与した行為に本件各財務会計行為の違法と別個独立の違法事由がある旨の主張もしていないと認められる(本件監査請求書には,本件各財務会計職員が補助参加人と明示的又は黙示的に意を通じて本件請負契約を締結した旨の記載があるが,そのような記載をもって,本件各財務会計職員が本件各財務会計行為とは別の不法行為をした旨を主張しているとは認められない。)。また,本件各財務会計職員のうち,A市長は本件請負契約の締結権限を有する者であり,B副市長,C総務部長及びD環境部長は職制上A市長を補助する職員であること(地方自治法158条1項,161条1項,167条1項,172条1項,○市事務処理規程4条及び5条…),E参事は支出命令の専決権限を有する者であり(前記前提となる事実(1)エ),F主幹は職制上E参事を補助する職員であること…,G会計管理者は支出の権限を有する者であり(法168条1項,170条1項及び2項),H会計室室長は職制上会計管理者を補助する職員であること(法171条5項…)が認められる。以上の事情を総合すると,上記の本件各財務会計職員に対する損害賠償請求権は,本件各財務会計行為の権限を有する者による財務会計上の行為及びこれを補助する職員による補助行為が財務会計法規に違反して違法であることを理由とするものであって,上記の補助行為の違法は財務会計上の行為の違法を構成する関係にあるというべきである。そうすると,本件監査請求のうち,上記の本件各財務会計職員に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分については,本件請負契約の締結,本件支出命令及び本件支出のあった日を基準として法242条2項本文を適用すべきである。そして,本件各財務会計行為は,公金の支出を構成する一連の行為ではあるものの,互いに独立した財務会計上の行為というべきものであり,法242条2項本文所定の監査請求期間は,それぞれの行為のあった日から各別に計算すべきものである(最高裁平成14年7月16日第三小法廷判決・民集56巻6号1339頁)。そうすると,本件請負契約が締結されたのは平成24年3月5日,本件支出命令は同年5月11日,本件支出は同月18日であり…,本件監査請求がされたのは平成25年5月15日であるから,本件監査請求のうち,本件支出及びその補助行為の違法を理由とする本件支出職員に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分は監査請求期間を徒過したものとはいえないが,本件請負契約の締結及びその補助行為の違法を理由とする損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分並びに本件支出命令及びその補助行為の違法を理由とする損害賠償請求権の行使を怠る事実を対象とする部分は,いずれも監査請求期間を徒過したものというべきである。
○この点,原告らは,本件各財務会計職員に対する損害賠償請求権が発生するのは現実に補助参加人に金員が支払われたときであるから,上記損害賠償請求権の行使を怠る事実の監査請求期間の起算日は現実の支出がされた平成24年5月18日であるとして,平成25年5月15日にされた本件監査請求は監査請求期間を徒過していないと主張する。しかし,○市は,本件請負契約の締結により請負代金相当額の支払義務を負担し,本件支出命令に基づく本件支出により上記の支払義務が現実に履行されたのであり,上記各財務会計上の行為の違法は,○市に請負代金相当額の支払義務の負担又は履行を防止しなかった点にあると解される。そうすると,上記各財務会計上の行為の違法はそれぞれが○市の請負代金相当 額の損害と相当因果関係を有するということができるから,本件請負契約の締結が違法であることによる損害賠償請求権及び本件支出命令が違法であることによる損害賠償請求権は上記各行為日において発生したといえる。したがって,本件各財務会計職員に対する損害賠償請求権が本件支出の時に発生するとする原告らの主張は採用することができない。
市が国庫補助金を原資として事業者に補助金を交付したが事業者の補助金申請に不正が判明し市が国から国庫補助金の返還命令を受けたところ市が事業者に命じた補助金返還がなされていない事案において、補助金の交付行為にかかる市長への損害賠償請求を怠る事実には不真正怠る事実に係る監査請求期間制限の判断枠組みを適用したが、事業者が補助事業で取得した財産を無償譲渡したことに対する損害賠償請求を怠る事実については申請怠る事実の判断枠組みを適用し、また不真正怠る事実部分については、平成9年1月28日最判の判断枠組みを適用して、監査請求期間の起算点を市が事業者から補助金返還を受けることなく国庫補助金を返還した日とした事例 広島地判令4.3.30判例時報2565.5
(市は国庫補助金を原資として事業者に補助金を交付したが、当該事業者は事業破綻した。また当該事業者が市補助金を不正受給していたことが判明し、事業者の代表取締役等に刑事処分がなされた。市は事業継続を検討したが中止のやむなきに至り、国は不適正な経理を理由に補助金適正化法17条2項により市に対する補助金交付決定の取消しおよび返還命令を行った。市は事業者に補助金の返還を命じたが返還されていない。本件は上記補助金が地方自治法232条の2に違反すること、事業者が補助事業で取得した油圧ショベルを無償譲渡したことについて適正な管理監督を行わず放置したことを理由とし、市が責任者の前市長に有する損害賠償債権の請求を怠るとしてなされた4号訴訟。本判決においては、下記判示内容の前提たる判断枠組みとして、最判昭62.2.20民集41.1.122、最判平14.7.2民集56.6.1049を引用する)
○ …のとおりの本件監査請求に係る住民監査請求書の内容に照らせば、原告らは、本件監査請求において、〈1〉前市長による本件各補助金の交付が地方自治法232条の2に反し違法であり、これにより市が損害を被ったとして、市が前市長に対して取得した損害賠償請求権を被告が行使しないという怠る事実を監査請求の対象に取り上げ、被告に対して必要な措置を講ずるよう請求するとともに、〈2〉G社が本件事業により取得した本件油圧ショベルに関し、前市長が管理監督義務を怠ったため、同社が本件油圧ショベルを無償譲渡することを放置し、このことにより市が損害を被ったにもかかわらず、市が前市長に対して取得した損害賠償請求権を被告が行使しないという怠る事実を監査請求の対象に取り上げ、被告に対して必要な措置を講ずるよう請求していたものと認められる。
○ 本件監査請求のうち上記〈1〉の部分についてみると、市監査委員は、同部分の監査を遂げるため、前市長による本件各補助金の交付が財務会計法規である地方自治法232条の2に反し違法であるか否かを判断しなければ、上記怠る事実の監査を遂げることができないという関係にあるものというべきである。したがって、本件監査請求のうち上記〈1〉の部分は、本件各補助金の交付を対象とする監査を求める趣旨を含むものと解すべきであるから、同法242条2項所定の期間制限の適用があるものと解するのが相当である。これに対し、原告らは、本件監査請求は本件各補助金の交付が何らかの財務会計法規に違反することを理由とするものではないから、同項所定の期間制限は適用されない旨を主張するが、上述した本件監査請求の内容に反し、採用できない。
○ 他方、本件監査請求のうち上記〈2〉の部分についてみると、市監査委員は、同部分の監査を遂げるため、前市長による上記管理監督義務違反の有無を判断すれば足り、特定の財務会計上の行為が財務会計法規に違反して違法か否かを判断しなければならない関係にはないというべきである。したがって、本件監査請求のうち上記〈2〉の部分については、地方自治法242条2項所定の期間制限の適用はないものと解するのが相当である。
○ これに対し、被告は、本件油圧ショベルに関する前市長の管理監督義務は、本件各補助金の交付を前提として発生するものであるから、本件各補助金の交付に関する注意義務に包含されるとして、上記管理監督義務違反が特定の財務会計上の行為に該当し、市監査委員において、これが財務会計法規に違反して違法か否かを判断しなければ、本件監査請求の上記部分の監査を遂げることができない旨を主張する。しかし、前市長による本件油圧ショベルの管理監督は、本件各補助金の交付に後続して行われるものの、これが損害賠償請求権の発生原因となる不法行為に該当するか否かは、本件各補助金の交付の財務会計法規違反とは別に判断されるべきものであることに照らせば、市監査委員において、本件各補助金の交付の財務会計法規違反の有無を判断しなければ上記管理監督義務違反の有無を判断できないという関係を見いだすことはできない。したがって、被告の上記主張は採用できない。
○ 期間制限の起算日について
特定の財務会計上の行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実(いわゆる不真正怠る事実)とする監査請求については、当該行為のあった日又は終わった日を基準として地方自治法242条2項の規定を適用すべきであるが(前記最高裁昭和62年2月20日第二小法廷判決参照)、実体法上の請求権が財務会計上の行為のされた時点においてはいまだ発生しておらず、又はこれを行使することができない場合には、実体法上の請求権が発生し、これを行使することができることになった日を基準として同項の規定を適用すべきものと解するのが相当である(最高裁平成9年1月28日第三小法廷判決・民集51巻1号287頁参照)。
○ 市は、同市の予算措置を講じた上で、市農林漁業振興補助金として本件各補助金を交付したものであることに照らせば、本件各補助金が違法に交付された場合、その交付の時点で、直ちに本件各補助金相当額の財産を失うこととなり、その交付がなかったとしたらあるべき同市の財産状態との差額に当たる本件各補助金相当額の損害を被ったものと認めるのが相当である。なお、このことは、本件各補助金が、補助金適正化法の各規定によって、補助事業以外の用途に流用されることが許されないなどの拘束を受ける国庫補助金(…交付金)を原資とするものであることによって左右されるものではない。
○ もっとも、市は、国から交付を受けた上記交付金を原資として、本件各補助金を交付したものであり、本件各補助金が違法に交付された場合に発生する損害は、実質的には上記交付金によってあらかじめ補填されていたものといえ、その交付時点において、市が前市長に対して本件各補助金相当額の損害賠償請求権を行使することができるとする場合、市は、本件各補助金相当額の財産を正当な理由なく保有することとなることに照らせば、市は、本件各補助金の交付時点では、本件各補助金と同額の上記交付金の交付を受けながら、他方で前市長に対して本件各補助金の交付により損害を被ったと主張して損害賠償請求をすることはできない立場にあったものというべきである。そうすると、仮に本件各補助金の交付が違法であり、その交付の時点で本件各補助金相当額の損害が発生していたとしても、市が、G社から本件各補助金の返還を受けることのないまま、上記損害をあらかじめ補填していた上記交付金を国に返還し、上記損害を補填する財産を欠くこととなった時点において、初めて上記損害に係る同市の前市長に対する損害賠償請求権を行使することができるものと解するのが相当であるから、上記返還の日を基準として、地方自治法242条2項の規定を適用すべきである。
○ したがって、本件監査請求のうち、本件各補助金の交付が違法であることに基づいて発生する前市長に対する損害賠償請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実とする部分については、市が、G社から本件各補助金の返還を受けることのないまま、国に対して上記交付金を返還したX年12月19日を基準として、地方自治法242条2項の規定が適用され、同日から監査請求期間が進行するというべきである。
○ そして、本件監査請求は、X+1年4月30日に行われたものであるから、上記の監査請求期間内に行われたものと認められる。

宮崎鵜戸神宮にて。東映のイントロのように太平洋の高波がダッパーンです。左の岩は、白頭鷲が威儀を正しているのか、どこかの怪鳥がケーーーッと雄叫びをあげているのか。