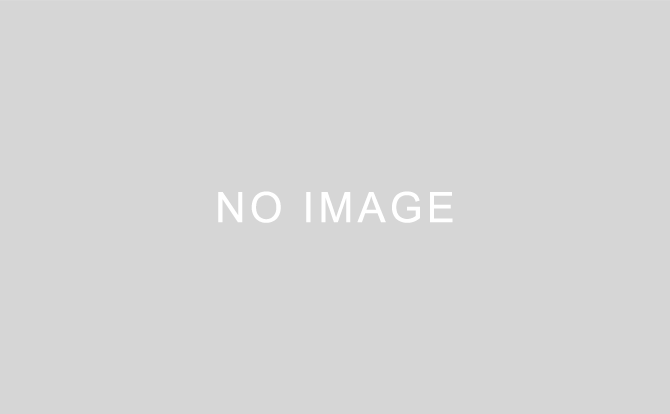本ページの一番下に、本ページのPDF版リンクを設けています。
最終改訂 2025.2.13(2.14誤字訂正) 改訂内容は改訂履歴のページ参照
住民監査請求は、原則として、請求の対象とする財務会計行為があった日または終わった日から1年を経過した後になされた場合は、他の要件を充足していたとしても不適法な請求となります。
なお、この期間後に請求することについて正当な理由がある場合は、適法な請求となり得ます。
ちなみに、監査請求期間(制限)の要件(≒出訴期間制限)は、住民監査請求の請求要件としては、請求人の住民要件、請求対象の財務会計行為性と並ぶものであり、前二者とは独立した要件となります。
また、監査請求期間の論点については、財務会計行為1年経過後の請求についての「正当な理由」も重要なものとなりますが、この点は別稿「5.2 財務会計行為1年経過後の請求についての正当な理由」で扱います。
1 総論
(1) 地方自治法の規定
地方自治法242条2項は「前項の規定による請求は、当該行為(地方自治法242条1項列挙の財務会計行為)のあつた日又は終わつた日から一年※を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない」としています。
つまり、住民監査請求には行政訴訟や行政不服審査と同様の「出訴期間制限」があり、たとえ他の請求要件(住民要件、監査対象の財務会計行為性要件)がすべて充足した請求であっても、所定の期間を経過した後になされた住民監査請求は、不適法な請求となります※※。
| ※ この1年の期間について、昭38年自治法改正詳説p.335では、行政不服審査法の審査請求期間(当時の14条3項、現在の18条2項)を参考にしたとします。 |
| ※※ このような請求期間制限を設ける趣旨は、「普通地方公共団体の執行機関・職員の財務会計上の行為は、たとえそれが違法・不当なものであったとしても、いつまでも監査請求ないし住民訴訟の対象となり得るとしておくことが法的安定性を損ない好ましくないとして、監査請求の期間を定めた」(最判昭63.4.22集民154.57)であるとされます。参照:松本逐条本条関係。なお昭38自治法改正詳説p.335が同趣旨の見解を示しており(「監査請求の対象となる行為の多くは私法上の行為であるけれども、地方公共団体の行為である以上、いつまでも争いうる状態にしておくことは法的安定性の見地から見て好ましいことではなく、なるべく早く確定させることが望ましいという配慮に基づくものである」)、本要件の趣旨としての早期の法的安定性確定要請は、自治省・総務省における伝統的・確定的な解釈であり、最高裁もその趣旨を参照したものと考えます。そして、この点に関する主要最高裁判例を見る限り、最高裁は、監査請求期間要件の判断において、この考え方をとても重要視していると筆者は推察します。 |
(2) 概説・・・監査請求期間の原則枠組み
住民監査請求の監査請求期間に関する枠組みは、次の通りとなっています。
【地方自治法242条2項に直接基づく原則】
① 住民監査請求は、対象となる財務会計行為があった日(当該財務会計行為またはその効力が相当期間継続性を有する場合※は、終わった日)から1年を経過した後になされた場合、その請求は不適法となる。
② 財務会計行為のあった(終わった)日から1年を経過した後に住民監査請求がなされたことについて、正当な理由があるときは、①の監査請求期間を経過した後の請求は適法である。つまり上記①は、完全な不変期間を定めたものではない。
| ※ 松本逐条242条関係参照 |
【最高裁判例による敷衍】
そして、この原則についての最高裁判例に基づけば、さらに次の原則(上記①②の詳細化・具体化)が敷衍されます。
③ 【原則①関連】 怠る事実を対象とする住民監査請求においては、監査請求期間の制限は適用されない(最判昭53.6.23集民124.145)。
これは、地方自治法242条2項の規定が怠る事実を対象としていないこと、怠る事実はその事実状態が継続する限り、違法不当な状態が継続しているというべきであること(継続的財務会計行為に似ている)、明確な事実としての行為が存在しないため監査請求期間の起点が観念しがたいことによる。
ただし、財務会計職員(首長含む)による財務会計行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使を財産の管理を怠る事実と構成し、これを請求対象とする場合は、①の原則が適用される(最判昭62.2.20民集41.1.122)。
④ 【原則②関連】 財務会計行為があった(終わった)日から1年を経過した後に住民監査請求がなされたことについて正当な理由がある場合には、監査請求期間の起点は、財務会計行為のあった(終わった)日ではなく、特段の事情のない限り、「住民が相当の注意力をもって調査すれば客観的にみて監査請求をするに足りる程度に対象行為の存在及び内容を知ることができたと解される時」に移動し、その起点から「相当の期間内」に監査請求した場合に限り、監査請求期間に関する要件を満たすことになる。つまり事実上、監査請求期間の起点と監査請求期間が変更されたことに等しいことになる。(最判平14.9.12民集56.7.1481。なお最判昭63.4.22集民154.57)※。
| ※ 一般には、④に示す条件が全体として成就されている場合に、監査請求期間後の請求について「正当な理由がある」ものとされています。 |
(3) 監査請求期間制限の効果
監査請求期間を経過した後(財務会計行為1年経過後の請求について正当な理由がない場合を含む)の住民監査請求は、不適法な請求となります。
そしてその派生的効果として、監査請求期間経過後になされた住民監査請求の請求人は、その請求の対象となる財務会計行為について、住民訴訟を提起する資格が生じない、ということとなります。
| 【参考】
住民監査請求がなされたが監査請求期間が経過した(つまり適法な監査請求をすることができなくなった)財務会計行為について、監査委員が、地方自治法199条に基づき独自の判断で監査を行うことには、何らの問題はありません(地方自治法199条監査については、242条2項のような期間制限規定はない)。しかしそのような監査が行われたからといって、上記の住民監査請求が適法になることがなければ、住民訴訟の提訴資格が変動することもありません(請求人は住民訴訟を提起する資格は生じない)。 |
2 財務会計行為(怠る事実ではない)を請求対象とする場合の監査請求期間の取扱い
(1) 監査請求期間の一般原則
ここでは、監査請求期間の一般原則として、次の点について説明します。
ア:監査請求期間の起算日の概念的定義
イ:監査請求期間起算日の客観性の原則
ウ:期間の計算方法
ア 監査請求期間起算日の概念的定義
この期間制限規定は、まさしく「期間」により請求の適法性が左右される一方で、「期間」そのもの(要は期間の実効長)は「1年」と決まっており、また期間の計算法で疑義が生じることはないので(地方自治法では特段の規定がないので、期間計算は下記ウの通り、民法の規定によることとなります。つまりきわめて一般的な計算方法が取られるだけのことであり、期間の計算自体は問題の生じようがない簡明なものです)、「期間の起算日はいつか」を確定することが、この要件の検討における最重要の論点となります。
そして地方自治法242条2項の法文による限り、監査請求期間の原則的な起算日、つまり地方自治法242条2項ただし書きの「正当な理由」が問題になる(通常の監査請求期間のルールが適用されない)ケース以外の場合の起算日は、「当該行為」すなわち監査対象とされる地方自治法242条1項所定の財務会計行為が「あった日」または「終わった日」です。
(法文上の原則です。上記1(2)④の通り、この期間を経過した後の請求について正当な理由がある場合は、別の考え方により監査請求期間要件の審査を行うこととなります。)
とすれば、地方自治法242条2項が「あった日『又は』終わった日」とする以上、「あった日」と「終わった日」の内容と違い、つまり「あった日」「終わった日」を適用するのは、それぞれどのような場合か※を明瞭とする必要があります。
| ※ 財務会計行為が「あった日」については、概念的にさほど問題となる要素はないので、その論点は実質的には、どのような場合において「終わった日」を監査請求期間の起算日とするか、ということとなります。 |
ところで地方財務実務提要では、「「当該行為があった日又は終わった日」とは、「当該行為があった日」が一時的行為のあった日を意味するのに対し、「終わった日」とはその文理上継続的行為についてその行為が終わった日(例えば、財産の貸付であれば、その貸付期間の満了の日又は貸付契約が解除された日)を意味します」と説明しており、松本逐条では、「財務会計行為が終わった日」を「当該行為又はその効力が相当の期間継続性を有するものについて、当該行為又はその効力が終了した日を指す」とし、例示として
・財産の貸付・・・貸付期間の満了した日又は貸付契約の解除された日
・債務保証契約・・・現実に債務の弁済が行われた日
をあげています(財務会計行為があった日については、独立した説明は設けていない)※※。
| ※※ なお昭38自治法改正詳説p.335でも同じ説明がされています。 |
また最高裁も、例示内容は別として、概念上は上記と同様の判断を示しています※※※。
| ※※※ 「(地方自治)法242条2項本文は、財務会計上の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは監査請求をすることができない旨を定めるところ、上記行為のあった日とは一時的行為のあった日を、上記行為の終わった日とは継続的行為についてその行為が終わった日を、それぞれ意味するものと解するのが相当であ」るとする(最判平14.9.12民集56.7.1481)。 |
つまり概念的には、財務会計行為が一時的な行為の場合は「当該行為があった日」が、財務会計行為が継続的行為(期間継続性を有する行為)の場合は「当該行為が終わった日」が、監査請求期間の起算日、ということになります。
なお、以上が監査請求期間の起算日に関する概念的定義ですが、「一時的行為」「継続的行為」については、その概念の具体化が必要であり、その点については下記(2)で説明します。
イ 監査請求期間の起算日の客観性の原則
監査請求期間の起算日が監査対象となる地方自治法242条1項所定の財務会計行為があった日または終わった日であることは、法文上明らかな事項ですが、この点および上記1(1)※※の制度趣旨から、監査請求期間の起算日は「現実に財務会計行為がなされた日(終わった日)」であって、「請求人が当該財務会計行為のあったことを知った日」ではない、すなわち監査請求期間の起算日は客観的に定まる(決定要件から主観性が排除される)という原則が導出されます※。
この点は、近接制度である行政事件訴訟法14条1項や行政不服審査法18条1項が主観的出訴期間制限要件を設けているのと異なる構造となっているので、念の為留意しておく必要があります。
| ※ 参照:最判平14.9.12民集56.7.1481は、「(地方自治)法242条2項本文は、財務会計上の行為のあった日又は終わった日から1年を経過したときは監査請求をすることができない旨を定めるところ、上記行為のあった日とは一時的行為のあった日を、上記行為の終わった日とは継続的行為についてその行為が終わった日を、それぞれ意味するものと解するのが相当であり、当該行為が外部に対して認識可能となるか否かは、同項本文所定の監査請求期間の起算日の決定に何ら影響を及ぼさないというべきである」とします。これは、①「財務会計行為のあった日」の定義を明らかとすること(一時的行為のあった日、たとえば契約の締結、公金の一回的支出、財産の取得・処分のような、それ自体で完結する一つの行為を監査対象とするのであれば、それらがなされた日)、②財務会計行為があった日は客観的に定まる(主観性が排除される) ことを意味するものです。 また大阪高判昭46.8.31判例タイムズ271.199は「控訴人は・・・日付新聞記事によりはじめて事実を知ったと主張するけれども、地方自治法242条2条は、監査請求のできる期間の起算日を「当該行為のあった日又は終わった日」と規定しているのであって、「当該行為を知った日」としておらず、このことは、監査請求が普通地方公共団体の住民に一般的に与えられている権利であり、しかも監査請求の対象となる行為が行われたことについて個々の住民に個別的に告知されるわけのものではないことから、その起算日を個々の住民の個別的な知不知にかからせると、個々の住民の主観的事情によって起算日が区々となり、いつまでも法律関係が不安定な状態にとどまるおそれがあるため、法が、住民の個別的事情の考慮よりも、法律関係の画一的安定を優先させることとし、監査請求をする住民が当該行為をいつ知ったかにかかわりなく、客観的に、「当該行為のあった日又は終わった日」を起算日としたものと解するのが相当であるから、控訴人が・・・日付A新聞の記事によってはじめて本件売渡処分の事実ないしはその違法不当性を知ったとしても、そのことの故に右起算日が左右されるものではないし、従ってまた、そのことのみによって当然には、右期間を遵守できなかつた「正当な理由」があったとすることもできない」とする。 このように、住民監査請求・住民訴訟は、請求人の権利義務に直接関わらない事案に対する、法が特に創設した制度であることから、法律関係の画一的安定を重視する制度解釈がなされているところです。なお、この判示内容は、法解釈の空白地帯を埋める創設的(新たな)な解釈提示ではなく、地方自治法242条2項明文の内容を確認的に具体化したもの、つまり当然の事理を示したものと考えるべきものです。 |
なおこうすると、すべての自治体は恒常的に大量の財務会計行為を行い、大概の問題のある財務会計行為は、住民にとっては、それがなされたかどうかすらよくわからず、違法不当な財務会計行為がなされたとしてもほとんど住民にとっては不可知状態もまま時が過ぎていくため、この点だけ取り上げれば財務運営の適正化を図るという住民監査請求制度の趣旨がほとんど実現不可能となるようにも思われますが、この問題については、財務会計行為がなされて1年経過した後の請求についての正当な理由の存否判断によってカバーされることになっています。
ウ 期間の計算方法
監査請求期間の計算方法については、特に地方自治法上の定めがないため、民法のルールによって期間計算することとなります。したがって初日不算入ルール(民法140条)が原則的に適用されることとなります。
⇒ 財務会計行為日がX年10月5日の場合、翌X年10月6日から起算して、1年を経過するX+1年10月5日の終了までが監査請求期間となる
なお、本稿で契約締結日を起算日云々と記述する場合、実際は、上記の通り「契約締結日の翌日」が第1日ということですので、注意して下さい(記述や話を単純化しています)。
(2) 一時的財務会計行為と継続的財務会計行為
ア 基本的な考え方
地方自治法242条2項で、監査請求期間の起算日を「当該行為のあった日」または「終わった日」と定める以上、一時的行為(「あった日」で決定)と継続的行為(「終わった日」で決定)の概念定義を明確とした上で、対象となる財務会計行為は、一時的行為なのか、継続的行為なのかが決定されなければなりません。
ところで住民監査請求の対象は地方自治法242条1項所定の「財務会計行為」である以上、その対象行為が「あった日」が存在することは自明であり、またすべての財務会計行為が期間継続性を有するわけでないことも明らかである(たとえば、公金や売買した物の所有権が相手方に渡っているかぎり公金支出や売買行為の効力が継続しているとするのであれば、継続性のない財務会計行為は事実上存在しないこととなり、「一時的行為」を概念すること自体現実的にはほぼ無意味となる、つまり請求期間制限制度が現実的には無効化されることにほかならなくなります)ことからすれば、一時的行為が財務会計行為としては一般的なものであり、継続的行為が非一般的なものであると考えることができそうです。
とすれば、終わった日が起算日となる継続的行為は、財務会計行為という全体集合中の特定部分集合であり、その余の部分が一時的行為と考え(上記の松本逐条でも「あった日」の説明を独自に行っていないように)、期間継続性を有する行為の範囲を具体化すれば、それ以外の財務会計行為については一時的行為と考えてよいこととなります。
イ 継続的財務会計行為の範囲
では、どのような財務会計行為が継続的財務会計行為と定義されるのかについて、上記(1)アの松本逐条等の例示や裁判例をもとに整理します。
① 前提
上記(1)アでは、松本逐条や地方財務実務提要は財産の貸付(契約を前提とする例示)や債務保証契約を継続的行為に例示していると説明しましたが、最高裁は、土地賃貸借契約の締結を監査対象とする事案で、これを一時的行為とし、契約締結日を監査請求期間の起算日とする判断を示しています(最判平14.10.15集民208.157)※1。
この判示内容が、売買契約のように、契約の履行(売買代金の支払と売買対象物の引渡し・所有権移転)によって契約内容が一時に完結終了する典型的一時的行為ではなく、賃貸借契約という、契約内容が継続的に履行されることを前提とする契約において、(契約の締結行為それ自体が一時的な事実・事象であることをとらえて)当然に、契約の締結行為を一時的行為としていることからして、最高裁は、監査対象の財務会計行為が契約締結の場合(つまり契約自体の違法性が問題となる事案)については、契約の内容(それが継続的に履行されるかどうか)を問わず、これを一時的行為として、監査請求期間の起算日を契約締結日と判断していることとなります(→ 同判決は賃貸借契約に対する事案だが、その判断論旨は、賃貸借契約に限らない※2)。
以上については、契約自体の違法性が問題となるかぎり、契約により履行される内容に継続性があろうがなかろうが、契約により規律される(自治体を含む)当事者間の法律関係が「契約締結」という(一時的)行為により社会的に固定されることになるという現象をとらえて、最高裁はこれを一時的行為として契約締結時点を監査請求期間の起点とすることとしたのであり、その背景として、法的安定の早期確保を図ることが意図されている、と筆者は考えます。
| ※1 事案内容は、自治体と被告企業等の間で締結した土地賃貸借契約が無効であるとして、住民が自治体に代位して、本件土地の賃貸借契約に基づき土地上の建物を所有し土地を占有等する各被告に、所有権に基づき、建物収去・土地明渡し等を求めるとともに、土地の無権原占有を理由とする不法行為等に基づく、上記各被告及び首長への賠償請求等を求めるもの及び市の土地賃貸借契約条項にある借地権第三者譲渡の際の承諾料支払を求めるものであり、住民監査請求は賃貸借契約締結から1年以上経過後に提起されたものである。判示内容は、「(地方自治法242条2)項本文にいう当該行為のあった日とは一時的行為のあった日を、当該行為の終わった日とは継続的行為についてその行為が終わった日を、それぞれ意味するものと解するのが相当である。前記事実関係によれば、本件監査請求においては、本件賃貸借契約の締結がその対象となる行為とされているところ、契約の締結行為は一時的行為であるから、これを対象とする監査請求においては契約締結の日を基準として同項本文の規定を適用すべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる」。 なお、本件の原審は次の通り判示(仙台高判平9.11.26判例タイムズ982.123)。「控訴人らは、賃貸借契約のようにその効力が相当期間継続する契約の締結の場合には、契約が終了した日が「当該行為の……終わった日」として監査請求期間の起算点となると主張するが、「当該行為のあった日」が一時的行為のあった日を意味するのに対し、「当該行為の……終わった日」とは、行為自体が継続して行われる場合において、その終わった日を意味するものと解すべきであるし、契約の効力がその終了・消滅事由が発生するまで継続することは、何も賃貸借契約に限られるものではなく、すべての契約に当てはまるものであるから、控訴人ら主張のように解することはできない。(地方自治)法242条2項本文が監査請求に期間制限を設けたのは、地方公共団体の執行機関又は職員の財務会計上の行為をいつまでも争い得る状態にしておくことが法的安定の見地からみて妥当でないとの趣旨にでたものであるところ、控訴人ら主張の見解をとると、賃貸借契約についてのみ他の売買契約等と異なり、長期間契約締結の違法を主張して監査請求をすることができることとなって、監査請求に期間制限を設けた右の趣旨が没却されることとなり、相当でない。また、控訴人らは、その監査請求は契約締結行為とともにその履行を継続していることも対象としていたもので、賃貸借契約における履行としての「土地の賃貸」という財務会計上の行為は現在も継続しているから、監査請求の期間制限は問題とならないと主張する。しかしながら、契約の締結行為とその履行行為とは、財務会計上の行為として別個のものであり、それぞれが独立して監査請求及び住民訴訟の対象となり得るものと解すべきであるところ、第一事件の対象とされる財務会計上の行為が本件賃貸借契約の締結行為であることは、前記のとおりであり、控訴人らは、その後の本件賃貸借契約の履行行為について、契約締結行為とは別個の違法事由があるとして、これを本件住民訴訟の対象としているものではなく、かつ、本件賃貸借契約締結行為自体を違法・不当な財務会計上の行為として監査請求の対象としているもので、その履行行為を右締結行為とは別個の対象として監査請求していないから、控訴人らの右主張は失当である」。 |
| ※2 参照:宇賀自治法p.387、実務住民訴訟p.40 |
② 財産の貸付
上記①による限り、松本逐条や財務提要の見解と必ずしも整合していないように見受けられます。
この点、すくなくとも財産貸付契約自体を問題とし、これを監査対象事項とする住民監査請求においては、上記①の前提に立つ限り、対象財務会計行為(契約締結行為)は一時的行為であるとせざるを得ません。
一方で下記(3)にあるように、契約の締結行為と履行行為は、監査請求期間の決定においては異なる財務会計行為とされるので※1、財産貸付という期間継続的な契約履行行為(相手方に使用収益させるため自治体の財産を提供する)において、履行行為全体に一体的な継続性ある場合は、契約締結行為が一時的行為であるという判断とは別に、契約履行行為を継続的行為として、貸付期間終了(満了・解除)時が監査請求期間の起算日とすることはあり得ることです(たとえば適法な賃貸借契約において、自治体が賃貸した物件が契約条件を満たさなかった(債務の本旨に従った履行をしなかった)ことがしばらくして判明し、契約解除され(上記(1)アの松本逐条の例参照)これ以降の期待賃料収入を失う、また債務不履行責任としての損害賠償をせざるを得なかった場合などが例として考えられるでしょう)※2。
| ※1 前提として、監査請求期間の起算日決定において契約の締結と履行が異なるものとされることについては、最判平14.7.16民集56.6.1339参照。つまり一つの契約関係での契約締結と履行行為は、監査請求期間の計算上は、別個の財務会計行為とされます(契約締結後1年以上経過したが契約履行から1年経っていない事案についての住民監査請求では、契約締結に対する住民監査請求は(原則として)適法な請求とはならず、その場合契約締結上の違法性は問題とすることができません。下記(3)イ参照)。その上で上記※の仙台高判判示事項参照。 |
| ※2 なお、住民監査請求の要件審査の問題ではなく本項に関連する参考事項ではありますが、締結された契約自体の違法性が、履行行為の違法性にどのように影響するか(契約に違法性がある場合、履行者は履行責任をどこまで負うか)については、最判平4.12.15民集46.9.2753(一日校長事件。原因行為に基づきなされた財務会計行為について損害賠償責任を問うことができるのは、原因行為に違法があった場合であっても、その原因行為を前提として財務会計職員がした財務会計行為が財務会計法規に違反して違法な場合に限られる)を前提としての、最判平25.3.21民集67.3.375(契約が違法である場合の契約履行行為(支出命令)の違法性)、また同判決の先行的判断である最判平20.1.18民集62.1.1(土地開発公社に土地先行取得を委託した場合のその契約履行としての公社取得土地の買取契約の違法性)が参考となります。なお、違法性の承継といわれるこの論点は、考慮要因が多岐に亘り複雑なところがあるため、詳細については、別稿「7 先行する行為の違法性の請求対象財務会計行為への影響(違法性の承継)」のページ、または「全体集約版」の該当箇所をご覧下さい。 |
③ 債務保証およびその類似契約
上記(1)アで松本逐条が例示する債務保証契約(保証契約の締結自体は一般に(特別法措置のある土地開発公社など除き)、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律3条により禁止されており、ここでは三セク等への金融機関の与信を容易にするために昭和29年の行政実例を踏まえて行われる、金融機関との損失補償契約を含む)、は上記①の論理では、財務会計行為としては一時的行為であり、実際に、損失補償契約について同旨の判断を示す裁判例※があります。
結局のところ、損失補償契約そのものの違法不当性を問題とする限り、契約締結時点で契約の違法不当性に関する判断要素は出揃っており、契約の違法不当性に関する監査を完結的に行うことが可能であること、その後の契約履行は契約締結とは独立した別の問題であることからすれば、損失補償契約の締結行為は、上記①前提の通り、これを一時的行為として契約締結時点を監査請求期間の起算日とすべきと考えます(債務保証契約においても、これと異なる判断を行う理由は、原則的にないものと考えます)。
| ※ 横浜地判平18.11.15判例タイムズ1239.177(三セク会社への金融機関融資に係る金融機関との損失補償協定を締結の10年以上後に三セク破産により協定に基づく和解契約で市が金融機関に公金を支出した事例) 「支出負担行為(本件協定の締結)についての監査請求について、本件協定の締結は平成6年5月10日にされているから、この締結日を起算点とすれば、本件監査請求は監査請求期間を経過した後にされたものというべきであるが、原告は、支出がされた日(平成17年1月14日)を起算点とすべき旨主張する。 そこで検討すると、住民監査請求は、財務会計上の行為又は怠る事実を対象として行われるものであるところ、当該行為についての監査請求は、当該行為のあった日又は終わったから1年を経過したときは、これをすることができないものとされている(地方自治法242条2項本文)。そして、ここにいう当該行為のあった日とは一時的な行為のあった日を、当該行為の終わった日とは継続的な行為についてその行為が終わった日を、それぞれ意味するものと解される。本件監査請求においては、本件協定の締結がその対象となる行為とされており、同契約の締結行為は一時的行為というべきであるから、これを対象とする監査請求は契約締結の日を基準として同項本文の規定を適用すべきである(最高裁判所平成14年10月15日第三小法廷判決・判例時報1807号79頁参照)。 原告の上記主張は、財務会計上の行為がされても損害が発生していなければ、監査請求において損害を補てんするため必要な措置を講じることを請求したり、その後の住民訴訟において当該職員に対して損害賠償の請求(又は賠償命令)をすることを求めることができないという点を根拠としている。しかし、監査請求においては、その対象である財務会計上の行為又は怠る事実を特定して、必要な措置を講ずべきことを請求すれば足り、措置の内容等を具体的に明示することは必須ではなく、仮に、執るべき措置内容等が具体的に明示されている場合でも、監査委員は監査請求に理由があると認めるときは、明示された措置内容に拘束されずに必要な措置を講ずることができる(最高裁判所平成10年7月3日第二小法廷判決・裁判集民事189号1頁参照)。すなわち、監査請求は、財務会計上の行為又は怠る事実を対象としてされるものであって、監査委員に求める措置が、当該行為の防止、是正、怠る事実を改めること及び損害のてん補のいずれであるかによって、監査請求の対象が異なるというわけではない。また、監査請求を前置してされる住民訴訟についてみても、その対象とする財務会計上の行為又は怠る事実について監査請求を経ていると認められる限り、監査請求において求めていた具体的措置とは異なる内容の請求をすることも許されると解されるから、この点からも監査請求の期間を住民訴訟で求める請求の内容ごとに考える必要があるとは解されない。 原告は、支出負担行為がされた時期を基準にすると、当該職員に損害賠償請求(賠償命令)することを求めることができず、そのような請求をする機会が保障される必要がある旨を主張する。しかしながら、住民訴訟制度の目的は、住民が納税者としての立場から、地方公共団体が違法な財務会計上の行為によって損害を被ることを防止し、あるいは被った損害を回復する手段を設け、これによって地方公共団体が適正な財務会計処理を行うことを保障する点にある(監査請求制度も、その対象が不当な財務会計上の行為を含む点を除けば、同趣旨の制度であるということができる。)。このような制度趣旨からすると、監査請求及び住民訴訟において、契約の締結行為の当否、適否を争うことができるとされているのも、その後に予定された契約の履行により地方公共団体が損害を被ることを防止したり、あるいは被った損害を回復するためであって、契約の締結時において、履行行為の差止めや法律関係の不存在確認(旧法下)を求めることができれば、契約が締結された結果として発生した損害について当該職員に対する損害賠償請求等を求める機会が保障されることが必須の要請とまでは解されない。もとより、監査請求の可否とは関わりなく、当該地方公共団体は当該契約に起因して損害が発生すれば、当該職員に対して損害賠償等の請求をなし得るわけであるし、その請求が行われないときには当該請求を怠る事実についての監査請求や住民訴訟の提起も可能なのであるから、上記のように解することによって特段の不都合があるとも認められない」 |
④ その他参考となる事例
条例に基づく給与支給が違法である場合、給与支給自体は継続的に行われるため、その監査請求期間の起算日が争われた住民訴訟(大阪地判平12.4.28)で、これを一時的行為と判断じた事例があります(類似例として大阪地判平15.10.30判例地方自治258.49)。いずれも同一原因行為(職員の任用、業務委託契約)による連続的な支出とはいえ、個別の支出自体は例月給与または例月委託料としてそれぞれに独立性があり、各支出を一体として見なければ監査に適さないというものではないという判断が前提となっており、当然の帰結と考えます。
一方で、土地開発公社に対してある一つの委託契約で土地買収を委託し、その代金を10年割賦で支払う約定をした場合、その支出を一体のものとみて、最終支出日が監査請求期間の起算日とみる事例があります(秋田地判昭56.5.25判例時報1036.62)※。上記の給与支給や駐車場管理業務が、あくまでも各月の支出は個々別々の月になされた勤務や業務に対する支出であり、それぞれに独立性があるのに比して、本事例は、本来一つの支出が便宜的に割賦の形で分割されているに過ぎず、分割された各支出は一体性があるという判断を前提としているものと考えます。
| ※ 本判決は、「その支出を一体のものとみて、その支出の原因である契約が締結された日や個々の支出が行われた日ではなく、右支出が終了する日をもって「当該行為の終わった日」と解し、その日から監査請求期間を起算するのが相当」としますが、その後の裁判例の動向を考慮すれば、本判決の判示に関わらず、すくなくとも監査請求期間の起算日の決定において契約締結部分まで一体的に観察すべきではない(契約の締結行為と履行行為は監査請求期間の上では分離すべき)と考えます。 |
ただし類似の事例で、道路拡幅工事に伴い町が団体と締結した移転補償合意に基づき、当該合意額を年度内に複数回に分割して支払った事例においては、「本件移転補償合意の違法を根拠として本件訴訟を提起するのであれば、原告らの主張するように、本件公金支出全体を一体のものと見る余地があるように思われる。しかし、前記のとおり、原告らは、町長の本件支出命令の違法を問題として本件訴訟を提起しているのであるから、各支出について各別の支出命令がなされている以上、個別の支出命令ごとに監査請求期間を計算するのが相当」という判断が示されています(福岡地判平23.4.19判例地方自治357.33)。
判断自体は上記昭和56年秋田地判と必ずしも整合していませんが、上記判決理由をみる限り、支出全体を一体として把握する可能性を排除していないものの、本件は支出命令の違法性が問題となっているため、個々の支出命令を分解して個別に監査請求期間が計算するとの判断を示しています。本件における支出は上記の通り複数回に分割して行われていますが、各支出の名目および金額はそれぞれ異なり(合意内容通りの名目・金額ではある)、単なる一つの支出の分割ではないという事情も影響していると考えます。
(なお本件住民訴訟では、移転補償合意の違法性も争点となっている。ただし本訴における実質的な法律上の争点は、前記移転補償の違法性が肯定された場合に移転補償合意の違法性が支出命令の違法原因となるかであり、当審はそれを肯定したが最高裁(平25.3.21民集67.3.375)は違法性の承継について限定的な解釈を示した)
⑤ まとめ
以上の諸実例を見るかぎり、松本逐条や最高裁判決が示す定性的概念的定義はともかく、継続的財務会計行為が(より具体的には)どのようなものかについて、断言的な定義を明示することは難しいところがありますが、監査請求期間制限制度の趣旨である早期の法的安定確保の要請を踏まえつつ(ということは、継続的財務会計行為であると認めるべき事案以外は、原則的には一時的財務会計行為と判断すべきベクトルが働くこととなる)、期間継続的行為のうち全体を俯瞰して明らかに一体性があるものについてのみ※、継続的財務会計行為として判断することが適当である、と筆者は考えます。
| ※ たとえば上記④の平成23年福岡地判の事例では、数回に分けて異なる名目で支出された移転補償費は、実質的には一体的なもので、単に(資金交付の都合等で)形式上、名目上分けただけなのかもしれません。しかしながら、形式上、異なる支出命令について異なる名目(と金額)が計上されている以上、原則的にはその外形を尊重して判断を出発させるべき、ということになるものと考えます。 |
(3) 監査請求期間起算日の具体的な特定
ア 一般原則
監査請求期間の起算日(現実的には「財務会計行為のあった日」)は、具体的にはどのように決定されるのでしょうか。
「財務会計行為があった日」は具体的には、監査対象となる個々具体の財務会計行為が実際になされた日(例えば契約の締結行為を監査対象とするのであれば、当該契約の締結日ですし、財産の取得を対象とするのであれば財産の取得日※)を指すものとされ、この日によって決定されることが原則です(参照:最判平14.7.16民集56.6.1339)
| ※ 参照:判例行政法p.67(海老名富夫)、実務住民訴訟p.40。なお碓井p.48はこの点に関する事例として、東京地判昭57.7.14行裁例集33.7.1502(契約締結、公金支出、財産取得)、松山地判昭55.11.17行裁例集31.11.2402(契約締結)等を例示する。 |
イ 一の目的のために複数の行為が複合する場合の取扱い
多くの財務上の行為においては、あるひとつの目的、たとえばある特定の公金の支出や財産の取得などをなすために、いくつかの事務プロセス、たとえば支出負担行為(契約締結)をおこなったのち、支出命令、現実の公金支出をする、また売買による財産の取得では、これに伴って財産の所有権移転をする、といったプロセスが複合して構成されています。
ではこのような場合、どの時点をもって監査請求期間の起算日とするのか、特定するルールを明確化しなければなりません。
この点について、上記アの平成14年最判によれば、関連する行為が一連性をもつものであっても、それぞれの行為の権限、行為目的、時期等が異なるものは、監査請求期間の観察上は独立した財務会計行為として扱われることになります。
そもそも地方自治法242条1項をみると、たとえば平成14年最判で問題となった公金の支出の場合、その事務プロセスを構成する支出負担行為(契約の締結)、支出命令、現実の支出は、それぞれが財務会計行為の類型として規定されています。そしてこれらの行為は、それぞれに根拠規定、行為目的、権限者が異なり、いずれを監査対象とするかで監査内容も異なってくることとなります。
よってこれら行為は、一体的な財務会計行為として監査請求期間の算定をするのではなく、それぞれを独立した財務会計行為として扱い、監査請求期間の起算日は、独立した権限・目的をもつ個別の行為単位に分解して個別に決定することとなるのです※1、※2。
| ※1 本判決に関する地方自治判例百選4版p.148/5版p.139では、かねて公金の支出のように一連の行為を経て行われる財務会計行為の監査請求期間の起算日について、公金の支出全体を1個の行為ととらえその終了時点(現実の支出)を起算日とする考え方と個別の行為(支出負担行為、支出命令、現実の支出)がなされた時を起算日とする考え方(本判決が採用)が主張されてきたことについての説明がなされています。 |
| ※2 むろん、一つの公金の支出を行うために向けた一連のプロセス・・・支出負担行為(契約等)→支出命令→現実の支出・・・は、ある一つの特定の公金の支出を最終の目的として連続して行われるものなので、実際に住民監査請求を提起するにあたり、これら各行為を明確に区分せず一体として監査請求の対象としても何らの差支えはありませんし、それによって請求の特定(「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」、「2.2 請求の対象行為等の特定」参照)に欠けることもありません(上記最判参照)。 なおこの場合において、上記※で引用の判例百選4版p.149/5版p.139では、上記平成14年最判はこのような一体としての請求の場合の監査請求期間の起算日について明示しておらず、判断が分かれる可能性があるとしているところ、監査実務においては、本最高裁判決でも一体的請求の場合に同判決が示す原則の適用除外の可能性を示す判示事項がなく、その他の最高裁判例において包括的な監査請求期間起算の考えを示すものが見受けられない以上、個々の財務会計行為を分解して、それぞれに監査請求期間の算定を行わざるを得ないのではないかと筆者は考えます(なお参考:本判決に関する時の判例Ⅰp.296(大橋寛明)同旨)。 |
またこの理によれば、公金の支出に限らず、ある行為が複合的な財務会計行為を形成する場合も同様とすべきものです。
たとえば土地売買契約による土地の取得であれば、売買契約の締結、代金の支出、土地(財産)の取得という、それぞれが地方自治法242条1項に定める住民監査請求の対象となる財務会計行為(類型)が複合して一つの目的行為を形成しています。上記公金の支出同様、請求人がこれら行為を一体的に監査請求することには何らの問題もないのですが、監査請求期間については、上記公金の支出と同様に、一連の関連行為が終結した時点から監査請求期間が起算されるのではなく、あくまでも個々に分解される上記の財務会計行為ごとに、監査請求期間が起算されることとなります。
したがって、とりわけ契約が問題となる事案では、契約の締結と履行(公金の支出や財産の取得・処分等)という異なる局面が生じますが、これらは、監査請求期間の算定においては、別々のものとされることとなります(上記2(2)イ説明と重畳しますが、ある契約の違法性を問いこれを監査対象とする場合、監査請求期間の起算は履行終了日ではなく契約締結日ということになります)。
そして上記の帰結として、公金の支出において支出負担行為(契約等)からは1年以上経過、支出命令や現実の支出からは1年以内に住民監査請求が行われた場合、住民監査請求の内容が如何なるもの、つまり支出負担行為・支出命令・現実の支出を分解して観察し、それぞれの違法不当性を問う内容であったとしても、支出負担行為(契約等)から現実の支出までの行為を区分せず一体としてその違法不当性を問う内容であったとしても、いずれにせよ、当該住民監査請求においては、支出負担行為部分(契約締結等。そのような契約を締結することの適否であり、つまりは契約自体の適法・違法性が直接の問題となる)に関する請求は不適法となり、その住民監査請求では、支出命令や現実の支出に関する部分の違法不当性のみが監査の対象となる(支出負担行為たる契約の違法不当性は直接監査の対象とならないし、その点を請求人は直接主張できない)こととなります※3〜※6。
これは、支出負担行為から現実の支出までを一体的に観察して、現実の支出から監査請求期間を起算する主張を容認することとなると、財務会計行為に関するタイムスパンの長い短いでとりわけ契約締結の是非を問う住民監査請求の監査請求期間が左右されることとなり、監査請求期間の規定を設けた意味がなくなるからです。
| ※3 よって、たとえば契約内容の違法性を理由として契約締結から履行までの財務会計行為を一体的に監査対象としている場合で、既に契約締結日から1年経過後している(履行後1年は経過していない)ときは、契約履行行為固有の違法事由が請求中で明示的にせよ黙示的にせよ主張されていない(または主張の内容は別としても、明らかに契約履行行為中の違法事由が見受けられる等でない【注】)限り、請求全体として監査請求期間を経過したものと扱うべきこととなります(参考:大阪地判平3.4.24判例タイムズ771.121、仙台高判平9.11.26判例タイムズ982.123(最判平14.10.15集民208.157原審)、盛岡地判平12.6.16)。 【注】 請求人の請求時に監査対象たる財務会計行為の特定摘示は要求され(監査委員もその対象行為特定には拘束され)るが(最判平2.6.5民集44.4.719)、監査委員は請求人の主張内容には拘束されないこと(最判昭62.2.20民集41.1.122)、監査の進行は職権探知主義をとることからすれば、請求人が主張していなくても、監査委員において、契約履行行為固有の、違法を疑う事由を、何らかの理由で探知した場合は、当該請求を監査請求期間中に請求されたものとして扱うことは可能と解します(し、住民監査請求制度が持つ財務運営の自浄的適正化機能を考慮しれば、そうすべきです)。 |
| ※4 ということは、契約の締結から履行までを一体的に(または特にこれを分別せず)監査対象として住民監査請求がなされた場合において、請求人が契約の違法性を主張し、それゆえに履行行為も違法と主張する限り、監査の論点は事実上、契約の違法性に局限されるのであり、監査請求期間の検討においては、そのような違法な契約を法律上有効とした契約締結行為が、監査対象の財務会計行為となる以上、契約締結日が監査請求期間の起算日となる、という理屈になります。 |
| ※5 判例行政法p.68(海老名富夫)で例示する横浜地判平18.11.15判例タイムズ1239.177では、支出負担行為から監査請求までは1年以上経過、支出命令および現実の支出から監査請求までは1年以内の事例につき、上記平成14年最判を引用して、監査請求期間の起算日を支出負担行為、支出命令、支出行為の各別に設定した上で、(監査請求期間の起点を支出負担行為日とすべきとの被告の主張に関し)「支出負担行為、支出命令及び支出はそれぞれ独立した財務会計上の行為と解されるから、支出命令及び支出についての監査請求は直接的にはこれら各行為の違法、不当を問題としているのであって、これらの各行為を違法、不当ならしめる事由として支出負担行為の違法、不当が主張されているとしても、この点に変わりはない。ただ、支出命令及び支出が違法、不当であるかどうかということと、それに先行する支出負担行為の違法性とは無関係ではないし、支出負担行為が違法である場合に後行の支出命令及び支出がいわばその違法性を承継して違法になるという場合もあり得ることから、そのような場合には上記の審査において支出負担行為について違法性が審査されるにすぎない」としています。これを見る限り、支出命令・現実の支出の段階で、支出負担行為の違法不当性を問う余地があるとも解されますが、実際には、違法性の承継に関する最高裁判例(最判平4.12.15民集46.9.2753、最判平25.3.21民集67.3.375など)を見る限り、支出命令等を対象とする監査において支出負担行為の違法不当性を審査する局面は、ある程度限定的なものとなるものと考えます。詳細は別ページを参照して下さい。ただし、下記※6についても留意が必要です。 |
| ※6 上記本文および上記※5のとおり、支出命令から住民監査請求までは1年が経たないが、支出負担行為からは1年経過した場合、支出負担行為を監査対象財務会計行為とすることも、その支出負担行為の違法性を直接主張することもできませんが、そのような場合においても、監査において監査対象財務会計行為としての支出命令の違法性を検討するにあたり、支出命令の前提行為である支出負担行為の内容を検討することはあり得ることです。 たとえば、最判平25.3.21民集67.3.375は、違法性の承継(別ページ参照)で参照される判例であり、町有地上の建物の使用者と建物取壊しに伴う移転補償合意(契約)をX年3月に締結、同4月に1回目の移転補償費の支払、X+1年3月に残額の支払を行ったところ、X+1年8月に住民監査請求が提起されたという事案ですが、本判決では、X+1年3月の支払(支出命令)について適法な監査請求を経たものとした上で、その支出命令の違法性の存否を判断するにあたり、監査請求の1年以上前に締結された支出負担行為(移転補償合意契約がどのような法的評価を受ける場合に、その支出負担行為に基づく支出命令の実行が財務会計法規上違法となるか(参照:最判平4.12.15民集46.9.2753)について判断しています。これは、支出命令の固有の違法性を審査するにあたり、前提となる支出負担行為の内容および支出命令との関連を考慮しなければ、この審査ができないためです。 このように、上記の監査請求期間ルールは、この期間内に住民監査請求がなされたかった財務会計行為については、それ自体を監査対象財務会計行為とすることはできない、とするものですが、それを超えて、監査において一切の審査の視野から排除する、という意味合いまでにはならないことに留意する必要があります。 |
ウ 留意すべき形態の財務会計行為の取扱
① 変更契約
変更契約がなされた場合、変更契約はそれ自体完結した1個の契約として当初(先行)契約の内容を変更するのですから、財務会計行為としても、また監査の対象としても独立した財務会計行為とみるべきであり、変更契約の締結を対象とする住民監査請求の監査請求期間は、変更契約締結の日を起算日とすべきものと考えます(参考:大阪地判平3.4.24判例タイムズ771.121)※。
なお上記の理にしたがえば、補助金の変更交付決定なども同様に考えるべきです。
| ※ ということは、変更契約があった場合において、当初契約を監査対象とする住民監査請求の監査請求期間の起算日が、変更契約日に後ろ倒しとなることはない(当初契約日のまま)し、当初契約と変更契約が監査請求期間の判断において一体的に観察されるということもない、ということになります。 |
② 概算払
概算払された公金の支出について違法不当があるとする住民監査請求については、概算払の時点で監査請求期間が起算されるとするのが判例です(最判平7.2.21集民174.285)。
概算払は、それ自体は財務会計行為としては未完成であり、確定精算行為が後行するものとはいえ、それ自体は独立した公金の支出行為であり、個別の独立した監査対象として、その違法不当性を監査・判断することも可能であることからくる帰結です。つまり、それ自体が完結していない財務会計行為であっても、その部分を個別に監査して違法不当性を判断できるのであれば、未完結の財務会計行為であろうとも、それ自体を独立した財務会計行為としてみることとなり、監査請求期間は、当該概算払等のあった日から起算されることとなるのです※。
またそうであれば、確定精算の違法不当を問う住民監査請求の監査請求期間は、確定精算の日から起算される(概算払の日ではない)ことになりますし(上記最判参照)、監査請求期間内である限り、両者を一体として請求することには何の支障も生じないこととなります。
| ※ 実務住民訴訟p.41は、資金前渡、前金払による公金の支出も同様とします。上記の論理によれば当然の帰結であると考えます。またそうであれば、補助金の支出(交付決定、確定、精算のプロセス)も同様となります。 |
3 怠る事実を請求対象とする場合の監査請求期間の取扱い
怠る事実を監査請求対象とする場合は、複雑な問題を生じます。
地方自治法242条2項は「当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない」としており、条文上、監査請求期間は財務会計行為が存在することを前提としていることは明らかであるため、怠る事実については監査請求期間の制限は適用されないと読め、実際最高裁は下記の通り、怠る事実を監査対象とする請求については、原則をそのように解しています。
しかし実際は、怠る事実を監査対象とする請求内容であっても、その実質が財務会計行為自体の違法不当性を問うものもあり、そのため監査請求期間の適用についてのヴァリエーションルールが形成されていることに留意する必要があります。
これを相当程度単純化して分解すると、次のようなフローとなります(必ずしも網羅的なものではなく、ざっくりと単純化したものです。いくつかの付帯的な考慮要素は省略しています)。
| その請求は、(損害賠償請求権等の行使を)怠る事実を対象としているか? |
⇓ YES
| 請求の実質的な内容が、財務会計職員が財務会計法規に反して財務会計行為を行い、その財務会計行為が違法(無効)であるため、財務会計職員等に対して生じる実体法上の請求権(損害賠償請求権等)の行使を、自治体が怠っている、というものか? | NO → 監査請求期間制限の適用なし【怠る事実の場合の原則】 |
| YES → 次へ |
⇓ YES
|
次の請求権行使を怠る事実を監査対象とする場合は監査請求期間制限の適用あり |
| ○ 監査対象の財務会計行為を行う権限のある財務会計職員(財務会計職員の権限行使を補助する職員を含む)に対する実体法上の請求権の行使を怠る事実 ○ 問題となる財務会計行為が違法であり無効であることから、自治体がその財務会計行為の相手方に対して生じる不当利得返還請求権などの行使を怠る事実 (相手方が自治体へ違法な行為を行ったことによる請求権ではない) |
(1) 監査請求期間の一般原則・・・監査請求期間制限の適用なし
怠る事実を監査対象とする場合、住民監査請求の監査請求期間の制限(地方自治法242条2項)は適用されないことが原則です(最判昭53.6.23集民124.145※)。
| ※ 本事案は、収入役が勝手に町長公印を使って金融機関から金銭を借り入れたという事例につき、町長に対し、共謀または監督義務違反を原因とする損害賠償請求権の行使を怠るという主張となっています。町長には本来的な財務会計行為(借入れ)の決定権限があるため、下記(2)の適用があるとも考えられ得るところですが、本件判断は、あくまでも町長の不法行為により町に損害を被らせた(損害賠償責任がある)点を観察したものとなっています(町長の加担状況は明確ではないが、なればこそ、町長の財務会計行為ではなく(また長の補助機関たる職員による財務会計行為に対する監督責任でもなく)、長の補助機関たる職員の(たまたま金銭借入という形態をとった)犯罪行為を阻止するという注意義務違反に主眼を置くこととなっているものと推測)。 |
これはそもそも「怠る事実」が監査対象である場合は、監査請求期間の制限について定める地方自治法242条2項の規定にいう、監査請求期間の起算日となるべき「財務会計行為があった(終わった)日」(端的に言えば「財務会計行為」の存在事実)がありませんし、またその「怠る事実」が事実状態として存在している限り、財務会計上の違法不当な状態が継続して(存在して)いるからであり、そうである限り、監査請求期間制限制度の目的である早期の法的安定の確保を追求する必然性がないからです※※。そしてこの怠る事実の事実状態としての継続性を言い換えれば、上記2でいう継続的財務会計行為と同様の状態であり、継続的財務会計行為については、その対象行為が継続する間は住民監査請求ができるのですから、怠る事実についても同じ考え方によることとなるのです。
以上の通り、原則的には、「怠る事実」が存続する限り、その怠る事実がいつ発生したかに関わらず、住民監査請求は提起可能ということになり、怠る事実を監査対象とする場合の監査請求期間の制限適用の有無は、この原則が、詳細な検討を行う上での第一歩となリます。
| ※※ 「怠る事実」が終了している場合については、下記(2)イ③参照。 |
これによれば、たとえば、自動車の運転者が運転を誤って(またはわざと)自治体の庁舎を損壊した場合、庁舎損壊行為に対する損害賠償請求権(不法行為による損害賠償請求権)は、請求権の行使が放置されている限り(請求権が時効等で消滅した場合については下記(2)イ③参照)、上記損壊事故のあった日から1年を経過していようとも、請求権行使を怠る事実に対する住民監査請求について地方自治法242条2項は適用されないので、事故から1年経過のゆえをもって請求が不適法となることはありません(損害賠償請求権の発生原因である庁舎損壊行為は地方自治法242条1項所定の財務会計行為ではないので、242条2項の適用の余地がありません)。
(2) 怠る事実を対象とする住民監査請求で監査請求期間制限の適用がされる場合
ア 基礎となる考え方
上記(1)は、怠る事実を監査対象とする場合の原則ルールです。
しかし、怠る事実を監査請求の対象とする場合すべてにおいて、監査請求期間制限の適用がないわけではありません。
具体ケースは下記イで説明しますが、上記(1)のような「真正怠る事実」ではなく、「不真正怠る事実」を監査対象とする場合は、(1)の原則ルールの適用が排除され、監査請求期間の制限が適用される、ということです。
| 【参考】
怠る事実が監査請求期間の制限にかかるかどうかの点に着目して、 ○ 怠る事実のうち、本項で説明するように、監査制限期間の制限にかかるものを「不真正怠る事実」と、 一般に称しています【注】。 【注】 真正怠る事実、不真正怠る事実の用語は広く使用されています。なお最判昭62.2.20民集41.1.122に関する最高裁判解昭62年度p.84(石川善則)参照。 |
ではどのような考えにより、どういったケースで上記(1)の原則ルールが排除されるのか、についてですが、請求内容が外形的には「自治体が請求権の行使を怠っている事実」に対するものとなっていても、請求内容が実質的には、
○ 財務会計職員※が財務会計法規に反して※※財務会計行為を行い、その財務会計行為が違法となっていることを問題としている(たとえば強行法規違反の財務会計行為:不適法な随意契約方式の選択や行政財産の売り払い、またもっと直截な例として、官製談合による不当な価格の契約)
○ それを踏まえ、財務会計行為が違法であるがために発生する、自治体が財務会計職員に対して有する請求権を行使していない事実をとらえて、その「怠る事実」を請求対象事項としている(たとえば上記不適法な随意契約の実行、行政財産の売り払いにより生ずる職員への損害賠償請求権、売り払い相手方への不当利得返還請求権や上記官製談合による担当職員への損害賠償請求権(ただし契約相手方と共謀する官製談合の契約相手方への損害賠償請求権は別の考え方となるので注意。下記ウ参照))
このような場合は、実際には直接その財務会計行為の違法不当を問題として是正を求める請求と、実質的な監査対象事項・監査内容が同じであるというほかなく、そうであるのに請求書の作文方法で監査請求期間の制限が適用されたりされなかったりするというのはおかしい、という問題意識を出発点にしています。
(たとえば上記の財務会計行為(地方自治法242条1項所定の「契約の締結・履行」や「公金の支出」に該当)が財務会計法規に違反しており、自治体に損害が生じているので、この是正や関係者への損害補てんを求める、また違法・無効な財務会計行為についての相手方への不当利得の返還を求める、などにかかる請求。これが監査請求期間制限を適用されることは、地方自治法242条2項の規定から明らかだし、上記の怠る事実と構成された請求内容とは実質的には同内容である点もまた明らかである)
| ※ 財務会計職員とは、地方自治法242条1項の「地方公共団体の職員」のことであり、監査対象となる財務会計行為等について権限を有する者(本来的に財務会計権限を有する首長を含む)となります。最判昭62.4.10民集41.3.239(地方自治法242条の2第1項4号の「当該職員」の定義)および最判昭62.2.20民集41.1.122の財務会計職員に関する判示事項を参照。なおいうまでもありませんが、住民監査請求の対象となり得る財務会計行為等は、それらの行為等について権限のある執行機関または職員が行なった(怠っている)ものであることが前提です(地方自治法242条1項の法文から明らかです)。 なお、上記の「権限」は実質的にその権限を保有しているかではなく、法令や自治体の権限委任・決裁規程等で誰に財務会計行為の実行についての権限を設定しているかにより判断されます(次パラグラフの参照先で説明)。たとえば下記3(2)エの最判平14.10.3民集56.8.1611では、担当部長を財務会計職員とし、部長の職制上の直接の上司である副知事を権限外職員としていますが、これは実質的な権限の所在(官製談合について副知事は担当部長に事実上の影響を与え得たとも考えられる)ではなく、あくまでも上記の規程審査により判断される(副知事は地方自治法上の本来的な財務権限行使権はなく、また当然の代理権もない。そして決裁規程等で部長専決事項とされており、たとえ部長の上級者で一般的な指揮命令権があっても規程上の権限はない。ただしそのことは副知事の財務会計職員性の否定にとどまり、副知事が担当部長に違法な財務会計行為の決裁を指示した場合にその責任が免責されることではない(一般論としての不法行為責任は発生)ことに注意)こととなります。 以上の財務会計職員や当該職員の概念定義・説明については、「3 当該普通地方公共団体の執行機関・職員」の2(2)を参照下さい。 |
| ※※ 最判平4.12.15民集46.9.2753は、先行行為(教育委員会の人事(昇任)発令)と監査対象事項(左記昇任発令に基づく首長の給与支給)の関係について「地方自治法242条の2の規定に基づく住民訴訟は、普通地方公共団体の執行機関又は職員による同法242条1項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実の予防又は是正を裁判所に請求する権能を住民に与え、もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的とするものである(最高裁昭和51年(行ツ)第120号同53年3月30日第一小法廷判決・民集32巻2号485頁参照)。そして、同法242条の2第1項4号の規定に基づく代位請求に係る当該職員に対する損害賠償請求訴訟は、このような住民訴訟の一類型として、財務会計上の行為を行う権限を有する当該職員に対し、職務上の義務に違反する財務会計上の行為による当該職員の個人としての損害賠償義務の履行を求めるものにほかならない。したがって、当該職員の財務会計上の行為をとらえて右の規定に基づく損害賠償責任を問うことができるのは、たといこれに先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、右原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反する違法なものであるときに限られると解するのが相当」としていますが、これは、住民監査請求・住民訴訟における財務会計行為の違法性判断は財務会計法規違反に限定されることを明らかにする趣意とされています(参考:判例行政法p.20(石津廣司)。上記引用部分の解釈として合理的な帰結です。本判決はいわゆる4号訴訟において先行行為と後行財務会計行為の違法性の承継問題を正面から論ずる事例とされますが、いずれにせよその点を検討するためには、そもそも「住民訴訟(住民監査請求)において参照されるべき、財務会計職員の行為義務の枠組みを定める行為規範」が何かが明確とされていることが前提となることは、いうまでもないことです。また本判決に関する最高裁判解平成4年度p.542(福岡右武)の説明(4号訴訟において問題となる職員の行為の違法性は、その職員が財務会計行為を行うに当たって負っている職務上の行為義務ないし行為規範違反とし、これを財務会計法規上の義務と捉え、先行原因行為との関係での判断基準を演繹している)もそれを前提としていると解します)。 そしてこれは、住民監査請求・住民訴訟における「財務会計行為の違法」は、(上記※の通り、その行為主体が財務会計職員であることを前提として)財務会計法規に違反することにより生じる、ということを意味します。また、住民監査請求・住民訴訟における財務会計職員の責任追求を財務会計法規違反の範囲に限定し画然とさせるということを同時に意味することとなります(参照:塩野Ⅱp.275)。 ただし、以上はあくまでも原則的な枠組みないし前提を示すのみであり、そもそも「財務会計法規」が具体的に何を意味するのかは、この最判により確然とするところではありません(参照:上記判解同ページ、また参考:塩野同の注(2))。 また、職員の非財務会計行為(財務会計行為を行うに当たりその財務会計行為に関する権限を有しない職員の加担等を含む)での自治体への加害や第三者による談合等の不法行為によって生じた自治体の損害については、財務会計法規違反を論ずることなく、これらの者に対する損害賠償請求権等の行使を怠る事実を監査対象として請求すれば(下記ウのパターン)これらの責任追及は可能ですから、この領域については財務会計法規違反を前提とする意味はありません。 |
このポイントは、請求内容※※※が、実質的に次の要素を備えるかどうか、という点です。
○ 財務会計職員が行なった財務会計行為が存在し
○ 財務会計職員が、その財務会計行為を行うに際し、財務会計法規に違反し
○ その財務会計行為は違法なものとなった
○ そのことにより、自治体は財務会計職員等に対して、(実体法上の)請求権を有しているが、これを行使していない
|
【(実体法上の)請求権とは?(代表例)】 ・ 財務会計職員が、財務会計法規に反する違法な財務会計行為を行い、自治体に損害を与えた場合に、不法行為法【注1】により発生する損害賠償請求権 ・ このような違法で、かつ無効な【注2】財務会計行為がなされたことにより、財務会計行為の相手方(たとえば契約の相手方)に対して生じた不当利得返還請求権(たとえば自治体が民間の者に補助金交付決定をして補助金を交付した場合で、この補助金交付決定が無効であれば、補助金を受けた者は補助金を不当利得しており、自治体は返還請求権を有することになる) ※平成14年改正前の地方自治法242条の2第1項4号では、いわゆる4号住民訴訟の類型として、上記の損害賠償・不当利得返還請求のほか、財務会計行為(怠る事実)の相手方に対する原状回復、妨害排除請求があげられており、これも実体法上の請求権ということができます。なお現在の住民訴訟法制では原状回復、妨害排除請求は、いわゆる3号訴訟で訴求すべきものと整理されていますが、住民監査請求では一体的に請求権として監査を求められることが十分あり得ます。 注1 民法(および地方自治法243条の2の2(予算執行担当職員に対して適用))。 注2 最判平14.10.3に関する最高裁判解(平成14年度)p.765(高世三郎)は「当該職員が財務会計上の行為を行うについて要素の錯誤があったこと等により当該行為が無効となる場合に、当該行為の相手方に対する不当利得返還請求権及び原状回復請求権の行使を怠る事実をその対象とするものである場合についても、(地方自治法242条2)項の適用があると考えられる(財務会計上の行為が無効となる以上、このように考えざるを得ないであろう)」※としています。財務会計行為の無効が財務会計職員の介在を前提とする地方自治法242条1、2項の規定からすれば、あからさまな財務会計法規の明文違反(たとえば随意契約規定違反)のほかにも、このような無効原因も含み得るとすることは合理的見解であり、その点からすれば、財務会計行為の相手方に対する請求権を怠る事実が不真正怠る事実となるのは、財務会計職員の行為に起因して無効原因が生じたと、幅広くとらえることが適当であるということになります(ただし、下記※の現状からすれば、財務会計法規の規律外で財務会計職員の行為に起因する無効というのは、およそ考えづらいところではあります(無効原因が財務会計職員に起因しないものではないケースは、業者談合(公序違反)など現実的に考え得るところですが))。 ※ 本判解は、民法上の錯誤(同法95条)を法律行為の無効原因としていますが、その後の民法改正により現在は取消し原因に変更されています。また、平成14年地方自治法改正に伴い、4号訴訟で原状回復請求権の行使を求めることはできなくなっています(3号訴訟で対応に変更)。 |
| ※※※ この判断においては、「請求内容」を具体的にどのようなものと解釈整理するかにより、判断が定まることになります。 ところで、「何を請求内容としての監査対象事項とするのか」、つまり対象事項に何を選択するのかは、請求人の任意の選択により決定されますが(民事訴訟の処分権主義と同じ考え方であり、この選択行為に監査委員の裁量が入る余地はありませんし、請求人には、住民監査請求提起時において、監査対象財務会計行為等を特定摘示する義務があります)、その請求内容が真正怠る事実か不真正怠る事実かの具体的な解釈判断は、監査委員において、請求人が何を対象として取り上げたのか,請求書の記載内容,添付書面等に照らして客観的,実質的に判断すべきもの、とされています(参照:最判平14.7.2民集56.6.1049。なお参考:東京地判平11.1.28判例時報1693.39は「監査請求期間の制限が及ぶか否かは、怠る事実の内容に関する客観的解釈の問題であり、当事者の法律構成により別異に解釈すべきものではない」とする。ただし本件は最判平14.7.18集民206.887の一審であり、事案内容および上告審の結論は上記最判平14.7.2民集56.6.1049と概ね同旨であるが、本東京地裁判決は、業者談合による業者への損害賠償請求を怠る事実を不真正怠る事実と結論しており、最高裁判断とは結果として結論が異なる点に注意。同様に上記平成14年7月最判以前の、談合事案を不真正怠る事実とするケースではあるが津地判平10.8.20判例時報1694.83も「当該監査請求が「不真正怠る事実」を対象とするものであるか否かは、当事者の法律構成にとらわれず、客観的にみて、当該監査請求が財務会計行為の違法無効を前提としているものか否かによって判断されるべき」とする。これらの判断基準は上記最判と平仄が合うものですが、平成14年最判以前の時点では、自治体部外者の談合等不法行為による、財務会計行為を媒介とした自治体への加害に対し、これによる損害賠償等請求権行使を怠る事実を、不真正怠る事実とするか真正怠る事実とするかについての判断基準が明瞭とはいえない状態であったために、上記の概念定立部分はともかく、判断の結論部分は結果として、平成14年最判と異なるものとなってしまったということになります。前記各裁判例については、参考:平14.7.12最高裁判解平14年度p.517以下(大橋寛明))。 |
【怠る事実が監査対象の場合の監査請求期間適用の検討フロー】
| 監査対象を「怠る事実」とする請求 |
| 【原則】 監査請求期間制限の適用なし (最判昭53.6.23集民124.145) その上で下記について検討 |
⇓
| 条 件 | 監査請求期間の扱い |
|
請求内容が次のいずれにも当てはまるもの ○ 財務会計行為が違法であることを前提としている 例えば ・ 財務会計職員に対する、違法な財務会計行為を行なったことによる損害賠償請求権※ |
監査請求期間制限の適用あり |
| 【原則(下記以外):下記イ①】 その財務会計行為があった(終わった)日が起算日(最判昭62.2.20民集41.1.122) |
|
| 【特例:下記イ②】 財務会計行為があった(終わった)時点で、左記請求権が未発生か権利行使不能・・・請求権が発生した・権利行使可能となった日が起算日(最判平9.1.28民集51.1.287) |
|
| 請求内容が次のいずれかに当てはまるもの
○ 監査対象の怠る事実の対象である請求権が消滅している(怠る事実が終わっている) |
監査請求期間制限の適用あり【下記イ③】 起算日は、左記の上の○にかかる怠る事実が終わった日(最判平19.4.24民集61.3.1153) |
⇓
| 【ただし】 上の「原則適用なし」の表に当てはまるケースで、かつ次のすべてに該当 ○ 損害賠償等を求める相手が、問題の財務会計行為に関する財務会計職員ではない(自治体の部外者や、自治体職員でもその財務会計行為を行う権限と関係のない立場の者) |
| 監査請求期間制限の適用なし【下記ウ】 (最判平14.7.2民集56.6.1049 確認的なものとして最判平14.10.3民集56.8.1611) |
| ※ 地方自治法242条の2第1項4号による住民訴訟(いわゆる4号訴訟)の場合、怠る事実の相手方(職員もあり得るし補助金交付先や契約相手方等の第三者もあり得る)へ求める請求内容は、同号の規定により損害賠償請求か不当利得返還請求に限定されていますが、住民監査請求の場合は、請求人はいかなる措置を求めても構いませんので、「等」としています(なお、監査委員はその請求内容に拘束されません。最判平10.7.3集民189.1および「4 請求において求める措置」参照。 |
| ※※ これはあくまでも、上記の条件により財務会計行為が無効となることによる、財務会計行為の相手方に対して自治体に生ずる(例示としての)不当利得返還請求権(上記の「【(実体法上の)請求権とは?】」のカコミ参照)であり、この請求権の発生原因には、財務会計行為の相手方の帰責事由は要求されていません(相手方の行為がどうかではなく、財務会計職員の違法な財務会計行為により財務会計行為が無効となったことが要件)。つまり、財務会計行為の相手方の行為に起因して生じる自治体の請求権(例:業者談合を通じた契約により自治体に生ずる損害賠償請求権)ではありません。そのようなケースについては、下記ウ参照。 |
イ 監査請求期間制限が適用される「怠る事実」の具体パターン
① 財務会計職員による財務会計行為の違法等により生ずる請求権の行使を怠る場合
財務会計職員の行なった、その自治体の財務会計行為が、財務会計法規に違反した違法、無効なものであり、そのことに基づいて発生する実体法上の請求権を自治体が行使しないことに対して、これを財産の管理を怠る事実として監査対象とする住民監査請求においては、この財務会計上行為のあった(終わった)日を基準として、監査請求期間制限(地方自治法242条2項)が適用されます(最判昭62.2.20民集41.1.122)※1、※2。
| 【上記昭和62年最判】
普通地方公共団体において違法に財産の管理を怠る事実があるとして(地方自治)法242条1項の規定による住民監査請求があった場合に、右監査請求が、当該普通地方公共団体の長その他の財務会計職員の特定の財務会計上の行為を違法であるとし、当該行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実としているものであるときは、当該監査請求については、右怠る事実に係る請求権の発生原因たる当該行為のあった日又は終わった日を基準として同条2項の規定を適用すべきものと解するのが相当である。けだし、法242条2項の規定により、当該行為のあった日又は終わった日から1年を経過した後にされた監査請求は不適法とされ、当該行為の違法是正等の措置を請求することができないものとしているにもかかわらず、監査請求の対象を当該行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使という怠る事実として構成することにより同項の定める監査請求期間の制限を受けずに当該行為の違法是正等の措置を請求し得るものとすれば、法が同項の規定により監査請求に期間制限を設けた趣旨が没却されるものといわざるを得ないからである。 |
上記アの説明と重畳しますが、模式的にいえば、次の要件を満たす請求は、怠る事実を監査対象とする請求であっても、監査請求期間の制限が適用されることになります。
○ 財務会計職員が財務会計法規に違反する違法なものであり
○ これにより行われた財務会計行為が違法、無効であることにより自治体について生じた
○ 次の請求権の行使を怠る事実を監査対象としている
・ その財務会計職員が違法な財務会計行為を行い自治体に損害を与えたことに対する、当該職員に対する※3損害賠償請求権等の行使
・ 財務会計行為が違法であるにとどまらず無効であることにより発生する、財務会計行為の相手方に対する不当利得返還請求権等の行使※4、※5
これを端的にいえば、監査対象とされる怠る事実および請求内容は、ある財務会計行為が違法(無効)であり、その損害補てん等の措置を求める請求内容に置き換えられるか、ということになります(上記アのように、等価的な請求であるがゆえに、監査請求期間の制限も同様に適用すべきという考えが成立するということです)。
| ※1 ここでいう「財務会計行為」は、支出負担行為や支出命令、現実の支出といった財務会計行為そのもののほか、一定の条件下での違法な財務会計行為の準備行為(たとえばその財務会計行為を行うため必要な予算案の作成等)も含まれます(最判平14.10.3民集56.8.1611)。 いうまでもなく、予算案作成行為は、地方自治法242条1項所定の財務会計行為のいずれの類型にも該当しないので、それ自体を単独で住民監査請求の対象とすることはできません。ここで取り上げる本平成14年最判は、違法な財務会計行為を行った財務会計職員の前任財務会計職員が、違法な財務会計行為(官製談合による契約)のための準備行為としての予算案作成を行い、その前任財務会計職員に対する自治体の損害賠償請求権の行使を怠る事実を監査対象とする住民監査請求が提起された場合において、その前任財務会計職員に対して監査請求期間制限が適用されるかどうか、という点に関する判断です(予算案作成が住民監査請求の対象たる財務会計行為かどうかにかかわらず、官製談合のための予算案を作成する行為は自治体に対する不法行為を形成し得るので、その職員に対する損害賠償請求を怠る事実について住民が住民監査請求を通じて訴求すること自体は、予算案作成行為の財務会計行為性有無にかかわらず可能である)。下記エ参照。 |
| ※2 なお叙上と重畳しますが、ここでいう「財務会計行為の違法」は、財務会計職員が財務会計法規に反して行い、これにより違法性を持つに至ったものに限られます(最判平14.7.2民集56.6.1049)。 つまり、財務会計職員が行なった財務会計行為が財務会計法規に照らして違法の評価を受けない場合に、その財務会計行為に起因する損害賠償等の請求権の行使を怠る事実を監査対象とする場合(たとえば財務会計職員は適正な手続で財務会計行為を行なったが、実際は契約相手先の談合により違法な価格形成となっていたような場合、自治体にはその権利法益侵害行為によって損害が生じますが、財務会計職員の行為で生じたわけではありませんので、財務会計職員が行なった財務会計行為が財務会計法規に照らして違法の評価を受けるわけではありません)昭和62年最判の示す監査請求期間制限の規定は適用されない、つまりその財務会計行為がなされた(終わった)日から1年以上経過していても、その請求は監査請求期間制限違反のため不適法な請求と評価されることはない、ということになります。 なお、地方自治法242条1項で「当該普通地方公共団体の長・・・又は・・・職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある・・・と認めるとき」とあり、同条2項が「前項の規定による請求」について監査請求期間の制限を設けていることに留意が必要です。 以上の点については、下記ウで詳述します。 |
| ※3 権限ある職員(財務会計職員)の補助行為をする職員(たとえば専決権者の、その財務会計行為に関するライン上の部下)に対する損害賠償請求権等の行使を怠る事実についても、財務会計職員との一体性があるため、同じ結論となります(最判平14.10.3民集56.8.1611)。財務会計職員と同義的である地方自治法242条の2第1項4号の「当該職員」について「その適否が問題とされている財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有するものとされている者及びこれらの者から権限の委任を受けるなどして右権限を有するに至った者を広く意味」(最判昭62.4.10民集41.3.239)との定義とも平仄が合います。
【注】 補助職員がその財務会計行為に関するライン上の部下に概ね相当するということは、財務会計職員の直接の部下であっても、「その財務会計行為」のライン上になければ、その財務会計行為に関して業務上の関与関係が見出せない限り、ここでの補助行為をする職員にはならないことになります。 |
| ※4 本件昭和62年最判は「財務会計職員の特定の財務会計上の行為を違法であるとし、当該行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権・・・」としますが、上記アの【(実体法上の)請求権とは?】注2の通り、財務会計行為が無効となる原因は、財務会計職員の行為に起因して、といった幅広な理解の方がよいとも解されます(当時の民法規定によれば要素の錯誤は法律行為の無効原因だったのでこのような説明になっています)。 |
| ※5 この請求権については、財務会計行為の相手方(この場合は、財務会計職員が自らの利得を図ったことによる財務会計職員への不当利得返還請求権ではなく、自治体からすれば第三者への不当利得返還請求権等を想定している。財務会計職員の自己利得問題は、当該職員への損害賠償請求権『等』に含まれている)の行為には財務会計行為の違法無効原因がないことを想定しています。たとえば違法な給与条例に基づく給与支給(公金の支出)のようなものです。財務会計行為の相手方に違法原因がある場合については、上記※2の通りです。 また、本件昭和62年最判で「財務会計職員の特定の財務会計上の行為を違法であるとし、当該行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権」とされるところ、この「違法・無効」の意味合い及びどのような場面で「無効」が意味をもつのかについては、上記の仕分けにより整理されることとなります。 |
たとえば、次に掲げる請求権行使を怠るとしてなされる住民監査請求は(その契約締結や給与支給決定自体を監査対象とすることもできることから、これら内容の住民監査請求の場合と同様)上記契約締結や給与支給決定の日から監査請求期間が起算され、契約日から1年を経過した場合、正当な理由がない限り、もはや監査請求はできない、ということになります※6、※7。
○ 財務会計行為を行う権限のある職員が、競争入札ルール(財務会計法規)に違反していることを承知で、契約を締結(違法な財務会計行為)し、自治体が損害を被る場合のその財務会計職員に対する損害賠償請求権の行使
○ 首長が、法令に違反する給与条例に基づき給与を支給決定した場合の(無効な財務会計行為たる公金の支出)、給与を支給された職員に対する不当利得返還請求権の行使
いずれにしてもここでのポイントは、「財務会計職員の行為のために、その財務会計行為が違法(無効)となった」という要素が存在する(必須である)ことです。
| ※6 行政訴訟においては、違法な処分の取消しを求める取消訴訟の場合は出訴期間制限がありますが(行政事件訴訟法14条)、無効な処分についての無効確認を求める訴訟については出訴期間の制限がありません。 しかしながら住民監査請求においては、財務会計職員による違法な財務会計行為を対象とする以上は、対象とする財務会計行為が当初から無効なものであるのか、単に取り消しできるものであるに過ぎない(当初から無効とはいえない)かによって、監査請求期間の制限の適用が変わる(無効な財務会計行為であれば監査請求期間の制限は適用されない)、ということは生じません(参照:碓井p.49は「契約の無効を前提とする損害の塡補を求める場合等も、当然に期間制限を受けるとされている」とする。なお同書で例示される裁判例は、最判平14.10.3民集56.8.1611の一・二審判決である)。 |
| ※7 上記(1)の例でも本件の例でも、何らかの行為((1)の例でいえば自動車による庁舎損壊事故、本例では(違法な)契約等)が先行・介在しています。 (1)の例と、本例の違いは、先行している行為が「財務会計職員の行なったその自治体の財務会計行為か」、という点です。いうまでもなく、自動車運転の誤りによる庁舎損壊行為は、それが誰の起こしたものであろうとそもそも財務会計行為ではありません。そして、自治体の請求権の発生原因が財務会計行為ではない以上、財務会計行為のあった(終わった)日を起算日と明確に定める地方自治法242条2項の適用のしようがありません。しかし本件の例の場合は、財務会計職員が財務会計法規に違反して締結した契約や違法な条例による給与支給決定という財務会計行為が請求権の原因となっており、そうであれば契約自体を監査対象として是正等の措置要求をするという住民監査請求の内容も取り得るものですし、その場合は地方自治法242条2項の適用を受けることになるのです。 |
これは叙上の通り、財務会計行為に権限を持つ職員に起因する(この点については、地方自治法242条1項が、住民監査請求の対象となり得る財務会計行為(怠る事実)について「当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について」としていることを想起しましょう)その財務会計行為の違法性を問題とせざるを得ない以上は、監査対象を怠る事実としていても、実質的には、当該職員によりなされたその財務会計行為の財務会計法規上の違法性を直接問い、その財務会計行為の是正や損害の補てんを求める請求と何ら変わるところがないこととなるため、単に「怠る事実」を監査対象と外形的に作文することにより監査請求期間の制限が適用されなくなるとすれば、財務会計行為に対する監査請求期間の制限を設けた制度的な意味がなくなるからです※8、※9。
| ※8 本件昭和62年最判によれば、ある財務会計行為の違法不当について是正を求める住民監査請求は、特段の事情がない限り、その財務会計行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使を違法、不当とする財産の管理を怠る事実についての監査請求をもその対象として含むものと解すべきものとしており、その結果として、同一住民が同一の財務会計行為について、財務会計行為の是正を求める請求を起こした場合に、さらにその後その財務会計行為の違法無効を前提とする損害賠償(不当利得)請求を怠る事実の是正を求める住民監査請求を提起しても、後者の請求は不適法とされることとなります。一方で、前者の住民監査請求を提起した請求人が、住民訴訟において怠る事実に基づく4号訴訟を提起することは、当該財務会計行為等についての住民監査請求前置要件を満たしていることから、適法となります。また住民監査請求の請求内容をどちら(財務会計行為の是正を求めるか、それにより生ずる請求権行使を怠る事実の是正を求めるか)にせよ、監査請求期間制限の適用内容は変わりません。 |
| ※9 以上に関する一つの参考として、宇都宮地判平10.5.14判例時報1670.12の事例を見てみます。 本事例は、A年度は課税後減免、B年度以降は課税免除(地方税法6条1項)の内容を包括していますが、A年度分は町長による債権放棄(地方自治法242条1項の財産の処分)の違法性を問うことに等しいから監査請求期間制限の適用あり、B年度以降は(そもそも租税債権が発生しておらず)真正怠る事実として監査請求期間の制限適用なし、としており、真正怠る事実と不真正怠る事実のわかりやすい区分例として参考となるものと考えます。 |
② ①の場合における監査請求期間起算日算定の特例ケース
上記①に該当するケースで、行使を怠るとされる請求権が、財務会計行為のされた時点ではいまだ発生していないか、これを行使することができない場合には、実体法上の請求権が発生し、これを行使することができることになった日を基準として地方自治法242条2項の規定を適用することになります(監査請求期間の起算日の特例。最判平9.1.28民集51.1.287※1、2)。
| 【上記平成9年最判】
・・・財務会計上の行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実とする住民監査請求において、右請求権が右財務会計上の行為のされた時点においてはいまだ発生しておらず、又はこれを行使することができない場合には、右実体法上の請求権が発生し、これを行使することができることになった日を基準として同項の規定を適用すべきものと解するのが相当である。 |
| ※1 この事例は、転売禁止特約付きで自治体が買い受けた土地を自治体が転売(特約違反の財務会計行為)したが、その違約金の発生そのものに紛議がある(本事例は、違約金の発生自体が争われた結果、売主・自治体間の訴訟となり、被告自治体側は請求棄却を求める答弁をしたが、裁判上の和解で決着)場合は、転売により自治体が元の土地売却者に対して直ちに損害賠償責任を負うということができないため、上記昭和62年最判の法理をストレートに適用、つまり転売日に監査請求期間が起算されるということは事実上できず、上記判示の法理により監査請求期間ルールの整理を図った、というものです。本事例では、転売の後に自治体がその転売(特約違反)行為に対する賠償を支払うことが確定したことにより、賠償確定の日から監査請求期間が起算される(監査請求期間の起算が可能になるので)ことになります。 なお類似する要素を含む例として名古屋高(金沢支)判平14.4.15(カラ出張旅費財源の一部に国庫補助金が充当されていたため加算金込みの返還命令がなされたことに対する住民監査請求・住民訴訟につき、監査請求は国庫精算返還金の支出によって県に生じた損害の回復・是正、住民訴訟はその回復・是正をしないことの違法確認請求、すなわち国庫精算返還金の支出に基づいて発生したと主張する損害賠償請求権を知事が行使しないことの違法確認であり、本件監査請求も、同旨の趣旨を含むものと認めるのが相当である以上、これを敢えて旅費支出が違法無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって怠る事実と構成しているとみなす合理的根拠はなく、国庫返還の予算議決または実際の返還日を監査請求期間の起算日と認めた事例)、広島地判広島地判令4.3,30判例時報2565.5(国庫全額財源の市補助金を交付したが事業破綻等で市が国へ補助金を返還したところ、事業者から市への市補助金返還がなされない場合において、国への返還日を監査請求期間の起算日とした事例)。 |
| ※2 この平成9年最判と上記昭和62年最判の関係について、怠る事実を請求対象とする場合の監査請求期間制限は適用されない原則がまずあるが(昭和53年最判)、請求対象が不真正怠る事実である場合は昭和62年最判の法理が適用され、すすんで財務会計行為時点での請求権の発生ないしはその行使の可能性によって、平成9年最判の法理の適用の有無が問題となることとされています(参照:最判平14.7.2民集56.6.1049の最高裁判解(平成14年度)p.521(大橋寛明))。同じく上記アのフロー。 |
なお上記平成9年最判の事例は、自治体側が特約違反による違約金債務の成立自体を最後まで争っていたので、裁判上の和解の日から監査請求期間が起算されるとされましたが、仮に違約金債務の成立自体は争わず、その金額のみが争われた場合、(損害補てん措置要求の)住民監査請求は、自治体の被った損害額を特定することなく提起できる※3のですから(参照:最判平10.7.3集民189.1)監査請求期間の起算日は、転売の日または遅くとも自治体が損害賠償責任の成立を認めた日とすべきものと考えます※4。
| ※3 なお、監査委員が措置勧告する場合であっても、金額を特定明示する必要はありません。 ちなみに住民訴訟(4号訴訟)の場合は、民事訴訟の原則にのっとり、自治体が請求すべき相手先や賠償等の請求額を特定する必要があります(ただし、判例行政法p.138(石津廣司)は、大阪地判平20.10.31判例タイムズ1295.94において、住民が相当の注意力をもって調査を尽くしても相手方氏名等や請求額の具体数額を特定できない請求を例外的に適法とする事例を紹介する)。 |
| ※4 上記の平成9年最判判示の請求権が財務会計行為のされた時点ではいまだ発生していないか、これを行使することができない場合について、「財務会計上の行為がなされた時点で右請求権自体が法律上発生していない場合、又は、請求権自体は既に発生しているが、それを行使するについて法律上の障害若しくはこれと同視しうるような客観的な障害のある場合をいうと解するのが相当であって、財務会計上の行為がなされた時点で請求権自体は既に発生しているのに、地方公共団体の財務会計担当者が当該財務会計上の行為が違法であることを知らなかったために事実上右請求権の行使ができなかったにすぎない場合は含まれないと解するのが相当」と判断のうえ、談合事案について公正取引委員会の課徴金納付命令発表まで談合業者への請求権行使ができなかった(前記公取命令発表の日が監査請求期間の起算日となる)との原告主張について、その主張は、それまでは当該自治体においても業者の談合を知り得なかった、すなわち財務会計行為たる本件契約の締結が違法であることを知らなかったというにすぎない(平成9年最判事案は、自治体が買い取った土地の特約違反の転売に対する違約金請求について、違約金債務自体を自治体が否認し、自治体と土地売主間の裁判上の和解成立ではじめて自治体の損害(違約金)が具体化したが、本件では談合による契約の時点で自治体の損害は具体化している)として、上記原告主張(平成9年最判の法理が適用される)を排斥(なお、監査請求期間徒過の問題は、正当な理由の有無についての判断によって具体的妥当性(の確保)をはかることが可能)した事例があります(名古屋高(金沢支)判平10.4.22判例時報1671.50。ただし本件の上告審最判平14.7.2民集56.6.1049に注意)【注】。 監査請求期間制限制度が、早期の法的安定性確保のためのものであることからすれば、このように解すべきものと考えます。【注】 公正取引委員会の判断は権威あるものであるには違いありませんが、談合による損害賠償請求権は談合による自治体の法益侵害・損害発生時点で生ずるのであって公取判断の時点で生じるものではないこと、損害賠償請求権については公取の発する排除措置命令の確定を前提とする独占禁止法25条の規定はあるものの、この規定による損害賠償請求権と民法(不法行為法)の損害賠償請求権は排他的関係に立たないこと(以上については最判平元.12.8民集43.11.1259、また最判昭47.11.16民集26.9.1573参照。なお参考:最判平21.4.28集民230.609(談合業者に首長が損害賠償請求しないことが違法な怠る事実に当たるかについての事例))などが、上記判断を参照するうえで参考になります。 |
③ 怠る事実による請求権が消滅した場合
怠る事実を請求対象とする場合は、上記(1)にある通り、怠る事実が継続する間は住民監査請求を提起することができるのが原則です(監査請求期間の制限は適用されない)。
しかし、請求権行使を怠る事実があったが、その請求権が除斥期間経過により消滅するなど※1して怠る事実が終わった場合には、この「怠る事実が終わった日」を監査請求期間の起算日として監査請求期間制限ルールが適用され、怠る事実の終わった日から1年を経過したときはこの怠る事実を対象とする監査請求をすることができません※2。
またその帰結として、請求権の行使を怠り、除斥期間の経過により請求権を消滅させるなどしたことが違法であるとして怠る事実(「第1の怠る事実」)が違法であることに基づいて発生する実体法上の請求権(損害賠償請求権等)の不行使をもって財産の管理を怠る事実(「第2の怠る事実」)とした上で、第2の怠る事実を対象とする監査請求がされたとき※3は、第1の怠る事実の終わった日を基準として1年の監査請求期間の制限にかかることとされています(最判平19.4.24民集61.3.1153)。
| 【上記平成19年最判】
・・・財産の管理を怠る事実に係る実体法上の請求権が除斥期間の経過により消滅するなどして怠る事実が終わった場合には,継続的な財務会計上の行為の終わった日から1年を経過したときはこれを対象とする監査請求をすることができないのと同様に,怠る事実の終わった日から1年を経過したときはこれを対象とする監査請求をすることができないものと解するのが相当である。また,上記の場合において,上記請求権の行使を怠り,同請求権を除斥期間の経過により消滅させるなどしたことが違法であるとし,当該怠る事実(以下「第1の怠る事実」という。)が違法であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実(以下「第2の怠る事実」という。)とした上で,第2の怠る事実を対象とする監査請求がされたときは,当該監査請求については,第1の怠る事実の終わった日を基準として1年の監査請求期間の制限に服するものと解するのが相当である。 |
| ※1 ここでは除斥期間経過による請求権消滅が原因として示されていますが、下記に示す本判決の趣意を考慮すれば、除斥期間以外の理由(時効等)で請求権が消滅する場合も含まれるべきと考えます。なお参照:実務住民訴訟p.44。 一方で、自治体側の何らかの積極的な行為(例:新たに債権放棄の約定を締結)により請求権が消滅した場合は、その行為自体が独立した財務会計行為(財産の処分)となるので、その行為に対しての監査請求期間を考えればよいこととなるのは、いうまでもないことです。 |
| ※2 本件平成19年最判は、自治体の発注した道路工事に不備があったのに、町が補修請求に代わる損害賠償請求を怠り、工事請負契約中の所定の期間を経過して損害賠償請求権が消滅した、という事例です。 |
| ※3 本平成19年最判事案は、上記※2の請求権消滅から1年以上経ってから、瑕疵の修補に代わる損害賠償請求権の行使を怠り同請求権を除斥期間の経過により消滅させたことを違法であるとして、この怠る事実が違法であることに基づいて発生する実体法上の請求権の権利者である町の、町長に対する前記損害賠償請求権の不行使を財産の管理を怠る事実として監査対象とする住民監査請求を提起したというものであり、最高裁は、上記の法理により、本件請求を監査請求期間経過により不適法な請求と判断したものです。 |
これは、早期の法的安定確保という監査請求期間制限制度の趣旨は、このような事例でも適用されるべきであり、かつ継続的財務会計行為の終わった日から1年を経過したときは、監査請求期間制限により適法な監査請求ができなくなることと、なんら事情が変わらないためと、上記平成19年最判で説明されています(また、本件事例のように請求権を除斥期間経過で消滅させることは、自ら債権の放棄・免除(地方自治法242条1項の財産の処分であり、同項の財務会計行為となる)を行うに類する行為であり、これらの処分行為に対する監査請求期間制限に準じて考えるべきともいえます)。
つまり、監査対象としての怠る事実は、監査請求期間の論点で考えれば、いわば継続的財務会計行為(その行為が終わるまでは、監査請求期間は起算されない=その行為(状態)継続の限りいつでも住民監査請求はできる)と同じものであり、それゆえこのような結論に至る、ということです。
ウ イに類似するが監査請求期間制限が適用されないパターン
怠る事実を監査対象とする請求であって、上記イに類似するが、怠る事実の場合の監査請求期間の原則ルールに立ちかえり、監査請求期間の制限が適用されないパターンがあります。
これは、監査請求期間制限ルールが、財務会計職員の違法な財務会計行為に対して適用されるという前提の反対解釈として、実質的に監査対象となる財務会計行為を媒介して生じる自治体の請求権が、財務会計職員の行為に起因しない、つまり、自治体が請求権行使を怠る相手方が、財務会計職員ではない※場合です(最判平14.7.2民集56.6.1049)。
| ※ 上記イ①昭和62年最判のパターンでは、財務会計職員の行なった財務会計行為が違法であるのみならず無効であり、その結果生じる財務会計行為の相手方に対する不当利得返還請求権等の行使を怠る事実も、監査請求期間制限の対象に含まれることとなりますが、本項で説明するパターンには、当然ながらこうした事例は(怠る事実の相手方が自治体外の第三者であるというだけでは)該当しません。 |
上記平成14年7月最判は、業者の談合による高値落札契約について、当該業者への損害賠償請求を怠る事実を対象とする請求であり、財務会計行為が介在して自治体に損害が生じていること、怠る事実を監査対象として請求している点、不真正怠る事実と同様にも見える事例内容です。
ところが同最判では、監査委員が怠る事実の監査を遂げるためには、特定の財務会計上の行為の存否、内容等について検討しなければならないとしても、その財務会計行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはない場合には、これをしなければならない関係にあった上記イ①(昭和62年最判)の場合と異なり、当該怠る事実を対象としてされた監査請求には、監査請求期間の制限は適用されない、と判断しています。
| 【上記平成14年7月最判】
・・・監査委員が怠る事実の監査を遂げるためには,特定の財務会計上の行為の存否,内容等について検討しなければならないとしても,当該行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはない場合には,これをしなければならない関係にあった上記第二小法廷判決(注:最判昭62.2.20民集41.1.122)の場合と異なり,当該怠る事実を対象としてされた監査請求は,本件規定の趣旨を没却するものとはいえず,これに本件規定を適用すべきものではない。 |
このロジックを、もう少し分析的に整理すると、次のような内容となります。
(a) 監査委員は、契約が締結された事実、そしてその契約額が不当に高額だったかを検討する必要は(当然)ある
(b) この請求内容によれば、財務会計職員の行なった契約締結(行為)やその代金額の決定が財務会計法規に違反する違法なものであったとされて、初めて自治体の談合業者に対する損害賠償請求権が発生するものではない
(c) 業者間の談合があり、これに基づく落札業者の入札および自治体との契約締結が不法行為法上違法の評価を受けるものであること、これにより自治体に損害が発生したことなどを確定しさえすれば、監査は可能(上記(b)の点を監査で判断しなくても、本件住民監査請求の結論、すなわちこれらの業者に損害賠償請求を怠っている事実があるか、その損害の補てんを要求する措置を首長に勧告すべきか、という結論は出る)
(d) つまり、本件監査請求は、財務会計職員が財務会計法規に違反して違法な財務会計行為を行なったかどうか(=地方自治法242条2項の前提条件:上記イ①参照)は論点ではないのであり、上記イ①のパターンとは異なるもの。本件に地方自治法242条2項の監査請求期間制限は適用されない
これをさらに分解すれば
(a) この点は、談合による高値入札に基づく(違法不当な)契約締結を監査対象としている以上、当然のことです
(b) この判示内容は正直わかりにくいので、ざっくりと内容を整理してみます。
上記イ①昭和62年最判のケースでは「財務会計職員の行なった違法な(本件平成14年最判の判示内容にそくして言えば「財務会計法規に違反して違法」な)財務会計行為」が問題の中心にあり、この財務会計行為で自治体がこうむった損害の賠償請求をしないことを怠る点を監査対象とするのは、問題の中心である、財務会計職員が財務会計法規に違反して行なった違法な財務会計行為を直接の監査対象とすることと、実質的には変わらない、としています。
一方、本件平成14年最判では、その財務会計行為を行う権限の外にいる者(本例では自治体外の第三者であり、当然ながら財務会計行為を行う権限はない者)の自治体に対する権利法益侵害行為によって、その財務会計行為を通じて自治体に損害を与えています。
つまり、本件平成14年最判のパターンでは、財務会計職員の財務会計法規上の違法が論点ではなく(本件最判の判示内容にそくしていえば、特定の財務会計行為の存否、内容等の検討は必要だが、その財務会計行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはない)、自治体にとっての第三者である関係業者による談合、そして談合に基づく高値落札が問題となっているわけです(自動車を故意に庁舎にぶつけて自治体に損害を加えたという上記(1)の事例の自治体への加害手段としての自動車運転が、本事例ではたまたま財務会計行為たる契約(とその履行による公金の支出)という手段によっている、と考えればよいでしょう)※1。
| ※1 既述の事項ですが、地方自治法242条1項の法文からも明らかな通り、住民監査請求制度においては、監査対象となる行為は、その財務会計行為を行う権限を法令上本来的に有する者およびこれらの者から権限の委任を受けるなどして上記権限を有することとなった者が行ったものに限られているという大前提があること(参照:最判昭62.4.10民集41.3.239)を想起しましょう。 上述地方自治法242条1項では「当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出・・・がある・・・と認めるとき」と定めています。さらにいえば、自治体に損害を与える公金支出等の財務会計行為があるとしても、それが「普通地方公共団体の長・・・又は当該普通公共団体の職員について」でなければ、その行為による損害の是正を直接求めるという内容(地方自治法242条1項の前半部分)の住民監査請求の対象とはなり得ないものとなります。 つまり、契約相手方の談合(不法行為)のために財務会計行為を通じて自治体に損害を与えているとしても、その者が財務会計行為について権限を有する職員でない以上、監査請求期間制限の対象となる「違法不当な財務会計行為の是正やそれによる損害補てんを求める請求」には該当しないことになります。 |
(c) ということは、本事例では、財務会計職員による財務会計法規違反の財務会計行為の実行かということは、監査において問題にはならず※2、業者の談合事実、その結果としての違法不当な高値落札と自治体への損害発生という点の事実存否や法的評価について審査すれば、監査の目的は達成できる((a)の要素は、この審査事項に当然含まれる)ことになります。
| ※2 実際の監査実務では、財務会計職員の財務会計行為(のプロセス)に違法不当(外部第三者の違法行為への加担や過失・重過失(参照:地方自治法243条の2の8)による見逃しなど)がないか、といった審査は、事実関係が最初から明らかな場合を除き、当然必要でしょう。 |
d) 要するに、上記イ①のように、その自治体の首長その他の財務会計職員により行われた特定の財務会計行為が、財務会計法規に違反して違法かどうかが問題とならない以上、地方自治法242条2項の要件に合致するものではなく、よってイ①のルールを適用する理由はない、すなわち監査請求期間の制限はない、ということになります※3、※4。
| ※3 以上によれば、財務会計行為の「違法」とは、(財務会計職員による)財務会計法規違反を意味するのであって、それ以外の違法問題、例えばその財務会計行為が不法行為法上の違法評価を受けるかどうかではない、ということになります(上記ア※※、本件平成14年最判に関する最高裁判解平成14年度p.526(大橋寛明)参照)。 |
| ※4 本件平成14年最判は、次の点を明示していることにも留意すべきです。 ・ 真正怠る事実か不真正怠る事実かの判断は、何が実質的な監査対象なのかによって判断されるところ、監査請求の対象として何を取り上げるかは、基本的には請求をする住民の選択に係るものであるが、具体的な監査請求の対象は、当該監査請求において請求人が何を対象として取り上げたのかを、請求書の記載内容、添付書面等に照らして客観的、実質的に(監査委員が)判断すべきもの ・ 怠る事実を監査対象とする場合は、監査請求期間の制限がないことが原則であり、②のルールは例外ルールであること |
これを総括していえば、
○ 地方自治法242条1項の「違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実・・・があると認めるとき」、つまり対象が怠る事実であるときは、原則として、監査請求期間の制限はない(昭和53年最判の法理)
○ しかし、地方自治法242条1項所定の「当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担があると認めるとき」、つまり請求における監査対象については、財務会計職員が財務会計法規に違反した結果、その行なった財務会計行為が違法かどうかが実質的な問題となるときは、結局その財務会計行為の違法性を摘示して所要の措置を求める請求内容と変わるところがなく、そのような請求には監査請求期間制限の適用がある以上、上記のような内容の怠る事実を対象とする請求は、同様に監査請求期間の制限がある(昭和62年最判の法理)
ということを前提とすれば、
○ 財務会計職員でない者の行為の結果として、財務会計行為を通じて自治体に損害が生じた場合は、監査請求期間制限の適用はない(本件平成14年最判の判断)
ということになります。
エ 上記の監査請求期間ルールが複合した実例
自治体部内・部外の者双方、かつ自治体内部でも対象財務会計行為についての権限関係が異なる者が行為に関与した事例として、最判平14.10.3民集56.8.1611をみてみます。
この事例は、上記の各監査請求期間ルールのパターンをどのように当てはめるのかという理解を深める上では、適切な事案と考えます(事案内容自体は相当込み入ったものであり、論点も多岐にわたりますが、本稿の説明に必要な範囲で類型化します)。
本事例の監査請求の内容は、原告の主張によれば、県の公共工事の変更契約による増額支出において違法な金額水増しが行われており、受注企業(JV)側のほか発注自治体側の関係者(議員、知事、副知事、直接の担当である建築担当部の職員、担当部ではない総務部の職員)が関与していた、とするものです(いわゆる官製談合事件(のようなもの))。
つまり違法な財務会計行為について、自治体からみれば第三者(受注企業)のほか、自治体の職員も関与しており、このうちには、本件契約の担当権限のある財務会計職員(担当部の部長)やその業務ラインの管下職員(担当課長等)も、本件財務会計行為にかかる財務会計職員とはいいがたい者(議員、公共工事契約の財務会計行為の意思決定とは異なるラインにある総務部の職員)も関与している、という構図の請求内容となっています。
ところで本判決で明示される通り、ある財務会計行為が財務会計職員およびそれ以外の者双方の行為の複合により違法性を帯びる場合において怠る事実を監査対象とする住民監査請求(上記イとウの複合パターン)における監査請求期間制限の適用関係については、あくまでも叙上の各原則の通り、その請求権行使を怠るとされる相手方(財務会計職員、その他の職員、部外第三者)が、問題となる財務会計行為についてどのような法令・規程上の権限をもつかによって判断されることとなります。つまり単純に、財務会計職員のみに違法がある場合(上記イのパターン)、または外部第三者にのみ違法がある場合(同ウのパターン)ではなく、これらが複合する形態の場合においても、監査請求期間制限については叙上の原則に基づく(要するに、請求権行使を怠るとされる相手方別に)判断がなされるのであり、たとえば外部第三者の違法行為についての請求権行使を怠る事実に対する請求について監査請求期間制限が適用されないこと(上記ウのパターン)については、その事案について同時に財務会計職員の財務会計法規違反行為があることにより(上記イ)その判断は左右されない、ということとなります。
ということはこのような場合においては、同一事案について、請求権行使を怠る相手方によって、監査請求期間制限の適用の有無が分かれる結果となります。
【本件最判による請求の相手先ごとの最高裁の判断】
下表表頭①「財務会計職員か」・・・本件住民監査請求において、損害賠償請求の対象者は、問題の財務会計行為について財務会計職員といえるか(財務会計行為についての権限を持つ者か・・・上記イ①昭和62年最判当てはめの前提)
下表表頭②「監査請求期間制限の適用」・・・本件住民監査請求において、自治体が損害賠償請求権行使を怠る事実の相手先とされる者にかかる、その怠る事実は、真正怠る事実であり、監査請求期間制限の適用なし(上記(1)昭和53年最判適用)か、不真正怠る事実であり、制限の適用あり(上記イ①昭和62年最判当てはめ)か
★ 要旨中の「当該職員」・・・地方自治法242条の2第1項4号(当時の規定)の「当該職員」(叙上の通り、財務会計職員とこの場合は同義)。したがって、当該職員(財務会計職員)であることが否定されているということは、住民訴訟において「当該職員」に対するものとしてなされた損害賠償請求(その財務会計行為について権限のある職員として、その違法な財務会計行為を行ったことに対して、当時の地方自治法242条の2第1項4号で損害賠償を原告が自治体に代位して直接する請求)が法的主張として成立しないことを意味する
| 請求で対象とされた者 | ①財務会計職員か | ②監査請求期間制限の適用 | 判断の要旨 | |
| 自治体の職員 | 副知事 | × | なし | ・本契約締結権限の委任・専決権付与がされていない(「当該職員」そのものである建築部長の直接の職制上の上司であることは関係ない。あくまでも委任専決規程上の権限がないということ)ので、「当該職員」に対するものとしての損害賠償請求は不適法 ・怠る事実については、監査委員は、副知事が業者の不法行為(談合)に違法に荷担し、それが不法行為法上違法評価されるか、自治体に損害を与えたか等確定すれば足りる →監査請求期間制限適用なし【上記ア該当】 |
| 議員 | 判断なし | なし | ・怠る事実については、監査委員は、同議員が業者の不法行為(談合)に違法に荷担し、それが不法行為法上違法評価されるか、自治体に損害を与えたか等確定すれば足りる →監査請求期間制限適用なし【上記ア該当】
※ 副知事と異なり、執行機関の職員ではなく、かつ事案が純然たる執行機関内での予算執行(財務会計行為)の問題である以上、議員については「当該職員(財務会計職員)」かどうかの問題は生じ得ない |
|
| 前建築部長 | × | あり | ・本契約締結時点で建築部長の職になく、「当該職員」に対するものとしての損害賠償請求は不適法 ・怠る事実については、前部長が部長(財務会計職員)当時に行った違法な予算案作成行為は、(財務会計職員としての)違法な財務会計行為と一体をなす → 監査請求期間制限適用あり【上記イ①(※1)該当】 |
|
| 建築部の幹部職員 (部技監、課長、部建設専門監) |
× | あり | ・対象財務会計行為(工事請負契約締結決定)について委任決裁規程上の権限はないので財務会計職員には該当しない ・怠る事実については、財務会計職員の補助をする職員の違法な補助行為は、財務会計職員の違法な財務会計行為と一体をなす → 監査請求期間制限適用あり【上記イ①(※3)該当】 |
|
| 総務部次長 | × | 当審では判断未確定 | ・財務会計職員には該当しない(副知事と同じ) ・怠る事実については、職制上建築部長を補助する職員ではなく、その行為が変更契約締結に関する事務を補助する行為(その職制上、知事の予算調製・議会提出行為の補助に当たると推測)に当たると認めるべき特段の事情もいまだ確定されていない【注】【注】こうした事情は、事実認定の問題であり、法律審である上告審では、その点は審理されません。差戻審で改めて審理され、必要な事実認定がなされることとなります。 |
|
| 第三者 | 談合したJV会社 | なし | ・怠る事実については、監査委員は、これら会社が談合による水増し請求をしたか、不法行為法上違法評価されるか、自治体に損害を与えたか等確定すれば足りる ・自治体の関係職員が違法な財務会計行為の実行に関与していることは、この判断を左右しない → 監査請求期間制限適用なし【上記ア該当】 |
【注】 本訴訟では、県知事、契約時の建築部長も被告となっているが、これらの者に対する請求を却下した原審判断を最高裁は維持している(上記表は、最高裁が各被告のうち特段の判断を示したもののみの表である)。なお談合した会社についての判断は上記ウ(最判平14.7.2民集56.6.1049)と同内容であるが、本件は前記7月2日最判の3か月後の判決であり、それより前に判決がなされた原審の判断はこれと異なる結論(監査請求期間制限適用あり)であって、これに対して上告受理申立てがなされており、本判決の論旨によれば、この部分に関する原判決を破棄する必要があるため、上記7月2日判決と同内容の判旨を判示したものである。
本件事例に対する最高裁の判断(上表)をまとめれば、財務会計行為たる契約締結についての権限ラインにない副知事およびそもそも執行機関の職員ではない議員(総務部次長も、財務会計職員の補助職員に準じる事情が認められなければここに含む)に対して損害賠償請求を怠る事実は、真正怠る事実と認め、監査請求期間の制限が適用されない、としたことになります※、※※。
なお本件請求においては、受注企業を怠る事実の相手方とするほか、損害賠償請求を怠る事実の相手方とされる自治体職員は、知事や建築部長なども含まれていますが、原審(一審含む)は、請求全体を不適法として却下する判断を示しており、最高裁は、これら被告のうち受注企業側および副知事等についての原審判断を覆し(これらの者は真正怠る事実の相手方であり監査請求期間の制限は適用されない)、その他の者の判断(不真正怠る事実)は維持しているので、結局職員側については、財務会計行為の権限がある者(財務会計職員)やその準備・補助行為をする者(知事や建築部長、建築部幹部職員等)に対する損害賠償請求を怠る事実は不真正怠る事実、それ以外の者(副知事、議員。場合により総務部次長)に対するそれは真正怠る事実、ということになります。
| ※ 類似の判断事例として、大津地判平22.7.1判例タイムズ1342.142。 |
| ※※ これと一見整合しない判断の事例として、函館地判平17.6.16。町長・助役・担当課長が関与して、落札業者を指名する「本命割付」を行い、これに基づき業者談合が行われた事例において、町長以外の職員への賠償請求を怠る事実を真正怠る行為(監査請求期間の制限なし)と判断(町長は死亡により訴え取下げ)。理由として、監査請求の対象は、町長の本命割付および業者の談合による損害賠償請求権を怠る事実であり、町の契約締結やその代金額の決定が財務会計法規に違反する違法なものであったとされて初めて町の本件債務者らに対する損害賠償請求権が発生するものではなく、町長による本命割付、指名業者間の談合行為、これに基づく落札業者の入札及び町との契約締結が不法行為法上違法の評価を受けるものであること、これにより町に損害が発生したことなどを確定しさえすれば足りるのであるから、本件監査請求について監査委員が怠る事実の監査をするに当たり、当該行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはない、と判示。 この函館地判の判断が外見上この判断と合致していないのは、同判決が監査対象事項について、財務会計行為の違法により発生する請求権行使を怠る事実ではなく、財務会計行為の前段階である町長の落札業者指名(本命割当)行為(要は契約である以上、契約の申込と承諾があってはじめて契約が成立するところ、契約の申込(応札)以前の段階での問題と捉えている)が不法行為を構成するために発生する請求権の行使を怠る事実と構成している、つまり財務会計行為の違法性は監査対象の焦点ではないとしているためです(とすれば、この判断は上記最高裁の判断に背馳するものではない)。 なお本件は、仮に町長が財務会計職員である場合(当審は町長を決裁権者と認定)、本命割付行為は財務会計行為の準備行為としてその違法が財務会計行為の違法を構成する関係にあるといえ(上記本件平成14年最判)、またそのような条件下にある契約締結は当然に財務会計法規に違反する違法なものとしての評価を受けるものであるところ、助役以下がその準備行為に加担した上で町長の(違法な)財務会計行為の補助行為(支出負担行為たる契約締結決議の起案、審査にライン上関与)を行っていれば、補助行為の違法(本命割付に加担した上で契約締結行為を補助しているのだから)は財務会計行為の違法を構成する関係なのであり、助役以下の行為は町長の違法な財務会計行為と一体的な行為と評価されることとなるので、上記平成14年最判の法理によるかぎり、助役以下も監査請求期間の制限が適用され得るものとも考えることができる点に注意すべきです。 |
オ まとめ
以上を総合し、自治体がその者に対する請求権行使を怠る事実を監査対象とする住民監査請求が、真正怠る事実(監査請求期間制限適用なし)か、不真正怠る事実(監査請求期間制限適用あり)か、について、その判断の枠組みの概略をまとめると、次の通りとなります。
監査請求期間制限の適用ありが不真正怠る事実、なしが真正怠る事実と評価されます。
| 対象とされる職員 | 監査請求期間制限の適用 | 備考 | |
| 自治体の職員に対する請求権 | ① 財務会計法規に違反する財務会計行為について権限のある財務会計職員 ・首長(本来権限者) ・委任等受けた執行機関(たる職員) ・委任、専決権付与等をされた(決裁権のある)職員 |
あり | 要は、その職員の権限行使による(財務会計)行為が、違法性の責任を問い得るか、という点を検討の出発点にすれば、わかりやすいのではないかと考えます |
| ② ①に該当する財務会計職員の行う違法な財務会計行為の補助をする職員 | あり | 補助行為の違法性は、財務会計行為の違法性と一体をなすこと(補助行為の違法が財務会計行為の違法を構成)が必要(その財務会計行為が違法であることを承知の上で起案、審査を行った等) | |
| ③ その財務会計行為を現に行う財務会計職員ではないが、対象財務会計行為を行うため必要な準備行為(例:予算案作成等)を行った財務会計職員 | あり | ・準備行為の違法性は、財務会計行為の違法性と一体をなす(準備行為の違法が財務会計行為の違法を構成)ことが必要(例:その財務会計行為が違法であることを承知の上で、その財務会計行為を実行するために必要な予算案作成を行った) ・準備行為の実行は、財務会計行為職員の行う財務会計行為の実行と一体的であることを前提とするので、前任財務会計職員等、対象財務会計行為について権限のある財務会計職員の地位にあったことを前提とする(予算案作成時点でのその者の権限行使上の補助職員は上記②で整理すればよいと考えます) ・なお、予算案の作成行為はそれ自体単独では地方自治法242条1項所定の財務会計行為に該当せず、したがって独立して住民監査請求の対象となることはないので注意。あくまでも、財務会計行為と一体化した準備行為を、全体としてどう法的評価して、その中で、直接財務会計行為を行ったわけではないが、それに準ずる準備行為を行った者への訴求に対する監査請求期間をどう判断するか、という問題 |
|
| ④ 上記①〜③に当てはまらない職員 | なし | ||
| 自治体の外部の者に対する請求権 | ⑤ 対象財務会計行為が、財務会計職員が財務会計法規に違反して行われ、その結果その財務会計行為が違法のみならず無効であるために、財務会計行為の相手方(契約先、補助金交付先等)に対して生じると住民監査請求でされている不当利得返還請求権等の相手方 | あり | ・たとえば財務会計職員の行った財務会計法規上違法な公金支出、契約、補助金交付等が法律上無効であり、そのため契約先・補助金交付先が契約代金や受納した補助金の返還をしなければならないような場合です。 ・この請求権の相手方の行為が違法かどうかの評価の問題ではありません。 |
| ⑥ その外部の者の違法な行為により、対象財務会計行為が自治体に損害を与えたことにより生じる不法行為の損害賠償請求権等の相手方 | なし | ・たとえば業者談合で高値落札・契約したような場合です(談合関与業者に自治体は不法行為による損害賠償請求権が生じます)。 ・官製談合のように、自治体職員側の財務会計行為に財務会計法規上の違法があったかどうかは、左記の相手方(自治体からすれば第三者)にとっては問題となりません(自治体職員側の責任がどうであろうが、業者側の不法行為責任に対する監査請求期間ルールの判断は左右されないため)。 |
なお上記エにもあるとおり、上記表⑥の「官製談合」事例などでは、同一事件において、その請求権の相手方によって監査請求期間制限の対象となる者と、ならないものが混在することとなり得ますが、これは地方自治法242条1、2項の規定がそのようになっている以上、止むを得ないことです※。
| ※ 上記最判平14.10.3に関する最高裁判解(平成14年度)p.763(高世三郎)参照。なお参照:下記Q2。 |
| 【Q1】 支出負担行為について専決権のある職員が軽過失で行った違法な契約締結については、地方自治法243条の2の2第1項後段により賠償責任を負わないが、この違法な契約締結について当該職員への賠償請求を怠る事実を対象とする住民監査請求においては、最判昭62.2.20民集41.1.122の判示事項の適用はあるか? |
【A1】
あります
○ 同判決は「財務会計職員の特定の財務会計上の行為を違法であるとし、当該行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって財産の管理を怠る事実としているものであるときは、当該監査請求については、右怠る事実に係る請求権の発生原因たる当該行為のあった日又は終わった日を基準として同条2項の規定を適用すべき」と判示しています。
○ 同判決の法理が適用されるかどうかは、請求内容が実質的に、財務会計職員が財務会計法規に違反して違法な財務会計行為を行なったかどうか、がポイントとなることは、叙上の通りです。
○ つまり、この前提部分においては、その財務会計行為担当職員が、上記の行為を行った結果として地方自治法243条の2の2による賠償責任を現実に負っているのかは問題とされていません。その判断(軽過失かどうか等)は、監査を行い判断されるべき本案の問題です。
○ 結局、不真正怠る事実かどうかの判断において、頭首の点は検討すべき事項ではない(これを要件審査で検討することは他事考慮となる)のであり、その上で昭和62年最判の法理が適用されるかどうか判断することとなります。
| 【Q2】 上記の、特に真正怠る事実、不真正怠る事実に関する説明は、財務会計行為が「違法」であるかどうかを判断基準としているが、住民監査請求は不当な財務会計行為についても提起することができる。請求内容において不当性を主張される場合の取扱いはどうなのか? |
【A2】
○ 監査請求期間について定める地方自治法242条2項は「前項の規定による請求」について適用されるところ、同条1項は「当該普通地方公共団体の長・・・又は・・・職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある・・・と認めるとき」としています。
○ ということは、自治体の財務会計職員の行った財務会計行為の違法・不当(判断基準が財務会計法規となることは、叙上の通り)について、その是正等を求める住民監査請求を提起でき、またその請求について出訴期間が定められるという法構造である以上、監査請求期間制限の検討において、違法か不当かの区別は、その検討においては意味がない問題となります。

京都花園妙心寺塔頭群。どうみても時代劇のセット。そういえば太秦もここから遠からず。