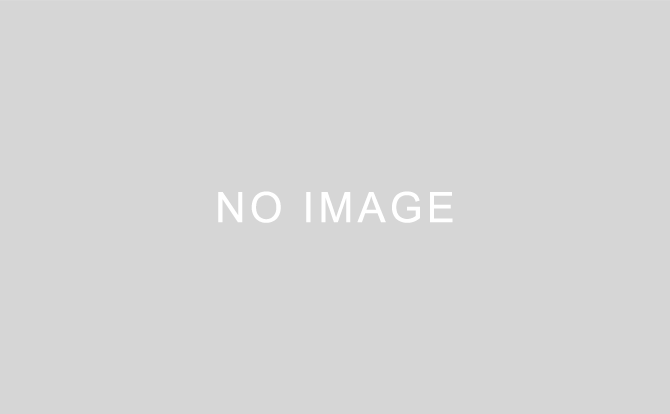本ページの一番下に、本ページのPDF版リンクを設けています。
最終改訂 2024.5.7 改訂内容は改訂履歴ページ参照
請求の対象となる財務会計行為行為(怠る事実)は、その自治体の執行機関か財務会計職員が行ったものであることを要し、住民監査請求の請求書には、通例、その執行機関・職員を記載することが求められます。
ただし、この要求事項の趣旨は、住民監査請求の対象とする財務会計行為等を、その自治体の財務会計行為等に限ることにあり、よって住民監査請求の請求書に、対象機関・職員を明記されていない場合や、記載が不正確である場合であっても、請求の内容から、請求の対象がその自治体の財務会計行為等であることが判断できれば、対象機関・職員の記載がないことや、その内容が誤っていることを理由として請求を不適法とすることは、適当ではありません。
1 概説
住民監査請求は、その自治体の財務会計行為について権限のある自治体の執行機関や職員が行う(怠る)、財務会計行為等に対して行うものであり、その自治体の執行機関や財務会計職員でない第三者が行った行為等を直接対象とすることはできません※。
| ※ この点は地方自治法242条1項の条文から明らかですが、実際は(特に、同じ自治体の職員であってもその財務会計行為について権限を有する財務会計職員かそうでないかで、怠る事実を監査対象とする場合の監査請求期間の扱いに差異を生じる)複雑な問題を生じますので、留意が必要です。詳細は「5.1 監査請求期間」参照。 |
ということは、住民監査請求の対象となる財務会計行為等は、その自治体の財務会計行為等に限られ、土地開発公社など、いかにその自治体と密接な関係がある(その団体の長を、自治体の首長が充て職等で務めているなど)ものであっても、そうした団体における財務会計行為等は、住民監査請求の対象とはなり得ません※※。
| ※※ 地方財務実務提要では、首長が理事長を務め、運営費の大部分を市負担金によっている外郭団体の事業の執行に違法があるとして、理事長たる市長に返還請求する住民監査請求について、地方自治法242条1項列挙事項に当たらず、却下すべきとの事例をあげています。また、地方独立行政法人の支出についても、同旨の説明がされています。外郭団体の理事長を市長が兼務していても、理事長職自体は、当該自治体の職員としての職ではないのですから、地方自治法242条1項の規定からして、当然の結論です。 なお、当該自治体が外郭団体や地方独法に対してした支出、出資等の財務会計行為については、住民監査請求の請求となり得る、ともしています。 |
これを住民監査請求の要件審査の次元でいえば、地方自治法242条1項の「当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について」とは、住民監査請求の対象とする財務会計行為が、その自治体の財務会計行為等であることを要する、という意味合いとなります。
なお、下記3で述べますが、この条文による限り、住民監査請求の請求書等において、請求の対象とする財務会計行為を行った(その財務会計行為について責任がある)執行機関、職員を示す必要があるようにも解されますが、住民監査請求の請求要件段階における限り、その点は重要視されません。あくまでも、住民監査請求の要件審査においては、請求の対象とする財務会計行為等が、その自治体の財務会計行為等であるかどうかがポイントとなります。
【参考事例①】
本事例は、地方公営企業の支出に対する住民監査請求を適法な請求と認めた裁判例です。このように、地方公営企業における財務会計行為等は、住民監査請求の対象になると解されています。
| 地方公営企業事業における公金の支出に対する住民監査請求について、これら支出はすべて地方公営企業たる事業の経営努力により得た収入の中から支払われたものであり、公租公課等による県の住民の負担に係る金銭の支出ではないから、本件支出は県に対し何らの財産上の損害を与えるものではなく、したがって、本件公金支出を訴訟の対象とする本件住民訴訟は、地方自治法242条の2所定の住民訴訟の趣旨、目的からして許されないとの被告の主張を退けた事例 名古屋地判昭59.9.21行裁例集35.9.1379
○ 被告は、本件公金の支出が、すべて地方公営企業である○事業の経営努力により得た収入の中から支払われたものであり、公租公課等による県の住民の負担に係る金銭の支出ではないから、右支出は県に対し何らの財産上の損害を与えるものではなく、したがって、本件公金支出を訴訟の対象とする本件住民訴訟は、地方自治法242条の2所定の住民訴訟の趣旨、目的からして許されない旨主張する。 |
【参考事例②】
本事例は、土地開発公社や第三セクターの財務会計行為に対する住民監査請求を適法な請求と認めなかった事例です。土地開発公社や三セクがいかに設立自治体と密接な関係にあろうとも、土地開発公社や三セクは自治体とは別の団体であり、その財務会計行為等を直接住民監査請求の対象とすることはできないと解されます(類似の団体についても、上記論理からすれば結論は同じ)。
なお、やはりこの論理の帰結として、最高裁は、土地開発公社理事の違法な行為について、設立者たる自治体の住民は、地方自治法242条の2第1項4号の住民訴訟を提起することはできないとの判断を示しています(最判平3.11.28集民163.611)。
| 公有地の拡大の推進に関する法律10条に基づいて設立された土地開発公社の財務会計上の行為につき、公社の設立者である普通地方公共団体の住民は、地方自治法242条の2の規定による住民訴訟を提起することはできないとした事例 福岡高判昭61.11.28行裁例集37.10・11.1392
○ 土地開発公社は、地方公共団体が地域の秩序ある整備を図るために必要な公有地となるべき土地の取得及び造成その他の管理等を行わせるために設立する公法人であって(公有地の拡大の推進に関する法律10条)、その設立にあたっては、これに対する出資を地方公共団体に限定し、しかも基本財産の額の2分の1以上に相当する資金その他の財産の出資を地方公共団体に義務づけており(同法13条)、その解散にあたっては、その残余財産を出資者に分配しなければならず(同法22条2項)、その債務については、地方公共団体の保証を得ることができ(同法25条)、また地方公共団体の長その他の執行機関は、その管理に係る土地、建物その他の施設を無償で土地開発公社の利用に供することができる(同法26条1項)などその財務面において、これを設立した地方公共団体と密接な関連性を有しており、そのうえ、土地開発公社の理事及び監事は、地方公共団体の長によって任命、解任され(同法16条2項、3項)、予算、事業計画及び資金計画の作成、変更については、その都度地方公共団体の長の承認を受けなければならず(同法18条2項)、その業務の運営についても、地方公共団体の長が業務命令をすることができる(同法19条1項)など地方公共団体の長は、その人事、財務及び業務について指揮監督をすることができる立場にある。更に、土地開発公社が地方公共団体に代わって土地の先行取得を行うために設立された公社であることや、これを設立した地方公共団体の監査委員は、地方自治法199条6項(現7項)により土地開発公社の財務について監査を行う権限を有していると解することができることなどを考えると、実体としては、土地開発公社は、地方公共団体の機能の一部を分担し、その一機関ともみることができる。 |
| 土地開発公社の理事の違法な行為につき、その設立者である普通地方公共団体の住民は、地方自治法242条の2第1項4号の規定による訴訟を提起することができない 最判平3.11.28集民163.611
○ 公有地の拡大の推進に関する法律10条に基づいて設立された土地開発公社の理事の違法な行為につき、その設立者である普通地方公共団体の住民は、地方自治法242条の2第1項4号の規定による訴訟を提起することができないとした原審の判断は正当として是認することができる。 |
| 市長が市出資第三セクターの代表取締役としてなした売買契約は住民訴訟の対象とはならないとした事例 浦和地判平6.10.31判例地方自治140.22
○ 本件会社は、市が資本金の50パーセントを出資して設立されたいわゆる第三セクターの株式会社であるが、あくまで市とは別個の法人である。したがって、たとえ市長が本件会社の代表取締役を兼ねていても、法律上、市の代表者としての地位と本件会社の代表取締役としての地位は全く別個のものであって、両者を同一視することはできないから、被告が本件会社の代表取締役として本件売却物件につき本件売買本契約を締結した行為を市長の行為と認めることはできない。それ故右売買本契約の締結行為は、住民訴訟の対象となし得ないものである。 |
【参考事例③】
本事例は、参考事例②に類似するものですが、一部事務組合である退職手当組合から職員の退職手当を支給する場合は、その退職手当の支給に対する住民監査請求は、職員の所属自治体ではなく、退職手当組合の監査委員になすべきものとしてものです。監査の対象となる財務会計行為は、あくまでも一部事務組合である退職手当組合が行ったものですから、特別地方公共団体である一部事務組合の構成自治体(普通地方公共団体)は、別の自治体ということになります。
ただし、一部事務組合には地方自治法292条により、普通地方公共団体の規定が準用され、独自の監査委員を有するので、一部事務組合の監査委員に監査請求することができますが、そのような準用規定のない財産区については、行実昭29.3.9によれば、財産区所在市区町村の監査委員に行うことになります(「1 地方公共団体の住民」1(2)Q2参照)。
| 一部事務組合である退職手当組合からの退職手当の支給を住民監査請求の対象とする事例において、当該住民監査請求は退職手当組合の監査委員に行うべきであり、これを職員所属自治体の監査委員に行ったのは不適法とした事例 富山地判昭60.8.30判例時報1182.74
○ 退職手当組合のような一部事務組合(特別地方公共団体)については、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除く外、普通地方公共団体に関する規定が準用されることは地方自治法292条の明定するところであるが、かかる一部事務組合につき、同法242条所定の監査請求を準用しない旨の特別規定は、すべての法律又は政令中にも存在しない。 ★本裁判例については、「2.1.1 財務会計行為各論:公金の支出」4(4)も参照 |
2 執行機関・職員の定義
(1) 執行機関
地方自治法242条1項では「…住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出…がある…と認めるときは…請求することができる」とあります。
執行機関とは、このうち「当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員」、つまり首長(都道府県知事・市町村長)と、行政委員会(教育委員会、選挙管理委員会など)・委員(監査委員)が該当します。これらは、その自治体の事務を管理・執行する権限を持つ機関として、地方自治法7章で定められています。
そして、地方自治法242条1項の執行機関(長または委員会若しくは委員)とは、請求の対象となる財務会計行為等について権限のある執行機関が、これに該当することになります。ただし首長以外の執行機関の財務会計に関する法令上の本来的権限は極めて限定されているので(会計管理者、公営企業管理者、教育委員会(教育財産の管理は地教行法21条2号で教育委員会権限))、首長以外の執行機関において財務会計行為等について権限があるとは、首長から委任された権限ということになります。
なおいうまでもなく、同項の条文には「当該普通地方公共団体の」とあることから、上記1参考事例②③のような事案に関する請求は、住民監査請求の請求要件を満たさないこととなります。
(2) 職員
地方自治法242条1項「…住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出…がある…と認めるときは…請求することができる」のうち、職員とは、「当該普通地方公共団体の職員」となりますが、具体的には、執行機関での説明と同様に、請求の対象となる財務会計行為等について権限のある職員が、これに該当します。「当該普通地方公共団体の」についての説明も、同じです。
なお、権限ある職員については、次のように定義されます(最判昭62.4.10民集41.3.239)※1、2、3、4。
○ その適否が問題とされている財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有するものとされている者(首長や公営企業の管理者、教育財産管理に関する教育委員会が該当)
○ これらの者から権限の委任を受けるなどして右権限を有するに至った者(権限委任や専決権付与をされた者、補助執行担当など。こうした権限を有する者を広くカバー)
【注】
一方で、このような権限を有する地位・職にあると認められない者は、該当しないとされていることに注意
| ※1 本判決の上記定義は、地方自治法242条の2第1項4号の住民訴訟における「当該職員」の定義ですが、この定義は職員が財務会計法規に違反して違法に行われた場合に損害賠償請求の対象となる者(なお地方自治法243条の2の2第1項の対象職員と等価ではない。たとえば首長の財務会計行為が違法で自治体に損害を与えた場合、首長は自治体に対する損害賠償義務を負うが、首長には同条は適用されない(参照:地方自治法243条の2の2第1項))であり、そうであれば地方自治法242条1項にいう、違法な財務会計行為を行なった職員(その財務会計行為を行う権限のある職員・・・財務会計職員)と等価概念となります(やはり参照:前記自治法の条文。また最判平14.10.3民集56.8.1611の最高裁判解(平成14年度)p.758(高世三郎)もこれを前提とした説明がある))。 なお「当該職員」の定義については、最判平3.12.20民集45.9.1455、同平5.2.16民集47.31687、同平18.12.1民集60.10.3847も参照。 ちなみに松本逐条は、地方自治法242条1項の「地方公共団体の職員」(上記にいう財務会計職員)について、「一般的には、地方公共団体の議会の議員を除き、一般職たると特別職たるとを問わずすべての職員を包含するが、実際には主に会計管理者その他第一項に列挙されているような財務会計上の事務に関係のある職員となろう」としています。やや上記の定義より幅広にも解されますが、これは下記(3)の議員等の事例を想定しているためと推測されますが(松本逐条上記説明に続いて、議長交際費について議長が対象職員となり得る(行実昭40.5.12)説明がある)、これら議員や議会事務局の職員にも財務会計行為の執行権限が個別に付与されることはあり得るのであり、上記の最判の判示事項にも照らせば、これらの者が執行機関の職員でないことをもってこの財務会計職員の範疇から一律に排除すべきではないこととなります。 |
| ※2 最高裁判例では「財務会計職員」と「当該職員」の用語を使い分けていますが、これは地方自治法242条(住民監査請求)が問題になる場合は「財務会計職員」を、地方自治法242条の2第1項(特に4号)の住民訴訟が問題になる場合は「当該職員」を使用しているのであり、その概念が示す職員の範囲は、上記※1の通り、同一と考えるべきものです。 なお、最判昭62.2.20民集41.1.122で「普通地方公共団体の長その他の財務会計職員」という記述があるように、「財務会計職員」には、財務会計行為の本来的権限を持つ首長が含まれます。 |
| ※3 住民監査請求の要件審査において財務会計行為の行為者が職員かどうかが問題(争点)となるとすれば、上記1掲記のようなそもそもその自治体の職員でない者の行為かどうかが単純明快なケースですが、こうしたもののほか、①自治体の有する請求権行使を怠る事実を対象とする監査請求がなされたとき、監査請求期間制限規定が適用されるかどうか(不真正怠る事実に該当するかどうか。特に自治体職員であっても監査対象の財務会計行為についての権限を有する者と有しない者では監査請求期間の適用についての扱いが異なる。参照:最判平14.10.3民集56.8.1611)、②権限を有さない職員が権限者の名義を冒用する等(公印を不正に使用して契約書を偽造し契約締結、支出関係決裁書類の偽造等)で財務会計行為を行なった場合 などが想定されます。 なお①の問題については監査請求期間の問題であり、詳細は「5.1 監査請求期間」で説明します。②は財務会計職員が行なった財務会計法規違反の財務会計行為ではないので、ストレートに地方自治法242条1項の「当該普通地方公共団体の長・・・又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出・・・がある・・・と認めるとき」に該当しないこととなるため、この部分を根拠とする住民監査請求(直接的にその財務会計行為(のようなもの)の違法不当を理由に所要の是正措置や損害補てんのための措置を求めること)は不可となりますが(参照:上記昭和62年最判)、そのような不正行為を行い自治体に損害を与える行為は民事上の不法行為に該当するため、自治体がその者に損害賠償請求をしない場合は、地方自治法242条1項の「怠る事実」(「当該普通地方公共団体の長・・・又は当該普通地方公共団体の職員について、・・・違法若しくは不当に・・・財産の管理を怠る事実・・・があると認めるとき」が根拠)を監査対象として住民監査請求をすることは、当然に可能です。参考: 最判平14.10.3民集56.8.1611(いわゆる官製談合に関与したとする副知事や議員(いずれも財務会計職員や補助職員に該当しない)への損害賠償請求権行使を怠る事実について)。この平成14年最判の詳細については、「5.1 監査請求期間」を参照。 |
| ※4 本判決に関する地方自治判例百選(第4版)p.165(紙野健二)は、本事案について、原判決(議長の当該職員性を肯定)は地方自治法が住民訴訟制度を設けている立法趣旨と当該行為の実質的責任の所在を重視するのに対し、本最高裁判決は、権限の有無に関する法令と予算執行に関する内部規程の定めから結論を導いている点に特徴があるとします。 要すれば、権限のある者とは、実質的に対象財務会計行為についての権限(責任)が帰属する者ではなく、法令や自治体の権限配分規定上誰に権限があるかにより、この判断が決せられるということです(最高裁の具体的な判断当てはめもそのようになっています。また地方自治法243条の2の2に関する松本逐条は、「権限を有する職員」について、「法令(条例、規則を含む。)に基づき権限を行使する職員をい」うとしています)。また上記「5.1 監査請求期間」3(2)ア※、同エ(上記※3平成14年最判関係)を参照。 |
(3) 議員等
地方自治法242条1項は「…住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出…がある…と認めるときは…請求することができる」とあるのですから、議会、議員や議会事務局の職員はここには含まれません(例:最判平14.10.3民集56.8.1611)。また議会の議決などは、地方自治法242条1項での財務会計行為等にあたらないため、やはり住民監査請求の対象とはなりません(参照:松本逐条)。
そもそも、議会は執行機関ではないため(地方自治法6章が議会、7章が執行機関であり、地方自治法上の区分けが違う)、自治体事務の執行行為である財務会計行為を自ら行う権限はなく、議会・議員が首長から財務会計行為等に関する権限を委任されることもありません。
ただし、では実質的に議会で支出等の対応がなされる行為等がすべて住民監査請求の対象外になるのかというと、そうではありません。
行政実例において、議長を対象とした、議長交際費の使途等についての監査請求は受理できないのではないかとの質疑に対し、受理すべきとした事例があり(行実昭40.5.12。松本逐条もこの実例を引用)、地方財務実務提要でも、例えば議長交際費は、いったん議長に支出され、正当な債権者に支出されるまでは、公金としての性質を有し、議長は、その自治体の職員として、公金の支出を行うこととなることなる、とされています。議会の構成員である議員は、地方自治法242条の職員には含まれないとされているものの、いかなる場合も「職員」に含まれ(ず、その行為等が住民監査請求の対象とならないものでは)ないものではないことに注意する必要がある、とされています。
以上の論理によれば、議員に対して資金前渡がなされた場合も、同様の結論となります。
また、上記のような地方自治法上の機関の建付けから、執行機関ではない議会の事務局の職員に本来は首長の権限である財務会計行為等を補助執行させることもできません(地方自治法180条の2のような規定がありません)が、事務局職員を首長部局の職員に併任し、財務会計行為等を行わせることはあり得ることです(参照:松本逐条149条2号関係)。
いずれにしても、議員や議会事務局職員は、原則的には、地方自治法242条1項の職員には該当しませんが、常にそうであるとは限らないことになります。また議会費の執行は、その自治体のいずれかの職員が権限をもって行っているので、議会費が住民監査請求の対象にならない、という理屈は成り立ちません。
3 住民監査請求の要件審査における「執行機関・職員」の意味合い
住民監査請求は、「当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある・・・と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実・・・があると認めるとき」に提起することができますが、これを敷衍すれば、請求の対象は、その自治体の職員としての権限により行われた(行われるべき)、その自治体の財務会計行為等である、ということになります。
そして、対象となる財務会計行為等については、「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」4で述べた通り、請求書等により特定される必要がありますが、その特定により、請求の対象である財務会計行為等がその自治体の財務会計行為等であることが明らかとされれば、同ページ(3)イで説明の通り、その行為権限者である執行機関・職員を厳密正確に特定明示する必要はなく、極論すれば、監査対象とする事項、つまり対象の財務会計行為等が適法に特定されていれば、端的にはこれら執行機関・職員の特定がなくとも、請求要件の判断には影響しないと考えます。つまり本ページ冒頭掲記の通り、住民監査請求の請求書に、対象機関・職員を明記されていない場合や、記載が不正確である場合であっても、請求の内容から、請求の対象がその自治体の財務会計行為等であることが判断できれば、対象機関・職員の記載がないことや、その内容が誤っていることを理由として請求を不適法とすることは、適当ではないと考えます(理由については、上記ページ掲記の通りです)※1〜3。
| ※1 なお、上記2(2)において、昭和62年最判により住民監査請求の対象となる財務会計行為は首長その他の財務会計職員によりなされたものでなければならないとしていますが、これは請求に対する終局判断の際に、監査請求の対象となった行為がその属性として上記条件を満たしていないと不適法な請求と判断されるということであり、ここでの説明事項、つまり請求時にどこまで監査対象の財務会計行為等を行なった(行うべき)職員を特定明示すべきか、という要件事項とは別の問題となります。 |
| ※2 たとえば住民訴訟においては、公営企業の財務会計行為について首長を被告とするものは却下されますが(例:神戸地判平6.3.30判例地方自治127.59)、住民監査請求においては請求内容が首長に対する措置要求であったとしても、上記の理由からすれば、それをもって請求不適法とする理由がないというべきです。 |
| ※3 また、財務会計行為自体がその自治体の財務会計行為といえない、たとえば権限のない職員が決議書の偽造、公印の冒用等で公金の支出等を行った(例:和歌山地判平成3.6.5:職員が公印を冒用して公金口座から現金を払い戻して横領した事案)ような事例では、関係者に対する損害賠償・不当利得返還請求を怠る事実に着目して住民監査請求をなし得るうえ、請求人は請求においては対象事項を特定して然るべき措置を講ずるよう請求するのみでよいので(最判平10.7.3集民189.1)、かかるケースにおいて住民監査請求がなされたとしても、監査委員は要件審査において行為者の財務会計職員性を問題とする必要がないことは当然です。 |
| 【Q】 市町村立小中学校教職員のような、任命権がその自治体にない職員の行為による財務会計行為等は住民監査請求の対象とすることができるのか? |
【A】
住民監査請求の対象とすることができます。
○ 通常、その自治体の職員は、その自治体の機関が任命し、その自治体が給与を負担するのですが、いわゆる県費負担教職員や、地方警務官(都道府県警察職員のうち警視正以上の警察官)は、その自治体に任命権がありません。
○ ところで、住民監査請求は、ある自治体の住民が、その自治体の財務行政の適正化を求めるためのものですから、ポイントは、地方自治法242条1項に明記される通り、対象となる財務会計行為等が、その自治体のものであり、その自治体の機関・職員がこれをおこなったかどうか、ということとなります。
○ 県費負担教職員は、任命権は都道府県教育委員会にありますが、文科省の資料などみても、これら職員は、その学校所属市町村の職員であるとされており、実際、服務等、市町村教育委員会の指揮監督に服することとされています(地教行法43条1、2項)※。また、警察法55条3項(及び1項)では、地方警務官もその都道府県警察の職員であることが明記されており、都道府県の執行機関である公安委員会の管理に直接(警視総監又は道府県警察本部長:警察法48条2項)又は間接(その他の都道府県警察職員:警視総監又は道府県警察本部長の指揮監督下に置かれる。警察法48条2項)服することとされています。そして、これら職員は当該自治体の職員としての権限(財務権限※※)を行使し得ることとなります。
○ 結局、これらの職員は、任命権や給与負担がどうであれ、まぎれもなくその自治体の機関の職員であり、実際に、その自治体の業務執行に一定の権限と責任を行使しているのです。したがって、自治体財務運営の適正化を図るという住民監査請求の趣旨に照らしても、これらの職員が関与するからといって、住民監査請求の対象から外れる、ということにはならないと考えます。
| ※ 木田宏(著)教育行政研究会(編著)「第四次新訂 逐条解説 地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第一法規(2015年)p.336(同法43条関係)では「県費負担教職員は、市町村の公務員として市町村立の学校に勤務する。したがって、その職務に関して制定された国の法令に従うことはもとよりであるが、その学校の管理運営等に関して定められたその市町村の条例、規則、並びに教育委員会規則及び規程に従わなければならず、市町村の教育委員会を頂点とする職務上の上司の職務上の命令に従わなければならない。このことは勤務関係にある以上法令の規定を待つまでもないことではある・・・」とする。 |
| ※※ 地方自治法施行令173条の規定は、地方警務官が財務権限を違法に行使することにより自治体に対して賠償責任が発生することを前提としたものと見ざるを得ません。実際に、警察本部長(地方警務官)の行った財務会計行為に対する4号訴訟で同本部長の損害賠償責任を認容した事例として、名古屋高判令3.10.7 |

ここは、さる有名なテレビ番組の舞台となったところです。ヒント:振り子の等時性。