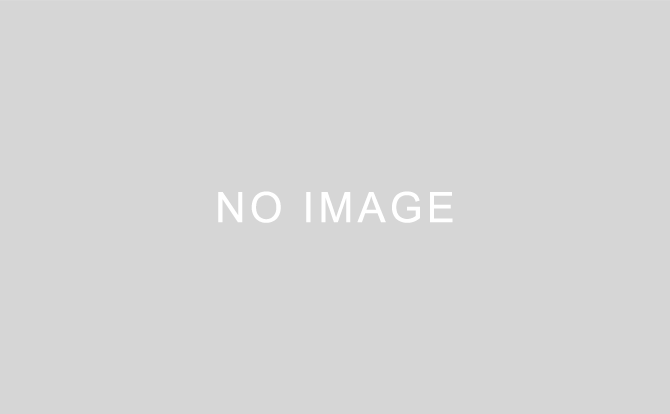本ページの一番下に、本ページのPDF版リンクを設けています。
最終改訂 2024.9.7 改訂内容は改訂履歴ページ参照
このページは、「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」4で概説した請求の対象行為等の特定について、各論部分をもう少し詳しく説明するページです。
【注】 参考事例の判決文は、必ずしも原文通りではなく、項目の表記にあうように若干の修正をしていることがあります。
1 判断の基礎となる最高裁判例
住民監査請求において、対象行為等の特定を請求要件とすることは、地方自治法242条の明文規定にはなく、最高裁判例により形成された法理です。
そのため、まず以下に、判断の枠組みを示すリーディングケースの判例を示します。
① 平成2年6月5日 民集44巻4号719頁 【原則】
住民監査請求においては、対象となる財務会計行為等を請求人が特定することを要し、これが住民監査請求の適法要件となることを示した事件です。
請求対象の特定に関する判断枠組みの論点は、本判決ですべて示されているといえ、②以下で紹介する判例は、本判決をどのように適用するのかというヴァリエーションケースと考えるとよいと思います。
本判決で示される原則は、次の通りです。
a) 請求人は、請求対象となる財務会計行為等を、監査委員が他の事項から区別して特定認識できるように個別的、具体的に摘示することを要する。
b) 対象財務会計行為等が複数あるときも、原則として、各行為等を他の行為等と区別して特定認識できるように個別的、具体的に摘示することを要する。
ただし、当該行為等の性質、目的等に照らしこれらを一体とみてその違法又は不当性を判断するのを相当とする場合を除く。
c) 上記は、監査請求書及びこれに添付された事実を証する書面の各記載、監査請求人が提出したその他の資料等を総合して判断する※。
d) 請求対象特定の要件を満たさない住民監査請求は、不適法であり、監査委員は当該請求について監査をする義務を負わない。
【注】 c)のその他の資料等の範囲については、下記②平成16年最判で、より具体化された判断基準が示されました。
| 住民監査請求は、その対象とする財務会計上の行為又は怠る事実を他の事項から区別し、特定して認識できるように個別的、具体的に摘示し、また右行為等が複数である場合には、右行為等の性質、目的等に照らしこれらを一体とみてその違法又は不当性を判断するのを相当とする場合を除き、各行為等を他の行為等と区別し、特定して認識できるように個別的、具体的に摘示してしなければならない
(事実関係) (判決内容) |
| ※ 特に上記c)の原則を確認するものとして、最判平14.7.2民集56.6.1049 において「監査請求の対象として何を取り上げるかは,基本的には請求をする住民の選択に係るものであるが,具体的な監査請求の対象は,当該監査請求において請求人が何を対象として取り上げたのかを,請求書の記載内容,添付書面等に照らして客観的,実質的に判断すべき」という。前段は、監査の請求対象事項は請求人の選択に委ねられる(他事考慮が認められない)原則の確認であり、その上で後段は、上記c)の確認、すなわち請求人の提出資料により監査対象は客観的実質的に判断把握されるものであ(り、請求人の法律構成により請求対象が異なることはないこととな)る、となります。 なお、本判決は怠る事実を請求対象とする場合の監査請求期間の適用が論点となっており、監査対象事項は何かは客観的実質的に何かという判断で決まる(客観的実質的に同一の内容である限り、例えば請求人が財務会計行為の是正を対象とするか財務会計行為の違法無効を前提としてそれにより生じる請求権行使を怠る事実を対象とするかは、請求内容としては等価である)という結論を導出しています。なお監査請求期間の論点については「5.1 監査請求期間」も参照。 |
② 平成16年11月25日 民集58巻8号2297頁 【外部資料等の利用で対象行為等を特定できる場合の請求要件の可否】
上記①の判旨では、監査請求書及びこれに添付された事実を証する書面の各記載、監査請求人が提出したその他の資料等を総合して判断するとしていますが、その資料等の範囲についての判断を示したものです。
上記①最高裁判決後、下級審裁判例の中には、特定の程度について過度に厳格に解するものもありましたが、本最高裁判決において、請求人がすべての対象財務会計行為等を個別具体に摘示していない場合、請求内容から判断される、請求人提出の資料以外のもの(請求内容から、参照すべき外部資料が判明し、かつその資料は監査委員が容易にアクセスできるものであることを要すると考えるべきですが)によって、監査委員が請求対象を特定できれば、住民監査請求の請求要件は充足することが、明らかにされました※。
| ※ 参照:判例行政法p.52(海老名富夫)が引用する増田稔「最高裁判解(平16下)」p.723。 |
| 住民監査請求においては,対象とする財務会計上の行為又は怠る事実を,他の事項から区別し特定して認識することができるように,個別的,具体的に摘示することを要するが,監査請求書及びこれに添付された事実を証する書面の各記載,監査請求人が提出したその他の資料等を総合して,住民監査請求の対象が特定の財務会計上の行為等であることを監査委員が認識することができる程度に摘示されているのであれば,これをもって足りるのであり,このことは,対象とする財務会計上の行為等が複数である場合であっても異ならない
(事実関係) (判決内容) |
③ 平成18年4月25日 民集60巻4号1841頁 【一体的事業における対象特定の程度】
上記①の判旨では、監査対象を個別具体に特定することを、住民監査請求の請求要件とすることの例外として、行為等の性質、目的等に照らしこれらを一体とみてその違法又は不当性を判断するのを相当とする場合をあげています。本判決は、そのケースに関する具体的な判断事例であり、特定された事業を違法・不当とする場合のそれに係る財務会計行為等についての請求人の特定義務に関しては、当該事業に係る財務会計行為等を監査委員が容易に把握特定できる条件が整っておれば、請求人が対象財務会計行為等を個別具体的に摘示する必要はないものとされています。
なお、差止訴訟について、本判決と同様の判断を示すものとして、最判平5.9.7民集47.7.4755があり、当該行為防止請求の住民監査請求においても、参考となるものです。
| 市の施行する予定の土地区画整理事業は違法であると主張し,市作成の当該年度一般会計歳入歳出決算書の抜粋等を添付して,同年度に同事業のために支出された公金を市に返還し,今後もこのような不当,違法な事業に対し公金を支出しないよう適切な措置を求める旨の住民監査請求につき,
①上記事業にかかわる公金の支出を全体として一体とみてその違法性又は不当性を判断するのを相当とする場合に当たること など判示の事情の下においては,上記監査請求は,請求の対象の特定に欠けるところはない (事実関係) (判決内容) |
2 特定の程度に関する実例
(1) 一般的な特定判断
平成2年最判の枠組みに基づく、一般的な請求対象の特定に関する裁判例を、請求人(原告)の特定を否定した例と是認した例に分けて紹介します。
下記裁判例は平成2年最判以降のものであり、特定要件の成否について、平成2年最判に基づき判断されています。ただし、とりわけ特定を肯定する事例について、裁判例により判断の幅が見受けられますが、そうした点も踏まえ留意のうえで、参考として頂ければと考えます。
(裁判例は、事案ごとの個別具体の事実関係が異なることも考慮すべきですし、裁判所により判断の細かい振り幅があることに留意が必要です)
ところで下記(3)に掲出する平成30年大阪地判と下記否定事例中の平成10年東京地判が、一部返還請求という点で類似性があるものの、特定要件の充足に関する結論は異なっています。
この点について、平成30年大阪地判の事案は、請求人において監査の対象とすべき財務会計行為は特定されているのであり、住民訴訟においては対象財務会計行為の総額の一部についての一部請求となっているため、請求対象の特定要件については、要件はクリアされている(監査対象は、請求人が指摘する全支出)と判断されたものと考えます。
一方で、平成10年東京地判の事例は、事実関係が詳細に判明しないところがありますが、請求人は、監査請求書に添付した支出一覧表の全支出(合計額は3億円を超える)を不適正支出と主張するところ、返還を求める支出額については、上記一覧表記載の全支出としつつも、その額を一覧記載の支出額の合計より少ない3億円としており、監査を求める支出の対象が一覧表記載支出の全部なのか一部なのか判然とせず、結局監査対象の特定ができないという結論になったものと推察します。
【対象財務会計行為等の特定を否定する事例】
| 特定年度の会議費支出が違法であるとする住民監査請求について、監査請求書及びその添付資料(支出の一覧)によってもいずれの支出を違法とするものかの特定がなされておらず、具体的な違法性又は不当性に関する指摘もないこと、個々の支出に関する領収書等の添付もないことなどから、対象の特定を欠く不適法なものであるとした事例 東京地判平10.10.14判例地方自治189.29
○ 原告は、本件監査請求において「重大な不適正支出」として返還を求めている支出は本件監査請求書添付の「別紙1」記載の支出すべてであると主張するが、本件監査請求書において原告が不適正支出として返還を求めている金額は3億円と記載されているところ、本件監査請求書添付の「別紙1」記載の支出額を合計した金額が3億円を超えていることは明らかであり、原告が本件監査請求において「重大な不適正支出」であるとして返還を求めている支出が本件監査請求書に添付された「別紙1」記載のすべての支出であると解することはできない。仮に、本件監査請求が本件監査請求書添付の「別紙1」記載の平成X年度の会議費の支出の一部を違法と主張する趣旨であるとしても、本件監査請求書及びその添付資料には、そのいずれを違法とするものかの特定がされておらず、本件監査請求の対象の特定を欠くというほかない。 |
| 県のある部所属全職員の5か年度間における旅費支給が違法である旨の住民監査請求について、違法とされる旅費支給に関する出張職員の氏名、出張の目的、日時、場所などの具体的内容が何一つ特定されていないから、対象の特定を欠く不適法なものである、とした事例 岡山地判平10.10.20判例地方自治192.61
○ 原告らは、県監査委員に対し、県A部所属職員全員の平成3年4月1日から平成8年3月31日までの間における旅費支給に関し違法な公金の支出があるとして監査請求を行ったものであるが、そこでは違法とされる旅費支給に係る出張職員の氏名、出張の目的及び日時場所といった具体的内容は何一つ特定されておらず、所属部局と期間をもって所属職員の出張旅費の支給に関し違法な公金支出がなされている旨包括的網羅的に主張するに過ぎないものであるから、本件監査請求は、対象の特定を欠くことが明らかであり、不適法といわざるを得ないものである。原告らは、本件監査請求が前述の期間におけるA部所属職員全員の旅費支給全部を対象とするものであり、人的・期間的に限定されているから、特定性の要件を満たした適法な監査請求であると主張するが、出張旅費の支給については各支給行為毎にその違法性の有無が問題となるものであり、右期間中における旅費支給のすべてが違法な公金支出に当たるとみるべき事情の存しない以上、適法な旅費支給は当然除外した上で、違法なもののみを監査対象とすべきであることは当然の理であるといってよい。原告ら主張のような特定の仕方による監査請求を認めるならば、事実上財務会計上の行為等の全般にわたって包括的網羅的な監査請求を行うことを許容する結果となり、個別の財務会計上の行為等に係る過誤の是正を通じて普通地方公共団体における財務行政の適正な運営を確保しようとした住民監査請求制度の目的から逸脱することとならざるを得ないものである。したがって、本件監査請求に係る出張旅費の支給について原告ら主張のような人的・期間的限定がなされているからといって、その対象が特定されているとは到底いえないものである。さらに、原告らは、本件監査請求では、A部所属職員の旅費支給手続のあり方そのものに問題があるため、出張旅費の支給全体を対象とするものであり、請求の特定に欠けるものでないとも主張するけれども、個々の旅費支給手続と離れて支給手続そのものを問題としたところで個別の財務会計上の行為である旅費支給における違法性の有無を確定することができるわけではなく、それゆえ違法な旅費支給を特定する必要性がなくなるというものでもないから、右の主張も理由がなく、採用の限りでない。 |
| 中央薬事審議会が医療上の有用性を否定したために、薬価基準から一部の薬剤が削除されたところ、有用性のない薬剤に保険給付をしてきた区は製薬会社に対して不当利得返還請求権を有するのに、この請求を怠っているとして、同請求権の行使を怠る事実の違法確認を請求する住民訴訟(3号請求)について、原告らは製薬会社が販売した薬品名を明らかにしたほか、区国保特別会計から診療報酬の支出があった時期を包括的に特定しただけであり、個々の不当利得返還請求権が個別的、具体的に特定されているとはいえないから、請求の対象の特定を欠き、不適法であるとした事例 東京地判平12.1.26判例地方自治206.80
○ 原告らは、本件薬剤のうち、少なくとも、A錠(T社製)、E錠(Y社製)及びS錠(E社製)については、区国民健康保険特別会計から保険給付金が支出された医療機関が特定できるので、右3件の支出についての不当利得返還請求権は特定に欠けないと主張し、区国民健康保険特別会計から、E錠20ミリグラム2錠については国家公務員共済組合連合会総合病院S病院に対する平成10年4月分の診療報酬が、A錠3錠についてはT大学医学部付属O病院に対する同年5月分の診療報酬が、S錠50ミリグラム3錠についてはT医科大学病院に対する同月分の診療報酬が、それぞれ支出されていることが認められる。 |
| 約3年間に実施された土木工事一式及び舗装工事の約90パーセントについて談合が行われてきたので業者に損害の補填を求めるという趣旨の住民監査請求は、監査請求の対象が特定されておらず不適法とした事例 横浜地判平14.4.24判例地方自治238.29
○ 監査請求の趣旨は、監査委員がまとめているように、要するに「少なくとも平成7年度以降、平成10年3月3日までの間に実施された土木工事一式及び舗装工事(316件、入札価格累計約85億円)のうち、その約90%について談合が行われて来た」ということを前提に、市長に対して、談合が排除されて公正な競争が実現していたなら、落札価格が予定価格の85%程度の水準に下がったであろうと推定できるとして、現実の落札価格と右推定価格との差額(85億円×90%×15%で約11億円となる。)の損害賠償を請求して業者に補填させることを求めるというものである。 |
【対象財務会計行為等の特定を肯定する事例】
| 土地区画整理事業施行区域内の土地を原価を下回る価格で売却する契約を締結したことが違法であるとする住民監査請求において、監査の対象となる各契約につき相手方、契約締結日、売買面積等を特定していなかったとしても、監査対象たる市有地等の件数、処分価額合計と原価または予定価格合計等が特定されていることを考慮すれば、特定の市有地等に係る契約締結等を他の契約締結等から区別して個別的に特定しているものと認められ、財務会計上の行為の特定に欠ける違法はないとした事例 福島地判平9.12.1判例地方自治178.79
○ 原告は平成元年12月4日、市監査委員に対し、被告が同市長として、特定の者の利益のために、本件土地区画整理事業施行区域内の土地を売却処分したため、市に金2億0792万円余りの減収を生じたとして、被告において右減収を負担するように求める内容の本件住民監査請求を行ったこと、同請求書には、昭和63年12月に開催された市議会によって右売却処分の大略が判明した旨が記載されていたこと、原告が本件住民監査請求に際して提出した資料は、特別委員会資料と題する書面、建設委員会審査報告書、決算特別委員会審査報告書、市議会議事録の抜粋であったこと、右各書証は、原告が市議会事務局に対して自ら直接または知人であった○党所属の市議会議員を介して交付を要請し入手したものであったことに加え、特別委員会資料と題する書面には、市有地をS石材外6件に対して、原価価格合計金1億8739万3202円のところを処分価格合計金1億5474万1419円で、保留地をT建設外10件に対し、保留地予定価格合計金4億9412万2205円のところ、処分価格合計金2億2087万8942円で売却処分されたこと、市有地、保留地及び公社有地についての、原価価格合計金、保留地予定価格合計金、公社用地の原価合計金と各処分価格合計金との各差額合計金が金2億0792万4593円であること等の記載があることが認められる。右事実によれば、本件住民監査請求の対象とされている行為は、被告が市長としてなした、本件土地区画整理事業施行区域内の保留地11件及び市有地7件についての売買契約であることが理解されるが、右のような種類の契約の締結ないし財産の処分の違法又は不当性は、事柄の性質上個々の契約ないし処分ごとに判断するほかないと考えられるから、右契約の締結等についての監査請求においては、各契約の締結等を他の契約の締結等から区別して特定認識できるように個別的、具体的に摘示することを要するものというべきである。 |
| 市の公共工事につき公取委が受注各社に排除勧告をした場合において、「公取委によれば、平成7年度及び同8年度に係る313件、受注総額約55億円の市発注工事につき談合があったというものである」として損害賠償請求権の行使の勧告を求めるという趣旨の住民監査請求は、対象となる工事を他の工事と区別して特定認識することができる程度に摘示しており、対象が特定されているとした事例 前橋地判平15.6.13判例タイムズ1163.188(本件は、市及び県土木事務所の発注工事に係る談合事件であるが、請求対象特定要件についての判断は、市分と県事務所分は同様であるので、市分について抜粋する。公取委の市分発注工事についての平成9年12月16日にした排除勧告の対象となる工事(平成7・8年度分)の件数・総額は次の通り。第21号勧告(第1談合):市が指名競争入札の方法により発注する土木一式工事 件数219件受注総額41億7000万円 第22号勧告(第2談合):市が指名競争入札の方法により発注する建築一式工事 件数39件受注総額8億2500万円 第23号勧告(第3談合):市が指名競争入札の方法により発注する舗装工事 件数55件受注総額4億5900万円)
○ 原告の監査請求の際の請求の要旨は下記のとおりである。 ○ したがって、上記監査請求は、A市が平成7年度又は平成8年度に発注した工事における談合を対象とするものであって対象となる行為が複数であることから、原則として他の行為等と区別して特定認識できるように個別的、具体的に摘示することを要するものといえる。 |
| 政務調査費につき、「補助参加人Aに対する平成15年度政務調査費のうち381万3363円の返還請求をしない事実」を請求対象とする住民監査請求が、請求対象の特定に欠けないとした事例 仙台高判平17.10.12
○ 控訴人(住民監査請求請求人)の本訴請求は、要するに、被控訴人が補助参加人(政務調査費受給会派)らに対し本件政務調査費から必要経費として支出した額を控除した残額の返還を求めないという不作為を違法として、補助参加人らに対しそれによる不当利得返還請求をすることを求めるもので、地方自治法242条の2第1項4号所定の請求のうち、「怠る事実に係る相手方に不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関に対して求める請求」であり、補助参加人らの支出の違法を理由にその支出先から補助参加人らへの返還を求めるものではない。したがって、本訴の前提としての住民監査請求の対象は、地方自治法242条1項所定の事項のうち「違法若しくは不当な公金の支出」ではなく「違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」(怠る事実)であるといわなければならず、その特定においても「怠る事実」が他の「怠る事実」と区別して特定認識できるかが問われることとなる。 |
| 政務調査費について議員ごとに疑問のある支出があるという具体例を摘示し、政務調査費の全部又は一部が違法又は不当に支出されているとするとして政務調査費の全部または一部の返還を求める等の措置を要求する住民監査請求について、政務調査費の報告書には領収書の添付が要求されていないこと、議員の大半が政務調査費の収支に係る会計帳簿の閲覧要請にも応じなかったこと、そのために原告らにおいては上記の程度以上に個々の支出のいずれが違法又は不当であるかについて具体的に指摘することが困難であったことに照らすと、監査対象としての特定が足りているとした事例 青森地判平18.10.20判例タイムズ1244.149
○ 本件においては、原告らは、A議員らに対して平成15年度に交付された政務調査費の全部又は一部について、議員ごとに疑問のある支出が含まれているという具体例を摘示するとともに、政務調査費の全部又は一部が違法又は不当に支出されているとして、その相当額の返還を求めるなど必要な措置を採るよう被告に勧告するよう求めて監査請求をしているのであり、監査対象としては平成15年度にA議員らに対して交付された政務調査費の全部又は一部であるとして認識することができる。そして、本件条例及び本件規則において本件政務調査費の報告書には領収書の添付が要求されていないことや、議員の大半が原告らからの本件政務調査費の収支に係る会計帳簿等の閲覧要請にも応じなかったことから本件政務調査費の各科目の具体的使途の大半が不明であり、そのために原告らにおいて上記の程度以上に政務調査費の個々の支出又は使用目的のいずれが違法又は不当であるかについて具体的に指摘をすることが困難であったことに照らすと、本件住民監査請求においては、上記程度の特定をもって監査対象としての特定が足りているというべきである。 |
| 政務調査(活動)費に係る住民監査請求において、支出先の名称を特定することによりこれに対する複数の支出を個別に摘示しなくても対象となる怠る事実とそうでないものとの識別は可能であるし、これらを一体として違法性又は不当性を判断することが可能かつ相当ということができるから、住民監査請求の対象の特定に欠けないとした事例(複数の支出を一体として違法性又は不当性を判断することが可能とする判断を含むが、判旨を踏まえ、一般的な特定審査の事例として本項に掲出した) 神戸地判平29.4.25判例時報2381.47
○ 監査請求書によると、議員Aは同級生の会社やペーパーカンパニーの領収書を利用して政務活動費等を着服していると主張されており、ペーパーカンパニー分領収書として、平成25年11月30日から平成26年3月20日までの合計216万9800円分が添付、同級生会社1領収書として添付されているものは、平成23年3月26日(平成26年3月26日の誤りと思われる。)から平成26年2月25日までの車両リース代合計72万円であるが、1台の単価が極めて高く、領収書の日付に誤りが多いことなどから、適正な支出であるとは考えられない、同級生会社2へ現地調査に行ったが、同社は通常の介護施設であり、収支報告書に添付されている領収書には「通信費、コピー機パソコン利用費その他」として一律3万円の領収書が10枚分添付されているが、実態のないものと思わざるを得ないので、議員Aの支出は実態がない支出であり、違法、不当な支出と判断される、としており、事実を証する書面として、使途項目別の領収書等添付様式に平成25年度中の一定期間分の各整理番号を付した領収書の写しが添付されている書面を提出した。 |
(2) 一体的な財務会計行為等に係る特定判断
上記1③(最判平成18年4月25日)以前の事例を含みます(ただし、全事例、平成2年最判より後のものです)。
| 港湾整備事業に伴う漁業補償交渉に際し、接待のために支出した食糧費が社交儀礼の範囲を逸脱した違法なものであるとして、県知事等に損害賠償を求めた住民訴訟(4号請求)につき、本件支出は一体としてその違法性又は不当性を判断することが相当であるから、個々の支出が具体的に摘示されていなくても、監査請求の特定に欠けるところはないとした事例 広島地判平7.3.16判例地方自治142.18 (本件における監査請求書での請求人が本件支出を不当とする理由の主張は大要、〈1〉A漁協分の補償交渉妥結後の支出は本来必要のないものであるから全額不当であること、〈2〉新聞報道によれば1回の支出が本件内規の基準を大きく超えているから不当であること、〈3〉昭和59年度におけるA漁協以外の漁協との補償交渉は1回だけであるから、それ以外の支出は全額不当であること、〈4〉本件支出は本件各漁協全体で138回もなされており、常識の範囲を超えて不当であること)○ 本件監査請求の対象とされた本件支出は、その個別的、具体的な支出の時期、金額は明らかにされていないが、昭和59年度及び昭和60年度の本件漁業補償交渉における本件各漁協との接待に支出された食糧費であり、その目的、名称、期間からして包括的に他の支出と識別することができ、その違法又は不当とする理由については、昭和60年度のA漁協に関する食糧費の支出について、同漁協との漁業補償交渉が妥結した昭和60年3月20日以降に行われた飲食にかかるからすべてを不当な公金の支出とし、また、右以外の部分(昭和59年度のA漁協ほか10漁協に関する食糧費及び昭和60年度のA漁協を除く10漁協に関する食糧費についての部分)も含めた本件支出について、本件内規の定める一人1万5000円という基準に違反し、社交儀礼上相当と認められる範囲を超えた飲食であるから不当な公金の支出としていることは明らかであり、本件支出の大部分が不当であると主張しているのであって、本件支出につき、一体としてその違法又は不当性を判断することが相当である(監査請求の性質に照らし、監査請求の特定は、他の支出と識別して違法又は不当性を判断するに必要な程度で足り、具体的な損害賠償額が直ちに確定できなくとも、請求の特定に欠けることはないと解する)から、その限度で、個々の支出について個別的、具体的に摘示されていなくても、監査請求の特定に欠けるところはないというべきである。 |
| 副主幹以下の全職員3千数百名への一律定額の手当支給を対象とする住民監査請求について、監査対象を一体としてその違法又は不当性を判断することが相当な場合といえるので、個々の支出について個別的、具体的に摘示されていなくとも監査対象の特定に欠けないとした事例 宇都宮地判平9.12.18判例タイムズ981.93 (市長と職員組合の合意により、一般職員3千数百名に対し一律定額の一時金を支給することとし、ただし給与条例上の根拠がないため、職員互助会からの貸付形式で支給し、後日超過勤務手当等のカラ支給、増額支給で清算したことについて、市長に損害賠償を求める住民訴訟)○ 住民監査請求においては、その対象とする当該行為又は怠る事実を他の事項から区別して特定、認識できるように個別的、具体的に摘示することが必要であり、当該行為等が複数である場合には、原則として、各行為等を他の行為等と区別して特定、認識できるように個別的、具体的に摘示することを要するものといわなければならない。しかしながら、当該行為等の性質、目的その他諸般の事情に照らし、これらを一体とみてその違法又は不当性を判断するのを相当とする場合においては、その限度において、個々の行為等を逐一具体的に摘示することなく監査請求の対象を特定し得るものというべきである。その際、監査請求の対象の特定の有無については、事柄の性質上、住民訴訟と同程度の厳密な特定を要するものではなく、また、その判断に当たっては、監査請求書の記載のみならず、これに添付された事実を証する書面の記載や監査請求人が提出したその他の資料等を総合考慮すべきである。 ○ これを本件についてみるのに、本件監査請求の対象とされた支出は、その個別的、具体的な支出の時期、金額は必ずしも明らかでないものの、事実証明書その他の資料等を総合考慮すれば、平成元年9月ないし12月にかけて副主幹以下の全職員に支給された超過勤務手当等のうち一人当たり2万2000円に相当する部分を一律にその対象とする趣旨であり、これを包括的に他の支出と識別することは可能であるし、その違法とする理由については、右支出が架空の超過勤務等に対するヤミ手当であるから、およそ違法な公金の支出であるとしていることが明らかであって、右支出については、その性質、目的等に照らし、一体としてその違法又は不当性を判断することが相当な場合といえる(監査請求の性質に照らし、監査請求の特定は、他の支出と識別して違法又は不当性を判断するに必要な程度で足り、具体的な損害賠償額が直ちに確定できなくとも、請求の特定に欠けることはないと解する。)から、その限度で、個々の支出について個別的、具体的に摘示されていなくとも、監査請求の対象の特定としては欠けるところはないというべきである。 |
| 市営地下鉄延伸工事の事業全体あるいは本件鉄道全線の建設工事のために公金を支出することの差止めを求める住民監査請求について、公金支出の原因として本件事業に関する工事あるいは本件計画というものが特定されており、差止めの対象となる公金支出の範囲を識別することができるので、対象が特定されているとした事例 横浜地判平13.1.17判例地方自治224.82
○ 本件各監査請求は、本件事業に対する公金支出自体が違法であるとして、その差止めを求め、全線地下式にするように工事計画を見直すことを求めたのであり、一部地上式を採用した本件計画に対して、包括的に一切の公金の支出を差し止める趣旨でされたと解することができる。・・・本件各監査請求の対象が特定しているかという争点については、本件事業全体あるいは本件鉄道全線の建設工事のために公金の支出をすることを差し止めるという監査請求により、請求が特定しているかが問題とされるわけである。そうすると、このように公金支出の原因として、本件事業に関する工事あるいは本件計画というものが特定されているから、本件各監査請求が求められた差止めの対象となる公金支出行為の範囲を識別することができる。また、原告らは、本件事業の適否ないし本件事業に先行する本件都市計画決定等の違法性を本件公金支出の具体的な違法事由として主張するのであるから、本件公金の支出行為を一体とみてその適否等を判断することができる。換言すれば、本件のような場合は「当該行為等の性質、目的等に照らしこれらを一体とみてその違法又は不当性を判断するのを相当とする場合」に該当するといえ、本件各監査請求の対象は特定されているというべきである。 |
| 学校建設事業に係る住民監査請求において、現に行われた支出命令をすべて対象とする趣旨が見て取れ、監査請求がされた時点で総額8億3102万4565円の各支出命令が既に行われていたことが認められるから、本件監査請求はこれらの各支出命令の一部ではなく全部を対象としたものであって、請求の対象を各支出命令とする点において、その特定に欠けるところはないとした事例 東京高判平27.9.28判例地方自治410.33
○ 本件監査請求書には、請求の趣旨として、監査委員は、区長Aに対して、個人の資格においてH地区小中一貫校建設請負工事費用である金202,039,786円を区に返還させるための、必要な措置を講ぜよ。また請求者の知り得ない、この建設工事で年度を跨いで区議会へ報告なく繰越した他の区負担金全てを返還させよとの記載があり、請求の原因として、区長が本件各契約についてした専決処分の区議会への報告、本件事故繰越し、本件事故繰越しの同議会への報告という本件の経緯に関する記載に引き続き、「Aの責任原因」として、「故意で区議会の承認を得ずに区の支出負担行為を、事故を装い平成24年度に支出する事は明らかに違法である。」、「事故繰越として区議会に報告された、平成24年度に文部科学省からの補助をうけた国庫負担金(国の負担分は法令により1/2)以外の1/2区支出負担行為分、学校施設環境改善交付金(国の負担分は法令により1/3)以外の2/3区支出負担行為分と残りの当該請求人が知り得ない、平成24年度に支出された分。そして、平成24年度に入って支出された、区立C学園への区支出負担行為分の202,039,786円の損害を区財政へ与えたことは明白である。」、「区立C学園への平成23年度分の国庫負担金、学校施設環境改善交付金等と予算の繰越は、区議会での議決が可能であったのに故意に怠った。」、「国から平成23年度に使い切れなかった国庫負担金、学校施設環境改善交付金の交付を受け、区負担分を議会に未議決で事故繰越として平成24年度に202,039,786円損害を与えたことは明白であり、区はAに求償権を有する。」、「地方公共団体が、公務員に対し求償権を有する場合、当該地方公共団体は、当該公務員に対し、求償権を行使しなければならない。」等の記載がある。また、本件監査請求書に添付された本件計算書には、前記のとおり、本件整備事業に係る平成23年度の支出未済額と同額の831,024,565円が平成24年度に繰り越され、その支出のための財源として未収入の特定財源628,984,779円と一般財源202,039,786円とが予定されている旨の記載がある。しかしながら、実際に支出がされた金額の記載はなく、本件監査請求書に添付された事実を証する他の書面にも、支出の金額や年月日等を記載したものはなかったことが認められる。 |
| 本監査請求では、請求人は、万博誘致推進事業自体が違法と主張し、特定年度以降の「2025日本万国博覧会大阪誘致推進事業」に伴う公金の支出を対象として既に支出されたものに係る損害賠償と今後の支出の差止めの措置を求めていたことが認められるから、請求を受けた監査委員においては上記事業に伴う公金の支出を全体として一体とみてその違法性を判断するのが相当であるということができ、また同事業関係支出を上記事業名目で整理公表していたという事情のもとでは、監査の対象は識別可能となっているとした事例 大阪地判令2.11.13判例地方自治477.22 (2025万博誘致推進するための公費支出及び建設費用等の公金支出の差止め、2025万博に関し既に支出した無駄な費用相当額の賠償請求することを求める旨の監査請求に基づく住民訴訟)○ 監査請求者は、夢洲での2025万博という事業が違法であるから、その事業に伴う公金の支出全体が違法であると主張し、当該各地方公共団体が公表した資料に基づき、平成28年度以降の「2025日本万国博覧会大阪誘致推進事業」に伴う公金の支出を対象として、既に支出されたものに係る損害賠償と今後の支出の差止めの措置を求めていたことが認められるから、請求を受けた監査委員においては、上記事業に伴う公金の支出を全体として一体とみてその違法性を判断するのが相当であるということができる。 ○ また、本件各監査請求において上記事業に伴う支出の特定は、当該各地方公共団体が公表した予算・決算の内容に基づいてされたものであり、当該各地方公共団体では、上記事業に伴う支出を「2025日本万国博覧会大阪誘致推進事業費」の名目で整理して公表していたと認められるから、本件各監査請求のうち損害賠償請求に係る既支出分が、当該各地方公共団体において平成28年度以降に上記の名目で支出されたものを指すことは明らかである。そうすると、複数の支出につき個別の摘示がされていないとしても、請求を受けた監査委員においては、上記の名目に基づいて、監査の対象となる支出と対象外の支出との区別をすることは可能ということができる。 ○ そして、上記の名目に基づいて事業を特定することにより、本件各監査請求において差止めの対象となる公金の支出の範囲も識別することが可能となると考えられ、そうするとさらに、その公金の支出がされることが相当の確実性をもって予測されるかどうかの判断を可能とする程度の特定性もあったということができる。 ○ よって、本件各監査請求は、複数の支出につき個別の摘示はされていないが、経費の支出全体を違法とする事業が特定されることによって、監査の対象が識別可能なものとなっていると認めることができる。 |
(3) 請求の一部の特定を認める判断・請求対象の一部の措置を求める事案
請求の一部について、対象行為等の特定を認めた事例を紹介します。
請求の一部について、請求対象の特定を認め、それ以外の部分は請求対象不特定である場合、下記裁判例によれば、特定要件を満たしている部分の請求について、適法な監査請求と認め監査を行うこととなります。
また、請求対象不特定とされた部分について、同一の住民が、請求対象を十分に特定したうえで住民監査請求をした場合、同一住民の同一の財務会計行為等についての再度の監査請求であることを理由に不適法とすることはできないと考えます。
これは、同一住民の同一の財務会計行為等についての再度の監査を認めないとした昭和62年最判の論旨は、監査委員の監査結果に不服がある場合は、請求人たる住民は、住民訴訟を提起すべきであり、重ねての監査請求を行うことは許されていないからとしているところ、住民監査請求の要件審査で不適法請求とされた部分は、適法な監査を経ていないので、この昭和62年最判の論旨には該当しないこと、また適法な監査請求を不適法却下した場合に、住民訴訟の提起および再度の住民監査請求のいずれも可能と判断した最判平10.12.18民集52.9.2039の趣旨からすれば、監査委員が適法に要件審査した結果、不適法請求と認めたものについても、適法な請求内容に転化可能である限り(請求対象の特定不十分というのは、請求人が住民でないなどそもそも補正不能の問題ではなく、多くは補正可能な技術的な問題でしょう)、そうした請求は不適法とすべき論拠に欠け、結局、住民監査請求の自浄的機能もあわせ考えれば、同一住民による同一請求の論理を持ち出して不適法判断すべき理由がないことになるからです。
なお、平成30年大阪地判の例は、他の事例と異なり、住民訴訟において原告(請求人)が違法と主張する支出の一部の返還請求となっており、その一部が支出のどの部分を指すのか特定されていないので不適法請求と被告が主張したというものですが、裁判所は、請求対象の財務会計行為は、原告が違法と主張する全部の支出と特定されているとし、その上で同件は一部請求として本案の審理をしていますが、住民監査請求についても、ある財務会計行為等を特定し、その一部について是正等の措置を求める場合もあり得ます。
こうした住民監査請求がなされた場合、民事訴訟での金銭債権に係る単純一部請求と同様に扱えばよく、是正等を求める対象が特定されていないことをもって、請求対象不特定とすべきではないと考えます。ただしこうした請求の場合、監査の対象は請求人が違法不当と主張する財務会計行為等の全体に対して及ぶため、この財務会計行為等について同一請求人が、是正等要求をしなかった残部分に対し再度の住民監査請求を行うことは、認められないと考えるべきです。
これは、住民監査請求の対象は請求人によって既に特定されており、かつ同一請求人の同一対象に係る再度の住民監査請求を認めない昭和62年最判および監査委員が請求人の請求に拘束されず監査結果をおこなうことができるとする平成10年最判による限り、監査委員は、請求人が違法不当と主張する財務会計行為等の全部について監査を行い、請求人の請求内容にかかわらず、監査委員は監査対象の全部について勧告してもかまわないのであり、結局、請求人は請求の全部について適法な監査請求を経ている(よって再度の同一財務会計行為等に対する監査請求はできない)ことになるためです。
| 監査請求の内容が包括的に過ぎ監査対象の特定に欠けるが、添付書面の記載や請求人提出のその他の資料等を総合斟酌するところによれば、一部については対象が特定されているとして、その部分については適法な請求とした事例 東京高判平3.10.30行裁例集42.10.1704 (学校勤務職員に超過勤務手当のカラ支給がされているので、その部分の返還を求める住民訴訟)○ 本件の監査請求書には、冒頭に「A区長及びA区教員委員会(事務局を含む)に対して」と括弧書し、「請求の主旨」として、A区立の小、中学校では、長年の間、事務職員等の超過勤務手当を、超過勤務をしたから(実績)ではなく、実際に超勤をしていないのに、予算で割り振る、いわゆる空支給をしてきたこと、これら超過勤務手当の空支給は区教委ぐるみのものであること、本体小学校の現業関係主事の実際の勤務時間の状態からして、超過勤務すべき仕事はないこと等の記載がされており、「措置要求」として、実績のない空支給分超過勤務手当を過去1年前に遡り返還すること等の記載がされていることが認められ、これらの記載のみからすると、本件監査請求は、A区立の小、中学校全部の事務職員等に対する過去1年間分の超過勤務手当の支給を全体として抽象的に問題としているように見え、そうだとすると、超過勤務手当の支給が違法であるか否かは、当該個々の職員が手当の支給を受けたという特定の日に現実に超過勤務をしたか否かを認定しなければ判断できないのに、個々の職員や支給を受けた日も特定されていないことからして、包括的に過ぎ、具体的な当該行為等の特定に欠けるものといわなければならない(監査請求をする側からすれば、超過勤務全部を問題にしているのであるから、それで監査の範囲も判るはずだといいたいのであろうが、先に判示した住民監査請求の制度の趣旨(注:最判平2.6.5判旨)からいって、このような方法によって具体的な特定がなされたと解することはできないというべきである。) ○ しかしながら、控訴人は、本件監査請求にあたり、本件小学校の勤務時間の割振りを説明した書面、控訴人が昭和59年4月1日に本件小学校に着任する以前から本件小学校では事務職員等に超過勤務をしていないにもかかわらず超過勤務手当を支給するいわゆる空支給がされていること、控訴人が同校の主事達の超過勤務命令簿を調べたところ、同僚の訴外N主事のみは控訴人の勧告を受け入れて同年7月から不正受給をやめているが、その他の主事達は、その後も毎月予算で割り振った超過勤務手当を受給していることが判明したこと、被控訴人Tが学芸会や作品展の前に午後4時を過ぎて残業をしていたことは数回見掛けたが、その他の主事達が残業をしているのは見たことがないこと、被控訴人本件小学校校長は、主事達が実際に超勤していないのに毎月超勤手当を支払っているのはなぜかという控訴人の問いに対し、あれ(超過勤務手当)は予算で割り振ることになっていると答えたこと、現在(昭和62年4月2日)も主事達への超勤手当の空支給は続いていること等々を記載した申立書を提出したことが認められ、さらに、控訴人は、本件小学校の主事達に対する具体的な超過勤務手当の支給状況等を明らかにする書面として、被控訴人Tら10名を含む本件小学校の主事の昭和60年4月から同年6月分までの超過勤務等命令簿の写し、及び右の者らの昭和61年度の月別超過勤務手当執行状況一覧表を提出したことが認められる。そして、控訴人の提出した右の各書面によれば、控訴人は、監査請求書においてはA区の小、中学校の事務職員等全体の問題であることを指摘しつつ、添付書類において、自己が実際に見聞したところに基づいて、具体的に本件小学校の主事に対する超過勤務手当の支給は、被控訴人Tの学芸会等の前におけるわずかの例外を除いてすべて「空」であり違法であることを主張しており、しかも、被控訴人Tら10名に対する昭和60年4月から6月分までの超過勤務手当の支給については、前記超過勤務手当命令簿の写しにより各々その超過勤務をしたという日及び時間並びに手当の額も明らかにされているのであるから、少なくともこの部分については監査を請求する対象は具体的に特定されていると認められる。したがって、右部分に関する監査請求に限っては、本件監査請求は、特定性に欠けるものではないといわなければならない。 |
| 監査請求の内容が包括的に過ぎ監査対象の特定に欠けるが、請求の内容から対象が特定されている部分については適法な請求とした事例 大阪高判平4.12.25判例地方自治114.35 (定数超過職員への給与に係る損害賠償請求を求める住民訴訟)○ 本件監査請求において摘示されている財務会計上の行為が「定数超過職員に対する給与の支出」というだけのものであって、特定の職員に対する給与の支給を具体的に指摘するものでなかったところ、単に定数超過職員というだけでは、それがどの職員であるかを特定することはできず、ひいてはどの職員に対する給与支出が違法な財務会計上の行為たる公金の支出に当たるのかも不明というよりほかはない。 ○ しかしながら、本件監査請求の内容によれば、無試験で採用された被告の選挙運動員19名が右定数超過職員に含まれているとの趣旨に解される摘示があり、本件監査請求書にはそれら職員が具体的に誰を指すのかは記載されていないものの、昭和61年○月○日施行の市長選挙における○事務所の選挙運動員であった者で、その後市の市長の事務部局に採用された者ということでその範囲はおのずから特定されてくるはずであるから、本件監査請求は、採用後昭和63年2月分までの右19名に対する給与の支出を対象とするかぎりにおいて、他の行為と区別して特定認識できる程度に個別的、具体的に摘示されているものということができるから、請求の対象の点でも特定性に欠けるところはないといわなければならない。 |
| 高校において教職員が違法なヤミ手当、ヤミ休暇の慣行により給与を不当に利得しているとして、その返還を求める住民訴訟において、請求の一部については監査請求の対象が特定されている(その他は特定を欠く)とした事例 東京地判平成5.6.7判例タイムズ865.180 (教職員のヤミ休暇・ヤミ手当返還を求める住民訴訟)○ ヤミ手当に係る監査請求書には、「・・・高等学校教職員のやみ手当に関する措置請求の要旨」との表題の下に、「請求の要旨」として、実勤務がない場合は規定上定時制通信教育勤務手当及び通勤手当を支給することができないとの規定があるため、A高校定時制においては長期休業に掛かる月及び長期休業期間中には実際に勤務しなくとも右規定に「引っかからない」ように出勤簿に押印するよう指導している旨記載され、「措置要求」として、「前記支給要件に欠けるものについて過去1年間に逆のぼり返還すること」と記載されていることが認められる。このことと前記の当事者間に争いのない事実とによれば、同監査請求は、昭和58年4月14日から1年間の期間におけるA高校定時制の教員に対する定時制通信教育勤務手当及び通勤手当の支給について、その中に長期休業期間中実際に勤務しなかったために支給の要件を欠くものがあり、これが違法であるとして、これによって東京都が被ったとする損害の回復を求める趣旨のものであることが認められる。そうすると、かかる各手当の支給が違法であるかどうかは、右各手当の支給に関する制度の建前上、支給を受けた個別の職員について、支給を受けた月毎に支給の要件を充足する事実がないかどうかを審査しなければこれを判断することができないものであるから、監査請求書に右の程度の記載しかされていないのでは、到底請求人が本訴において違法であるとする各手当の支給の全部について、その特定認識が可能となるような個別的、具体的な摘示がされているとはいい難く、監査請求の対象としてはその特定に欠けるものというほかはない。 ○ もっとも、前掲(書証番号略)には、「昭和58年8月のH教諭(別紙申立書)に対する指導は別紙の通りです」「S教諭の8月18日は私が電話で出勤を確認した処、『良く憶えていないが多分、出勤していなかったと思う』とのことでした」「その他にもG教諭の8月19日、N教諭の8月12日も私が昭和58年9月19日から20日の午後に見たときは押印がありませんでした」「出勤簿整理担当のY主査が7月初め~9月20日の出勤簿の整理をしたのは9月21日でした。翌9月22日に私が出勤簿を見たときには既にG教諭、N教諭、共に押印がありました」との記載があり、右にいう別紙申立書である(書証番号略)には、原告が出勤簿の整理をした際、被告Hについては7月21日から8月31日まで、被告Nについては同月12日、被告Gについては同月19日に押印がなかったためこのままでは同月分の定時制通信教育勤務手当を戻入する必要があると思った旨の原告の供述記載がある。これら同監査請求に際し提出された事実を証する書面の記載に、右に認定した同監査請求の趣旨を総合すれば、同監査請求においては、被告G、被告S及び被告Nに対する昭和58年8月分の各定時制通信教育勤務手当の支給並びに被告Hに対する同月分の通勤手当の支給は、その要件を欠くにもかかわらずされたものであることが指摘されているのであって、右各被告らについての定時制通信教育勤務手当の支給及び通勤手当の支給に限っては、同監査請求の対象として、財務会計上の他の行為又は事実から区別して特定認識され得る程度に個別的、具体的に摘示されているというに足りる。 ○ ヤミ休暇に係る監査請求書には、「試験休み中の教職員のやみ休暇に関する措置請求の要旨」との表題の下に、「請求の要旨」として、A高校定時制においては、9月、12月及び3月の各定期試験の数日間並びに7月の夏期休業前の数日間を授業を行わないいわゆる「試験休み」(クラブ活動期間)とし、この期間中は勤務を要する日であり、自宅研修も許可されていないにもかかわらず、教員と司書にとっては「自由出勤の日」となっており、そのため出勤する教員もいるが1日も出勤しない教員もいる旨、「当方」の記録によると昭和58年12月15日から同月19日までの期間に実際に出勤した教員及びその勤務した時間は別紙のとおりである旨記載され、「措置要求」として、「前記の事実は学校職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例を初め、すべての勤務条例に違反する上、学校職員の給与に関する条例にある“ノーワーク・ノーペイ”の原則に違反であるので、1年前に逆のぼって給与の返還を求めます」と記載されていること、右監査請求書には、右にいう別紙として同月15日に給料等を受領した職員の氏名及びその受領時刻等並びに同月16日、17日及び19日に出勤した職員の氏名等をそれぞれ記載した原告作成の各書面が添付されて提出されたことが認められる。このことと前記の当事者間に争いのない事実とによれば、同監査請求は、昭和58年4月14日から1年間の期間におけるA高校定時制の教員及び司書に対する給料等の支給について、その中にそのいうところの試験休み期間中実際には勤務をしなかったために支給の要件を欠くものがあり、これが違法であるとして、これによって東京都が被ったとする損害の回復を求める趣旨のものであることが認められる。そうすると、かかる給料等の支給が違法であるかどうかは、給料等の支給に関する制度の建前上、支給を受けた個別の職員について、支給を受けた月毎に支給の要件を充足する事実がないかどうかを審査しなければこれを判断することができないものであるところ、右認定のような監査請求の記載にその添付書類の記載を併せてみても、A高校定時制の教員及び司書に対する昭和58年9月分、同年12月分及び昭和59年3月分の各給料等の支給を問題とする趣旨は窺われるものの、複数の右教員及び司書のうちいずれが右各月において勤務をしなかったにもかかわらずこれに係る減額をしない給料等の支給を受けたのかを知ることはできない。右認定の同年12月16日、17日及び19日の状況に関する各書面の記載についても、これはそこに言及された職員についてそれぞれの出勤状況ないし出勤時刻又は退庁時刻等を指摘するに止まるものというほかはない。原告は、右各書面をもって、A高校定時制に当時在職した教員及び司書のうちそこに出勤時刻等を記載した職員以外の者についてその全員が右各日に勤務をしなかったという事実を指摘するとの趣旨に出たとするものであるとも解し得ないではないが、右監査請求書及びその添付資料にA高校定時制に当時在職した教員及び司書の全員が摘示されておらず、右記載によっても具体的にそのいずれの者がその主張の日に出勤しなかったというのかを読み取ることはできないといわざるを得ないから、右各書面によってそこに出勤時刻等を指摘した職員を除くその余の者の行為を特定して認識することができるということもできない。したがって、監査請求書及びその添付資料の右に認定した程度の記載をもってしては、到底請求人が違法であるとする各給料の支給について、その特定認識が可能となるような個別的、具体的な指摘がされているとはいい難く、監査請求の対象としてはその特定に欠けるものというほかはない。 ○ そうすると、被告G、被告S及び被告Nに対し、昭和58年8月分の各定時制通信教育勤務手当に係る不当利得の返還及びこれに対する法定利息金の支払を求める訴えの部分並びに被告Hに対し同月分の通勤手当に係る不当利得の返還及びこれに対する法定利息金の支払を求める訴えの部分は、いずれも適法な住民監査請求を経たということができるが、その余の部分の訴えはいずれもこれを経たとはいえないから、不適法である。(以下複数の事件について、同様の判断が重ねられている) |
| 県事務所の特定月の全旅費支出を監査対象とする以上は請求対象の特定に欠けるが、同期間の全旅費支出のうち、課名、期間、行き先、行程等を特定し、これらの旅費支出を問題ありとする理由毎に分類して整理した書面を提出しており、少なくとも期間、行き先、行程、旅費の額等が明らかにされる支出については、対象が特定されているとした事例 山形地判平14.2.12判例地方自治237.36
○ 監査請求においては、対象となる当該行為等を他の事項から区別して特定認識できるように個別的、具体的に摘示することを要するところ、本件監査請求は、県○事務所の平成7年及び同8年の各2、3月分の全旅費支出を問題にしているといえ、具体的な当該行為等の特定に欠けるものといわざるを得ない。 |
| 原告が違法と主張する政務活動費の一部の返還請求について、監査対象の特定に欠けないとした事例 大阪地判平30.12.19判例地方自治449.11 (政務活動費返還請求住民訴訟において、被告の本案前答弁として、A党に対して不当利得返還請求をすることを求める部分は、原告らが主張する違法な支出のうちの一部について不当利得返還請求をすることを求めるものとなっているところ、どの支出に関するものかが特定されていないから、この部分は不適法である旨主張)○ 原告らは、本件各支出のうち補助参加人A党の支出に係るもので違法であると主張するもの(事務所費196万3411円、人件費1388万4761円及び事務費123万5324円の合計1708万3496円)の一部である合計1533万4835円について、補助参加人A党に対して不当利得返還請求をすることを求めている。 ○ 裁判所は、本件A党支出の全部についてその違法性を判断し、違法であると判断される支出額が請求額以上であるときはこの請求を認容し、違法であると判断される支出額が請求額に満たないときは違法であると判断される支出額の限度でこの請求を認容し、本件A党支出の全部が違法でないときはこの請求を棄却するのであって、当事者双方の主張立証の範囲、程度も、通常は本件A党支出の全額について不当利得返還請求をすることを求める場合と異なるところはない。そうすると、原告らの本件A党支出に関する請求が特定に欠けるということはできない。 |
(4) 外部資料の利用(参照:平成16年最判)
| 町税・国保税の不能欠損額を対象とする住民監査請求において、不能欠損処理に当たり個々の徴税債権のリストを作成して措置しており、国保税も同様と推認されることから、対象の特定に欠けないとした事例 大阪地判平19.7.27判例地方自治299.56
○ 本件監査請求は、不納欠損処理に係る旧A町の町税及び国民健康保険料の全額について、その徴収を怠る事実が違法であるなどとして、これによる旧A町の損害を補てんするために必要な措置等を講ずることを求めるものであると解される。 |
3 特定の内容に関する実例
(1) 違法性の摘示の必要性
この点に関しては、「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」4(3)ウで述べた通りですが、上記(1)の平成10年東京地判および下記裁判例は、検討の上での参考事例になると考えます。
| 住民監査請求において必要とされる財務会計上の行為または怠る事実の違法性または不当性に関する主張は、監査請求全体の趣旨からみて当該財務会計上の行為または怠る事実が具体的な理由によって、法令に違反し、または行政目的上不適当である旨を指摘すれば足り、特定の法令を挙げてこれに違反する旨までをも常に指摘しなければならないものではないとした事例 東京地判平3.3.27行裁例集42.3.474 (清掃工場建替えに伴い、建設当初周辺住民と締結した協定と異なる内容の施設設計委託料を支出したことについて、契約締結担当職員に賠償を求める住民訴訟。被告は監査請求において、執行機関又は職員が行った財務会計上の行為が特定の法令に違反している等、行為についての具体的な違法性又は不当性の主張がされていない不適法なものとの本案前の主張をした)○ 監査請求において必要とされる財務会計上の行為あるいは怠る事実の違法性あるいは不当性に関する主張は、監査請求の全体の趣旨からみて、当該財務会計上の行為あるいは怠る事実が具体的な理由によって、法令に違反し、あるいは行政目的上不適当である旨を指摘すれば足り、特定の法令を挙げてこれに違反する旨までを常に摘示しなければならないものではないというべきである。 ○ 弁論の全趣旨によれば、監査請求書には、自治体が、第一次協定3条により原則として緑地とする旨が合意されている場所に還元施設を建設することを前提として、反対同盟がAに作成せしめた還元施設基本設計図の作成料を支払うことは、協定に違反し違法であるとする趣旨が記載されていることが認められ、右事実によれば、本件監査請求は、特定の法令を挙げてはいないものの、その全体の趣旨からみて、作成料の支払が、第一次協定3条に違反する施設の建設を前提としていることを理由に、その支払が法令違反となる旨を主張していることが明らかであり、したがって、適法なものというべきである。 ○ そうすると、監査委員が、特定の法令に違反している等の具体的な事実の摘示がないとの理由で本件監査請求を却下したのは、適法な監査請求を誤って却下した不適法なものというほかはなく・・・。 |
| 食糧費の支出が違法であるとする住民監査請求につき、約200件の支出のうち領収書等が添付された6件以外の支出については、領収書が偽造され又は違法支出が隠されている疑いが濃厚である旨の記載がなされているにすぎないから、違法・不当な行為が個別的に特定されているとはいえないとした事例 東京地判平10.9.16判例タイムズ1041.195
○ 本件監査請求の対象たる支出は、その監査請求書に引用された「別紙」により特定されることになるが、この「別紙」は、本件食糧費に関する情報公開可否決定通知書に添付されていたものであって、別紙1の「支出項目」欄の記載を文書の表題とする文書の一覧表であり、支出の日時、金額の記載はないが、各支出そのものは、摘示された開示文書によって特定が可能であるということができる。 |
(2) 執行機関・職員および措置を求める相手方の摘示の必要性
「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」4(3)イで述べた通り、請求対象となる財務会計行為等について権限を有する執行機関・職員の特定をすることが、住民監査請求の適法要件かについては、裁判例上、見解が一致しません。
ただし、裁判例の大勢は、監査の対象となるべき財務会計行為等が特定されていれば、監査委員において監査対象者たる財務会計職員等を特定することは容易である一方、自治体の財務会計規程類は相当に複雑であり、一般住民が特定の財務会計行為等について、だれに権限があるのか判断することは困難であることを踏まえ、この特定は請求要件としては不要とすると見受けられます。
筆者も、当該職員の特定をすることは、「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」4(3)イ住民監査請求の要件としては不要であると考えます。
また、損害補てん等の相手方の特定については、最判平10.7.3集民189.1によれば、そもそも必要とされません。
| 監査請求の対象となる行為が特定されている以上、支出行為者を特定して挙げていないからといって不適法とするのは相当でないとした事例 東京高判平3.10.30行裁例集42.10.1721 (学校勤務職員にヤミ休暇が与えられているので、その部分の給与返還を求める住民訴訟) ○ 被控訴人(一審被告)らは、控訴人(一審原告)において給与支出行為を問題とするのであれば、誰のどの支出行為を監査の請求の対象にしているかを明らかにすべきであるのに、これが明らかでないと主張するが、専門家ではない一住民に対して監査委員に住民監査請求をする権能を与えている地方自治法の趣旨、及び支出命令権者を特定することは部外者にとってはしばしば非常に困難である(法律に詳しい者にとってすら、難解である。)ことを考えると、本件監査請求の対象とされる行為が特定されている以上は、支出行為者を特定して挙げていないからといって、これが不適法であるとするのは相当ではないものというべきである。 |
| だれを監査対象者とするかということは監査請求の本質的な部分であり、単純な形式上の不備と同視して監査委員に補正を促す義務があったということはできないというべきであるとした事例 名古屋高判(金沢支)平9.9.3判例タイムズ972.172 (県立美術館所蔵品の処分について教育委員会委員長に損害賠償等を求める住民監査請求を経た住民訴訟。なお県の教育財産の管理者は教育長であるため、住民監査請求提起の際、監査委員から請求人に、県教育委員会委員長による売却、焼却が不当違法である旨の記述があるが、財産の処分は、知事の補助執行者である教育長が所管する事務であるので補正するよう要求したが、最終的に請求人は補正しなかった) ○ 地方自治法には、住民監査請求に関し補正手続を定めた条項は存在しないし、監査委員に対して要件を具備しない請求に対する補正を促す義務を課するような条項も存在しない。そうすると、地方自治法の規定からは、不適法な住民監査請求について監査委員に補正を命じたり促す義務を課していないと解するのが相当である。もっとも、行政手続法7条は、行政庁に、形式的要件に適合しない申請に対して補正を求めることを義務づけていること、行政不服審査法21条は、審査庁に、審査請求が不適法であって補正が可能な場合には、相当の期間を定めて補正を命じることを義務づけていること、国税通則法91条は、国税不服審判所長に、補正可能な審査請求について相当の期間を定めて補正を求めることを義務づけていること、さらに住民監査請求の制度が普通地方公共団体の財政の腐敗防止を図り、住民全体の利益を確保する見地から、住民の請求により当該普通地方公共団体の執行機関や職員の財務会計上の違法な行為等の予防、是正等を自治的、内部的処理によって図ることを目的とした制度であること、住民監査請求を行うについては期間制限があり、同一の事項について再度の住民監査請求はできないと解されていること等からすると、容易に補正できる形式上の不備があるような場合には、監査委員においてその補正を求める権限があることはもとより、補正を促す義務があること、すなわち補正を促さずに直ちに監査請求を却下することは許されないと解する余地がある。 |
| 4号訴訟において当該職員又は相手方がその氏名等でもって特定表示されていない場合であっても,これを氏名等以外の方法で客観的に特定することができるときは,当該訴えは請求の特定に欠けるところがないとした事例 大阪地判平20.10.31判例時報2050.27
○ 地方自治法242条の2等の規定等からすれば、地方自治法242条の2第1項4号に基づく請求においては、損害賠償又は不当利得返還を求める客体としての当該職員又は相手方を具体的に特定するとともにこれらの者各自に対する損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を具体的に特定することを要するものと解される。そして、当該職員又は相手方の特定は、通常は、その氏名及び住所を表示することにより行うものとされ、また、上記損害賠償請求権及び不当利得返還請求権については、その請求金額を具体的な数額でもって特定表示することを要するものと考えられる。もっとも、地方自治法242条の2第1項4号所定の住民訴訟が自己の法律上の利益にかかわらない当該地方公共団体の住民という資格で特に法によって出訴することが認められている民衆訴訟の一種であることからすれば、住民において特定の財務会計上の行為に係る当該職員ないし当該行為又は怠る事実に係る相手方の氏名等を容易に知ることができない場合も少なくないと考えられ、他方で、上記住民訴訟の被告となるべき普通地方公共団体の執行機関又は職員において上記当該職員又は相手方の氏名等を容易に知ることができるのが通常であると考えられる。しかるところ、普通地方公共団体の住民においていわゆる情報公開条例に基づく情報公開請求を行うことなども含めて相当の注意力をもって調査を尽くしても上記当該職員又は相手方をその氏名等により特定することができない場合にまで常に上記当該職員又は相手方をその氏名等でもって特定表示することを要するものと解すると、上記当該職員又は相手方に対する損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを求める訴訟を提起するみちが封じられる場面も生じ得ることとなって妥当とはいい難い。 |
| 県警の違法支出に係る4号請求において、「当該職員」及び「相手方」がその氏名等によって特定されていない場合あるいは各自に対する請求額が明示されていない場合でも、これらを客観的に特定することができれば当該訴えは請求の特定に欠けるところはないとした事例 福井地判平26.8.27判例地方自治400.26
○ 地方自治法242条の2第1項4号本文に基づく請求においては、損害賠償を求める客体としての当該職員又は相手方を具体的に特定するとともにこれらの者各自に対する損害賠償請求権を具体的に特定することを要するものと解される。そして、上記客体の特定は、通常、その氏名及び住所を表示することにより行うものとされ、また、上記損害賠償請求権については、その請求金額を具体的な数額でもって特定表示することを要するものと考えられるのであって、弁論の終結時点においてこれらの者の氏名及び具体的な数額が特定されていないということは法の許容するところではない。もっとも、地方自治法242条の2第1項4号に基づく住民訴訟が自己の法律上の利益にかかわらない当該地方公共団体の住民という資格で出訴することを法が特に認めている民衆訴訟の一種であること、予算執行権限を有する者が極めて多岐にわたる規則・規程類によって定められていることも少なくないことからすれば、住民において特定の財務会計上の行為に係る当該職員ないし当該行為又は怠る事実に係る相手方の氏名等を容易に知ることができない場合も多いと考えられ、他方で、上記住民訴訟の被告となるべき普通地方公共団体の執行機関又は職員において上記当該職員又は相手方の氏名等を容易に知ることができるのが通常であると考えられる。したがって、訴え提起時点において上記当該職員又は相手方をその氏名等をもって特定表示することを要求することは相当ではない。 |

ある年度の全国会議、なぜか観光シーズン真っ盛りの京都で開催しかも泊まりがけさらにお宿は自分でどうぞ、ってあんたねえ・・・(いうまでもなくこの写真の周りにもゲンナリするほどの人の集団、でも紅葉ベストには1週間早かった)