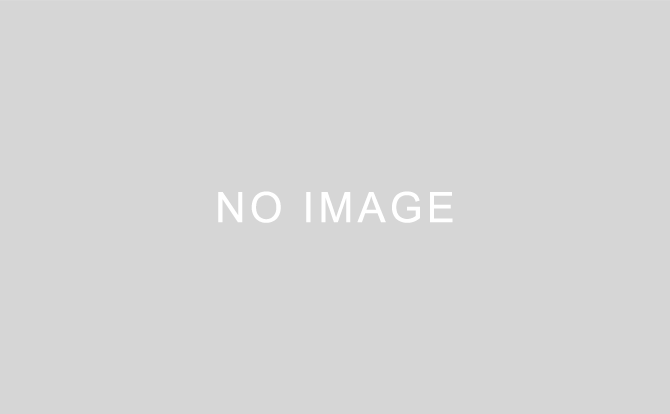本ページの一番下に、本ページのPDF版リンクを設けています。
このページは、「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」2(6)で説明した怠る事実について、主な類型事例にそって説明するページです。
【注】 参考事例の判決文は、必ずしも原文通りではなく、項目の表記にあうように若干の修正をしていることがあります。
1 総論
「(違法・不当に)怠る事実」の要件審査判断においては、怠るとされる行うべき行為は、公金の賦課徴収行為か財産管理行為のいずれかです(これら行為の概念については、「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」2(6)ア、イ参照)。
また請求の対象が「行為義務を」怠っているのかどうかは、通常は要件審査の問題ではありません。なぜならば、行為義務があるかどうかは、違法・不当性の存否判断の核心事項であり、監査を行って判断すべきものであるためです※。
つまり、何らかの不作為について住民監査請求がなされ、それが行為義務を怠っているのかどうかはともかく、実際に住民監査請求で摘示された不作為の状態が存在する場合は、原則的には※※、それを前提として監査をして、実際に行為義務を怠っているのかを判断すべきものです(「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」2(6)ウ(b)参照)。
| ※ たとえば財産管理行為としての金銭債権(損害賠償請求権など)行使を怠るとする住民監査請求がなされた場合、その金銭債権が具体的に発生していれば(金銭債権が弁済期に達して、自治体としては金銭の支払いを債務者から受ける権利がある)、原則としてこの請求を放置することは許されない(最判平16.4.23民集58.4.892)ので、自治体には債権の請求という財務会計行為の行為義務が生じます。この行為義務のある行為がなされていない(不作為)ことが「違法不当に怠る事実」ですが、このうち「不作為」という事実は外形上その存否が明らかですが、「行為義務の存否」は、法的評価を経て判断される事項です。そしてそうした法的評価は、は、違法不当性の核心的事項であるので、本来的に「本案」(訴訟等において、訴訟等を提起する要件が満たされている場合に、請求の実質的な内容に関する判断を行うこと)の問題であり、したがって監査を行ったうえで判断されるべき事項です。 |
| ※※ 例外事例としては、要件審査の段階で、明らかに怠る事実に違法不当性が認められない場合が考えられます。住民監査請求の機能の一つに、住民によって自治体側に自浄的な財務運営適正化の機会を付与するということがある、ということは、監査を行う目的には、住民と自治体(執行機関等)側での当該財産管理行為の適法適正性に関する見解の相違について、当該自治体の機関である監査委員が監査行為を経て結論を出すことがあると考えられ、そうすると、監査を経るまでもなく適法適正性に結論が出る場合は、監査を行う実益がなく、適法な請求とはならないものと考えます(ただしこうした事例は、現実には想定しづらいところがあります)。 |
なお、怠る事実の性質がいわゆる「真正怠る事実」か「不真正怠る事実」かにより、監査請求期間が異なるため、しばしば大きな争点となりますが、これは監査請求期間の判断における問題ですので、そちらで詳しく説明します。
【参考事例(怠るとされる賦課行為の財務会計行為性)】
| 政策的な使用料免除に対する怠る事実の違法確認訴訟において、対象となる使用料の賦課をするかしないかは、町の観光産業の振興政策等の観点からされるべき性質のものであり行政一般の問題であって、当該財産の財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の財産管理行為とはいえないから、財産の管理を怠る事実には該当しないとした事例 札幌高判平24.2.28判例地方自治367.28(民間ホテルの宿泊客に対し、町営温泉施設の入浴券を提示すれば同日中は何度でも利用できるという取扱いをしている場合において、町長が2回目以降の入浴料を賦課しないことは違法であるとして、怠る事実の違法確認を町長に求めた住民訴訟)
○ ホテルAは設立計画段階より、産業育成の見地から町に行政支援を要請し、同ホテル宿泊者が町営温泉施設の利用に関し便宜を受けることが前提とされていたものであり、当時、町には、来町者や観光客に薦めることができる宿泊施設に乏しかったことなどから、ホテルAを経営することは、町にとって、同町の観光産業の発展や雇用創出、地域経済の活性化に繋がるものとの期待の下に、ホテルA経営会社が設立され、同ホテルが、その後建設されたこと、ホテルAは営業開始時から、同ホテルと町営温泉施設とは渡り廊下で連結されており、同ホテルの宿泊客は、一度入浴券を提示すれば、同日中である限りその後何度でも町営温泉施設に入浴できること、町条例には、町営温泉施設の入浴料について、公益上特に必要と認めるときは、これを減免することができる旨規定されているところ、ホテルAの宿泊客に対し2回目以降の入浴料を賦課しないこととしたのは、町の観光産業の発展、地域経済の活性化等を図ることの方策の一つとして、上記減免の措置を執ったものと解することができることが認められる事実関係のもとでは、ホテルAの宿泊客について2回目以降の入浴料を賦課するかしないかは、町の観光産業の振興政策等の観点からされるべき性質のものであるということができ、これは行政一般の問題であって、当該財産の財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の財産管理行為とはいえない |
2 主な類型事例
(1) 怠る対象行為が既になされている場合
この点については、「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」2(6)ウ(b)で説明の通りです。
【参考事例】
| 支払済み公金支出に係る怠る事実の違法確認の訴えを不適法とした事例 京都地判昭54.11.30判例時報962.57
○ 地方自治法242条1項は、「違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担」を「当該行為」とし、「違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」を「怠る事実」として区別し、「違法若しくは不当な公金の支出」は、「当該行為」の内容とされ、「怠る事実」の内容とされていないこと、「怠る事実」とは、財務会計上の作為義務を負担しながら不作為状態を継続している場合をいうことからみて、既になされた公金の支出は、法242条の2第1項3号にいう「怠る事実の違法確認」の対象とならない。 |
(2) 対応不能な行為を行わない状態
公金の賦課徴収や財産管理行為を行うことが不能な場合は、これら行為ができないといって、怠る事実にはあたらないとする裁判例があります(ただし、却下ではなく棄却事例)。
【参考事例】
| 在日米軍施設内にある家屋について、基地司令官に立ち入り調査を拒否されたため固定資産税の賦課徴収をしなかったことは、地方自治法242条の2第1項3号にいう違法に公金の賦課徴収を怠ったものとはいえないとした事例 横浜地判昭54.10.31判例時報947.35
○ 市町村は、固定資産税を賦課徴収しうるものであるが、固定資産税の賦課徴収は市町村が優越的な地位に基づく権力主体として行なうところの行政処分であるから、課税主体たる市町村は、その賦課徴収にあたり、課税客体である固定資産について、その状況、所有者、評価額等必要事項を調査し、課税要件事実を確定したうえで賦課徴収すべきものであることは言うまでもなく、課税要件事実を十分把握することなく課税することは厳に慎まねばならないところである。その反面、市町村は、右調査により課税要件が充足されていると認定される場合に、法令又は条例により、非課税とされている場合又は固定資産税の減免が認められる場合を除いて、その裁量により非課税としたり、固定資産税を減免したりすることは、これまた許されない。 |
(3) 補助金の返還請求
補助金の返還請求事例は、可能性として相当程度にあり得るものと思われます。
一般的には、下記事例のように、何らかの目的外使用を疑われる事象が認められたとすれば、補助金返還請求の不作為の事実はあると主張することは可能でしょうし、その請求義務の存否は、監査を経てでないと判断され得ないことが通常なので、いずれにしても、このような事例で要件審査の問題が生ずることは、まずないものと考えます。
【参考事例】
| 補助金の一部が目的外に使用されている場合、補助金交付決定の取消決定が行われていない時点においても、他用途に使用された場合に合理的な理由なく補助金の返還を求めない場合、返還請求を怠る事実の違法確認訴訟として適法とした事例 仙台高判平27.7.15判例時報2272.35(市が交付した補助金の一部が目的外に使用されているとして、その返還を請求することを怠る事実の違法確認を求める住民訴訟) ※最判平9.1.28も参照
○ 市においては、補助金の返還を求めるためには、他用途に支出された場合にも、補助金交付決定の取消決定を行うことを要するものとされていることからすれば、本件補助金について、補助金返還請求権が債権に属する権利として具体化するのは、本件補助金について、補助金交付決定の全部又は一部の取消決定があった時点ということになる。 |
(4) 過料
裁判例では、過料を科すことは、財政の維持充実を目的とする財務会計上には当たらないため、過料を取り立てないことは、公金の賦課徴収を怠る事実にあたらない、とされています。
過料を科すかどうかは行政判断事項であり、具体に発生した過料債権の管理は別として、過料の賦課徴収を怠る事実を対象とする住民監査請求を不適法とすることは、然るべき結論であると考えます。
【参考事例】
| 過料を科さないことは、公金の賦課又は徴収を怠る事実に当たらないとした事例
徳島地判平2.11.16判例時報1398.57 ○ 地方自治法は、行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができ(225条)、詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については条例でその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する規定を設けることができ(228条2項)、過料を科することを普通地方公共団体の長の担任事務とする(149条3号)旨を定めている。これを受けて、都市公園条例は、県知事は、偽りその他不正の行為により都市公園の使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する旨を定め、さらに、法255条の2は、普通地方公共団体の長がする過料の処分につき、告知弁明の機会を与えるべきこと及び過料の処分についての審査請求ができることを定めているところである。右各規定によれば、条例所定の過料は、都市公園使用料の不正免脱行為があったときは県知事がその不正免脱者に対してこれを科することとし、もって、右不正免脱行為の発生を防止し、適正な都市公園使用料収入を確保するとともに都市公園の維持管理又は行政事務遂行の円滑化を図る目的で設けられた行政罰の一種であって、県知事において右過料を科することは、県財政の維持及び充実を目的とする財務会計上の行為とはいえないと解される。 東京地判平9.7.17判例地方自治171.80 ○ 条例には、偽りその他の不正な手段により(下水道)使用料を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科すると定めているが、この過料は講学上にいう行政上の秩序罰に該当するものであり、過料を科するか否かは財務会計上の行為ということはできない。 |
3 その他の参考事項
(1) 積極行為と怠る事実
怠る事実は、なされるべき行為がなされていないという消極的な事実状態を指すものなので、積極的な行為が存在する場合に、怠る事実として監査対象とすること自体は認められません。
ただし、住民訴訟の場合は、地方自治法242条の2第1項各号の類型に該当しない訴訟は不適法なので、怠る事実の違法確認を求める3号訴訟で対象とされる事実が積極行為の場合は、不適法な訴えとなりますが(参照:上記(1)昭和54年京都地判)、住民監査請求の場合は、請求類型が厳密に定まっておらず、監査対象となる財務会計行為等が請求人において特定されていれば、監査委員は請求人の主張に必ずしも拘束されることなく判断ができるため(最判平10.7.3集民189.1)、住民監査請求の要件審査において、この論点を厳密に考える必要性は薄いものであると考えます。よってたとえば下記裁判例のような事例が住民監査請求で取り上げられ、使用許諾が違法であることの確認及び是正措置を求める旨の請求がなされた場合、3号訴訟のように違法確認は「怠る事実」の場合のみなし得ると解して請求を不適法とするのではなく、監査委員においては、請求人の意思・意図を踏まえつつ、積極行為部分、つまりこの使用許諾が、財務会計行為に該当するか(たとえば知的財産権(地方自治法238条1項5号)の無償使用許諾となっている場合、それが財務的処理を直接の目的とする財産管理行為といえるか等)等について、さらに検討することが適当であると考えます(なお、住民訴訟の要件としての監査請求前置要件については、上記平成10年最判によれば、一般に対象となる財務会計行為等が特定されていればこれを満たすとされるため、監査委員による判断範囲の拡張が住民訴訟の請求適格に影響することは少ないものと考えられるところです)。
【参考事例】
| 県の行った海洋調査の結果使用承諾についての財産管理を怠る事実の違法確認訴訟は、その対象が積極的行為を内容とすることは明らかであるので、当該訴えを不適法とした事例 金沢地判平3.3.22行裁例集42.3.398
○ 地方自治法242条の2第1項3号に規定するいわゆる3号請求は、「公金の賦課・徴収を怠る事実」と「財産の管理を怠る事実」とを対象としているところ、両者は行政機関が法令に基づいて負担する財務会計上の作為義務に反していること、すなわち不作為を対象とする点において共通している。 |
(2) 公金の賦課徴収を怠る事実の「徴収」
ここでの「徴収」について、「賦課」の対象である公権力に基づく公金債権に限らず、幅広い債権を指すとする裁判例があります。ただし、「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」2(6)アに述べる通り、一般的な契約等により生ずる金銭債権の取り立てを怠る事実については「財産の管理を怠る事実」により住民監査請求の対象としてカヴァーすることは可能であり、その意味からすれば、「公金の徴収」の概念を厳密に整理する実益は乏しいところがあります。
【参考事例】
| 不当利得に基づく債権の取立ては、地方自治法242条1項の公金の徴収に当るとした事例
大津地判昭57.9.27行裁例集33.9.1886 (市の公営ガス事業について、大口需要家Aに低料金でガス供給する契約は違法であり、料金不当利得部分の賦課徴収を怠る事実の違法確認を求める住民訴訟) ○ 地方自治法においては、「徴収」という用語は多義的に用いられ(同法223条ないし227条、240条等)、必ずしも、行政主体が法令の規定に基づきその優越的地位において住民に対して金銭給付義務を発生せしめる行政処分をすることを意味するにとどまらない。殊に、同法240条3項は債権の「徴収停止」を規定しているところ、右債権とは「金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利」(同条1項)を言い、これには不当利得に基づく債権も含まれると解されるから、同法においては、「徴収」という用語に、不当利得に基づく債権の取立てという意味をも包含させているものと言わざるを得ない。 (本件控訴審 大阪高裁昭59.5.31行裁例集35.5.679※) ○ 地方自治法において、「賦課」とは、被控訴人らが主張する如く、地方公共団体が法令の定めるところによりその優越的地位においで住民に対して金銭給付義務を課する行政行為をいうのであるが、「徴収」とは、公金についてみても、地方公共団体の歳入を調定し、納入の通知をし、収納する行為をいうのであって、同法上「徴収」という用語は、地方税(同法223条)ばかりではなく、分担金(同法224条)、使用料(同法225条)、加入金(同法226条)及び手数料(同法227条)等にも用いられており、要は、地方公共団体がその有する債権を取立てて収納する行為をいうに過ぎないものである。それ故同法242条にいう「徴収」も、地方税や分担金のみならず使用料や手数料債権の収納をも意味すると解するのが相当であって、必ずしも強制徴収等の行政処分を意味するとは解し得ない。 |
| ※ 本控訴審判決の上記2項目について、碓井p.99は、ガス料金は金銭債権であり、地方自治法所定の財産に該当するのだから、ガス料金徴収懈怠を「財産の管理を怠る事実」も問題を生じる余地はないとするのは、法律の誤解ではないかとする。 |

なぜか写真OKということで撮影したルノワールのイレーヌ・カーン=ダンヴェール嬢肖像(本物)。わたくしは絵はサッパリなのですが、それでも1回お目にかかりたい美女が3人。一人目がこのイレーヌちゃん。普段はチューリヒにおわし遠くてとてもとてもですが、このたび日本に御来駕頂いたので速攻でGo!。ルノワールはまったく自分の趣味から外れるんですが、やっぱりこの絵の本物には茫然の一語。次がエヴァレット・ミレーのオフィーリアちゃん。普段はロンドンにおいでであり夏目漱石にも出てくるせいか日本でも知られた絵です。こちらも先日東京へ御光臨遊ばしたので、某省でのしょーもない(?)用事はさっさと切り上げ(!)森ビルへGo!。こちらも噂違わずすごいの一語。あとはフィレンツェはウフィツィ美術館においでのレオナルド・ダ・ヴィンチのマリア様、白百合もった大天使ガブリエル様をあんた誰みたいなご表情でお迎えなさっているアレですね。かなり前に東京まで遊ばしたのですが、テレビニュースでの人の列のあんまり度にゲンナリして行くのは取り止め、といってもフィレンツェはハンパなく遠く・・・