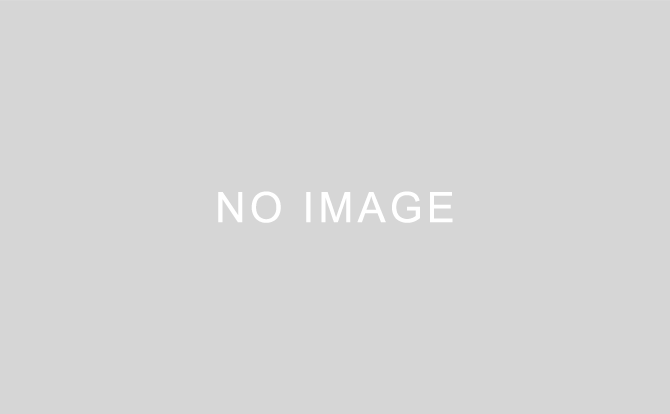本ページの一番下に、本ページのPDF版リンクを設けています。
最終改訂 2023.10.28 改訂箇所は改訂履歴のページ参照
このページは、「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」3で説明した「財務会計行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」について、参考裁判例を紹介するページです。
【注】 参考事例の判決文は、必ずしも原文通りではなく、項目の表記にあうように若干の修正をしていることがあります。
「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」の要件等については、「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」3で説明の通りであるので、本ページでは、参考となる裁判例(年次順)を紹介します。なお、請求要件判断において「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」に違法性要件を要するかについては、ベクトルが異なるものがあるので、留意して下さい。
【参考事例】
特別区内に設置の予定されている新駅駅舎建設費用および用地取得費用に充てるため区が基金に公金を積立している場合において、公金の支出の具体的時期および金額が確定していなくても、「当該行為がなされることが相当の確実をもって予測される場合」に当たるとした事例 東京地判昭55.6.10行裁例集31.6.1291
(特別区が、国鉄新駅を自己負担で設置するための区負担費用を基金に積み立てることとしたが、区が直接費用負担すると当時の地財再建促進特措法に違反する可能性があるため、期成同盟を結成してこれをトンネルとして支出することを計画したことについて、支出差止めを求める住民訴訟)
○ 被告は、期成同盟がまだ設立されてはいないこと及び本件基金の設置目的が新駅設置費用に充てるためと限定されたものではないことの二点をあげて、被告が区の公金から新駅設置費用を支出することが確実であるとはいえない旨主張する。しかしながら、期成同盟がいまだ設立されていないのは、公金支出が将来中止される具体的な可能性があるからではなく、現在まだ新駅建設工事が開始されるに至っていないため、今のところ期成同盟の名でその費用を支払う必要がないからにすぎず、その必要が生ずれば被告が中心となって新駅設置賛同者を加え短時間のうちに期成同盟を設立して前記のような経費処理をすることが予定されているものと認められる。
○ 基金条例がその条文の文言上「公共施設の建設資金に充てるために本件基金を設置する」との一般的表現を用いているとしても、前認定の事実の経過に徴するならば、本件基金が専ら仮称○○○駅新設費用に充てる資金として積み立てられていることは明らかといわなければならない。
○ 区の財産の管理処分権者である被告が仮称○○○駅の駅舎建設費用及び同用地取得費用に充てるために本件基金から区の公金を支出することは、その支出の具体的な時期や金額が現時点において最終的に確定するまでは至っていないにせよ、単にその可能性が漠然と存在するというにとどまるものではなく、公金の支出自体については相当程度の客観的、具体的可能性があるものであって、地方自治法242条1項にいう「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」に当たるというべきである。
震災時の初期消火・飲料水確保のための三角バケツ配付事業に関する補助金支出について、現在は予算に計上されず実際に補助金の交付もされていない等の事情を踏まえ、当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合に当たらないとした事例 東京地判昭56.6.26行裁例集32.6.959
(東京都は、上記趣旨の三角バケツ配付事業について、昭和52、3年度に一部市町に補助金を交付したが、事業見直しにより昭和54年度以降は予算計上していなかったところ、同支出の差止め等を求め提起された住民訴訟)
○ 本件は地方自治法242条の2第1項1号に基づき、「被告は、三角バケツ配布事業について補助金を支出することを中止せよ。」との判決を求めるものであるが、前記認定のとおり、三角バケツ配布事業の補助金は、都において昭和54年度以降予算にも計上されず、実際にも交付されていないのであって、今後近い将来にその支出がなされるであろうと予測することもできないものである。
○ よって、原告の請求は、現在なされておらず、将来もなされるか否か全く不明な行為について、その差止めを求めるものであり、右請求に係る訴えは、訴えの対象を欠くものとして不適法というべきである、と判示。
既に完了した支出に関する1号訴訟は、訴えの利益を欠くとした事例 名古屋地判昭60.9.20判例タイムズ596.38
(市立病院建設工事の進行、経費支出差止めを求める住民訴訟)
○ 本件は地方自治法242条の2第1項1号に基づき本件病院の建設工事の進行及び同工事の請負代金の支出の差止めを求める訴えであるが、右のとおり、既に、本件病院の建設工事は完成し、その請負代金は支払を完了しているのであるから、現時点において、本件請求は訴えの利益を欠くに至ったものといわざるを得ない。
※「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」3(2)ア平成11年大分地判、平成23年大阪地判なども参照
村有地を民間会社にゴルフ場用地として賃貸しようとしていることが違法であるとして村長を被告として提起された差止請求について、現時点においては大規模土地開発事業に関し県条例で義務付けられている開発事業者と知事との事前協議が終了しておらず、いついかなる意見表明がなされるかが未だ不明である現時点においては、単に本件賃貸がされる可能性が漠然と存在するにとどまり、相当程度の客観的・具体的可能性があるものとはいえず、したがって当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合に当らないとした事例 前橋地判平元.1.31行裁例集40.1・2.87
○ 県は、県土の保全と秩序ある開発を図り、もって県民の福祉に寄与することを目的として、大規模土地開発事業の施工に関し必要な規制を行うために県条例を制定しており、土地の区画形質の変更を伴う事業で、当該事業に係る一団の土地の面積が5ヘクタール以上のものを、大規模土地開発事業として、規制の対象と定め、「開発事業を行おうとする者は、当該開発事業に係る計画を作成し、所有権その他土地を利用する権利の取得に係る契約の締結前に、知事に協議しなければならない」と規定し、開発事業を行おうとする者に対し、県条例が定める事項を記載した協議書を提出して、知事との協議(事前協議)を行うことを義務づけている。そして、本件ゴルフ場建設計画は、開発事業に該当するため、訴外会社が村と本件村有林の賃貸借契約を締結するためには、事前協議が必要であり、そのため、訴外会社は、村に計画協議書を提出し、同計画協議書は、同村を経由して、県知事に提出され、事前協議に付されることとなった。
○ 知事は、協議があったときは、その協議に係る開発事業計画について、次の事項を審査し、その協議をした者に対して当該開発事業計画に係る異議の有無を通知するものとする。この場合において、異議あるときは、その理由をあわせて通知するものとする。」と規定し、事前協議において、県知事が事前協議に係る開発事業計画を審査することを定めている。条例所定審査事項は、(1)いっ水、たん水、がけくずれ等による災害の発生のおそれのある土地に関する事項、(2)開発区域に含まれる土地の利用状況に関する事項、(3)開発事業計画に対応する公共施設及び公益的施設についての整備の見通しに関する事項、(4)用水の確保の見通しに関する事項、(5)公害の防止に関する事項、(6)開発事業の地域への貢献度に関する事項、(7)開発事業を行おうとする者の資力及び信用に関する事項、(8)その他規則に定める事項として県条例施行規則に定める事項、であり、更に、県条例は、各事項の審査についての細目を県条例施行規則の定めに委ね、同施行規則はこれを受けて、多岐にわたる細目を定めている。
○ 事前協議における事業開発計画の県知事による審査手続は、実際上、別表大規模土地開発事業計画協議書の事務処理手続一覧のとおり、専ら(県)企画部土地対策課、土地利用対策専門部会及び企画調整会議の各機関が、大規模土地開発事業計画協議書の事務処理要領に基づいて、これにあたり、この審査手続きを経た後、県大規模土地開発事業審議会に諮問し、その答申を受けたうえで、右審査結果について、県知事の意見表明という形で事前協議に係る開発事業計画に対する異議の有無を協議者に通知するという手続きがとられている。
○ 事前協議に付された本件ゴルフ場建設計画の審査手続は、現時点においては、土地利用対策専門部会による現地調査が実施された程度で、未だ、本件ゴルフ場建設計画に対する県知事の意見表明の段階には至っていない。以上の事実によれば、本件ゴルフ場建設計画に関する事前協議の手続きは未だ終了しておらず、この先、県知事が、何時、いかなる内容の意見表明をするかについては、現時点において予測ができない状態にあることが認められる。
○ 開発事業計画に対する県知事の異議の有無の通知は、事前協議に係る開発計画に対し、法的拘束力を有するものではないから、仮に、県知事が本件ゴルフ場建設計画に対し、異議を述べた場合であっても、本件賃貸が不可能になるわけではないが、県条例は、市町村の責務として、「市町村は、県の施策に協力するとともに、当該市町村における土地の保全と秩序ある開発を図るように努めるものとする。」と定め、市町村の県の施策への協力義務を定めていること(なお県条例、更に、事業主及び工事施行者の責務として、県または市町村が実施する施策への協議義務を定めている。)、反面、県条例は、事前協議があったときは、あらかじめ、関係市町村の長の意見を聞かなければならない旨規定し、県知事に対し、事前協議に係る開発事業計画の審査にあたって、当該市町村長の意見を聴取すべき義務を定めており、事前協議の中に当該市町村の意見を反映させる手続きが取られていること、被告においても、本件ゴルフ場建設計画に対し、県知事から異議が述べられた場合には、前記県条例上の市町村の協力義務からして、訴外会社との間で、本件村有林の賃貸借契約を締結することは、事実上できないものと考えていること、が認められ、この認定に反する証拠はないから、実質的には、県知事の意見表明は、本件賃貸に対して事実上の拘束力を有しているものと認められる。
○ 前認定のとおり、本件ゴルフ場建設計画について、事前協議が終了しておらず、県知事が、右計画に対し、いかなる意見表明をするか未だ不明である現時点においては、単に被告が本件賃貸をする可能性が漠然と存在するにとどまり、相当程度の客観的・具体的可能性があるものとはいえず、したがって、地方自治法242条1項にいう「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」に該当しないというべきである。のみならず、仮に知事の意見表明の結果、本件村有林の賃貸借契約が締結されることがあるとしても、前認定のとおり、大規模土地開発事業の施工に関し必要な規制を行うことにより、県土の保全と秩序ある開発を図り、もつて県民の福祉に寄与することを目的として、いっ水、たん水、崖崩れ等による災害の発生のおそれのある土地に関する事項並びに開発事業を行おうとする者の資力及び信用に関する事項等について、事前協議が行われることに鑑みれば、原告らが違法事由の中核として憂慮する災害のおそれと、訴外会社の資力信用の欠如等については、事前協議の段階において、これらに対する適切な措置が講ぜられるものと期待してよいと考えられるから、いわゆる違法の蓋然性が高度に存するとは断定できず、この点からいっても、原告らの主張する違法行為が近い将来行われる確実性があるとは認められない。
議会会派への県政調査費支出が、過去の実績から見て相当の確実さをもって予測されるとした事例 千葉地判平2.12.21判例地方自治84.32
○ 差止請求訴訟は、その性質上差止めの対象である行為(本件においては県政調査費の支出行為)が少なくとも口頭弁論終結時において未だ完了していないことを当然の前提とするものである。そうすると、県政調査費のうち、既に支払いのあった分については、その支出行為が既に完了していることは明らかであるから、本件訴のうち、この分についての差止請求は不適法である。
○ 支出未完了の年度以降の県政調査費の支出の差止請求について、差止請求の訴は、差止めの対象である行為が、単に漠然と予想されるだけでは足りず、当該行為の行われる可能性が相当の確実さをもって客観的に推測される程度に具体性を備えていなければならない。
○ 弁論の全趣旨によれば、原告らが本件訴において、その差止めを求めている県政調査費の支出は、遠い将来にまで亘るものではなく、現在の県政調査費の支出の検査体制が維持されるであろう次年度あるいは、ここ数年間の差止めを求めているものと解されるところ、県議会における県政調査費は、過去十数年に亘り議員報酬と同様に既定の事実として予算が組まれ、毎年例外なく支給されてきていることが認められる。そうすると、このような過去の実績からみて、少なくとも、ここ数年間は、その支出の可能性が相当程度確実であると客観的に推測できる程度に具体性を備えているものということができる。
差止めの請求は、ある財務会計上違法な行為がなされることが相当な確実さをもって予測される場合でなければ行うことができないとした事例 東京地判平5.9.8判例時報4478.99
(児童遊園敷地売却差止めを求める住民訴訟)
○ 地方自治法242条の2第1項1号の請求は、行為の差止めを求めるものであるから、その行為がいまだ行われていないことが前提となる。これに対応する同法242条の監査請求は、当該行為を防止するため必要な措置を講ずべきことを求めるものであって、この請求は、同条1項かっこ内において当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含むとされていることにより、このような条件がある場合にのみ行うことができるものと解される。したがって、この監査請求に対応する訴えも、このような条件がある場合にのみ行うことができるものと解すべきことになる。
○ そして、右にいう当該行為とは、住民訴訟においては、公金の支出等同条1項に列記された財務会計上の行為のうち違法なものをいうのであるから、同法242条の2第1項1号の請求による差止めの対象となる行為も違法な行為でなければならないこととなる。
○ 以上を要するに、同号の差止めの請求は、ある財務会計上違法な行為がなされることが相当な確実さをもって予測される場合でなければ行うことができないということになる。
○ 本件においては、本件児童遊園を廃止する条例が可決されており、その廃止は、甲土地を第三者に売却し、乙土地を第三者から購入して、本件児童遊園を甲土地から乙土地へ移転することを目的として行われるものであることは当事者間に争いがないから、いずれ本件行為が行われることは相当の確実さをもって予測される場合であるということができる。そこで、問題となるのは、本件行為が違法なものとして行われることが相当の確実さをもって予測されるかどうかである。
○ 原告が、本件行為の違法事由として主張するもののうち、本件児童遊園の移転に公益上の必要性のないことをいう分は、公園の設置目的に即した管理ないし維持という財務会計とは別個の行政目的の達成の有無の問題であるから、そのような違法があると主張して本件行為の差止めを求めることは、住民訴訟として行うことができないものというべきである。そうすると、原告が、本件行為の違法事由として主張するもののうち、住民訴訟として意味のあるのは、被告が甲土地の評価額を現実の価額より著しく低廉に評価し、一方乙土地のそれを高額に評価して、両土地の客観的な価額が均衡を失していることを問題とする分であることとなる。
○ (認定事実によれば)甲乙両土地については、いまだこれを売却・購入するについてよるべき価額がおよそ決定されていない段階に止まっているものというほかはない。そうであるとすれば、価格の決定のない物件についてその評価が低廉であるとか価額が均衡を失するとかいうことが生じることはありえないから、本件行為が違法に行われることについては、それが相当の確実さをもって予測される場合であるとは認め難い。したがって、現時点においては、本件行為を対象としてその差止めを求める住民訴訟を提起する要件が欠けるといわなければならない、と判示。
差止請求は、違法な財務会計上の行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合に限り許されるが、本件は違法な契約締結及び公金支出が行われることが相当の確実性をもって予測される場合に該当するとは到底いい難く、よって不適法な訴えとした事例 大阪地判平8.7.17判例地方自治168.44 ※控訴審:大阪高判平9.2.21判例地方自治168.42下掲
(公共施設建替事業に係る建築請負契約の締結及び公金支出の差止めを求める住民訴訟)
○ 地方自治法242条1項1号に基づく差止請求は、違法な財務会計上の行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合に限り許されるところ(同法242条1項参照)、原告は、請求において、非財務会計行為たる本件建替計画の内容の不当性やその通知手続の瑕疵等を主張するにすぎず、これらの瑕疵等によって本件建替計画に係る建築請負契約の締結や公金支出が違法となるものでないことは明らかであるから、右差止請求につき違法な契約締結及び公金支出が行われることが相当の確実性をもって予測される場合に該当するとは到底いい難い。
○ また、原告は、請求において、右請負契約締結及び公金支出の差止と併せて工事の差止をも求めているけれども、地方自治法242条の2第1項1号は、財務会計上の行為の差止請求を求めるにすぎないから、非財務会計上の行為たる工事の差止請求は、地方自治法が認める住民訴訟の類型に該当しない訴えとして、不適法である。
差止請求は違法な財務会計上の行為が行われることが相当な確実さをもって予測される場合に限り許されるが、当該行為が違法であるかどうかは実体法上の判断であり、差止請求の適法要件ではないから、そのような予測がなされる場合に当たらないとしても、本件訴えは適法であるとした事例 大阪高判平9.2.21判例地方自治168.42 ※原審:大阪地判平8.7.17判例地方自治168.44上掲
○ 原判決は、地方自治法242条の2第1項1号に基づく差止請求は、違法な財務会計上の行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合に限り許されるところ、本件においては、本件建替事業に係る違法な公金支出が行われることが相当の確実性をもって予測される場合に該当しないとして、右公金支出に係る差止請求を不適法な訴えと判断したが、地方自治法242条の2第1項1号に基づく差止請求は、差止めの対象である財務会計上の行為が行われることが相当の確実さをもって予測される場合に限り許されるものと解されるが、当該行為が違法であるか否かは専ら実体法上の判断であり、当該行為に違法性のあることが右差止請求の訴えの適法要件であると解することはできない。これと異なる原判決は差止請求の適法性の要件を誤ったもので、失当である(なお、本件建築請負契約が締結されていることからしても、右公金支出がなされること自体は確実であると認められる。)。
第三セクターへの追加出資につき相当の確実さをもって予測できるとはいえないとした事例 東京地判平9.2.25判例時報1603.52
(小田急線・西武線の連続立体交差化事業において、NTT資金による無利息融資の受け皿となり同事業を施行することを目的として第三セクター(株式会社)が設立された。本件原告たる住民は、当該会社への出資等の違法を主張して住民訴訟を提起し、その請求の一つに、同社への将来の追加出資の差止めがあった。被告東京都知事は、都としては現在のところ同社に追加出資する予定はないと本案前答弁で主張し、これに対し原告は、同社の事業規模(千億オーダー)と比べ資本金は10億と過少であり追加出資等の公金支出が相当の確実さをもって予測されると主張する)
○ ・・・当面、東京都・・・が追加出資を行うことが相当の確実さをもって予測されるとの事情は認めることができない。この点につき、原告らは、事業規模との対比における資本金の過少という点から、将来における出資の可能性を指摘するが、原告ら指摘の事情があるとしても、後に検討する訴外会社の事業内容に照らして、監査請求の対象とすべき将来の財務会計上の行為として、追加出資を行うことが相当の確実さをもって予測されるということは到底できない。
進出企業に対する工業用水道供給のための公営企業繰入支出、水道料金補助支出の差止めについて、企業進出の進捗状況からすれば、当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測されるとした事例 秋田地判平9.3.21判例時報1667.23
○ A社の当地進出については、覚書及び基本協定によって確認され、これに伴う工場用地造成のための公有水面埋立事業が、国の許可と知事の免許を得て着工され、現在も工事が続行されている。工場の建設は、平成6年4月に着工され、操業開始は平成12年と予定されている。また、この操業開始に向け、平成2年より第二工業用水道建設事業が開始され、現在も続行されている。したがって、本件補助として県と市の公金が支出されることは相当の確実性をもって予想されることについて、当事者間に争いはない。
○ 県、市及びA社との間で合意された「本件覚書」「基本協定書」「変更覚書」「変更協定書」及び「附属覚書」の内容とその成立経緯、A社が県及び市に提出した事業計画及び変更事業計画の内容、県議会及び市議会におけるA社誘致及びその財政支出に対する動向、A社工場予定地等に供するための公有水面埋立工事関係の進捗状況、その他、第二工業用水の本件負担価格の合意がA社工場進出の決定の要因となっていることなどの諸事情に照らすと、県一般会計から県工業用水道事業会計(特別会計)に対する補助として本件公金が支出されることが相当の確実さをもって客観的に推測される程度に具体化されているものと認められる。
○ なお、本件公金の支出までには条例の整備(改正等)、予算の議決等、各種手続が残されていることは、被告の主張のとおりであるが、これまでに県知事及び市長からA社の誘致に関連した従前の政策方針を変更するなどの意見表明がなされたこともなく、また、これまで県議会及び市議会においても、右政策方針に反対したり、見直しすべきとの意見が知事や市長の政策方針を指示する賛成意見と拮抗しているとの状況もみられないし、さらに、A社において、平成12年同市進出等の経営計画を見直しするとの動向も窺われないから、本件公金の支出についての前記判断は、条例の未整備及び予算の未議決等の事情により左右されない。
誘致した大学に対する補助金の支出が、大学進出の進捗状況から見て、相当の確実さをもって予測されるとした事例 大分地判平11.3.29判例タイムズ1061.190
○ 本件補助金については、学校法人から提出された「A大学設置事業基本計画」をもとに、県、市及び学校法人の三者で協議検討し、同大学の用地開発造成費についての概算事業費を45億円と見積もった上で、うち42億円までの分を市が補助するものとし、その他同大学の開学時期や学部・定員、設置場所・校地面積等の概要等の内容からなる本件基本協定書案が作成されたこと、右協定書案の内容に沿って、本件補助金限度額42億円中X年度分の14億円を歳出とし、残余の28億円を債務負担行為として計上した市X年度一般会計予算の調製、市議会への提出、同市議会の議決の手続が行われ、被告市長に本件補助金の支出権限が付与された後、県、市及び学校法人の三者で右内容のとおりの本件基本協定に調印したことが認められる。
○ 本件基本協定に調印した段階では、本件補助金について被告市長による交付決定はなく、未だ学校法人の市に対する実体的な補助金交付請求権が発生したわけではないし、また被告市長は、学校法人から本件補助金の交付申請があったときに、その内容を審査し、適当と認めるときに本件補助金の交付決定をする取扱いであることが認められるから、本件基本協定の成立をもって、市と学校法人との間に本件補助金の贈与の予約が成立したと解することも相当でない。
○ しかしながら、前記認定したところによれば、本件補助金の交付計画、交付対象事業等は、本件基本協定書案の作成、市議会における予算の議決、本件基本協定の調印という一連の段階を経て概ね特定しており、たとえ本件補助金の最終的な支出金額、支出時期、支出方法まで確定するに至っていなくとも、右協定の調印時点で、本件補助金の交付予定が相当の確実さをもって客観的に推測される程度に具体性を備えるに至ったと解するのが相当である。
○ したがって、本件基本協定調印時であるX年4月○日において、本件補助金の支出が相当の確実性をもって予測されるに至ったと解するのが相当である。
財務会計行為が相当の確実さをもって予測されるかどうかは1号訴訟の訴訟要件とした上で、市が県に土地を寄附することについて、相当の確実さをもって予測されないので、不適法な訴えとした事例 津地判平11.6.24判例地方自治168.42
(昭和47年市が県立高校の招致を行い、その際は用地造成の上寄附するとしていたところ、同49年市土地開発公社から買受予定地に県立高校が設立、同58年までに市は土地開発公社に代金を支払ったが市から県への土地の寄附は未だ実行に移されておらず、現在市において本件土地について、寄附といった方法によることのない財産管理の在り方が検討されている段階で、土地の寄附の差止めを求め提起された住民訴訟)
○ 1号請求において差止めの対象とするものは未だ行われていない財務会計行為であるから、住民が1号請求を行うためには、法242条1項により、「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」であることが必要である。
○ 市は、本件土地の所有権を取得してから既に十数年が経過しているにもかかわらず、未だ県に対する寄附を実行していないことが認められるのであり、本件訴訟においても、被告市長は、現在のところ、本件土地の寄附手続を行う予定はない旨答弁している。したがって、このような現況下では、被告市長が県に対し本件土地の寄附を行うことが、相当の確実さをもって予想されるとは認められず、原告らの差止め請求に係る訴えは不適法といわざるをえない。
県が市町村振興資金により市に対して「A大学進出関連特別貸付」をすることが違法であるとして、県知事を被告として貸付けの差止めを請求した1号住民訴訟につき、差止請求は口頭弁論終結時においていまだ貸付申請のされていない年度分の貸付けの差止めを求めるものなので、当該行為が行われることが相当の確実さをもって予想される場合には当たらないとした事例 大分地判平11.9.20判例地方自治200.48
○ 本件差止請求訴訟は、振興資金からの貸付けという公金の支出の差止めを求めるものであるところ、地方自治法242条の2第1項1号の差止請求訴訟は、未だ行われていない財務会計上の行為の差止めを求めるものであり、同法242条1項が、このような財務会計上の行為について、「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」には、これを対象として住民監査請求をすることができるとしていることからすると、右のような場合であることが、住民監査請求及びこれに対応する差止請求訴訟の適法要件になると解される。そして、住民訴訟においては、右の適法要件にいう「当該行為」とは、同法242条1項にいう公金の支出等の財務会計上の行為のうち違法なものをいうのであるから、本件差止請求訴訟の訴訟要件としては、当該財務会計上の行為が違法に行われること、すなわち原告たる住民が違法の根拠として主張する事実を伴ってなされることが相当の確実さをもって予測される場合であることが必要であると解される。また、右にいう「相当の確実さをもって予測される場合」とは、当該財務会計上の行為にかかわる諸般の事情を総合的に考慮して、当該行為が違法になされる可能性、危険性が相当の確実さをもって客観的に推測される程度に具体性を備えている場合をいうと解するのが相当である(相当の確実性の要件)。
○ (振興資金は、各年度の貸付けごとに、対象事業のヒアリング、内示等の手続を経て、これに沿った貸付申請が行われることにより、貸付対象事業、貸付条件が概ね特定されるに至るという認定を前提として)本件貸付けについては、各年度ごとに市からの貸付申請がされた時点において、右申請に係る貸付決定、貸付金の支出が違法になされる危険性につき、相当の確実さをもって客観的に推測される程度に具体化するものと解するのが相当である。そして、本件差止請求訴訟は、本件口頭弁論終結時において未だ貸付申請のされていない平成11年度分の本件貸付けの差止めを求めるものであるから、相当の確実性の要件が認められず、不適法である、と判示。
【注】 本件について、県の振興資金担当課と市の担当者間で、平成8年〜11年度の各年度で、総額25億の振興資金貸付を行う旨の協議がなされている。なお、県の振興資金予算は、単年度で措置されており、債務負担行為を定めることはしていない。
空港建設のための環境影響事前評価を行うための調査等請負契約の締結及びそのための予算の執行、公金の支出の差止めを求める事案において、いまだ事前評価及びその実施のための請負契約の締結等に着手するまでには至っておらず、他方で地元住民の一部から空港の建設計画や前記事前評価の実施に対する根強い反対意思が表明されているなどの事情に照らすと、空港建設及びそのための環境影響事前評価が実施されるかどうかは未確定な状態にあると認められるから、事前評価の実施のための請負契約の締結等が行われることが、相当の確実さをもって予測されるとは認められないとした事例大津地判平11.12.20判例地方自治202.58
(事実関係は標記の通り)
○ ・・・県は、○空港の建設に向け、その計画を推進する方針であり、平成X年度の予算において空港整備推進対策事業費を計上し、被告は、県知事として、○空港建設計画の実施に必要な手続である本件アセスメント実施の下準備となる現況調査を開始するなどの施策を講じているものの、いまだ本件アセスメント及びその実施のための請負契約の締結、公金の支出及び予算の執行に着手するまでには至っておらず、他方で、地元住民の一部から○空港の建設計画や本件アセスメントの実施に対する根強い反対意思が表明されており、国(運輸省)の○空港の建設に関する方針も前記のとおり微妙なものであるというべきであり、これらの事情に照らすと、○空港の建設及びそのためのアセスメントが実施されるか否かは未確定な状態にあると認められる。
○ そうすると、本件口頭弁論終結時において、本件アセスメントの実施のための請負契約の締結、公金の支出及び予算の執行が行われることが、相当の確実さをもって予測されるとは認められないというべきである。
第三セクターへ県が派遣した職員の給与の差止め請求について、現在は派遣職員に県は給与を支給していないことや、公益法人等派遣法の制定があった等の事情を考慮すれば、相当の確実さをもって予測される場合にあたらないとした事例 広島高(岡山)判平13.6.28判例地方自治224.62
○ 本件訴えは、地方自治法242条の2第1項1号に基づくものであるが、同号に基づく差止めの訴えを提起するためには、当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合であることが必要である。
○ 一審被告知事が平成2年2月20日から平成9年3月31日まで一審被告会社に県職員を派遣し、右派遣職員に対する給与等を県の公金から支給したことは当事者間に争いがなく、弁論の全趣旨によれば、一審被告知事は平成9年4月1日以降も一審被告会社に対する職員派遣を継続していることが認められる。しかし、右同日以降、一審被告知事が右派遣職員に対して給与等を支給していないことは一審原告らの自認するところである。
○ 一審原告らは、一審被告知事が派遣職員に対する給与支給を再開する可能性は高いと主張するが、平成12年に「公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」が制定され(施行は平成14年4月1日)、地方公務員の派遣についての法制度が整備されたことは公知の事実であり、右法律の内容に照らすと、同法が施行される平成14年4月1日以降一審被告知事が一審被告会社に県職員を派遣するとは考えられず、本件の経過に照らすと、それ以前においても、一審被告知事が一審被告会社に派遣した県職員に対して給与等を支給することが相当の確実さをもって予測されるということはできない。
○ よって、一審被告知事に対する本件公金支出の差止めの訴えは不適法である、と判示。
公園事業を運営する三セクに対し市が実行する予定の15年間にわたる各単年度低利貸付の将来部分が、下掲の事情を考慮すれば、相当の確実さをもって予測されるものとした事例 岡山地判平14.3.13判例地方自治239.40
(市が公園事業を運営する三セクに対し平成8から12年度まで各年度に低利貸付を行い、14年度以降も23年度まで各年度に単年度の貸付を行う方針(ただし債務負担行為議決は経ておらず各年度の予算措置によるため後年度の貸付は各年度の予算措置がなされることが前提)であることについて貸付差止めを求める住民訴訟)
○ 平成8~12年度各貸付についての金銭消費貸借契約書には、市が三セク会社に対して期間15年(うち3年据え置き)で無利子融資15億円、低利融資70億円を行う旨の記載のされた別記がいずれにも添付されている。
○ 市は、平成13年4月にも、三セク会社に対し、期間を貸付日から1年として12億5000万円を利息を付さずに、61億2490万円を年1.0パーセントの利率で貸し付けたとうかがわれる。
○ 平成14年度以降も、市が三セク会社に対して貸付を行う場合には、平成13年度までと同様の約定による貸付が予定されている。ただ、平成14年度以降の貸付については、各年度の予算に貸付金として計上し、市議会の議決を経なければ、これを執行することはできないものであり、貸付が確定しているわけではない。
○ 議会特別委員会の資料には、市から無利子融資15億円及び低利子融資70億円を15年の期間(うち3年据え置き)で借入れる旨の資金調達計画が記載されている。
○ 以上のように、市は、平成9年度から毎年度三セク会社に対して貸付を行っており、平成12年度からは前年貸付金額から、無利子貸付分については1億2500万円を、低利貸付分については2億9170万円を、それぞれ控除した金額を貸し付けていることからすると、これら貸付は、形式的には単年度貸付の形をとっているものの、実質的には貸付初年度から3年間は据え置きとし、4年目から一部弁済をする旨の合意がなされた期間15年の消費貸借契約であると同一視するとができる。したがって、市の財産の管理処分権者である被告が、三セク会社に対して、前年度の貸付金額から弁済額を控除した額の金員を無利子及び年1.0パーセントの利率で平成23年度まで毎年度貸し付けることは、これが市の予算にいまだ計上されておらず、各年度の予算について市議会の議決を経ていないとしても、単にその可能性が漠然と存在するというにとどまるものではなく、公金の支出自体については相当程度の客観性、具体的可能性があるものと認められる。よって、本件貸付は、地方自治法242条1項にいう、「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」に当たるというべきである。
ダム建設事業負担金のうち将来支出計画がある部分は、当該財務会計行為がなされることが相当の確実性をもって予測される場合にあたるが、計画のないものはあたらないとした事例 岐阜地判平15.12.26判例時報1859.43
(水資源開発公団(当時)建設ダムの負担金支出の差止めを求める住民訴訟。負担金は平成2年度から継続して支出されており、ダムが予定通りに完成した場合には、公団の県に対する負担金賦課行為は平成43年3月まで継続し、県は本件負担金を支出する予定。なお負担金の具体的金額は、公団の県に対する納付通知の際に県にとって明らかとなるものであり、費用負担同意の際には費用負担割合及びダム建設事業概算額が決定済みであるにとどまり、具体的な負担金の額が決定していたわけではない)
○ 差止請求は当該行為がされる以前又は現にされつつあるときにのみ可能であって、既に差止めの対象となる行為がされた後にその行為の差止めを請求することはできず、このような差止請求には訴えの利益がなく、不適法であると解するのが相当である。
○ 県は、平成15年3月25日、平成14年度第4四半期分まで本件負担金を既に支出したことが認められる。したがって、原告らの本件負担金の支出等の差止を求める訴えのうち、上記部分についての支出等の差止めに係る訴えは、訴えの利益を欠くものであって、いずれも不適法である。
○ 差止請求は、地方公共団体の執行機関又は職員の当該財務会計行為がなされることが相当の確実性をもって予測される場合に限り可能であって、これが認められない場合、このような差止請求は不適法であると解される。
○ 県は、本件負担金については、平成43年4月以降の支出は予定しておらず、平成43年3月まで支出を予定しているにとどまることが認められるから、平成43年3月まで本件負担金の支出が行われることは相当の確実性をもって予測されるものといえるが、他方、平成43年4月以降については、同支出が確実に行われるとは認められない。したがって、原告らの本件負担金の支出等の差止を求める訴えのうち、上記部分についての支出等の差止めに係る訴えは、いずれも不適法である。
公金支出の差止めを求める住民訴訟が、一部の支出は既に完了しているので差止め請求の対象としては不適法であり、予定される将来支出部分については相当の確実さをもって予測されるとした事例 福岡地判平19.3.1判例タイムズ1277.215
○ 差止めの対象としている公金支出が完了すれば、差止めの余地はなくなるから、当該公金支出の差止めの訴えは不適法となるところ、前記認定事実によれば、市が本件事業の用地取得費、建設費として、平成15年6月30日(平成14年会計年度)までに上記公金の支出を完了したこと、また、本件事業の用地造成費として、本件土地区画整理組合に対する本件道路整備費用の負担金である2億7000万円の支出を完了したことが認められる。そして、本件事業により建設された各施設がいずれも本格的な稼働を開始していること、現時点で稼働している各施設以外に、新たに用地を取得したり、新たな建設物を構築する予定はないことにかんがみれば、本件事業に関する用地取得、造成、建設に関する公金支出は完了したものと認められるから、本件訴えのうち、上記公金支出に関する部分は不適法である。
○ 市は、本件清掃施設組合に対し、本件○センターの事業主体である同組合の運営に必要な経費として、同市分の負担金を以下のとおり、支出し又は支出することを予定している。
・ 平成15年度 6億4846万5000円
・ 平成16年度 8億2872万6000円
・ 平成17年度 9億0983万3000円
・ 平成18年度
a 同年7月20日時点での支出額 2億7380万円
b 同月21日以降の支出見込額 11億1821万2000円
○ 前記公金支出のうち、本件口頭弁論終結時である同年10月12日以前に完了した公金支出行為の差止めを求める部分は、差止めの余地がないから不適法である。他方、前記認定事実によれば、同市は、同年7月21日以降も前記公金支出を予定していることが認められ、本件口頭弁論終結後も前記公金支出がされることが相当の確実さをもって予測される。したがって、本件○センターの修理、改修及び関連施設としての仮置、常設スペースの設置、維持等に関する同年10月13日以降の公金支出の差止めを求める訴えは適法である。
これまでの庁舎内食堂事業者が今次の選定で落選したが場所を明け渡さないまま係争事案となっている状況下での、落選事業者による新事業者への庁舎目的外使用許可の差止め請求は不適法とした事例 大阪地判平22.1.28判例地方自治335.34
○ 平成10年4月以降、原告に使用許可が与えられ、原告は、本件物件において食堂営業を行ってきたが、原告に対する最後の使用許可の期間は平成21年3月31日をもって終了したこと、所長は、平成21年度に本件研究所において食堂営業を行わせるための本件物件の使用許可については、許可に係る申請者を、募集要項に基づき、公募と選定審査会による審査を経て選定することとしたこと、そして、平成21年度に係る使用許可に関し、事業者の公募並びにその後の審査及び選定を経て、所長から原告に対し、平成21年2月16日付け書面が交付され、原告が選定事業者とされなかったこと等が通知されたこと、Aが選定事業者となったこと等の記載があること、これを受けてAは、同年2月23日、行政財産使用許可に係る申請をしたこと、一方、原告は、平成21年3月31日をもって上記のとおり使用許可期間が終了して本件物件の占有権原を失い、被告から本件物件の原状回復及び返還の期限を同年4月7日と定められたにもかかわらず、その後も権原なく食堂部分の占有と食堂営業を継続し、任意に明け渡す意思のないことを明らかにしたこと、このため被告は原告に対して本件物件の明渡し等を求める民事訴訟を提起しており、Aの上記使用許可申請に対していまだ使用許可をすることができないでいること、以上の事実を認めることができる。
○ 原告が、無権原での占有と食堂営業を継続し、任意に明け渡す意思のないことを明らかにしているなどの各事情に照らせば、現在Aに対する使用許可をすることができない状態にあり、そうすると、本件においては、地方自治法242条の2第1項1号の差止請求が適法であるための上記要件を満たさないというべきである。
市が出資している第三セクターの株式会社に対して市が損失補償を履行することの差止めを求める住民監査請求は、損失補償がなされることが相当の確実性を有する場合でなければ監査委員にはその適否について監査の機会が与えられていないことになるところ、本件監査請求時点においては本件各損失補償の対象となる社の経営破綻が確実と推認できるとの主張立証はない等、回収不能債権の発生が予測されている訳ではなく、損失補償の履行がなされる可能性、危険性が相当の確実性をもって推測される程度に具体性を備えていたということはできなとした事例 大阪地判平23.1.14判例地方自治350.19
○ 地方自治法242条1項は、普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長その他の財務会計職員について、「違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。)と認めるとき」に監査請求をすることができる旨規定し、「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」には、まだされていない当該行為を対象としてその防止等を求める監査請求ができることを明らかにしている。そうすると、上記規定の文理上、「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」に該当しない場合には、普通地方公共団体の住民は、当該行為がされる前にその防止等を求めて監査請求をすることはできないと解される。したがって、「当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合」(相当の確実性)の要件は、当該行為がされる前にその防止等を求める監査請求の適法要件であるということができる。
○ 本件各損失補償条項は、いずれも、本件各補償債権者の本件3社に対する免除後の残債権等について、担保物件の処分などの回収努力をしてもなお回収不能が発生した場合には、本件各補償債権者に対し、当該回収不能額を損失としてその損失額を補償するという内容のものであり、本件各補償債権者において担保物件の処分などの回収努力をしてもなお回収不能が発生することが損失補償債務の履行の条件とされている。これを端的にいうならば、本件各損失補償条項は、本件3社の再建計画が行き詰まり、その経営が破綻した場合に、本件各補償債権者の最終的な回収不能額(損失)について市が補償することを約束するものであるといえ、そういった事情もないのに、市が本件各補償債権者に対する損失補償債務を履行することは想定し難い。そうであるところ、平成17年2月22日の本件監査請求の時点において、本件3社が本件各特定調停に定められた本件各補償債権者に対する弁済を遅滞し期限の利益を喪失したとか、本件3社や市が再建計画の遂行を断念する旨を表明するなどといった事情は何らうかがわれず、本件3社の再建計画が行き詰まり、その経営が破綻することが確実な状況であったことを推認できる事実の主張立証はない。
○ 以上によれば、本件監査請求時点において、本件各損失補償履行がされる可能性、危険性が相当の確実さをもって客観的に推測される程度に具体性を備えているということはできない。

有楽町交通会館てっぺんの回転レストラン。鉄道模型のように電車が動きまくるのを眺めていると時間はあっという間。