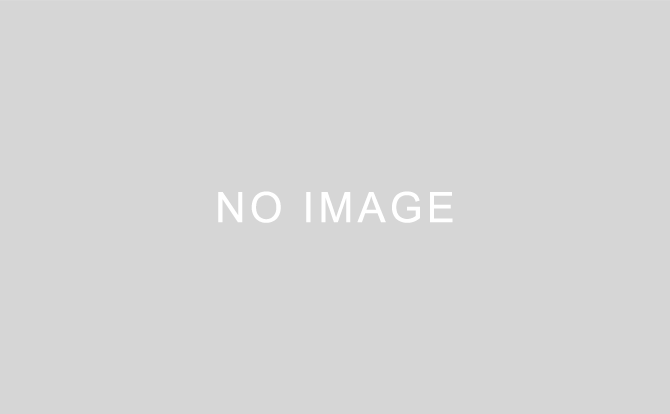本ページの一番下に、本ページのPDF版リンクを設けています。
最終改訂 2024.1.29 改訂箇所は改訂履歴のページ参照
このページは、「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」2(2)で概説した公金の支出について、各論部分をもう少し詳しく説明するページです。
【注】 参考事例の判決文は、必ずしも原文通りではなく、項目の表記にあうように若干の修正をしていることがあります。
1 総論
公金の支出そのものが、地方自治法242条1項の住民監査請求の対象となるかどうかについては、なることで、ほとんど問題になることはないものと考えます。
なお他の類型、たとえば財産の取得管理処分等では、実際の自治体の行為が住民監査請求の対象となるのかは、しばしば問題となります。
これは、ある行為が地方自治法242条1項で住民監査請求の対象と明示されている「公金の支出」に該当するかどうかの判断において、たとえば財産の管理などと比べればほとんど迷う要素がないこと、およそ公金の支出が、財務会計行為そのものといえる性格であることによります。
「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」2(1)イにある通り、住民監査請求の対象となるのは、地方自治法242条1項列挙の行為等の類型に外形上該当するのみならず、それ(ら)が財務的処理を直接の目的とする、という性質を有することを要求され(参照:最判平2.4.12民集44.3.431)、財産管理行為等では、しばしばこの目的・性質的な該当性が問題となりますが、公金の支出では、住民監査請求の対象となることについて疑義が生ずることは、まずありません※。
| ※ 住民監査請求の対象となる財務会計行為に当たるかどうかについては、主にその行為の目的によって判断されることが多いとされますが(参照:野呂充地方自治判例百選(第4版)」有斐閣(2013年)p.173、同第5版(2023年)p.151。リーディングケースは最判平2.4.12民集44.3.431)、公金支出事例については、幅広く住民訴訟で争うことができるとするのが大方の扱いとされます(参照:実務住民訴訟p.111)。 |
これをもうすこし詳しく見ると、上記平成2年最判などの判断枠組みによれば、たとえば財産の管理を問題として提起された住民監査請求・住民訴訟では、対象となる行為(怠っているとされる行為)が地方自治法242条1項にいう「財務会計行為(怠っている行為)」に該当するかどうか(外形的に該当するのみならず、上記の通り、財務的処理を直接の目的とする、という性質を有することを要する)がまず判断され(上記の平成2年最判の例では、訴訟の対象となった道路建設工事施行決定は地方自治法242条1項の財務会計行為といえるのか?ということ)、請求対象が財務会計行為であると判断されてはじめて、監査を行い、対象行為等の違法(不当)性の有無や講ずるべき措置の内容の検討に進むのですが、公金の支出は、それ自体が財務会計行為そのものとしての性格を有するため、支出されたのが自治体の資産としての公金であるか疑わしいような特異的なケースを除けば、地方自治法242条1項の財務会計行為であるかどうか判断する必要性がない、ということになります。
なお、たとえば財産管理処分行為を対象とする住民監査請求・住民訴訟では、その行為が財務的処理を目的とするもの以外は対象から排除されるのに、公金の支出の場合は、行為が財務的処理を目的とするかどうかという目的性のフィルタがないため、そうした排除が働かず、公金支出を通じて、公金支出の原因となる政策判断を問うような事例が頻出する、また財産管理等の場合と比べ、考え方や取扱いに統一を欠く、という問題が指摘されていますが(参照:上記※実務住民訴訟該当箇所)、公金の支出はその目的性のいかんを問わず財務会計行為とされる以上、財務会計行為と認められる事項を対象とする現在の住民監査請求・住民訴訟制度のもとでは、法律に基づく行政の原則(違法な行政上の行為は、法効果を有するべきではなく、よって存続させるべきではない)からしても、やむを得ないことです。
2 公金の範囲
公金は、「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」2(2)アに述べる通り、自治体がその目的を達成するための作用を行うにあたって用いる金銭であり(法律学小辞典p.362)、歳計現金、基金に属する現金、歳入歳出外現金、一時借入金がこれにあたるとされます(参照:新自治用語辞典編纂会編「新自治用語辞典」ぎょうせい(2000年)p.253/同改訂版(2012年)p.263)。要は、自治体の所有する資産であることがポイントとなります(なお歳入歳出外現金もここでいう「公金」に含まれる※)。
| ※ 「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」2(3)アの平成10年最判紹介で説明する通り、昭和38年自治法改正後の現行の住民監査請求・住民訴訟法制度のもとでは(旧法下では昭和38年最判)、住民監査請求の対象とされる財産が住民の負担に係る公租公課等で形成されたかどうかは問わないと解されています。 |
なお注意すべきは、公金の支出がされて支出手続が完結し、その金銭が自治体の手から離れれば、それがその後に公金的な利用をされたとしても、その金銭は公金としての性格を失い、住民監査請求の対象とはならないのですが(下記平成8年名古屋地判事例など)、資金前渡された資金は、資金前渡職員の保管下にある限り公金としての性格を失わず、資金前渡職員の支出行為は、公金の支出となります(最判平18.12.1民集60.10.3847)。概算払についても、精算前段階でも公金の支出があったとされ、精算行為も別途住民監査請求の対象とすることができる、とされます(最判平7.2.21集民174.285)。
【参考事例】
| 概算払は、精算手続の完了を待つまでもなく、住民監査請求の対象となる財務会計上の行為としての公金の支出に当たる 最判平7.2.21集民174.285
○ 概算払は、地方自治法が普通地方公共団体の支出の一方法として認めているものであるから(232条の5第2項)、支出金額を確定する精算手続の完了を待つまでもなく、住民監査請求の対象となる財務会計上の行為としての公金の支出に当たるものというべきである、と判示。 |
| 公金と類似する性格の金銭であっても、自治体から支出され他者に渡った金銭は公金とはいえないとした事例 名古屋地判平8.6.28判例地方自治159.53(教職員に支給される旅費の一定額を超えた部分をプール金として留保し、諸経費に支出していたことが違法であるとして、県給与事務所長及び学校長らに対して支出の違法確認及び不当利得返還を求めた住民訴訟)
○ 旅費について正規の受領手続を経た後、別途プール用の預金口座において保管されていたものであることが認められるから、プール金はもはや、公金ということはできず、プール金からの支出行為をもって住民訴訟の対象となる公金の支出行為とみることはできない、と判示。 |
| 資金前渡職員による前渡資金の支出は、公金の支出である 最判平18.12.1民集60.10.3847(秘書室長に資金前渡された市長交際費に関する住民訴訟)
○ 資金前渡職員に対する資金の交付は、債権者に対する支払の便宜のためにされるにすぎず、交付された資金が公金としての性質を失うものではない。○ 地方自治法も、243条の2(現243条の2の2)において、資金前渡を受けた職員がその保管に係る現金を亡失したときは損害を賠償しなければならないことを規定している。そして、地方自治法施行令161条の規定等に照らせば、資金前渡職員は、普通地方公共団体の規則等において別段の定めがされていない限り、各個の経費の目的に従い、交付された金額の範囲内で、契約を締結するなどして普通地方公共団体に債務を負担させる権限を有し、また、当該普通地方公共団体がそのようにして負担した債務又は既に負担していた債務を履行するため債権者に対する支払を行う権限を有すると解される。 |
3 公金の支出行為としての支出負担行為・支出命令・(狭義の)支出
(1) 支出負担行為・支出命令・支出の財務会計行為としての性格
「2 違法・不当な財務会計行為及び怠る事実 概説」2(2)イにあるように、住民監査請求の対象となる財務会計行為としての公金の支出は、実際の金銭支出行為(狭義の支出行為、すなわち実際の金銭払出し)のみならず、その前提行為である支出負担行為、支出命令を含みます。
支出負担行為、支出命令、実際の支出は、一連の行為として、最終的な前記の実際の支出に向けて行われるものですので、住民監査請求の対象として公金の支出を取り上げる場合、これら行為を一体として取り上げることも、支出負担行為、支出命令、実際の支出を分解して、個別の行為を取り上げることも可能です(参照:最判平14.7.16民集56.6.1339)※。
これは、これらの行為は、原権限者が異なり(支出負担行為、支出命令は首長に原権限、支出は会計管理者に原権限)、委任・専決先が異なることもあること、それぞれの行為の根拠法規、考慮事項が異なること、異なるタイミングで行われることが多いこと、という特性を踏まえたものです。
| ※ これらの行為を区分することなく住民監査請求の対象とすることは、監査の対象事項の特定を欠き不適法となるものではない、とされます(上記平成14年最判参照)。 なお、普通は支出負担行為と支出命令、支出を分解して住民監査請求の俎上にのせることはないと思われますし、請求人がそのような意図をもつこともまずないと考えます(請求上も、そうした区分をせずに一括して、○○契約に基づく支出は違法、という内容になるでしょう)。 この区分が、住民監査請求の要件審査の段階で意味を持つのは、下記のように、監査請求期間(地方自治法242条2項)の関係で、支出から住民監査請求の提起までは1年以内だが、支出負担行為(契約等)からは1年以上経過しているような場合に限られると思われます。 |
ところで、住民監査請求は、請求期間(行為日から1年以内:地方自治法242条2項)が定められており、住民監査請求提起の日から見て、実際の支出からは1年以内ですが、支出負担行為の日から1年以上経っていることは当然あり得ます。この場合は、支出負担行為、支出命令、支出の行為それぞれで監査請求期間を計算し、期間内にある行為のみ住民監査請求の対象とすることができるのですが(参照:下記平成14年最判)、こうしたケース、たとえば支出負担行為(契約締結)日から1年以上経過、支出日から1年以内に住民監査請求を行った場合、支出負担行為(契約締結)の違法性を問題とすることは、原則として(地方自治法242条2項ただし書きの正当の理由がない限り)できませんし、その結果として、支出負担行為固有の違法不当事由を監査でとりあげることを求めることもできません(参照:実務住民訴訟p.112)。この点については、監査請求期間に関する別ページで説明します。
【参考事例】
| 公金の支出を構成する支出負担行為・支出命令・支出は、個別の財務会計行為としても、区別せず一体の行為としても、住民監査請求の対象とすることができる 最判平14.7.16民集56.6.1339(支出負担行為兼支出命令日から1年以上経過、支出日から1年以内に住民監査請求がされた事例)
○ 公金の支出は、具体的には、支出負担行為(支出の原因となるべき契約その他の行為)及び支出命令がされた上で、支出(狭義の支出)がされることによって行われるものである(地方自治法232条の3、232条の4第1項)。これらのうち支出負担行為及び支出命令は当該地方公共団体の長の権限に属するのに対し、支出は出納長又は収入役の権限に属するのであり、そのいずれについてもこれらの者から他の職員に委任等により各別に権限が委譲されることがある。また、これらの行為に適用される実体上、手続上の財務会計法規の内容も同一ではない。このように、これらは、公金を支出するために行われる一連の行為ではあるが、互いに独立した財務会計上の行為というべきものである。 |
(2) 支出負担行為・支出命令・支出の詳細
ア 支出負担行為
支出負担行為は、支出の原因となるべき契約その他の行為のことです(地方自治法232条の3)。多くは契約によると思われますが、給与の支給決定、不法行為による損害賠償のように、契約に基づかないものもあります。
なお、その行為の後にそれに基づき公金の支出が発生するものであっても、その行為自体が公金の具体的な支出義務を自治体に発生させるものではない、たとえば職員の採用、生活保護の決定、支払金額や支払時期の定めのない将来に向けた契約などは、支出負担行為にはあたりません(参照:実務住民訴訟p.113)。
イ 支出命令・支出
支出命令・現実の支出については、個別の行為がこれに該当するかどうかの問題は少ないのではないかと考えます。
4 公金の支出に関する参考事例
(1) 議会の議決を経た公金の支出等
議会の適法な予算議決を経てなされた公金の支出であっても、住民監査請求の対象とすることは可能です(主に請求の適法要件の問題ではなく、支出の適法性判断の問題です)。
【参考事例】
| 議会の議決があった公金の支出についても、住民訴訟によりその禁止・制限を求めることができる 最判昭37.3.7民集16.3.445(昭和29年改正警察法に基づき議会の議決を経て措置された警察費予算について、同改正法は違憲として支出禁止を求めた住民訴訟)
○ 長その他の職員の公金の支出等は、一方において議会の議決に基づくことを要するとともに、他面法令の規定に従わなければならないのは勿論であり、議会の議決があったからといっても、法令上違法な支出が適法な支出となる理由はない。 |
(2) 自治体内部での会計間の支出・地方公営企業の支出
自治体の会計間での資金移動のための支出や、原資が公租公課とはいえない地方公営企業会計での支出は、住民監査請求の対象としての「公金の支出」と解されています※。
【参考事例】
| 地方公営企業会計の支出(当年度の経営に伴う収入で賄われたもの)は、公金の支出であるとした事例 名古屋地判昭59.9.21行裁例集35.9.1379
○ 被告は、本件公金の支出がすべて地方公営企業事業の経営努力により得た収入の中から支払われたものであり、公租公課等による住民負担に係る金銭の支出ではないから、支出は自治体に何らの財産上の損害を与えるものではなく、本件公金支出を訴訟の対象とする本件住民訴訟は、地方自治法242条の2所定の住民訴訟の趣旨、目的からして許されないと主張。 |
| 会計間の繰入は、公金の支出であるとした事例 名古屋高判平12.7.13判例タイムズ1088.146(一般会計から工業用水道事業会計へ支出(一般会計繰入)した事例)
○ 国家財政については財政法2条3項が、同条1項の「収入」及び「支出」は会計間の繰入を含むと規定しており、一般会計から特別会計への繰入が「支出」に該当する旨規定されている。 |
| ※ ただし、会計間資金移動に財務会計行為性を認めない裁判例もあリます(上記名古屋高判の原審である津地判平12.1.27判例タイムズ1031.79は、本件において対象とされている行為は公金を一般会計から右の工業用水道事業会計へ支出する行為であるが、一般会計も工業用水道事業会計も ○県という同一の法人格に分属する手続であるから、右行為は実質的には同一法人格内部の公金の振替にすぎず、このような内部行為については、住民訴訟の対象とするにはいまだ成熟していないというべきであるし、公金が一般会計から工業用水道事業会計に支出されたのみでは ○県が保有する公金の額は何ら減少するものではないから、 ○県に何らの財産的損害を与える客観的可能性もない。以上からすれば、本件支出は住民訴訟の対象適格を有しないといわざるを得ない、とする)。 |
(3) 国県補助金を財源とする支出
国県補助金等を特定財源とする支出であっても、その自治体の支出である限り、住民監査請求の対象としての「公金の支出」と解されています。その自治体の公金が払い出されるものについては、その財源の性格によって住民監査請求の対象となるかどうかが左右されることは、住民監査請求の制度趣旨に沿わないものと考えます。
【参考事例】
| 県補助金を財源とする町補助金の支出は、公金の支出であるとした事例 神戸地判昭56.6.12判例時報1051.77
○ 被告は、町が本件補助金を交付することがなかったなら、県補助金の交付を受けることはなく、また県補助金が町に交付されても町がこれを交付しなければ、これを県に返還すべきものであるから、町が本件補助金を交付するにせよ、しないにせよ、町がこれと同額の金員を保有することはなく、したがって、町の組合に対する本件補助金の交付自体によって町に損失を与えることはない旨主張。 |
(4) その他の事例
その他いくつか参考となる裁判例をあげます。下の参考事例①は、住民監査請求の対象となる財務会計行為と認めた事例、②は認めなかった事例です。
○ 公金の支出の原因行為、すなわち自治体が金銭債務を負う原因は、ほとんどが契約によると思われます。こうした金銭債務負担を内容とする契約が、住民監査請求の対象としての財務会計行為となることは、ほぼ問題がないでしょう。
そのため、下の例では職員手当の例が多いのですが、ここでの「住民監査請求の対象としての財務会計行為かどうか」の判断の違いは、対象となる行為が、契約締結のような「支出負担行為」といえる内容かどうかによるものと考えます。
例えば「該当する」とされたものは、行為者が支出負担行為―支出命令のライン上にあり、かつその行為が支出負担行為とは銘打っていなくとも、実際は手当請求権の存在や、その具体的な金額を確定させる行為であり、その内容において支出負担行為というべき内容の行為であることに着目しており、一方で「該当しない」とされたものは、手当請求権の存在や額の決定を行う実質的な決定権者が別におり、対象行為は、そのための資料を提出しているに過ぎない立場である、つまり実質的な支出負担行為としての性格を持たないことを重視しての判断と考えます(財務会計行為と、前提・類似の効果をもつものであっても財務会計行為そのものではない行為を明確に分別するのが、最高裁判例の示す立場でもあります)。
○ 事例②のうち昭和56年大阪高判は、土地区画整理事業での換地処分を財務会計行為としない昭和51年最判を基礎としていますが、土地区画整理事業では、自治体が自らの財産の取得・処分を目的として財務的行為を通じて土地を取得・処分しているのではなく、土地区画整理事業の目的及びその計画に従って所定の土地の区割りを差し繰りする性格のものである以上、こうした事案を住民監査請求の対象と認めた場合、住民監査請求・住民訴訟で土地区画整理事業における換地計画の適否という、財務会計上の問題ではない行政政策そのものの適否を争うことができることとなり、住民監査請求・住民訴訟制度の趣旨に沿わないこととなるためによる判断、と考えます(参照:大橋寛明「時の判例Ⅰ」p.300)。
○ 事例②のうち平成10年最判は、経済効果的には補助金の交付と同視し得る効果を持つ措置ですが、住民監査請求の対象となる財務会計行為かどうかについては、最高裁は、あくまでも支出としての外形があるかという外形基準で判断している、と考えるべきでしょう。
【参考事例①・・・住民監査請求の対象として該当するとしたもの】
| 退職手当の支出命令に先立ち首長がした退職手当の裁定は、退職手当額を具体決定しており、その後の支出の手続はこの裁定を基礎として進められていることを踏まえれば、当該裁定は、住民監査請求の対象である財務会計行為であるとした事例 東京高判昭55.3.31行裁例集31.3.824(収賄職員を分限免職として、退職手当を支給したことを違法とする住民訴訟。なお上告審 最判昭60.9.12集民145.357では、先行行為(分限免職)の違法性が後行財務会計行為(退職手当支出)の適法性に影響するかについて判断)
○ 規程上、市における退職手当の裁定は職員局長、支出命令は給与課長が決裁権者だが、規程上、重要異例事項は上司の決裁を求めることとしており、本裁定決裁書には職員局長に続き助役、市長の捺印があり、市長決裁と記載されていた。 |
| 期末手当の増額承認行為は、住民監査請求の対象である財務会計行為であるとした事例 横浜地判昭61.10.29判例時報1220.53(給与条例の「任命権者が必要と認める場合は、知事の承認を得て・・・期末手当の額の増額をすることができる」との規定に基づきなされた期末手当の増額支給を違法とする住民訴訟)
○ 知事としてした承認に基づき、各任命権者が職員一人当たりにつき一律25,000円を支給したというものであるから、本件承認行為は、期末手当の増額支給を承認する行為でありそれ自体財務会計上の行為として住民訴訟の対象となると解することができる、と判示。 |
【参考事例②・・・住民監査請求の対象として該当しないとしたもの】
| 市施行の土地区画整理事業における仮換地指定およびこれに伴う補償金契約の締結およびその支払は、財務会計上の行為に当らない、とした事例 大阪高判昭56.12.22判例時報1047.72 なお参考となる先行事例として最判昭51.3.30集民117.337 (土地区画整理法に基づく換地処分を住民訴訟の対象とすることはできない)
○ 土地区画整理法によれば、土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため土地区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいい、換地処分あるいはその換地処分に至るまでの間、工事の施行その他の必要上暫定的な土地使用関係の変更をする仮換地指定処分等は、すべて整理事業施行者としての立場で行なう処分である。また仮換地指定処分がなされた結果、建築物等を移転除却する必要が生じたときは、事業施行の一環として施行者から建築物所有者らに対して一定の損失補償が行われる。 |
| 市長が職員退職にあたり、職員が提出した退職手当請求書が内容正当と証明して退手組合長に提出した行為は、財務会計上の行為ではない、とした事例 富山地判昭60.8.30判例時報1182.74
○ 規程上、退職組合構成市町村等の職員が退職し退職手当を請求するには、所定の退職手当請求書を退職当時所属の市町村等の長を経由して退職組合長に提出し、市長村長等が退職手当の請求書を受理したときは、これを調査し、その記載の正当であることを確認のうえ証明し、すみやかに退職組合長に提出しなければならない。退職組合長は、退職手当の請求を受けたとき、これを審査し、その請求が正当であると認めたときは裁定通知書を市町村長等を経て請求者に交付し、組合長において、退職手当の請求書に不備があるとき、又は給付を受ける権利がないと認めたときは、その理由を付して所属長を経て請求者に通知しなければならない、給付金は退職組合から直接請求者に請求のあった翌月末日までに支給するとされている。 ★本裁判例については、「3 当該普通地方公共団体の執行機関・職員」1【参考事例③】も参照 |
| 市が職員宿舎として民間マンションを借り上げて職員に使用させた場合の実際のマンション借上げ賃料と職員の現実の使用料の差額を職員への給付とみなして、当該部分を条例外給与支給として市長に損害賠償を求めた場合において、当該差額分の給付なるものは地方自治法242条1項所定事項のいずれにも該当しないので住民監査請求の対象とならない 最判平10.6.30判例地方自治178.9(市が職員宿舎として月45,000円で民間マンションを借り上げて、月1万円未満の使用料で職員に使用させたところ、これは差額分を職員に給付したものであり、この給付は、法律又は条例に基づかない職員に対する給付を禁じた地方自治法204条の2に違反し、住居手当の支給限度額を定めた市の給与条例に実質的に違反するとして、市長に損害賠償を求める住民訴訟)
○ 原告が違法な財務会計上の行為と主張しているものは、差額分の給付であることが明らかだが、この給付なるものは、市が職員に現実に金銭等を支給したというのではなく、実質的にみて同人に右差額分に相当する利益を与えたということを指す。 |

尾道の箱庭的風景。上から見ると川のような幅狭な尾道水道を左右に行き交う多数の船、尾道と向島を行き来するEテレ0655でおなじみ尾道の渡し船(乗りました)、ごとごとと爆走する山陽線の長大貨物列車など、ずっと見ていても飽きません。