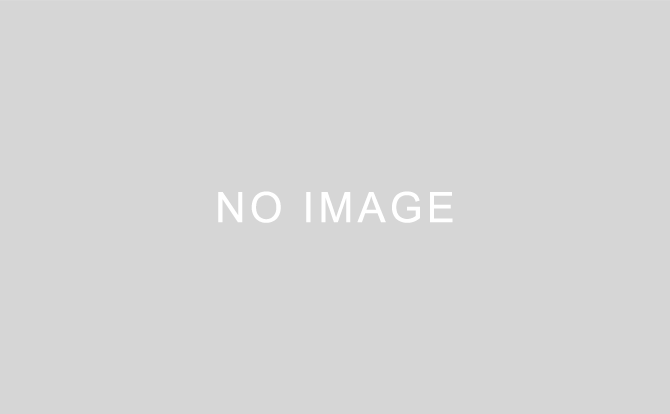本ページの一番下に、本ページのPDF版リンクを設けています。
最終改訂 2025.2.13 改訂内容は改訂履歴ページを参照
住民監査請求を行うには、行為能力を要するというのが行政実例であり、有力な学説です。制限行為能力者が単独で行う住民監査請求で問題となるのは、実際のところ未成年の場合でしょうが、これによれば、未成年者は単独で(親権者等の同意・代理なしに)行うことはできない、ということになります。しかしこれと異なる見解があり、実際に見解の相違に伴う問題が発生しています。
この点については、監査委員が、現時点、双方の見解を考慮して、より妥当と考える結論を選択するしかありません。
1 前提
(1) 未成年者の行為能力
民法5条1項は、未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない、としています。法律行為とは、一般に「一定の法律効果の発生を欲する者に対してその欲する通りの法律効果を生じさせるための行為」(法律学小辞典p.1210)とされ、適法な住民監査請求の提起によって、監査委員に法律上の(監査の実施等の)応答義務が生じるので、法文の字義上のみで考える限り、未成年者の住民監査請求の提起は、単独ではできないこととなります(ただし単独でした請求は無効ではなく(民法5条2項)、民法上の規定に厳密に沿うと、「単独ではできない」とすることには語弊が生じます)。
(2) 住民監査請求関係法令における規定等
地方自治法には、未成年者の取扱いについて、なんらの規定はありません。最高裁の判例もないようです。
2 一般的な考え方
(1) 住民監査請求に直接関するもの
行政実例は、住民監査請求をするには、行為能力が必要としています。これによれば、未成年者は民法上の行為能力を制限されているので、親権者等の同意・代理※がない未成年者単独で請求することはできず、よって未成年者単独の請求は不適法な請求になると考えています。この趣旨のものとして、
○ 地方公共団体の住民としては、法律上行為能力を認められている限り、法人たると個人たるとを問わず監査請求をすることができる(松本逐条、行実昭23.10.30。なおこの行政実例は、下記日弁連要望で指摘の通り、住民監査請求に行為能力を要するとする理由を示さない)。
○ (住民)監査請求をすることができる者は、当該普通地方公共団体の住民であれば足りる。法人であると個人であるとを問わず、国籍・性・年齢(但し行為能力を有することを要するものと解すべし)のいかんにかかわりない(田中 中p.115)。
| ※ 理念的には、未成年者の法定代理人(親権者等)が未成年者を代理して請求するケースも考えられはしますが、現実に引き直した場合、そうする意味合いや実益が考えづらいところがあります。また法定代理人が住民でない場合には、未成年者をロボットとする住民でない者の請求であるかどうかの検討が必要かもしれません。 |
○ 一方で、未成年であることを不適法とはとらえていない有力な見解もあります。たとえば「住民監査請求・住民訴訟の要件、対象等については、解釈論上各種の問題のあるところではあるが、ごく大まかにいえば。住民(国籍、年齢、自然人、法人を問わない)であると誰でも…」(塩野 Ⅲ p.236)※※
| ※※ その他に碓井p.41は、直截に、請求人の資格として行為能力の有無を問う必要は無い、とする。 |
(2) 未成年者の行政上の能力に関する主要な考え方
未成年者が、行政に対してどのような行為が単独でできるのか、について考えてみます。
一般には、行為能力に関する民法の規定は、行政法関係においても適用があるとされています。ただし本来、民法の行為能力の規定は、財産の保護など私的・財産法的な観点から、制限行為能力者を保護するのが目的なので、行政分野の内容ごとに、別の解釈をする必要があるとされます(塩野 Ⅰ p.405※)。
たほう、意思能力を欠く者の行為は無効であり、行為能力については、少なくとも財産上に関係ある行為については、民法上の規定が類推適用されるべきとの考えのもと、私人の公法行為は行為能力を要する、とする有力な見解もあります(田中 上 p.110。なお上記(1)の田中説は住民監査請求に関する説明であり、ここに掲げる田中説は、より一般的な内容である)。
これらをみる限り、行政に対し未成年者が行う行為(すくなくとも住民監査請求の提起)について、当然に民法5条1項が適用される、とすることには、一考の余地ありとせざるを得ません。
| ※ 上記塩野によれば、例として、運転免許や旅券発給申請などは、未成年者でも単独でできる、また、納税申告についても、納税義務自体は客観的に成立しており、税務署長との取引の観念が法律上存在しないので、納税申告も法定代理人の同意は不要であろう、としています。たしかに、高校生が原付免許をとるのに、警察の免許試験場での申請書には、親の同意は不要とされているようです。なお旅券発給申請書には、上記塩野の説明と実情が異なり、未成年申請の場合は親権者の同意署名を求める欄が設けられていますが、この点については下記4(1)※に述べるように、行為能力とは別の考慮事項があるため、旅券申請において未成年者の申請に行為能力を要求したとは、直ちに判断できないところがあります。 |
3 問題が顕在化した事例
以上の通り、この問題については、行政実例の態度は明確である一方、理論的には相当の見解の対立があり、法解釈論的に考えても、行政実例の示すあり方が、強固な理論的地盤に立っているとは言いづらいものがあります。その上で、その対立が具体的な問題として顕在化したものとして、次の日本弁護士連合会(日弁連)の要望事例があります。
この事例は、未成年者が行った住民監査請求を監査委員が不適法としたことに対して、当該未成年の請求人が日弁連に人権救済申立てを行い、日弁連は、請求先監査委員に対し、未成年者であるがために請求の権利行使を拒む合理的根拠はなく、少なくとも自己の行おうとする住民監査請求の内容・効果を弁識できる能力のあるものの請求と判断できれば、監査を実施すべきものとの見解の表明および要望を行った、というものです。
なおこの事例において、日弁連のWeb上に公表される要望書による限り、未成年者たる請求人が単独で住民監査請求をしたのか、親権者等の同意があったのかどうか、判然としません(監査委員は、未成年であることをもって、適法な住民監査請求を行うことはできないと判断。未成年単独の請求であることを理由としていない)。
しかしながら、本事例での日弁連の見解は、未成年者が住民監査請求を行うことができるかどうかについて、住民監査請求において民法の行為能力規定を適用することの合理性等の点から、未成年であるがために一律に住民監査請求提起の権利を拒むことは適当ではない、とするものであり、未成年者の住民監査請求行為を行う法律上の能力そのものを正面から論じている点、未成年者が単独で住民監査請求ができるかという検討と、内容は等しいものです。
| 【事例】
① 概要 ② 事案内容 ※令和4年4月から、民法上の成年年齢が18歳に引き下げられていますが、本事案の場合は、請求人が15歳であり、民法改正による成年年齢引き下げ後においてもなお未成年であり、しかも選挙権も有しない、という構造となっています。 |
4 検討
この問題は、法的論拠が明確とはいえず、最高裁判例がない中で、行政実例とは異なる結論を示す有力な見解も存在するため、単純に結論を割り切ることが難しいものです。といって、上記のように問題が現に具体化した事例もあり、仮にこうした請求がなされた場合、放置することはできません。
ついては、論点を整理しつつ、以下で検討します。
(1) 前提
すくなくとも、制限行為能力者であることをもって、当然に住民監査請求のような行為ができないとすることは、根拠薄弱を疑わざるを得ません(上記2(2)塩野参照)。現に法律行為そのものである原付免許の申請は親権者の同意は不要の扱いとなっており、行政実務において、未成年者であることをもって、一律かつ当然に、単独の法律行為を認めないと主張することは、どう考えても無理があります(無論、原付免許申請と住民監査請求は、単純比較し得るような行為内容の同質性があるわけではないのですが、私人の行政への行為に「当然に」年齢による行為能力獲得を要するものではない、とする実例が現に存在することには違いありません)。※、※※
また行為能力論による限り、未成年でも婚姻により完全行為能力を獲得し(民法753条。ただし2022年4月1日前まで)、であるならば、婚姻により未成年者でも住民監査請求を単独でできるようになる、と構成することもできますが(上記日弁連要望書によれば、そのような取扱いをする団体もあるようです)、これも如何にもおかしな話です。なぜなら、住民監査請求を行うことができる能力の問題は、財産の取扱能力ではなく自治体財務行政に対する判断能力の問題であるところ、結婚によっても選挙権に成年擬制が及ばなかったのに、なにゆえ私的財産管理行為より選挙への参加との同質性が高い住民監査請求については、結婚によりその能力を認め得るのか、その理屈は何か、という疑問が生ずるからです。
| ※ 上記2(2)塩野例示にある旅券(約3千万人所持)発給申請は、運転免許(約8千万人所持)申請と並び国民に一般的な行政手続ですが、実務においては、未成年者の旅券申請には親権者の同意が必要とされています(旅券発給申請書様式参照)。 事実関係の公証を本質とする身分証明書である旅券の発給申請において、許可処分の申請である原付免許の申請より親権者同意について厳しく運用されているのは奇異にも思われますが、旅券申請の場合、未成年者の保護など、行為能力とは関連しない個別の政策目的への顧慮が必要とされており、旅券発給申請の事例を、未成年者の行為能力をストレートに認めていない例として、住民監査請求の検討材料とするには限界がありそうです。 (いわゆるハーグ条約上の問題が、政策的に考慮されているとされ、外務省Webサイト(ハーグ条約関係)では、子の国際間の連れ去り問題への対応の一つとしての未成年者の旅券発給申請時の親権者同意の必要性について、説明があります。したがってこの場合、旅券発給を単純な公証行為(国際身分証明書発行という、公の権威に基づく事実の確認行為)ではなく、出入国管理及び難民認定法60条による海外渡航の一般的許可処分(参照:旅券法研究会編著「旅券法逐条解説」有斐閣(2016年)p.45)として観察することとなります。余談ですが、旅券発給のこうした性格にかんする有名な事例が最判昭33.9.10民集12.13.1969) |
| ※※ 下記の通り、未成年者は単独の訴訟行為を認められていません(民事訴訟法31条)が、これを行為能力要否の考慮事情とすることも限界がありそうです。民訴法31条については、独り立ちできない者の保護は取引界における場合と異ならず、かつ訴訟追行は取引行為より複雑であるためであり、法定代理人の同意があれば自ら法律行為ができる取引行為と異なり、訴訟追行は必ず法定代理人が代わってこれにあたらねばならない(新堂幸司 「新民事訴訟法(第5版)」弘文堂(2011年)p.152)、請求について審判を求めるためには、訴えの提起をはじめとして、さまざまな訴訟行為を行わなければならず、訴訟行為の結果によって当事者は、重大な利益・不利益を受けるので、法は、訴訟能力を一定の者に限って認めている(伊藤眞「民事訴訟法(第7版)」有斐閣(2020年)p.132)とされ、つまりはあくまでも取引安全の延長線での措置であり、行為能力と同質的な考え方による制度といえます。 |
そうなると、日弁連要望書が主張する通り、未成年者(単独)の請求を拒むとすれば、それにどのような合理的な理由があるのか、について検討する必要があります。そして、そのような合理的理由がないとなると、この問題については、結局のところ決め手なし、といわざるを得なくなります。
なお、上の日弁連要望書では、公選法や民法の仕組みを参照して、請求を拒む合理性がないのではないか、との論旨を展開しており、それ自体は、この問題に関する本質的な制度(特に民法)の検討なので、十分理解できるものですが、一方でこの論旨が決定的な結論を導く切り口かといえば、必ずしもそうではないことは明らかであり(これはこれで一般論の次元であり、そもそも、そうした制度論解釈で明快な答えがでるなら、すでに答が出ているでしょう)、もっと別の論点を通して考えてみる必要があります。
(2) 未成年者の単独請求を認めた場合の問題の存否
そこで、未成年者の単独請求を認めると、住民監査請求制度の適切・合理的な運用、また住民監査請求・住民訴訟制度の目的達成のために重大な問題がおこるのか?という観点で考えてみます。
そもそも、地方自治法が住民監査請求・住民訴訟という制度を用意して、自治体財務運営の適正化を図る手段を住民に用意した以上は、その制度が十分に機能するかどうかは、制度運営の一番根源的な課題であり、当然ながら真っ先に考えなければならない論点です。また、そうした問題が法律・制度上存在するかどうかは、結論を得やすいものだからです※。
| ※ なお、未成年者では住民監査請求や住民訴訟で未熟で拙劣な主張等をなされ、適切な問題の追及ができないのではないか、という考え方も出てきそうですが、ここでは無視します。なぜなら、当事者が誰かによって生ずる主張等の差異・巧拙は「住民なら誰でも住民監査請求・住民訴訟が提起できる」仕組みをとる以上、必然的に起こる問題であり(そこらの大人より賢明かつ巧みな主張ができる高校生は、相当の人数がいそうです)、また、そのような要素も制度上織り込まざるを得ないからです。 |
ア 未成年者と住民訴訟
民事訴訟法31条によれば、未成年者の単独の訴訟行為は無効です。つまり、未成年者が単独で住民監査請求を行うことができたとしても、その未成年者は、単独では住民訴訟を提起することができず、その限りにおいて、住民監査請求+住民訴訟、という制度を十二分に活用することができないことになります。
イ 本当の問題は何か?
ただし、上記アの問題は、当該未成年者に限定された問題であり、制度論的な観点から、ある未成年者が単独で住民訴訟を起こせないことを踏まえ、本当に検討すべき問題は、次のようなものとなります。
住民監査請求制度は、住民訴訟制度とあいまって、終局的には、対象財務会計行為等の違法性の判断、それに対する予防・是正の具体的措置とを裁判所にゆだね、一種の司法的統制に服させるものです(松本逐条242条関係)。
この制度が、米国の納税者訴訟制度に範をとって創設されたことも考慮すれば(塩野Ⅲp.236、昭38自治法改正詳説p.327など)、ある条件の発生により、特定の財務会計行為等について、終局的に住民訴訟で違法性を問うことができなくなるのは、住民監査請求(+住民訴訟)制度の適正な運用、制度目的の達成という点で、重大な問題というべきものです。
とすれば、その未成年者が住民監査請求で取り上げた財務会計行為等について、別の住民が改めて住民監査請求を提起することが、一事不再議等により認められないのであれば、その財務会計行為等について住民訴訟で争う途が完全に閉ざされことになり、制度運用上看過しがたい問題となります。仮にそうであれば、何らかの意図をもった者が、住民訴訟を阻止するために、親権者の協力のない未成年者に住民監査請求を起こさせることにより、その財務会計行為等についての住民訴訟を阻止することができるので、その点を考えただけでも、この論点がはらむ問題の重要性は明らかです。
ウ 他の住民による住民監査請求の提起の可能性
ところで一般には、同じ内容の住民監査請求を別の住民が行うことは、下記の行政実例が示すように、可能と理解されています。
| 行実昭34.3.19では、住民Aから住民監査請求があり、監査結果を通知した後、別の住民Bから同一内容の請求がなされた場合において、「請求者が異なる以上「一事不再議」※の原則を援用することはできないが、すでに行った監査の結果に基いて、請求に係る事実がないと認めるときは、その旨請求者に通知すれば足りる」としています。つまり、Bの請求自体は適法であり、Bは(Aが既に住民訴訟を起こしていなければ(地方自治法242条の2第4項))住民訴訟を提起する資格が得られます。また監査を再度行うかは、行政経済(効率)の点から考えて、既に行った監査結果を覆す(見直す)必要が見いだせなければ、その監査結果を活用しよう、ということです。 |
| ※ 「一事不再議」は、行政の世界では、裁断的な判断が蒸し返されたとき、どう取り扱うか、という場面で持ち出されることが多いようです(参照:塩野Ⅰp.175-(不可変更力、実質的確定力))。重要な判例として、最判昭29.5.14民集8.5.937があります(一事不再議を判断の直接の論拠とはしていない)。 ただし、住民監査請求も裁断的な判断とはいえますが、一般の裁断的判断(特に不服審査など)は、請求内容に権利義務等の法律上の利害関係がなければ当事者になれないのが通常であるのに対し、住民監査請求の場合は、同一の事案に対して、住民ならだれでも請求人になれる、という構造的な違いがあり、そのため、別の住民にまで一事不再議の原則は及ばない、ということになると考えられます。なお、同一の請求内容に対し、必要がなければ再度の監査をしない、というのは、行政経済・行政効率の問題であり、一事不再議とは別の問題です(後でされた請求に対しても、監査結果を示す応答を監査委員がしていることには違いがなく、いわば間接的に監査を行ったということができる)。 この行政実例の後、最高裁は、同一人が同一内容の住民監査請求を再び行うことは不適法との判断を示しています(最判昭62.2.20民集41.1.122。なお本判決は、一事不再議の原則を、判決結論の論拠とはしていない)。ただし、最高裁は、適法な請求を監査委員が不適法とした場合は、再度の住民監査請求を行うことを認めています(最判平10.12.18民集52.9.2039) |
なお監査請求では、先順後順で、すくなくとも住民訴訟の提起資格の点では何ら影響はないですし(適法な住民監査請求を経ていれば、住民監査請求の先順後順に関係なく、住民訴訟の原告適格を得ることができる)、住民訴訟では先順後順は問題が生じますが(地方自治法242条の2第4項)、上記の通り未成年者は単独で訴訟の提起はできないので、後順の請求人が住民訴訟を提起するには、その限りで法律上の障碍は生じません。
となると、この行政実例の法理が通用する限り、未成年者の単独請求を認めたとしても、住民監査請求⇒住民訴訟という、司法審査を含めた請求対象行為の審査という制度上の仕組みを完全に追行することは可能ということになるので、未成年者の単独請求を認めることが、住民監査請求制度の運用を機能不全にする可能性はないということになります。そしてこれ以外に、未成年者の単独請求を認めたがために、住民全体で、自治体財務運営の適正化の機会が損なわれるような事情が発生する問題点は考え難いところです。
したがって、未成年者が行為能力制限を受けるがために、未成年者の単独請求によって、住民監査請求制度の適正運用・目的達成の障碍が生じるものとはいいがたい、ということになります。
5 結論
このように考えると、未成年者単独の請求を適法とするか違法とするかについては、法的論拠が明確とはいえず、最高裁判例がない現時点においては、明確な論拠をもった結論が出しがたい問題となります。
ただし、住民監査請求が一人からでもでき、請求に対して監査委員は監査の実施を義務付けられる制度であることを考えると、一定の行政コストを消費する請求行為には相応の判断能力を求めるべきではないかという一般常識的な疑問も否定すべくもなく、そうなると、たとえば民法上の行為能力獲得年齢(成年)と選挙権獲得年齢が同じである(令和4年4月~)ことも考慮すれば、18歳で線引きして住民監査請求権行使に枠をはめるべきではないか、などといいった考えを無視することもできないでしょう※。
| ※ 未成年者は、親権者の同意により法律行為を完全に行うことができますが(民法5条1,2項)、これは未成年者の財産上の権利を保護するための仕組みであり、請求人個人の権利利益とは直接の関連がない事項を対象とする住民監査請求(住民訴訟)においては、親権者の同意は法律上の有意性がないといえます(親権者の同意は、この請求はマトモなものですというお墨付きだとでもいうのでしょうか)。 こうしたことや、制度運用の法的安定性確保、また行政実務の実態面からの適正運用という観点からすれば、親権者同意のような停止条件的要素は無視して、ある年齢で一律に請求適格を認める、認めない、の外形基準による線引き運用(民事訴訟や選挙のような)を行うことが適当であり、その年齢は、住民監査請求を提起するに足るとみなし得る一般的発達段階、ということになるのでしょう。それはたとえば、選挙権を獲得するに足りる発達段階と社会的に認められた18歳なのかもしれませんし、公民としての基礎的資質能力の教育が義務教育課程で一応賄われるとすれば(学習指導要領は、そのような前提に立っているようです)、義務教育修了段階(15~16歳)なのかもしれません。 |
結局、行政実務の適切な運用という観点も考慮すれば、監査委員としては、各論を比較検討して、より妥当と考える結論を選択し、画一的な基準によって対応すべきものでしょう※※。
| ※※ この点に関する筆者の私見は、全体集約版に記載する通り。 |
ただし、「請求人が請求内容及び効果を弁識できる能力があると考えられる」かどうかという点は、無視し得ない論点を含むことに注意しましょう。
「請求内容及び効果を弁識できる能力があるかどうか」は、言い換えれば請求人に意思能力があるかどうかに接近する問題であり、その点は未成年者に限らず、すべての請求において留意しなければならない問題です。
なぜならば、請求人は住民として、請求内容や自治体財務運営の適正化を求める趣旨を理解して、請求を行う明確な意思を持っているかどうかは、住民監査請求制度の趣旨からしても、常に考慮しなければならないことであり、またそもそも意思能力のない者の法律行為は民法上無効とされており(民法3条の2)、住民監査請求においても、そのような請求は無効と解すべきものだからです。

久しぶりにこの地に来てみたら波消しブロックがドーン! まあ波静かなところとはいえ台風など来れば浜の前の家など大変なことになるのでしょうから、やむを得ないのでしょう。