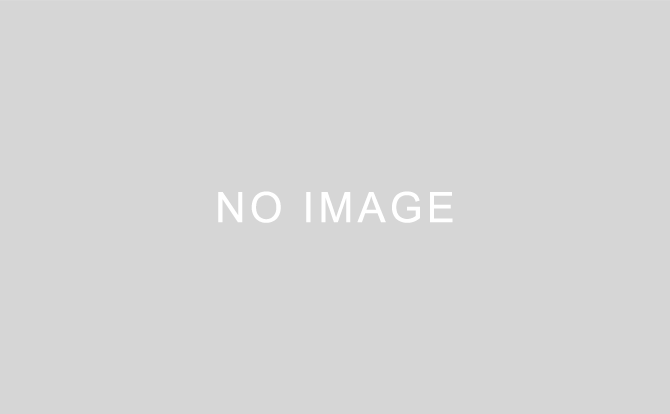本ページの一番下に、本ページのPDF版リンクを設けています。
最終改訂 2025.2.13(改訂箇所は改訂履歴ページ参照)
住民監査請求は、その自治体の住民のみが行うことができます。住民でない者の請求は、住民監査請求の要件を満たさない、不適法な請求です。
1 住民であれば、自然人(法人に対して生物としての「人」。以下「個人」として説明)、法人のどちらでも、また国籍を問わず請求できます。
2 法律上の行為能力を必要とします(異なる見解があります)。
3 住民が住民監査請求を行った後、住民監査請求の終了(完結)までに、住民でなくなった(当該自治体外に転出、死亡)場合は、請求は不適法なものになります。
4 住民たる請求人が、請求に際し代理人を立てることは可能であり、代理人が住民でない場合であっても、住民の正当な授権があれば、適法です。
|
はじめに 本ページで説明する、「請求人が当該自治体の住民であること」は、「0.2 住民監査請求の要件は?」冒頭で説明の通り、 この要件は、いうまでもなく、住民自治的制度である住民監査請求制度においては、根幹をなす重要な要件です。ただし、数多くの議論が生じている対象の財務会計行為等該当性、監査請求期間ほどには議論が生じていない要件ともいえます。 |
1 住民監査請求ができる「住民」
(1) 概要
住民監査請求は、住民である限り、誰でも、一人からでも、行うことができます。個人ではない、法人や外国人でも可能です(法人について行実昭23.10.30。外国人については、地方財務実務提要参照)。
逆に言えば、住民でない者からの住民監査請求は、住民監査請求の要件を満たさない不適法な請求であり、監査を行うことなく、請求を退けるべきものです。
(2) 「住民」とは
ア 総論
地方自治法242条1項に定める「住民」について、そもそも地方自治法では10条1項で住民の定義をしているところ、242条は住民に関する固有の要件を定めておらず、また住民監査請求の制度目的・趣旨から考えても、地方自治法10条に定める住民と異なる概念・要件を必要とするとは考えられないところです。
とすれば、地方自治法242条で定める住民監査請求の請求権者としての住民は、当然に地方自治法10条1項に定める住民定義によるものとなります。行政実例や松本逐条で、住民監査請求固有の「住民」概念が説明されていないのも、こうした趣旨によるものと考えられます。
ところで地方自治法10条1項は、「市町村の区域内に住所を有する者」を、当該市町村およびこれを包括する都道府県の住民と定義しています。そして地方自治法10条1項で定める住民は、松本逐条(10条関係)同条2項の権利義務のほか、住民監査請求を行う権利を有する者とされています。
つまり「市町村の区域内に住所を有する者」が、当該市町村及び市町村を包括する都道府県において住民監査請求を提起できる者となります。
次に、この住民の範囲について、松本逐条(10条関係)では、自然人、法人の双方を含む、国籍の如何を問わない、としています。
ということは、地方自治法10条1項の住民の定義が上記の通りであり、地方自治法242条1項の規定や、住民監査請求の制度趣旨からみて、その他の除外条件が何ら見いだせない以上、住民監査請求ができる「住民」は、当該自治体に住所を有する者であり、個人・法人の別や国籍を問わない、ということになります。なお、法人には下記イの通り、いわゆる権利能力のない団体も含まれます。
また、請求の時点以降に住民であればよく、請求の対象となった財務会計行為の時期との関係は問われない(対象となる財務会計行為の行われた時点以降に住民となっても、問題とならない)とされています(参照:実務住民訴訟p.21)※。
地方自治法242条1項の明文による限り、また住民監査請求の制度趣旨が自治体財務運営の適正化にあるところ、その本質は、住民監査請求を通じて、請求以後の将来に向けて、自治体財務の健全化を図ることを目的とするものであることからすれば、このように、請求の時点において住民としての資格を有すればよい、と解するべきと考えます。
| ※ 参考:秋田地判昭55.3.17判例時報1086.90。本件は、市町村合併前の旧A町の職員の行為を、旧A町を含め合併した新B市の住民(ただし合併前は旧A町の住民ではなかった)が、合併後に住民監査請求した事案であり、これについて、旧A町の権利義務はすべて合併後のB市に継承されるので、旧A町が同職員に損害賠償請求権を有するなら、合併後のB市は同請求権を有し、合併後のB市の住民となった原告が、B市長に代位して損害賠償請求権の行使について住民監査請求をなし得ることは、地方自治法242条の規定からして明らかである、とする |
なお実務上は、個人については、原則として住民票上の住所により、法人については、法人登記簿上等の主たる事務所・本店の住所※※により判断することとなるでしょう(詳細は下記(3)参照)。
| ※※ 主たる事務所・本店が自治体内に所在せず、支所・支社・営業所のみしかない場合は、住所を有するとは認められません。参考事例として、神戸地判平14.9.19判例地方自治243.77 |
イ いわゆる権利能力のない(法人格のない)団体の扱い
いわゆる権利能力のない(法人格のない)団体については、明確な法令根拠があるものではありませんが、一定の条件をみたし、かつ当該自治体に住所がある限り、住民監査請求の請求人となることができるとされています※1。例えば最判平18.6.1集民220.353は、いわゆる権利能力のない社団の提起した住民訴訟について、最高裁は、原告に当事者としての資格があることを前提として審理をしています※2(本件は、住民監査請求の請求期間徒過について正当理由がないことを理由に訴え却下)。
| ※1 このような団体も、団体としての社会的実体があり、権利能力のない団体の法理により、一定の範囲で法律行為の主体となることを認められていることからすれば、法律上の法人と扱いを異とする理由がありません。また住民税の納税義務も発生し得る(地方税法24条6項、294条8項)ことからして、いわゆる権利能力のない団体は、個人や法人同様、自治体の財政のあり方に利害関係を有し得るものであるといえ、これらが住民監査請求の請求人となり得る論拠として考えられます。下級審の裁判例でも、こうした点を、いわゆる権利能力のない団体が住民訴訟を提起し得る論拠としてあげるものがあります(例:下記東京地判平12.7.31等)。 |
| ※2 権利能力のない団体の提訴事例は、本件が初見ではなく、それ以前にも下級審裁判例で多数あり、特に大きな争点となることもなく、原告適格を認められています。上記平成18年最判は、権利能力なき社団の住民監査請求提起能力について判例行政法p.42(海老名富夫)で取り上げられているものであり、参考としました。 |
なおこの場合、どのような団体でもよいのではなく、まず、住民訴訟の際適用される民事訴訟法29条において「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる」とされていることからして、「代表者又は管理人の定めがある」ことは当然に必須と考えるべきです。
その上で、いわゆる権利能力のない団体としての取扱いを受けるためには、①団体としての組織を備えている ②多数決の原則が行われている ③構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続する ④その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定している ことが要件とされており(最判昭39.10.15民集18.8.1671。「社団」に関する。)、前記の住民訴訟提起者としての資格との関係においても、住民監査請求の請求人となるためには、その団体が法律行為の主体となり得るものとして、この要件を満たす必要があるべきです(参考:福岡地判平10.3.31判例時報1669.40。また参照:奥田p.20は権利能力のない社団の法理が適用される場合は、法人格が付与されたと同様に取り扱われるため、監査請求をすることができると解する、としている)※3。
ただし、このような要件を備える場合でも、もっぱら住民としての資格をかいくぐる目的で、いわゆる権利能力のない団体を隠れ蓑として住民訴訟を提起した場合は、住民訴訟制度の趣旨に反するので、原告適格は否定すべき、とする裁判例があります※4、※5。この判決のいう住民訴訟制度の趣旨の一つは、住民自治の実現手段にあり、請求人たる資格は、住民監査請求・住民訴訟に共通することが当然なので、上記の裁判例で示されたような、住民としての資格をかいくぐるような性質の団体を排除する考え方は、住民訴訟のみならず、住民監査請求にも当然に適用されるべきものでしょう(参照:実務住民訴訟p.22)。
| ※3 権利能力のない団体の名で請求された事案において、その団体が上記の権利能力のない団体としての要件を満たさない(代表者や規約がない等)の場合に、団体名に事務局代表として付記された個人(他に個人名の表示がない)が請求人であり、監査の陳述時に出席した団体のメンバーと称する者は請求人とはならない、と判断した事例があります(東京地判昭53.5.31行裁例集29.5.1111)。 このように、表示された団体の適格性がない場合に、直ちに請求を不適法とするのではなく、無効行為の転換に類する措置により救済することは、十分あり得るものと考えます。 |
| ※4 参考となる裁判例として、
① 前記福岡地判平10.3.31判例時報1669.40 ② 東京地判平12.7.31 ③ 青森地判平18.3.17 |
| ※5 ただし、上記裁判例のうち、福岡地判の論旨中、後半部分は、まさに住民自治の趣旨に反する問題であり、これを否定する論拠はないと考えますが、前半部分は、これのみをもって住民監査請求・住民訴訟制度の趣旨から逸脱しているとどこまでいえるのかは疑問なしとしないところです。たとえば、本判決は、本件原告が上記条件に該当し、当事者適格を欠く論拠として「原告自身、福岡市の職員など、個人名を明かして住民訴訟を提起することが憚られる者の利便もあることを自認していること」(本件は福岡市の事案)ともしていますが、仮にその福岡市職員が福岡市民であれば、本来的に住民監査請求・住民訴訟を提起する資格を有するのであり、その場合に住民訴訟を提起する際に大人の諸般の事情により団体の名に隠れたとしても、住民要件を潜脱しているわけではなく、果たしてそれが住民監査請求・住民訴訟制度の趣旨に反するといえるでしょうか。 |
| 【Q1】 複数の請求人のうち、一部の者が住民でないときは? |
【A1】
その他の不適法要件がない限り、請求自体は適法です。
○ このような場合は、請求人のうち住民である者の請求は、住民としての要件を満たしているものとして取り扱います(行実昭57.10.26)。
○ なお、実務上は、後続する住民訴訟の原告適格を画定する上からも、決定文等では、請求人名は住民である請求人の氏名のみ記載し、あわせて「なお請求人○○は、住民ではなく、地方自治法242条1項に規定する請求の要件を満たさないので、同人は本件請求から排除した」などと追記すればよいでしょう。
○ 複数の請求人の一部が、請求後に死亡や転出で住民でなくなったとき(下記3参照)も、同様の手続によるべきでしょう。
| 【Q2】 一部事務組合・財産区に関する住民監査請求は、誰が行うことができるのか? |
【A2】
一部事務組合構成自治体の住民、財産区所在市町村の住民が行うことができます。
○ 一部事務組合には、普通地方公共団体に関する法規定が適用される(地方自治法292条)一方、一部事務組合の住民というものは存在しないため、請求人資格を住民とする住民監査請求の可否は即断しづらいところがありましたが、行政実例(昭45.7.14)は、一部事務組合を構成する自治体の住民は、一部事務組合の監査委員に、住民監査請求ができるとしています。広域連合についても、同様です(広域連合構成自治体の住民が、広域連合の財務会計行為について、同連合の監査委員に住民監査請求を行い、その後住民訴訟となった事案について、最判平25.3.28集民243.241は、本訴訟は地方自治法292条により準用される同法242条の2に基づくものとして、広域連合の財務会計行為等に対する住民訴訟の提起は適法であるという前提のもと、請求対象財務会計行為の違法性に関する本案審理を行っています)。
○ 財産区については、地方自治法292条に相当する条文がなく(地方自治法294条1項をもって同法242条を準用できるのかは、議論がありそうです)、かつ本来の自治体の業務を分担する一部事務組合と異なり、市町村の一部で財産等を有するという性格のものであることから、住民監査請求の可否について、一部事務組合以上に判断に迷うところがありますが、行政実例(昭27.11.4)は、財産区が所在する市町村の住民(当該財産区所在区域ではなく、市町村全体の区域の住民)は、財産区の財産管理について、住民監査請求を行うことができるとしています。また、別の行政実例で(昭29.3.9)、請求の相手先は、財産区所在市町村の監査委員となる、としています。
なお下級審の裁判例は、財産区について住民監査請求をできる者の範囲に関し、昭和27年行実と同じく財産区所在市町村の住民であれば可とするものと、財産区所在区域居住者に限るとするとするものの両方が存在します。実務上は、行政実例により、財産区所在市町村の住民であれば、誰でも住民監査請求を行うことができるものとすべきと考えます。その理由は、下記平成19年大阪地判判示の通り、財産区の財務運営の適正化については、財産区所在市町村全体の利害に関わるため、財産区所在市町村住民であれば住民監査請求が行い得るとするのが妥当と考えるためです。なお下記昭和58年京都地判や平成5年大阪地判については、その論旨において、財産区の業務執行は所在市町村長が行い、財務的一体性も地方自治法上考慮を求められ、市町村全体の財務的利害と関連が生ずる以上(とりわけ京都地判(三)のような懸念事項があるならなおさら)としており、であれば住民監査請求の機能を考慮する限り、逆に市町村全住民に住民監査請求の権利を認めるべき論拠とすべきではないでしょうか※。
| ※ 【市町村全住民の請求を可とする裁判例】 ① 大阪高判平8.6.26行裁例集47.6.485 (分権一括法前の地方自治法の規定による。下記平成5年大阪地判控訴審) 財産区は、市町村及び特別区のうちの一定範囲の地域及びその地域の住民を構成要素とする特別地方公共団体であって…、独立の法人格を有する…されているが、その権能は、所有する財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に限られており、原則として固有の機関を有していない。すなわち、財産区の財産等について、『その財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止については、この法律中地方公共団体の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止に関する規定による。』(294条1項)とされているものの、その機関に関しては、条例により財産区の議会又は総会を設けて議決にあたらせ…、あるいは条例により同意機関として財産区管理会を置くことができる…とされている以外、特別の規定はない。そうすると、右議会又は総会が設けられたとき以外の財産区の意思決定機関は市町村等の議会ということになると解される…。また、財産区の執行機関については、これを明記した特別の規定は何ら存しないが、その事務処理に関する規定をみてみると、市町村等の長は、財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止で重要なものについては、財産区管理会の同意を得なければならず…、財産区の財産又は公の施設の管理に関する事務の全部又は一部を財産区管理会又は財産区管理委員に委任することができるとされ…、都道府県知事は、財産区の事務の処理について市町村等の長に報告等を求めることができるとされており…、これらのことからすると、法は市町村等の長が財産区の事務の処理に当たることを予定しているものと解することができる。以上にみてきた財産区の沿革と財産区に関する各規定及び財産区がそれなりの法人格を有する特別地方公共団体であることを考慮すると、法294条1項が前示のように規定しているのは、財産区の所在する市町村等にその事務を委任する趣旨であると解することができ、財産区の所在する市町村等は、財産区の事務を団体委任事務として処理するものと解する…のが相当である。そうだとすると、財産区についても法242条及び同条の2が適用されるといわなければならず… …右のとおり、財産区についても法242条及び同条の2が適用されるとすると、財産区の住民のみならず、当該財産区の所在する地方公共団体の住民にも財産区についての住民訴訟の原告適格を認められるというべきであり…② 大阪地判平19.12.27判例タイムズ1270.293 …財産区の所在する地方公共団体の一部としての性格も有しており,財産区のある市町村又は特別区は,財産区と協議して,当該財産区の財産等から生ずる収益を市町村の事務に要する経費の一部に充てることができるとされているなど…,財産区の所在する市町村又は特別区の住民も財産区の財産等の管理等の適正を要請する立場にある。したがって,財産区の沿革等を考慮しても,財産区の所在する市町村又は特別区の住民に,財産区財産についての住民訴訟の原告適格を否定することはできない。【財産区所在区域の住民のみ請求資格を認める裁判例】 ①京都地判昭58.10.21判例時報1100.50 (一) 財産区の財産等から生ずる収益は、主として財産区の住民に帰するものである。したがって、財産区の財産等の管理等に利害関係をもつのは、主として財産区の住民である。法296条の5第2、3項、法施行令218条の2は、このことを前提としているものと解される。(二) 法242条の2は、普通地方公共団体の住民に注民訴訟の原告適格を認めているから、これを財産区に準用する場合、原告適格のある者を財産区の住民に限るのが至当である。(三) 原告は、財産区がその財産で支払うことのできない多額の債務を負った場合、その財産で支払えない債務分は、その財産区の所在する市町村の負担となることから、その市町村の住民にも原告適格を認めるべきであると主張するが、このような例外的場合を考慮して、住民訴訟の原告適格を拡張すべきではないし、また、右の場合にも、財産区の住民による住民訴訟を通して財産区の違法な債務の負担行為等の是正を図ることが可能である。② 大阪地判平5.12.22行裁例集44.11・12.1038 財産区について住民訴訟の規定の準用を認める場合、法242条の2第1項の「普通地方公共団体の住民」とあるのは「財産区の住民」と読み替えることになるので、その原告適格を有するのは財産区の住民に限られろと解せられる。このように解することは、沿革的に財産区制度が、市町村制の制定に当たって財産を有する旧村や旧部落に対して市町村とは別個の権利帰属主体としての地位を与え、当該財産区住民がその財産につき有していた利益をそのまま確保できるようにすることを意図して設けられた制度であること、及び、地方自治法の上でも、財産区の財産等に関し特に要する経費は財産区の負担とされ…、財産区の財産等の管理等についてはその住民の福祉を増進するように努めねばならず、財産区の設置の趣旨を逸脱する虞のあるものについては都道府県知事の認可を要するとされていること…等に鑑みても妥当であると考えられる。財産区の財産等の管理等については財産区のある市町村の一体性をそこなわないように努めねばならず…、財産区のある市町村は、財産区と協議して、当該財産区の財産等から生ずる収益を市町村の事務に要する経費の一部に充てることができるとされているから…、財産区のある市町村ないしその住民も財産区の財産等の管理等について利害関係を全く有しないわけではないが、それは一般に財産区住民が財産区財産について有する利害関係に比すればはるかに希薄かつ間接的であり、このことをもって財産区のある市町村の住民にまで財産区についての住民訴訟の原告適格を認めなければならない根拠とすることはとうていできない。 |
| 【Q3】 議員や首長は、住民監査請求を行うことができるか? |
【A3】
議員は可能ですが、首長は不可と考えるべきです。
○ 議員については、できると解されます。例えば名古屋地判昭45.7.11行裁例集21.7・8.1005では、地方自治法242条および242条の2に、何らの限定を加えていないことをこの論拠としており、参考となるでしょう。議員は自治体の事務の執行について権限を有する機関の職員ではなく、また議会自体には強力な権限(例:地方自治法100条、98条)はありますが、議員が単独でこれらを行使するのではなく、これら権限は、議員の集合体としての議会の議決を通じて行使するものであり、議員が住民監査請求を行うことについて、下記の首長のケースのような問題は生じないためと考えればよいでしょう。
○ 首長については、現役の首長が住民監査請求を提起することはおよそ考えられないところではありますが、たとえば住民監査請求を提起した後、首長に就任した場合は、次の理由により不適法とする裁判例があります(大阪高判平18.3.23)。
・ 住民監査請求は、首長などの執行機関等に対して必要な措置を求める制度であり、首長がみずから住民監査請求をすることは、制度上予定されていない
・ 首長は自ら違法・不当な行為を行わず、またはこれを是正できる
・ 首長が住民訴訟を提起できるとすると、本来は必要な議会の議決なしで訴えの提起ができることとなる
この論旨に加えて、住民監査請求によらずとも、首長は監査委員に監査要求権があり、この場合監査委員は、監査を行う義務が生じること(地方自治法199条6項)、その監査で行う得る内容や、監査結果に対する監査委員の勧告権限などは住民監査請求の監査委員権限と同等であることも含め考え合わせれば、参考となると考えます。
(3) 住所について
ア 個人の場合
上記の通り、実務においては、原則として、住民票の住所を基本として判断することとなるでしょう。ここで「原則として」というのは、次の例外が考えられるためです。
○ 住民票があっても、その自治体に居住実態がない場合(通常は、監査委員の職権で調査・判断されるものと考えられる) ⇒ 住民とみなさない判断も可能
○ 住民票がないことにやむを得ない事情があり、生活の本拠があることが請求人により証明される場合 ⇒ 住民と判断することも可能
① 個人の「住所」の原則
地方自治法において、個人の「住所」とは、生活の本拠地(民法22条)を意味します※。
| ※ 参照:松本逐条(10条関係)、塩野Ⅲ p.156、田中 中p.97。また最判昭29.10.20民集8.10.1907(公選法における住所事案)において「およそ法令において人の住所につき法律上の効果を規定している場合、反対の解釈をなすべき特段の事由のない限り、その住所とは各人の生活の本拠を指すものと解するを相当とする」。 |
なお地方自治法では、個人・法人は住所を必ず1か所もち、本人の意思にかかわらず当然に、その住所のある市町村・都道府県の住民になると考えます(松本逐条 10条関係)。民事法では、同一人が複数の住所をもつことがあり得るというのが有力説ですが、地方自治法ではこのように住所は1か所という考え方であり、ということは、住所は排他的性格をもつ、つまりA市(町村)の住民は、A市(町村)以外の住民としての立場を併有できない、よって同一人が同時に複数の自治体で住民監査請求をすることはできない、ということになります。
② 住民票の住所の住民監査請求実務における意義
市町村は「その住民につき」住民たる地位に関する正確な記録を常に整備することが、地方自治法13条の2で求められています。この記録は、具体的には住民基本台帳になります。
そもそも、住民票の制度があるにもかかわらず、住民監査請求のたびに請求人に住所要件を充足していることについて、個別に証明を求め、その調査検討を行うことは、請求人・監査委員双方にとって煩瑣でしかありません。
また住民票には住民の居住関係の公証機能があること(住基法1条)、住民側にも正確な届出に関する努力義務を課すこと(同3条3項)、さらには住民基本台帳法4条で、住民の住所に関する法令の規定は、地方自治法10条1項に規定する住民の住所と異なる意義の住所を定めるものと解釈してはならないと規定していることからも明らかなように、住民は、地方自治法10条1項でいう「住所」(=民法22条の生活の本拠としての住所※)のある市町村の「住民」として、その市町村の住民基本台帳に記録され、これに基づいて、その市町村の住民として、各種の権利を行使する等が予定されていること(松本逐条 13条の2関係)を考慮すると、地方自治法や住民基本台帳法には、住民票の住所を地方自治法10条1項の住所と推定※※する決まりはありませんが、住民監査請求の実務においては、原則として、住民票の住所のある市町村の住民であると推定してよいと考えます※※※。
| ※ 参考 市町村自治研究会 編著「全訂 住民基本台帳法逐条解説」 日本加除出版(2014年)p.61 |
| ※※ 法令で「推定する」とある場合は、当事者間に別の合意があったり、それと反する事実が証明されない限り、法令で「推定する」事実があるものとして扱われることになります。 |
| ※※※ 参考:奈良地判昭57.3.31行裁例集33.4.785 「地方自治法…10条1項によれば、住民とは市町村の区域内に住所を有する者であるが、当該区域内に住所を有するか否かの確定については特に規定するところがない。しかしながら住民の居住関係の確定、証明一般については住民基本台帳法がこれを定めており、同法による住民票の記載は住民の届出に基づいて市町村長がこれを作成するものであって高度の公証的機能を有し、選挙人名簿の登録を始めとして住民に関する各種行政事務はこれを基礎として行なわれていることに照すと、法242条の2第1項の住民とは原則として当該市町村の備える住民基本台帳に記録されたものすなわち当該市町村に住民票を有する者を指すものと解するのが相当である」(原告のうち1名は住民票がないことを理由に、訴えを却下)。 ただし、判示事項中「原則として」という以上は例外があり、下記③のような例外についてどのように解釈すべきかは、この判決の内容からは明らかではありません。あわせて参考:塩野Ⅲp.157、宇賀自治法p.22。また藤田p.316。 |
③ 例外
しかし上記ア本文下線部にあるように、例外があります。これは、地方自治法の住所が、生活の本拠という生活実態により定められることを予定されており、住民票上の住所が必ずしもこれと一致するとは限らないことによるものです。こうした住所認定の問題は、松本逐条10条の運用の項でも説明されているところです(修学中の学生、病院の長期入院者、長期の単身赴任者等)。
ということは、住民票の住所と、生活の本拠が異なる場合は、生活の本拠を優先して住所を決定することが、地方自治法の予定するところとなる※、※※ため、こうしたケースでは(であることが判明・推測される場合は)、住民票の住所を離れて、個別に調査・検討を行う必要が生じます。
| ※ 参考となる事例として、和歌山地判昭63.9.28行裁例集39.9.938(住民訴訟)で、「確かに、住民基本台帳法による住民票は、住民の届出に基づいて市町村長が作成するものであり、高度の公証的機能を有するものと認めることはできるが、その記載は住民の生活の本拠を推認する重要な一資料にすぎず、その生活の本拠を確定する唯一の絶対的資料であると認めることはでき」ず、「地方自治法10条1項の住民の住所が、常に住民票記載の住所によって決定されることまでを規定したものということはできない」としています。(控訴審大阪高判平元.3.22行裁例集40.3.264同旨)。 また地方財務実務提要は、住民登録をしていなくてもその行政区域に住所を有すれば、請求権者と認めてよいかとの設問に対し、お見込みの通りであり、客観的に生活の本拠をもつ者であればよく、住民基本台帳法による住民登録は必要でないと解される、としています。 |
| ※※ この記述の通りではありませんが、個人住民税の納税義務者の考え方も、参考となるでしょう。住民税も住民監査請求も、実質的な負担・受益が誰に対してなされるべきかの観点で、対象者である住民の範囲を決定しているものであり、双方の考え方は共通のところがある、と見ることができます(参照:地方自治法10条2項)。 個人の市町村民税の納税義務者 ⇒ 『市町村内に住所を有する』個人(地方税法294条1項1号 (その定義について同条2項) 前項第1号の市町村内に住所を有する個人とは、住民基本台帳法の適用を受ける者については、当該市町村の住民基本台帳に記録されている者をいう。 (同条3項) 市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。 |
【ケース1】 住民票の住所に生活の本拠がない場合
請求人の生活の本拠たる住所が、請求先の自治体にない場合は、請求人は請求先自治体の住民とはいえないこととなります。(参考:上記和歌山地判昭63.9.28行裁例集39.9.938)。
実務上は、住民票上の住所が生活の本拠地と言えるか疑わしい場合に、生活実態を調査して判断することになるでしょう。何をもって生活の本拠地と判断するかについては、さまざまなケースが考えられ、一義的で明快な基準を導き出すのは難しいですが、いずれにしても、客観的居住の事実を基礎とし、これにその居住者の主観的居住意思を総合して決定すべきとする松本逐条(10条関係)の説明が、基礎的な判断基準となるでしょう(前記については「住民台帳事務処理要領について」(昭42.10.14通知)により、さらに同書は下記最高裁判例を参照して、客観的事実を重視すべきとする※。なお我妻栄「新訂 民法總則(民法講義Ⅰ)」岩波書店(1965年)p.94は、上記松本逐条(下線部)と同様の解釈を示しており、住所決定に関するコンヴェンショナルな解釈であることがうかがえる)。また可能であれば、首長部局の住民担当・税務担当部門の対応状況も念のため踏まえておくことが、望ましいでしょう。
・ 大阪において十数人の雇人を使用して金融業等を営む株式会社を経営し、大阪府豊中市所在の同人次男宅から右営業所に通勤し、妻も次男宅に同居しており、兵庫県津名郡a町には月2、3回数日間帰るにすぎない者は、同町において主要な人々を招いて帰郷挨拶の宴会を催したことがあり、同町で配給物資の配給を受け選挙権を持ち町民税を納めていた事実があっても、同町に住所を有するものと認めなければならないものではない(最判昭27.4.15民集6.4.414。事案は住民訴訟ではない)
・ 「選挙権の要件としての住所は、その人の生活にもっとも関係の深い一般的生活、全生活の中心をもってその者の住所と解す」る(最判昭35.3.22民集14.4.551)
| ※ 住所の決定要件として、客観的にみて生活の中心地であれば足りるのか、それに加えて生活の本拠とする意思を必要とするか、という問題がありますが、最高裁は、上記昭和27年最判など、客観的な事実重視に近い立場をとっていると理解されています(法律学小辞典p.607参照)。 またこの客観性の点に関し、贈与税法の住所についてですが最判平23.2.18集民236.71は「ここ(平15年法8改正前の相続税法1条の2)にいう住所とは,反対の解釈をすべき特段の事由はない以上,生活の本拠,すなわち,その者の生活に最も関係の深い一般的生活,全生活の中心を指すものであり,一定の場所がある者の住所であるか否かは,客観的に生活の本拠たる実体を具備しているか否かにより決すべきものと解するのが相当」としており、参考となるでしょう。 |
【ケース2】 住民票上はその自治体に住所がないが、生活の本拠としての実態はある場合
この場合は、住民票の記載にかかわらず、生活の本拠地がある自治体の住民として扱うことができます。
具体的には、転出転入届が間に合っていないなど、住民基本台帳の整理が間に合っていないことに、やむを得ない事情があるようなケースが考えられますが、意図的に住民票を移さないケースなどでも、上のやむを得ない事情がある場合と、扱いを別にする根拠がない以上、生活の本拠があれば、その自治体の住民とすることができるというべきでしょう。地方財務実務提要でも、当該行政区域内に客観的に生活の本拠を持つ者であれば、住基法による住民登録は必要ないとしています。
なおこのようなケースでは、生活の本拠としての実態があることについては、まずは請求人が証明を行うべきです。なぜならば、一定の公証力を予定される(住民基本台帳法1条)住民票上の住所がその自治体にないにもかかわらず、請求人は、自分がその自治体の住民であると主張して住民監査請求をするのですから、その主張をする請求人から、住民票の住所の内容をくつがえす証明をする責任がある、と考えるべきだからです※。
| ※ 証明の責任をまずは誰が負うべきかという、順番の問題と考えるとよいでしょう。なお、訴訟における立証責任の考え方に近いようですが、立証責任そのものではないので、訴訟のように、立証責任を負う者が必要な事実を証明できなかった場合は不利益を負う(この場合は、住民として認定されない)とすべきか、難しいところであり、ケースバイケースで対応するしかないと考えます。なお監査委員が、法令上許される範囲内で、職権により調査することを不可とする論拠はありませんが、当然ながら請求人の証明がどのようになされるのか、行政コスト等はどうかも考慮する必要があるものであり、職権調査が優先して行われるべきものではなく、行う場合は、請求人の証明を補充するものとなるのが通常と考えます。 |
イ 法人格のある団体の場合
法人格のある団体の場合、その住所は関係各法により、主たる事務所(社団・財団法人、NPO法人)・本店(会社)の所在地が住所となることが法定されているので、実務上は、法人登記簿に記載された主たる事務所・本店の住所により判断することとなります。具体的には、次の通りとなります。法定の法人種別は非常に多数ですが、ここでは主に住民監査請求の請求人となりそうなものを掲出しています。
なお上記1(2)アにある通り、主たる事務所・本店が自治体内に所在せず、支所・支社・営業所のみしかない場合は、住所を有するとは認められません(参考:前掲神戸地判平14.9.19判例地方自治243.77は、上記の理由により、会社による住民訴訟を却下)。法人住民税は、本店以外の事業所所在地でも納税義務が生じる点、住民監査請求とは扱いが異なる点は注意が必要です(負担と権能が一致しませんが、住民監査請求は法律上特に認められた制度であり、地方自治法に規定される者のみが請求できるものであると考えることになります)。
| 法人の種類 | 法人住所の根拠法条 | 登録簿 |
| 社団法人・財団法人(一般・公益) | 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律4条 | 一般社団法人登記簿・一般財団法人登記簿 |
| 特定非営利活動法人 | 特定非営利活動促進法6条 | 組合等登記簿 |
| 会社 | 会社法4条 | 商業登記簿(株式会社登記簿・・・) |
ウ 法人格のない団体の場合
法人格のない団体、いわゆる権利能力のない団体の場合も、法人格のある団体に準じ、主たる事務所の所在地が住所となります。実務的には、規約等の記載で確認することになるでしょう。
この点については、当然ながら法的な根拠はありません。しかし、法人格のある団体、法人格のない団体いずれも社会的実体としての団体に違いがなく、団体の住所の決定に差異が生じる理由はないので、法人格のある団体の住所決定の考え方に準拠すべきものです※。
| ※ 参考までですが、住民監査請求に後続する住民訴訟では、行政事件訴訟法に規定のない事項は民事訴訟法が適用されるところ、同法29条で、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、訴訟の当事者能力が認められ、同4条4項で、法人その他の社団・財団(当事者能力があるものと解されています)の普通裁判籍は、その主たる事務所により定まることとされている、つまり、法人格の有無にかかわらず、法人その他の団体の住所(個人の場合の普通裁判籍は、住所により定まる)は、主たる事務所等の所在地とされていることが、法人格のない団体の住所決定の考え方の参考となるでしょう。 ただし民事訴訟法の訴えの管轄は、被告の普通裁判籍所在地によることが原則であり(つまり、被告としての立場に立たない法人格のない団体には関係がない)、しかもそもそも、住民訴訟は当該自治体所在地の管轄裁判所の専属になるので、法人格のない団体の住所を民事訴訟法上の考え方で整理するのは、実効的な意味合いはあまりありません。社会的実態としての法人格のない団体の住所決定を考えるための、参考情報程度としてとらえて頂ければと考えます。 |
(4) 住民監査請求できる「住民」の国籍要件
自治体の住民には、外国人も含まれており(地方自治法10条)、住民監査請求の規定における「住民」の定義がこれと異なる理由はないため、外国人の住民監査請求も可能です(参照:田中・中p.115 塩野Ⅲp.236)。
外国人も地方自治法10条に定める住民に含まれ、自治体と受益と負担(住民税など)の関係に立ち、それには自治体財務が深く関係すること、また住民監査請求制度が参政権の行使、つまり自治体の政策のあり方・方向性の決定に参画する行為そのものではなく、財務会計行為等の違法・不当の是正という、より判断における客観性が高いものへ関与する行為だから、と考えることができます。
2 請求人の行為能力について
地方自治法には規定がありませんが、一般的には、住民監査請求を行う住民は、法律上の行為能力が必要とされています(行実昭23.10.30(昭38年改正前)、田中 中p.115(同 上p.110)、松本逐条。なお昭38自治法改正詳説p.331でも行為能力を要求しており、松本逐条等でもこの内容が継承されていることから、現行規定成立以来の総務省(自治省)の公式解釈とみられます)。これは、住民監査請求は法律行為であり、これを単独で完結的に行うには、行為能力を有することが当然、という考えによるものと思われます※。
よって、行為能力が制限される者(未成年者、成年被後見人等)の単独の請求※※は、不適法とすることが、通常の実務取扱いと言えるでしょう。
なお、制限能力者のうち住民監査請求を請求するのは、現実には未成年者以外には考えづらいところですが、未成年者が単独で住民監査請求できるかに関しては、上記行政実例と異なる有力な見解があり、留意しておくべきです※※※。この点は、別のページ「1.1 未成年者単独の請求についての論点」で詳述します。
| ※ 参照:実務住民訴訟p.21、奥田p.15。なお行政実例、松本逐条では、行為能力を要する理由を明らかにしていません。 |
| ※※ つまり、未成年者は法定代理人(親権者等)の同意または代理、成年被後見人は代理(同意制度がない)、被保佐人・被補助人(被補助人は訴訟行為について同意を要するもの)は、保佐人・補助人の同意を要する、ということになります。なお、上記については、これらの者(とりわけ被保佐人、被補助人の行為能力)は、訴訟行為を単独ではすることができない(民事訴訟法31条、民法5条1項、9条、13条1項4号、17条1項)ことを踏まえたもの解されます(参照:奥田p.15)。ただし、訴訟行為を単独で行う能力と関連づけて検討することの当否については、別ページにあるように、議論があり得るところです。 なお、地方財務実務提要では、被保佐人について、被保佐人の行為能力制限に関する民法13条1項の規定にない行為は単独で完全に有効になすことができ、住民監査請求については、被保佐人も行為能力を認められていると解されるので、単独で保佐人の同意なしに住民監査請求ができるとしています。ただし、そう解すると、住民監査請求は単独でなすことができるが、住民訴訟は単独でなすことはできない(民法13条1項4号)こととなり、はたしてそれが適切といえるのかは疑問なしとしないところと考えます。そもそも、被保佐人が請求人である場合、被保佐人をダミーとして住民外の者が住民監査請求を提起するなど、法定の住民監査請求の要件を潜脱する目的ではないか等について、考慮した方がよいかもしれません。 |
| ※※※ たとえば、塩野Ⅲ p.236は、住民監査請求の住民要件は、年齢を問わない、という記述になっています。また塩野Ⅰ p.405では、私人の行政過程に関わる法行為についての行為能力の要否を、必ずしも硬直的にとらえていません。田中・上p.110は私人の公法行為(一般)について行為能力を要すると取れる記述ですが、同p.111においては「少なくとも財産上に関係のある行為については、原則として、民法の無能力に関する規定が類推適用されるべきものと解すべき」とし、若干の留保があるようにもとれます。松村p.7は、住民監査請求を行う「住民」は、年齢は要件となっていないので、未成年者も含まれると解される、としています。 別ページ(1.1)で詳述していますが、民法の行為能力規定は、財産の管理の観点からの制度なので、行為能力制限者の財産保護という趣旨を必ずしも考慮する必要がないケースもある(例:運転免許申請)行政法の世界で、行為能力の規定が当然適用されるというものではないのではないか、ということが、上記の考えの前提にあります。 |
| 【Q】 行為能力には制限がないが、意思能力のない者の請求はどう取り扱うのか? |
【A】
民法3条の2により、無効な請求として取り扱うべきです。
○ 意思能力とは「法律関係を発生・変更させる意思を形成し、それを行為の形で外部に発表して結果を判断・予測できる知的能力」(法律学小辞典p.18)をいい、民法3条の2では、法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする、とされています。
○ そして「意思能力」の有無は、未成年だとかで一律で判断されるのではなく、個々の法律行為と行為者ごとに、個別・具体的状況ごとに判断されます。なお、一般には乳幼児、重度の認知症患者、意識を失った者は、意思能力を欠いた者とされています(参照:潮見佳男『民法(全)』有斐閣(2022年)p.20)。
○ 意思能力のない者の法律行為を無効とする仕組みは、民法の基本原理である私的自治の原則を実現するためのものとされ、わが国において明治以来認められてきたものです。
○ 意思能力に関する考え方を基礎に、本人の権利保護や取引安全などの観点から、個人の判断能力が十分でない者の権能を類型化したものが、行為能力制度です。この行為能力制度を行政法の領域でどこまで直截に適用するのかは、上記の通り議論のあるところですが、すくなくとも、自治体の事務執行を評価して、積極的に関与しようという住民監査請求制度を利用するに当たり、請求人が意思能力を欠く、というのは、住民監査請求制度の趣旨・目的から見て、適切でないことは明らかというべきでしょう※。なお、田中・上p.110は、私人の公法行為について(一般に)意思能力を要するとしています。
○ なお、請求の後に意思能力を喪失する(たとえば請求後に突然重篤な脳疾患に罹患する等)場合は、それによって請求要件を欠くことにはならないと考えます。なぜならば、請求人は、請求後に何らかの行為を求められ、それに対応することが、住民監査請求の手続を進めるうえで必須である、という仕組みがとられておらず、適法な請求があれば、監査委員としては、監査を行い、その結果を通知公表等するしかないからです(たとえば、地方自治法242条7項の陳述等へ請求人が対応しなくとも、監査を進めることはできます)。
| ※ 同旨:碓井p.41は「当該自治体の区域内に住所を有する者が意思能力を欠く場合に、その者を請求人・原告として、法定代理人の代理により住民訴訟を提起することは、住民の意思を尊重した財務統制という制度の趣旨から逸脱するように思われる」としています。ただし碓井同は、異なる見解の存在も紹介しています。 |
3 請求人が住民でなくなった場合
住民監査請求を行った請求人が、転居して住民でなくなった場合や、死亡した場合は、請求の要件を欠くことになります(松本逐条)ので、不適法な請求となります。
つまり、住民監査請求を行った請求人は、請求時点で住民であることは当然として、請求の後も、住民監査請求の終了(完結)まで(実務的には、監査結果の通知・公表まで、となるでしょう)、継続して住民であるという客観的事実が継続していることが必要です※、※※、※※※。
以上について、判例においては、住民訴訟の原告が死亡したときは、訴訟は当然に終了する(請求人としての立場は相続されない)としており(最判昭55.2.22集民129.209)、住民監査請求でも、死亡のみならず転出も含め、同様に考えられています(参照:地方財務実務提要)。
実務においては、例えば単独の請求人が決定通知前に死亡したことが判明したときは、「本件請求は、○年○月○日に請求人が死亡したことにより終了した」と決定することが適当でしょう。
| ※ 地方財務実務提要は、山口地判昭44.12.25行裁例集20.12.1762における、住民訴訟は訴訟係属中常に当事者適格たる住民たる資格が存続する必要があり、これを失った場合は、訴えは当事者適格を失った不適法なものとして却下を免れない、とする判示事項を参考に、住民監査請求でも、請求人たる住民の転出により、請求が終了したものとして打ち切る扱いをなし得るとしています。 |
| ※※ 例外的な事例として、住民訴訟提起後、転出したが、口頭弁論終結までに当該自治体に転入して住民の資格を回復した事案について、原告適格を認めたものがあります(秋田地判昭60.4.26行裁例集36.4.613)。ただし、この事例は、転出が行政区画の変更のため生じたもので、請求人の意思による転出ではないこと、住民でなくなった期間が短期間(3月半)であること、住民税が継続して当該自治体から課されたこと、現住所が一時的・便宜的ではなく、将来も生活の本拠とすることが見込まれる、といった事情を考慮したものであり、本判決について判例行政法p.129(石津廣司)は、極めて特殊な事情のある事例であって、一般論として、いったん住民資格を失っても、事実審口頭弁論終結時までに住民たる資格を回復しさえすれば、原告適格を認められるとしたものではない、としています。このようなケースもあり得る、という認識で理解していればよいでしょう。 |
| ※※※ 住民監査請求を行うことの本質が、自治体財務運営の適正化を自治体自らが果たすよう働きかけるものとして、特定の財務会計行為等につき監査委員に監査の端緒を与えることを、その機能の本質ととらえる場合(「0.1住民監査請求の制度設計の考え方」2(6)参照)、請求人は請求後に監査の追行について、制度上は特段の行為を要求されていないことも考えあわせれば、請求時点でのみ住民としての要件があれば足りるようにも思われます。この点について、住民訴訟において、原告適格(適法な原告たる資格。住民要件など)は訴訟係属中必要とされていることとの類似性、また、訴訟とは異なるとはいえ、請求後(陳述はともかく)、請求人が監査委員の行動からまったく遮断されるわけではなく、請求人が監査委員に対して何らかの行動を行う機会は絶無となるものではないことや、住民監査請求が住民訴訟制度を後置する仕組みであることも考えあわせれば、監査委員が請求に対する結論を出すまで、住民として監査の追行に責任ある立場を保持し続けるべきである、と考えられるのではないでしょうか。 |
| 【Q】 監査結果がまとまった後で、結果の通知公表までに請求人が死亡・転出していたことが判明した場合は? |
【A】
住民監査請求自体は、不適法な請求とすべきです。
○ 適法な住民監査請求が存在しない状態となっているので、本来監査委員には、地方自治法242条5項に定める対応(監査の実施、結果の通知公表等)を行う義務は発生しないことになります。請求人に対する応答も、後続があり得る住民訴訟の提起資格がないことを明確にするため、請求人は請求後に住民でなくなったので、本件住民監査請求は不適法である旨のみとすべきです。地方財務実務提要でも、請求人の請求後の死亡・転出については、死亡・転出により、その請求が終了したものとして打ち切る(却下する)扱いとし得るとしています。
○ ただし、既に監査が行われた場合、住民監査請求による監査でも地方自治法199条に基づく監査でも、監査結果は公表されるべきことが同法で規定されており、たまたま住民監査請求の要件が欠けたという理由のみで監査結果を公表しないことは、住民に何らかの隠蔽を疑われかねず、ときには自治体の信頼毀損につながります。とりわけ、勧告事項がある場合や、勧告までは至らなくとも、監査委員意見を示すなどの問題が探知された場合などは、そうでしょう。
○ よってこのような場合、内部行為である関係機関への通知・勧告はもとより、監査結果は公表すべきと考えます。請求自体は不適法であり、請求人は監査結果の通知を受ける資格を有しないものではありますが、一方で監査は、その時点において適法であることを前提として、地方自治法242条に基づき行われたものであり、そのような完結した事実関係が存在する以上、公表及び勧告についても同条に基づいて行われるべきものです。この場合、適法な住民監査請求を経ることが、請求人が住民訴訟を提起する条件となる制度なので、そういった事実関係を明らかにすることも必要です。実務上は、通常の住民監査請求の公表形式によることとし、あわせて、請求人○は、○年○月○日(死亡、転出)により、当市…の住民ではなくなったが、この事実(が判明する)前に、本件請求に基づく監査を行っていたので、念のため監査の結果を公表する、との付記をすることが適当でしょう。
○ 監査の事後、同一の財務会計行為等について、別に適法な住民監査請求があった場合、既に行った監査の結果に基づいて、請求に係る事実がないと認めるときは、その旨請求人に通知すれば足りるとされていることから(行実昭34.3.19)、そのような場合は、この監査結果を援用して判断すればよいでしょう。
4 請求人の代理・非住民の代理
住民監査請求においては、請求人が任意の代理人を立てることはできると考えられています(参考:奥田p.12、松村p.7、実務住民訴訟p.22)。
なお請求人が住民であり、請求権の行使がその住民の意思に基づくことが明らかであれば、住民以外の者を任意代理人として行う住民監査請求を適法とする裁判例※があり、参考となるでしょう。
| ※ 「(地方自治)法上、代理人による住民監査請求を行うことができないとする定めは設けられていない。そして、住民監査請求が代理人の意思表示によって行われたものであったとしても、その請求権の行使が当該地方公共団体の住民である本人の意思に基づくものであることが手続上明確に確認できるのであれば、事柄の性質上、特段支障が生じるとは解されない」(熊本地判平16.8.5判例地方自治276.94。なお本件は、代理人が住民でない事案)。 |
なおこの場合、住民監査請求がその自治体の住民である請求人本人の意思が存在し、それに基づくものであることが、手続上明確に確認できることが必要ですので、実務的には、請求時に、請求人が代理人にその住民監査請求の提起と手続の追行に関する権限を委任したことを証明する委任状※※が提出されなければ、代理人の請求等の行為は認めるべきではないでしょう(参照:民事訴訟規則23条1項では、訴訟代理権の権限は文書で証明しなければならないとされている)。
提出がないときは、請求人に補正を求めるべきですが、提出がない場合でも、請求人本人の意思が明確なら、代理を認めるかどうかはさておき、請求自体を不適法とする論拠は乏しいものと考えます。
| ※※ 代理権を証明する書類に記載すべき事項としては、日本弁護士連合会の訴訟委任状のひな形などが参考となるでしょう。最低でも委任状の日付(住民監査請求の請求書の日付と矛盾がないこと)、請求人・代理人の住所氏名、いつ、どの監査委員に提出したどのような内容の住民監査請求か(代理される請求事案を特定するため)、代理権の内容(普通は、本住民監査請求を追行するための一切の行為を代理する権限が考えられます)は必要です。 |

スイス・ローヌ川右岸を川岸、鉄道路線沿いから2,000メートル上がったところにあるエッギスホルン(Eggishorn)。ウィンパーのアルプス登攀記にも出てきた(ハズ)。眼下はスイス・アルプス最大の氷河アレッチ氷河。はるか向こうにメンヒ(氷河源頭鞍部の右)とアイガー(そのさらに右の黒い山)が見えます。ということは、氷河の源頭鞍部は、かの有名な観光地ユングフラウ・ヨッホ。ここは、アレッチ氷河の屈曲点にあたり、流れ下る氷河を正面から見上げるため、氷河そのものや向こうの山の眺めが頗る良く(ユングフラウ・ヨッホは氷河を見下ろすため、氷河自体は良く見えない)、その割には(交通の便が悪いこともあり)ユングフラウ・ヨッホほど人はいないので、なかなかの穴場感満載のところです。ちなみに反対方向には遠くですがマッターホルンも見えます。残念なことに撮影したフィルムはボロボロに色調が劣化しており(同じような現像所に出し同じように保存している30年以上前のものでも褪色がほとんどないフィルムもあるんですが、このメーカーのフィルムはどれもこれもズダボロの褪色具合・・・)アドビイラストレーターで補正しまくっても素人仕事では限度あり、何だか冴えない色調の写真というのが。