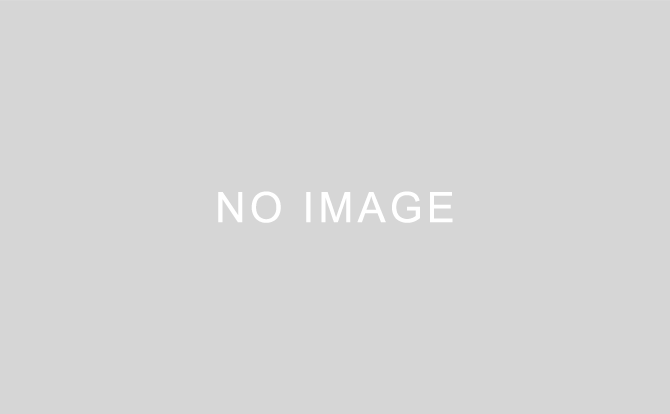本ページの一番下に、本ページのPDF版リンクを設けています。
最終改訂 2025.9.6 改訂内容は改訂履歴のページ参照
地方自治法には、何も書いていません。
一般には、不適法な請求に対して、監査委員は監査を行う義務はないとされており、監査委員は、それに応じた決定をして、請求人に応答することとされています。
1 地方自治法の定め
地方自治法242条5項には「第1項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知するとともに、これを公表し、当該請求に理由があると認めるときは、当該普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関又は職員に対し期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を請求人に通知し、かつ、これを公表しなければならない」とあります。
つまり、適法な住民監査請求が提起されたときは、監査委員には次の義務が発生することになります。
① 監査を行うこと
② 監査結果を請求人に通知・公表すること
③ 監査の結果、請求に理由があると認めるときは、関係機関に必要な措置を講ずべきことを勧告(この内容についても請求人に通知し公表)
一方で、不適法な請求であった場合、上記の義務は発生しないということになります(「監査を行ってはならない」といった反面義務が発生するわけではなく、「監査を行わなければならない」といった積極行為義務が発生しないだけです)※、※※。
なお、不適法な請求への対応については、地方自治法には何の定めもありません(行政不服審査法45条1項のような規定がありません)。
| ※ 実際には、監査を行った結果、請求要件不適格な請求であったことが判明する事態も当然にあり得ます。このような場合は、監査結果として、本件住民監査請求は、地方自治法242条1項(2項)の要件に照らして不適法である、と宣言するほかないでしょう。なお、本案の部分についての監査報告がある場合は、地方自治法242条ではなく199条に基づく報告を、住民監査請求に対する応答とは別に行うこととなります。 |
| ※※ 地方自治法242条7項の規定による、請求人に対する証拠提出・陳述機会の付与義務については、その請求が不適法であるときは、この機会を付与する義務はないと解されます。これは、同項が「監査を行うに当たって」この機会付与を義務付けていることから明らかです(参考:横浜地判平3.6.19判例タイムズ772.147)。 |
【まとめ】
| 請求が適法 | 請求が不適法 |
| 監査を行い※、その結果を請求人に通知・公表することが必要 請求に理由がある場合 ○議会、首長その他の執行機関、職員に対し、期間を示して必要な措置を講ずべきことを勧告 ○上記を請求人に通知・公表 請求に理由がない場合 ○請求に理由がないことを、理由を付して請求人に通知・公表 |
監査を行う義務は生じない |
| 請求人は、住民訴訟を提起する資格が生じる(適法な住民監査請求を経ている)※※ | 請求人は、住民訴訟を提起する資格が生じない(適法な住民監査請求を経ていない)※※ |
| ※ ただし、適法な請求であっても監査がなされない場合があります。これは、既にある財務会計行為等を対象とする住民監査請求がなされて監査が行われたのち、別の請求人から、同一の財務会計行為等を対象とする請求がなされた場合です(参照:行実昭34.3.19)。なお、事情変更や見落としていた事項の指摘などもあり得るので、同一の財務会計行為等を対象とする請求はすべて再監査の必要はないとすべきではなく、請求内容その他諸事情を考慮して、改めて監査をする必要があるかどうかを判断することが求められます。 そして、このケースで再監査を行わずに先の監査結果を示して、これに基づき請求に対する応答(請求に理由があり、既に勧告等をした、または請求に理由がない)をしても、後発の請求人に対しては、適法な監査請求があり、それに対する監査結果が示された、という効果が生ずることになります。 なお、再監査の実施をしなくてもよいというのは、同一事情で同一の業務を行う必然性がない、という行政経済的な理由によるものと考えられます。また、地方自治法242条に基づく監査と199条に基づく財務監査は同質的なものです。よって昭和34年行実では先行監査が住民監査請求によるものを想定していますが、これに限らず、地方自治法199条に基づく財務監査において同一の財務会計行為等を対象とする監査を既に行っていた場合でも同様に、監査の再実施を省略する措置が執り得るものと考えます。 ところで上記と類似するパターンとして、一の住民監査請求に対する監査終結前に同一の対象事項について他の住民から住民監査請求があったときは、これを併合して、つまり各請求について一括して監査を行い、監査結果についてそれぞれの請求人に対して応答するということもあり得るであろうと考えます。住民訴訟では、すでに当該対象事項について訴訟係属がある場合に他の住民が重ねて提訴することは地方自治法242条の2第4項により認められませんが、住民監査請求では、柔軟な対応は可とされるべきです。 |
| ※※ なおこの説明は、監査委員が請求不適法の判断を示した住民監査請求事案について住民訴訟が提起された場合、裁判所は自動的に訴訟要件なしとして却下する、ということを意味するのではありません。 住民訴訟が提起された場合、裁判所は、自ら住民監査請求の請求要件を審査し、実際には請求要件を満たしていたと判断すれば、監査委員の判断に関わりなく本案審理(請求人たる原告の主張する請求に実体的に踏み込んだ審理)を行うこととなり、却下判決はされないことになります。逆もまた真であり、適法な請求と監査委員が判断し、監査を実施した事案であっても、裁判所が請求要件を満たさない不適法な請求であると判断すれば、住民訴訟では却下判決がなされることになります。 つまり、住民監査請求が適法な請求であったか不適法だったかは、住民訴訟における訴訟要件(請求の内容に踏み込んだ実体審理(本案審理)をするか、それをせずに却下するかを決める要件)ではありますが、それは監査委員の判断にかかわらず、裁判所が独自に判断する内容である、ということです(参考:横浜地判昭56.4.27行裁例集32.4.698)。 |
2 請求書の受付時の取扱いと不適法請求時の措置
ここでは、実務的なプロセスに大まかに沿った記述としていますが、これらは念のための記述であり、実際の事務の進め方等については、「前書き」ページ紹介の実務参考書等をご覧頂ければと思います。
(1) 請求書の提出・受付
請求書が監査委員事務局(職員)に提出されたときは、これを受け付け(文書収受)します※、※※。
事務局職員(事務職員)には、一見して不適法な場合でも、請求書の受け取りを拒み、または請求を不適法なものと判断決定する権限はなく、そのような決定権限を監査委員が職員に委任することもできません※※※。
| ※ 事務職員には、請求書の受理・不受理の審査権限はなく、補正等の指導に請求人が任意で応じることがない限り、事務職員は必ず受付をしなければならないと、一般的には解されています。参考として「およそ、請求人が監査委員事務局に提出した住民監査請求書類に一見明白な瑕疵があったとき、当該事務局職員はその請求人に対し、補正、追完あるいは任意の撤回を促すなどの行政指導をすることができるが、その場合、その請求人が任意でこれに応じるという態度を示さない限り、当該事務職員としては、右住民監査請求書を必ず受付(当該請求書を文書取扱規程に基づき収受する行為をいい、当該請求書が後日監査委員の合議によって受理決定されると、右受付日が受理決定の日となる)なければならないものであって、前記監査請求書を適法なものとして受理するかどうかは専ら監査委員会の合議によって決定される事項というべきである」(神戸地判昭62.10.2判例タイムズ671.193。なお行政手続法の施行前である。) |
| ※※ 要件審査に関することではありませんが、住民監査請求において、多数の請求人が連名で請求を行うことがあります。請求に対する請求人への監査委員からのアクションはいくつかありますが(陳述機会付与、監査結果通知)、とりわけ下記の補正対応の場合は問題となります。なぜなら各請求人に補正対応を求め、これに対する各請求人の応答が不統一であったり、相互矛盾していた場合、監査の進行が遅滞するだけでなく、監査委員(事務局・職員)に無駄な労力が発生するからです。 たとえば代理人が選定されていれば、代理人を通じて対応すればよいのですが、そうでない場合は、地方自治法には規定はありませんが、行政不服審査法の総代選定要求(同法11条2項)の例により、総代を選出するよう求めることもあり得るでしょう。 なお民事訴訟法30条の選定当事者はやや類似する制度ですが、選定当事者の選定を監査委員が要求し得る性格のものではないこと、また住民側からしても選定当事者を選定する必然性がないうえ、選定当事者以外の者が住民訴訟の原告となり得る資格を得られるか不明確であるため(参照:民事訴訟法30条2項)、住民監査請求において監査委員がこの制度について考慮する必要はないでしょう。 |
| ※※※ 地方財務実務提要では、一見して正規の要件を欠くと認められる請求書が提出された場合の形式要件の審査についても、監査委員の職務権限に属するので、監査委員の補助職員が監査委員の判断を待たずに受付を拒否することはできないし、委任もできない、としています。つまり、このような場合であっても、決定は職員の専決事項ではなく、監査委員直接の判断によるべきこととなります。 |
(2) 補正要求
請求書を受け付けた後は、速やかに、請求の内容が地方自治法に定める要件を満たしているか、事務局(事務職員)において、審査のための事務を行います。
この際、直ちに請求要件を満たさないことが判明することがあり得ます(例えば添付を要する事実証明書がない、請求書に地方自治法施行規則13条所定の事項が記載されていない、請求書記載の対象となる財務会計行為発生日から請求日まで1年以上経過しており、遅延の正当理由が示されていない等)。
また直ちに判明しなくとも、その後の調査検討の結果、要件を満たさない(請求人が住民でない、当該自治体の財務会計行為ではない等)、またはその疑いがある(請求内容が判然としない、請求の対象が財務会計行為といえるか判然としない、対象となる財務会計行為等の特定に疑義がある等)ものが出てくることがあり得ます。
【請求の要件】 ⇒ 「0.2 住民監査請求の要件は?」 参照
★実質的要件★
① 請求人がその自治体の住民であること
② 請求の対象が財務会計行為等であること
③ その自治体の執行機関・職員が上記②の行為をするか、怠っていること
④ 請求において求める措置の内容が地方自治法242条1項所定のものであること
⑤ 請求が、対象となる行為があった日又は終わった日から、原則として1年を経過していないこと(経過している場合は、そのことについての正当理由を請求人が申し立てることが必要)
★形式的要件★
⑥ 必要な事項の記載がある監査請求書の提出
⑦ 事実証明書の提出
⑧ 資格証明書の提出(地方自治法所定事項ではなく必須ではないが、場合によって必要となり得る。例えば住民票写しや代理権を証する書類等)
なお、これら項目について、どの程度までその内容を完備することが、住民監査請求の請求要件を満たすことになるのかについては、本サイトの各論部分で説明します。
いずれにしても、請求内容が地方自治法の請求要件を満たさないと判断されたが、補正により請求要件を満たすことになり得る場合(例:事実証明書がない、請求書の記載事項不足、請求内容が判然としない等)は、地方自治法の根拠はありませんが※、適切な期間を定めて※※、請求人に補正を要求すべきです※※※、※※※※。
なお、補正しても請求が適法となる余地がない場合(例:請求人が住民でない、当該自治体の財務会計行為でない等)は、補正を求めることなく、監査委員が不適法な請求と決定することは止むを得ないことです(参照:行政不服審査法24条2項、行政手続法7条)。
| ※ この点について参考となる事例として、住民監査請求が不適法な場合に、行政手続法、行政不服審査法や国税通則法は所管庁に補正要求を行うよう義務付けているが、地方自治法には、こうした義務をなんら規定せず、これを前提とする規定も存在しないことから、地方自治法は、監査委員に対して、補正を命じたり促す義務を課していないと解する、もっとも、住民監査請求を行うについて期間制限があり、同一の事項について再度の住民監査請求はできないと解されていることなどからすれば、いったん提起された住民監査請求は、できるだけこれを適法なものとして処理しうるように取り計らうのが望ましいと解されるから、監査委員は、当該住民監査請求が不適法であり、補正が可能と認めた場合には、その裁量により、当該住民監査請求の請求人に対し補正を促す権限を有していると解するのが相当、とする裁判例があります(富山地判平8.10.30判例地方自治161.81。判決は却下)。 また本件の控訴審(名古屋高(金沢支)判平9.9.3判例タイムズ972.172)においては、地方自治法の規定からは、不適法な住民監査請求に対しては、監査委員は補正を命じ、または促す義務を課していないと解するとする一方で、行手法、行審法、通則法の上記規定、また住民監査請求の制度が自治体財政の腐敗防止を図り、住民全体の利益を確保する見地から、住民の請求により当該自治体の執行機関、職員の財務会計上の違法な行為等の予防、是正等を自治的、内部的処理によって図ることを目的とした制度であること、住民監査請求を行うについては期間制限があり、同一の事項について再度の住民監査請求はできないと解されていること等からすると、容易に補正できる形式上の不備があるような場合には、監査委員においてその補正を求める権限があることはもとより、補正を促す義務があること、すなわち補正を促さずに直ちに監査請求を却下することは許されないと解する余地がある、としています(本件の判決は控訴棄却(訴え却下)、上告せず確定)【注】。 なお参考までに、大藤p.376(田中信義)は、監査請求手続における補正について、法令上の義務とは言い難く、その義務の根拠を求めるとすれば、行政手続上の条理に求めることになろうか、といいます。【注】 本名古屋高裁金沢支部判決の論旨のうち、再度の監査請求はできないという点については、本判決の後、最高裁が、次のような判断を示しているので、注意が必要です。 ○ 監査委員が適法な住民監査請求を不適法として却下した場合、当該請求をした住民は、同一の財務会計行為等を対象として、再度の監査請求をすることが許される(最判平10.12.18民集52.9.2039)。なお、これは適法な請求が不適法な請求と監査委員に判断された場合の問題であり、住民監査請求が適法なものとして監査が行われた場合は、同一人による同一内容の再度の監査が認められないことは、本判決が示す通りです(最判昭62.2.20民集41.1.122)。 |
| ※※ 適切な期間については、住民監査請求の場合、請求から60日以内の期間制限があるので(地方自治法242条6項)、これも踏まえた期間設定となるでしょう。上記平成8年富山地判において、監査委員は、補正を求める必要がある場合は、調査、判断、通知に必要な時間を勘案して相当な期間を定めて補正を促すことができると解すると判示した例があり、参考になるでしょう。 なお、住民監査請求に関する補正の法規定がなく、上記の60日の監査期間から補正期間を除外する法規定もないのですが、実務上は、補正期間は60日の期間から除くのが通例です(地方財務実務提要では、要件を具備しない請求書の提出に対し補正指導し、請求人がこれに応じて補正した場合、地方自治法242条6項の請求があった日は、正規の監査請求書が再提出され、監査委員において監査することが可能となった日、すなわち再提出された日としています(補正前の監査請求書は未だ受理されておらず、監査も当然なし得ない)。また参照:行政不服審査法5条2項1号など)。これはすなわち、補正に要した期間は60日の期間には含めないということを意味します。 また同項でいう監査を行うとは、この期間内に監査を終了(して結論を出す)を意味し、監査の着手の意味ではないことになります(参照:松本逐条)。 |
| ※※※ ただし、地方財務実務提要によれば、市町村合併により監査委員が一時不在になる場合に、新監査委員就任までの間、60日期間が中断するかとの設問について、監査請求があった日から60日以内に監査・勧告が行われない場合は、地方自治法242条の2第2項3号により住民訴訟の提起ができ、監査・勧告を60日以内に行わなかった理由について制限を設けていないことから、上記の事情があったとしても、請求のあった日から60日経過後に住民訴訟を提起することができるとしています(本趣旨については、参照:東京高判平14.4.10判例地方自治246.8。なお本件は住民訴訟ではなく、上記のような事案に対する国賠訴訟である。)。地方自治法242条の2第2項および3項の明文規定を見る限り、そのように解さざるを得ないものと考えます。これらを敷衍すれば、補正においても、同様の結論とならざるを得ません。 なお補正その他の事情がある場合の監査結果提示期限については、請求人と監査委員の相互理解を形成した上での監査の執行・進行がなされることが望ましいものです。 |
| ※※※※ 補正の要求は、一種の救済措置であり、その性格上、監査委員でなければ決定し得ないものではないと考えられ、実務上もそのように取り扱われているようです。 なお当然ですが、監査委員が請求人に補正を命ずる法律上の権限は定められていないので、ここでの補正要求は、行政指導に類するものとなるでしょう。つまり監査委員が補正を求めることはともかく、命ずることはできず、請求人は補正要求に応ずる法律上の義務はないことになります。無論、補正に応じないと、住民監査請求が不適法な請求として退けられるリスクを、請求人が負うことには違いありません。 |
(3) 整理
事務局(事務職員)で要件審査の検討を行った上で、請求が不適法であることについて、監査委員の判断が可能な程度に整理ができれば、下記のように、当該住民監査請求が不適法であることについて、監査委員の合議による決定を求めることになります。
なお、制度上要件審査の終期は定められていない(というより、要件審査に関する規定がなく、終期を推定できる規定もない。民事訴訟の口頭弁論終結や中間判決に類する仕組みもない)ので、論理的にはこの要件審査は、住民監査請求に対する結果を決定し通知公表するまでは、継続して行い得るものです(監査に着手した後に要件審査判断をすることは、行政経済的に不効率ですが、法的な適否は別問題となります)。
3 請求が不適法であることの決定等の実務手続
(1) 不適法な請求であることの確認決定
以上のプロセスにより請求を審査した結果、これが不適法と判断される場合は、請求が不適法であることを確認し、請求人へ通知すること等について、監査委員の合議※で決定します。一般には、これを「却下」決定としています※※、※※※。
この決定を行う際の監査委員の合議については、地方自治法では何の定めもありません。しかし、監査を行った場合は、結果決定には監査委員の合議が必要で(地方自治法242条11項)、請求が不適法であるとの意思決定も、監査結果の決定と、監査委員としての責任および決定の重要性は変わらないことを考慮すれば、同様に監査委員の合議によることが適当です※※※※。
| ※ 監査の結果については、地方自治法242条11項で合議事項とされ、この合議とは、全監査委員が協議し、最終的には意見が一致することを意味し、合議が整わない場合は、監査委員としての監査及び勧告等の決定はなし得ないとされています(松本逐条。なお昭38自治法改正詳説p.339は、監査を行わなかったのに同じ状態になるとみるべきとする)。上記の通り、請求を不適法として決定する場合の手続は何ら法定されていませんが、これを合議事項とする場合、やはり、合議が整わない場合は、請求を不適法として決定することができず、請求に基づく監査を行うべきものとなります(参考:奥田p.105)【注】。【注】 請求要件が充足していることが監査実施の前提であるには違いありませんが、グレーの場合、請求要件が充足していることが確定して初めて監査がなし得る(請求要件充足は停止条件的に働く)のではなく、請求要件が充足していないことが確定(この場合は、不適法請求であることの確認決定について、監査委員の合議が成立すること)しない限り、監査委員は監査を行う義務がある(請求要件充足は解除条件的に働く)というべきだから、であると考えます。またそもそも請求要件に関する認定において監査委員の判断が分かれる、ということは、要件認定やその前提となる事実関係に即断できない要素がある、ということにほかならないことにもよります。参考までに、松本逐条では、監査を行わないことは例外的事例であり、通常の場合は監査を行うべきとしています。 |
| ※※ 参照:奥田p.88、松村p.50、実務住民訴訟p.62 |
| ※※※ 本Web全体を通して、住民監査請求の請求要件を満たさない場合に、その旨の決定を表示し、手続を終結する応答については、特に必要がない限り「却下」の用語を使用せず、請求要件不適法等の表記としています。これは、却下の用語が地方自治法242条に法定されていないことによりますが、実務一般で広く使用される現状があり、また訴訟法や行審法の用例との親和性を考えれば、必ずしもこれを否定する論拠はなく、あくまで法定されていない用語の使用を回避しているに過ぎません。なお、地方自治法242条5項の請求に理由がない旨の決定については、本Webサイトでは、特に必要がない限り「請求に理由がない」という用例としています。実務では「棄却」の用例も見られますが、この点は管見ながら、筆者としては、これが法定用語でない以前に、住民監査請求の制度構造上、棄却の用語を使用することは必ずしも望ましい用例ではないと考えており、ためにそのような表記を採用しています(住民監査請求は、請求人の要求する具体的な措置内容に対して認容・棄却の応答をする制度ではないという理解に重点を置いているためです。ただし、請求人の具体的請求が財務会計行為等の違法不当性そのものと理解すれば、その判断請求に対して請求認容、請求棄却という考え方が出てくることは否定しませんが、それは請求人の意図の本質的な内容とはいえないでしょう)。 |
| ※※※※ 参照:上記2(1)※掲出昭和62年神戸地判、奥田p.104 |
(2) 請求人等への通知
(1)の通り、請求人から自治体の機関に対して、法律に定める請求行為があったのですから、監査委員の決定後、請求人へ、この請求は地方自治法第242条の請求要件を満たさないので、監査は行わない旨の通知を、請求不適法の理由を付して、行うべきです※、※※。
また、請求があったことを、首長などに通知していた場合は、当然に、同様の通知をすべきでしょう。なお、令和2年から新たに地方自治法242条3項 「第1項の規定による請求があつたときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならない」 という規定が設けられているので、注意しましょう。
| ※ ここで、「監査を行わない旨」とした趣旨は、地方自治法242条ではこのような不適法請求への応答についての規定がないところ、請求人は監査委員に対し、監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求しているのであり、そうなると、不適法な請求への応答としては、適法な請求に対して監査実施が義務となるところ、不適法請求の場合は監査実施をする義務がないのだから、監査実施を拒否する、とすることが適当、という考えによります。 なお、適法な請求であっても監査を行わない場合もあり得ますので(過去あった住民監査請求と同内容の申立てが別の請求人からあり、改めて監査を行う必要がないと認めた場合が、このパターンに当たると考えられます。参照:行実昭34.3.19)、不適法な請求への応答については、単に「監査を行わない」だけでなく、請求要件を満たさない(不適法)請求あることを明示して通知すべきであると考えます。ちなみに昭和34年行実は、すでに行った監査結果があり、事情の変更等がなく、改めての監査を行う必要がないと認められる場合に、行政経済的観点から、すでに行った監査結果を流用するという趣旨であり、その場合形式的には、適法な監査は行われている(また、後続の住民訴訟提訴要件としての適法な監査請求を経ている)ことにはなります。 |
| ※※ 不適法な請求の場合の応答義務について、直接に言及したものではありませんが、最判平10.12.18民集52.9.2039の内容を見れば、不適法な請求の場合の通知の重要性が、御理解いただけるのではないでしょうか。本判決は、住民監査請求を却下決定した場合の再監査請求の可否、住民訴訟の提起期間が論点であり、そのうち後者の論点に関し「監査委員が適法な住民監査請求を不適法であると認めてその旨を書面により請求人に通知した場合には、当該請求に対する監査委員の監査は行われていないものの、当該請求に対する監査委員の判断結果が確定的に示されている点において、監査委員が請求に理由がないと認めてその旨を書面により請求人に通知した場合と異なるところがない。そうすると、当該請求をした住民は、却下の通知を受けた時点において、当該請求に係る行為又は怠る事実について住民訴訟を提起することが法的に可能な状態になったものとして、同項1号にいう監査委員の監査の結果に不服がある場合に準じて、却下の通知を受けた日から30日以内に住民訴訟を提起しなければならないと解するのが、住民訴訟の出訴期間を規定した同項の趣旨に沿うものというべき」と判示しています。 |
(3) 公表
上の1にもありますように、適法な住民監査請求があったときは、監査結果の公表義務が監査委員に生じますが、不適法な請求の場合は、地方自治法には何の定めもありません。つまり、公表しなければいけない法律上の義務は定められていないことになります。筆者の知る限りでは、不適法な請求の公表については、団体によって対応はまちまちのようです。
ところで、住民監査請求は住民誰でも行えるものであり、同件について別の住民が請求を行うかもしれません。また住民監査請求は住民訴訟が後続する仕組みであり、住民訴訟が提起された場合、同件の改めての監査請求を経て訴訟参加しようとする住民が出現することは、制度上予定されているということになります。そしてこうした事情は、不適法請求の場合も変わるところはありません。こうしたことも考慮すると、不適法な請求に係る監査委員の応答の事実についても、できる限り広く公開されるべき、と考えることが適当と考えます。
さらに考えれば、住民監査請求制度は、自治体財務活動の自浄作用を促すことを目的にしており、監査委員は、自治体財務活動の適正な運用に対する責任の一部を負う機関であって、住民などからの請求がなくとも、自らの判断で監査を行うことも可能な権限を与えられています。とすれば、適法な請求ではなかったとはいえ、自治体の財務活動に疑問が呈された、という事実は、広く住民に公表されることが望ましく、それが自治体の説明責任、また住民監査請求制度の趣旨に沿う、とも言えそうです。
以上のように、すくなくとも、地方自治法242条を単純に反対解釈して公表の義務なしと簡単に考えるべきではないと考えます※,※※。
| ※ 地方財務実務提要では、住民監査請求を却下する場合、公表義務はないかとの設問に対し「住民監査請求を受理した場合は、その結果の如何を問わず、自治法第242条第5項の公表を行う必要があ」る、としています。そして財務提要の別の設問で、公表の意義として住民訴訟における他の住民の訴訟参加を考慮したものであるとしています。請求要件不適法された事案であっても住民訴訟の可能性はありますので(請求要件が重要な争点となった訴訟事案は多い)、要件不適法の事案でも公表すべき意義はあると考えるべきでしょう。 なお、財務提要には、住民監査請求を不受理とすべき例として、明らかに違法である場合(事実証明書を提出していない、住民でない者の請求等)をあげる記述があり、受理云々はそのような前提で記述されているようです。昭和38年現行法制定時の自治省の考え(参照:昭38自治法改正詳説p.336)が似たようなところ、それを踏まえた記述と考えられますが、そもそも昭和38年には行政手続法が制定されていなかったことにも留意すべきでしょう。 |
| ※※ ただし、請求書の必要な記載事項が不備、必要な書面が揃っていない、といったケースまで公表するのかというと、上記※の住民訴訟時の意義を考慮しても、疑問も出るかもしれません。 このような事例については、住民監査請求の制度趣旨から考えても、公表すべき実質的な必要性(必然性)は見い出し難いとも考えられ、そもそも不適法として監査を行わない事例の結果を公表しないこと自体、これが違法となるとは考えられないため、こうしたケースでは公表をしない、とするのも、あり得る対応ではないでしょうか。 |
4 不適法決定への不服申立て
提起された住民監査請求について、監査委員が請求要件不充足(不適法判断)と判断した場合(に限らず請求に理由なしと判断した場合も含まれる)、国家賠償訴訟が提起される可能性がありますが、裁判例は結論として、いずれも賠償責任の容認に否定的です※。
また、監査委員の判断に抗告訴訟を提起することにも裁判例は否定的です※※。国賠訴訟はともかく、監査委員の決定を否認するのなら、住民訴訟を提起すれば良いのですから、当然の結論です。
| ※ 請求人の地位が不法行為法上の保護の対象とならないとする例として、横浜地判平3.6.19判例タイムズ772.147、名古屋高判平8.7.30判例時報1582.39、東京地判平9.4.21判例タイムズ971.129。国家賠償法上の賠償責任発生の枠組みは認めるものして神戸地判昭62.10.21判例タイムズ671.193、同控訴審大阪高判昭63.8.23判例時報1306.44、大阪地判平成9.1.23判例地方自治163.25、福井地判平14.7.10判例時報1808.59。 |
| ※※ 東京地判昭52.4.26行裁例集28.4.347 |

背後の山を見ればここが何処かは直ぐに(笑)。某朝ドラ女優さんが、地元民が行く温泉ということでテレビで紹介していたここ、地元自治体三セクが運営している露天風呂と砂蒸し風呂ですが、それを見てこの辺り旅行の折、行ってみる気になりました。砂蒸し風呂は極楽であり、露天風呂は男女が日替わりで風呂を入れ替え、行った日は男湯はこっち方向の眺望が利かないほうの風呂ではありましたが、そうはいっても快晴の大海原の景色はそれはそれで大層なものでした。