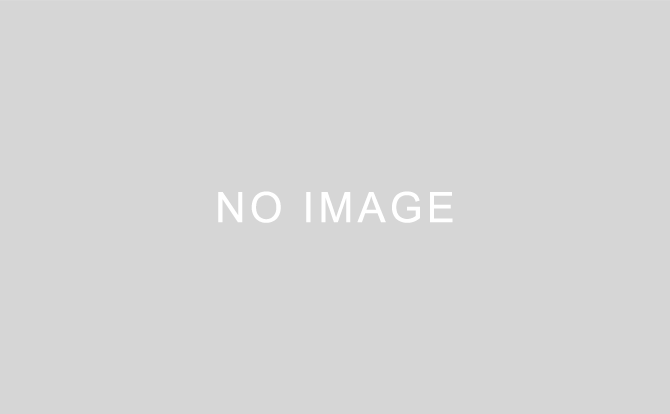本ページの一番下に、本ページのPDF版リンクを設けています。
最終改訂 2025.2.13(改訂箇所は改訂履歴ページ参照)
住民監査請求制度においては、請求は、申立人や請求内容について、下記の要件をすべて満たす必要があります。
この要件を満たす請求については、監査が行われ、所要の結果が示されますが、下記の要件の要件を一つでも満たさない請求については、その請求は不適法なものとなります。ただし、要件を満たす程度については、疎密、つまり、厳しく充足の程度を問う要件もあれば、そうでない要件もあります。
住民監査請求における監査の本質は、請求人が監査請求した対象の財務会計行為等の違法不当性について判断して、その判断に基づき監査委員が必要と認める措置を決定することにあります。
そして、監査請求に応じて監査委員に監査義務が生じるための条件が定められている以上、その条件に該当するのか(請求人が住民か、請求人が対象とする行為等が法定の類型に該当するものとして存在するのか、請求は法定期間内か等)は、請求に基づき監査をしなければならないか、という監査実施の前提としての事実関係の判断となるものです。
【実質的要件】
請求人の請求資格、請求内容などに関する要件です。
なお一般に、住民監査請求の要件審査においては、請求人が、①、②、③の下線部、⑤の要件を満たすことを明らかにしているかどうか、または満たしているかは、特に重視されています。要件審査の要諦といえます。
ちなみに、これら①、②、③下線部および⑤の要件は、
【ア】 請求人が、その自治体の住民であること(住民要件) ← ①
【イ】 請求対象が、財務会計行為性を有すること(財務会計行為性要件) ← ②③
【ウ】 請求が、監査請求期間内になされたこと(請求期間制限要件) ← ⑤
にまとめることができ(これら3要件から、下記の各①~⑤の要件が演繹されている、とみることもできる)、またこれらア、イ、ウの要件は、相互に独立したものとなっています。
① 請求人がその自治体の住民であること 詳細はこちら
住民監査請求ができるのは、その自治体の住民に限られています。
② 請求の対象が財務会計行為等であること 詳細はこちら
住民監査請求の対象となるのは、財務会計行為等※に限られています。具体的には、
・公金の支出
・財産の取得、管理又は処分
・契約の締結又は履行
・債務その他の義務の負担
※以上4つの行為については、まだ行われていなくとも、これら行為がなされることが、相当の確実さで予測される場合も請求は可能です。
・公金の賦課又は徴収を怠る事実
・財産の管理を怠る事実
| ※ 「等」は、本Webサイトでは「怠る事実」を指します。 |
なお、請求人が監査委員に監査を求める対象となる財務会計行為等は、原則として、監査委員が請求書等から、他の行為等と区別して特定して認識できるよう、個別・具体的に示すことが必要です。
③ その自治体の執行機関・職員が上記②の行為をするか、怠っていること 詳細はこちら
請求の対象となるのは、上記②の財務会計行為等につき、その自治体の執行機関や職員が行ったもの(怠っている事実)に限られています。言い換えれば、その自治体の権限ある職員が自治体の業務として行った、その自治体の財務会計行為等が、住民監査請求の対象となり、当然ながらそうでない、たとえばその自治体の財務会計行為でないものや、私的な行為等は、対象となりません。
④ 請求において求める措置の内容が次のものであること 詳細はこちら
請求は、次の内容のものを求めるものとされています。
・上記②の行為の防止・是正に必要な措置
・上記②の怠る事実を改める措置
・上記②の行為・怠る事実により、その被った損害を補塡するために必要な措置
⑤ 請求が、対象となる行為があった日又は終わった日から、原則として1年を経過していないこと 詳細はこちら(監査請求期間) (正当な理由)
請求は、正当な理由がない限り、請求の対象となる行為のあった日・終わった日から1年を経過していないことが、請求の条件とされています。
【形式的要件】 詳細はこちら
どのような書類が揃っているか、といった要件です。
⑥ 監査請求書
地方自治法施行令172条で、請求は「その要旨を記載した文書」で行うこと、請求書の様式は、総務省令で定める様式(具体的には地方自治法施行規則13条で定める様式)によることとされています。
なおこの様式では、地方自治法242条1項により請求する旨のほか、
・請求の要旨
・請求者の住所氏名(氏名は原則自署。なお地方自治法242条1項では「請求人」の用語を使っているが、本様式では「請求者」となっている。)
・請求日
・宛先の監査委員
が項目としてあげられています。
⑦ 事実証明書
地方自治法242条1項では、請求は、請求対象の財務会計行為等を「証する書面」を添えてすることとされています。
⑧ 資格証明書※
地方自治法には特に規定はありません。そのため、資格証明書がないことをもって請求要件を充足しないと直ちに判断することはできません。しかし請求人の資格(住民であること等)は、一義的には自ら証明すべきであり、住民であることを証明するもの(住民票写し、登記簿謄本、団体規約名簿類)、請求の代理権があることを証明するものなどを求めることが考えられます(住民票など官公庁が発行する書類は、監査委員が発行官庁に依頼して公用取得することも考えられます)。結局、こうしたものが提出されないと、監査委員としては、請求人の請求資格がないと判断せざるを得なくなることも考えられ、その意味で事実上、請求要件たる書面に準じるものとして扱われる可能性があるということになります。
| ※ 参考:奥田p.9 |
| 【Q1】 予算など、財務会計行為(支出等)が行われることを前提とする議会の議決は、住民監査請求の対象とならないのか? |
【A1】
なりません。
○ 住民監査請求の対象となるのは、上の②に掲げられた財務会計行為等に限られており(地方自治法242条1項に掲げる事項(「違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある・・・と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」)は、限定列挙とされています。地方財務実務提要など参照)、議会の議決は、この列挙事項中に含まれませんので、住民監査請求の対象となりません※。
| ※ 参照:最判昭37.3.7民集16.3.445 「地方自治法243条の2(注:昭和38年改正前)による住民の監査請求及び訴訟は、地方公共団体の公金または財産に関する長その他の職員の行為を対象とするものであって、議会の議決の是正を目的とするものでない…」。また参照:田中 中p.116 |
○ そもそも条例の制定や予算の議決によって直ちに公金の支出などが行われるのではないことは、皆さんよく御承知と思います。予算の存在などを前提として、執行機関が執行行為として現実の支出(などの財務会計行為)を行うことで、現金その他公金の支出や財産の処分等の事実が生じるのですから、あくまでも条例・予算などの議会の議決は、それに基づく執行機関の執行行為が行われた段階で、はじめて財務会計行為という形になり、その財務会計行為が住民監査請求の対象として問題となるのです(怠る事実は、財務会計行為を裏面、つまり「行為をした」ではなく、「行為がされていない」ことをとらえているのですから、やはり執行行為としてとらえるべきものとなります)。
なお松本逐条では「議会の行為(条例の制定、予算その他の議決等)が違法又は不当な場合であっても、それだけで本条(地方自治法242条)の監査請求を行うことはできず、当該条例又は議決に基づき執行機関の具体的な行為が行われる段階になってはじめて請求の対象となる」としています※※。
| ※※ 昭38自治法改正詳説p.331でも同旨の説明があり、現行規定整理時における総務省(自治省)の制度設計自体がそのようなものであったということができます。 |
○ 予算の執行や財産の管理処分などの財務会計行為等は、自治体行政事務の執行行為そのものであり、首長など執行機関の権限に属しています(地方自治法149条2号、6号など。教育財産の管理権限は、地教行法21条2号で教育委員会の権限)。また地方自治法は、自治体について議会と執行機関の二元制を採用し、議決機関である議会と執行機関である首長や行政委員会等の権限を分立・区分させています。つまり、住民監査請求の対象は、執行機関の行う執行行為である財務会計行為等であり、こうした執行行為を行うことを予定しない議会の、議決機関としての行為(議決、条例制定等)は、仕組みとして住民監査請求の対象となり得ないのです。○ ただし、これは議会の議決が、地方自治法242条1項に定める住民監査請求の対象となり得る財務会計行為等に該当しないということではありますが、同条5項で明らかなように、監査の結果、監査委員は議会に勧告することができます。松本逐条においては「監査請求自体は執行機関又は職員の具体的な行為について行うことを要するが、請求があった場合においては、監査委員は、さかのぼって当該行為のもととなった議会の議決、条例等の内容についても監査をすることができ、議会に対しても必要な措置(例えば、違法な条例の改廃等)を講ずべきことを勧告することができるわけである」と説明しています。
| 【Q2】 損害の発生は、住民監査請求の要件となるのか? |
【A2】
なります。
○ この要件は、地方自治法242条の規定には明示されていませんが、下記の判例・行政実例を踏まえれば、監査委員事務局の実務としては、自治体に損害を与えない(最高裁の判決文に沿って記述すれば、公金の支出、義務の負担ないしは財産上の損失を伴わない単なる収入のみ発生する)財務会計行為は、住民監査請求の請求要件を満たさない不適法な請求として処理することが適当、となります※1、※2、※3。○ ところで上記の通り、地方自治法242条に定める請求の対象は「違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある…と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実」であり、住民監査請求の対象となる財務会計行為等は、自治体に損害が発生したことを要件に含むと明文上直ちに読み取ることはできません。また同項によれば、住民監査請求では「当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体の被った損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求」するのですが、損害の補てんを求めるケースで損害の発生が必須なのは当然としても、それ以外のケースで損害の発生が必要なのかどうかまでは、良く分りません。そうなると、この要件が成立するのかどうかは、地方自治法242条1項の解釈論、つまり、住民監査請求制度は、請求の対象が自治体に損害をもたらすことを要求していると解釈できるのかという、制度解釈的視点からの検討が本来必要であり、現実に学説の上では、住民監査請求・住民訴訟の役割として、自治体の財産上の損害回復(防止)機能を重視するものと、自治体財務の適法性確保機能を重視するものとが対立しています※4。○ しかしながら上記の判例等は、判断の理論的根拠(制度論的解釈)を詳らかにしているものではなく、およそ住民監査請求の対象は、自治体に財産上の損失を伴うことを要することを当然の前提としているように見えます(無論、そのような割り切り判断がおかしな訳ではありません)。またそもそも、ここで示される判断基準自体、突き詰めれば、かなりアバウトなものともいえます※5。○ 以上のように、理念的・概念的には考え出せばキリのないところはありますが、実務上は、損害の発生を要件とする、つまり財務会計行為等のうち損害が発生するものを住民監査請求の対象とするのが運用原則となっています。裁判例においても、損害の発生が一般的な要件として考慮されており、収入のみ発生する案件において「実質的な損害発生」がある場合は、住民監査請求の対象と認めるもの※6もあります。したがって、財務会計行為等のうち「実質的に何らかの損失が発生する」ものを請求の対象として認め、それに当てはまらない財務会計行為等を対象とする請求は、不適法なものとして扱うことが適当と考えます(現実的には、監査の対象行為が財産の取得管理処分、契約の締結の場合において、問題になり得ます)。○ なお、上記判例、行政実例を踏まえ、住民監査請求としては不適法と判断したとしても、請求された事案の内容からして、何らかの監査を行うことが必要と監査委員が判断すれば、別の機会に地方自治法199条5項による随時の監査を行うことはあり得るでしょう。ただし、適法な住民監査請求を経ることは、住民訴訟の提訴要件ですから、監査委員が請求要件上不適法と判断した住民監査請求については、何らかの監査を要すると考えるケースであっても、住民監査請求としてなされた請求に対しては、不適法として退ける応答をすべきです※7。
| 【判例】 住民から町への金員贈与契約に対する住民訴訟について、「(旧地方自治法)243条の2第4項に基づく住民訴訟は、法律の定める限度で許される訴訟であって、旧法243条の2第1項掲記の行為に徴すると、公金の支出、義務の負担ないしは財産上の損失を伴わない単なる収入を発生させるにとどまる行為は、かりにそれが違法な場合であっても、同条4項所定の住民訴訟の対象とすることはできないものと解するのが、相当である。本件訴訟の対象は、普通地方公共団体である被上告人を受贈者とする贈与契約であって、単に被上告人に収入を発生させるにとどまるものであるから、右契約が、かりに上告人主張のような理由で違法であるとしても、住民訴訟の対象とすることができないものといわなければならない。したがって、右贈与契約が住民訴訟の対象事項にあたらないとした原審の判断は、結論において正当である」(最判昭48.11.27集民110.545)。 (参考:上記判例で参照する昭和38年改正前の旧地方自治法243条の2条文(昭和23年改正)) 第243条の2 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長、出納長若しくは収入役又はその他普通地方公共団体の職員について、公金の違法若しくは不当な支出若しくは浪費、財産の違法若しくは不当な処分、特定の目的のために準備した公金の目的外の支出、違法な債務その他の義務の負担、財産若しくは営造物の違法な使用又は違法若しくは権限を超える契約の締結若しくは履行があると認めるときは、その事実を証する書面を添え、監査委員に対し、監査を行い、当該行為の制限又は禁止に関する措置を講ずべきことを請求することができる。(2、3項略) ④ 前二項の規定による監査委員若しくは普通地方公共団体の長の措置に不服があるとき、又はこれらの者が措置を講じないときは、第一項の規定による請求人は、最高裁判所の定めるところにより、裁判所に対し、当該職員の違法又は権限を超える当該行為の制限若しくは禁止又は取消若しくは無効若しくはこれに伴う当該普通地方公共団体の損害の補てんに関する裁判を求めることができる |
| 【行政実例】 (問)県立商業学校に対する土地、物品、金銭等の寄附が地方財政法4条の5及び27条の3違反であるとして住民監査請求があった場合、これを受理すべきか? (答)設問の場合においては、当該行為により県が損害をこうむるおそれがないので、地方自治法242条の趣旨にかんがみ、同条に規定する住民監査請求の対象となる行為に該当しないものと解する。(昭45.4.21)。 (参考:松本要説p.582は、上記昭和48年最判を引用し、住民訴訟は、住民監査請求の対象とされた違法な行為または怠る事実について請求できるが、自治体に損害もたらすような行為であることを要する、とする。) |
| ※1 なお参考までに、射程が財産管理行為にほぼ限定されると思われるものの、「損害発生」と異なる用語での要件設定をする下級審裁判例「財産…の財産的価値が何らかの影響を受ける場合にのみ当該作為または不作為が財産の管理を怠る事実として住民訴訟の対象になりうる」があります(東京地判昭54.12.20行裁例集30.12.2047)。ここでの「財産的価値が何らかの影響」がマイナスの影響に局限しているのかは、判然とするところではありません。 事案は市道両側にフェンスがあり、原告所有地との境界にフェンスがあるため原告の市道利用が妨げられているところ、フェンスを除去しないのは財産の管理を怠る、とするものであり、裁判所は、フェンスの存否によって市の財産の財産的価値に変動が生ずるとは到底考えられず、本件は住民訴訟の対象とならないと判示。 |
| ※2 本昭和48年最判では、上記の要件を住民訴訟の要件としており、住民監査請求の要件とは記述していません。松本逐条も、おそらくはこの判文に忠実に依拠する意図により、242条(住民監査請求)ではなく242条の2(住民訴訟)の項でこの判決について説明しています(「住民訴訟の対象は住民監査請求と同じ…であるが、「財産の管理」について、財産的損失をもたらさない行為は対象とならない(最高裁昭48.11.27参照)」)。 ところで判決文を見る限り、住民訴訟の対象とならない理由を「(旧)地方自治法243条の2第1項掲記の行為に徴すると」しており、これを見る限り、上記最高裁判決の論理は、公金の支出、義務の負担ないしは財産上の損失を伴わない単なる収入を発生させるにとどまる行為の財務会計行為該当性を問うているのであり、そうなれば、住民監査請求の請求要件として解するべきものです。 |
| ※3 上記昭和48年最判について、最高裁Webサイト(最高裁判例集)の当判例の説明には、判決の要旨として「普通地方公共団体を受贈者とする贈与契約は、地方自治法(昭和38年法律第99号による改正前のもの)243条の2第4項所定の住民訴訟の対象とならない」としています。一方、判例行政法p.7(石津廣司)は、上記昭和48年最高裁判決以降の裁判例は、本最高裁判決の判断を前提として、問題とされた行為が自治体に損害を与える可能性があるか否かを検討して住民訴訟の対象となるかを判断するようになっている、としています。例として、 ・広島高判昭43.8.12判例時報555.35(上記昭和48年最高裁判決の原審判決) 旧地方自治法243条の2に規定する違法若しくは権限を越える契約締結は、この契約締結によって、自治体の公金や財産等に対し損害をもたらすような行為であることを要するものと解するのが相当(本件贈与契約に仮に違法無効事由があるとしても、贈与契約締結が自治体の公金や財産等に損害をもたらす関係にはなく、住民訴訟の対象事項に該当しないとして、訴えを却下した一審判決を是認) ・浦和地判昭60.9.30行裁例集36.9.1638 地方自治法242条の2に定める住民訴訟の訴訟要件として、問題とされる財務会計行為が自治体に対する損害を与えるものであることが必要(本件により自治体は財産的損害を被るものではないので、訴訟要件を欠くとして、訴えを却下)。なお本判決は、他にも本件訴えが訴訟要件を欠く点があると判断している。 ・福岡地判平5.8.5 住民監査請求の対象となる行為等は、自治体に積極消極の損害を与えひいては住民全体の利益に反するものでなければならないというべき(本件行為は、自治体に損害をもたらすような関係にないことは明らかで、住民監査請求の対象となる行為等には該当しないとして、訴えを却下し、控訴審・上告審も本結論を維持)。 【注】平成5年福岡地裁判決は、控訴審でも是認され上告審でも上告棄却となっています(最判平6.9.8判例集未登載。なお上記浦和地判は一審確定)が、この上告審判決は、旧民訴法時代のいわゆる三行判決(定型文判決)です。そして事案は、市が人格なき社団法人になした法人市民税の申告納付を求める通知の取消しを求めるものですが、この通知に処分性を認めがたい以上、そもそも本件訴えは普通に考えれば、地方自治法242条の2第1項各号非該当という法規定のない「損害発生」要件を持ち出すより法律的にさらに直截な理由付けで却下相当の事案であるといえ、よって上記のロジックが最高裁の是認を経ているとすべきではないと考えます。 |
| ※4 参照:碓井p.82。ここでは、住民訴訟(=住民監査請求)の目的(保護法益)を、自治体の財産的損害の回復ないし防止にあるとするものと、財務会計行政の適法性確保にある(財産上の損害を訴訟(監査請求)要件とすべきでない)とする説が紹介されています。 なお同書は、特定納税者に過大な課税がされたことまで住民訴訟で取り上げる必要は認めないが(そもそもこのような事例は当の納税者による抗告訴訟によればよい)、住民訴訟の1~3号訴訟類型では、現に損害が生じている場合のほか、将来損害が発生する可能性について個別具体に判断するのが適当とする説をとり、その例示として、一般会計から公営企業会計への繰出(一般会計からすれば支出であるが、公営企業会計には同額の収入が計上されるので、自治体の財産総体としてはプラスマイナスゼロであり、よって自治体の損害は具体化されていない)についての名古屋高判平12.7.13判例タイムズ1088.146で「違法な会計間の繰入行為はそれ自体税金の減少を来し、住民全体の利益を害するものとして、地方公共団体の執行機関又は職員に対し、その予防又は是正を求める住民訴訟を提起できる権限が住民には与えられている」とする例を引いています。 また井上p.107は、旧4号訴訟ですが、住民訴訟には損害賠償・不当利得返還のような本質的に損害の存在を前提とするもののほか法律関係不存在確認や原状回復請求のように損害ないし損失の存在を前提としないものがあることを踏まえ、住民訴訟の制度の趣旨・目的・規定の構造・文言などに照らすと、住民訴訟のすべてが自治体に損害が生じていることを制度的な前提としているものはなく、これを要件としていないものもある、と判示する東京高判平13.2.7を参照して、1ないし3号訴訟では抽象的な損害又は損失の発生可能性で足りるとしています。 一方、最新地方自治法講座p.105(関哲夫)は、財務的処理を直接の目的としてはいるが、当該自治体に対して損害を与える可能性のない行為は住民訴訟の対象行為から除くことが、最判昭38.3.12民集17.2.318の判示する住民訴訟の制度目的に照らして妥当というべき、としています。 |
| ※5 上記昭和48年最判の判断は、次の①②のいずれなのか、文理上判然としないところがあります。 ① あくまで「単なる収入を発生させるにとどまる行為」を住民監査請求の対象行為から排除しているのか (「公金の支出、義務の負担ないしは財産上の損失を伴わない」は「単なる収入を発生させるにとどまる行為」を請求対象行為から排除する理由付けとして、行為の性格を記述する連体修飾語的なものとする) ② 「財産の損失を伴わない」行為を住民監査請求の対象から排除する本質的な要件とし、その例示として本件訴訟の対象となった「単なる収入を発生させるにとどまる行為」をあげたのか (公金支出、義務負担は、旧地方自治法243条の2に明記されているので、法定事項に当たらないものを排除することは当然ですが、「財産の損失」は旧地方自治法243条の2(現242条)の法定事項ではなく、そうなると、同条所定の行為であっても、さらに「財産の損失を伴う」ことを請求対象の本質的な要件とする、と解釈することができる) 最高裁Web判例集の判決要旨は、おそらくは判決文の忠実な要約を意識して、上記※3のように「贈与契約は住民訴訟の対象外」としていますが、下記※6記載の裁判例に対する最高裁の反応を見る限り、最高裁は、その判断において、実質的な「財産上の損害」の存否を重視しているように受け取れます。 |
| ※6 下級審裁判例において、県が基金に属する現金の運用について、一部を引き合い預託(複数の金融機関の見積合わせにより最高の見積金利を示した金融機関に預託)としたものの、大半を、引き合い預託の金利より低い利率で指定金融機関に相対預託(特定金融機関との合意により金利を決定し預託)運用したことにより、県に損害を与え指定金融機関に利得を得させたとして、知事以下の職員及び指定金融機関に対し損害賠償・不当利得返還を求める住民訴訟(旧4号)を提起した事案につき、一審は引き合い預託、相対預託とも定期預金で元本保証があり預託行為の直接かつ固有の効果として県に財産的損害を与える客観的可能性がないことを理由に、訴えを却下した(徳島地判平11.9.3判例地方自治200.45)ところ、控訴審(高松高判平12.3.6判例地方自治200.40)では、基金に属する現金を、より確実かつ効率的若しくは有利な方法で管理・運用・保管できるのに、合理的な根拠なく不確実・非効率的若しくは不利な方法で管理等の方法をとったときは、違法な財務会計行為とされる余地があることは否定できない、そして元本保証があるとはいえ、正当な管理等により得られたであろう運用上の利益を喪失する損害を被る可能性があることは否定できず、元本保証のみをもって、本預託行為がその直接かつ固有の効果として県に財産的損害を与える客観的可能性を有しないということはできない、したがって、このことを理由に本預託行為が住民訴訟の対象とならないということはできない(上記昭和48年最判は単に自治体に収入を発生させるにとどまるから住民訴訟の対象ではないとするもので、本事案と事案が異なる)と判断して、一審判決を取り消し、差し戻した事例(要は、契約締結における、競争入札によるべきものを随意契約で契約した、の収入バージョンと考えれば分かりやすい)があります。なお、本高裁判決は上告・上告受理申立てをされていますが、最高裁はいわゆる三行決定でこれを退けており、高裁判決(地裁の却下判決を取り消して差戻し)の結論が確定しています。本件の財務会計行為(現金預託行為)が住民監査請求の対象に該当するか判断するに当たり、他の考慮要件が考えづらいことからして、最高裁は本件において、「単に収入のみを発生」の案件であっても「形式的にはともかく、実質的には財産の損失を伴う可能性がある」という要素を考慮して、本件は昭和48年判決とは事案性格を異とすると判断したものと考えられます。 |
| ※7 例えば、地方財政法で違法とされる寄附等(4条の5、27条の2から27条の4までに該当するもの。上記昭和45年行政実例は、こうした寄附に対するもの)、また誤って、もしくは相手に損害を与える目的で、過剰な額の寄附を相手方から受け入れる等の事例が考えられるでしょう。ただし例えば、過剰寄附部分の償還はもとより、これにたいする遅延利息等があわせて生じるケースの場合、自治体の本来あるべき財産の状態(正当な寄附を得た状態)より、利息等の分だけ減少するのですから、そのような事例では、損害発生要件で悩む必要はないでしょう。 |
| 【Q3】 自分の法律上の利益のために住民監査請求を利用することは適法か? |
【A3】 適法と考えられます。
○ 下級審裁判例に「住民訴訟は普通地方公共団体の住民がその職員の違法な行為の是正等を期する制度の一であって…本件においては、(住民)が、本件…処分の違法を主張しているものである以上…、それが同時に(当該住民)の個人的利益を目的としていても、本訴を不適法として排斥することはできない」(広島高判昭43.7.17行裁例集19.7.1217)とするものがあり、参考になると思われます※。
| ※ 一応、机上の考察となりますが、行政処分の取消しを求めるケース(地方自治法242条の2第1項2号に定める行政処分の取消請求に該当するもの)では、行政処分に係る取消訴訟の排他的管轄【注】という考え方が認められており、また出訴期間制限の違い(取消訴訟の出訴期間は原則6か月(行訴法14条1項)であり、住民監査請求の提起期間である1年より短く、住民訴訟は適法な住民監査請求を経ておれば提訴可能)があることを考えれば、取消訴訟を提起できる者(処分の対象者など)が住民監査請求を利用することは、論理的には、制度潜脱行為であり、認めるべきではないというべきでしょう。ただし実際には、住民監査請求で問題となるような行政処分によって発生する法的効果は、請求人と自治体側ではトレードオフでしょうから(住民監査請求の対象となるような行政処分であれば、請求人に利益、自治体側に不利益が生ずるであろうから、請求人は取消訴訟を提起しようにも、訴えの利益がない)、そのような事例が生ずることが想定はできないのではないでしょうか。 【注】 訴訟手続で行政処分の効力を否定できるのは、行政事件訴訟法による取消訴訟のみである、という仕組み・考え方。法が「取消訴訟」という制度を用意し、一定の枠組みを形成している以上、行政処分の効力を訴訟で争うには、取消訴訟によるべきであり、例えば取消訴訟を経ずに一般民事訴訟で、行政処分の違法無効を前提として何らかの権利関係を争うことは認められない、とされています。なお一般的には、取消訴訟の排他的管轄は行政行為に「公定力」を認める論拠とされています(参照 塩野Ⅰp.160以下)。 |
| 【Q4】 除斥により、監査を行うことが可能な監査委員が不在となった場合は? |
【A4】 住民監査請求を受け付けることができません。なお請求人は、住民訴訟を直ちに提起できます。
○ 監査委員には地方自治法199条の2で、事案について除斥事由が定められており、住民監査請求においても当然適用されるべき条項なので、同条で定める事由に該当する監査委員は除斥されます。
○ これにより、提起された住民監査請求に対して監査ができる監査委員が不在となった場合は、そもそも監査ができません。住民監査請求が、住民訴訟の前置手続として、監査委員に監査の機会を与えて、自治体の自治的、内部的処理で違法不当な財務会計行為等の予防是正を図ることを目的とする(最判昭62.2.20民集41.1.122)ことからすれば、監査委員不在によってこのような事態となることはやむを得ない事です。
○ なお請求自体に不適法要因がなければ、不適法な請求とはなりませんが、監査委員の応答としては「監査委員全員が地方自治法199条の2により除斥されるため、本件請求に関する監査を行うことができない」とするほかありません。
○ またこの場合は、請求人は直ちに住民訴訟を提起できると解されています(参考:大阪地判平18.7.7判例タイムズ1247.186)。
○ なお参考までに、監査委員不在(除斥欠缺)の場合に、首長が住民監査請求権保障のため適切な措置をとるべき義務の確認を求める住民訴訟を不適法とした事例があります(東京地判昭55.6.4行裁例集31.7.1528。監査委員事務局の超勤手当を対象とするため、監査委員が全員除斥となったものであり、あわせて監査委員が棄却決定した住民監査請求についての監査結果の無効確認を求めたもの)
本稿のPDF版

奈良元興寺。正面の屋根瓦のまだらのところは、飛鳥・元興寺の屋根瓦を移築したものだそうです。飛鳥にはいまも蘇我馬子発願の丈六仏がおわし、その飛鳥元興寺の本尊だったとされていますが、そこはまた大化改新・乙巳の変のおり中大兄皇子、中臣鎌足などがここに立て籠り甘樫丘の蘇我蝦夷と対峙した場所ともされ、であれば、この瓦を蘇我馬子蝦夷入鹿推古天皇聖徳太子天智天皇藤原鎌足天武天皇持統天皇など飛鳥オールスターチームも目にしたのでしょうか。