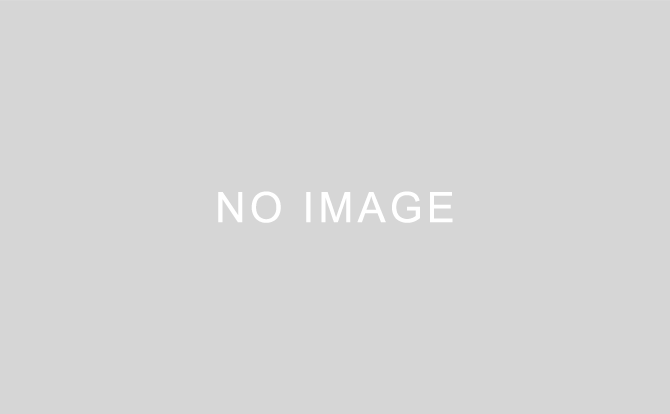本ページの一番下に、本ページのPDF版リンクを設けています。
最終改訂 2025.2.13(改訂箇所は改訂履歴ページ参照)
| このページは、住民監査請求の要件審査に関する理解を深める一助にと考え、住民監査請求の制度設計の考え方、つまり制度のおおもとの仕組み・考えかたについての私見を記述したものです。
本サイト記述の通奏低音のようなものですが、要件審査そのものの記述や要件の具体論ではなく、必須の内容でもありませんので、必要なければ、飛ばしていただいても構いません。 |
以下の概念は、住民監査請求の性格のすべてを網羅しているわけではありません。しかし、住民監査請求の制度設計に、このような考えが置かれていることを念頭におけば、各論の理解がより容易になるのではないかと考えます。
また最高裁判所の判例や総務省(自治省)の行政実例等は、概ねこれらの考え方を基礎に置いているものと推察しています。
なお、本サイトの各論部分も、以下の考え方を根底において、内容を整理しています。
① 住民監査請求は、一定の個別具体の特定された財務会計行為等に、違法・不当がないかについて監査を求めるもので、自治体の政策のあり方を直接問う仕組みではない
② ①の仕組みを前提に、最高裁判所の判例などは、住民監査請求の要件を厳格にとらえる方向性がある
③ 住民監査請求は住民である請求人の請求により行われるが、それを除けば、監査委員の行うべきこと、行い得ることは、通常の財務監査と大きく変わるところはない
④ 監査委員は、請求人である住民の指摘する財務会計行為等を監査する必要はあるが、その判断は、請求人の請求内容に必ずしも縛られる必要はなく、自治体の財務運営の適正化を図るために必要と考える措置等を、監査委員自らの判断で示すことができる
1 住民監査請求制度とは
住民監査請求制度とは、平たく言えば、「住民が、住所地自治体の財務運営の適正を図ることを通じて住民全体の利益を確保するために、監査委員に、特定の違法・不当な財務会計行為等に関して監査を行い、これに基づき、関係機関等が必要な対応を取ることを求める」請求制度、となります。
①主体 ⇒ 住民です。
②客体(相手方) ⇒ 住民の属する自治体の監査委員です。
③何を求める? ⇒ その自治体の、特定の違法・不当な経費の支出など(財務会計行為等)に関して、監査を行い、その結果に基づき必要な対応を取ることを求める(地方自治法では「必要な措置を講ずべきことを請求する」)ことができます。
④何のために? ⇒ 住民全体の利益のためにです(請求人の個人の利益のためではありません)。
参考までに、自治体の実務担当者が主に参照すると想定される資料等で、どのような制度としての位置付けがされているか、確認してみましょう(住民訴訟に関するものを含みますが、住民監査請求に妥当するものです)。
| 住民監査請求…の制度は、直接には、地方公共団体の職員のなした不当、違法な…財務会計上の行為をただして、地方公共団体の財務行政の適切な運営を図るもの(塩野Ⅲ p.236) |
| 住民監査請求…は、直接民主主義の制度の一環ではないけれども、地方の財務行政に対する住民の参加を求めて、財務行政の適正化を図ろうとするもの(塩野同 p.238) |
| この制度は、地方公共団体の執行機関又は職員による違法又は不当な行為又は不行為(怠る事実)により、納税者たる住民が、直接間接、何らかの損失を被むることを防止するために、住民全体の利益を確保する見地に立ち、執行機関又は職員の違法又は不当な行為の予防及び是正を図ることを目的とする(田中 中p.115) |
| 地方公共団体の職員による違法又は不当な行為等により地方公共団体の住民として損失を被ることを防止するために、住民全体の利益を確保する見地から、職員の違法、不当な行為等の予防、是正を図ることを本来の目的とするもの(松本逐条 242条) |
| 普通地方公共団体の執行機関又は職員による(地方自治)法242条1項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実が究極的には当該地方公共団体の構成員である住民全体の利益を害するものであるところから、これを防止するため、地方自治の本旨に基づく住民参政の一環として、住民に対しその予防又は是正を裁判所に請求する権能を与え、もって地方財務行政の適正な運営を確保することを目的としたものであって、執行機関又は職員の右財務会計上の行為又は怠る事実の適否ないしその是正の要否について地方公共団体の判断と住民の判断とが相反し対立する場合に、住民が自らの手により違法の防止又は是正を図ることができる点に制度の本来の意義がある。すなわち、住民の有する右訴権は、地方公共団体の構成員である住民全体の利益を保障するために法律によって特別に認められた参政権の一種であり、その訴訟の原告は、自己の個人的利益のためや地方公共団体そのものの利益のためにではなく、専ら原告を含む住民全体の利益のために、いわば公益の代表者として地方財務行政の適正化を主張するものであるということができる。住民訴訟の判決の効力が当事者のみにとどまらず全住民に及ぶと解されるのも、このためである。(最判昭53.3.30 民集32.2.485) |
| 住民監査請求の制度は、普通地方公共団体の財政の腐敗防止を図り、住民全体の利益を確保する見地から、当該普通地方公共団体の長その他の財務会計職員の違法若しくは不当な財務会計上の行為又は怠る事実について、その監査と予防、是正等の措置とを監査委員に請求する権能を住民に与えたもの…。 また、住民監査請求の制度は、住民訴訟の前置手続として、まず当該普通地方公共団体の監査委員に住民の請求に係る行為又は怠る事実について監査の機会を与え、当該行為又は当該怠る事実の違法、不当を当該普通地方公共団体の自治的、内部的処理によって予防、是正させることを目的とするものであると解せられる(最判昭62.2.20民集41.1.122) |
2 住民監査請求制度の特質
1で述べた項目の多くは、各論で詳述することになりますが、各論について理解を深める前提となる、制度の枠組みについての特質について、考えてみましょう。
(1) 地方自治法で創設された特別の制度であり、同法所定の枠内で運用されるものである
住民訴訟(昭和38年自治法改正により現行規定となる前の住民訴訟制度に関するもの)に関する最高裁の判例として、次のようなものがあります。
| 旧地方自治法243条の2のような訴訟の制度を設けるか否かは立法政策の問題であり、これを設けないことが、地方自治の本旨に反するとはいえない 最判昭34.7.20民集13.8.1103
○ 論旨は、原判決が地方自治法243条の2(注:現行規定に改正される前の住民監査請求・住民訴訟の根拠条項)の遡及適用がないとしたのは、憲法92条、94条、98条に違反すると主張する。しかし憲法92条は、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める、と規定しているだけで、「地方自治の本旨」が何であるかを具体的に明示してはいない。そして地方自治法243条の2のような訴訟の制度を設けるか否かは立法政策の問題であって、これを設けないからとて、地方自治の本旨に反するとはいえない。従ってかかる制度を設けていなかった、昭和23年7月の改正以前の地方自治法を憲法92条に違反するものということはできないし、また右の改正によって始めてかかる制度を設けた規定の遡及適用を否定した原判決を同法条に違反するものということもできない。原判決が憲法94条、98条に違反しないことはいうまでもない。 |
これは要するに、住民訴訟(+住民監査請求)は、地方自治法によってはじめて創設された仕組みであって、住民訴訟(住民監査請求)制度を成り立たせるべき前提が、地方自治法の規定以前(例:憲法)に存在し、その手続等を地方自治法242条や242条の2の規定で具体化したものではなく、同条を国会が立法することで、はじめて住民が利用することができることとなった制度である、ということになります。
また訴訟制度の仕組みから見ると、「民衆訴訟」である住民訴訟は、裁判所の本来的な権限の対象である「一切の法律上の争訟」ではなく、これを裁判所が扱い得るのは、法律によって特に設けられた裁判所の権限であるためとされ(裁判所法3条1項)、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、住民訴訟は提起することができるもの(行政事件訴訟法5条、42条)とされています。
つまり、住民訴訟(その前提となる住民監査請求も)は、あくまでも、制度を設けた地方自治法の定める枠内で、解釈・運用されるべきものであり※※、最高裁の判例など、そのような前提を基礎とする判断が積み重ねられているところです。
| ※ 上記の最高裁判例の後段で「手続法上の権利ではなく実体法上の権利」というのは、住民監査請求や住民訴訟制度は、憲法など地方自治法以外の法令により制度が創設されており、その手続を地方自治法242条等で定める、というものではなく、地方自治法242条等が、住民監査請求や住民訴訟制度を創設する根拠規定である、ということです。 |
| ※※ 参照:碓井p.13及びp.147。なおこの点については、住民訴訟が法律により特に認められた民衆訴訟(その先行行為であり、対象財務会計行為等についての前提を設定する住民監査請求において同じ)としての性格のみならず、原告適格や処分性など訴えの提起自体に一定の枠組みを設ける抗告訴訟の代替機能となることを問題視する(抗告訴訟の制度枠組みを設けた意味がなくなる)見方から、このような判断が導かれるところもあります。 |
(2) 自治体運営のあり方を問う参政権行使的な請求権ではなく、特定された個別の財務会計行為等の違法・不当を問うものである
上記1掲出の昭和53年最高裁判決では、住民訴訟制度について「地方自治の本旨に基づく住民参政の一環」としています。
しかしながら、たしかに住民監査請求制度は、住民がみずから能動的に、自治体に対して何らかの行動を求め、自治体側には一定の応答義務が生じる、という意味では、住民参政の性格を持ち得るものではありますが、住民監査請求制度の利用をもって、住民がみずからの意思で自治体の政策のあり方を決する(問う)という、本来的な意味での「参政権」の行使と見ることには、無理があるでしょう※。
| ※ 参照:塩野Ⅲp.238以下。なお住民訴訟に関する目的について、昭和53年最高裁判決では住民参政について言及していますが、最近の最高裁判決では、参政的機能に言及することには慎重になっているように考えられます。例:最判平12.12.19民集54.9.2748。。なお、住民訴訟の参政権的性格を「消極性の強い参政権」と解する見解があり、参考になるものと考えます(山本隆司「住民訴訟」(南・高橋・市村・山本編「条解行政事件訴訟法(第4版)」弘文堂(2014年))。この見解は、選挙や直接請求のように自治体の意思形成・決定に積極的に参加するのではなく、裁判所に適法性コントロールを求めることにより、自治体の意思決定の統制・監督に参与するという点から論じられているものです。 |
地方自治法75条では、監査の直接請求制度、いわゆる事務監査請求制度が定められており、住民監査請求と類似の制度となっています。この事務監査請求は、行政運営上に生じる諸問題に関連してその究明を行うために行うもので、監査結果公表により、責任の所在や行政の適否を明白にすることを目的とする、住民参政の一手段とされています。
一方で住民監査請求は、対象を具体的な財務会計上の行為等に限り、終局的には、その違法性の判断とそれに対する具体的措置を裁判所にゆだね、一種の司法的統制に服させるものである、とされています(参照:松本逐条)。
実際、現行の地方自治法242条等が整備されるにあたって、当時の自治省は ① 住民監査請求制度と事務監査請求制度は、趣旨目的を異にする全く別の制度である ② そのため、住民監査請求制度は、地方自治法の事務監査請求の規定の並び(第2編第5章 直接請求)ではなく、「財務」の枠の中(第2編第9章)で改正することとした としています(昭38自治法改正詳説p.328)。そして、地方自治法242条1項では、住民監査請求で対象とできるのは、同項に掲げられた財務会計行為等に限定しています。
現実の住民監査請求では、しばしば政治的に論争がある問題を事実上のテーマとして、その当否を問うことを意図する事案が見られます(最判昭62.2.20民集41.1.122において、監査請求においては「特段の事情が認められない限り、右監査請求は当該行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権を当該普通地方公共団体において行使しないことが違法、不当であるという財産の管理を怠る事実についての監査請求をもその対象として含む」と判示した上で、「実体法上の請求権」に限定を設けないことにより、事業の失敗などの政争問題を住民監査請求(実際は住民訴訟)の俎上に載せる方法論が明示的とされたともいえます※※。無論元が政争問題であっても、形式上住民監査請求や住民訴訟で直接対象とする事項そのものが財務会計法規上の違法性評価が可能であるものである限り、それを住民監査請求や住民訴訟で扱い得ることは立法政策上認められており、住民監査請求や住民訴訟制度の設計趣旨や方針にも矛盾しないといえば、それまでの話ですが)。
しかし今日的な民主制のもとでは、原則的には多数決原理で決せられるべき自治体の一般的な政策のあり方を問題の対象とする直接請求諸制度(条例制定請求、事務監査請求、リコール)とは異なり、制度としての住民監査請求・住民訴訟は、あくまでも一定の個別具体に特定された財務会計行為等を対象として(下記平成2年最判参照)、その違法・不当性を問題とするものです。
住民監査請求に当たり、多数の住民の意思統合を要しないのは、そもそも違法性の有無は、法令を行為等にあてはめて客観的に決するものであって、多数決で決める問題ではないからであり※※※、そうした制度的性格を持つ以上、住民監査請求を通じて政策のあり方など多数決原理によるべき問題を扱うことは、民主制の原理に照らしても、予定されるものではなく、政策のあり方等を問う場合は、上記の事務監査請求その他の直接請求制度や選挙などを通じることが本来のあり方です※※※※。
| 住民監査請求の対象とできる事項は、一定の具体的な財務会計上の行為または怠る事実に限られる 最判平2.6.5民集44.4.719
○ (地方自治法242条1項は)住民に対し、当該普通地方公共団体の執行機関又は職員による一定の具体的な財務会計上の行為又は怠る事実…に限って、その監査と非違の防止、是正の措置とを監査委員に請求する権能を認めたものであって、それ以上に、一定の期間にわたる当該行為等を包括して、これを具体的に特定することなく、監査委員に監査を求めるなどの権能までを認めたものではないと解するのが相当である。けだし、法が、直接請求の一つとして事務の監査請求の制度を設け、選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務等の執行に関し監査の請求をすることができる旨規定している(75条)ことと対比してみても、また、住民監査請求が、具体的な違法行為等についてその防止、是正を請求する制度である住民訴訟の前置手続として位置付けられ、不当な当該行為等をも対象とすることができるものとされているほかは、規定上その対象となる当該行為等について住民訴訟との間に区別が設けられていないことからみても、住民監査請求は住民一人からでもすることができるとされている反面、その対象は一定の具体的な当該行為等に限定されていると解するのが、法の趣旨に沿うものといわなければならない |
| ※※ 参考 実務住民訴訟p.301 |
| ※※※ ただし、違法性の判断が多数決になじまないということは、住民監査請求を住民一人からでも認める理由付けの一つにはなりますが、そのことから住民一人からの請求も認めるという結論に当然に至るものではなく、一人から請求できる制度としたのは、あくまでも立法府の判断によるものであり、例えば請求には一定人数が必要と制度構築することは可能であると考えられます。 |
| ※※※※ 参照:塩野Ⅲp.238。なお上記平成2年最判の担当最高裁調査官解説では「住民が、一定期間にわたる当該行為等を包括して、これを具体的に特定することなく、監査委員に監査を求めるなどの権能は認められていないと解するのが相当であると思われる。当該行為等を特定することなく、包括的、網羅的に監査を求めるという場合には、右事務の監査請求の制度によるべきものといえよう」とする(青柳馨「最高裁判解(平2)」p.227。 |
したがって住民監査請求は上記の通り、あくまでも一定の個別具体に特定された「財務会計行為等」の違法・不当性のみが対象となるものであり、その前提・背景としての政策のあり方を対象とすることは、住民監査請求制度の予定するところではありません。
そしてその帰結として、上記※平成2年最判の示す通り、個別特定の行為等を超えた一般的・包括的を対象とすることは、政策のあり方等を問うに等しい(または接近する)ものであり、認められないこととなります(たとえば、○年度の土木行政部門における支出一切の監査請求は、その自治体の土木行政のあり方を問うに等しく、そうした請求は不適法である、ということです)し、対象となる「財務会計行為等」は、地方自治法242条1項所定の類型に外形的に該当するのみならず、財務上の処理を目的とすることを必要とされることとなります(最判平2.6.5民集44.4.719参照)。
(3) まとめ(1)
以上をまとめると、住民監査請求は、あくまでも一定の個別具体的に特定された財務会計行為等の違法・不当がないかについて監査を求める制度として、地方自治法で構築されているものであり、これを外れて運用されることは制度として予定されておらず、自治体の政策のあり方を直接問う仕組みではない、ということになります【冒頭のポイント①】。
また、こうした制度の性質を踏まえ、各論部分で詳述するように、最高裁判所の判例などでは、住民監査請求を利用できる要件については、とりわけ対象の財務的事項性について厳格に、つまり拡大解釈的圧力を認めない方向で※、考え方が整理されているところです【冒頭のポイント②】。
| ※ これは、判例等の方向性、ということですが、監査委員の実務においては、地方自治法199条10条による意見を付するなど、住民監査請求の法的な制度の枠外で、柔軟な対応を行う例もあるようです(参考:田中孝男「地方監査制度の改革と住民監査請求・住民訴訟制度」 会計検査研究(会計検査院) No.44 (2011年) p.112注15)。また念のため塩野Ⅲp.239。ただし、上記(1)碓井指摘の点には、留意が払われて然るべきです。 |
(4) 個人の権利利益を争う仕組みではなく、争点は請求人の権利利益とは直接の関係がない
住民監査請求制度は、後段に住民訴訟制度が用意されています。当然ながら、住民訴訟での構図は、対立当事者間が争う訴訟そのものです。また住民監査請求の運用においては、しばしば請求人である住民側と、請求の対象機関側の主張が対立し、相争うかのような構図が出現することがあります。
しかしながらそもそも住民監査請求は、対立する紛争当事者間で、その当事者に関わる具体的な権利義務ないし法律関係の存否を争う※制度ではありません。
| ※ 参照:最判昭56.4.7民集35.3.443。行政事件訴訟法5条の民衆訴訟(住民訴訟はこれに該当)の定義では「選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するもの」と、請求の対象が原告の法律上の利益と関連しないことを明確にしている。 |
一般に訴訟や行政不服審査は、当事者間に生じた、行政上の権利義務ないし法律関係についての争いを裁断する制度であり、これを提起できるのは、原則として、その問題に法律上の利害関係を有する者に限られています。また裁判所は、提起された請求の趣旨から外れた結論を出すことを認められていません(民事訴訟法246条)。
これは、これら制度がこれを提起する者の紛争を解決する手段として設計されており、また当事者の請求内容と異なる判断を裁断機関が行っても、紛争の解決には有用ではなく、場合によっては当事者の予期しない結論に至ることにより、当事者の権利義務や利益を不要に害することになりかねず、またこうした事態によって、紛争解決機能に求められるべき、法的安定の実現という社会的要請を損ねることになるからです※※。
| ※※ 例えば、友人が貸した金が返してもらえず困っているが、裁判をする金もないと聞き、自分が代わって原告となり貸金返済を求める訴訟を起こすことは、通常認められていませんし(当事者適格がないため。行政不服審査も同様の立場をとる(最判昭53.3.14民集32.2.211))、請求額1000万円の貸金返済請求の訴訟で、裁判所が、証拠調べの結果返済残額が2000万あり、原告は全額返済を求める意図であるが、その貸金の全額を1000万円と勘違いしていることがわかったからといって、2000万円の支払を命ずる判決を下す、または解雇処分取消のみ請求する訴訟で、不法行為が証拠上認められたからといって請求にない損害賠償を命ずる判決を下す、といったことはできません(ヴェニスの商人のような裁判を現代で罷り通らせるわけにはいきません)。行政不服審査においても、同様と考えられています(参照:塩野Ⅱp.24)。これは、上記のような社会的要請から制度構築されていることによる帰結です。行政訴訟の代表的な形態である抗告訴訟、当事者訴訟も、その原則から外れるものではありません(参照:塩野Ⅱp.280)。 しかしながら、住民訴訟や選挙訴訟は、当事者の権利利益に関わることなく提起することができる訴訟です。その点でこれら訴訟は例外的な制度であり、法律でも、一般的訴訟制度の例外として、特に認められた制度と位置付けられています(行政事件訴訟法42条。なおこの訴訟は、裁判所法3条1項で裁判所が扱うこととされる「法律上の争訟」には含まれない、というのが一般的な理解です)。 これら制度の設計上の考え方は、次の通りと一般にされています(芦部信喜(高橋和之補訂)「憲法(第7版)」岩波書店(2019年)p.347による。傍点(下線代替)は同書の通り)。 ○ 憲法76条1項で「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」とし、三権分立構造の中で、司法権は、他の国家機関(国会、内閣)から独立して裁判所の系統に属することとされている ○ そして「司法権」とは「当事者間に、具体的事件に関する紛争がある場合において、当事者からの争訟の提起を前提として、独立の裁判所が統治権に基づき、一定の争訟手続によって、紛争解決の為に、何が法であるかの判断をなし、正しい法の適用を保障する作用」とされる ○ このうち具体的事件性については、裁判所法3条の「一切の法律上の争訟」も同じ意味であり、判例は「法律上の争訟」の意味について、以下2条件をともに満たすものに限られるとしている。 ① 当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であって(したがって、裁判所の救済を求めるには、原則として自己の権利または法律によって保護される利益の侵害という要件が必要とされる)、 ② それが法律を適用することにより終局的に解決することができるもの (参照:最判昭56.4.7民集35.3.443(いわゆる板曼荼羅事件)、最判昭41.2.8民集20.2.196) ○ 具体的事件性を前提としない住民訴訟のような民衆訴訟については、具体的事件性を前提とせずに出訴できる制度をとくに法律で設けているもの(法律で例外的に認められた訴訟)、と理解されている |
一方住民訴訟は、法律上、自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起することができるものであり(行政事件訴訟法5条)、上記昭和53年最判にある通り、住民訴訟の原告は、自己の個人的利益のためではなく、住民全体の利益のため、いわば公益の代表者としての立場に立ちます。いうまでもなく、住民監査請求の請求人の立場も同じことになります。
つまり住民監査請求では、請求人の権利義務ないし法律関係を争点とする請求人と対象機関の間の具体的紛争が存在せず※※※、よってこうした紛争を解決する制度ではないことになり、訴訟などにおける枠組みを住民監査請求で求めることは、必然ではなくなります。
| ※※※ ただしこれは、あくまでも請求人の権利義務関係について、請求人と自治体で相反する利害関係が存在し紛争に至っているのではないということであり、請求人と自治体の間に争訟上の紛争が存在しないということではありません(住民訴訟の場合、住民と自治体の機関が原告被告で争うのですから、すくなくとも両当事者間での対立関係の存在は自明です)。 請求人たる住民は、住民全体、ひいては自治体の利益のために住民監査請求・住民訴訟を提起しているのですが、監査で執行機関側が請求人の主張と異なる主張を述べたり、住民訴訟で自治体側が応訴するということは、原告たる住民のもつ住民全体・自治体の利益の観念と、実際の財務会計行為を執行する自治体側のもつ利益の観念が異なっており、それがゆえに住民と自治体の認識および立場が分離し、住民が自治体の財務運営の違法を問う訴訟を提起する、つまり住民と自治体間の紛争が発生するという構図が生ずるのです(おそらくは、これが実態にも実際の感覚にも適合するものでしょう。この点について最判昭53.3.30民集32.2.485は「損害補填に関する住民訴訟は、地方公共団体の有する損害賠償請求権を住民が代位行使する形式によるものと定められているが、この場合でも、実質的にみれば、権利の帰属主体たる地方公共団体と同じ立場においてではなく、住民としての固有の立場において、財務会計上の違法な行為又は怠る事実に係る職員等に対し損害の補填を要求することが訴訟の中心的目的となっている」と述べています)。そしてさらには旧4号訴訟(被告は個人)において自治体が被告側に補助参加する、つまり職員の行為で自治体がこうむった損害の代位賠償請求訴訟で、賠償について利益を受ける側の自治体が、訴訟上自治体に加害したとされる側に加勢するという事例(参照:東京高決昭56.7.8行裁例集32.7.1017。本件は、旧4号訴訟において、当該自治体自身が、旧4号訴訟の被告(当該自治体の職員)のために補助参加することを認めたもの)すらも起こり得るのです(同決定では上記昭和53年最判を引用した上で「住民訴訟の原告が、形式上地方公共団体に代位してその権利を主張するからといって、右訴訟において、原告と利害関係が同一でない地方公共団体が、被告らのために補助参加しても、対立訴訟構造をもつ民事訴訟の本質に背馳するものということはできない」とする)。 |
(5) 住民監査請求と通常の財務監査は本質的な違いがない
次に、住民監査請求で求められる監査と、通常の財務監査での、監査委員の職務権限について、比較してみます。
| 住民監査請求(242条) | 通常の財務監査(199条) |
| ① 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体の被った損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
5 第1項の規定による請求があつた場合には、監査委員は、監査を行い、普通地方公共団体の経営に係る理を監査する。 |
① 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体の被った損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
① 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。 |
住民監査請求における監査の内容、さらにはそれを支える監査委員の権能は、意見提出権(地方自治法199条10項)の規定上の違い(同11項と242条5項)などあるものの※、本質的に、通常の監査委員の職務権限を定める地方自治法199条による財務監査のそれと変わらないことが見て取れます。
(199条3項の内容は、監査着眼点の基本原則であり、当然に住民監査請求においても準用されるでしょう。同8項の権限は、242条に同種の権限設定や準用規定がなくわかりにくいところですが、住民監査請求の監査結果のもつ法的効力が、199条に基づく財務監査と比して強力である(損害賠償請求等の住民訴訟に移行することがあり得る)こと、また同項の調査権が強制力を伴わないものであることを考えれば、監査に当たっての199条8項の調査権限が住民監査請求では準用されない、という考えは成り立ちがたいと考えます。なお242条8項で、住民監査請求において、首長その他の執行機関や職員の陳述の聴取を行うことができることが前提の規定となっています)。
要すれば、住民監査請求において、通常の199条財務監査と住民監査請求の監査で、監査委員に求められる権能には、本質的な違いが無く※※、双方の監査における目的、なすべきことなど、基本的には変わるところはないものです。
| ※ 地方自治法199条10項の意見提出権限と同様の規定が242条にはありませんが、住民監査請求の場合に監査委員が関係機関に、監査結果に基づく意見を提出できないということではなく、実際も、住民監査請求時の監査意見表明は、ごく普通に行われていることでしょう。住民監査請求の請求人にとっては、必要な措置を講ずるよう求めているのであって、それに直結しない意見の表明は、請求人にとっての直接の要求の焦点ではない(ので法的に位置づける必然性がない)ため、あえて地方自治法242条に監査委員権限として明文規定しなかっただけ、ということだと思われます。 なお、199条の勧告の対象に職員を含まないという違いがあるのは、住民監査請求における地方自治法242条1項に「職員」を含むことによる、法文の構成に基づく当然の帰結です。 |
| ※※ 地方自治法199条11項の勧告権限は、平成28年3月16日第31次地方制度調査会答申(人口減少社会に的確に対応する地方行政体制及びガバナンスのあり方に関する答申)に基づき、平成29年に法改正され、令和2年から施行されたものですが、監査一般の実効性を高めるために、住民監査請求において従来から設けられていた監査の実効性にあわせた、と見ることができるでしょう。 |
(6) 請求の本質は「特定の財務会計行為等に対する、監査の実施を通じた監査委員職権発動の請求」である
最高裁は、住民監査請求の目的として「住民訴訟の前置手続として、まず当該普通地方公共団体の監査委員に住民の請求に係る行為又は怠る事実について監査の機会を与え、当該行為又は当該怠る事実の違法、不当を当該普通地方公共団体の自治的、内部的処理によって予防、是正させることを目的とするもの」(最判昭62.2.20民集41.1.122)と述べ、住民監査請求が、(特定の財務会計行為等について)監査の機会を与えることを通じ、自治体の財務運営に関する自浄機能を働かせるためのものであることを明らかにしています。
ところでそもそも監査委員は、自治体の執行機関の一つとして、自治体行政のうち自己統制領域に関する業務と責任を分担しており、そのため、定時臨時の財務監査を行い、監査の結果に関する報告を決定・公表し(地方自治法199条9項)、監査の結果に基づいて必要と認める場合は、自治体の組織運営の適正化を図るための意見を表明し(同10項)、議会・執行機関において特に措置を講ずる必要があると認める事項については必要な措置を講ずべきことを勧告することができる(同11項。令和2年度から施行)など、広範な権限が付与されています。またこの権限行使において、地方自治法は特段の制約を設けていません。
よって、監査の実施及びその結果に基づく意見・勧告決定に際し、監査委員は、広範な裁量判断を行うことができると解されます。また上記(5)の通り、住民監査請求における監査委員の監査及びその結果取扱いに関する権能は、上記の地方自治法199条に基づく権能と大きく変わるものではありません。
さらに上記(4)のように、住民監査請求で問題となる財務会計行為等は、請求人の権利義務ないし法律関係とは直接的な関わりのないものであり、その是正のための措置がどのようなものとなろうと、請求人の個人的な権利・利益に直接的な影響を与えるものではないので、こうした個人の権利・利益に関わる紛争解決のための争訟の枠組みを住民監査請求制度で堅持する必然性は、乏しいものとなります。
これらを総合すれば、住民監査請求は、訴訟や行政不服審査のように、請求人の請求内容の当否判断、例えば訴訟のように、原告の請求を(すべて、あるいは一部)認めるか(請求認容)、認めないか(請求棄却)の判断をその核心とし、その上で、請求される措置要求内容の枠内で対象機関にいかなる行動を求めるか(勧告)の判断を行う、というものではなく、監査委員は、請求の対象となった財務会計行為等を監査する義務は発生するものではあるが、監査の結果勧告する措置の内容については、監査委員は、請求人の請求内容に必ずしもとらわれることなく、監査委員の職権の範囲内で、必要(適切)と認める内容の判断することが可能なもの、と構成すべきものです。実際、最高裁は直截に、住民監査請求における監査委員の権限について、そのように判示しています※。
これを換言すれば、住民監査請求は、住民が監査委員に、(特定の財務会計行為等について)未だ行われていない本来の権限の発動としての監査の実施を求め、これを通じ、自治体財務運営の自浄と適正化を図ることを求める仕組み、ということができるでしょう。
| ※ 最判昭62.2.20民集41.1.122では「監査委員は、監査請求の対象とされた行為又は怠る事実につき違法、不当事由が存するか否かを監査するに当たり、住民が主張する事由以外の点にわたって監査することができないとされているものではなく…」と述べ、また、最判平10.7.3集民189.1ではより直截に「住民は、監査請求をする際、監査の対象である財務会計上の行為又は怠る事実を特定して、必要な措置を講ずべきことを請求すれば足り、措置の内容及び相手方を具体的に明示することは必須ではなく、仮に、執るべき措置内容等が具体的に明示されている場合でも、監査委員は、監査請求に理由があると認めるときは、明示された措置内容に拘束されずに必要な措置を講ずることができると解される…」としており、最高裁は、監査委員の判断は請求人の請求内容には拘束されず、自らの職権上の判断において必要な措置を示すことができる旨を明示しています。なお上記昭和62年最判の調査官解説において「『・・・極端な言い方をすれば、住民監査請求者たる住民の役割は、特定の疑惑を提示することによって、権限を有する機関に対し監査の端緒をもたらすことにあり、対象事実の全体像の解明及び取(執)られるべき具体的措置の選択は、むしろ請求を受理した監査委員の守備範囲に属する』と考えられる」としています(石川善則「最高裁判解(昭62)」p.78。なお上記の引用部分:関哲夫・判例評論286.20)。 また松本逐条では、「監査委員の勧告の「必要な措置」とは、一般的には、請求人の請求内容である必要な措置を指すものであるが、監査委員は、必ずしも請求人の請求内容に拘束されず、これを修正して必要な措置を勧告することもできるものと解すべきである」。なお現行規定制定時の自治省の見解も同様(昭38自治法改正詳説p.339)。 なおそうすると、地方自治法242条5項は「当該請求に理由がないと認めるときは、理由を付してその旨を書面により請求人に通知…し、当該請求に理由があると認めるときは、…必要な措置を講ずべきことを勧告」とあります。監査委員の判断は、必ずしも請求人の請求内容にとらわれないとなると、「請求に理由がある(ない)」の規定と食い違いが生ずるようにも思われます。この点については、請求人は、監査対象とされた財務会計行為等についての違法不当性を主張していることを前提として、監査委員は、その財務会計行為等について、請求人の主張する事由はもとより請求人の主張しない観点も含んだ広範な観点からの監査を行い、その結果、請求の対象となった財務会計行為等について、違法不当の点があれば「請求に理由がある」、さもなければ「請求に理由がない」の規定を適用すればよいと考えます。上記平成10年最判の「監査請求に理由があると認めるときは、明示された措置内容に拘束されずに必要な措置を講ずることができる」という判示内容は、そのように考えると平仄がとれるでしょう。 |
(7) まとめ(2)
以上をまとめると、住民監査請求における監査委員の権限は、通常の財務監査と大きく変わるところはなく【冒頭のポイント③】、監査委員は、請求人である住民の指摘する財務会計行為等を監査する必要はあるが、その判断は、請求人の請求内容に必ずしも縛られる必要はなく、自治体の財務運営の適正化を図るために、必要と考える措置等を自らの判断で示すことができる、ということになります【冒頭のポイント④】。
3 おまけ1:住民監査請求が要件を満たすかどうかは、住民訴訟を提起する前提条件である
上記2とは、異なる視点での住民監査請求の特徴です。
住民訴訟を提起することができるのは、住民監査請求を行った住民ですが(地方自治法242条の2第1項)、これは「適法な」住民監査請求を行った住民とされています。
なお、実際は住民訴訟においては、「住民監査請求を行った住民」である事実があれば、監査委員が請求を適法と判断したか適法でないと判断したかの事実に関わらず、裁判所は独自に住民監査請求の内容を審査して、その請求の適法性判断を行い、実際の事実関係では監査委員がたとえ適法な請求と判断して監査を行ったとしても、裁判所が上記適法性の判断の結果、地方自治法の定める請求要件を満たさないと判断した場合は、適法な住民監査請求が行われなかったものとみなして住民の訴えを却下し、逆に監査委員が住民監査請求を適法でないと判断した事実があっても、裁判所が適法な請求と判断すれば、前記の事実関係に関わりなく、住民訴訟において請求に対する実体的な審理(本案審理)が行われています。
そのため、最初から住民訴訟を提起するつもりの住民にとっては、監査委員に住民監査請求を提起したという事実さえあればよく、極論すれば、その後の監査委員の監査行動や判断等はどうでもよいことになります。
このような構図があるのではありますが、だからといって、自治体の自己統制・自浄機能発揮の一端を担う監査委員の責任が軽減されるものでないことは当然です。
4 おまけ2:住民監査請求における監査委員の権限を考えるための事例
上述の住民監査請求における監査委員権限のありようを、次の判例を通して考えてみます。
| 市有地を無償で神社施設敷地としての利用に供していることに対する施設撤去・土地明渡しを請求しないことの怠る事実の違法確認訴訟において、上記土地利用は違憲であるところ、原審は、違憲性を解消するための上記以外の合理的で現実的な手段が存在するか否かについて適切に審理判断するか、当事者に対して釈明権を行使する必要があるのに、これを行わなかったとして、請求を一部認容した原審判決を破棄して差し戻した事例 【砂川政教分離(空知太神社】事件】 最判平22.1.20民集64.1.1
【事案の内容】 【最高裁の判断】 ※ 本判決において反対意見を述べる2裁判官のうち今井功裁判官は、釈明権行使に関する部分について多数意見と異なる見解に基づき破棄差戻し判決の結論に反対し、一方で多数意見に立つ裁判官のうちに、今井裁判官反対意見を踏まえた補足意見(上記多数意見の論旨を補強する意見)を述べる裁判官がある |
本件では、控訴審までは、原告の請求の核心事項である「神社施設等の撤去・土地明渡」を焦点として、それ以外の手段の存否や手段採用の合理性等を争点とせずに当事者・裁判所とも訴訟の進行を行ってきたところ、最高裁は、市有地を神社に無償使用させる現状は憲法違反状態であるが、この違憲状態の解消には、原告の主張する神社撤去・土地明渡以外にも方法があることは明らかであり、その点の検討をしないままに「財産管理を怠る事実の違法確認」をすることはできない(審理不尽である)として、原告の請求を概ね認めた高裁判決を職権で破棄して、高裁に差し戻しました。すなわち最高裁は、本件について、同市内別神社での住民訴訟事案において市が土地譲与の措置をとったことなども含め、こうした事案においては、原告の主張する手段、すなわち神社施設撤去等以外の手段も存在することは当然考えられ、また市には適切な手段を選択する裁量権があることから、下級審に対し、原告の主張する手段以外の方策も当事者に主張を尽くさせ、これを検討するよう、差戻審に再考を求めたものです。
なお、最高裁がこのような判断を行った場合に当然予想されることですが、本件のてん末については上記の通り、差戻し控訴審の間に、市と関係者が神社施設の撤去等をせずに問題を解決する方向に動き、差戻し後控訴審・上告審ともその対応を踏まえて、最終的には、原告住民の「神社施設等撤去・土地明渡をしないことが、違法に財産管理を怠る事実であることの確認」という訴訟上の請求を退ける判断を示しました。その意味では、この最高裁判決は、事実上、関係者に対して、本住民訴訟では原告の請求する内容ではない、神社施設撤去等以外の方法で、問題解決を模索・実現する効果を生じさせた、ということがいえるでしょう。
いうまでもなく、住民訴訟は民事訴訟の枠組みを基本利用するものであり、よって当事者主義をとるものです(ここでは概ね、裁判所は当事者が申し立てた請求の範囲でのみ判決ができる、つまり判決を求める内容は当事者が決定し、裁判所はそれに拘束される。また判決に必要な事実と証拠は当事者が主張しなければ、裁判所は判断に用いることができない、という意味合いと考えて下さい)。
そして、控訴審までの本件訴訟では、この当事者主義の線に沿い、まさに原告住民の請求内容の核心、つまり神社施設の撤去を焦点として審理が進行し、地裁高裁とも原告の請求の範囲内での判断を行いました(市も控訴審まで、市の措置の適法性論拠としての神社施設の非宗教性などを主張しており、神社施設撤去以外の方法による違憲・違法性解消の主張はしていません。おそらくですが、訴訟という特性から、当然のものとして、このような主張をおこなったのでしょう)。
一方で最高裁は、本件の違憲性は、神社施設のもとで一定の行事を行う氏子集団に、長期に土地を無償で使用させているためであり、神社施設撤去をしないことのみで生じているものではなく、その違憲性解消には神社施設撤去以外にも方法が当然にあり得ることに着目して、またこの訴訟が住民訴訟、つまり原告は原告自信の個人的な利害関係ではなく、公益の代表者として訴訟を追行する立場の者となる訴訟であり、かつ判決の与える影響が小さくない※ことを踏まえ、当事者の主張をいったん脇に置き、職権でこのような下級審とは異なる建て付けでの判断をおこなっているのです※※。
| ※ 参照:清野正彦「時の判例Ⅶ」p.13 なお、住民訴訟も構造的には当事者主義をとる民事訴訟の枠組みを基礎として進行されているものの(行政事件訴訟法7条)、上記判決においては、原審での釈明権不行使を当事者が主張していないにかかわらず職権で探知し、原審判決違法の根拠としていることなど踏まえ、公益の代表者により、住民全体に影響を及ぼす請求内容について審理する住民訴訟という特性からは、職権探知主義への親和性があるのではないかとの考察もなされているところです(参照:山岸敬子「民衆訴訟・機関訴訟」((高木・宇賀(編)「Jurist増刊 行政法の争点」有斐閣(2014年)p.143))。ただし上記清野説明では、本判決の個別事情等も踏まえれば、判決の射程はかならずしも大きいものではないとしており、また訴訟の立脚する当事者主義を重視した反対意見(今井裁判官)も付されているところです。 |
| ※※ 訴訟の公益性や影響の大きさについては、訴訟に関与していない神社関連の地域住民などの第三者にも影響が生じることなど考えられます(ちなみに本訴訟に、これらの者が被告市のために補助参加した形跡は見受けられません)。 また本判決では触れていませんが、住民訴訟の結果は自治体財務運営という住民全体の利益にかかわるものとなるため、結論自体が、当事者の主張はともかく、一定の客観的・普遍的な妥当性を備えるべきものである、という制度的要請が働くべきである、との考え方もあり得ます。 そして結論の客観性・普遍性については、こうした訴訟において得られる結論は、誰が訴訟を提起してもできるだけ同様のものであることが望ましいが、住民訴訟が住民だれでも原告となり得て、その請求内容は原告が任意に決定できる(民事訴訟における処分権主義)以上、誰が原告となるかで当然、原告が主張する請求内容は変わり得ることとなり、よって本判決の示すように、当事者主義の枠内で、裁判所が一定の積極関与(釈明権行使)をすることもあり得るとの考えが、成立し得るものです(参考:本判決の田原睦夫裁判官補足意見)。 |
本最高裁判決は、あくまでもこの事件の個別の事実関係・事情を踏まえて示されたものです。さらに、いうまでもないことですが、最高裁は、本件においても当然ながら、あくまでも上記の当事者主義の枠組み、また訴訟法に定められた仕組みの中で判断を示しているものです。
しかしその上で考えても、この最高裁判決は、わざわざ職権で、控訴審まで(上告審においても)当事者の主張などのぼらなかった神社施設撤去以外の手段の存否等について、審理を尽くすよう差戻審に求めたものであり、自治体実務担当者からみれば「踏み込んだ」ものと見えます。実際、差戻審においては、神社施設撤去以外の手段によって問題解決を図る方向に向かったことは、説明の通りです。あるいは、最高裁は(裁判所の権限事項ではないのですが)、問題の解決に向けて、より政策的に妥当な方策の検討への誘導を、言外に意図していたのかもしれません。
そして裁判所において、場合によってではあれ、このような判断がなされ得るのであれば、当該自治体の執行機関であり、より幅広い手段の検討がなし得る監査委員においては、監査請求における請求人の請求内容のみならず、場合によっては、これにとらわれずに、より広範かつ全般的な観点から、自治体の財務運営適正化のための監査結果の取りまとめを行うことは、当然に期待されることといえるのではないでしょうか。
なお上記最高裁の判断は、本件が3号訴訟※※※、つまり自治体の行為が住民監査請求や住民訴訟に先行して存在しないため、自治体の選択可能な行為の幅が広いと裁判所としても想定し得るのであり、それがゆえに、裁判所の権能や訴訟法の構造による制約下においても、このような判断が可能であったといえなくもありません。
しかし住民監査請求においては、監査委員はそもそも当該自治体の執行機関であり、また監査委員は請求人の請求内容にとらわれることなく、必要な措置を講ずることが可能なのですから(最判平10.7.3集民189.1)、特定の財務会計行為が存在する場合であっても、住民全体の利益のために、広範な選択肢を模索して、適切妥当な結論を見い出すべき、といえるでしょう。
| ※※※ なお松本逐条では、地方自治法242条の2第1項3号の、怠る事実の違法確認請求訴訟に関する説明において、本判決に基づき、「この第3号の請求について、違法是正のための措置に選択肢があるような場合、解決するための他の手段を尽くせば、原告の請求どおりの措置をとらないことをもって、必ずしも違法に怠る事実があるということにはならない」としています。 |
以上については、最高裁の一判決を例にとったものではありますが、考え方の参考になり得るものとして、記述しました。

新幹線には何遍も乗りましたが、なかなか富士山が綺麗に見えることは少ないものです。そもそもかなりの確率でこの辺りを通る時分は日が暮れているし。。。ということで、富士山がよく見えると、何か得した気分になります。いいオッサンが窓にへばりついて富士山の写真を撮っているというのも絵ヅラはよろしくはないのでしょうが。